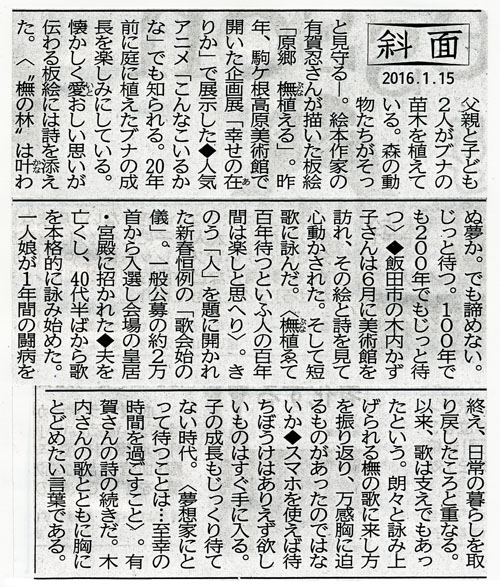
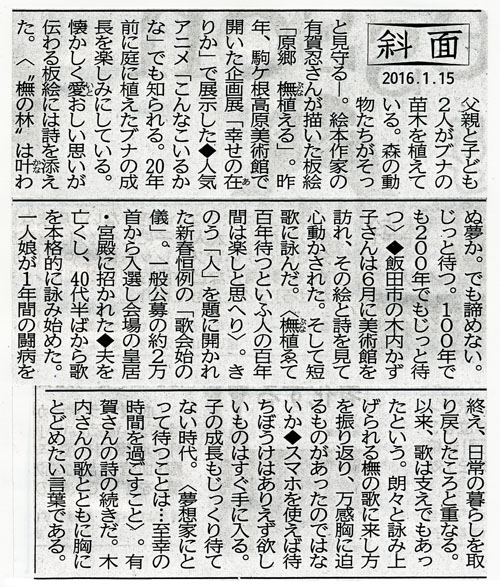 |
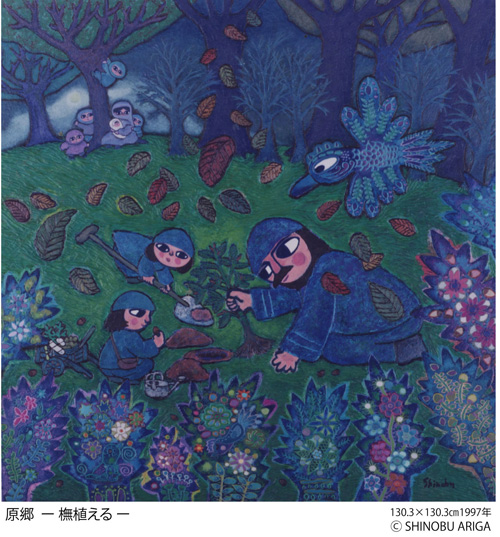 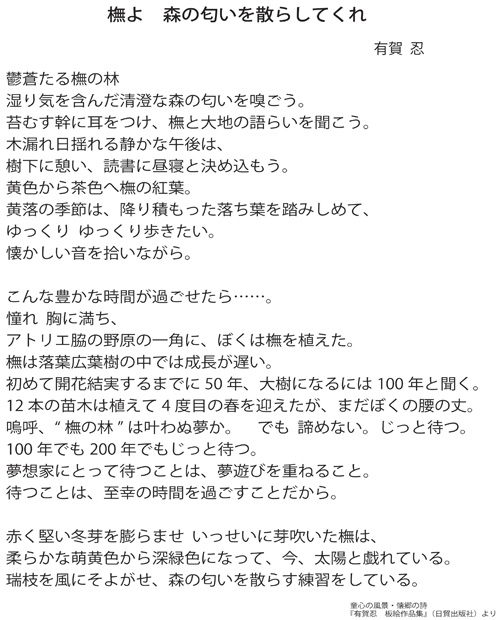 |
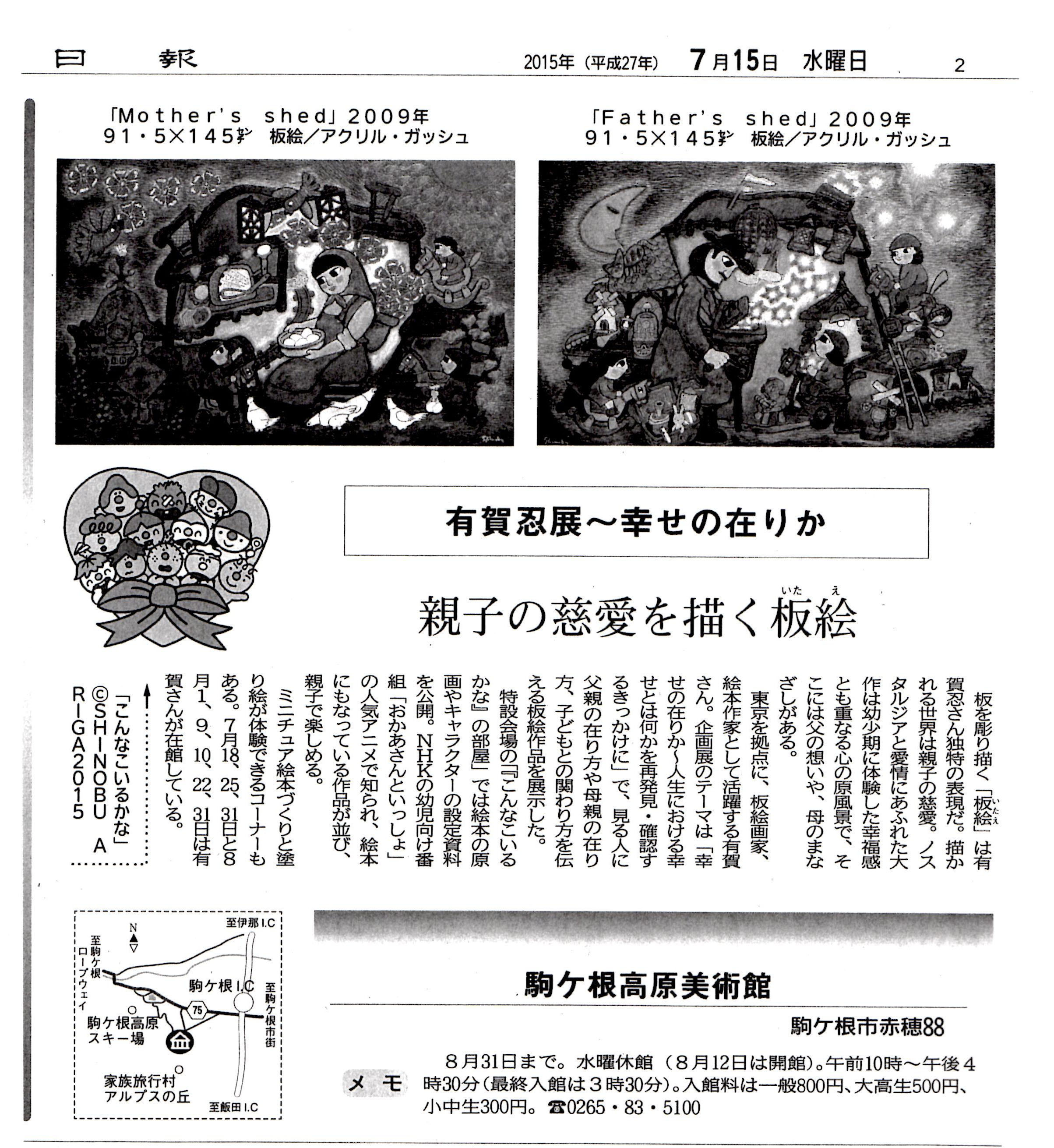
■有賀在館日の変更
下記在館予定日のうち7月31日(金)はキャンセルいたします。仕事の都合で美術館には参れません。
あしからずごご了承ください。申し訳ございません。
■有賀忍展 駒ケ根高原美術館 KOMAGANE KOGEN ART MUSEUM
5月1日(金)~8月31日(月) 10時~16時30分 入館は15時30分まで
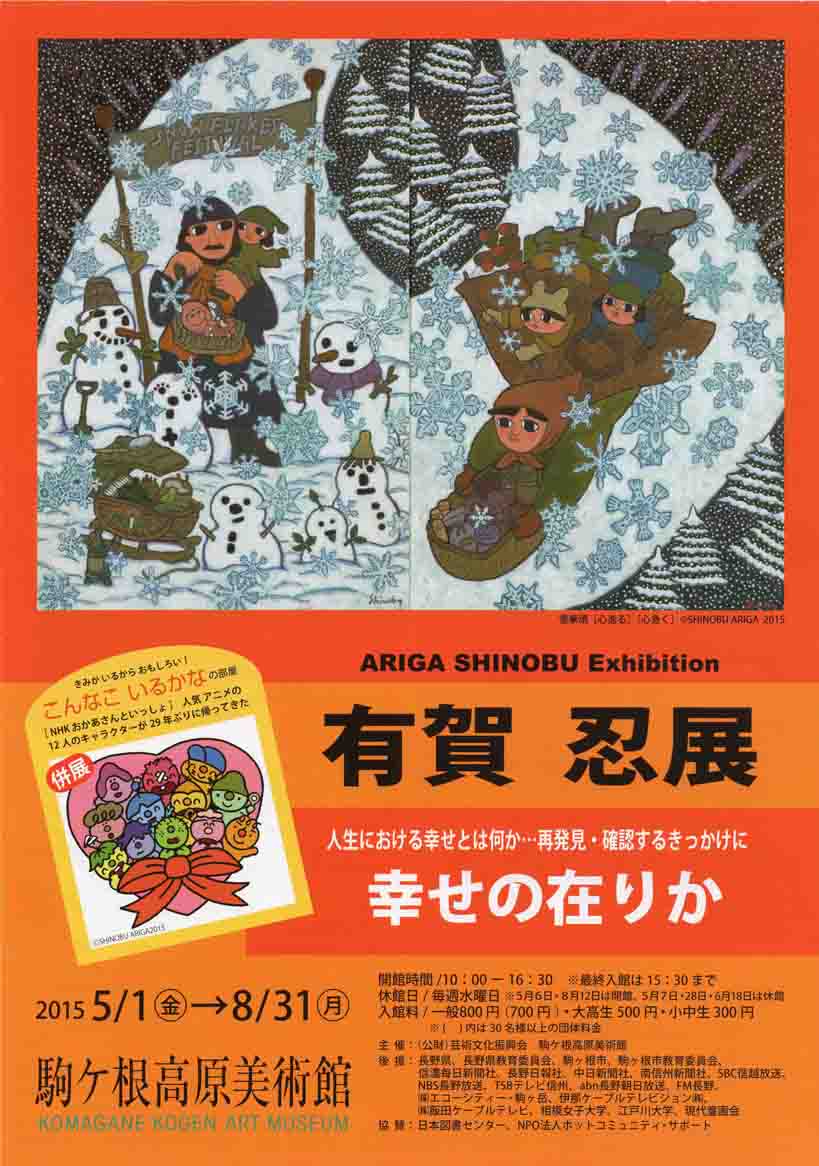

●5月 1日(金) 2日(土) 16日(土) 29日(金) 30日(土)
●6月 6日(土) 20日(土) 27(土)
●7月 11日(土) 18日(土) 25日(土)
●8月 1日(土) 9日(日) 10日(月) 22日(土) 31日(月)
※予定です。ご確認ください。赤字は追加です。
■新装版『こんなこいるかな』出版記念 絵本原画展
●会期:3月7日(土)~20日(金)
●会場:ジュンク堂書店・池袋店8F


■新装版『こんなこいるかな』出版記念 絵本原画展
●会期:3月7日(土)~20日(金)
●会場:ジュンク堂書店・池袋店8F
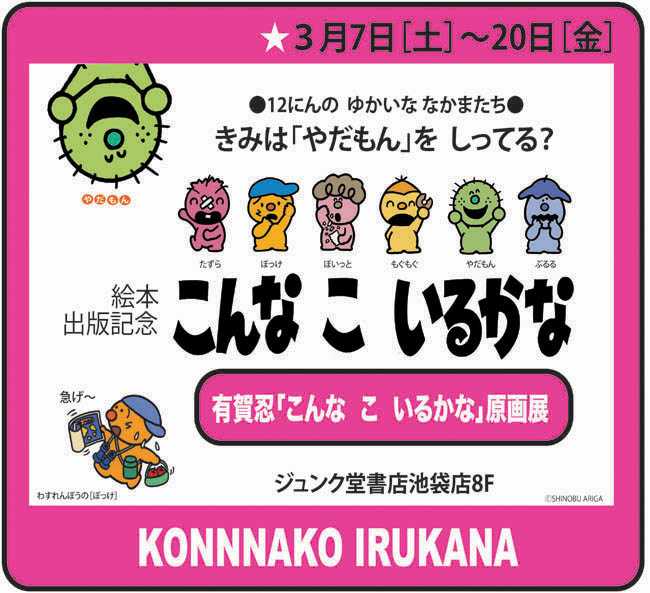
■3月3日は ひなまつり
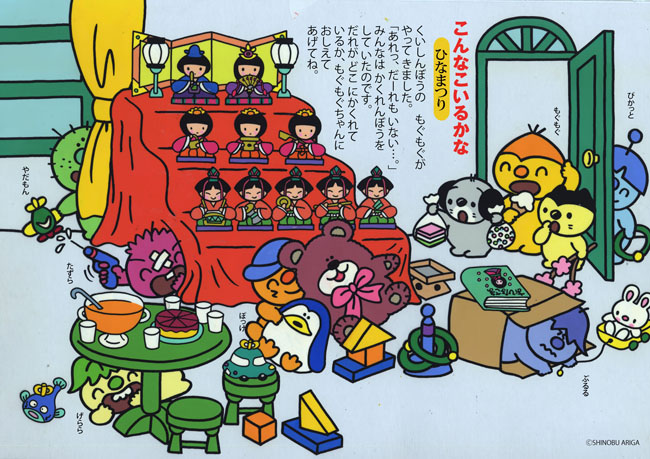
■おふろって いいね
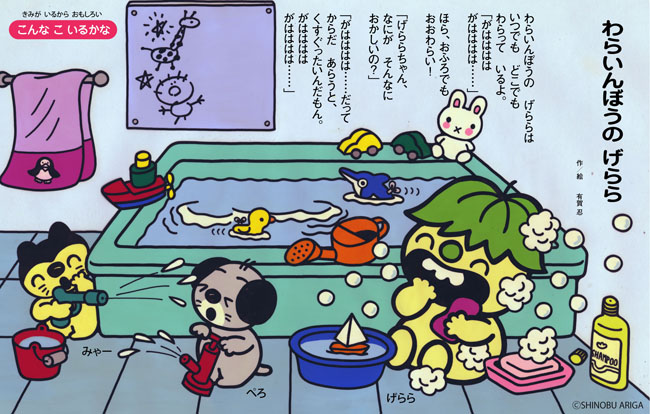
■きみが いるから おもしろい![こんな こ いるかな]12人のなかまたち
《ふねが でるよー!》

■バレンタインデー chocolateだいすき!!!!

■板絵『あげる』 F3号

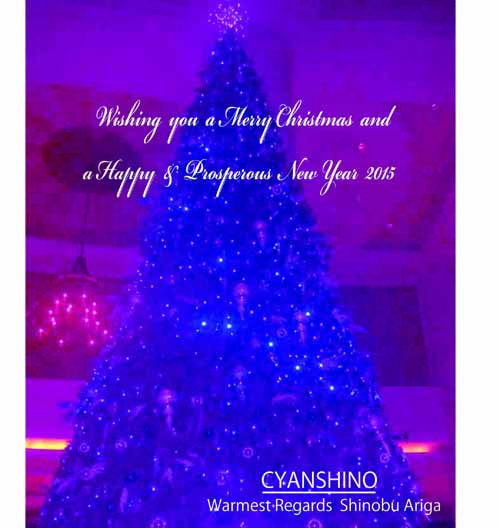
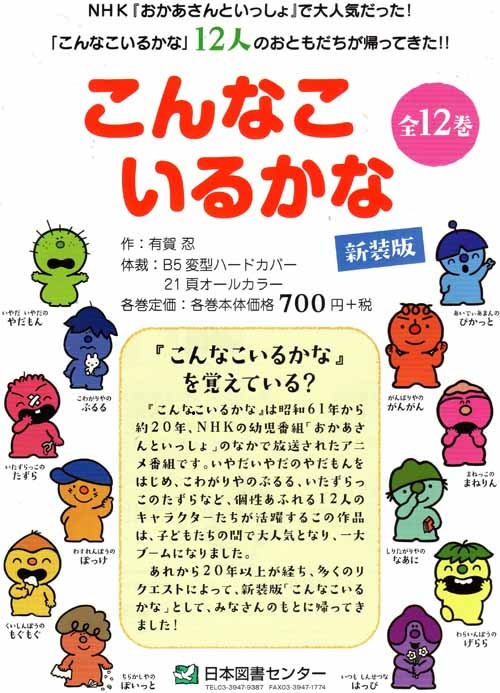
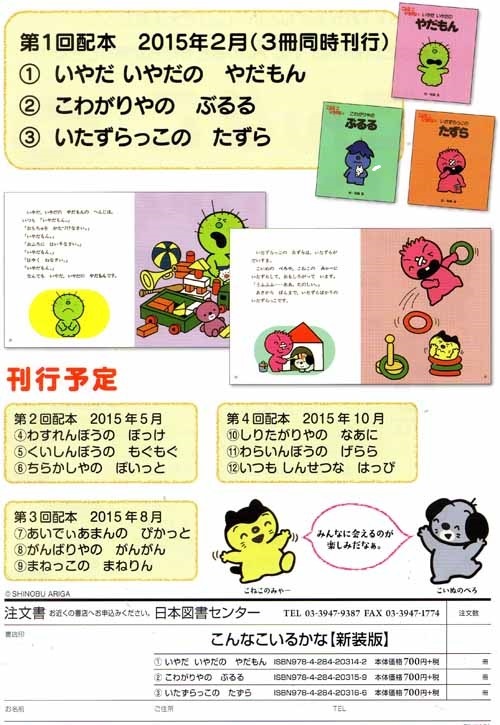
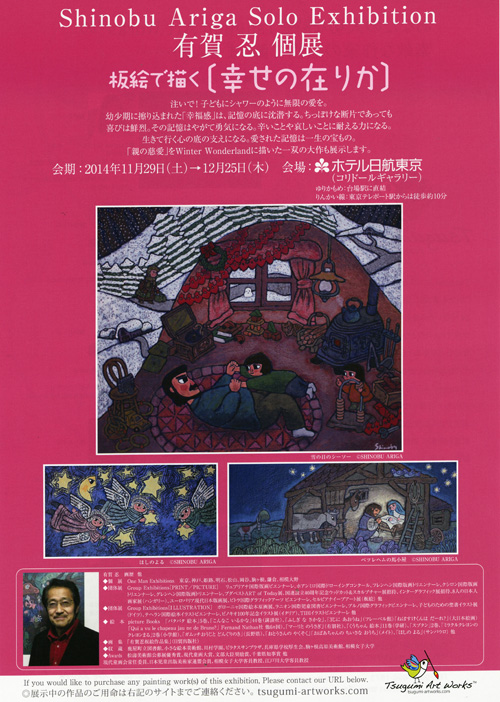 |
●有賀忍個展「幸せの在りか」
|
| 2月のアトリエだより |
■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)
 |
雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (2月29日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
■ゲージを作る


・ゲージ(型紙)6個 ・ゲージを使って切った牛乳パック ・ミルクカートンキューブ(未完成品)7×14 /
7×7
小学校の図工展(開催前日の教員お披露目日)を見る。小学校の図工の教諭の解説を聞きながら会場を回った。
一年生から三年生までは、自由に制作した後がはっきり表現に現れていた。
一年生の自分の等身大の体を模造紙に描いたものは、本当にすべて子どもが独力でやったかどうかと、
首を傾げさせるくらいの迫力。それにしても、余りに整いすぎているのが気になって仕方なかった。
同じテーマで描かせた絵でも、バックの処理が均一化。ベタ塗りが徹底しており、白い紙そのままが
全くないのも不自然。指導の難しさをあらためて考えさせられた。小学生全員の旗が校庭に翻っていたのはよかった。
また、寄席小屋が設けられていて、落語を数名が演じるとのこと。これは凄い自己表現!是非とも聴いてみたいところだが、
今日は一般公開前日であり叶わず、残念だった。
研究室に戻り、寸暇を惜しんでミルクカートントイ製作のためのゲージを作った。演習室の机の数に合わせて6個。
牛乳パックは素材としてよく用いるが、様々な玩具等製作の時間を効果的に使うため、ゲージが必要となる。
今日作ったのは7×14センチのキューブブロック製作のためのゲージ。これがあれば、大量のキューブを簡単に
作ることが出来る。カットした時間は創作表現のほうに活かす。学生に言い続けていることは「何でも大量に作ってみろ!」
一個や二個じゃだめ。ぼくは”馬力”をもって演じてみせる。「このおじさん、何、力んでいるの!」冷ややかな視線を
感じないわけではないが。そんなこと、どうでもいい。ぼくは作ることが好きだから、全く苦にならない。
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候)
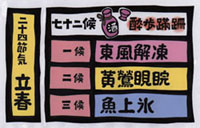 |
●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
・枯れ葉は腐葉土作りに利用する。円形の井戸囲いの中に放り込んでおく。井戸枠の下に設けた
取り出し口からは、真っ黒いいかにも養分たっぷりの腐葉土が顔を見せている。
・今日買ったもの: ジャーマンカモミールの苗20鉢(一鉢80円、寒風の下では、誰も見向きもせず)
植物名札製作用木っ端(何かを切り抜いた後の半円形の廃材。一束10枚120円を5束)
小鳥の水飲場用鋳物容器
・今年はモグラが我が物顔であちこち土の山。モグラ退治機の電池は切れていた。電池はあっても、そう効果は
なかったけど。悩まされるのは、ヘビ(ヤマカガシ。以前マムシも出た。アシナガバチに、さらには恐いスズメバチ……夏の
招かざる客だ。)小鳥の声の中に身を置くのも、恐々……ということも。
■額を製作
10号二枚、4号一枚つくる。サンダーをかけ、ペイントは10回重ねた。10号一枚は絵も完成しており、完全に乾燥し次第額装する。


・写真手前の丸太は、新しいもの。3個は大学の研究室で使用中。 ・小石に顔を描いた
■鳩山枯野原、ロウバイ蕾を開き北風の中、黄色を誇っている。


・ロウバイ。質感は蝋細工!
・ブナの木が好き。葉をなかなか落とさない。
今、冬芽鋭くとがり、春の準備中。
芽

| 1月のアトリエだより |
■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)
二十四節季の大寒。七十二候の末候は文字どおり七十二番目、おしまい。めぐる季節。時の流れの早さよ。
一分一秒の無駄も許されない。内省の日々だが、見つめて、突き詰めて、出来る限り正直に、自己表現。
”出来る限り”に甘さが露呈。ただ、「純度がすべて」……この尺度は、脳裏にはびこる”監視人”が常に攻め立てることにより、
かろうじて「思いの羅針盤」として機能している。
 |
●1月2日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■卒論指導①
卒論指導に時間をとられる。テーマが絵本制作ということで、ゼミ生ではない学性の指導がぼくに回ってきた。絵本を
卒業研究に選ぶ学生は他にもいるが、実際に制作となるとしり込みをしてしまうのだろう。ただ絵本を制作するのなら、
受けなかったかもしれない。”子ども参加型絵本”に挑戦したいといわれ、アイディアを提案。紙芝居形式にパネルシアターの
要素を加えた、おもしろい仕掛けの作品制作をめざした。肝心のお話は「食育」。勿論面白くなければ意味がない。”学び”の
部分は表に出さず、楽しめる内容であること。学生のやる気に期待したが、就活で、取り掛かったのが遅く、時間との戦いとなった。
■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)
 |
●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月11日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月16日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
キャンパスの銀杏並木。とうに葉は散り落ち、梢が空にくっきり。彼方を雲が流れていく。枝間を過ぎるのを見ていた。首が痛い。
足元には、今まだ落ち続けているギンナンが転がる。ほとんどは容赦なく潰されていくけれど。学生は避けて通ることもしないのか。
晦日の頃、すっかり降り止み、ギンナンはすべて落ち尽くしたかと思った。そう言えば、昨年も一昨年もそうだった。枝から容易に離れず、
ずうっと、”へばりついて”がんばるギンナンがいた。ギンナンの塊が、梢の先で震えている。今日は、ことし一番の冷え込みだ。
授業開始。「絵画造形活動Ⅱ・応用」 課題 「11片タングラムの自由表現」。時間があれば「絵変わりカード」アイディア研究。
| 12月のアトリエだより |
■鳩山は冬景色。枯れ葉で埋め尽くされる
アトリエの周りはすべて枯れ葉で覆われた。この間まで鬱蒼と茂っていた木々は裸。空が広がり明るくなった。
ブナの木だけが薄茶色の葉をまだ落とさずにいる。風に飛ばされまいと、しわしわの葉の塊がしがみつくように付いている。
枯葉を集めて井戸を改造した腐葉土枡へ運ぶが枡はすぐ満杯。諦めた。「一面枯葉の野」に与すパワー不足だ。
創作行為とはことなるが、草取りや枯れ葉集め……これらは、妙に楽しい。いえ、楽しいとは違う。何も考えない時間を
すごす嬉しさかなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
ノロウイルスか、風邪か。張り切ろうにも力がでない。普段から低体温で、一寸でも熱っぽいと頑張ろうにもだるさには抗えずダウン。
今年も無事に乗り切ったかと油断したわけではないけれど、この暮れ、最後の仕事にブレーキがかかる。とはいえ、しがみつくように
ダラダラと作業。 熱が引いて、即コートへ。鈍った体に喝を!荒療治!………無謀なり。
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
師走になり、日が過ぎるのが一入早く感じられる。毎年のことだが……。追いかけられているようだ。追いかける位の
心の余裕がほしい。アクセク、バタバタ、アタフタ……で、今年も暮れそうだ。 嗚呼。
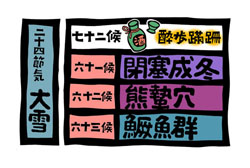 |
12月7日は大雪 (12月22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
■寒さものともせず(ウソ、大強がり)テニス
昨日は冷たい雨。幼稚園講演会。会場は100名を越し満員だったが、冷え冷えとしていた。終了後のサイン会では、足元が冷たく
膝をすりあうようにした。寒かった。
今日は曇り。オムニコートは湿っているだろうが打ちに行く。メンバーはぼくより高齢な方が多い。それも、週一のぼくと違って、
週三、四回はプレーしている兵ばかり。捻られるのを覚悟の上参戦!ただ時間を気にせず打ってみたい。忙しないなあ。
■鳩山は落葉の季節。”目の幸せ”紅葉もおしまい
モミジは峠を越えた。サクラはすべて葉を落とした。ブナの茶葉、カシワ、モクレンの薄茶色……、あたりは茶色に染まっている。
中で鮮烈な赤色を留めているのがハゼだ。植えてよかった。来年はもっと植えよう。ローズヒップ、ブルーベリーの葉も。
雨に洗われて秩父の山並みがくっきり見える。日差しも柔らかく、のんびり……としたいところだが、仕事仕事!
描いている10号の絵を二枚直しをいれる。フレームの製作にも着手。手を洗う間もなく車上の人。慌しい。よくないなあ……。
■師走……キャンパスを走る……アタフタ アタフタ
授業はいつも時間が足りない。演習科目のつらいところだ。準備や試作で休む間もない。研究室に来訪者があれば、昼飯抜きとも
なり、空腹と戦いながらの教室。この季節も汗びっしょりで、キャンパスの風が一入冷たく感じる。気力で持っているのだろうが、
おかげでメタボとも無縁、カゼ菌も寄り付かず元気。(多分に、やせ我慢)
■小石に絵付け 3


・ジェッソ(下地剤)を塗り描く。顔、顔、顔…… ・人面石 ・拾った(顔が描かれていた)石
| 11月のアトリエだより |
■小石に絵付け 2


紙芝居《やさしいこころ》に添えて配ろうと、小石に登場人物”おにぎりん”の絵を描いた。
今日の授業は先週に続きPEEK A BOO……「いないいないバー」は幼児が好む遊びの一つ。紙一枚で2場面、4場面
変化するカードを制作した。仕組みは簡単。学生は思い思いのイラストを描く。シンプルなものほど応用性がある。遊び方も
工夫できる。スイッチを入れたらお終いのICを使った高価な玩具より、やはり手づくりだ。工夫の余地があるかないか。
想像力と創造力を育む遊び、玩具とはどんなものかを学生には考えさせたい。
■二十四節気 <小雪> 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
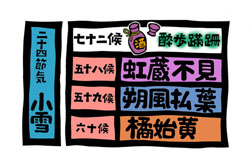 |
11月23日 小雪 (12月7日 大雪) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
アトリエまで、今日は関越高速を使わず川越街道を走る。三芳あたりのケヤキ並木の紅葉が目当て。春から夏、
街道を覆い隠すほどだった緑のトンネルは葉を落とし秋空をのぞかせていた。今年は遅いのか。黄色、茶色、赤色……の
紅葉はまだだった。このあと、一気に紅葉、黄葉がはじまり、嵐のように葉を落とすのだろう。残念だが見られそうもない。
アトリエの庭のハゼは鮮やかな紅色。ブナは茶褐色、桜、モミジ……冬の入り口、風に震え、舞い落ちる……色の饗宴、
静かな時間、心穏やかなる一時。
■小石を拾う……形を楽しみ、絵をつける



校内の駐車場の脇で小石を拾う。一つ一つ形を吟味しながらビニール袋に入れるぼくを、学生や教員が怪訝そうに見ている。
20個、30個、相当な重さだ。洗って改めて形を眺める。石に絵付けをするのだが、なんと”先客”がいた。顔が描かれた楕円形の
小石があったのだ。小学部もあり、子どもが描いたのだろう。見つけたときは、思わずにっこりだ!嬉しくてねえ。描かれた目、鼻
、口はかすれてはいたが白色が美しかった。これを描いた子と会いたいなあ。
紙芝居『やさしい こころ』を制作した。少年と作業服を着た工事現場のおじさんが登場するお話。そのおじさんの顔がおにぎり
そっくりで、少年は<おにぎりん>と呼んでいた。少年は図工の時間、小石に絵を描いた。ペンギンやカメや自動車などいろいろ。
<おにぎりん>もね。 中央の写真はぼくが作った<おにぎりん>。おにぎり形の小石は結構多い。幾つか作って、紙芝居を演じる
方に差し上げようと思う。”実物”を見て、子供たちが、自分でも作ってみようと言う気になったらうれしい。
■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)
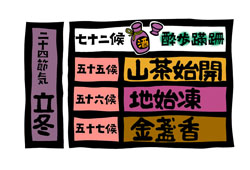 |
11月8日は立冬 (11月23日 小雪) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■赤い実の季節
鈴なりの渋柿が熟して枝を撓らせている。ナツメが落果。サルナシも柔らかに……、
カマツカの暗紅色、カラスウリの朱赤……陽に照り映え、今 秋真っ只中。






面白い実を見つけた。見たことのない形、蔓に二十数個の赤い実の塊まりが10センチおきについている。蔓は「長い。引っ張り手繰って
根元まで近づこうと試みるが、山の斜面が崩れやすいこともあって難儀。根は深く、球根を持っていた。わがアトリエの庭で育ててみたくなり
図鑑で調べた。サルトリイバラ……ユリ科の多年草。実もそうだが、葉の脇に一対の髭があり、この特徴からすぐ名前が解った。
細いさつまいも状の球根は漢方薬「山帰来」となる。北斜面の日当たりの悪い茂みの中で育ったサルトリイバラ……大事に、といっても
似たような場所に移植、根付くよう祈った。
| 10月のアトリエだより |
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
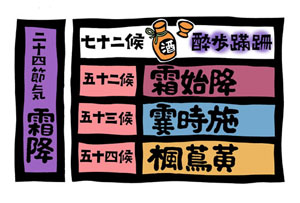 |
10月24日は霜降 (立冬……11月7日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
24日は二十四節季の霜降なれど、汗ばむほどの陽気。現代童画展審査に臨んだ。25日は一転襟を立てて歩く寒さ。終日、
審査会場に詰めていて分からなかったが、木枯らし一番が吹いたのだそうだ。賞の決定、推挙会議と慌しかった。
『現代童画展』第37回!ぼくも、まあよくも出品し続けたものだ。本年の目玉は、過去の大賞作品を集めての特別展示。
ぼくは第3回展で大賞を受賞したが、その作品も久しぶりに”お披露目”。ただ、会場が狭いため、『星の海』一点のみ。
『花の野』が飾れないのは残念である。
本展出品作は『星の道』。 7月の選抜展で発表した”『沈黙の闇』の後”を描く。 選抜展をご覧下さった方は、
イメージを重ねていただけたらと思う。
鳩山アトリエ、秋真っ最中。ハゼの紅葉がはじまり、パンパスグラスに絡むカラスウリが風に揺れている。こっちに一つ、あっちに一つ……
濃い朱赤が目の奥に染み込んでいく。雑草に負けずに蕾を抱いたニオイスミレを見つけた。数株集め周りを煉瓦で囲い”スミレの園”に。
イーゼルから作品を降ろし車に積み込んだ。いつもながら、アトリエ立ち去りがたし。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)
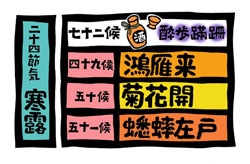 |
10月9日は寒露 (10月24日は霜降) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展は東京都美術館が改修工事のため、本年も上野の森美術館で開催される。会場壁面の都合で30号とサイズも
制限される。大作に臨みたい気持ちも強いが、この春以降モチーフが少し変わってきており、画面の小ささはさほど気にならない。
今まで <心のふるさと……懐郷の詩> <親子・父と母・父性・幸福感>を描いてきた。今回の作品も底辺に流れるものは、
そう変わらないが、さりとて明るいものでもない。春は『沈黙の闇』。今仕上げの段階にあるのが『星の道』。絶望感の中に一筋の
光明……出発だ!それも力強く、頼もしく、矜持を……ぼくは描く。是非ともご高覧あれ。
(展覧会詳細については後日)
■キャンパスのイチョウの木、銀杏落ち始める
教室の机の間を歩き、いや小走りで回っている。コマネズミの譬どうりチョコチョコ忙しなく。声がかからずとも、その人その人
描き出すものの、ユニークな点、おもしろい所を見つけようと。見逃すまい、学生は気が付かない線の流れ、動きを。
教室の暑さは一頃とくらべ過ごしやすくはなったが、ばくは汗びっしょりだ。授業を終え研究室に戻るまでの僅かな時間、
秋の風を満喫。深呼吸して歩く。銀杏を踏まないように避けて、コマネズミは時間を惜しみながらゆっくり歩く。
| 9月のアトリエだより |
■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)
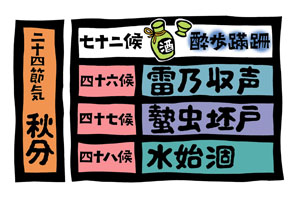 |
9月23日は秋分 (10月9日は寒露) ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
■鳩山、冷え込む!長袖で板絵に向かう



二日間、板絵に取り組む。
アトリエから一歩も出なかったと言うのはうそで、体、殊に目を休めるために鬱蒼としげる葉を掻き分け栗の木まで進む。
まさにジャングルを”進む”感じ。栗を拾おうにも腰高の草が邪魔して、落としても見つけるのが大変。それでもビニール袋は直ぐ
いっぱいになった。
幾種類か植えた萩は雑草に覆われてしまい目を凝らさねば小花が見えない。
自然に生えた道路沿いの柿の木には青い実が枝を撓らせている。大豊作だが残念ながら渋柿。辺りにフジバカマが咲いている。
紅葉は”ハゼが一番”と植えた苗木は雑草に囲まれながらも育っているが、葉の色はまだ緑。アトリエの窓からは見えないが、
工作部屋のわきの山葡萄の房が膨らんでいた。昨年、一昨年と実がつかず枯れたのかと……、今年ヤマブドウの苗木を求め、
近くに植えたのが良かったのかもしれない。ナツメもサルナシもよく実った。マタタビ、ムベ、アケビは葉を茂らせただけで終わった。
アケビは花を沢山咲いたので、実りを待っていたのだが……(アケビの皮のバターソテーは好きな酒肴)
「30分だけ」と予定しても、庭に出れば一時間くらいすぐ過ぎてしまう。制作に没頭も集中力のなせる業だが、自然に実を置くのは
もっともっと自然体。自分の素を丸出しにするという点で、自然に身を置くことと創造の世界に住むことは似ている。
下の田圃の主、石井さんが新米と玄米を届けてくださった。
軽四輪の助手席にはいつも満面の笑みの奥さん。アクをすくい、すくい丁寧に煮あげた栗の渋皮煮、栗の形をきれいにそのまま留めた
上品な味、見事な”作品”を持ってきてくださった。石井さんの前で、ぼくは二つもペロリ!美味い!感謝感謝!
秋の味覚、贈り物が嬉しかった。 気力充填して、仕事に戻る!
■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)
鳩山は大気澄み星が降るようだ。今晩は星の瞬きを妨げるような明るい月夜。十五夜だ。中秋の名月、観月のゆとりもなく、
アトリエでパネル作り。プリンター置き台も製作する。工作は性に合っており楽しくて、なかなかその後の、“本来の”制作に
はいれないで困る。
もろもろの教習、講習会も終わり、秋学期が始まるまで制作に没頭する。時間がなくあせりながら……いつものことだが。
ナツメが赤く色づき始めた。サルナシが頭を下げねばアーチをくぐれないほどたわわに実った。栗の実はやたら降り落ちている。大粒だ。
地域物産販売所でアスナロの幼木を見つけた。“明日は檜になろう”から翌檜と書く。百円!。植木鉢代にもならないだろうに。
勿論買って、杉の木の根元に植えた。吾、アスナロと思ったことなし。今思えども、もはや遅し!
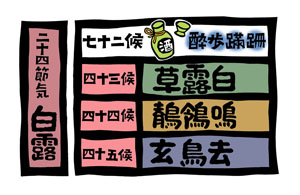 |
9月8日 白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
| 8月のアトリエだより |
■二十四節気<処暑> 七十二候 (四十候、 四十一候、 四十二候)
 |
8月23日は処暑 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月29日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月3日) ・いなほ みのる 稲が実る |
■楽しきかな、ブリコルール!
牛乳パック、ペットボトル、ガムテープや食品ラップの巻き芯などの山に埋まる生活をしている。図工の先生方の研修会に
ブリコラージュを基本テーマに選んだ。(ブリコラージュ人間をブリコルールという) 廃物を活用しての造形遊び。遊びといっても、
楽しめるだけではなく、美しくて飾っておきたくなるようなもの、かなり雑に扱っても壊れない頑丈なものの考案だ。遊戯性と造形美!
工作は楽しいが、わが渋谷の狭き仕事場は、ゴミ箱と化している。フローリングや空間はいつになったら、再び現れるのだろう。
■鬱蒼と生い茂る鳩山の庭……ハチとの戦いはじまる
鳩山のアトリエで教員研修会の“メニュー”作りをしている。最近、わが鳩山町は熊谷に次ぐ暑さで
、テレビに地名のテロップ流れる始末。地形が似ているのだろうか。暑い!でも夜は東京より涼しく感じられる。
土と緑のおかげだ。伸び放題の木々、背丈を越える雑草にも感謝だ。
喜んでばかりはいられない。誰も踏み込まないのをいいことに、ハチが我が物顔で飛び交っている。
デッキを補修、ペイントしようとして蜂の巣を発見!ご飯茶碗ほどもある。スズメバチなら手の負えないから業者に
頼むが、幸いにもアシナガバチだった。防護服でいざ戦!二挺拳銃よろしく両手に防虫スプレー、棒で巣を掻き落とした。
アシナガの群舞は恐ろしいほどだ。巣がなくなっても、ハチはどんどん集まってくる。ペイント作業は中止だ。
階段下の薪置き場にもう一つ、アシナガバチの巣を発見。これも退治。仕事どころではない。いま、巣作りの季節だ。
取っておかないと大変なことになる。昨年はスズメバチに悩まされた。そういえばミツバチがいない。アトリエの壁の間に
巣作りし蜜を部屋に滴らせたミツバチは何処に消えたのだろう。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
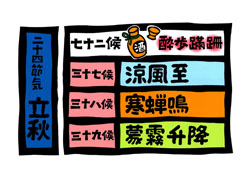 |
8月8日は立秋 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■大学のオープンキャンパス 《子ども教育学科》受講生みな熱心!
今年のオープンキャンパスはティーチングアシスタントに大学二年生三名を起用。万全の態勢で臨んだ。
一時限の授業で、早朝からの出席を心配したが、生徒がつめ掛け満室状態。アンケートでは「満足」が多く、
アシスタントと喜び合った。三名には、月末に行われる教員研修会でも、手伝ってもらう。彼女らがいると、
教室が明るくなる。
研修会が終わる間もなく、幼稚園教員指導が待っている。園児が作って遊べる、“凄くおもしろい”おもちゃを
披露しようと今、試作を繰り返している。仕事場は雑然!がらくたの山だ。本来の絵画活動が
疎かになっている。制作に入れるのは9月になってからか。目の前の仕事が多すぎる!
■ホップの間に植えたもの
珍しいものを植えた。日差し避けにゴーヤや朝顔が話題になっているが、ぼくは野ブドウを植えた。
ホップの苗が育ち、180センチのトレリスから蔓が巻きつくところを探して揺れている。そのホップの間に
これまた蔓性の野ブドウ。
山葡萄はある。枯れかけたが今年見事に再生、今小さな固い実をつけている。
山葡萄の掌より大きい葉っぱと違い、野ブドウは小さいが形が美しい。野ブドウは食べられないが
葉を見ているだけで、何だか嬉しい。この炎天下、根が着くか心配だ。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
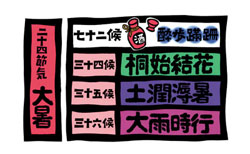 |
7月23日は大暑 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 3日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
■ミルクカートンTOY


・(左)3単位体 テーマ クリスマス菓子 ・(左上) スイーツ ・(右上) 泣き笑い
・(右)1単位体 こんなこいるかな ・(下) こんなこいるかな


・ペロ&ミャー
今回の廃物利用ミルクカートンTOY。牛乳パックを開き裏返してカット。三枚組み合わせたものが1単位体。
その単位体を三個単位でつなげて行く。学生は時間の関係で2単位体の構成がやっと。ぼくは3単位体構成、
4単位体構成の作品を見せた。一単位体で12面ある。それらすべてに絵を描くか、切り抜いた写真を貼る。
6面が泣き顔、6面が笑い顔……、コツが解れば絵変わりもスムーズにできるが、初めての人は面食らうだろう。
面白いキューブパズルだ。学生は思い思いの動物や表情豊かなお化けの絵をつけて、友と交換しては楽しんでいた。
遊びを通じてのコミニュケーションも狙いの一つ。時に”学び”は楽しさの中で行われる。
| 7月のアトリエだより |
■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 小暑 (7月23日 大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月13日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
7日は<小暑>。《温風至る》だが、熱風の”風”さえ吹かず。教室も節電のため空調の温度設定厳しく汗まみれの授業だ。
新校舎は”モダンデザイン”で窓が開かない。暑さには強いぼくも閉口の日々。絵の具を乾かすためドライヤーを使うときなど、
もう炎熱地獄。我慢我慢。
■現代童画会 選抜展開催中
現代童画会 選抜展が只今開催中。 (銀座アートホール10日まで)
板絵『沈黙の闇』を出品しております。ご高覧ください。”蒼”の表現に悩んだ作品です。

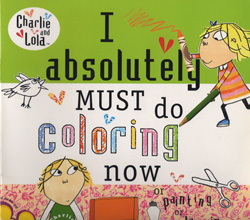
アストリッド・ リンドグレーン展(世田谷文学館) 《長くつしたのピッピ》《やかまし村シリーズ》《ロッタちゃんシリーズ》原画を見る。
子どもの時代、子どもの世界を生き生きと描いたリンドグレーン。見慣れた挿絵から、現代のアーティストのイラストまで多数展示。
中では、ローレン・チャイルドの《長くつしたのピッピ》。一目でわかる、キュートな表情。目が強い。
ローレン・チャイルドの塗り絵本(ペーパーバック)を持っているが、塗り絵には否定論者であるぼくも、この絵本には魅力を感じている。
ただ塗るだけのカラーリングブックではなく、自由に描きこめ、またそのリードして行くネームが効いている。塗り絵本は数々あれど、
このようなものがもっとあったらと思う。
| 6月のアトリエだより |
■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
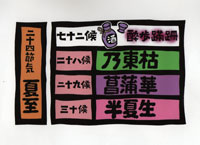 |
6月22日 は夏至 (7月7日/小暑) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■スタンピング……葉脈の美しさ……人工物との組み合わせ


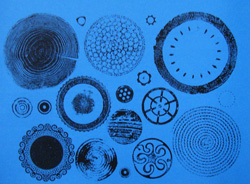
トチ、サンショ、トチュウ(杜仲)、ウメ、 クヌギ、ムベ、ベイ、リンデン、メープル、ブナ、ナナカマド、オニグルミ
絵画造形表現活動基礎Ⅰの授業。オートマティック技法(モダンテクニック)。要は子どもの造形表現遊びの基本。
デカルコマニー、フロッタージュ、スパタリング、ウオッシング、コラージュに続いて、今回はスタンピング。自然物(葉っぱなど)と人口物を
ペタペタ押して再構成。こらー^ジュ作品の制作。
鳩山で葉っぱを採取。形の面白いもの、葉脈が鮮明に写し取れそうなものを選ぶ。3クラス分を冷蔵ボックスに詰める。
クヌギ、山葡萄、菩提樹、桑、サンシュユ、ハナミズキ、オニグルミ、オオシマザクラ、イチョウ、モミジ、サトウカエデ、山椒、
ブナ、トチ、トチュウ、ワイルドストロベリー、ヤツデ、ミニチュアローズ、ローズゼラニウムなど。学生には植物の話(名前の由来、エピソード)も
聞かせた。ローラーを転がし刷り取った者をカットし台紙に再構成する。楽しめたようだ。
ウオッシングについで面白かったとの声も。演習は先ず楽しむこと。楽しんでこそ学習となる。みんな、始めはインクが手に付くのを
嫌がっていたが、仕舞いには指紋どころか手にローラーを転がし手形をペタペタ押していた。
とにかく夢中にさせること。集中させること、これに尽きる。
ローラーやインクバットを洗ったり、葉っぱの始末など後片付けが大変だが、学生の”満足感”が、ぼくの疲れを軽減させてくれる。
次回は墨流し、マーブリング。ぼくは市販のマーブリング剤やセットになったものは使わない。墨のマーブル模様の美しさ、そして
油絵の具を溶いたものを掬い取るカラー版にTRYする。出来合いのマーブリング液を使えばきれいでかんたんだが、それでは
力がつかない。すべて作る。大事なことは、「これがなければ出来ない、これが揃ってないとダメ……」ではなく、応用力、創意工夫する心。
表現とはそういうものだ。準備万端、用意周到からは生まれない。不自由なくらいがいい。足りなくてちょうどよい。恵まれすぎは、
想像力や創造性を培う環境によろしくないとぼくは思う。
■木っ端で名札を作る



・木っ端 (切り抜かれた円形の上部) ・両端をカット (ステインを塗ったもの) ・黒ペンキで名前を書いて完成
地域の産物の即売所ができた。米、果物、野菜の農産物が主だが、植物を売るコーナーもあって、鳩山に行くときは
必ず寄ることにしている。都会の園芸店では見られない面白いものがあって楽しい。キンズ、カマツカ、ヤブコウジ、ハゼ、
マートルの苗木はみなここで買った。一鉢500円~800円と安い。アトリエの畑に茂るムベやサルナシも珍しいと思っていたが、
これらも売られていたからびっくりだ。
即売所には木工製品もある。まな板や鍬の柄。ぼくが買うのは木っ端の束。何かを切り抜いた残材、10枚束ねたものが、何と120円!
昨年は100円だった。これをぼくは名札に利用している。もう数十枚は作っただろう。ブナやクヌギ、昨秋植えたオオシマザクラなど
樹木の苗木が主だが、まだまだ足りない。販売物にはすべて生産者の名前が記されている。木工製品も然り。○○清作……。
この木工の主はどんな方だろう。
このなだらかな山型の木っ端は何を作った後の物なのだろう。大量に出るから不思議だ。「清作さん」に聞いてみたい。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候
 |
6月5日は芒種6月6日 (夏至は6月22日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
■板絵「沈黙の闇」制作没頭。
夜来の雨があがり鉛色の空、水田は天を写す鏡だ。周辺緑一色の中で銀色反射、”何も無い美しさ”だ。小鳥もまだ訪れず
静寂そのもの。幾度も深呼吸をしてアトリエに入る。
このところ週末は板絵に取り組んでいるのだが、モチーフが<哀しみ>そのもの。描いていても辛くて苦しくて感極まってしまい、
「これではいかん」、冷静に冷静に……言い聞かせながらの作業。
顔の色が出来ない。塗っては「違う」、塗り重ねては「違う」の繰り返しだ。絵が重く暗い。描けなかった時から、絵筆を
取る、表現する気力漲るまで時間を要した。『哀しみの船』、『悲泣の丘』以来だろう。胸が塞がる思いの制作は。
■茶の木を探す
今年も茶の木の新芽を摘んでフリッターにして食べた。香りがよい。もちろん酒の友。制作の後の「反省の酒」だが、目一杯
表現出来さえすれば美酒となる。なかなか、そう美味くはいかない。
Sさんが、茶を育てたいと言う。苗木を差し上げたが、楽しみにしていた新芽が何者かに採られてしまった(消えてしまった
そうな)と、がっかりしておられた。そこで今回は少し大きめのものを用意した。零れ種からあちらこちらに発芽しているが、
適当なサイズのものを選ばなくてはならない。植木鉢がSさんの自転車の篭に収まらなくてはならないから。
新芽は手もみ茶に、おひたしに、天ぷらに……、すくすく育ちますように。
■学生の習作を発表する場がほしい
子ども教育学科には、ほぼ隔月発行の『ミンミン新聞』があるが、学生の制作物が発表できるページの余裕はない。
絵本でも数冊、ペーパーカッティング「シンメトリーデザイン」や連続模様制作でもかなりの秀作があった。講評して返却するのだが
何とも惜しい。作品を並べて見せるが、他のクラスの学生には鑑賞させられず残念だ。創作する一方、良い作品を見ることも大事だ。
一部修整、補作し学生に”作品集”として配布することにした。学生は色んな紙で(薄い色など)自由に制作するから、
版下にするには墨画線に置き換えなくてはならない。一昨年も作ったが、この作業は時間がかかりめんどうくさい。
「素晴らしい作品を作った」……学生に自信をもって貰いたい。園や学校の現場でも制作のヒントに資料としてきっと役に立つだろう。
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
ホップを植える! 実を何に使おうか……早すぎる夢想……
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (6月1日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
アトリエ周辺の田圃は田植えが終わり人影なし。水面を横切る鳥の影。静寂の中に時おり鳥の声。「ホーキョ」「ホーキョト」……
下手だったウグイスも「ホーホケキョ」。すっかりうまくなった。
東北の被災地では作付けを諦めた水田が多いという。緑の苗が黄金の稲穂に変わるまで、ずーっと惨い災厄が頭から
離れないだろう。
絵を描いていても、テキストを作っていても、お話を書いていても、胸は重苦しく、気が晴れない。集中力乏しく苛立ちを覚える。
創作はいつだって厳しいものであるが、これほどキツイとは……。
気分転換のテニスも楽しめない。”逃避”だからであろう。大分前のことだが、サッポロビールが運営していたクラブでプレーした
ことがある。このコート脇のフェンスで、さすがビール会社だ、ホップを育てていた。ホップが高さ10メートル以上も薄緑のカーテンを
作っていた。今ゴーヤなど壁面緑化が話題になっているが、あの、コートを覆い隠すようなホップは見事だった。
少し失敬してきて、ホップのリースをつくったこともあったっけ。
そして、とうとうホップの苗を手に入れた。野生のものではないが、自然に還したいと、竹やドクダミやスギナの生い茂る土地を耕し
腐葉土を敷き詰め苗床を作った。トレリスを立て水を遣る。
しっかり根付きますように!少しだけ、ほんの少しだけでも実をつけますように。
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
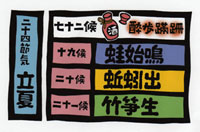 |
5月6日は立夏 (5月21日は小満) ・十九候 (5月 6日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
■アトリエのフェンス倒壊す
筆を取る、板に向かう気力興らず。胸は塞がったままだ。それでもアトリエに入れば……と、久しぶりの鳩山詣で。だが、
それどころではなかった。地震か強風か、フェンスが倒れていた。フェンスと言っても三寸の角材を組み合わせた頑丈なものだ。
それが、道路に沿って横倒し!滅多に人が通る道ではなく事故に繋がらなかったのは幸いだった。連休中だが、設計図をひき
工務店を呼んで交渉した。
■今年はミツバチ大丈夫…………か。
昨年は全国的にミツバチの姿が消え、何が原因かもわからず問題になった。わが鳩山の庭でも明らかにその数が減少した。
それまでは乱舞する大群、母屋の壁の間にも巣を作り蜜をたらすミツバチだったのに。今年は大丈夫……かもしれない。
花の間を忙しく飛び交っている。カマツカの小さな花から、アケビやムべの花、少し前までは、ミツマタ、杏、サンシュユ、
プラムなど、花の季節をミツバチは我が者顔だ。



・百花繚乱……ミツバチの季節 ・アケビの花(五つ葉) ・カマツカの花


・ムべの花 花弁に見えるのはガク。 ・たった一輪咲いたリンゴの花(ヤーノシュの絵本『おばけりんご』の一ページを彷彿)
乳白色で内部には紅の線
| 4月のアトリエだよりエだより |
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
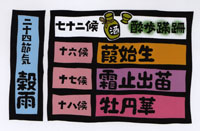 |
4月20日は穀雨 (立夏は5月6日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (5月1日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
新学期が始まった。『実践遊び学』3クラス。『絵画造形表現活動・Ⅰ』3クラス。昨年よりパワーアップした授業展開をしたい。
具体的にはカリキュラムの調整以外に、『実践遊び学』では殆ど毎回、”おまけ”と称してごく簡単にでき、子どもをアッと言わせる
楽しい造形手遊びを紹介していく。そして『絵画造形表現活動』では、”帽子百貨店”と題したクラフト製作を、今まで十数点だった
ものを、今年は創作5点追加、学生にはかなりハードな作業(時間がタイト・集中力勝負)となる。
月曜日『実践遊び学』第一回は、鏡面紙を用いたシンメトリー図形遊び(製作・発見)および万華鏡考察。製作だった。この時の
”おまけ”は、「紙一枚(A4大)左手のひらに穴を開ける」法………というものであった。紙をクルクルまるめ円筒形にする。これを
用いて掌に穴を開けるには、さてさてどうする?(授業では万華鏡作りに用いる紙筒でやらせた)
「あっ、あいた」「穴が開いた!」「向こうが見える!なに、これ!」「わあー!」教室がどよめいた。
「穴があかない」「えー、穴、見えない!」何人かは、始めうまくいかず、とまどっていたが、学性同士教えあって全員、手に穴が
開いたことを”確認”した。一体、どうやって手のひらに穴を開けたのでしょうか?
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
杏の花が咲いた。明るい青色の空のもとでミツバチを誘っている。ミツマタ、サンシュユの黄色
土佐ミズキの淡い黄、レンギョウも。やはり杏がいい。杏の白を際立たせるかのように、空には雲がない。
遠慮してくれているかのようだ。杏は梅の花をふっくら大きくした感じ。清らか。
穏やかな日和、春景色。平安なれど、このところの心中、苛立ったまま。
オニグルミ、カマツカ、ブナ……まだまだ、芽は堅い。ときおり吹き来る(荒れる)冷たい風が木々を揺らしている。
ケキョ…ケキョ… ウグイスの囀りトレーニングも始まった。 さあ、我も始動!!!
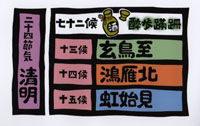 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
| 3月のアトリエだより |
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
板絵 『おやすみの前に』 完成!
 |
3月21日は春分 (4月5日は清明) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
天変地異、大震災。胸塞がる。
4月4日開催の現童春季展出品の作仕上げ作業中だった。言葉を失う。筆は止まる。
父と母と子の関係を描いた 『おやすみ前に』 は、もっとも心やすまる刻の物語。でも、
むごい光景を映像を見、今や表現の気力失せる。
何としても描かねば、表現せねば……。無力感。
己が抱えた悩みに埋もれているうちに世界は大変なことに。
厳しい便りもいただいた。その方は体の不調にもめげず”感謝の念”を
語っておられた。なんという心の広さ、包み込む温かさを感じ、
自分の甘えを情けなく思った。。厳しさ、苦しみの深さは人それぞれでも、みんな、みんな大変なんだ
……当たり前の事……、自戒自省。
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
過去はなし。未来も定めなし。あるは今のみ。脚下照顧。拘りから離れられれば活路もあろうというもの。が、その拘り
だらけで(雑事が人生ではなかったのに。いや人生は雑事の中にあるのかも)忙殺される日々。このところ寒暖の差が大きい。
それでも北風が止むと春を思わせる日差しが。春三月。怠惰の我が身に、鞭をくれねば!
■二十四節気<雨水> 七十二候(四候.五候.六候)
 |
2月19日は雨水 (啓蟄 3月6日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
激しかった夜来の雨嘘のように上がるもわが心、暗闇にあり。仕事に逃げ込む不埒な心を嗤い、
見張りの「もう一人の自分」が攻め立てる。手は止まり作業も捗らず。我慢……しかない。
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候
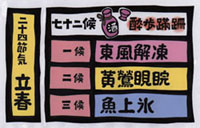 |
●2月4日は立春 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
鳩山の枯野。寒空、一切の葉を落とした木々の枝がくっきり。常緑樹も萎れ勢いは無い。ロウバイの香しさが消え、梅がプチッと
はじけ始めていた。幾分か柔らかになった光の中に春の訪れを感ずる。が、ぼくの心は今や冬真っ只中。芳しくないこと、
身に降りかかる哀しいこと……、暗澹たる思いに沈み、浮き上がる気力もなし。制作空間に身を押し込めて自ら鞭打つしか、
癒しはあり得ない(かった)ことはぼくの人生経験上の結論なのだが……。それさえも……今は。
| 1月のアトリエだより |
■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)
 |
●1月20日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■現代童画展出品作 (上野の森美術館)


■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)
 |
●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
| 12月のアトリエだより |
MERRY CHRISTMAS


師走でなくとも、アタフタ……。安らぐ時なきまま歳が暮れようとしている。嗚呼………。
[日々新生・日々創造] を胸に抱き歩むも、我が羅針盤、現実路線に針路。頑な。
”静かな創作の日々”は夢か!今年、描いた板絵の少なさよ……情けない。
自省自戒の念で多分また大晦日の深酒……。進歩ないなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■『紋型切り紙』の研究 『紋型』から『切り紙』へ
江戸時代は寺子屋でも教えていた紋切り型あそび。明治、大正、昭和……小学校の図工教科書で
どう取り上げられて来たかを調べている。(昭和30~60年代は盛んだった)平成の教科書ではごく小さく載っている程度。
姿が消えたも同然だ。
紙を折りはさみで切る。開くときの驚き、ワクワクする遊びだ。壁面装飾、カード、モビールにと使い道は多く、折り方の
工夫やカットの技術、ポンチの活用など奥が深い。1回折から4回折まで、サンプル作品を100は作ったか。
今回は1、2、3、4回折りまで学生に試させたが、蛇腹折り(屏風折り)は連続模様として別に時間を設け制作させる。
時間があれば切り絵にも挑戦させたい。例としてデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの切り絵でも
見せようか。学生に思う存分自由に紙を切らせてみたい。
・創作切り紙
中央の「二つの馬蹄に挟まれた四葉のクローバー」は、明治39年1月1日小山内薫がドイツから
森林太郎に宛てた年賀状にあった図案をもとにデザインした。
上下の作品は、切り紙「一回折り」で制作
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
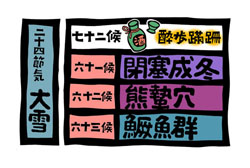 |
12月7日は大雪 (22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
| 11月のアトリエだより |
■二十四節気 <小雪>、 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
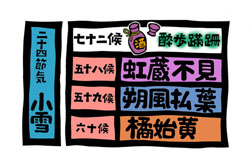 |
11月22日は小雪 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
冷たい雨。キャンパスの舗道にイチョウの葉が張り付いている。踏みつけられ潰れた銀杏も。研究室、先生の在室ランプも
殆ど消えた9時半、大学を出る。寒い。ノートパソコンと大量の制作教材の入ったバッグを肩に、傘を風に飛ばされないように
傾げ持ち駐車場まで歩いていく。
自分の制作が出来ない日々を送っている。このところ学生に見せる教材サンプル作りに明け暮れている。が、これはこれで面白い。
「PEEK・A・BOO(いないないばー)」カードのアイディアを考え、試作するのだが、1枚の紙の可能性追求でもあり、奥が深い。
基本形は裏、表の変化。回転(たとえば、こぶた→たぬき→きつね→ねこ)。めくり。折りなど。 今回は”めくり”に挑戦させる。
「カーテンの向こうは?」カーテンを開けるとどうなるか……。
この制作と遊びは、想像力を鍛えることになる。学生は日頃、「正しい答え」を求めて学習する。自らの考えを述べたり、表現したり
する機会は少ない。造形表現活動を通じて、答えのない世界もあることを、その大事なことを解ってもらう……それも狙いだ。
(NOV.22)
■ 現代童画選抜展 (地方巡回)作品戻る

現代童画展選抜展は銀座アートホールで開催後、四国、関西を巡った。
今年の出品作は「どんぐり嵐」 鳩山のアトリエに埋めたクヌギのドングリ(近くの公民館の庭で拾った)はあちこちで
芽を出し、今漸く腰の丈。
昔からあったマテバシイは剪定の失敗からか元気がない。毎年降るようにドングリを落とすが今年は地面にパラパラ
見かけるくらい。マテバシイのドングリでドングリ煎餅を焼いたことがあるが香ばしくてうまかった。クヌギのドングリは
食べられないけれど、ヤジロウベイやコマが作れる。なんといってもあの形が良い。
我がクヌギがドングリをつけるのは、ずうっとずうっと先のことだろう。下草を狩り、水を遣り幼木を育てる……”夢見”が楽しい。
■二十四節気 <立冬> 七十二候 (五十五候.五十六候.五十七候)
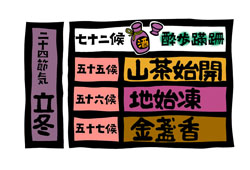 |
11月7日は立冬 ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■「紋型切り紙」を見直そう。けっして”紋切り型”のつまらぬ造形ではない
仕事場は紙くずの山。このところ「紋型切り紙」の原稿書きで色紙を折っては切る、折っては切る……。1回折りから5回折まで、
様々なモチーフをデザインしている。「紋型切り紙」は江戸時代は寺子屋でも教えていた。紋所を染めたり、商売でも子どもの遊び
でも紋切り型はポピュラーなものであった。明治大正、そして昭和の20年頃までは図工(当時は手工)の教科書にも載っていた。
”自由な制作”が教科書の編集方針に変わるとともに、紋型切り紙は姿を消した。昔からある紋や、定番の梅や桜や桃の花を切っ
ている限りでは”紋切り型”の名の如く、創造性、独創性は無いとの謗りは免れないだろう。が、日常性(紙一枚、ハサミがあれば
出来る)伝統の美しさ(継承)、幾何学性、手技の練磨(微細な運動----右脳の活性化)、コミュニケーション能力(教えあう母と子、
友達)など、得るものは多く、肝心の創造性に於いても、自由な造形をテーマにすれば、幾らでも独創的な、たった一つだけの作
品が出来るわけで、子どもに是非ともやってもらいたい造形表現の一つといえる。
1枚の紙でどれだけ遊べる?表現できるか? ……ゲーム機世代の子ども達を導くのは、大人の責任だ。素材の可能性を
最大限に引き出せるか否かは、想像力と創造力それに感受性次第。生きることはそれらを磨くことと考える。
■第36回現代童画展(上野の森美術館)
今年と来年は東京都美術館改修工事のため、会場が上野の森美術館となります。お間違えにならないように。
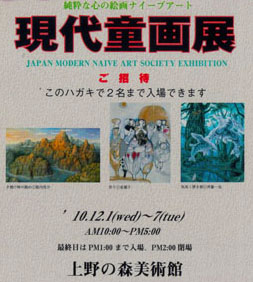 詳細は「展覧会」のページをご覧下さい
詳細は「展覧会」のページをご覧下さい■ 『相生祭』にて講演します -----きみはやだもんを しってる?-----
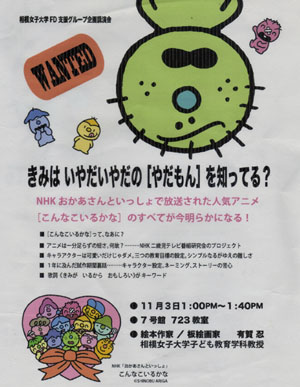

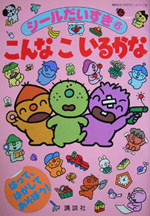


| 10月のアトリエだより |
■現代童画展(上野の森美術館)
出品作の板絵が完成した。東京都美術館が改修工事のため、《現代童画展》は今年と来年、上野の森美術館で開催される。
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
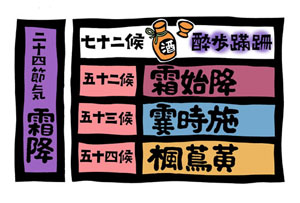 |
霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
■講演会準備に資料整理、パワーポイントつくり……時間が足りない
11月3日は《相生祭》。FDグループ主催の講演会で、ぼくは『きみは、やだもんを しってる?』と題して話す。
制作の裏側のすべてをラフ(下書き原画)などを展示しての講演。『こんなこいるかな』は、1986年から十数年にわたり放送され、
絵本も数多く出版された。現役の学生も、当時母親だった年齢層の方も聞きに来ていただけたらと思う。
ただ“可愛い”だけではないキャラクターの制作意図、NHKの教育目標、制作上悩んだ点、、そして何故今、”こんなこ”なのか?
など色々話したいことは多い。
■仕事の合間、息抜きは大好きな「工作」


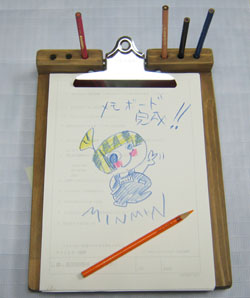

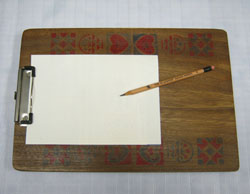

板絵の完成が近づいた。筆遣いが細かくなり遅くなった。今日は終日雨。時おり雨脚が激しくなる。息抜きに外にも出られない。
そこで”工作”。"図工少年"だったぼくは絵描きか大工さんになりたかった。その大工仕事を楽しむ。あり合わせの材料を使って
メモボードを作った。今までいくつも作っており、渋谷にも自宅にも大学の美術室や研究室にも置いてある。が、又一つ拵えた。
いいアイディアが浮かんだら即書き付ける……為だが、肝心のアイディアがそうそう浮かんでこない。
もっぱら忘れ物対策に使われている。情けないなあ。
ステイン塗料を刷り込んで完成。早速、完成間近の板絵を眺めつつ、作品タイトルを練る。メモボードの重量感が心地よい。
これで、「この絵には、これしかない」と思えるようなタイトルが浮かべば万々歳だが……。
(Oct.9)
■ハローウインをモチーフに切り紙トレーニング……学生の積極性、応用力を感じた
絵画造形表現活動応用の授業。保育、教育現場で図画工作、クラフトに使う、使える紙の説明とサンプル帳を作らせる。ラシャ紙、
エンボス紙、カラーケント紙、ミューズコットン紙、マーメード紙、レザック紙、上質紙、工作紙、波ダンボール紙、LKボード、
でんぐり紙等二十数種類切ったり破いたり描いたり、紙の特性を考えながら台紙に貼り付けていく。
…………紙の基礎知識も。「紙って、そもそも何?パピルスは”紙”ではない」「紙が現れる前は何に書いていたの?」
「紙のサイズにA版、B版があるのは何故?」「紙の裏表の見分け方」「ティッシュペーパーが水に流せないわけ」
「コート紙は”化粧”しているって本当?「奉書、麻紙、杉皮紙など和紙について」「紙の原料は?」「牛乳パックは何から
出来ている?」等等。
それだけではつまらないので、実習はハローウイン飾り作り。 紙を蛇腹折にして、ハローウインの”主役達”、パンプキン
{ジャックオーランタン}、コウモリ、魔法使い、ゴースト、ネコなどを切っていく。何体も連なるかぼちゃやコウモリに学生は
大喜び。型紙を渡しての制作だが、各自自由に切り出すから頼もしい。提供した魔法使いの型紙はお婆さん姿だが、ある学生は
「紋形四ツ折り」を使って5人の魔法使いのサークルを作った。それもお婆さんではなく可愛らしい少女のサークルだ。応用力の
芽生えが嬉しい。夢中になっての制作は必ずや身になるであろう。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候. 五十候. 五十一候)
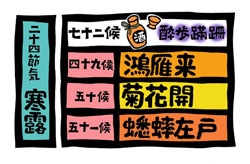 |
10月8日は寒露 (10月24日霜降) ・四十九候 (10月8日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月13日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月18日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展出品作制作のため鳩山詣が続いている。鳩山では終日描くのみ。外に出て萩の花を愛でるゆとりも無いのが
残念である。白萩、宮城野萩、だるま萩……花のトンネル?………が出来ているはずであった。ところが、雑草刈を依頼して
おいたシルバーさんが、萩の木も殆ど刈り取ってしまっていた。かろうじて茶の木の間から伸びた萩が花を風に揺らせている。
萩、薄(ススキ)、桔梗、撫子、女郎花(オミナエシ)、葛、藤袴 秋の七草……このうち、野で桔梗は見かけない。絶滅危惧種と聞く。
絵は完成が見えてきた。絵柄は板絵の性格上(彫が施されているため)大きな変更は出来ない。色だ。色でもって情感の表現をするのだが、
塗り重ねによって絵の表情はがらっと変わる。好ましい、望ましい心象風景が現れるまでひたすら塗り続ける。描く行為はイメージが画面に
現出するまで停まらない。
| 9月のアトリエだより |
■秋の収穫を喜ぶ





2,3日前は30度。今日は十数度の涼しさ。朝からアトリエに籠り板絵を制作する。今年は猛暑のせいかハチが増え
飛び交っている。スズメバチにアシナガバチ。多くて恐いほどだ。アトリエにも舞い込んでくる。ラケット状の電池式蚊取り器で
退治するのだが、空振りすると大変。ハチは攻撃されたと思い攻めてくる。今日もそうだった。一匹見事命中と思ったら、背後から
耳をかすめるように別の一匹が飛んできた。二匹部屋に入っていたのに気づかなかったのだ。危ない危ない!
先日地塗りを終えいよいよ”描ける”。好ましい状態になるまで幾度と無く色を塗り重ねる。ぼくの唯一の贅沢か、絵の具のチューブが
いくつも空になって行く。下層に沈んでいく色は決して無駄ではない。重層的に”我が望みの色”をかもし出してくれるのだから。
この”色遊び”は小学時代の絵の時間、ワクワクして描いた、あの楽しさと同じだ。仕上げるのが目的ではなくそのプロセスが
幸せな心持にしてくれる。この時のぼくは多分、最高に生き生きしていると思う。
「気、澄み渡る……」秋晴れ。台風が来ているそうだが、鳩山は嘘のように上天気。ヒガンバナの群生、原色の赤が目に痛いほどだ。
自分では為し得ずシルバーさんに頼んで刈り取ってってもらった野に出れば、木の葉はも早散り始めていた。栗の実も鈴なりだ。少しだけ
叩き落して集める。石造りの釜で新聞紙を燃やして焼き栗。3つぶほどだが、初物の熱々を味わう。これも我が贅沢。
胡桃も気になっていた。昨年は収穫時期を逸してしまった。今年こそはと、来るたびに注意していた。いつ、もいで良いのやら……。
木の根元に一粒落ちていた。果肉からクルミが露出している。今が収穫時と判断。収穫といっても6粒のみだけど。クルミは
仲良く二粒ずつ寄り添うように成っている。上の写真(中央)は果肉を半分取り除いたところ。胡桃の殻を一粒一粒取り出すのは
大変だ。この後、割る工程があるし……。食べるのは簡単だが……恵みには感謝しよう。
(Sep.25)
■二十四節気 <秋分> 七十二候 (四十六候、四十七候、四十八候)
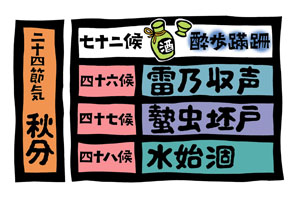 |
秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
HPの更新もままならず。慌しく活動の日々。落ち着いて制作なんて夢のまた夢。心やすまる時なし。情けない。
渋谷の仕事場→テニスコート(午前中二時間)→大学(レジュメ印刷)→自宅(今、HP更新)→鳩山アトリエへ。
創作に割り振る時間はまったくなし。嘆かわしい!明日は12時間はアトリエに籠り絵を描く決意。
創作といえば、紙皿で天使を作った。ペーパープレートクラフト、。そのゲージも学生の数分だけ用意(レジュメは豪華カラー版)したから
時間が足りなくなるわけだ。真っ白い紙皿の天使はシンプルで清らかだ。学生はきっと喜んで制作すると思う。手を使う。作って作って……
学生は体験を通じて何かを学ぶだろう。
■二十四節気 <白露> 七十二候 (四十三候、四十四候、四十五候)
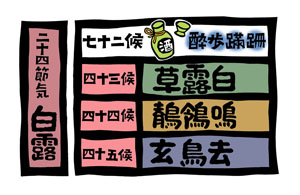 |
9月8日は白露 9月23日は秋分 ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (9月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
第三回『子ども教育学会』出席後、鳩山へ。板絵制作に集中する。このところ頻繁にアトリエを訪れるが、
それでも進行遅く焦る。眠る時間以外は彫っている。なんとか地塗りまで済ませた。この後も、塗っては彫る作業が続く。
板絵のしんどさは、終わりの時間が分からないところだ。今やっと”キャンバス”状態。やっと”描き”に入れる。”やっと……”の
ところまで漕ぎ付けたのに、アトリエを出なくてはならない。大学の仕事が待っている。
秋学期まで一週間。すべての時間をその準備のために使うが、それでも寸暇(あるだろうか)を見つけてアトリエに
向かうかもしれない。頭の中に作品の”骨格”がデーンと存在し、板絵作業の続行を促している。
栗の実が落ち始めた。古い木は元気ないが(2本は切り倒した)10年ほど前植えた3本は今年も”豊作”だ。 残念だが、
栗拾い(実際には口を開けたイガを叩き落す)する暇さえない。少しだけでも拾おうか……。
クルミは繁る葉の間から2個見えていたが、かき分けてみると5個!暗緑色の7~8センチ大の堅いボールが枝に
突き刺さるように付いている。昨年は収穫する前に落果したのか、動物に食べられたのか姿が消えてしまった。
この次鳩山へ来たときに実をもごう。クルミはいつ収穫してよいのかタイミングが分からない。表面の緑が段々黒ずんでいくが、熟れる
果実と違い大きな変化が無いから。いつもは袋で買うクルミ(カリフォルニア ウオルナッツ)だが、木に実るその姿は愛おしい。
割って「ウイスキーの友」に……、ゆとりのない日々の生活、夢想がしばしの慰めだ。
■《防災の日》はスズメバチ退治!





アトリエのシンボルツリー、チャンチンの老木(香椿)が枯れた。朽ち果てる寸前の幹にスズメバチが巣を作った。アカゲラが開けた穴が
日ごとに大きくなっていく。獰猛なスズメバチと、すぐ分かったがタカをくくっていた。いや、恐くて近づけなかったのだ。数百匹と群がる
スズメバチの大群、見るに見かねて役場に駆除を頼んだ。
消防署の車に、救急車。総勢8名。防護服に着替えた隊員2名。3名はバドミントン(?)のラケットを持って構える。ハシゴを架け
ほこらに薬品をぶち込む。窒息死させるのだという。そのあとバールで穴を大きくし巣を破壊、取り出した。何と6層も!
作業員は「これは大きいほうだ。巣に戻ってくるハチがいるから、暫くは近づかないように」。救護員は「今までに刺されたことは
ありますか?二度目なら死に至ります(ショック死)」と言い残し、引き揚げていった。スズメバチは恐い。
刺されて命を落としたというニュースも耳にする。 ふー、これで一安心だ。役場の方々、消防隊員に感謝感謝。
アトリエに入っても気になって仕方ない。デッキに出て、壊した巣の後を双眼鏡で見る。隊員が言った通りだ。スズメバチがまた群がって
きている。巣がなくなったことを諦めきれないのか、穴から出たり入ったり慌しい。大丈夫だろうか?又巣を作らなければ良いが。
板絵制作に入ったのは夕方。有線放送の『元気に遊んでいる良い子の皆さん、暗くならないうちに帰りましょう』が聞こえてきた。
「カラスウリの花が開くのを見たいなあ……」、「ビール&読書もいいなあ……」 ダメダメ!仕事仕事!、集中せねば……誘惑に蓋を
して……このところの低下した気力にカツを入れるべく水風呂、ねじり鉢巻! さあ、やるぞー!!!!
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■《愛媛の酒を楽しむ会》
京王プラザホテルで開催された蔵元18社出展の《愛媛の酒を楽しむ会》。畏友の杜氏、宇都宮君もブースを構えると言うので
出かけた。「千鳥」とならんで「月の滴」も展示されていた。「月の滴」はぼくの板絵(同名のタイトル)をラベルに用いた大吟醸酒だ。
会場はほぼ満員の盛況。利き酒しながら酒造主や日本酒党との歓談を楽しんだ。案内状通りの”ビュッフェディナー”だったが、
ぼくはテーブルから動かず、じゃこ天をかじったのみ。客の応対に忙しい宇都宮君とは一言二言話したのみ。握手して会場を後にした。
9月には大学。秋学期が始まる。その準備。板絵制作もある。造形遊び本の原稿も。明日は鳩山だ。アトリエの掃除も終わらせなくては
ならない。暑さで気力が萎えている。巻き返さねば!
■二十四節気 <処暑> 七十二候 (四十候、四十一候、四十二候)
 |
8月23日は処暑 (9月8日白露) ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
暦の上では処暑なれども、炎暑衰える気配なし。鳩山も暑い。板絵制作準備に訪れたが、暑さで退散する羽目に。
それでも掃除ぐらいはと収納庫をあけて溜息!思っていた以上にパネルがカビだらけ。パネルのみならずシナベニア板
すべてに白や黒のかび。炎天に日干しをする。幾度もパネルやベニア板を運ぶ。布で拭き落としながらの作業に体中の水分が
なくなるほどの
汗を流した。
胸が苦しい。深呼吸すると胸の上が板で覆われているような感じだ。カビを相当吸い込んだのだろう。なぜマスクを着け
なかった……、後悔しても後の祭り。いつもカビには悩まされているが、今回は大事だった。肺の中にカビ菌が育っている
のでは……ああ、胸が気持ち悪い!水道にホースを繋いで肺を隅々まで洗いたいなあ。

パネルを道路にならべて、”熱消毒”。枚数100枚ほどか、裏返してカビを殺す。湿気対策の名案なく、毎年板の天日干しに
時間を取られている。進歩なし!創作欲が削がれるし時間の無駄だ。東京への帰路も、今日一日の働きの虚しさが頭にあり
情けない思いでハンドルを握っていた。
我がアトリエが建つのは坂の下、更に半地下状態で湿気るのは仕方ないことだが、我慢我慢!贅沢を言うのはよそう。
”静かな小鳥の楽園”だ。「小鳥の帰る島」ではないか。
「小鳥の帰る島」は三十数年前現代童画展に出品した作品名
■交通渋滞覚悟で鳩山へ。

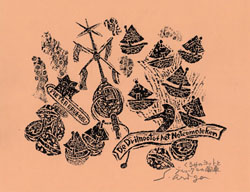
・「胡桃のヨットとブリューゲルの風車」 版画
講演会では板絵作品も何点か提示する。『胡桃のヨットとブリューゲルの風車』もその一つ。
ネーテルラントの画家ブリューゲルは1560年、《子どもの遊技》に91種類もの子どもの遊びを描いた。ブランコや、水鉄砲、竹馬など
分かりやすい遊びから、樽揺らし(シーソー)、煉瓦積み遊び、指骨あそび、目隠し鬼のスリッパ取り、洗礼ごっこ、お粥のかき混ぜっ
ごっこなど、フランドル地方の風俗、習慣色鮮明なもまで。
その中につくる遊びはただ一つ。「胡桃の風車」だけ。ぼくは絵を見て実際に作ってみた。それを板絵に描いたのが『胡桃のヨットと
ブリューゲルの風車』だ。10号Sサイズの小さなものだが、横浜の講演会で、胡桃の玩具ともども見せたいと思う。
炎天下、テニス3ゲームの疲れた体で、交通渋滞を恐れての運転、炎暑!気温が高いというより、この蒸し暑さ!鳩山のアトリエに
着いても、頭がボーとして他の仕事できず。ただ作品を積み込み帰途へ。
楽しみと言えば、庭で工事中の「井戸」の進行状況を確かめられたこと。誰も引き取り手が無いような巨大な砂岩の円柱形井戸枠を
破格の安値で購入。それを据え付ける土台工事を頼んであったのだ。井戸枠を何に使うか?地面を深く掘ろうとも、井戸が湧く保障もなし、
水をくみ上げる装置もないし。手押しポンプ設置も考えたが、これは井戸からの配管が必要で、大工事になる。そこで考えた。
名案浮かべり!!!!!この井戸枠の使途は?工事屋さんもぼくの描いた設計図を見て首をかしげた。構造を口で説明し、
わかってもらう。設置場所は庭の斜面だから、構造を描いた図面が理解できなかったのだろう。
< “名案”は工事終了後、この欄で答えを“白状” > ヒント………枯れ葉を入れる=○○○作り
工事は7割がた出来ていた。構造体はほぼ完成。煉瓦も積まれ後は配管と、井戸枠の運び込みだ。
あちこちに蝉のぬけがら。ミンミンゼミの鳴き声が蜩に変わった。アトリエのシンボルツリー《チャンチン》が、枯れた。アカゲラだろうか、
突いた穴が二つ寂しそう。主は見えず、チャンチンは今、アシナガバチの城となっている。ヤマカガシも手入れの無い庭で我がもの顔だ。
仕方ないことだが……。
(Aug.15)
■板絵運搬、準備を考慮しホテルの予約を入れる
18日の講演会会場はは横浜のホテル。当日車で行くつもりだったが、板絵、絵本、レジュメ(かなりの重量)の運び込みなどを
考え、前日宿泊することにした。『表現する喜び』と題し2時間の講演。一部<板絵の仕事>二部<絵本・雑誌の仕事>。いま資料
整理に忙しい。秋の現代童画展出品作(上野の森美術館)にも取り掛からねばならない。その前に、造形遊びの
指導本の原稿も。明日は大学へ。
風邪は何とか治まりそうだ。さあ、またフルスロットルで走らねば……。暑さにめげてはいられない!
(Aug.11)
■夏風邪!熱がある。仕事、スローペースにダウン!
疲れが溜まっていたのだろう、風を引く。頭痛が続き仕事ストップ!それでも、講演会の準備はしなくてはならない。
パワーポイントに板絵作品や絵本を取り込む作業。レジュメが先だが、今、考える力は無い。
講演会には板絵も持参して行こうと思う。その作品の決定は迷ったが、『いこい』『たたかい』(F50 1981)とする。
20年も前の作品だ。100人レベルの会場での可視性を考えると、”大柄”が良いだろうと。近作の小品も2~3点加える予定。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
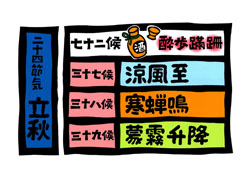 |
立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■鳩山アトリエは伸び放題の木々に隠れる
雑草生え放題、手入れする暇なく荒れ果てた鳩山のアトリエの庭。庭と言うより原野かジャングルか。それでも、植えまくった
果樹、花木が育っている。”植えまくった”というのは、畑にない樹木の苗木を見つけると、手当たり次第手に入れ植えていった
ということ。柿、リンゴ、スモモ、キウイなど果樹のみならず、ユズリハ、クロモジ、リンデン(西洋菩提樹)、イタリアンパイン、メープル、
それに後先考えずに(大木になったらどうしよう)ブナやトチに、ヒノキやケヤキまで植えた。紅葉が好きだからモミジもハゼも。
この間は大島桜も植えた。桜は昔からある山桜、それに、染井吉野が昨年から咲き出した。大島桜の”ねらい”は花より葉っぱだ。
この葉で桜餅をつくろうという算段。二本植えた大島桜(知人が種から育てたものを移植した)が楽しみだ。
ナツメ、サルナシ、山葡萄は放っておいても育つが、心配はナナカマド。一本を枯らし、昨年植えた二本も危やしい。
ナナカマドの赤い実を小鳥にとの思いは今秋も叶いそうもない。
■夏風邪?鼻クシュンクシュン……
オープンキャンパスで張り切りすぎたのか(満員御礼、大盛況)、雨の中のテニス(サーブ打ち込み200球)が
ハードだったのか、はたまた熱中症か、鼻水が止まらない。夏は大好きで暑さにも強いぼくも、”35度”には閉口!
只今ギブアップ状態。それでも休めず動き回っております……。○○○○、暇なしか!
■クレヨンまるDVD <ハーブおばさんのスイカのパラソル>
『幼稚園』(小学館)9月号付録に「夏チャレンジDVD」がついている。アンパンマン、ドラえもん、お話、歌、水族館に行こう、
忍者修行など盛りだくさんの120分。その中に「クレヨンまる」も納められている。まだワルズーやミイラばあや、それにチェリーや
ふるもとくんなど友達が登場する前の、最初期の作品。「ハーブおばさんのスイカのパラソル」の再録。
ここ2~3年前から、幼児雑誌にDVD(その前はVHSビデオ)がつくことが多くなってきた。”お得感”はあるが、その分雑誌の
ページ数は減っている。本文が充実してこその雑誌だ。
毎号付く”本物付録”(表紙にもこの文言が載っている)も、手替え品替えのアイディア玩具ではあるが、創造性を育むような物は
少ない。雑誌の黄金期70~80年代の付録と比べると、見た目の豪華さとは裏腹に、<創意工夫>する心が育つとは思えないような
ものばかりだ。
キャラクターを付けた刺激的な玩具(多くはICやボタン電池を使っている)は子どもには魅力だろうが、その興味は長続きしない。
持っているだけのもの、あるいは遊び方を限定する玩具に想像性、創造性がないからだ。
■2010 オープンキャンパス・模擬授業・アリガクン参戦!
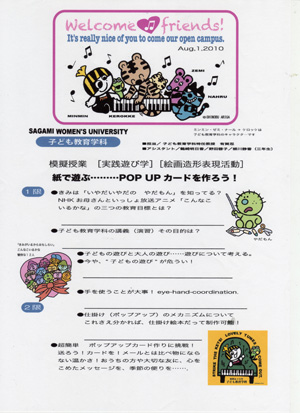
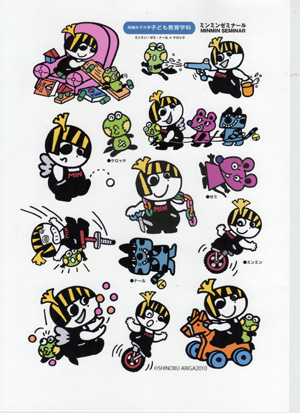
8月1日は相模女子大学のオープンキャンパス。真新しい建物、マーガレット本館5F2152教室でぼくは授業を行う。
昨年も一昨年も満員の盛況ぶり。補助机を出して対応した。当節の風潮として保護者の方々もお見えになる。ご父兄をも
納得させる講義でなくてはならず、頭をいためるところだ。(本来は制作を通じて自己表現し、体感が人間の底力を培っていくものだが)
今回はアシスタントの三年生が5名参加の強力体制だ。高校生諸君に「作る喜び、表現の素晴らしさ」を教えたい。
| 7月のアトリエだより |
■夏の法要は大変だ!寺は、今話題の植物園の傍らにあり
連日35度以上の「猛暑日」。先日は文京区にある寺で法要がありでかけた。本堂での僧侶の読経の後、炎熱の墓へ。
参会者はみな汗を滴らせている。お坊さんも配慮して短めの念仏。くらくらして倒れそうな暑さ、代わる代わる墓に水を
かけたが、かけた途端から乾いていく。
墓石には、○○家ではなく、倶会(旧字)一拠(旧字)と彫られていた。
寺から程近くに東京大学附属小石川植物園がある。いま、世界最大の花ショクダイオオコンニャクが開花し、大賑わいとの
報道。一万人以上が訪れ入園券の販売をストップしたとも。目と鼻の距離まで来ており、見ていこうか迷ったが、この暑さに
退散。 それにしても集まった10000人……。話題性……、本当に前々からこの植物に興味を持っていた人はどれくらい
いたんだろう? いろいろ考えてしまう。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
暑中お見舞い申し上げます。 23日は大暑! ”文字通り”を越していますよね。でも、
暦では大暑の次は立秋…………、”りっしゅう”の語感はいいねえ。暑さに負けませぬように、ご自愛専一に。
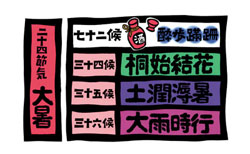 |
7月23日は大暑 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
猛暑日!夏が好き、熱さには強かったぼくも流石に閉口!先週まで頑張っていた”金曜テニス”も断念する。行かれないことも
ないが、コートに誰も集まらないだろうし。明日は法事がある、黒服の準備をする。汗だくだ。
HPの更新もできぬまま、8月1日のオープンキャンパスの用意、18日の講演会の準備に明け暮れている。講演会は長時間だから、
パワーポイントも活用する。そのためのデータ取り込みに大わらわ。
演題は『表現する喜び』一部は<板絵・版画……三つ子の魂、何とやら>で「幼少期の先生との出会い、環境、素材について」から現在に至る
表現人生を話す。 二部は<絵本の現場から>と題して、まず 「こんなこいるかな」誕生エピソードを。NHK2歳児テレビ番組研究会の教育目標などを紹介しつつ話す。これはぼくの基本的考え方、すなわち「色んな個性、それぞれを認め、一人ひとりを伸ばす」と、思いは一緒だから。
研修会は全国から集まる図工美術専門の先生方だから、絵本の様々な作法、制作技法も。更には小学校の先生方が受け持たれる子どもが、どのような環境に置かれて育ったのか、「月刊幼児雑誌の変遷」から見る試みも。30年間の幼児雑誌の本文はもちろん、殊に付録に着目。付録は
おもちゃだから、子どもに一番身近なもの。その変わり様から様々なことが見えてくる。大量の雑誌や付録の実物を提示しながら”驚くべき実体”を
知ってもらおうと。
大学の授業も大詰め。セメスター制は???だ。半年15回の講義(演習)では物足りない。いきおい詰め込むことになるが、学生が深く考え、自主的に制作するまでには至らない。学生は頑張ってついては来ているが、「これでもか、これでもか」と言うくらいやらねば力にならないと考えるぼくには
不満が募るばかりだ。”思いっきり””徹底的”にやりたいなあ……、学生には学ぶ時間が足りなすぎる。嗚呼。
■おでかけクイズ絵本『グー・チョキ・パーのいじわる魔女を追いかけろ』表紙初校あがる
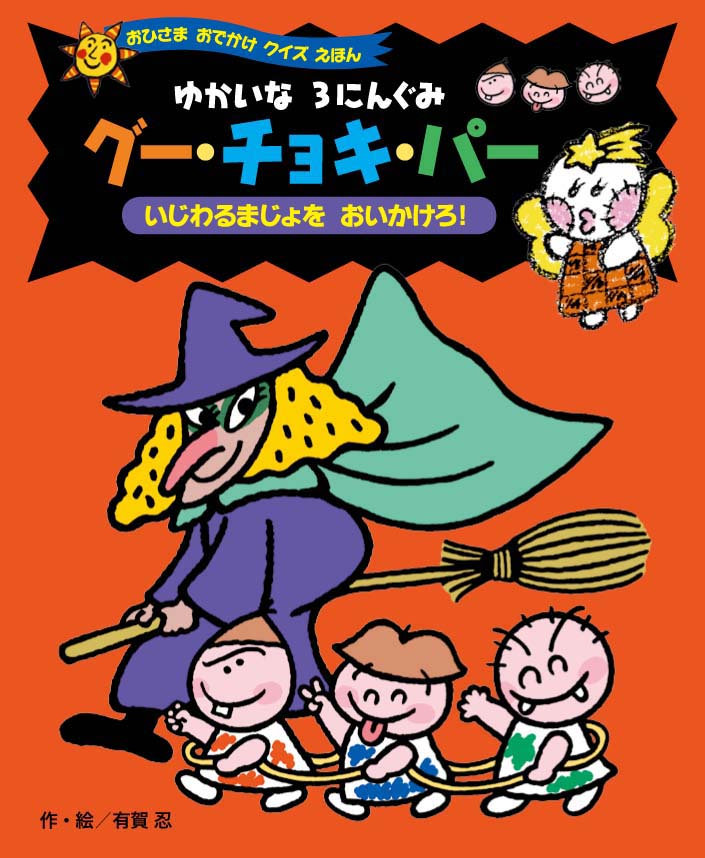
『グー・チョキ・パー』はお話とクイズ満載の絵本。<おまけクイズ>のボリュームもたっぷり。子どもを
長い時間楽しませたい。何度も絵本をめくって、隠されているものを探す楽しみも。
グー・チョキ・パーは腕白三人組。描いた絵から可愛らしい女の子が飛び出してくる。名前は『おやつちゃん』。
いじわる魔女『ズルーイ』との知恵比べ!乞うご期待!
(Jul.15)
■二十四節気 <小暑> 七十二候 (三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 は小暑 (7月23日は大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
現代童画選抜展終わる。今年は会場に行かれず仕舞い。出品作『どんぐり嵐』はこの後、坂出市民美術館展、神戸展で
展観される。お近くの方はご高覧を。
(Jul,5)
| 6月のアトリエだより |
■現代童画会選抜展が開催されます
「現童選抜展2010」開催。6月28日(月)~7月4日(日)
銀座アートホール
詳しくは展覧会のページをご覧下さい。
■古いスケッチブックが大量に出てきた 厚手の粗紙
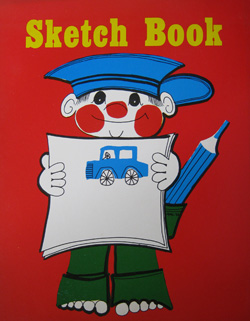
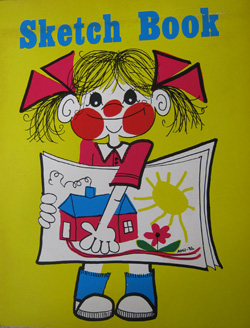
・粗紙32枚のスケッチブック。 27×34cm POLARPUBLISHING/FINLAND
絵本の原画やイラスト(教科書、雑誌、レコードジャケット、広告パンフ、百貨店ポスターなどに使用したもの)を捨てる。
ぎっしり詰まった紙袋を”仕分け”もせずに、幾つもゴミ置き場へ運んだ。見れば捨てるに忍びなくなるのが分かっているから。
版木の類もイラストを彫ったものから、版画作品まで山のよう。取っておきたい気も山々なれど、どこかで処分せねばと一大決意。
大量の和紙や紙類はカビや黄変したものを除き取っておく。中に写真のスケッチブックの束があった。数十冊、購入は
40年程前だろう。なぜ買ったのか?おそらくスケッチブックの粗い紙質が気に入ったのだと思う。ザラザラしていて厚さもある。
真っ白とはお世辞にも言えないが(藁半紙か馬糞紙の趣)、風合いが良い。一、二冊使った記憶もあるが、戸棚の奥に眠った
ままでいた。ツルツル、すべすべのコート紙や白い紙が当たり前の子ども達に、この”自然な紙の色”を見せてやりたい。
クレヨンの”塗り””滑り”が全く違う。”粗末な”ザラザラ画用紙の復活を望む。
何でも手に入る、恵まれすぎからは創造性は育たない。無いから工夫する、やっと手に入れたから大事にする……想像力と
創造力、この二つのソウゾウリョクは環境、人(導き)、そして素材(材料)で培われる。粗末なスケッチブックの山を見て
思った。物が無い時代に育ったぼくは幸せだったと。
(Jun.25)
■二十四節気 <夏至> 七十二候 (二十八候、二十九候、三十候)
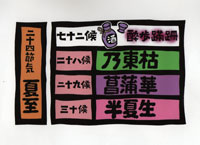 |
夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月21日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■いつも、アップアップ。切羽詰っての仕事……ゆとりがないなあ。
毎週木曜日は「自分の仕事日」としている。絵本制作、文書き、絵、研究といくつもメニューが多すぎて、大抵は
うまく行かない。時間を決めてやることを変えようとするのだが、仕事が不満足、区切りまで届かず延長となってしまう。
欲張り過ぎだが時間が足りないので仕方ない。睡眠時間も少なくてフラフラ状態……良いことではないなあ。
今日は絵本から入ろう。原稿書き(草稿)、それにやはり気になるレジュメ資料を作り直さねば。講演会の演目コンテンツも
考えたい。オープンキャンパスのメニューも、その他もろもろ、一つ一つ片付けてとは思うのだけれど、その一つが重たくて……。
昨日は小雨の中、キャンパスの植物の葉を採取した。キウイ、ドクダミ、ヤツデ……。「絵画造形表現」授業、スタンピングのためだ。
学生も色々な葉を持ち寄った。桜、銀杏、紫陽花、トマト、ヤマノイモ、柏、中に睡蓮なんてのもあった。残念ながら睡蓮は葉脈が浮き
出ておらず、スタンピングしてには向かないのであるが。
学生は自然物(葉など)と人工物(キャップ、容器)のスタンピングを楽しんだ。7色のインクをローラーに付け素材を写し取る作業に
夢中……、そしてその”転写コレクション”をコラージュする。自由に再構成する。完全自由を与えられた学生の表現は光った。いくつか
目を見張る出来栄えの物があった。
学生が制作自体を楽しんだ、その痕跡が作品なのだ。概念や意図しない無意識下のデザイン技法(AUTOMATIC……デカルコマニー、
フロッタージュ、ウオッシング、スパッタリングなど)を学んだ後の授業に、ぼくはスタンピングを選んだ。幼児造形教育の版画の元になる
スタンピングに、学生は時間を忘れて没頭した。その姿は無邪気に遊ぶ子どもと同じだ。幼児保育に携わらんとする者は子どもの心を
知らねばならない。作業に集中して子どもに還っている学生……、ぼくは学生が先生になって子どもに囲まれている情景を想像していた。
(Jun.24)
■リンデン(西洋菩提樹)の花にミツバチが……良い写真が撮れた



・リンデン(西洋菩提樹)の花の蜜を吸うミツバチ
「絵画造形表現活動」の今回のテーマはスタンピング。あらゆるものにローラーでインクを付け写し取ろうというもの。
自然物は葉っぱなど。学生は思い思いの葉っぱを集めてくることになっている。ぼくも葉脈のはっきりしたものを用意する。
桜、イチョウ、ヤツデなどはキャンパスにある。珍しいところで、杜仲茶、サンシュユ、ローズジェラニウム、ワイルドストロベリー、それに
きれいな形の”定番”モミジ。ハナミズキもアイビーも葉脈が美しく出る。全部で20種類くらい保冷材を敷いたバッグに詰めた。
リンデン(西洋菩提樹)の葉も珍しかろうと採取しようとして手を止めた。いまや激減、姿を消し問題となっているミツバチが、花の蜜を
吸っていたのだった。リンデンの花の蜜は最高と言われるが、一体このミツバチは何処に帰るのだろう?
アトリエを建てた頃は、ミツバチの大群の羽音うるさい群舞が見られたものだ。確かにここ、鳩山でもミツバチは減っている。
大急ぎでカメラを取りに。ピンとあわせに一苦労したものの何とか姿を納めた。
■クワノ実、グミ取り放題!ビワの実、甘露!



アトリエに籠りっぱなしは体に毒と、外に出る。荒れ放題の庭(庭と呼べないほど雑草が茂っている)、赤い実が目に入る。鈴なりの
グミ、ギッシリ密着する桑の実だ。どちらもいい具合に熟れて今食べごろ。口に含めば、かまずにとろける柔らかさだ。甘い。そう
たくさんは食べられないが、もいで食べるのは格別美味しく感じられる。びわの実も20粒ほどだが実を付けている。先週はまだ
固かったが、こちらも食べごろ。吐き出した種は辺りに埋めた。芽を出してくれるだろうか?忘れた頃、「あっ、あのときのだ!」
幼木を見つけられたら嬉しいだろうなあ。
■2010現代童画会選抜展搬入日迫る (展覧会詳細は別項)
毎年この時季恒例の「現童選抜展」も間近。銀座アートホール展示のあとは四国坂出、神戸と巡回する。作品の保護箱を
製作したが、利用していたホームセンターが閉鎖し材料の手当てが容易ではない。時間もなく、ありあわせの板で間に合わせた。
肝心の作品、タイトルは『どんぐり嵐』。毎年車の屋根に振り落ちるマテバシイのドングリが意識のベースにあった。それと、
旧作『どんぐり広場』だ。いま、種から芽を出したクヌギが育っている。”どんぐりの木”は種類が多いが、風に飛ばされてくるのか、
自然に生えてくるから嬉しくなる。ドングリノ木だけではない。サンショウ、ナツメ、スイカズラ、アケビ、モミジ……邪魔者扱いの杉も
あちこち芽を出して困る。さてさて『どんぐり嵐』の出来栄えは如何に……。
(Jun,22)
■「幼稚園実習」学生への試練……。耐えて超えてほしい。
昼休みのオフィスアワー(学生が質問等に自由に研究室を訪れる)に幼稚園で実地研修中の
学生が駆け込んで来た。園の先生から「責任実習」の制作物について厳しい指摘があったという。
廃材を用いての幼児の工作遊びで、学生は条件の一つ、「季節感を出す」から、カエルをテーマ
に選び、工作二種を用意した。新聞紙をまるめ先っぽにカエルを止らせゴムで“発射“するおも
ちゃ、 もう一つは、ティッシュボックスの中にカエルを4匹入れたもの。 蓋をあけると勢い
良く飛び出すおもしろい工作だ。
それが、「年長にはもう少し凝ったものを」「壊れにくく、長く遊べるもの」「カエルは4匹
いらないのでは」など等、相当言われ落ち込んでしまった。
”4匹”が面白いのに。学生がかわいそうになった。一匹しか入らない箱をわざわざ作るより、
4匹入るに越したことはない。カエルは3匹でも2匹でも自由だ。スペースを一匹用に限定して
しまえば、その後の遊びが広がらない。ぼくには何だか先生のアドバイスが”言いたい放題“に
思えてならなかった。
制作物をみてぼくは首を傾げた。いずれも問題はないと思えたから。「色んな見方があるんだね
この工作、子どもたちきっと喜ぶよ。頑張って!」ぼくも二点制作したものを見せたが、学生ので
十分行ける!「もっと自信を持っていいよ。」……励まして帰した。
聞けば、その園はセロハンテープ、ガムテープ類は一切使わせないという。段ボールを使う大形
おもちゃを作るときやペットボトルを束ねるとき等クラフトテープやビニールテーが重宝するのに、
すべて禁止とはなあ。先入観だ。そのくせ園児には英語を学ばせているという。何か偏ってる。ホチ
キスだって何だって危険視して使わせないのでは創造性は育たない。環境、素材(材料)それに、
やはり指導員だなあ。
子どもの感受性の萌芽期の立会人、極めて重責だ。
(Jun.14)
■実践遊び学……「連続模様切り紙あそび」
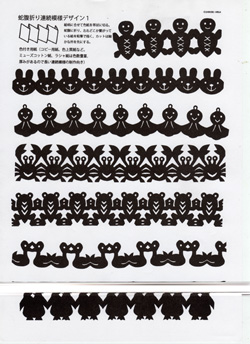
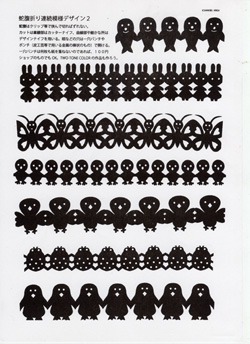
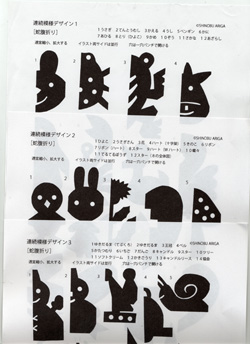
先週は江戸時代、寺子屋で盛んだった「紋型切り紙」を演習。昭和20年頃までは図工の教科にあった。3回折り、
4回折りを数多く制作。今回は「蛇腹折りの連続模様」。学生は思い思いのモチーフで数点の作品を仕上げた。
写真2枚
はそのレジュメ。右はデザイン参考資料1~3。このあと学生は”完全創作”に挑戦する。宿題にしたから、次週が
楽しみだ。自主性を喚起したい、いや何より制作”量”を求めたい。今は”質”ではなく、量だ。飽きるほど制作して初めて
身につくのだから。
毎回レジュメはこの調子だから、時間がかかる。今回は作りためた連続模様(すべて大型サイズで制作済み)その数40点。学生はこの40個を馬鹿馬鹿しいと思うのでなく、「だったら1個くらい作るぞー!」と発奮してほしいのだ。
(Jun.7)
■鳩山のアトリエ……目を休めに庭に出る。鬱蒼とした茂みに実りを見つけ嬉しくなる




週末は鳩山の生活が続く。現代童画展選抜展出品作の制作に入った。「アトリエだより」更新も儘ならぬ状態だ。
板を彫る手を休めて庭に出れば、嬉しい発見が!伸び放題のびた木々が実を付けていた。ビワはもうすぐ食べられそう。
サルナシはまだまだ小さいが、今年もどっさり実ったので楽しみ。グミは大粒が取りきれないほどだ。桑の実は口に含めば酸っぱく、甘くなるまで待とう。気にしていたオニグルミは(昨年はたった一粒しか生らず、それも収穫前に落ちてしまった)十個ほど実を付けた。クルミは信州で育った子ども時代の思い出があるので、何としても育てたかった。根元を虫にやられ穴が
開いてしまい心配していた。薬を塗布しロール布で養生する。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候)
 |
6月6日は芒種 (6月21日は夏至) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
2限3限授業の間に昼食をとるのだが、片付けがあったり、学生の質問などに時間を要し満足に食べられたためしがない。
10分くらいで立ち食い……出来ればいいほうだ。今日は昼飯を食べに研究室に入ったのが12時35分。そこへプロジェクト活動研究の
指導を求めて学生三名がやってきた。プロジェクト活動研究は学生が(教室外で)自主的に表現する科目だ。仕掛け絵本を作って、
幼稚園児の前で演じたいという。残念なことに、この学生達はぼくの「絵画造形表現Ⅱ応用」を受講していない。講座のコンテンツには
仕掛けを使っての「グリーティングカード制作」もある。ポップアップを中心に数種類の仕掛けを研究制作する。勿論カードのみならず絵本にも
応用可能だ。学生に授業で使った「仕掛けのゲージ」を貸し、コンセプトの再確認(仕掛けのおもしろさが狙い?しっかりした絵本?子どもたち
への読み聞かせが主?……いずれも大変なこと、中途半端にならぬように)をしてくるように言った。三人は仕掛けの習作を見せた。
すべては”ヤル気”だ。熱いエールをおくった。
先週は「なぜ絵が嫌いになったのか?いつごろから図工をしなくなったのか」アンケート調査をするという学生が訪ねてきた。文献を貸せと
いう。問題に即答といったものが簡単に手に入るわけが無い。子どもの絵、評価、造形表現等の資料として数冊渡したが、いずれもヒントには
なっても直接回答を求める者には不満だろう。考え迷い悩む……、研究する姿勢を見たい。
仕掛け絵本制作にせよ、アンケート調査にせよ、自主的活動の”芽生え”は素晴らしいこと。嬉しい。昼飯にありつけない日が続きそうだ。
(May.24)
■久しぶりの鳩山。雑草に庵埋もれそう。チェーンソーで木を切る。ブンブンゴマを作る。
多くの田圃で田植えが終わっていた。それも昨日か一昨日か、苗が植えられたばかりであることが直ぐ分かった。
鳩山には板絵制作用の木製パネルの在庫を見に来たのだが、アトリエに近づけないほどはびこる木の枝落としや雑草取りに
日がな格闘、板絵どころではなかった。
演習科目「コマの回転円盤デザイン制作」の前に見せる”伝承玩具”「ブンブンごま」を数個作った。ブンブンごまは回転するとタコ糸が指に食い込み引きちぎれるくらい引っ張られる。ブオーン ブオーンの音もダイナミックだ。ボール紙、ボタン、木片……何でも使える。昔は牛乳瓶のキャップで作ったものだ。路傍でメンコや釘刺しをして遊んだ少年時代、ぼくは毎日
何かを作っていた。このブンブンごまもその一つ。現代の子どもに糸巻きタンクなどと一緒に伝えたい遊びである。
(May.23)
■ウタリ神社の経木の風車を修理する

今年度の実践遊び学では4枚羽根に加えて8枚羽根の風車を制作した。紙製の風車以外にポリエステルベース
のものも学生に見せた。要は応用力だ。授業の始めには郷土玩具の「経木製の風車」も紹介したが、”経木”を
知る学生は皆無。「昔は肉屋でも魚屋でも包むのに使ったんだ。ほら、八百屋や魚屋の店先にあるだろう。あの墨で
値段を書いてある薄いやつだよ」……、そんなこと、いくら言っても無駄。隔世の感あり。
(May.22)
■子どもの造形遊びに「タイヤチューブプリント」を!
材料はたっぷり与えよう!「あれはいけない、これはやめよう」一切なしで、自由な「ペッタン遊び」を!


幼児や子どもの絵画造形は創造性を育む遊びだ。自由な造形をさせるには好奇心の喚起、環境、材料が必要。
環境は(お片付けのルールを教えるのは別)整理整頓された”キレイな場所”ではなく倉庫のような、思う存分”汚せる”空間がのぞましい。材料も高価な物や手に入れにくいものをちびちび”大切に使う”のではなく、身の周りに当たり前にある廃品利用、それも大量に与えることが肝要だ。壊したり、組み合わせたり、素材を本来の用途以外に応用する。正に想像力は創造力を育てることになる。
自転車のタイヤは廃棄物だ。入手簡単、大量に準備できる。絵画造形の素材にうってつけ、利用しない手はない。ゴムのチューブを木片に両面テープで貼り付けるだけで版材ができる。チューブ版画が幼児にも向くのは、彫刻等を使わないこと。
はさみ(カッターナイフの指導も)で簡単にカットできる。木版画、芋版画など、多くの版画は彫りミスしないよう神経を使うが、
チューブプリントは、粘着シートにチューブ片を貼り加えていくのだから、その心配はない。最も簡単な版画表現の一つと言える。
学生には、演習の前に版画の種別(凸,凹、平、併用版、モノプリント)の説明と、遊びの魅力を話した。が、何より大事なのは、造形教育に当たる者の”姿勢だ”。自らが楽しむ、目一杯遊ぶ、作る喜びを感じる……これらがなければ子どもの心は
捉えられない。「先生が、あんなに夢中になってる。おもしろそう!」教える側は”教える”のではなく、演じるのでもなく、楽しさを伝えられたら良いと思う。
(May.21)
■おでかけ絵本 愉快な三人組み『グー・チョキ・パー』制作順調
今月号で予告した、「ワン・パー・クー」は、ゆかいな三にんぐみ「グー・チョキ・パー」と名を変えた。クイズ、パズルを
どっさり盛り込む構成を楽しみながらやっている。<たぬき>クイズ……は、”た”抜きクイズ……”タ”の文字を消していくと
お菓子の名前が次々でてくる……、これは残念ながらカット!チョコレート、ドーナツ、ポテトチップス、キャンディー、
ビスケット、キャラメルなどカタカナが多く、編集部より幼児向きではないとの指摘。”狸クイズ?”の、ボケも入っているし
楽しめるのになあ。これに代わる面白い食べ物クイズを今考えている。もちろん絵本だから視覚的遊びの要素が大事……。
(May.16)
■クレヨンまる最終回!!掲載誌『おひさま』発売!!
■クイズ、パズル満載絵本の構想を練る
ゆかいな三にんぐみ グー・チョキ・パー
いじわる魔女を追いかけろ!
「おでかけクイズ絵本」のアイディアをまとめ,ダミーを制作する。意地悪魔女ズルーイが出す難問に、
腕白三人組グー・チョキ・パーが答えていく展開。描いた絵から飛び出てきたゲストキャラクターの
“おやつちゃん”が、それに絡む。
ことば遊び、迷路、シルエットクイズ、塗り分けパズル、形態パズル、絵探し、数遊び、本物探し、記憶クイズなど
満載予定だが、選択に頭を悩ましている。ボリュームたっぷりだが、読み終えても再びページをめくってクイズに
再度挑戦したくなる「おまけクイズ」付きだ。今は絵を描くというより、ゲーム的展開に頭を使っている。
スムーズな流れであるか?クイズは幼児に難しすぎないか?おやつちゃんの奪われたバッグの中身の秘密で、
ラストまで引っ張れるか?………キャラクターも(描いて描いて描いて)育てなければならないし、
ああ時間が足りない!今日は母の日。記憶の底から浮かび上がる母の微笑み……「ばかったいのを作りな!」
(“ばかったい”は母の口癖だった。非日常のおもしろさ、意外性、頓珍漢などを含めた、独特のニューアンス。
否定ではなくむしろ褒めことば)形式、常識、秩序、概念からフリーになるのがアーティスト!
母は厳しく、優しかった。
(May.9)
■移植したフキが根付き育った


テーブルソーやボール盤、ジクソーなどを備える作業小屋を建てた。用地はフキ畑。フキの根を少しだけ移植した。
芽は出したけれど、摘み取るには忍びず、蕗の薹はおあずけだった。来春が楽しみだ。その前にキャラブキという”手”もあった。
どうにも酒肴が頭から消えない。飲兵衛は春夏秋冬、恵みに感謝!
(May.5)
■おでかけ クイズ 絵本のタイトル決定!愉快な三人組『グー・チョキ・パー』のいじわる魔女を追いかけろ!
<おやつちゃん>て、何者?
キャラクター三人の名前、<ワン・パー・クー>、<ジャン・ケン・ポン>、<イチ・ニ・サン>、<ピー・カー・ブー>などの候補の中から、
<グー・チョキ・パー>に決めた。いたずらっ子が描いた絵から<おやつちゃん>も登場する。敵役のいじわる魔女、その名も<ズルーイ>。
いじわるクイズを連発する。<ズルーイ>は<おやつちゃん>のポシェットを奪って逃げる。<グー・チョキ・パー>は<ズルーイ>のだす
クイズを解きながら追いかけて行く。無事ポシェットは取り返せるか……?ポシェットの中味は……?
何度でも遊べるような仕掛けも。巻末には「おまけクイズ」を用意する。このノウハウは『こんなこいるかな』(知恵遊び絵本版4冊)で
用いたもの。楽しめる絵本にしたい。
(May.4)
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
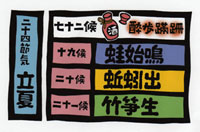 |
5月5日は立夏 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
久々のテニス。準備体操ももどかしくラリー。結果散散!右ふくらはぎの肉離れ。以前やったところだ。運動不足の鈍った体に
急激な刺激、”故障”は目に見えているのに。おお馬鹿者だ。足を引きずって歩く羽目に。
よって、また机に向かう生活と相成った。渋谷の仕事場からは中学校の校庭が見える。少年野球の練習試合が白熱を帯びている。
飛び交う声で分かる。皆、戦いに夢中だ。シップ薬を貼り、ぼくも絵本作りに精をだす。
(May.4)
■ペッタン、コロコロスタンプ 廃物利用による,幼児のための造形表現ツール




 テニスボールやボール缶の蓋を
テニスボールやボール缶の蓋を ペッタンコロコロスタンプは造形表現遊びの一つ。幼児は出現する轍の跡に目を輝かせる。型押し遊びの専用スポンジも市販されて
いるが、身の回りの物を活用することが、”応用する心”を育てる。手づくりした物は市販教材の完成品に、想像=創造……に至らせる
点で優る。材料は不要になったテニスボール(ゴミ処理に頭を悩ますクラブからは、いくらでも貰えるだろう)、クリーニングハンガー、
ペットボトルのキャップ。テニスボール缶キャップ(下段作品)いずれも廃物の再利用。
上段の針金ハンガーに通した二つのペットボトルキャップは頼りない装着に見えるだろうが、この”あそび”が大事。ボールをスムーズに
回転させるために必要なのだ。写真のほかにも数点試作した。転がした”おもしろ軌跡”は?また後日……
(May.2)
■鳩山は芽吹き……緑噴く。山笑う。春爛漫!



・五つ葉アケビ 雌花雄花 ・月桂樹の花 ・ダイコンの花群生
3本ある姫リンゴの木がいずれも白花満開。剪定を怠り屋根に届く高さに伸びた月桂樹も白黄、薄茶の細かな花を
ギッシリつけている。五つ葉アケビは至る所に育ち、赤薄紫の花を揺らせている。雌花、雄花が寄り沿うようで可憐だ。
今年色味がやや薄い紫モクレンははや散り始めている。ハナミズキが満開だ。手をかけて上げられないから、どれも伸び放題。
この間まで枯れ木同然だったブナが若緑の葉で覆われている。一番気にしていたメープルや(病気の)オニグルミも若葉を茂らせている。
一安心だ。白色、黄色、桃色……とりどりの色が咲き競うように乱舞。中で目に飛び込むのはダイコンの花の紫。何年か前までは
菜の花だった。隣地といっても境界もわからないような荒れ野原だが、今はダイコンの花で埋まっている。離れて見れば緑のなかの
紫模様のカーペット。
風もない穏やかな日和。日がな眺めていたいがそうもいかない。仕事に来たのだった。冷え冷えしているアトリエに入る。
目が慣れるまで闇だ。幼児造形教育のための教具教材作り……これはこれで楽しい。小鳥のさえずりを聞きながらアイディアを
考える。小さかったころから今に至るまで、ぼくは工作少年だ。
(May.1)
| 4月のアトリエだより |
■大学の研究室で仕事に没頭。先生の在室ランプも点灯まばら、訪れる者なし。静寂……わが天国!
先日学生がゴールデンウイークの過ごし方を聞いた。「どちらに行かれるのですか?」「仕事だよ。」
「えー、うっそー!」と言う具合。休日明けの授業のレジュメを準備し、さて我が仕事に取りかかる。
やっと取りかかれる。「おでかけクイズ絵本」の制作に入った。暖めていたアイディアをサムネールにおこし、
ネームを書き込んでいく。ダミーを作る。一冊36頁にストーリーを組み様々なクイズをちりばめる作業クイズや
パズルの考案、レイアウトなど楽しくもかなりハードな仕事ではある。
何より話が面白くなくてはならない。クイズやパズルを満載といっても、話の流れに不自然さがあってはならない。
頭を悩ませ、ため息をついては、それを打ち消すように、“面白く、楽しく”を念頭に……。
ぼくの“ゴールデンウィーク”は仕事三昧週間となる。
(Apr.30)
■一分間は楽に回り続けるコマを制作


身の回りにある廃物品の利用。今回はCD。どこの家庭にも一枚や二枚はあるだろう不要になったCD(CD・R、DVD)を
使ってのコマ作り。材料はCD一枚とビー玉。ビー玉をCDに接着するだけの簡単さ!誰にも出来る!これが実に優れもの。
よく廻る。一分間は当たり前に廻り続ける。。色紙を貼り合わせたり、模様を描いた回転円盤をセットすれば更に楽しい。
学生は回転円盤のデザイン(同心円、渦巻き、放射、格子、ドット、イラスト…・等)を多種制作させるが、コマ本体は
市販の物を使う。ただ、いつものことであるが「応用力」は要求する。身近なものを使ってのコマ遊びを考えさせる。これが
大事。その一アイディアとして「CDゴマ」を紹介する予定。
(Apr.25)
■晴れた!久々、光が目映い。風が香しい……かざぐるま かざぐるま かざぐるま……
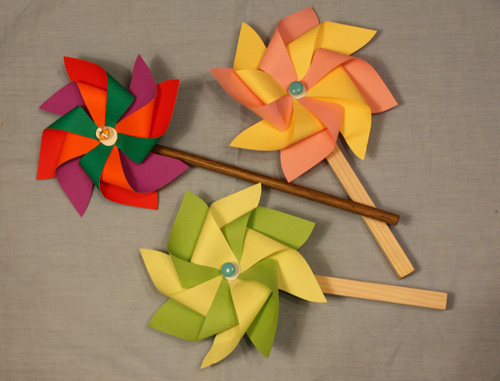


観測史上でも珍しい低温が続いたが、今日ようやく晴れ間が広がった。春風が気持ちよい。
風車をかざす。クルクル音もなく回る。幾つか並べて廻す。何てことないが、ホットする。知らず知らず幼き頃を想っている。
四枚羽根と8枚羽根を制作。8枚羽根(写真左)は、学生に型紙を提供するため、その準備も。風車をとめるピンやビーズや
丸棒も仕入れた。100人分、助手がいないのだから全部ぼく一人でやるしかない。準備がいつも大変だ。紙のカットや
組み立てはもちろん学生だが、配色やサイズなどでオリジナリティを演出してもらう。
{伝承工作}かざぐるまの次はでんでん太鼓だ。その準備もしなくてはならない。この一年、ほんの少し時間が空けば何か
作っていたが,でんでん太鼓も増えに増えた。その数数十個!ガムテープ、大小のセロハンテープの巻き芯、6Pチーズや
チョコレートのパッケージが溜ると気になり”でんでん太鼓化”したのだ。所狭しと吊るしてある。一つ一つみな音色が違う。
軽く重く小さく大きく、それぞれが愛らしい音を響かせる。「でんでん手遊び」は、仕事の合間の息抜きに一役買っている。
机の傍らにほんの小さなでんでんを一つ置かれたら如何だろう。ミニサイズは読書の妨げにもならない。耳を傾けたくなる
ような穏やかななんとも懐かしい音だから。
(Apr.24)
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
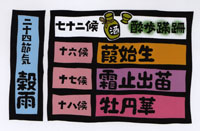 |
4月20日は穀雨 (5月5日は立夏) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
このところ震える寒さだ。校庭の桜はまだ散りきらない。駐車場の片隅、風に集められた
桜の花びらの山があちこちにできている。しゃがんで一掬い。ひんやり、しっとり……手に意外や、重みを感ずる。
ぼくは急に小人になる。花びらの褥に体を横たえ、埋もれるように花びらの間から空を見上げる。薄青の天、柔らかな日差し。
花びらの山を凝視している自分と中で休む自分。不思議な思いだ。日々の忙しさ、時に流されるわが身を
一瞬間蘇生させてくれた春よ、風よ,恵みをありがとう。
(Apr.20)
■子ども教育学会紀要扉絵

・胡桃のヨットとブリューゲルの風車
子ども教育学会の紀要が発刊された。創刊号の扉絵は『FATHER’S LETTER』
今回第二号は『胡桃の風車とブリューゲルの風車』。この愛らしいヨットも、風車も実際に
つくってみた。ヨットはアトリエに転がっている。風車は大事に飾ってある。父と子が物づくりを
通じて得るものは計り知れない。通い合う心……夢中になって遊ぶ……いつ何処で見ても
いい情景だ。幼き日の思いでは一生心で輝く宝。
(Apr.18)
■現代童画春季展出品作「harbor」


次回の発表は選抜展。乞うご期待。
(Apr.16)
■「こんなこ」工作。「二人は仲良し、いつも一緒」
『こんなこいるかな』コーナーに「★玩具を作ろう!⑦二人はなかよし いつもいっしょ」工作掲載。
次回は「スルスル シューTOY」を予定。 ★こんなこ いるかな のページへリンクできます
(Apr.11)
■現代童画春季展、(銀座アートホール)明日終了
明日11日、「現代童画春季展」最終日。一ヶ月の制作も、あっという間に展示期間が終わる。この次の展覧会は「選抜展」。
時間がなく制作も儘ならない状況だ。アイディアのラフスケッチだけでもと心がけてはいるが、思うようには行かない。
12日からは大学の授業が始まる「実践遊び学」「絵画造形表現活動Ⅰ基礎」。昨日は10時まで演習室、研究室でレジュメ制作。
一日の予定仕事分量の三分の一位しかできないもどかしさ。が、もう泣き言は言うまい!三年目、パワーアップして臨みたい。
(Apr,10)
■「ノビル畑」つくって、どうする!



春だ!でも鳩山の山桜の蕾は未だ固い。野原でノビルを見つけた。絡むように固まって生えるノビルを根こそぎ頂く。
幾塊ものノビルをアトリエ脇のヒイラギの根元に移した。ノビルには小さいころの思い出がある。引き上げ後、亡くなるまで
寝て過ごした父さんに、ノビルを摘むのがぼくの”仕事”だった。親父は医者から禁止されても酒をやめなかった。酒肴は
何でもよかったが、ノビルのヌタを好んだ。
「ノビルの畑」……記憶を蘇らせる場所を作った。
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
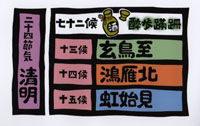 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
金曜日は週一テニスの日なのだが、生憎小雨、風も強く仕事日となった。天が仕事を命じたのだと観念し、新学期のレジュメを
考える。新たに「8枚羽根かざぐるま」「変色コマ」「切り絵連続模様」のレジュメを制作しなくてはならない。今日は風車だ。
紙皿、紙コップ、ペットボトルを使っての風車作りは制作見本を見せるに留め、今期は学生に基本形の4枚羽根の風車と、配色を
楽しめる8枚羽根の風車を作らせる。その試作を行った。型紙を起こし、形や色を変え5個作ってみた。さらに学生に貸す(時間
節約のため)型紙(ゲージ)をテーブル数×3=18組、一組2枚構成だから40枚近く白ボール紙から切り抜いた。デザインナイフを
握る右手親指は痛んだが、仕舞いには感覚がなくなり、指先が凹んだまま戻らなかった。そうまでしてと、いつも思うが、90分授業で
出来る限りたくさんの課題をやらせようとすると、ゲージを用意するしかないのだ。学生は簡単に「このゲージください」という。それでは
なんにもならない。同じものをたくさん作るとき、ゲージがあったら如何に便利かを分からせるためでもあり、幼児保育、子ども教育の
現場で、自ら”できる”力を養って欲しいから、「型紙は自分で作りなさい」と言う。かざぐるまのレジュメは型紙を入れて4枚になるが、
本日完成せず。ぼくは、”試作”を楽しみすぎるキライがあるようだ。
(Apr.2)
| 3月のアトリエだより |
■板絵 『 harbor 』描きあがる 日暮れまでナツメの木の移植に精を出す
28,29両日は寒の戻りか、冷たい北風が吹き荒れた。裸木立の枝が折れて飛ばされる強風だ。ぼくは鳩山のアトリエで
ストーブにしがみ付くようにして絵を仕上げていた。完成!いつもより少し色合いが生っぽいか。子どもへの”童画”然だ。
今回の作品は「harbor」=隠れ家で遊ぶ父子を、想いをこめて描いた。小学3年生のころ、ぼくは隠れ砦を作った。その記憶、
ワクワク感が筆を進めさせた。感動は創作の原動力だ。
額装が終わり、初めて外へ出た。まず深呼吸。そして日が暮れるまでの短い時間、何をしようか考える。やることは山のように
あるけれど、欲張ってもはじまらない。春、新芽が吹き出す前に済ませたいこと……、今は枯れ木にしか見えないナツメの木を移植
することに決めた。ナツメは実が落ち、あちらこちらで育っている。土が合っているのか、サンショウや迷惑なスギ同様増えて
困るほどだ。一年目ものは未だ良いが、3年、4年たった木は、棘はともかく根が張っていて掘りあげるのに一苦労。
10本掘れば、もうお手上げ。このまま大きくなれば、実を付けるけれど、通路を塞ぐ枝の棘が厄介だ。
掘り残した分はハサミでカット。かわいそう、もったいないけれど、鳩山にそうしょっちゅうは来られないから仕方ない。
ナツメの親木の勢いに負けて山葡萄が元気がない。去年も一昨年も実がならなかった。ナツメの移植より、こちらの方が
心配だ。酸っぱい山葡萄の実を煮詰めてシロップを作ったことがある。あの喜びをまた味わいたい。大匙数杯分しかできなかった
貴重なシロップを”大事に”口に含んだときの気持ち……嬉しさを再び。
(Mar.29)
■桜咲くキャンパスに人影まばら
子ども教育学科新入生に配る画材、用品の袋詰めをする。14アイテムを110セット。昨年は二人でおこなったが、
今年はもう一人助っ人を加えたから、まだ明るさが残る時間に終了した。
大学には「100年桜」の老大木があるが、校舎からはやや離れている。桜を見て帰りたかったが、今日は断念。
それでも幾本もの桜が咲き始めていた。3分咲きくらいか。美しい。ぼくは冷たい風に震えながら佇んでいた。
ふと足元を見れば、しぼんだ銀杏の実が幾つか。梢につかまっていたものが、ようやく落ちたのだろう。ぼくは
銀杏並木が好きで、秋の終わりにはキャンパスで銀杏を拾う。ぼく以外には誰も拾う者はいない。果肉を洗い落とし
乾燥させるのだが、土に埋けて果肉を腐らせ取り除く手もある。そこで植木鉢に埋めておいたのだが、何と十数本が
発芽してしまったのだ。
今は、20センチほどの”枯れ枝”にしか見えないが、しっかした芽をつけている。植木鉢は大振りだが、”枯れ枝”には所狭しだ。
春になったら、鳩山に移植しよう。鳩山にもイチョウの木はあるが、実が成らない。大学の鈴なりのイチョウの子どもだ。あやかって
銀杏を雨のように降らしてくれるようにならないかなあ。
(Mar.26)
■アケビ棚を補強……石井さんにまたまた、大感謝


杭を打つ音で目が覚めた。わがアトリエは訪れる人は稀なので、あわてて外に飛び出した。
石井さんだった。昨日はヨモギ餅を持ってきてくれ、今日は、倒れそうに大きく傾いているアケビ棚を
直しに来てくださったのだ。石井さんは先日、杉の木を剪定してくれたのだが、そのとき、アケビ棚が
壊れそうなのが気になったのだという。四本の足に角材を打ち込み補強、古い蔓も取り除いてくれた。
「花芽は残してありますからね。今年は実が成るでしょう」……と。人の佳い石井さんのとびきり上等の
笑顔に、ぼくの制作が捗ったのは当然のことであった。深謝。今回は二日間のアトリエ生活。明日からは
渋谷の仕事場に戻って働くことになる。
(Mar.23)
■出来立てのヨモギ餅をいただく
昨晩の強風(東京では瞬間最高風速20数メートル)鳩山の庭も多くの枝が折れていた。
プラムやすももは蕾をつけた枝が……。相当強い風が吹き荒れたのだろう。


アトリエ北側の田圃の主、石井さんがヨモギ餅を届けてくださった。朝作ったばかりの出来立て。
越辺川で摘んだ蓬、自家産の上新粉(都幾川村で精米))、小豆もすべて石井さんの収穫品だ。ヨモギの香りが
鼻腔をくすぐる。口当たりの良い適度の柔らかさ。美味い!餡と黄な粉で二つペロリ。
毎年、この時季きまって春の味覚の贈り物。嬉しくて、でも秋にいただく栗の渋皮煮や、採れたての
米、それにぼくの大好物の玄米(これと梅干さえあれば、おかずが要らぬほどだ)など、いつも頂いてばかりで
心苦しい。アトリエに車が停まるのをみて軽四輪でおいでなさる。ありがたい。手を振り頭を下げ、見送るが
お礼に何も差し上げられず何とも申し訳ない心持だ。ご好意に感謝。
(Mar.22)
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
 |
今年の春分は3月21日 (清明は4月5日) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
17日の当欄、ミツマタの花の写真を掲載したが、ミツマタは沈丁花と同じ科だった。甘い匂いは同じなれど、ミツマタは
鼻を近づけ嗅がねば分からないほど”上品”。ミツバチが減って困っているというニュースをたびたび目にするが、
わが庭には、ミツバチが群がって飛び交っている。ミツマタの花の蜜を集めることに夢中で、ぼくの存在なんておかまいなし。
ミツバチの羽音を耳にぼくはミツマタの花に顔を埋めたていた。
(Mar.21)
■板絵『harbor』制作進行中
現代童画春季展(別項「展覧会」参照)に出品する板絵、作品タイトルを
「harbor」と決め制作中。絵の具が乾く時間も絵から離れられない。額縁を
塗装したり絵皿を洗ったりもするが落ち着かない。完成が近づくといつもこうだ。
最後の筆を入れ、いすに座リ込むとき、時が止まる。まばたきさえ止まるくらい
集中して見入っているのだと思う。その後襲う疲労感でわかる。
「harbor」……父と子の遊び場所。内緒の(自分たち以外は誰も知らないと思っている)
隠れ家。想像力を全開させる、ぼくにとっての「板絵制作」同様、時間の止まる宇宙だ。
その宇宙を、今描いている。
(Mar.21)
■紙芝居「だいじな たまご」出来上がる


・「だいじなたまご」① いずれも画面はカットされています


社団法人「小さな親切」運動本部製作紙芝居『心の教育プロジェクト』
……紙芝居で「豊かな心」を育てよう…… 「だいじなたまご」が完成した。
紙芝居を用いた道徳授業のための指導資料もついている。視認
性を重視、太いシンプルなライン、色も
絞りスッキリさせた。せっかくもらったチャボの玉子が壊れて怒り、悲しむ主人公たっくん。たっくんの心情は
とらえたつもりだが、紙芝居は演者の力量による所が多い。持論「絵本も紙芝居も童話も面白くなくては」が、
今回は少々叶わなかった面もあるものの、ストーリーも絵もシンプルなだけに、授業展開に広く活用できると思う。
■伸びた蔓をグルグル巻いて……何のリースでしょう?



・キングサリの花 ・ブナの枯れ葉(新芽が堅く鋭く尖っている) ・オリーブの木に
リースなんて洒落たものじゃない。枝をグルグル巻いただけ。何の枝?ここがポイント!蔓は藤、アケビ…材料に事欠かないが、
今日は始めての蔓で制作した。キウイの棚に絡まっていく枝も長く伸ばしているマタタビ。花が咲き、実を期待させてはがっかり……の
マタタビの蔓が地面につくくらい垂れ下がっていたんだ。30分間のお楽しみさ。
マタタビの冠は何で飾ろう。まず水仙、それからクリスマスローズにかけて見た。似合わない。キングサリの黄やオリーブの濃い
緑もマッチするが、やはりブナがいい。芽吹く前だというのに葉を落とさず寒風に身を震わしているブナがいい。マタタビのリースに
ブナの枯れ葉色……美しいなあ。30分の楽しみに幕を引き後ろ髪引かれる思いでアトリエに戻った。
体は冷えたけど、嬉しさがねえ……。いい仕事が出来そうだよ。
(Mar.18)
■日がな一日板絵制作に没頭……



・ミツマタの花(木の高さ2メートル、殆ど花は白く見える ・同、しゃがんで見れば黄色 ・沈丁花
10時から7時までアトリエに籠る。いや、花の香りに誘われて一度外へ出た。
仕事場に甘い芳香が漂ってくる。沈丁花だ。朝東京を発ち鳩山に来たが、車を降りたときは気づかなかった。
満開。近づけばきつい位匂い発つ。沈丁花から数メートル先にはミツマタがこれまた咲き誇っていた。上から見れば
白(淡い黄色)、ちょっとしゃがんで下からのぞけば濃い黄色。ほのかに甘い香りがする。
いつかミツマタの皮で紙を漉いてみたいと思う。早く成長して欲しいものばかり。メープルシロップをとりたくて
サトウカエデを、ブナ林を夢見てブナの苗木を、とちもちを食べたくてトチノキを、果実酒を目論んでナナカマドやサルナシや
マタタビを植えた。が、すべて夢の夢で終わるだろう。それでも、夢の種まきはやめられない。
一旦外に出るとアトリエに戻りたくなくなるから困る。草木の息吹に気圧されそうだ。板絵に向えば、すぐ”復調”するから
未だ大丈夫だが。”大丈夫”はおかしいか。自然は敵ではないし……一体感。抱かれての仕事のはずだよね。
(Mar.17)
■タイトル決定!クレヨンまるファイナル「バイバイ クレヨンまる」
春季展出品板絵の作品名は絵より先行したが、クレヨンまるは文・絵が完成してから考えた。タイトル案は数種。
でも、一番おとなしいものを選んだ。「バイバイ クレヨンまる」あまり強く内容を暗示させたり、
感情移入過多にならないように。
1996年1月号から連載開始、155話がファイナル。普段のアイディアとは違った、最終回の展開には頭を使った。
“読み聞かせお話雑誌”『おひさま』はこの春から隔月刊になる。クレヨンまるは、5-6月号(4月15日発売予定)
で、さよならする。意外な結末……!? どうか、ご高覧あれ。
(Mar.11)
■これから制作する板絵の作品名を考える
現代童画2010春季展(4月5日~11日 於・銀座アートホール)出品作の制作に入る。
と言っても、鳩山アトリエ初日は雪降りでクローズ。渋谷に戻りエスキスを取る。
と同時に作品タイトルを考えねばならない。会場に置く出品目録印刷のため、作品名を申告する
ことになっているからだ。refuge, hide out, ……、悪事を働いて隠れる意が強いから、ぼくは「harbor」を選択。
隠れ家で遊ぶ父と子をイメージ。親とか子とかの意識をはずれ、幸せ無我の境で遊ぶ秘密の空間を描きたい。
今回のように作品名が絵より先行する例は、ままある。「瞬幸永憶」(F100号)もそうだ。
無論、瞬幸永憶などという熟語はない。言葉のイメージが絵を語らせた好例である。
(Mar.11)
■雪降り止まず退散
板絵制作に入ろう……遅れた時間を取り戻すべく一路鳩山へ。
予報では天気は午後から崩れるという。冷たい雨は昼前には雪に変わった。
とにかく寒い。久しぶりのアトリエ、震えながら板に向かう。が、外が気になって仕方がない。
春の日が射せば、シジュウカラやヤマガラそれにウグイスの声を期待できたのに、生憎の雪!
眼前に広がる田や畑は真っ白。積もれば、坂下にあるわがアトリエだ、
車はスリップして登れなくなる。何年か前、“脱出不能”となったことがあった。
というわけで、「アトリエ滞在2時間」のみ、の記録を本日つくった。
雪に埋もれていくフキノトウ、摘みたい気持ちを抑え帰京せり。
(Mar.10)
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
仕事に明け暮れHP更新もままならず。テニスにも行っていない。”外出”は現代童画会春季展作品用パネルを取りに行った
鳩山アトリエのみ。
おおよそ人間的でない生活。体が鈍ることを憂うも、窒息しないでやっていられるのは、表現欲求のなせるワザか。
このところ天気が優れない。菜種梅雨か。久しぶりに今日、雨上がる。最高気温18度、昨日より10度も高い。時間をきめて歩く。
代官山~恵比寿~渋谷、これで5000歩。恵比寿駅近くで「ロバの花売り」に出合った。暫し足を止めた。1メートルくらいの灰茶褐色の
ロバ、背中に花かごを付けている。チェック地のシャツにベレー帽姿。赤ら顔のおじさんはバラの花を一本一本小分けにしている。珍しさもあって
見物人が取り囲む。ロバは大人しくじっとしている。が、急に飛び跳ねた。おじさんのジャンパーの中に顔を隠した。おじさんはカメラの
フラッシュをやめてくれるように言った。
やさしいロバの目。花の中に桃の枝も……。「飼えたらいいなあ……」ロバは、ぼくの飼いたいものリスト、ベスト3上位だ。
(Mar.5)
| 2月のアトリエだより |
■「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」



『おひさま』連載の 「クレヨンまる」、次号で155話。これで見納め、読み納め。只今最終編を執筆中。別れは悲しいもの。
クレヨンまるはどうなる?仲良しのチェリーは?それに、大泥棒のワルズー、子分のコウモリ、コモリンは?三百数十歳の
ミイラばあやは………死ぬなよ!?………明るく明るくと念じても、想いがつのって……。さあ、どうなるか。〆切待ったなし!
描くぞー!!!!こう、ご期待!!!!
(Feb.28)
■「フータのひこうき」の朗読が放送されます
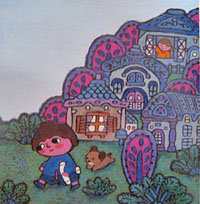



ぼくの絵話集「マーリと のうさぎ」の中から 『フータのひこうき』が放送されます。
童話として書いたものではないので、朗読でイメージがどう伝えられるか楽しみです。
(絵の世界がどう表現されるかなあ)
番組名:『童話の散歩道』
放送日時:32局ネット
「童話の散歩道」各局の放送時間
・ 北海道放送 3月27日(土)6:20~6:30
・ 青森放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ IBC岩手放送 3月28日(日)12:20~12:30
・ 秋田放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 山形放送 3月28日(日)7:15~7:25
・ 東北放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ ラジオ福島 3月28日(日)8:30~8:40
・ 新潟放送 3月28日(日)12:40~12:50
・ 北陸放送 3月28日(日)7:40~7:50
・ 北日本放送 3月27日(土)7:50~8:00
・ 信越放送 3月28日(日)8:50~9:00
・ 山梨放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 福井放送 3月28日(日)6:20~6:30
・ 静岡放送 3月28日(日)5:10~5:20
・ 中部日本放送 3月28日(日)8:35~8:45
・ ラジオ関西 3月27日(土)7:20~7:30
・ 京都放送 3月28日(日)17:30~17:40
・ 中国放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 山陰放送 3月28日(日)16:00~16:10
・ 和歌山放送 3月27日(土)16:44~16:54
・ 山口放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ 西日本放送 3月27日(土)7:00~7:10
・ 南海放送 3月27日(土)17:50~18:00
・ 高知放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 四国放送 3月28日(日)11:50~12:00
・ RKB毎日放送 3月28日(日)8:15~8:25
・ 大分放送 3月27日(土)8:20~8:30
・ 長崎放送 3月28日(日)7:00~7:10
・ 熊本放送 3月28日(日)9:05~9:15
・ 宮崎放送 3月28日(日)6:30~6:40
・ 南日本放送 3月28日(日)6:50~7:00
・ 琉球放送 3月28日(日)7:15~7:25
朗読アナウンサー 牛山美那子
(Feb25)
■コンソーシアム大学「作って遊ぼう」第三回
『コロコロ コロ玉バランスボード』を作る。ゲーム機では味わえない”微細な手の運動”。イライラさせて遊ぼうというもの。
長方形木片26個、円筒形4個使用。赤青緑黄に塗った木球4個を転がして遊ぶ。四隅から中央に集めたり拡散させたり、
時間を競ったり遊び方は色々。遊び方を考え出すのも狙いの一つ。シンプルで何度でも繰り返し遊べ何より”手加減の妙”を
味わう。勢いよく転がしても玉は思うところに入らない、留まらない。ビー玉、おはじきも皆そうだ。加減が技である。
教室に玉ころがしの音が響いた。気が付いてみれば二時間の授業中、トイレに行った子どもなし!何と言うことだ!えらい集中力!
授業の終わりに、ぼくはこのことに触れた。トイレさえ忘れ、夢中で頑張った子どもたちを褒め称えた。
(Feb.20)






■ コンソーシアム講座の終わり10分の”オマケ”
120分授業を、子供達が飽きさせないで楽しくやるのはたいへんなこと。これに一番頭を使う。絶対集中させるぞ……意気込んで!
メニューを幾つか用意するのも手だが、しっかりしたものを制作させるにはそうも行かない。所々刺激を与える仕掛けを用意したり、
あっと目を見張る(視覚効果)ものを隠しておいて広げて見せる等など、アシスタントの学生にも秘密の隠し物を前日から用意したりする。
講座終了10分前も大事!作品が完成し、自由に遊び、少々だれてきている。そこで強い印象で締めくくるには、新たな興味を惹く
出しものが必要となる。前回は「シュルシュル人形」。そして今回は「牛乳パックの水車」を用意。教卓に6っこずらりと並べ、
「さあ、こっち見てー!」子供たちが群がったのはいうまでもない。蛇口をひねり水車の羽根に当たるように置く……「ぼくにも!」
「やらせて!」「すげー!」子供達の楽しむ声が大人を気づかせる。「廃物利用、創意工夫……創造的遊びを」お母さん方は
作り方を熱心に聞いている。「お家で是非作ってくださいね。簡単で面白い工作を考えてね」……メッセージと共に授業は終了する。が、
帰らず遊び続ける子どもも多く、こんな姿をお母さん方は、目を細めてみておられた。子どもは輝く!凄い輝きを発す!



■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)
 |
雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
20日の日差しは春のもの。穏やかな日和。紅梅白梅の木立の間に銀杏が数粒ころがっていた。最後までしがみついていた
実が落ちたのだろう。キャンパスは人影もまばら、静寂。「コンソーシアム授業」会場に向かう足取りも軽かった。
■クレヨンまるファイナル 制作中!!必見!!クレヨンまるの最後!
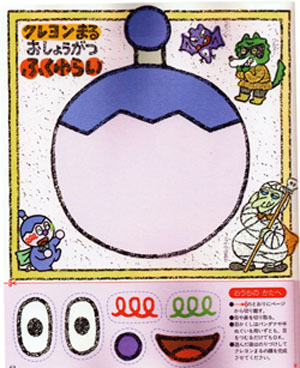
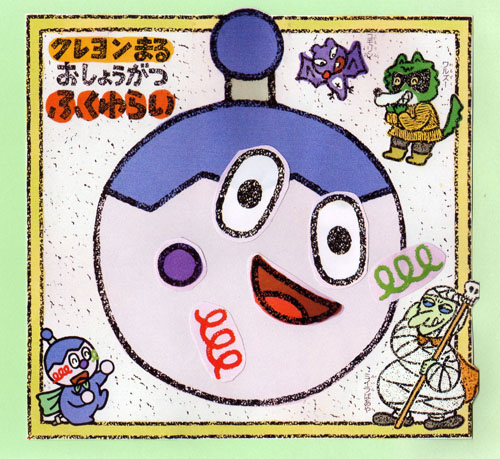 ・福笑い
・福笑い
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』
二日目 「回転円盤仕掛け絵本」”あんなかお、こんなかお、そんなかお、みななかお、どんなかお”」
雪交じりの寒い朝、20組の親子が集まった。前回同様みんなヤル気十分!お父さんの参加は4名、弟や妹を連れてきた方もいて
教室は満員。まず”宿題”の顔の絵を絵本の表紙に貼り付ける。もちろん”作家名”も記入する。絵本作家になった気持ちで、
制作スタート。子どもは4種類の”面白い””おかしな””楽しい””見たこともない”顔を描く。その間に保護者の方々は
仕掛け絵本のメカ(二枚の回転円盤、ジョイントなど)を制作する。顔の絵を上部と下部とに切断し本体に取り付ける。本体台紙に
開けられた二つの穴(目と口)に12個の表情を描きこむ。これで何百もの顔ができるのだ。製本は金属鋲をかしめる。これは、
かなり大変だったけれど、学生が要領よく流れ作業でこなしてくれた。世界で一冊だけの「ぼくのえほん」「わたしのえほん」で
子ども達は遊んだ。”へんてこな顔”が出現するたびに歓声をあげて……。作る楽しさ、遊ぶ楽しさ……、苦心して作り上げた
その達成感が子どもを成長させる。
講座終了間際にお家で簡単にできる工作を紹介する。今回は『しゅるしゅる人形』牛乳パックとストローとタコ糸があれば
誰でもできる玩具。試作品を吊るすと、子供達が群がった。シンプルだけど面白い。手加減で人形がしゅるしゅる昇っていき
スーと落ちてくる。子ども達は繰り返し繰り返し遊んでいた。つくり方をメモしているお母さんも。是非とも、お子さんと一緒に
作って遊んでほしい。

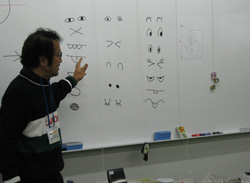

・「おもしろい顔ができたねえ」 ・表情の変化は色々だよ「泣いたり笑ったり、怒ったり眠ったり…」・「やって見せて!」



・糸を操り人形を天井まで昇らせて遊ぶ ・牛乳パックで作って見せる ・ちょっと”豪華な”「こんなこ」バージョン
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』 初日は「変身仮面を作ろう!きみの仮面はどんな仮面か、お話して!」
6歳~9歳の子どもに、お母さんお父さんを交えてのコンソーシアム大学「作って遊ぼう!」開講。
「●作って遊ぶ楽しさ●出来たものは、世界でただ一つの存在●表現は”自由”、この素晴らしさ」
第一回目は、『変身仮面』。仮面を作って、各自その仮面の秘密、凄さを語らせるもの。


・21人が仮面を制作。仮面にはそれぞれの秘密がある。想像させることが目的。



・マントは黒2着、白4着を用意。全員を写真に収める。 ・わが優秀なるアシスタント。子ども教育学科2年生
・下段中央は、河童(鼻から突き出しているのは”吹き戻し”が正義の味方○○仮面にやられるの図)
さて、この弱虫カッパは誰でしょう?
次回は『回転円盤仕掛け絵本』…………
「こんなかお、あんなかお、そんなかお、へんなかお、どんなかお」変な絵本のタイトルだねえ。
■クレヨンまる最終編! はたしてどうなるかクレヨンまる!


『おひさま』 が月刊から隔月刊になる。それにともない、クレヨンまるは『おひさま』6-7月号(5月15日発売予定)を
最後に休載する。おひさま創刊当初からクレヨンまるを描いてきたから感慨一入である。
第一話「クレヨンまる誕生」が1996年1月号、以来本年2月号「オリーブおばさんのプレゼント」が154話。
15年の連載を休止するのだが、ファイナル155話は特別編だ。クレヨンまるファンを悲しませないよう、そして、
最大級の”オチ”で締めくくろう。このところ毎日毎晩、結末をどうしようか考えている。
これじゃダメ!あれでもダメ!面白くて、悲しくて、くすっと 笑える……あっという最後で締めくくるんだ!ぼくは
クレヨンまると共に生きたから、ぼくなら出来るはず……言い聞かせて、寝ても覚めてもクレヨンまるの世界に
浸かっている。クレヨンまるファンの皆さん、待っててね。クレヨンまるの”最後”……悲しみを吹き飛ばすような
結末を、きっと描いてみせるからね。
(Feb. 10)
■二十四節気 <立春> 七十二候(一候.二候.三候)
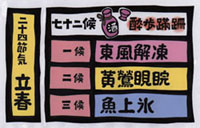 |
●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
暑いのは歓迎だが、ぼくは寒さに弱い。渋谷の仕事場は北側に位置しているから、部屋は外よりも寒い感じ……、そんな
バカなことは無かろうが暖めても暖めても室温上がらず。机の下には足温器、膝暖盤、更に温風ヒーター。背中にはハロゲン
ヒーターの遠赤外線をあてている。こうまでしないと、仕事が出来ない。ふくらはぎから下の冷え性だ。机に向かっている限りは
快適となるが、部屋全体が温まるわけではなく、よって机から離れられない。机にしがみ付き仕事をする破目に。
これが集中力のなせるワザならよいのだが……。
(2月3日)
■キャラクター{ミンミン}シール作製
もう何種類のシールを作ったろう。 相模女子大学の「子ども教育学科」は誕生まもない。いずれ
”卒業生の現場での評判”が歴史をつくってくれるであろうが、それまで手をこまねいているわけにはいかない。
イメージづくり(戦略)の一助にとキャラクター展開を試みている。
元気、明るい、素朴、自由……MINMINちゃん、頑張れ!!!
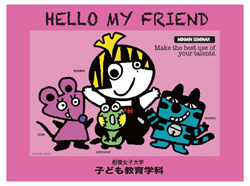
 、
、

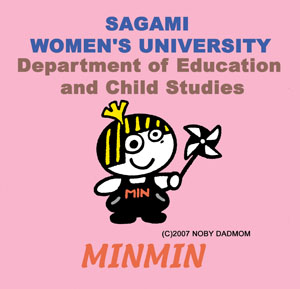
| 1月のアトリエだより |
■コンソーシアム大学……”仕込み”続く 「お化けの衣装」
渋谷の生地屋さんで白と黒の天竺木綿を買う。白はお化けの衣装、黒は○○○仮面のもの。頭からすっぽり
かぶる簡単な構造。子どもたちが作る仮面を引き立たせるよう体を覆い隠すのだ。まずはぼくが黒いので登場、
アシスタントの学生3名は白いお化けになってもらう。5日に試作品を作るが、学生もぼくも、子どもには勝てっこない。
”勝てっこない”は、競う気持ちの表れだ。もちろん、子どもなんかに負けてられない!想像力で、いざ勝負!
遊んで楽しんで、真剣勝負だ!”勝負”は”心のままの表現”と置き換えよう。そう、”心のままの表現”は
比べるものではない。当たり前のことであった。
(Jan.30)
■コンソーシアム大学 「作ってあそぼう」申し込み締め切り!
子どもと親とで作って遊ぶワークショップの申し込みは締め切られた。事務局より定員をオーバーしたとの報せあり。
熱心な方々の気持ちをかなえてあげたい。補助椅子を出して対応して貰う。
工作メニューは三つ。 2月6日、① 「世界に一つのミラクル仮面」(大きな覆面タイプと吹き戻しを使うもの2作)
13日 ②「絵変わり仕掛け絵本……あんなかお、こんなかお、どんなかお、みんなかお」20日 ③「イライライラ……コロ玉
バランスボード」作る喜びを味わってもらう。表現する素晴らしさを体験し、止みつきになってくれれば……。
頑張ろう!目一杯、精一杯やる!
5日にはアシスタントをしてもらう学生3名を特訓する。もちろん、ぼくも試作を楽しむ。それにしても教材の準備は大変!
仕事場は段ボール箱の山だ。買い集める、加工する、セットする(パーツを袋詰め)……、ああ今日も慌しく日が暮れた。
(Jan.29)
■造形応用 牛乳パックTOY② 「舌だし人形・・・愉快な仲間達」


 「こんなこいるかな」へ
「こんなこいるかな」へ
・アリガくん試作例 (「こんなこいるかな」バージョンを別項『こんなこいるかな』コラムに掲載)
造形表現活動(応用)最終回は牛乳パック(ミルクカートン)工作。材料はカートン一個半とゴム輪2本のみ。
カートンはTOY①同様裏返して使う。学生は始めの頃恐がっていたカッターナイフにも大分慣れてきた。手作業の
大事さ、それに廃物利用”創意工夫”する心を育てたかった。
TOY上部の持ち手を放すとパチン!の音とともに目が変化する玩具。単純素朴なことが「壊れにくい、飽きさせない、遊び方が工夫
出来る」など、よい遊びの条件の幾つかを満たしている。遊びといえばDSやPS一色の感があるが、自ら作る、その素晴らしさを
放棄しているようでもったいないことだ。遊びを創出する……ここにも自己表現がある。学習で疲れた学生が教室で
生き生きした表情に”蘇生”するのを見るにつけ、定まった答えのない表現の世界で遊ぶ(自由な心での表現)ことの
重要性を再認識する。
(Jan.27)





・学生制作作品例(舌は出たり引っ込んだりする。写真はすべて長い舌が伸びたところ)
■造形応用 牛乳パックTOY① 「回転円盤絵変り・・・六面相」



牛乳パックTOY制作その1 「回転円盤六面相」を作る
学生の積極性が感じられるようになってきた。バイト先のコーヒーチェーン店から、牛乳パックを大量に運んできた者、朝、研究室に
立ち寄り、パックの包みを置いて行く者……、牛乳離れが進んでいる若者が、何とかして授業に役立てようと頑張る姿……嬉しいことだ。
自主性こそ、創意工夫する心、自己表現する心、とともに学生に摺り込みたいことだから。
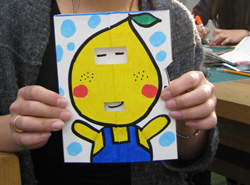

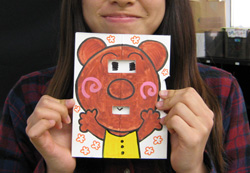

(Jan.22)
■二十四節気<大寒> 七十二候(七十候.七十一候.七十二候)
 |
●大寒は1月21日 ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
このところ寒い日が続いていたが、昨日今日は最高気温が14,5度。3月の温かさだ。明日は18度にもなるという。が油断は禁物。
あさって、金曜日はまたぐっと冷え込むとの予報。久しぶりのテニスを予定しているのに……。日差しに明るさが増してきた。
春が近づいている。もうすぐ立春だ(2月4日)。
(Jan.20)
■ NHK教育テレビ「絵本寄席」をご覧下さい


1月29日(金)午前7時45分~50分 NHK教育テレビ「テレビ絵本」にてえほん寄席のアニメが
再放送されます。『目黒のさんま』(有賀忍・絵 三笑亭夢太朗・落語)早朝ですが、どうぞお楽しみください。
■シラバス打ち込みと、紙芝居作画に明け暮れる
新年度の履修科目シラバス作りに大わらわ。昨年から提出がパソコン入力となり操作に戸惑う。キーボードから
20分離れると自動的にすべて消去されるし、「更新」「保存」が分かりずらく何度もやり直すはめに。10科目を
入力し終わる頃に漸く慣れたが。
授業が始まる前に、仕事の目処をつけねばと、紙芝居「だいじな たまご(仮題)」制作も頑張った。こちらの苦心は
鶏小屋の金網や、卵が割れて悲しむ少年の表現など。ストーリーが単調で、紙芝居の”単純明快、可視性”はクリア出来たとは
思う。が、やはり絵本も紙芝居も”面白くてナンボ”………不満がない訳ではない。
(Jan.15)
■エンターテイメント
正月テレビは殆ど見ない。ニュースを除いて。ただ、小朝の落語「親子酒」には抱腹絶倒。ろれつの回らない親子の酔っ払いの
掛け合いが見事。酔いが回るにつけ顔までが赤くなっていく様は感動物!話のおもしろさ、形振りの上手さ、完璧だ!
大学の帰り道、NHKラジオの「真打競演」を聞くことが多いが、漫才も落語も大笑いさせるもの少ない。話がつまらない。
生中継ではないし、”話芸”を収録するのなら、選ぶべきだろう。天才、小朝を聞いて思った。
■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候.六十八候.六十九候)
七十二候も最早六十九候。あと三候残すのみ。<小寒>の次は<大寒>。そして、
いよいよ<立春>……春の到来だ。
 |
●小寒 1月5日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
| 12月のアトリエだより |
■鳩山は冬景色。枯れ葉で埋め尽くされる
アトリエの周りはすべて枯れ葉で覆われた。この間まで鬱蒼と茂っていた木々は裸。空が広がり明るくなった。
ブナの木だけが薄茶色の葉をまだ落とさずにいる。風に飛ばされまいと、しわしわの葉の塊がしがみつくように付いている。
枯葉を集めて井戸を改造した腐葉土枡へ運ぶが枡はすぐ満杯。諦めた。「一面枯葉の野」に与すパワー不足だ。
創作行為とはことなるが、草取りや枯れ葉集め……これらは、妙に楽しい。いえ、楽しいとは違う。何も考えない時間を
すごす嬉しさかなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
ノロウイルスか、風邪か。張り切ろうにも力がでない。普段から低体温で、一寸でも熱っぽいと頑張ろうにもだるさには抗えずダウン。
今年も無事に乗り切ったかと油断したわけではないけれど、この暮れ、最後の仕事にブレーキがかかる。とはいえ、しがみつくように
ダラダラと作業。 熱が引いて、即コートへ。鈍った体に喝を!荒療治!………無謀なり。
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
師走になり、日が過ぎるのが一入早く感じられる。毎年のことだが……。追いかけられているようだ。追いかける位の
心の余裕がほしい。アクセク、バタバタ、アタフタ……で、今年も暮れそうだ。 嗚呼。
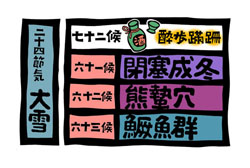 |
12月7日は大雪 (12月22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
■寒さものともせず(ウソ、大強がり)テニス
昨日は冷たい雨。幼稚園講演会。会場は100名を越し満員だったが、冷え冷えとしていた。終了後のサイン会では、足元が冷たく
膝をすりあうようにした。寒かった。
今日は曇り。オムニコートは湿っているだろうが打ちに行く。メンバーはぼくより高齢な方が多い。それも、週一のぼくと違って、
週三、四回はプレーしている兵ばかり。捻られるのを覚悟の上参戦!ただ時間を気にせず打ってみたい。忙しないなあ。
■鳩山は落葉の季節。”目の幸せ”紅葉もおしまい
モミジは峠を越えた。サクラはすべて葉を落とした。ブナの茶葉、カシワ、モクレンの薄茶色……、あたりは茶色に染まっている。
中で鮮烈な赤色を留めているのがハゼだ。植えてよかった。来年はもっと植えよう。ローズヒップ、ブルーベリーの葉も。
雨に洗われて秩父の山並みがくっきり見える。日差しも柔らかく、のんびり……としたいところだが、仕事仕事!
描いている10号の絵を二枚直しをいれる。フレームの製作にも着手。手を洗う間もなく車上の人。慌しい。よくないなあ……。
■師走……キャンパスを走る……アタフタ アタフタ
授業はいつも時間が足りない。演習科目のつらいところだ。準備や試作で休む間もない。研究室に来訪者があれば、昼飯抜きとも
なり、空腹と戦いながらの教室。この季節も汗びっしょりで、キャンパスの風が一入冷たく感じる。気力で持っているのだろうが、
おかげでメタボとも無縁、カゼ菌も寄り付かず元気。(多分に、やせ我慢)
■小石に絵付け 3


・ジェッソ(下地剤)を塗り描く。顔、顔、顔…… ・人面石 ・拾った(顔が描かれていた)石
| 11月のアトリエだより |
■小石に絵付け 2


紙芝居《やさしいこころ》に添えて配ろうと、小石に登場人物”おにぎりん”の絵を描いた。
今日の授業は先週に続きPEEK A BOO……「いないいないバー」は幼児が好む遊びの一つ。紙一枚で2場面、4場面
変化するカードを制作した。仕組みは簡単。学生は思い思いのイラストを描く。シンプルなものほど応用性がある。遊び方も
工夫できる。スイッチを入れたらお終いのICを使った高価な玩具より、やはり手づくりだ。工夫の余地があるかないか。
想像力と創造力を育む遊び、玩具とはどんなものかを学生には考えさせたい。
■二十四節気 <小雪> 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
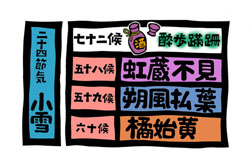 |
11月23日 小雪 (12月7日 大雪) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
アトリエまで、今日は関越高速を使わず川越街道を走る。三芳あたりのケヤキ並木の紅葉が目当て。春から夏、
街道を覆い隠すほどだった緑のトンネルは葉を落とし秋空をのぞかせていた。今年は遅いのか。黄色、茶色、赤色……の
紅葉はまだだった。このあと、一気に紅葉、黄葉がはじまり、嵐のように葉を落とすのだろう。残念だが見られそうもない。
アトリエの庭のハゼは鮮やかな紅色。ブナは茶褐色、桜、モミジ……冬の入り口、風に震え、舞い落ちる……色の饗宴、
静かな時間、心穏やかなる一時。
■小石を拾う……形を楽しみ、絵をつける



校内の駐車場の脇で小石を拾う。一つ一つ形を吟味しながらビニール袋に入れるぼくを、学生や教員が怪訝そうに見ている。
20個、30個、相当な重さだ。洗って改めて形を眺める。石に絵付けをするのだが、なんと”先客”がいた。顔が描かれた楕円形の
小石があったのだ。小学部もあり、子どもが描いたのだろう。見つけたときは、思わずにっこりだ!嬉しくてねえ。描かれた目、鼻
、口はかすれてはいたが白色が美しかった。これを描いた子と会いたいなあ。
紙芝居『やさしい こころ』を制作した。少年と作業服を着た工事現場のおじさんが登場するお話。そのおじさんの顔がおにぎり
そっくりで、少年は<おにぎりん>と呼んでいた。少年は図工の時間、小石に絵を描いた。ペンギンやカメや自動車などいろいろ。
<おにぎりん>もね。 中央の写真はぼくが作った<おにぎりん>。おにぎり形の小石は結構多い。幾つか作って、紙芝居を演じる
方に差し上げようと思う。”実物”を見て、子供たちが、自分でも作ってみようと言う気になったらうれしい。
■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)
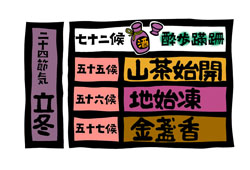 |
11月8日は立冬 (11月23日 小雪) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■赤い実の季節
鈴なりの渋柿が熟して枝を撓らせている。ナツメが落果。サルナシも柔らかに……、
カマツカの暗紅色、カラスウリの朱赤……陽に照り映え、今 秋真っ只中。






面白い実を見つけた。見たことのない形、蔓に二十数個の赤い実の塊まりが10センチおきについている。蔓は「長い。引っ張り手繰って
根元まで近づこうと試みるが、山の斜面が崩れやすいこともあって難儀。根は深く、球根を持っていた。わがアトリエの庭で育ててみたくなり
図鑑で調べた。サルトリイバラ……ユリ科の多年草。実もそうだが、葉の脇に一対の髭があり、この特徴からすぐ名前が解った。
細いさつまいも状の球根は漢方薬「山帰来」となる。北斜面の日当たりの悪い茂みの中で育ったサルトリイバラ……大事に、といっても
似たような場所に移植、根付くよう祈った。
| 10月のアトリエだより |
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
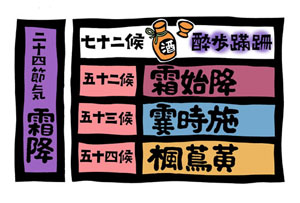 |
10月24日は霜降 (立冬……11月7日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
24日は二十四節季の霜降なれど、汗ばむほどの陽気。現代童画展審査に臨んだ。25日は一転襟を立てて歩く寒さ。終日、
審査会場に詰めていて分からなかったが、木枯らし一番が吹いたのだそうだ。賞の決定、推挙会議と慌しかった。
『現代童画展』第37回!ぼくも、まあよくも出品し続けたものだ。本年の目玉は、過去の大賞作品を集めての特別展示。
ぼくは第3回展で大賞を受賞したが、その作品も久しぶりに”お披露目”。ただ、会場が狭いため、『星の海』一点のみ。
『花の野』が飾れないのは残念である。
本展出品作は『星の道』。 7月の選抜展で発表した”『沈黙の闇』の後”を描く。 選抜展をご覧下さった方は、
イメージを重ねていただけたらと思う。
鳩山アトリエ、秋真っ最中。ハゼの紅葉がはじまり、パンパスグラスに絡むカラスウリが風に揺れている。こっちに一つ、あっちに一つ……
濃い朱赤が目の奥に染み込んでいく。雑草に負けずに蕾を抱いたニオイスミレを見つけた。数株集め周りを煉瓦で囲い”スミレの園”に。
イーゼルから作品を降ろし車に積み込んだ。いつもながら、アトリエ立ち去りがたし。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)
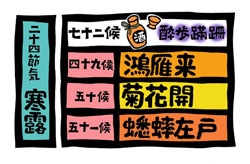 |
10月9日は寒露 (10月24日は霜降) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展は東京都美術館が改修工事のため、本年も上野の森美術館で開催される。会場壁面の都合で30号とサイズも
制限される。大作に臨みたい気持ちも強いが、この春以降モチーフが少し変わってきており、画面の小ささはさほど気にならない。
今まで <心のふるさと……懐郷の詩> <親子・父と母・父性・幸福感>を描いてきた。今回の作品も底辺に流れるものは、
そう変わらないが、さりとて明るいものでもない。春は『沈黙の闇』。今仕上げの段階にあるのが『星の道』。絶望感の中に一筋の
光明……出発だ!それも力強く、頼もしく、矜持を……ぼくは描く。是非ともご高覧あれ。
(展覧会詳細については後日)
■キャンパスのイチョウの木、銀杏落ち始める
教室の机の間を歩き、いや小走りで回っている。コマネズミの譬どうりチョコチョコ忙しなく。声がかからずとも、その人その人
描き出すものの、ユニークな点、おもしろい所を見つけようと。見逃すまい、学生は気が付かない線の流れ、動きを。
教室の暑さは一頃とくらべ過ごしやすくはなったが、ばくは汗びっしょりだ。授業を終え研究室に戻るまでの僅かな時間、
秋の風を満喫。深呼吸して歩く。銀杏を踏まないように避けて、コマネズミは時間を惜しみながらゆっくり歩く。
| 9月のアトリエだより |
■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)
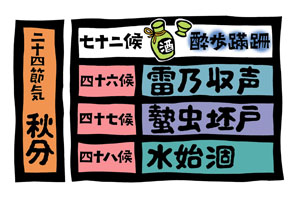 |
9月23日は秋分 (10月9日は寒露) ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
■鳩山、冷え込む!長袖で板絵に向かう



二日間、板絵に取り組む。
アトリエから一歩も出なかったと言うのはうそで、体、殊に目を休めるために鬱蒼としげる葉を掻き分け栗の木まで進む。
まさにジャングルを”進む”感じ。栗を拾おうにも腰高の草が邪魔して、落としても見つけるのが大変。それでもビニール袋は直ぐ
いっぱいになった。
幾種類か植えた萩は雑草に覆われてしまい目を凝らさねば小花が見えない。
自然に生えた道路沿いの柿の木には青い実が枝を撓らせている。大豊作だが残念ながら渋柿。辺りにフジバカマが咲いている。
紅葉は”ハゼが一番”と植えた苗木は雑草に囲まれながらも育っているが、葉の色はまだ緑。アトリエの窓からは見えないが、
工作部屋のわきの山葡萄の房が膨らんでいた。昨年、一昨年と実がつかず枯れたのかと……、今年ヤマブドウの苗木を求め、
近くに植えたのが良かったのかもしれない。ナツメもサルナシもよく実った。マタタビ、ムベ、アケビは葉を茂らせただけで終わった。
アケビは花を沢山咲いたので、実りを待っていたのだが……(アケビの皮のバターソテーは好きな酒肴)
「30分だけ」と予定しても、庭に出れば一時間くらいすぐ過ぎてしまう。制作に没頭も集中力のなせる業だが、自然に実を置くのは
もっともっと自然体。自分の素を丸出しにするという点で、自然に身を置くことと創造の世界に住むことは似ている。
下の田圃の主、石井さんが新米と玄米を届けてくださった。
軽四輪の助手席にはいつも満面の笑みの奥さん。アクをすくい、すくい丁寧に煮あげた栗の渋皮煮、栗の形をきれいにそのまま留めた
上品な味、見事な”作品”を持ってきてくださった。石井さんの前で、ぼくは二つもペロリ!美味い!感謝感謝!
秋の味覚、贈り物が嬉しかった。 気力充填して、仕事に戻る!
■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)
鳩山は大気澄み星が降るようだ。今晩は星の瞬きを妨げるような明るい月夜。十五夜だ。中秋の名月、観月のゆとりもなく、
アトリエでパネル作り。プリンター置き台も製作する。工作は性に合っており楽しくて、なかなかその後の、“本来の”制作に
はいれないで困る。
もろもろの教習、講習会も終わり、秋学期が始まるまで制作に没頭する。時間がなくあせりながら……いつものことだが。
ナツメが赤く色づき始めた。サルナシが頭を下げねばアーチをくぐれないほどたわわに実った。栗の実はやたら降り落ちている。大粒だ。
地域物産販売所でアスナロの幼木を見つけた。“明日は檜になろう”から翌檜と書く。百円!。植木鉢代にもならないだろうに。
勿論買って、杉の木の根元に植えた。吾、アスナロと思ったことなし。今思えども、もはや遅し!
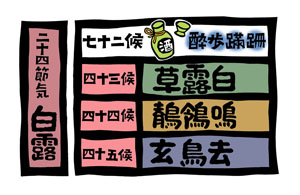 |
9月8日 白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
| 8月のアトリエだより |
■二十四節気<処暑> 七十二候 (四十候、 四十一候、 四十二候)
 |
8月23日は処暑 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月29日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月3日) ・いなほ みのる 稲が実る |
■楽しきかな、ブリコルール!
牛乳パック、ペットボトル、ガムテープや食品ラップの巻き芯などの山に埋まる生活をしている。図工の先生方の研修会に
ブリコラージュを基本テーマに選んだ。(ブリコラージュ人間をブリコルールという) 廃物を活用しての造形遊び。遊びといっても、
楽しめるだけではなく、美しくて飾っておきたくなるようなもの、かなり雑に扱っても壊れない頑丈なものの考案だ。遊戯性と造形美!
工作は楽しいが、わが渋谷の狭き仕事場は、ゴミ箱と化している。フローリングや空間はいつになったら、再び現れるのだろう。
■鬱蒼と生い茂る鳩山の庭……ハチとの戦いはじまる
鳩山のアトリエで教員研修会の“メニュー”作りをしている。最近、わが鳩山町は熊谷に次ぐ暑さで
、テレビに地名のテロップ流れる始末。地形が似ているのだろうか。暑い!でも夜は東京より涼しく感じられる。
土と緑のおかげだ。伸び放題の木々、背丈を越える雑草にも感謝だ。
喜んでばかりはいられない。誰も踏み込まないのをいいことに、ハチが我が物顔で飛び交っている。
デッキを補修、ペイントしようとして蜂の巣を発見!ご飯茶碗ほどもある。スズメバチなら手の負えないから業者に
頼むが、幸いにもアシナガバチだった。防護服でいざ戦!二挺拳銃よろしく両手に防虫スプレー、棒で巣を掻き落とした。
アシナガの群舞は恐ろしいほどだ。巣がなくなっても、ハチはどんどん集まってくる。ペイント作業は中止だ。
階段下の薪置き場にもう一つ、アシナガバチの巣を発見。これも退治。仕事どころではない。いま、巣作りの季節だ。
取っておかないと大変なことになる。昨年はスズメバチに悩まされた。そういえばミツバチがいない。アトリエの壁の間に
巣作りし蜜を部屋に滴らせたミツバチは何処に消えたのだろう。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
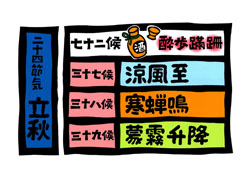 |
8月8日は立秋 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■大学のオープンキャンパス 《子ども教育学科》受講生みな熱心!
今年のオープンキャンパスはティーチングアシスタントに大学二年生三名を起用。万全の態勢で臨んだ。
一時限の授業で、早朝からの出席を心配したが、生徒がつめ掛け満室状態。アンケートでは「満足」が多く、
アシスタントと喜び合った。三名には、月末に行われる教員研修会でも、手伝ってもらう。彼女らがいると、
教室が明るくなる。
研修会が終わる間もなく、幼稚園教員指導が待っている。園児が作って遊べる、“凄くおもしろい”おもちゃを
披露しようと今、試作を繰り返している。仕事場は雑然!がらくたの山だ。本来の絵画活動が
疎かになっている。制作に入れるのは9月になってからか。目の前の仕事が多すぎる!
■ホップの間に植えたもの
珍しいものを植えた。日差し避けにゴーヤや朝顔が話題になっているが、ぼくは野ブドウを植えた。
ホップの苗が育ち、180センチのトレリスから蔓が巻きつくところを探して揺れている。そのホップの間に
これまた蔓性の野ブドウ。
山葡萄はある。枯れかけたが今年見事に再生、今小さな固い実をつけている。
山葡萄の掌より大きい葉っぱと違い、野ブドウは小さいが形が美しい。野ブドウは食べられないが
葉を見ているだけで、何だか嬉しい。この炎天下、根が着くか心配だ。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
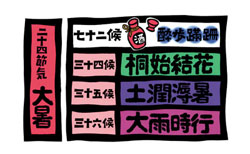 |
7月23日は大暑 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 3日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
■ミルクカートンTOY


・(左)3単位体 テーマ クリスマス菓子 ・(左上) スイーツ ・(右上) 泣き笑い
・(右)1単位体 こんなこいるかな ・(下) こんなこいるかな


・ペロ&ミャー
今回の廃物利用ミルクカートンTOY。牛乳パックを開き裏返してカット。三枚組み合わせたものが1単位体。
その単位体を三個単位でつなげて行く。学生は時間の関係で2単位体の構成がやっと。ぼくは3単位体構成、
4単位体構成の作品を見せた。一単位体で12面ある。それらすべてに絵を描くか、切り抜いた写真を貼る。
6面が泣き顔、6面が笑い顔……、コツが解れば絵変わりもスムーズにできるが、初めての人は面食らうだろう。
面白いキューブパズルだ。学生は思い思いの動物や表情豊かなお化けの絵をつけて、友と交換しては楽しんでいた。
遊びを通じてのコミニュケーションも狙いの一つ。時に”学び”は楽しさの中で行われる。
| 7月のアトリエだより |
■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 小暑 (7月23日 大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月13日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
7日は<小暑>。《温風至る》だが、熱風の”風”さえ吹かず。教室も節電のため空調の温度設定厳しく汗まみれの授業だ。
新校舎は”モダンデザイン”で窓が開かない。暑さには強いぼくも閉口の日々。絵の具を乾かすためドライヤーを使うときなど、
もう炎熱地獄。我慢我慢。
■現代童画会 選抜展開催中
現代童画会 選抜展が只今開催中。 (銀座アートホール10日まで)
板絵『沈黙の闇』を出品しております。ご高覧ください。”蒼”の表現に悩んだ作品です。

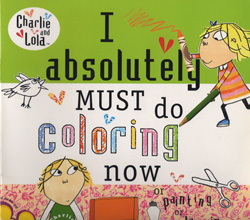
アストリッド・ リンドグレーン展(世田谷文学館) 《長くつしたのピッピ》《やかまし村シリーズ》《ロッタちゃんシリーズ》原画を見る。
子どもの時代、子どもの世界を生き生きと描いたリンドグレーン。見慣れた挿絵から、現代のアーティストのイラストまで多数展示。
中では、ローレン・チャイルドの《長くつしたのピッピ》。一目でわかる、キュートな表情。目が強い。
ローレン・チャイルドの塗り絵本(ペーパーバック)を持っているが、塗り絵には否定論者であるぼくも、この絵本には魅力を感じている。
ただ塗るだけのカラーリングブックではなく、自由に描きこめ、またそのリードして行くネームが効いている。塗り絵本は数々あれど、
このようなものがもっとあったらと思う。
| 6月のアトリエだより |
■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
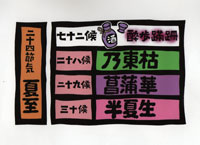 |
6月22日 は夏至 (7月7日/小暑) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■スタンピング……葉脈の美しさ……人工物との組み合わせ


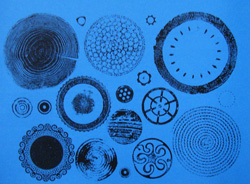
トチ、サンショ、トチュウ(杜仲)、ウメ、 クヌギ、ムベ、ベイ、リンデン、メープル、ブナ、ナナカマド、オニグルミ
絵画造形表現活動基礎Ⅰの授業。オートマティック技法(モダンテクニック)。要は子どもの造形表現遊びの基本。
デカルコマニー、フロッタージュ、スパタリング、ウオッシング、コラージュに続いて、今回はスタンピング。自然物(葉っぱなど)と人口物を
ペタペタ押して再構成。こらー^ジュ作品の制作。
鳩山で葉っぱを採取。形の面白いもの、葉脈が鮮明に写し取れそうなものを選ぶ。3クラス分を冷蔵ボックスに詰める。
クヌギ、山葡萄、菩提樹、桑、サンシュユ、ハナミズキ、オニグルミ、オオシマザクラ、イチョウ、モミジ、サトウカエデ、山椒、
ブナ、トチ、トチュウ、ワイルドストロベリー、ヤツデ、ミニチュアローズ、ローズゼラニウムなど。学生には植物の話(名前の由来、エピソード)も
聞かせた。ローラーを転がし刷り取った者をカットし台紙に再構成する。楽しめたようだ。
ウオッシングについで面白かったとの声も。演習は先ず楽しむこと。楽しんでこそ学習となる。みんな、始めはインクが手に付くのを
嫌がっていたが、仕舞いには指紋どころか手にローラーを転がし手形をペタペタ押していた。
とにかく夢中にさせること。集中させること、これに尽きる。
ローラーやインクバットを洗ったり、葉っぱの始末など後片付けが大変だが、学生の”満足感”が、ぼくの疲れを軽減させてくれる。
次回は墨流し、マーブリング。ぼくは市販のマーブリング剤やセットになったものは使わない。墨のマーブル模様の美しさ、そして
油絵の具を溶いたものを掬い取るカラー版にTRYする。出来合いのマーブリング液を使えばきれいでかんたんだが、それでは
力がつかない。すべて作る。大事なことは、「これがなければ出来ない、これが揃ってないとダメ……」ではなく、応用力、創意工夫する心。
表現とはそういうものだ。準備万端、用意周到からは生まれない。不自由なくらいがいい。足りなくてちょうどよい。恵まれすぎは、
想像力や創造性を培う環境によろしくないとぼくは思う。
■木っ端で名札を作る



・木っ端 (切り抜かれた円形の上部) ・両端をカット (ステインを塗ったもの) ・黒ペンキで名前を書いて完成
地域の産物の即売所ができた。米、果物、野菜の農産物が主だが、植物を売るコーナーもあって、鳩山に行くときは
必ず寄ることにしている。都会の園芸店では見られない面白いものがあって楽しい。キンズ、カマツカ、ヤブコウジ、ハゼ、
マートルの苗木はみなここで買った。一鉢500円~800円と安い。アトリエの畑に茂るムベやサルナシも珍しいと思っていたが、
これらも売られていたからびっくりだ。
即売所には木工製品もある。まな板や鍬の柄。ぼくが買うのは木っ端の束。何かを切り抜いた残材、10枚束ねたものが、何と120円!
昨年は100円だった。これをぼくは名札に利用している。もう数十枚は作っただろう。ブナやクヌギ、昨秋植えたオオシマザクラなど
樹木の苗木が主だが、まだまだ足りない。販売物にはすべて生産者の名前が記されている。木工製品も然り。○○清作……。
この木工の主はどんな方だろう。
このなだらかな山型の木っ端は何を作った後の物なのだろう。大量に出るから不思議だ。「清作さん」に聞いてみたい。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候
 |
6月5日は芒種6月6日 (夏至は6月22日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
■板絵「沈黙の闇」制作没頭。
夜来の雨があがり鉛色の空、水田は天を写す鏡だ。周辺緑一色の中で銀色反射、”何も無い美しさ”だ。小鳥もまだ訪れず
静寂そのもの。幾度も深呼吸をしてアトリエに入る。
このところ週末は板絵に取り組んでいるのだが、モチーフが<哀しみ>そのもの。描いていても辛くて苦しくて感極まってしまい、
「これではいかん」、冷静に冷静に……言い聞かせながらの作業。
顔の色が出来ない。塗っては「違う」、塗り重ねては「違う」の繰り返しだ。絵が重く暗い。描けなかった時から、絵筆を
取る、表現する気力漲るまで時間を要した。『哀しみの船』、『悲泣の丘』以来だろう。胸が塞がる思いの制作は。
■茶の木を探す
今年も茶の木の新芽を摘んでフリッターにして食べた。香りがよい。もちろん酒の友。制作の後の「反省の酒」だが、目一杯
表現出来さえすれば美酒となる。なかなか、そう美味くはいかない。
Sさんが、茶を育てたいと言う。苗木を差し上げたが、楽しみにしていた新芽が何者かに採られてしまった(消えてしまった
そうな)と、がっかりしておられた。そこで今回は少し大きめのものを用意した。零れ種からあちらこちらに発芽しているが、
適当なサイズのものを選ばなくてはならない。植木鉢がSさんの自転車の篭に収まらなくてはならないから。
新芽は手もみ茶に、おひたしに、天ぷらに……、すくすく育ちますように。
■学生の習作を発表する場がほしい
子ども教育学科には、ほぼ隔月発行の『ミンミン新聞』があるが、学生の制作物が発表できるページの余裕はない。
絵本でも数冊、ペーパーカッティング「シンメトリーデザイン」や連続模様制作でもかなりの秀作があった。講評して返却するのだが
何とも惜しい。作品を並べて見せるが、他のクラスの学生には鑑賞させられず残念だ。創作する一方、良い作品を見ることも大事だ。
一部修整、補作し学生に”作品集”として配布することにした。学生は色んな紙で(薄い色など)自由に制作するから、
版下にするには墨画線に置き換えなくてはならない。一昨年も作ったが、この作業は時間がかかりめんどうくさい。
「素晴らしい作品を作った」……学生に自信をもって貰いたい。園や学校の現場でも制作のヒントに資料としてきっと役に立つだろう。
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
ホップを植える! 実を何に使おうか……早すぎる夢想……
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (6月1日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
アトリエ周辺の田圃は田植えが終わり人影なし。水面を横切る鳥の影。静寂の中に時おり鳥の声。「ホーキョ」「ホーキョト」……
下手だったウグイスも「ホーホケキョ」。すっかりうまくなった。
東北の被災地では作付けを諦めた水田が多いという。緑の苗が黄金の稲穂に変わるまで、ずーっと惨い災厄が頭から
離れないだろう。
絵を描いていても、テキストを作っていても、お話を書いていても、胸は重苦しく、気が晴れない。集中力乏しく苛立ちを覚える。
創作はいつだって厳しいものであるが、これほどキツイとは……。
気分転換のテニスも楽しめない。”逃避”だからであろう。大分前のことだが、サッポロビールが運営していたクラブでプレーした
ことがある。このコート脇のフェンスで、さすがビール会社だ、ホップを育てていた。ホップが高さ10メートル以上も薄緑のカーテンを
作っていた。今ゴーヤなど壁面緑化が話題になっているが、あの、コートを覆い隠すようなホップは見事だった。
少し失敬してきて、ホップのリースをつくったこともあったっけ。
そして、とうとうホップの苗を手に入れた。野生のものではないが、自然に還したいと、竹やドクダミやスギナの生い茂る土地を耕し
腐葉土を敷き詰め苗床を作った。トレリスを立て水を遣る。
しっかり根付きますように!少しだけ、ほんの少しだけでも実をつけますように。
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
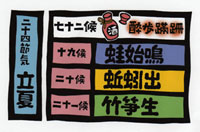 |
5月6日は立夏 (5月21日は小満) ・十九候 (5月 6日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
■アトリエのフェンス倒壊す
筆を取る、板に向かう気力興らず。胸は塞がったままだ。それでもアトリエに入れば……と、久しぶりの鳩山詣で。だが、
それどころではなかった。地震か強風か、フェンスが倒れていた。フェンスと言っても三寸の角材を組み合わせた頑丈なものだ。
それが、道路に沿って横倒し!滅多に人が通る道ではなく事故に繋がらなかったのは幸いだった。連休中だが、設計図をひき
工務店を呼んで交渉した。
■今年はミツバチ大丈夫…………か。
昨年は全国的にミツバチの姿が消え、何が原因かもわからず問題になった。わが鳩山の庭でも明らかにその数が減少した。
それまでは乱舞する大群、母屋の壁の間にも巣を作り蜜をたらすミツバチだったのに。今年は大丈夫……かもしれない。
花の間を忙しく飛び交っている。カマツカの小さな花から、アケビやムべの花、少し前までは、ミツマタ、杏、サンシュユ、
プラムなど、花の季節をミツバチは我が者顔だ。



・百花繚乱……ミツバチの季節 ・アケビの花(五つ葉) ・カマツカの花


・ムべの花 花弁に見えるのはガク。 ・たった一輪咲いたリンゴの花(ヤーノシュの絵本『おばけりんご』の一ページを彷彿)
乳白色で内部には紅の線
| 4月のアトリエだよりエだより |
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
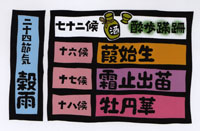 |
4月20日は穀雨 (立夏は5月6日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (5月1日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
新学期が始まった。『実践遊び学』3クラス。『絵画造形表現活動・Ⅰ』3クラス。昨年よりパワーアップした授業展開をしたい。
具体的にはカリキュラムの調整以外に、『実践遊び学』では殆ど毎回、”おまけ”と称してごく簡単にでき、子どもをアッと言わせる
楽しい造形手遊びを紹介していく。そして『絵画造形表現活動』では、”帽子百貨店”と題したクラフト製作を、今まで十数点だった
ものを、今年は創作5点追加、学生にはかなりハードな作業(時間がタイト・集中力勝負)となる。
月曜日『実践遊び学』第一回は、鏡面紙を用いたシンメトリー図形遊び(製作・発見)および万華鏡考察。製作だった。この時の
”おまけ”は、「紙一枚(A4大)左手のひらに穴を開ける」法………というものであった。紙をクルクルまるめ円筒形にする。これを
用いて掌に穴を開けるには、さてさてどうする?(授業では万華鏡作りに用いる紙筒でやらせた)
「あっ、あいた」「穴が開いた!」「向こうが見える!なに、これ!」「わあー!」教室がどよめいた。
「穴があかない」「えー、穴、見えない!」何人かは、始めうまくいかず、とまどっていたが、学性同士教えあって全員、手に穴が
開いたことを”確認”した。一体、どうやって手のひらに穴を開けたのでしょうか?
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
杏の花が咲いた。明るい青色の空のもとでミツバチを誘っている。ミツマタ、サンシュユの黄色
土佐ミズキの淡い黄、レンギョウも。やはり杏がいい。杏の白を際立たせるかのように、空には雲がない。
遠慮してくれているかのようだ。杏は梅の花をふっくら大きくした感じ。清らか。
穏やかな日和、春景色。平安なれど、このところの心中、苛立ったまま。
オニグルミ、カマツカ、ブナ……まだまだ、芽は堅い。ときおり吹き来る(荒れる)冷たい風が木々を揺らしている。
ケキョ…ケキョ… ウグイスの囀りトレーニングも始まった。 さあ、我も始動!!!
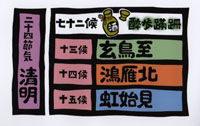 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
| 3月のアトリエだより |
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
板絵 『おやすみの前に』 完成!
 |
3月21日は春分 (4月5日は清明) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
天変地異、大震災。胸塞がる。
4月4日開催の現童春季展出品の作仕上げ作業中だった。言葉を失う。筆は止まる。
父と母と子の関係を描いた 『おやすみ前に』 は、もっとも心やすまる刻の物語。でも、
むごい光景を映像を見、今や表現の気力失せる。
何としても描かねば、表現せねば……。無力感。
己が抱えた悩みに埋もれているうちに世界は大変なことに。
厳しい便りもいただいた。その方は体の不調にもめげず”感謝の念”を
語っておられた。なんという心の広さ、包み込む温かさを感じ、
自分の甘えを情けなく思った。。厳しさ、苦しみの深さは人それぞれでも、みんな、みんな大変なんだ
……当たり前の事……、自戒自省。
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
過去はなし。未来も定めなし。あるは今のみ。脚下照顧。拘りから離れられれば活路もあろうというもの。が、その拘り
だらけで(雑事が人生ではなかったのに。いや人生は雑事の中にあるのかも)忙殺される日々。このところ寒暖の差が大きい。
それでも北風が止むと春を思わせる日差しが。春三月。怠惰の我が身に、鞭をくれねば!
■二十四節気<雨水> 七十二候(四候.五候.六候)
 |
2月19日は雨水 (啓蟄 3月6日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
激しかった夜来の雨嘘のように上がるもわが心、暗闇にあり。仕事に逃げ込む不埒な心を嗤い、
見張りの「もう一人の自分」が攻め立てる。手は止まり作業も捗らず。我慢……しかない。
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候
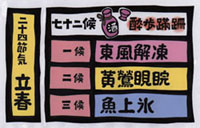 |
●2月4日は立春 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
鳩山の枯野。寒空、一切の葉を落とした木々の枝がくっきり。常緑樹も萎れ勢いは無い。ロウバイの香しさが消え、梅がプチッと
はじけ始めていた。幾分か柔らかになった光の中に春の訪れを感ずる。が、ぼくの心は今や冬真っ只中。芳しくないこと、
身に降りかかる哀しいこと……、暗澹たる思いに沈み、浮き上がる気力もなし。制作空間に身を押し込めて自ら鞭打つしか、
癒しはあり得ない(かった)ことはぼくの人生経験上の結論なのだが……。それさえも……今は。
| 1月のアトリエだより |
■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)
 |
●1月20日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■現代童画展出品作 (上野の森美術館)


■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)
 |
●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
| 12月のアトリエだより |
MERRY CHRISTMAS


師走でなくとも、アタフタ……。安らぐ時なきまま歳が暮れようとしている。嗚呼………。
[日々新生・日々創造] を胸に抱き歩むも、我が羅針盤、現実路線に針路。頑な。
”静かな創作の日々”は夢か!今年、描いた板絵の少なさよ……情けない。
自省自戒の念で多分また大晦日の深酒……。進歩ないなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■『紋型切り紙』の研究 『紋型』から『切り紙』へ
江戸時代は寺子屋でも教えていた紋切り型あそび。明治、大正、昭和……小学校の図工教科書で
どう取り上げられて来たかを調べている。(昭和30~60年代は盛んだった)平成の教科書ではごく小さく載っている程度。
姿が消えたも同然だ。
紙を折りはさみで切る。開くときの驚き、ワクワクする遊びだ。壁面装飾、カード、モビールにと使い道は多く、折り方の
工夫やカットの技術、ポンチの活用など奥が深い。1回折から4回折まで、サンプル作品を100は作ったか。
今回は1、2、3、4回折りまで学生に試させたが、蛇腹折り(屏風折り)は連続模様として別に時間を設け制作させる。
時間があれば切り絵にも挑戦させたい。例としてデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの切り絵でも
見せようか。学生に思う存分自由に紙を切らせてみたい。
・創作切り紙
中央の「二つの馬蹄に挟まれた四葉のクローバー」は、明治39年1月1日小山内薫がドイツから
森林太郎に宛てた年賀状にあった図案をもとにデザインした。
上下の作品は、切り紙「一回折り」で制作
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
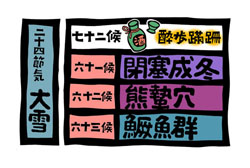 |
12月7日は大雪 (22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
| 11月のアトリエだより |
■二十四節気 <小雪>、 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
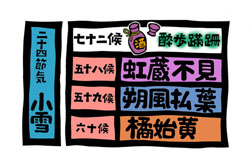 |
11月22日は小雪 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
冷たい雨。キャンパスの舗道にイチョウの葉が張り付いている。踏みつけられ潰れた銀杏も。研究室、先生の在室ランプも
殆ど消えた9時半、大学を出る。寒い。ノートパソコンと大量の制作教材の入ったバッグを肩に、傘を風に飛ばされないように
傾げ持ち駐車場まで歩いていく。
自分の制作が出来ない日々を送っている。このところ学生に見せる教材サンプル作りに明け暮れている。が、これはこれで面白い。
「PEEK・A・BOO(いないないばー)」カードのアイディアを考え、試作するのだが、1枚の紙の可能性追求でもあり、奥が深い。
基本形は裏、表の変化。回転(たとえば、こぶた→たぬき→きつね→ねこ)。めくり。折りなど。 今回は”めくり”に挑戦させる。
「カーテンの向こうは?」カーテンを開けるとどうなるか……。
この制作と遊びは、想像力を鍛えることになる。学生は日頃、「正しい答え」を求めて学習する。自らの考えを述べたり、表現したり
する機会は少ない。造形表現活動を通じて、答えのない世界もあることを、その大事なことを解ってもらう……それも狙いだ。
(NOV.22)
■ 現代童画選抜展 (地方巡回)作品戻る

現代童画展選抜展は銀座アートホールで開催後、四国、関西を巡った。
今年の出品作は「どんぐり嵐」 鳩山のアトリエに埋めたクヌギのドングリ(近くの公民館の庭で拾った)はあちこちで
芽を出し、今漸く腰の丈。
昔からあったマテバシイは剪定の失敗からか元気がない。毎年降るようにドングリを落とすが今年は地面にパラパラ
見かけるくらい。マテバシイのドングリでドングリ煎餅を焼いたことがあるが香ばしくてうまかった。クヌギのドングリは
食べられないけれど、ヤジロウベイやコマが作れる。なんといってもあの形が良い。
我がクヌギがドングリをつけるのは、ずうっとずうっと先のことだろう。下草を狩り、水を遣り幼木を育てる……”夢見”が楽しい。
■二十四節気 <立冬> 七十二候 (五十五候.五十六候.五十七候)
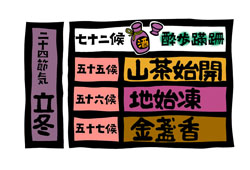 |
11月7日は立冬 ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■「紋型切り紙」を見直そう。けっして”紋切り型”のつまらぬ造形ではない
仕事場は紙くずの山。このところ「紋型切り紙」の原稿書きで色紙を折っては切る、折っては切る……。1回折りから5回折まで、
様々なモチーフをデザインしている。「紋型切り紙」は江戸時代は寺子屋でも教えていた。紋所を染めたり、商売でも子どもの遊び
でも紋切り型はポピュラーなものであった。明治大正、そして昭和の20年頃までは図工(当時は手工)の教科書にも載っていた。
”自由な制作”が教科書の編集方針に変わるとともに、紋型切り紙は姿を消した。昔からある紋や、定番の梅や桜や桃の花を切っ
ている限りでは”紋切り型”の名の如く、創造性、独創性は無いとの謗りは免れないだろう。が、日常性(紙一枚、ハサミがあれば
出来る)伝統の美しさ(継承)、幾何学性、手技の練磨(微細な運動----右脳の活性化)、コミュニケーション能力(教えあう母と子、
友達)など、得るものは多く、肝心の創造性に於いても、自由な造形をテーマにすれば、幾らでも独創的な、たった一つだけの作
品が出来るわけで、子どもに是非ともやってもらいたい造形表現の一つといえる。
1枚の紙でどれだけ遊べる?表現できるか? ……ゲーム機世代の子ども達を導くのは、大人の責任だ。素材の可能性を
最大限に引き出せるか否かは、想像力と創造力それに感受性次第。生きることはそれらを磨くことと考える。
■第36回現代童画展(上野の森美術館)
今年と来年は東京都美術館改修工事のため、会場が上野の森美術館となります。お間違えにならないように。
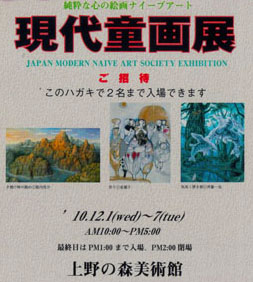 詳細は「展覧会」のページをご覧下さい
詳細は「展覧会」のページをご覧下さい■ 『相生祭』にて講演します -----きみはやだもんを しってる?-----
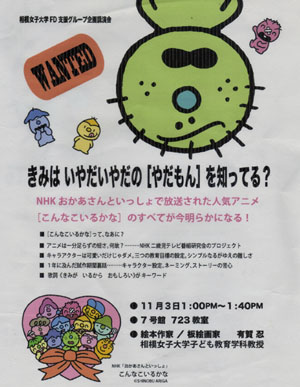

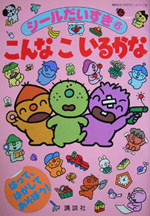


| 10月のアトリエだより |
■現代童画展(上野の森美術館)
出品作の板絵が完成した。東京都美術館が改修工事のため、《現代童画展》は今年と来年、上野の森美術館で開催される。
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
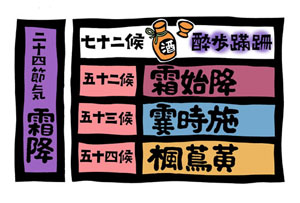 |
霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
■講演会準備に資料整理、パワーポイントつくり……時間が足りない
11月3日は《相生祭》。FDグループ主催の講演会で、ぼくは『きみは、やだもんを しってる?』と題して話す。
制作の裏側のすべてをラフ(下書き原画)などを展示しての講演。『こんなこいるかな』は、1986年から十数年にわたり放送され、
絵本も数多く出版された。現役の学生も、当時母親だった年齢層の方も聞きに来ていただけたらと思う。
ただ“可愛い”だけではないキャラクターの制作意図、NHKの教育目標、制作上悩んだ点、、そして何故今、”こんなこ”なのか?
など色々話したいことは多い。
■仕事の合間、息抜きは大好きな「工作」


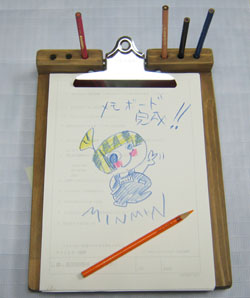

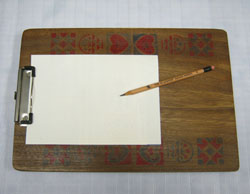

板絵の完成が近づいた。筆遣いが細かくなり遅くなった。今日は終日雨。時おり雨脚が激しくなる。息抜きに外にも出られない。
そこで”工作”。"図工少年"だったぼくは絵描きか大工さんになりたかった。その大工仕事を楽しむ。あり合わせの材料を使って
メモボードを作った。今までいくつも作っており、渋谷にも自宅にも大学の美術室や研究室にも置いてある。が、又一つ拵えた。
いいアイディアが浮かんだら即書き付ける……為だが、肝心のアイディアがそうそう浮かんでこない。
もっぱら忘れ物対策に使われている。情けないなあ。
ステイン塗料を刷り込んで完成。早速、完成間近の板絵を眺めつつ、作品タイトルを練る。メモボードの重量感が心地よい。
これで、「この絵には、これしかない」と思えるようなタイトルが浮かべば万々歳だが……。
(Oct.9)
■ハローウインをモチーフに切り紙トレーニング……学生の積極性、応用力を感じた
絵画造形表現活動応用の授業。保育、教育現場で図画工作、クラフトに使う、使える紙の説明とサンプル帳を作らせる。ラシャ紙、
エンボス紙、カラーケント紙、ミューズコットン紙、マーメード紙、レザック紙、上質紙、工作紙、波ダンボール紙、LKボード、
でんぐり紙等二十数種類切ったり破いたり描いたり、紙の特性を考えながら台紙に貼り付けていく。
…………紙の基礎知識も。「紙って、そもそも何?パピルスは”紙”ではない」「紙が現れる前は何に書いていたの?」
「紙のサイズにA版、B版があるのは何故?」「紙の裏表の見分け方」「ティッシュペーパーが水に流せないわけ」
「コート紙は”化粧”しているって本当?「奉書、麻紙、杉皮紙など和紙について」「紙の原料は?」「牛乳パックは何から
出来ている?」等等。
それだけではつまらないので、実習はハローウイン飾り作り。 紙を蛇腹折にして、ハローウインの”主役達”、パンプキン
{ジャックオーランタン}、コウモリ、魔法使い、ゴースト、ネコなどを切っていく。何体も連なるかぼちゃやコウモリに学生は
大喜び。型紙を渡しての制作だが、各自自由に切り出すから頼もしい。提供した魔法使いの型紙はお婆さん姿だが、ある学生は
「紋形四ツ折り」を使って5人の魔法使いのサークルを作った。それもお婆さんではなく可愛らしい少女のサークルだ。応用力の
芽生えが嬉しい。夢中になっての制作は必ずや身になるであろう。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候. 五十候. 五十一候)
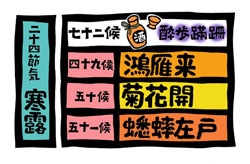 |
10月8日は寒露 (10月24日霜降) ・四十九候 (10月8日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月13日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月18日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展出品作制作のため鳩山詣が続いている。鳩山では終日描くのみ。外に出て萩の花を愛でるゆとりも無いのが
残念である。白萩、宮城野萩、だるま萩……花のトンネル?………が出来ているはずであった。ところが、雑草刈を依頼して
おいたシルバーさんが、萩の木も殆ど刈り取ってしまっていた。かろうじて茶の木の間から伸びた萩が花を風に揺らせている。
萩、薄(ススキ)、桔梗、撫子、女郎花(オミナエシ)、葛、藤袴 秋の七草……このうち、野で桔梗は見かけない。絶滅危惧種と聞く。
絵は完成が見えてきた。絵柄は板絵の性格上(彫が施されているため)大きな変更は出来ない。色だ。色でもって情感の表現をするのだが、
塗り重ねによって絵の表情はがらっと変わる。好ましい、望ましい心象風景が現れるまでひたすら塗り続ける。描く行為はイメージが画面に
現出するまで停まらない。
| 9月のアトリエだより |
■秋の収穫を喜ぶ





2,3日前は30度。今日は十数度の涼しさ。朝からアトリエに籠り板絵を制作する。今年は猛暑のせいかハチが増え
飛び交っている。スズメバチにアシナガバチ。多くて恐いほどだ。アトリエにも舞い込んでくる。ラケット状の電池式蚊取り器で
退治するのだが、空振りすると大変。ハチは攻撃されたと思い攻めてくる。今日もそうだった。一匹見事命中と思ったら、背後から
耳をかすめるように別の一匹が飛んできた。二匹部屋に入っていたのに気づかなかったのだ。危ない危ない!
先日地塗りを終えいよいよ”描ける”。好ましい状態になるまで幾度と無く色を塗り重ねる。ぼくの唯一の贅沢か、絵の具のチューブが
いくつも空になって行く。下層に沈んでいく色は決して無駄ではない。重層的に”我が望みの色”をかもし出してくれるのだから。
この”色遊び”は小学時代の絵の時間、ワクワクして描いた、あの楽しさと同じだ。仕上げるのが目的ではなくそのプロセスが
幸せな心持にしてくれる。この時のぼくは多分、最高に生き生きしていると思う。
「気、澄み渡る……」秋晴れ。台風が来ているそうだが、鳩山は嘘のように上天気。ヒガンバナの群生、原色の赤が目に痛いほどだ。
自分では為し得ずシルバーさんに頼んで刈り取ってってもらった野に出れば、木の葉はも早散り始めていた。栗の実も鈴なりだ。少しだけ
叩き落して集める。石造りの釜で新聞紙を燃やして焼き栗。3つぶほどだが、初物の熱々を味わう。これも我が贅沢。
胡桃も気になっていた。昨年は収穫時期を逸してしまった。今年こそはと、来るたびに注意していた。いつ、もいで良いのやら……。
木の根元に一粒落ちていた。果肉からクルミが露出している。今が収穫時と判断。収穫といっても6粒のみだけど。クルミは
仲良く二粒ずつ寄り添うように成っている。上の写真(中央)は果肉を半分取り除いたところ。胡桃の殻を一粒一粒取り出すのは
大変だ。この後、割る工程があるし……。食べるのは簡単だが……恵みには感謝しよう。
(Sep.25)
■二十四節気 <秋分> 七十二候 (四十六候、四十七候、四十八候)
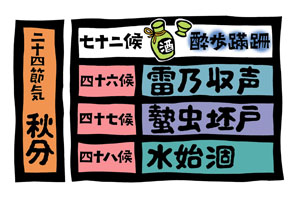 |
秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
HPの更新もままならず。慌しく活動の日々。落ち着いて制作なんて夢のまた夢。心やすまる時なし。情けない。
渋谷の仕事場→テニスコート(午前中二時間)→大学(レジュメ印刷)→自宅(今、HP更新)→鳩山アトリエへ。
創作に割り振る時間はまったくなし。嘆かわしい!明日は12時間はアトリエに籠り絵を描く決意。
創作といえば、紙皿で天使を作った。ペーパープレートクラフト、。そのゲージも学生の数分だけ用意(レジュメは豪華カラー版)したから
時間が足りなくなるわけだ。真っ白い紙皿の天使はシンプルで清らかだ。学生はきっと喜んで制作すると思う。手を使う。作って作って……
学生は体験を通じて何かを学ぶだろう。
■二十四節気 <白露> 七十二候 (四十三候、四十四候、四十五候)
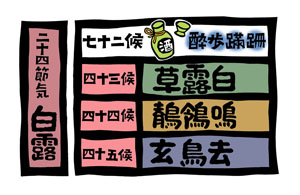 |
9月8日は白露 9月23日は秋分 ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (9月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
第三回『子ども教育学会』出席後、鳩山へ。板絵制作に集中する。このところ頻繁にアトリエを訪れるが、
それでも進行遅く焦る。眠る時間以外は彫っている。なんとか地塗りまで済ませた。この後も、塗っては彫る作業が続く。
板絵のしんどさは、終わりの時間が分からないところだ。今やっと”キャンバス”状態。やっと”描き”に入れる。”やっと……”の
ところまで漕ぎ付けたのに、アトリエを出なくてはならない。大学の仕事が待っている。
秋学期まで一週間。すべての時間をその準備のために使うが、それでも寸暇(あるだろうか)を見つけてアトリエに
向かうかもしれない。頭の中に作品の”骨格”がデーンと存在し、板絵作業の続行を促している。
栗の実が落ち始めた。古い木は元気ないが(2本は切り倒した)10年ほど前植えた3本は今年も”豊作”だ。 残念だが、
栗拾い(実際には口を開けたイガを叩き落す)する暇さえない。少しだけでも拾おうか……。
クルミは繁る葉の間から2個見えていたが、かき分けてみると5個!暗緑色の7~8センチ大の堅いボールが枝に
突き刺さるように付いている。昨年は収穫する前に落果したのか、動物に食べられたのか姿が消えてしまった。
この次鳩山へ来たときに実をもごう。クルミはいつ収穫してよいのかタイミングが分からない。表面の緑が段々黒ずんでいくが、熟れる
果実と違い大きな変化が無いから。いつもは袋で買うクルミ(カリフォルニア ウオルナッツ)だが、木に実るその姿は愛おしい。
割って「ウイスキーの友」に……、ゆとりのない日々の生活、夢想がしばしの慰めだ。
■《防災の日》はスズメバチ退治!





アトリエのシンボルツリー、チャンチンの老木(香椿)が枯れた。朽ち果てる寸前の幹にスズメバチが巣を作った。アカゲラが開けた穴が
日ごとに大きくなっていく。獰猛なスズメバチと、すぐ分かったがタカをくくっていた。いや、恐くて近づけなかったのだ。数百匹と群がる
スズメバチの大群、見るに見かねて役場に駆除を頼んだ。
消防署の車に、救急車。総勢8名。防護服に着替えた隊員2名。3名はバドミントン(?)のラケットを持って構える。ハシゴを架け
ほこらに薬品をぶち込む。窒息死させるのだという。そのあとバールで穴を大きくし巣を破壊、取り出した。何と6層も!
作業員は「これは大きいほうだ。巣に戻ってくるハチがいるから、暫くは近づかないように」。救護員は「今までに刺されたことは
ありますか?二度目なら死に至ります(ショック死)」と言い残し、引き揚げていった。スズメバチは恐い。
刺されて命を落としたというニュースも耳にする。 ふー、これで一安心だ。役場の方々、消防隊員に感謝感謝。
アトリエに入っても気になって仕方ない。デッキに出て、壊した巣の後を双眼鏡で見る。隊員が言った通りだ。スズメバチがまた群がって
きている。巣がなくなったことを諦めきれないのか、穴から出たり入ったり慌しい。大丈夫だろうか?又巣を作らなければ良いが。
板絵制作に入ったのは夕方。有線放送の『元気に遊んでいる良い子の皆さん、暗くならないうちに帰りましょう』が聞こえてきた。
「カラスウリの花が開くのを見たいなあ……」、「ビール&読書もいいなあ……」 ダメダメ!仕事仕事!、集中せねば……誘惑に蓋を
して……このところの低下した気力にカツを入れるべく水風呂、ねじり鉢巻! さあ、やるぞー!!!!
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■《愛媛の酒を楽しむ会》
京王プラザホテルで開催された蔵元18社出展の《愛媛の酒を楽しむ会》。畏友の杜氏、宇都宮君もブースを構えると言うので
出かけた。「千鳥」とならんで「月の滴」も展示されていた。「月の滴」はぼくの板絵(同名のタイトル)をラベルに用いた大吟醸酒だ。
会場はほぼ満員の盛況。利き酒しながら酒造主や日本酒党との歓談を楽しんだ。案内状通りの”ビュッフェディナー”だったが、
ぼくはテーブルから動かず、じゃこ天をかじったのみ。客の応対に忙しい宇都宮君とは一言二言話したのみ。握手して会場を後にした。
9月には大学。秋学期が始まる。その準備。板絵制作もある。造形遊び本の原稿も。明日は鳩山だ。アトリエの掃除も終わらせなくては
ならない。暑さで気力が萎えている。巻き返さねば!
■二十四節気 <処暑> 七十二候 (四十候、四十一候、四十二候)
 |
8月23日は処暑 (9月8日白露) ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
暦の上では処暑なれども、炎暑衰える気配なし。鳩山も暑い。板絵制作準備に訪れたが、暑さで退散する羽目に。
それでも掃除ぐらいはと収納庫をあけて溜息!思っていた以上にパネルがカビだらけ。パネルのみならずシナベニア板
すべてに白や黒のかび。炎天に日干しをする。幾度もパネルやベニア板を運ぶ。布で拭き落としながらの作業に体中の水分が
なくなるほどの
汗を流した。
胸が苦しい。深呼吸すると胸の上が板で覆われているような感じだ。カビを相当吸い込んだのだろう。なぜマスクを着け
なかった……、後悔しても後の祭り。いつもカビには悩まされているが、今回は大事だった。肺の中にカビ菌が育っている
のでは……ああ、胸が気持ち悪い!水道にホースを繋いで肺を隅々まで洗いたいなあ。

パネルを道路にならべて、”熱消毒”。枚数100枚ほどか、裏返してカビを殺す。湿気対策の名案なく、毎年板の天日干しに
時間を取られている。進歩なし!創作欲が削がれるし時間の無駄だ。東京への帰路も、今日一日の働きの虚しさが頭にあり
情けない思いでハンドルを握っていた。
我がアトリエが建つのは坂の下、更に半地下状態で湿気るのは仕方ないことだが、我慢我慢!贅沢を言うのはよそう。
”静かな小鳥の楽園”だ。「小鳥の帰る島」ではないか。
「小鳥の帰る島」は三十数年前現代童画展に出品した作品名
■交通渋滞覚悟で鳩山へ。

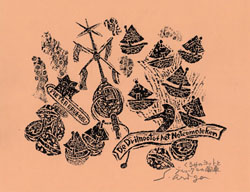
・「胡桃のヨットとブリューゲルの風車」 版画
講演会では板絵作品も何点か提示する。『胡桃のヨットとブリューゲルの風車』もその一つ。
ネーテルラントの画家ブリューゲルは1560年、《子どもの遊技》に91種類もの子どもの遊びを描いた。ブランコや、水鉄砲、竹馬など
分かりやすい遊びから、樽揺らし(シーソー)、煉瓦積み遊び、指骨あそび、目隠し鬼のスリッパ取り、洗礼ごっこ、お粥のかき混ぜっ
ごっこなど、フランドル地方の風俗、習慣色鮮明なもまで。
その中につくる遊びはただ一つ。「胡桃の風車」だけ。ぼくは絵を見て実際に作ってみた。それを板絵に描いたのが『胡桃のヨットと
ブリューゲルの風車』だ。10号Sサイズの小さなものだが、横浜の講演会で、胡桃の玩具ともども見せたいと思う。
炎天下、テニス3ゲームの疲れた体で、交通渋滞を恐れての運転、炎暑!気温が高いというより、この蒸し暑さ!鳩山のアトリエに
着いても、頭がボーとして他の仕事できず。ただ作品を積み込み帰途へ。
楽しみと言えば、庭で工事中の「井戸」の進行状況を確かめられたこと。誰も引き取り手が無いような巨大な砂岩の円柱形井戸枠を
破格の安値で購入。それを据え付ける土台工事を頼んであったのだ。井戸枠を何に使うか?地面を深く掘ろうとも、井戸が湧く保障もなし、
水をくみ上げる装置もないし。手押しポンプ設置も考えたが、これは井戸からの配管が必要で、大工事になる。そこで考えた。
名案浮かべり!!!!!この井戸枠の使途は?工事屋さんもぼくの描いた設計図を見て首をかしげた。構造を口で説明し、
わかってもらう。設置場所は庭の斜面だから、構造を描いた図面が理解できなかったのだろう。
< “名案”は工事終了後、この欄で答えを“白状” > ヒント………枯れ葉を入れる=○○○作り
工事は7割がた出来ていた。構造体はほぼ完成。煉瓦も積まれ後は配管と、井戸枠の運び込みだ。
あちこちに蝉のぬけがら。ミンミンゼミの鳴き声が蜩に変わった。アトリエのシンボルツリー《チャンチン》が、枯れた。アカゲラだろうか、
突いた穴が二つ寂しそう。主は見えず、チャンチンは今、アシナガバチの城となっている。ヤマカガシも手入れの無い庭で我がもの顔だ。
仕方ないことだが……。
(Aug.15)
■板絵運搬、準備を考慮しホテルの予約を入れる
18日の講演会会場はは横浜のホテル。当日車で行くつもりだったが、板絵、絵本、レジュメ(かなりの重量)の運び込みなどを
考え、前日宿泊することにした。『表現する喜び』と題し2時間の講演。一部<板絵の仕事>二部<絵本・雑誌の仕事>。いま資料
整理に忙しい。秋の現代童画展出品作(上野の森美術館)にも取り掛からねばならない。その前に、造形遊びの
指導本の原稿も。明日は大学へ。
風邪は何とか治まりそうだ。さあ、またフルスロットルで走らねば……。暑さにめげてはいられない!
(Aug.11)
■夏風邪!熱がある。仕事、スローペースにダウン!
疲れが溜まっていたのだろう、風を引く。頭痛が続き仕事ストップ!それでも、講演会の準備はしなくてはならない。
パワーポイントに板絵作品や絵本を取り込む作業。レジュメが先だが、今、考える力は無い。
講演会には板絵も持参して行こうと思う。その作品の決定は迷ったが、『いこい』『たたかい』(F50 1981)とする。
20年も前の作品だ。100人レベルの会場での可視性を考えると、”大柄”が良いだろうと。近作の小品も2~3点加える予定。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
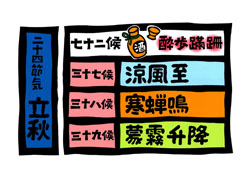 |
立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■鳩山アトリエは伸び放題の木々に隠れる
雑草生え放題、手入れする暇なく荒れ果てた鳩山のアトリエの庭。庭と言うより原野かジャングルか。それでも、植えまくった
果樹、花木が育っている。”植えまくった”というのは、畑にない樹木の苗木を見つけると、手当たり次第手に入れ植えていった
ということ。柿、リンゴ、スモモ、キウイなど果樹のみならず、ユズリハ、クロモジ、リンデン(西洋菩提樹)、イタリアンパイン、メープル、
それに後先考えずに(大木になったらどうしよう)ブナやトチに、ヒノキやケヤキまで植えた。紅葉が好きだからモミジもハゼも。
この間は大島桜も植えた。桜は昔からある山桜、それに、染井吉野が昨年から咲き出した。大島桜の”ねらい”は花より葉っぱだ。
この葉で桜餅をつくろうという算段。二本植えた大島桜(知人が種から育てたものを移植した)が楽しみだ。
ナツメ、サルナシ、山葡萄は放っておいても育つが、心配はナナカマド。一本を枯らし、昨年植えた二本も危やしい。
ナナカマドの赤い実を小鳥にとの思いは今秋も叶いそうもない。
■夏風邪?鼻クシュンクシュン……
オープンキャンパスで張り切りすぎたのか(満員御礼、大盛況)、雨の中のテニス(サーブ打ち込み200球)が
ハードだったのか、はたまた熱中症か、鼻水が止まらない。夏は大好きで暑さにも強いぼくも、”35度”には閉口!
只今ギブアップ状態。それでも休めず動き回っております……。○○○○、暇なしか!
■クレヨンまるDVD <ハーブおばさんのスイカのパラソル>
『幼稚園』(小学館)9月号付録に「夏チャレンジDVD」がついている。アンパンマン、ドラえもん、お話、歌、水族館に行こう、
忍者修行など盛りだくさんの120分。その中に「クレヨンまる」も納められている。まだワルズーやミイラばあや、それにチェリーや
ふるもとくんなど友達が登場する前の、最初期の作品。「ハーブおばさんのスイカのパラソル」の再録。
ここ2~3年前から、幼児雑誌にDVD(その前はVHSビデオ)がつくことが多くなってきた。”お得感”はあるが、その分雑誌の
ページ数は減っている。本文が充実してこその雑誌だ。
毎号付く”本物付録”(表紙にもこの文言が載っている)も、手替え品替えのアイディア玩具ではあるが、創造性を育むような物は
少ない。雑誌の黄金期70~80年代の付録と比べると、見た目の豪華さとは裏腹に、<創意工夫>する心が育つとは思えないような
ものばかりだ。
キャラクターを付けた刺激的な玩具(多くはICやボタン電池を使っている)は子どもには魅力だろうが、その興味は長続きしない。
持っているだけのもの、あるいは遊び方を限定する玩具に想像性、創造性がないからだ。
■2010 オープンキャンパス・模擬授業・アリガクン参戦!
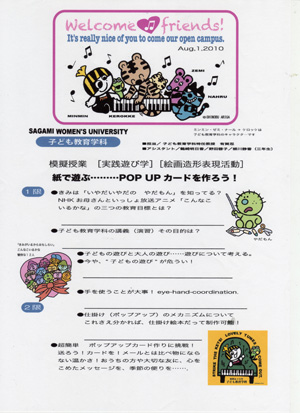
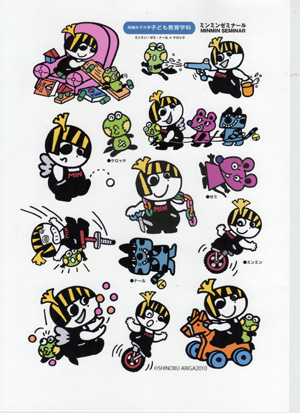
8月1日は相模女子大学のオープンキャンパス。真新しい建物、マーガレット本館5F2152教室でぼくは授業を行う。
昨年も一昨年も満員の盛況ぶり。補助机を出して対応した。当節の風潮として保護者の方々もお見えになる。ご父兄をも
納得させる講義でなくてはならず、頭をいためるところだ。(本来は制作を通じて自己表現し、体感が人間の底力を培っていくものだが)
今回はアシスタントの三年生が5名参加の強力体制だ。高校生諸君に「作る喜び、表現の素晴らしさ」を教えたい。
| 7月のアトリエだより |
■夏の法要は大変だ!寺は、今話題の植物園の傍らにあり
連日35度以上の「猛暑日」。先日は文京区にある寺で法要がありでかけた。本堂での僧侶の読経の後、炎熱の墓へ。
参会者はみな汗を滴らせている。お坊さんも配慮して短めの念仏。くらくらして倒れそうな暑さ、代わる代わる墓に水を
かけたが、かけた途端から乾いていく。
墓石には、○○家ではなく、倶会(旧字)一拠(旧字)と彫られていた。
寺から程近くに東京大学附属小石川植物園がある。いま、世界最大の花ショクダイオオコンニャクが開花し、大賑わいとの
報道。一万人以上が訪れ入園券の販売をストップしたとも。目と鼻の距離まで来ており、見ていこうか迷ったが、この暑さに
退散。 それにしても集まった10000人……。話題性……、本当に前々からこの植物に興味を持っていた人はどれくらい
いたんだろう? いろいろ考えてしまう。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
暑中お見舞い申し上げます。 23日は大暑! ”文字通り”を越していますよね。でも、
暦では大暑の次は立秋…………、”りっしゅう”の語感はいいねえ。暑さに負けませぬように、ご自愛専一に。
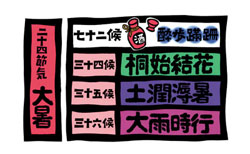 |
7月23日は大暑 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
猛暑日!夏が好き、熱さには強かったぼくも流石に閉口!先週まで頑張っていた”金曜テニス”も断念する。行かれないことも
ないが、コートに誰も集まらないだろうし。明日は法事がある、黒服の準備をする。汗だくだ。
HPの更新もできぬまま、8月1日のオープンキャンパスの用意、18日の講演会の準備に明け暮れている。講演会は長時間だから、
パワーポイントも活用する。そのためのデータ取り込みに大わらわ。
演題は『表現する喜び』一部は<板絵・版画……三つ子の魂、何とやら>で「幼少期の先生との出会い、環境、素材について」から現在に至る
表現人生を話す。 二部は<絵本の現場から>と題して、まず 「こんなこいるかな」誕生エピソードを。NHK2歳児テレビ番組研究会の教育目標などを紹介しつつ話す。これはぼくの基本的考え方、すなわち「色んな個性、それぞれを認め、一人ひとりを伸ばす」と、思いは一緒だから。
研修会は全国から集まる図工美術専門の先生方だから、絵本の様々な作法、制作技法も。更には小学校の先生方が受け持たれる子どもが、どのような環境に置かれて育ったのか、「月刊幼児雑誌の変遷」から見る試みも。30年間の幼児雑誌の本文はもちろん、殊に付録に着目。付録は
おもちゃだから、子どもに一番身近なもの。その変わり様から様々なことが見えてくる。大量の雑誌や付録の実物を提示しながら”驚くべき実体”を
知ってもらおうと。
大学の授業も大詰め。セメスター制は???だ。半年15回の講義(演習)では物足りない。いきおい詰め込むことになるが、学生が深く考え、自主的に制作するまでには至らない。学生は頑張ってついては来ているが、「これでもか、これでもか」と言うくらいやらねば力にならないと考えるぼくには
不満が募るばかりだ。”思いっきり””徹底的”にやりたいなあ……、学生には学ぶ時間が足りなすぎる。嗚呼。
■おでかけクイズ絵本『グー・チョキ・パーのいじわる魔女を追いかけろ』表紙初校あがる
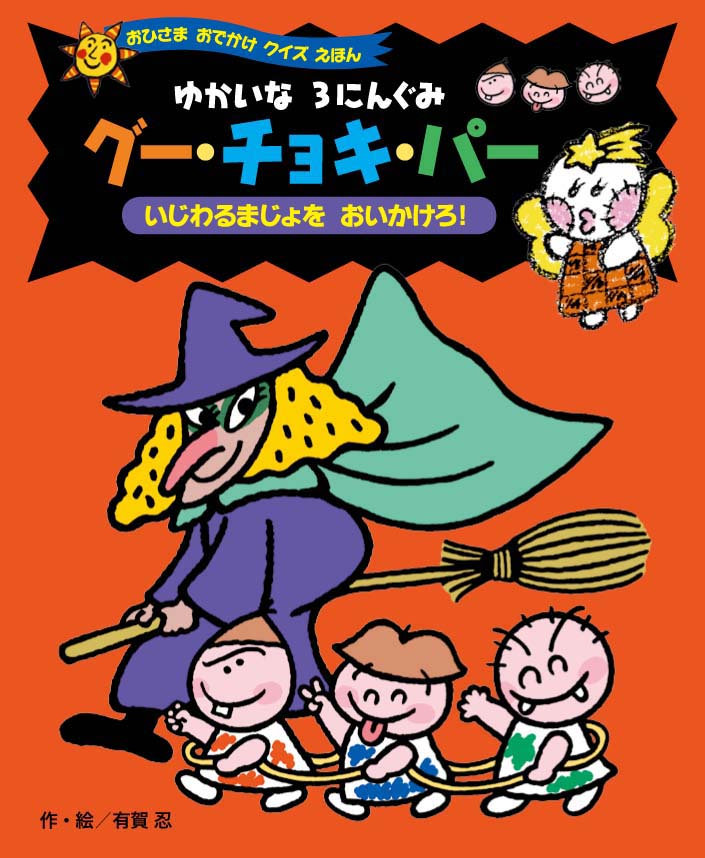
『グー・チョキ・パー』はお話とクイズ満載の絵本。<おまけクイズ>のボリュームもたっぷり。子どもを
長い時間楽しませたい。何度も絵本をめくって、隠されているものを探す楽しみも。
グー・チョキ・パーは腕白三人組。描いた絵から可愛らしい女の子が飛び出してくる。名前は『おやつちゃん』。
いじわる魔女『ズルーイ』との知恵比べ!乞うご期待!
(Jul.15)
■二十四節気 <小暑> 七十二候 (三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 は小暑 (7月23日は大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
現代童画選抜展終わる。今年は会場に行かれず仕舞い。出品作『どんぐり嵐』はこの後、坂出市民美術館展、神戸展で
展観される。お近くの方はご高覧を。
(Jul,5)
| 6月のアトリエだより |
■現代童画会選抜展が開催されます
「現童選抜展2010」開催。6月28日(月)~7月4日(日)
銀座アートホール
詳しくは展覧会のページをご覧下さい。
■古いスケッチブックが大量に出てきた 厚手の粗紙
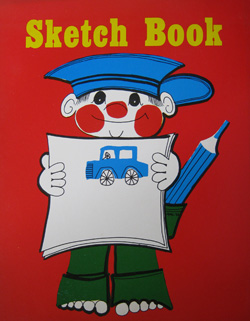
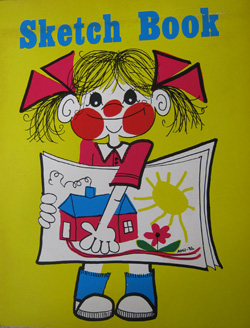
・粗紙32枚のスケッチブック。 27×34cm POLARPUBLISHING/FINLAND
絵本の原画やイラスト(教科書、雑誌、レコードジャケット、広告パンフ、百貨店ポスターなどに使用したもの)を捨てる。
ぎっしり詰まった紙袋を”仕分け”もせずに、幾つもゴミ置き場へ運んだ。見れば捨てるに忍びなくなるのが分かっているから。
版木の類もイラストを彫ったものから、版画作品まで山のよう。取っておきたい気も山々なれど、どこかで処分せねばと一大決意。
大量の和紙や紙類はカビや黄変したものを除き取っておく。中に写真のスケッチブックの束があった。数十冊、購入は
40年程前だろう。なぜ買ったのか?おそらくスケッチブックの粗い紙質が気に入ったのだと思う。ザラザラしていて厚さもある。
真っ白とはお世辞にも言えないが(藁半紙か馬糞紙の趣)、風合いが良い。一、二冊使った記憶もあるが、戸棚の奥に眠った
ままでいた。ツルツル、すべすべのコート紙や白い紙が当たり前の子ども達に、この”自然な紙の色”を見せてやりたい。
クレヨンの”塗り””滑り”が全く違う。”粗末な”ザラザラ画用紙の復活を望む。
何でも手に入る、恵まれすぎからは創造性は育たない。無いから工夫する、やっと手に入れたから大事にする……想像力と
創造力、この二つのソウゾウリョクは環境、人(導き)、そして素材(材料)で培われる。粗末なスケッチブックの山を見て
思った。物が無い時代に育ったぼくは幸せだったと。
(Jun.25)
■二十四節気 <夏至> 七十二候 (二十八候、二十九候、三十候)
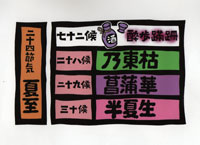 |
夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月21日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■いつも、アップアップ。切羽詰っての仕事……ゆとりがないなあ。
毎週木曜日は「自分の仕事日」としている。絵本制作、文書き、絵、研究といくつもメニューが多すぎて、大抵は
うまく行かない。時間を決めてやることを変えようとするのだが、仕事が不満足、区切りまで届かず延長となってしまう。
欲張り過ぎだが時間が足りないので仕方ない。睡眠時間も少なくてフラフラ状態……良いことではないなあ。
今日は絵本から入ろう。原稿書き(草稿)、それにやはり気になるレジュメ資料を作り直さねば。講演会の演目コンテンツも
考えたい。オープンキャンパスのメニューも、その他もろもろ、一つ一つ片付けてとは思うのだけれど、その一つが重たくて……。
昨日は小雨の中、キャンパスの植物の葉を採取した。キウイ、ドクダミ、ヤツデ……。「絵画造形表現」授業、スタンピングのためだ。
学生も色々な葉を持ち寄った。桜、銀杏、紫陽花、トマト、ヤマノイモ、柏、中に睡蓮なんてのもあった。残念ながら睡蓮は葉脈が浮き
出ておらず、スタンピングしてには向かないのであるが。
学生は自然物(葉など)と人工物(キャップ、容器)のスタンピングを楽しんだ。7色のインクをローラーに付け素材を写し取る作業に
夢中……、そしてその”転写コレクション”をコラージュする。自由に再構成する。完全自由を与えられた学生の表現は光った。いくつか
目を見張る出来栄えの物があった。
学生が制作自体を楽しんだ、その痕跡が作品なのだ。概念や意図しない無意識下のデザイン技法(AUTOMATIC……デカルコマニー、
フロッタージュ、ウオッシング、スパッタリングなど)を学んだ後の授業に、ぼくはスタンピングを選んだ。幼児造形教育の版画の元になる
スタンピングに、学生は時間を忘れて没頭した。その姿は無邪気に遊ぶ子どもと同じだ。幼児保育に携わらんとする者は子どもの心を
知らねばならない。作業に集中して子どもに還っている学生……、ぼくは学生が先生になって子どもに囲まれている情景を想像していた。
(Jun.24)
■リンデン(西洋菩提樹)の花にミツバチが……良い写真が撮れた



・リンデン(西洋菩提樹)の花の蜜を吸うミツバチ
「絵画造形表現活動」の今回のテーマはスタンピング。あらゆるものにローラーでインクを付け写し取ろうというもの。
自然物は葉っぱなど。学生は思い思いの葉っぱを集めてくることになっている。ぼくも葉脈のはっきりしたものを用意する。
桜、イチョウ、ヤツデなどはキャンパスにある。珍しいところで、杜仲茶、サンシュユ、ローズジェラニウム、ワイルドストロベリー、それに
きれいな形の”定番”モミジ。ハナミズキもアイビーも葉脈が美しく出る。全部で20種類くらい保冷材を敷いたバッグに詰めた。
リンデン(西洋菩提樹)の葉も珍しかろうと採取しようとして手を止めた。いまや激減、姿を消し問題となっているミツバチが、花の蜜を
吸っていたのだった。リンデンの花の蜜は最高と言われるが、一体このミツバチは何処に帰るのだろう?
アトリエを建てた頃は、ミツバチの大群の羽音うるさい群舞が見られたものだ。確かにここ、鳩山でもミツバチは減っている。
大急ぎでカメラを取りに。ピンとあわせに一苦労したものの何とか姿を納めた。
■クワノ実、グミ取り放題!ビワの実、甘露!



アトリエに籠りっぱなしは体に毒と、外に出る。荒れ放題の庭(庭と呼べないほど雑草が茂っている)、赤い実が目に入る。鈴なりの
グミ、ギッシリ密着する桑の実だ。どちらもいい具合に熟れて今食べごろ。口に含めば、かまずにとろける柔らかさだ。甘い。そう
たくさんは食べられないが、もいで食べるのは格別美味しく感じられる。びわの実も20粒ほどだが実を付けている。先週はまだ
固かったが、こちらも食べごろ。吐き出した種は辺りに埋めた。芽を出してくれるだろうか?忘れた頃、「あっ、あのときのだ!」
幼木を見つけられたら嬉しいだろうなあ。
■2010現代童画会選抜展搬入日迫る (展覧会詳細は別項)
毎年この時季恒例の「現童選抜展」も間近。銀座アートホール展示のあとは四国坂出、神戸と巡回する。作品の保護箱を
製作したが、利用していたホームセンターが閉鎖し材料の手当てが容易ではない。時間もなく、ありあわせの板で間に合わせた。
肝心の作品、タイトルは『どんぐり嵐』。毎年車の屋根に振り落ちるマテバシイのドングリが意識のベースにあった。それと、
旧作『どんぐり広場』だ。いま、種から芽を出したクヌギが育っている。”どんぐりの木”は種類が多いが、風に飛ばされてくるのか、
自然に生えてくるから嬉しくなる。ドングリノ木だけではない。サンショウ、ナツメ、スイカズラ、アケビ、モミジ……邪魔者扱いの杉も
あちこち芽を出して困る。さてさて『どんぐり嵐』の出来栄えは如何に……。
(Jun,22)
■「幼稚園実習」学生への試練……。耐えて超えてほしい。
昼休みのオフィスアワー(学生が質問等に自由に研究室を訪れる)に幼稚園で実地研修中の
学生が駆け込んで来た。園の先生から「責任実習」の制作物について厳しい指摘があったという。
廃材を用いての幼児の工作遊びで、学生は条件の一つ、「季節感を出す」から、カエルをテーマ
に選び、工作二種を用意した。新聞紙をまるめ先っぽにカエルを止らせゴムで“発射“するおも
ちゃ、 もう一つは、ティッシュボックスの中にカエルを4匹入れたもの。 蓋をあけると勢い
良く飛び出すおもしろい工作だ。
それが、「年長にはもう少し凝ったものを」「壊れにくく、長く遊べるもの」「カエルは4匹
いらないのでは」など等、相当言われ落ち込んでしまった。
”4匹”が面白いのに。学生がかわいそうになった。一匹しか入らない箱をわざわざ作るより、
4匹入るに越したことはない。カエルは3匹でも2匹でも自由だ。スペースを一匹用に限定して
しまえば、その後の遊びが広がらない。ぼくには何だか先生のアドバイスが”言いたい放題“に
思えてならなかった。
制作物をみてぼくは首を傾げた。いずれも問題はないと思えたから。「色んな見方があるんだね
この工作、子どもたちきっと喜ぶよ。頑張って!」ぼくも二点制作したものを見せたが、学生ので
十分行ける!「もっと自信を持っていいよ。」……励まして帰した。
聞けば、その園はセロハンテープ、ガムテープ類は一切使わせないという。段ボールを使う大形
おもちゃを作るときやペットボトルを束ねるとき等クラフトテープやビニールテーが重宝するのに、
すべて禁止とはなあ。先入観だ。そのくせ園児には英語を学ばせているという。何か偏ってる。ホチ
キスだって何だって危険視して使わせないのでは創造性は育たない。環境、素材(材料)それに、
やはり指導員だなあ。
子どもの感受性の萌芽期の立会人、極めて重責だ。
(Jun.14)
■実践遊び学……「連続模様切り紙あそび」
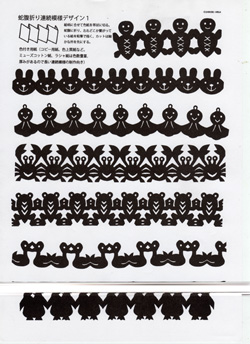
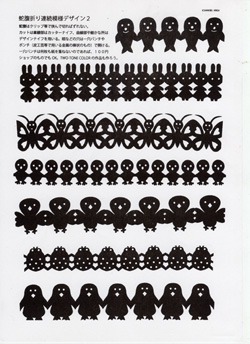
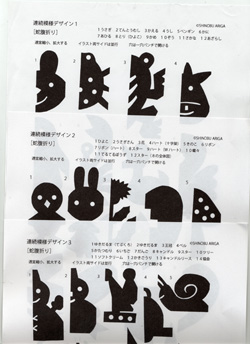
先週は江戸時代、寺子屋で盛んだった「紋型切り紙」を演習。昭和20年頃までは図工の教科にあった。3回折り、
4回折りを数多く制作。今回は「蛇腹折りの連続模様」。学生は思い思いのモチーフで数点の作品を仕上げた。
写真2枚
はそのレジュメ。右はデザイン参考資料1~3。このあと学生は”完全創作”に挑戦する。宿題にしたから、次週が
楽しみだ。自主性を喚起したい、いや何より制作”量”を求めたい。今は”質”ではなく、量だ。飽きるほど制作して初めて
身につくのだから。
毎回レジュメはこの調子だから、時間がかかる。今回は作りためた連続模様(すべて大型サイズで制作済み)その数40点。学生はこの40個を馬鹿馬鹿しいと思うのでなく、「だったら1個くらい作るぞー!」と発奮してほしいのだ。
(Jun.7)
■鳩山のアトリエ……目を休めに庭に出る。鬱蒼とした茂みに実りを見つけ嬉しくなる




週末は鳩山の生活が続く。現代童画展選抜展出品作の制作に入った。「アトリエだより」更新も儘ならぬ状態だ。
板を彫る手を休めて庭に出れば、嬉しい発見が!伸び放題のびた木々が実を付けていた。ビワはもうすぐ食べられそう。
サルナシはまだまだ小さいが、今年もどっさり実ったので楽しみ。グミは大粒が取りきれないほどだ。桑の実は口に含めば酸っぱく、甘くなるまで待とう。気にしていたオニグルミは(昨年はたった一粒しか生らず、それも収穫前に落ちてしまった)十個ほど実を付けた。クルミは信州で育った子ども時代の思い出があるので、何としても育てたかった。根元を虫にやられ穴が
開いてしまい心配していた。薬を塗布しロール布で養生する。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候)
 |
6月6日は芒種 (6月21日は夏至) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
2限3限授業の間に昼食をとるのだが、片付けがあったり、学生の質問などに時間を要し満足に食べられたためしがない。
10分くらいで立ち食い……出来ればいいほうだ。今日は昼飯を食べに研究室に入ったのが12時35分。そこへプロジェクト活動研究の
指導を求めて学生三名がやってきた。プロジェクト活動研究は学生が(教室外で)自主的に表現する科目だ。仕掛け絵本を作って、
幼稚園児の前で演じたいという。残念なことに、この学生達はぼくの「絵画造形表現Ⅱ応用」を受講していない。講座のコンテンツには
仕掛けを使っての「グリーティングカード制作」もある。ポップアップを中心に数種類の仕掛けを研究制作する。勿論カードのみならず絵本にも
応用可能だ。学生に授業で使った「仕掛けのゲージ」を貸し、コンセプトの再確認(仕掛けのおもしろさが狙い?しっかりした絵本?子どもたち
への読み聞かせが主?……いずれも大変なこと、中途半端にならぬように)をしてくるように言った。三人は仕掛けの習作を見せた。
すべては”ヤル気”だ。熱いエールをおくった。
先週は「なぜ絵が嫌いになったのか?いつごろから図工をしなくなったのか」アンケート調査をするという学生が訪ねてきた。文献を貸せと
いう。問題に即答といったものが簡単に手に入るわけが無い。子どもの絵、評価、造形表現等の資料として数冊渡したが、いずれもヒントには
なっても直接回答を求める者には不満だろう。考え迷い悩む……、研究する姿勢を見たい。
仕掛け絵本制作にせよ、アンケート調査にせよ、自主的活動の”芽生え”は素晴らしいこと。嬉しい。昼飯にありつけない日が続きそうだ。
(May.24)
■久しぶりの鳩山。雑草に庵埋もれそう。チェーンソーで木を切る。ブンブンゴマを作る。
多くの田圃で田植えが終わっていた。それも昨日か一昨日か、苗が植えられたばかりであることが直ぐ分かった。
鳩山には板絵制作用の木製パネルの在庫を見に来たのだが、アトリエに近づけないほどはびこる木の枝落としや雑草取りに
日がな格闘、板絵どころではなかった。
演習科目「コマの回転円盤デザイン制作」の前に見せる”伝承玩具”「ブンブンごま」を数個作った。ブンブンごまは回転するとタコ糸が指に食い込み引きちぎれるくらい引っ張られる。ブオーン ブオーンの音もダイナミックだ。ボール紙、ボタン、木片……何でも使える。昔は牛乳瓶のキャップで作ったものだ。路傍でメンコや釘刺しをして遊んだ少年時代、ぼくは毎日
何かを作っていた。このブンブンごまもその一つ。現代の子どもに糸巻きタンクなどと一緒に伝えたい遊びである。
(May.23)
■ウタリ神社の経木の風車を修理する

今年度の実践遊び学では4枚羽根に加えて8枚羽根の風車を制作した。紙製の風車以外にポリエステルベース
のものも学生に見せた。要は応用力だ。授業の始めには郷土玩具の「経木製の風車」も紹介したが、”経木”を
知る学生は皆無。「昔は肉屋でも魚屋でも包むのに使ったんだ。ほら、八百屋や魚屋の店先にあるだろう。あの墨で
値段を書いてある薄いやつだよ」……、そんなこと、いくら言っても無駄。隔世の感あり。
(May.22)
■子どもの造形遊びに「タイヤチューブプリント」を!
材料はたっぷり与えよう!「あれはいけない、これはやめよう」一切なしで、自由な「ペッタン遊び」を!


幼児や子どもの絵画造形は創造性を育む遊びだ。自由な造形をさせるには好奇心の喚起、環境、材料が必要。
環境は(お片付けのルールを教えるのは別)整理整頓された”キレイな場所”ではなく倉庫のような、思う存分”汚せる”空間がのぞましい。材料も高価な物や手に入れにくいものをちびちび”大切に使う”のではなく、身の周りに当たり前にある廃品利用、それも大量に与えることが肝要だ。壊したり、組み合わせたり、素材を本来の用途以外に応用する。正に想像力は創造力を育てることになる。
自転車のタイヤは廃棄物だ。入手簡単、大量に準備できる。絵画造形の素材にうってつけ、利用しない手はない。ゴムのチューブを木片に両面テープで貼り付けるだけで版材ができる。チューブ版画が幼児にも向くのは、彫刻等を使わないこと。
はさみ(カッターナイフの指導も)で簡単にカットできる。木版画、芋版画など、多くの版画は彫りミスしないよう神経を使うが、
チューブプリントは、粘着シートにチューブ片を貼り加えていくのだから、その心配はない。最も簡単な版画表現の一つと言える。
学生には、演習の前に版画の種別(凸,凹、平、併用版、モノプリント)の説明と、遊びの魅力を話した。が、何より大事なのは、造形教育に当たる者の”姿勢だ”。自らが楽しむ、目一杯遊ぶ、作る喜びを感じる……これらがなければ子どもの心は
捉えられない。「先生が、あんなに夢中になってる。おもしろそう!」教える側は”教える”のではなく、演じるのでもなく、楽しさを伝えられたら良いと思う。
(May.21)
■おでかけ絵本 愉快な三人組み『グー・チョキ・パー』制作順調
今月号で予告した、「ワン・パー・クー」は、ゆかいな三にんぐみ「グー・チョキ・パー」と名を変えた。クイズ、パズルを
どっさり盛り込む構成を楽しみながらやっている。<たぬき>クイズ……は、”た”抜きクイズ……”タ”の文字を消していくと
お菓子の名前が次々でてくる……、これは残念ながらカット!チョコレート、ドーナツ、ポテトチップス、キャンディー、
ビスケット、キャラメルなどカタカナが多く、編集部より幼児向きではないとの指摘。”狸クイズ?”の、ボケも入っているし
楽しめるのになあ。これに代わる面白い食べ物クイズを今考えている。もちろん絵本だから視覚的遊びの要素が大事……。
(May.16)
■クレヨンまる最終回!!掲載誌『おひさま』発売!!
■クイズ、パズル満載絵本の構想を練る
ゆかいな三にんぐみ グー・チョキ・パー
いじわる魔女を追いかけろ!
「おでかけクイズ絵本」のアイディアをまとめ,ダミーを制作する。意地悪魔女ズルーイが出す難問に、
腕白三人組グー・チョキ・パーが答えていく展開。描いた絵から飛び出てきたゲストキャラクターの
“おやつちゃん”が、それに絡む。
ことば遊び、迷路、シルエットクイズ、塗り分けパズル、形態パズル、絵探し、数遊び、本物探し、記憶クイズなど
満載予定だが、選択に頭を悩ましている。ボリュームたっぷりだが、読み終えても再びページをめくってクイズに
再度挑戦したくなる「おまけクイズ」付きだ。今は絵を描くというより、ゲーム的展開に頭を使っている。
スムーズな流れであるか?クイズは幼児に難しすぎないか?おやつちゃんの奪われたバッグの中身の秘密で、
ラストまで引っ張れるか?………キャラクターも(描いて描いて描いて)育てなければならないし、
ああ時間が足りない!今日は母の日。記憶の底から浮かび上がる母の微笑み……「ばかったいのを作りな!」
(“ばかったい”は母の口癖だった。非日常のおもしろさ、意外性、頓珍漢などを含めた、独特のニューアンス。
否定ではなくむしろ褒めことば)形式、常識、秩序、概念からフリーになるのがアーティスト!
母は厳しく、優しかった。
(May.9)
■移植したフキが根付き育った


テーブルソーやボール盤、ジクソーなどを備える作業小屋を建てた。用地はフキ畑。フキの根を少しだけ移植した。
芽は出したけれど、摘み取るには忍びず、蕗の薹はおあずけだった。来春が楽しみだ。その前にキャラブキという”手”もあった。
どうにも酒肴が頭から消えない。飲兵衛は春夏秋冬、恵みに感謝!
(May.5)
■おでかけ クイズ 絵本のタイトル決定!愉快な三人組『グー・チョキ・パー』のいじわる魔女を追いかけろ!
<おやつちゃん>て、何者?
キャラクター三人の名前、<ワン・パー・クー>、<ジャン・ケン・ポン>、<イチ・ニ・サン>、<ピー・カー・ブー>などの候補の中から、
<グー・チョキ・パー>に決めた。いたずらっ子が描いた絵から<おやつちゃん>も登場する。敵役のいじわる魔女、その名も<ズルーイ>。
いじわるクイズを連発する。<ズルーイ>は<おやつちゃん>のポシェットを奪って逃げる。<グー・チョキ・パー>は<ズルーイ>のだす
クイズを解きながら追いかけて行く。無事ポシェットは取り返せるか……?ポシェットの中味は……?
何度でも遊べるような仕掛けも。巻末には「おまけクイズ」を用意する。このノウハウは『こんなこいるかな』(知恵遊び絵本版4冊)で
用いたもの。楽しめる絵本にしたい。
(May.4)
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
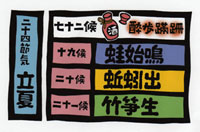 |
5月5日は立夏 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
久々のテニス。準備体操ももどかしくラリー。結果散散!右ふくらはぎの肉離れ。以前やったところだ。運動不足の鈍った体に
急激な刺激、”故障”は目に見えているのに。おお馬鹿者だ。足を引きずって歩く羽目に。
よって、また机に向かう生活と相成った。渋谷の仕事場からは中学校の校庭が見える。少年野球の練習試合が白熱を帯びている。
飛び交う声で分かる。皆、戦いに夢中だ。シップ薬を貼り、ぼくも絵本作りに精をだす。
(May.4)
■ペッタン、コロコロスタンプ 廃物利用による,幼児のための造形表現ツール




 テニスボールやボール缶の蓋を
テニスボールやボール缶の蓋を ペッタンコロコロスタンプは造形表現遊びの一つ。幼児は出現する轍の跡に目を輝かせる。型押し遊びの専用スポンジも市販されて
いるが、身の回りの物を活用することが、”応用する心”を育てる。手づくりした物は市販教材の完成品に、想像=創造……に至らせる
点で優る。材料は不要になったテニスボール(ゴミ処理に頭を悩ますクラブからは、いくらでも貰えるだろう)、クリーニングハンガー、
ペットボトルのキャップ。テニスボール缶キャップ(下段作品)いずれも廃物の再利用。
上段の針金ハンガーに通した二つのペットボトルキャップは頼りない装着に見えるだろうが、この”あそび”が大事。ボールをスムーズに
回転させるために必要なのだ。写真のほかにも数点試作した。転がした”おもしろ軌跡”は?また後日……
(May.2)
■鳩山は芽吹き……緑噴く。山笑う。春爛漫!



・五つ葉アケビ 雌花雄花 ・月桂樹の花 ・ダイコンの花群生
3本ある姫リンゴの木がいずれも白花満開。剪定を怠り屋根に届く高さに伸びた月桂樹も白黄、薄茶の細かな花を
ギッシリつけている。五つ葉アケビは至る所に育ち、赤薄紫の花を揺らせている。雌花、雄花が寄り沿うようで可憐だ。
今年色味がやや薄い紫モクレンははや散り始めている。ハナミズキが満開だ。手をかけて上げられないから、どれも伸び放題。
この間まで枯れ木同然だったブナが若緑の葉で覆われている。一番気にしていたメープルや(病気の)オニグルミも若葉を茂らせている。
一安心だ。白色、黄色、桃色……とりどりの色が咲き競うように乱舞。中で目に飛び込むのはダイコンの花の紫。何年か前までは
菜の花だった。隣地といっても境界もわからないような荒れ野原だが、今はダイコンの花で埋まっている。離れて見れば緑のなかの
紫模様のカーペット。
風もない穏やかな日和。日がな眺めていたいがそうもいかない。仕事に来たのだった。冷え冷えしているアトリエに入る。
目が慣れるまで闇だ。幼児造形教育のための教具教材作り……これはこれで楽しい。小鳥のさえずりを聞きながらアイディアを
考える。小さかったころから今に至るまで、ぼくは工作少年だ。
(May.1)
| 4月のアトリエだより |
■大学の研究室で仕事に没頭。先生の在室ランプも点灯まばら、訪れる者なし。静寂……わが天国!
先日学生がゴールデンウイークの過ごし方を聞いた。「どちらに行かれるのですか?」「仕事だよ。」
「えー、うっそー!」と言う具合。休日明けの授業のレジュメを準備し、さて我が仕事に取りかかる。
やっと取りかかれる。「おでかけクイズ絵本」の制作に入った。暖めていたアイディアをサムネールにおこし、
ネームを書き込んでいく。ダミーを作る。一冊36頁にストーリーを組み様々なクイズをちりばめる作業クイズや
パズルの考案、レイアウトなど楽しくもかなりハードな仕事ではある。
何より話が面白くなくてはならない。クイズやパズルを満載といっても、話の流れに不自然さがあってはならない。
頭を悩ませ、ため息をついては、それを打ち消すように、“面白く、楽しく”を念頭に……。
ぼくの“ゴールデンウィーク”は仕事三昧週間となる。
(Apr.30)
■一分間は楽に回り続けるコマを制作


身の回りにある廃物品の利用。今回はCD。どこの家庭にも一枚や二枚はあるだろう不要になったCD(CD・R、DVD)を
使ってのコマ作り。材料はCD一枚とビー玉。ビー玉をCDに接着するだけの簡単さ!誰にも出来る!これが実に優れもの。
よく廻る。一分間は当たり前に廻り続ける。。色紙を貼り合わせたり、模様を描いた回転円盤をセットすれば更に楽しい。
学生は回転円盤のデザイン(同心円、渦巻き、放射、格子、ドット、イラスト…・等)を多種制作させるが、コマ本体は
市販の物を使う。ただ、いつものことであるが「応用力」は要求する。身近なものを使ってのコマ遊びを考えさせる。これが
大事。その一アイディアとして「CDゴマ」を紹介する予定。
(Apr.25)
■晴れた!久々、光が目映い。風が香しい……かざぐるま かざぐるま かざぐるま……
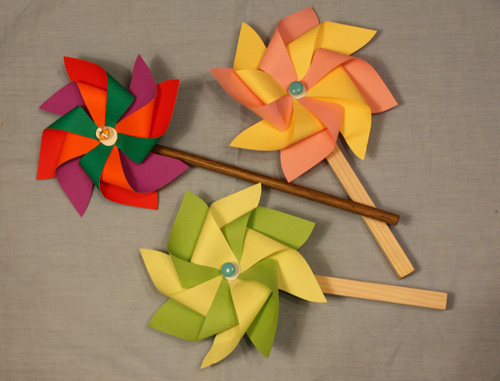


観測史上でも珍しい低温が続いたが、今日ようやく晴れ間が広がった。春風が気持ちよい。
風車をかざす。クルクル音もなく回る。幾つか並べて廻す。何てことないが、ホットする。知らず知らず幼き頃を想っている。
四枚羽根と8枚羽根を制作。8枚羽根(写真左)は、学生に型紙を提供するため、その準備も。風車をとめるピンやビーズや
丸棒も仕入れた。100人分、助手がいないのだから全部ぼく一人でやるしかない。準備がいつも大変だ。紙のカットや
組み立てはもちろん学生だが、配色やサイズなどでオリジナリティを演出してもらう。
{伝承工作}かざぐるまの次はでんでん太鼓だ。その準備もしなくてはならない。この一年、ほんの少し時間が空けば何か
作っていたが,でんでん太鼓も増えに増えた。その数数十個!ガムテープ、大小のセロハンテープの巻き芯、6Pチーズや
チョコレートのパッケージが溜ると気になり”でんでん太鼓化”したのだ。所狭しと吊るしてある。一つ一つみな音色が違う。
軽く重く小さく大きく、それぞれが愛らしい音を響かせる。「でんでん手遊び」は、仕事の合間の息抜きに一役買っている。
机の傍らにほんの小さなでんでんを一つ置かれたら如何だろう。ミニサイズは読書の妨げにもならない。耳を傾けたくなる
ような穏やかななんとも懐かしい音だから。
(Apr.24)
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
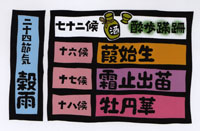 |
4月20日は穀雨 (5月5日は立夏) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
このところ震える寒さだ。校庭の桜はまだ散りきらない。駐車場の片隅、風に集められた
桜の花びらの山があちこちにできている。しゃがんで一掬い。ひんやり、しっとり……手に意外や、重みを感ずる。
ぼくは急に小人になる。花びらの褥に体を横たえ、埋もれるように花びらの間から空を見上げる。薄青の天、柔らかな日差し。
花びらの山を凝視している自分と中で休む自分。不思議な思いだ。日々の忙しさ、時に流されるわが身を
一瞬間蘇生させてくれた春よ、風よ,恵みをありがとう。
(Apr.20)
■子ども教育学会紀要扉絵

・胡桃のヨットとブリューゲルの風車
子ども教育学会の紀要が発刊された。創刊号の扉絵は『FATHER’S LETTER』
今回第二号は『胡桃の風車とブリューゲルの風車』。この愛らしいヨットも、風車も実際に
つくってみた。ヨットはアトリエに転がっている。風車は大事に飾ってある。父と子が物づくりを
通じて得るものは計り知れない。通い合う心……夢中になって遊ぶ……いつ何処で見ても
いい情景だ。幼き日の思いでは一生心で輝く宝。
(Apr.18)
■現代童画春季展出品作「harbor」


次回の発表は選抜展。乞うご期待。
(Apr.16)
■「こんなこ」工作。「二人は仲良し、いつも一緒」
『こんなこいるかな』コーナーに「★玩具を作ろう!⑦二人はなかよし いつもいっしょ」工作掲載。
次回は「スルスル シューTOY」を予定。 ★こんなこ いるかな のページへリンクできます
(Apr.11)
■現代童画春季展、(銀座アートホール)明日終了
明日11日、「現代童画春季展」最終日。一ヶ月の制作も、あっという間に展示期間が終わる。この次の展覧会は「選抜展」。
時間がなく制作も儘ならない状況だ。アイディアのラフスケッチだけでもと心がけてはいるが、思うようには行かない。
12日からは大学の授業が始まる「実践遊び学」「絵画造形表現活動Ⅰ基礎」。昨日は10時まで演習室、研究室でレジュメ制作。
一日の予定仕事分量の三分の一位しかできないもどかしさ。が、もう泣き言は言うまい!三年目、パワーアップして臨みたい。
(Apr,10)
■「ノビル畑」つくって、どうする!



春だ!でも鳩山の山桜の蕾は未だ固い。野原でノビルを見つけた。絡むように固まって生えるノビルを根こそぎ頂く。
幾塊ものノビルをアトリエ脇のヒイラギの根元に移した。ノビルには小さいころの思い出がある。引き上げ後、亡くなるまで
寝て過ごした父さんに、ノビルを摘むのがぼくの”仕事”だった。親父は医者から禁止されても酒をやめなかった。酒肴は
何でもよかったが、ノビルのヌタを好んだ。
「ノビルの畑」……記憶を蘇らせる場所を作った。
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
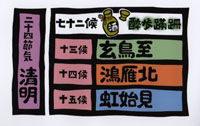 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
金曜日は週一テニスの日なのだが、生憎小雨、風も強く仕事日となった。天が仕事を命じたのだと観念し、新学期のレジュメを
考える。新たに「8枚羽根かざぐるま」「変色コマ」「切り絵連続模様」のレジュメを制作しなくてはならない。今日は風車だ。
紙皿、紙コップ、ペットボトルを使っての風車作りは制作見本を見せるに留め、今期は学生に基本形の4枚羽根の風車と、配色を
楽しめる8枚羽根の風車を作らせる。その試作を行った。型紙を起こし、形や色を変え5個作ってみた。さらに学生に貸す(時間
節約のため)型紙(ゲージ)をテーブル数×3=18組、一組2枚構成だから40枚近く白ボール紙から切り抜いた。デザインナイフを
握る右手親指は痛んだが、仕舞いには感覚がなくなり、指先が凹んだまま戻らなかった。そうまでしてと、いつも思うが、90分授業で
出来る限りたくさんの課題をやらせようとすると、ゲージを用意するしかないのだ。学生は簡単に「このゲージください」という。それでは
なんにもならない。同じものをたくさん作るとき、ゲージがあったら如何に便利かを分からせるためでもあり、幼児保育、子ども教育の
現場で、自ら”できる”力を養って欲しいから、「型紙は自分で作りなさい」と言う。かざぐるまのレジュメは型紙を入れて4枚になるが、
本日完成せず。ぼくは、”試作”を楽しみすぎるキライがあるようだ。
(Apr.2)
| 3月のアトリエだより |
■板絵 『 harbor 』描きあがる 日暮れまでナツメの木の移植に精を出す
28,29両日は寒の戻りか、冷たい北風が吹き荒れた。裸木立の枝が折れて飛ばされる強風だ。ぼくは鳩山のアトリエで
ストーブにしがみ付くようにして絵を仕上げていた。完成!いつもより少し色合いが生っぽいか。子どもへの”童画”然だ。
今回の作品は「harbor」=隠れ家で遊ぶ父子を、想いをこめて描いた。小学3年生のころ、ぼくは隠れ砦を作った。その記憶、
ワクワク感が筆を進めさせた。感動は創作の原動力だ。
額装が終わり、初めて外へ出た。まず深呼吸。そして日が暮れるまでの短い時間、何をしようか考える。やることは山のように
あるけれど、欲張ってもはじまらない。春、新芽が吹き出す前に済ませたいこと……、今は枯れ木にしか見えないナツメの木を移植
することに決めた。ナツメは実が落ち、あちらこちらで育っている。土が合っているのか、サンショウや迷惑なスギ同様増えて
困るほどだ。一年目ものは未だ良いが、3年、4年たった木は、棘はともかく根が張っていて掘りあげるのに一苦労。
10本掘れば、もうお手上げ。このまま大きくなれば、実を付けるけれど、通路を塞ぐ枝の棘が厄介だ。
掘り残した分はハサミでカット。かわいそう、もったいないけれど、鳩山にそうしょっちゅうは来られないから仕方ない。
ナツメの親木の勢いに負けて山葡萄が元気がない。去年も一昨年も実がならなかった。ナツメの移植より、こちらの方が
心配だ。酸っぱい山葡萄の実を煮詰めてシロップを作ったことがある。あの喜びをまた味わいたい。大匙数杯分しかできなかった
貴重なシロップを”大事に”口に含んだときの気持ち……嬉しさを再び。
(Mar.29)
■桜咲くキャンパスに人影まばら
子ども教育学科新入生に配る画材、用品の袋詰めをする。14アイテムを110セット。昨年は二人でおこなったが、
今年はもう一人助っ人を加えたから、まだ明るさが残る時間に終了した。
大学には「100年桜」の老大木があるが、校舎からはやや離れている。桜を見て帰りたかったが、今日は断念。
それでも幾本もの桜が咲き始めていた。3分咲きくらいか。美しい。ぼくは冷たい風に震えながら佇んでいた。
ふと足元を見れば、しぼんだ銀杏の実が幾つか。梢につかまっていたものが、ようやく落ちたのだろう。ぼくは
銀杏並木が好きで、秋の終わりにはキャンパスで銀杏を拾う。ぼく以外には誰も拾う者はいない。果肉を洗い落とし
乾燥させるのだが、土に埋けて果肉を腐らせ取り除く手もある。そこで植木鉢に埋めておいたのだが、何と十数本が
発芽してしまったのだ。
今は、20センチほどの”枯れ枝”にしか見えないが、しっかした芽をつけている。植木鉢は大振りだが、”枯れ枝”には所狭しだ。
春になったら、鳩山に移植しよう。鳩山にもイチョウの木はあるが、実が成らない。大学の鈴なりのイチョウの子どもだ。あやかって
銀杏を雨のように降らしてくれるようにならないかなあ。
(Mar.26)
■アケビ棚を補強……石井さんにまたまた、大感謝


杭を打つ音で目が覚めた。わがアトリエは訪れる人は稀なので、あわてて外に飛び出した。
石井さんだった。昨日はヨモギ餅を持ってきてくれ、今日は、倒れそうに大きく傾いているアケビ棚を
直しに来てくださったのだ。石井さんは先日、杉の木を剪定してくれたのだが、そのとき、アケビ棚が
壊れそうなのが気になったのだという。四本の足に角材を打ち込み補強、古い蔓も取り除いてくれた。
「花芽は残してありますからね。今年は実が成るでしょう」……と。人の佳い石井さんのとびきり上等の
笑顔に、ぼくの制作が捗ったのは当然のことであった。深謝。今回は二日間のアトリエ生活。明日からは
渋谷の仕事場に戻って働くことになる。
(Mar.23)
■出来立てのヨモギ餅をいただく
昨晩の強風(東京では瞬間最高風速20数メートル)鳩山の庭も多くの枝が折れていた。
プラムやすももは蕾をつけた枝が……。相当強い風が吹き荒れたのだろう。


アトリエ北側の田圃の主、石井さんがヨモギ餅を届けてくださった。朝作ったばかりの出来立て。
越辺川で摘んだ蓬、自家産の上新粉(都幾川村で精米))、小豆もすべて石井さんの収穫品だ。ヨモギの香りが
鼻腔をくすぐる。口当たりの良い適度の柔らかさ。美味い!餡と黄な粉で二つペロリ。
毎年、この時季きまって春の味覚の贈り物。嬉しくて、でも秋にいただく栗の渋皮煮や、採れたての
米、それにぼくの大好物の玄米(これと梅干さえあれば、おかずが要らぬほどだ)など、いつも頂いてばかりで
心苦しい。アトリエに車が停まるのをみて軽四輪でおいでなさる。ありがたい。手を振り頭を下げ、見送るが
お礼に何も差し上げられず何とも申し訳ない心持だ。ご好意に感謝。
(Mar.22)
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
 |
今年の春分は3月21日 (清明は4月5日) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
17日の当欄、ミツマタの花の写真を掲載したが、ミツマタは沈丁花と同じ科だった。甘い匂いは同じなれど、ミツマタは
鼻を近づけ嗅がねば分からないほど”上品”。ミツバチが減って困っているというニュースをたびたび目にするが、
わが庭には、ミツバチが群がって飛び交っている。ミツマタの花の蜜を集めることに夢中で、ぼくの存在なんておかまいなし。
ミツバチの羽音を耳にぼくはミツマタの花に顔を埋めたていた。
(Mar.21)
■板絵『harbor』制作進行中
現代童画春季展(別項「展覧会」参照)に出品する板絵、作品タイトルを
「harbor」と決め制作中。絵の具が乾く時間も絵から離れられない。額縁を
塗装したり絵皿を洗ったりもするが落ち着かない。完成が近づくといつもこうだ。
最後の筆を入れ、いすに座リ込むとき、時が止まる。まばたきさえ止まるくらい
集中して見入っているのだと思う。その後襲う疲労感でわかる。
「harbor」……父と子の遊び場所。内緒の(自分たち以外は誰も知らないと思っている)
隠れ家。想像力を全開させる、ぼくにとっての「板絵制作」同様、時間の止まる宇宙だ。
その宇宙を、今描いている。
(Mar.21)
■紙芝居「だいじな たまご」出来上がる


・「だいじなたまご」① いずれも画面はカットされています


社団法人「小さな親切」運動本部製作紙芝居『心の教育プロジェクト』
……紙芝居で「豊かな心」を育てよう…… 「だいじなたまご」が完成した。
紙芝居を用いた道徳授業のための指導資料もついている。視認
性を重視、太いシンプルなライン、色も
絞りスッキリさせた。せっかくもらったチャボの玉子が壊れて怒り、悲しむ主人公たっくん。たっくんの心情は
とらえたつもりだが、紙芝居は演者の力量による所が多い。持論「絵本も紙芝居も童話も面白くなくては」が、
今回は少々叶わなかった面もあるものの、ストーリーも絵もシンプルなだけに、授業展開に広く活用できると思う。
■伸びた蔓をグルグル巻いて……何のリースでしょう?



・キングサリの花 ・ブナの枯れ葉(新芽が堅く鋭く尖っている) ・オリーブの木に
リースなんて洒落たものじゃない。枝をグルグル巻いただけ。何の枝?ここがポイント!蔓は藤、アケビ…材料に事欠かないが、
今日は始めての蔓で制作した。キウイの棚に絡まっていく枝も長く伸ばしているマタタビ。花が咲き、実を期待させてはがっかり……の
マタタビの蔓が地面につくくらい垂れ下がっていたんだ。30分間のお楽しみさ。
マタタビの冠は何で飾ろう。まず水仙、それからクリスマスローズにかけて見た。似合わない。キングサリの黄やオリーブの濃い
緑もマッチするが、やはりブナがいい。芽吹く前だというのに葉を落とさず寒風に身を震わしているブナがいい。マタタビのリースに
ブナの枯れ葉色……美しいなあ。30分の楽しみに幕を引き後ろ髪引かれる思いでアトリエに戻った。
体は冷えたけど、嬉しさがねえ……。いい仕事が出来そうだよ。
(Mar.18)
■日がな一日板絵制作に没頭……



・ミツマタの花(木の高さ2メートル、殆ど花は白く見える ・同、しゃがんで見れば黄色 ・沈丁花
10時から7時までアトリエに籠る。いや、花の香りに誘われて一度外へ出た。
仕事場に甘い芳香が漂ってくる。沈丁花だ。朝東京を発ち鳩山に来たが、車を降りたときは気づかなかった。
満開。近づけばきつい位匂い発つ。沈丁花から数メートル先にはミツマタがこれまた咲き誇っていた。上から見れば
白(淡い黄色)、ちょっとしゃがんで下からのぞけば濃い黄色。ほのかに甘い香りがする。
いつかミツマタの皮で紙を漉いてみたいと思う。早く成長して欲しいものばかり。メープルシロップをとりたくて
サトウカエデを、ブナ林を夢見てブナの苗木を、とちもちを食べたくてトチノキを、果実酒を目論んでナナカマドやサルナシや
マタタビを植えた。が、すべて夢の夢で終わるだろう。それでも、夢の種まきはやめられない。
一旦外に出るとアトリエに戻りたくなくなるから困る。草木の息吹に気圧されそうだ。板絵に向えば、すぐ”復調”するから
未だ大丈夫だが。”大丈夫”はおかしいか。自然は敵ではないし……一体感。抱かれての仕事のはずだよね。
(Mar.17)
■タイトル決定!クレヨンまるファイナル「バイバイ クレヨンまる」
春季展出品板絵の作品名は絵より先行したが、クレヨンまるは文・絵が完成してから考えた。タイトル案は数種。
でも、一番おとなしいものを選んだ。「バイバイ クレヨンまる」あまり強く内容を暗示させたり、
感情移入過多にならないように。
1996年1月号から連載開始、155話がファイナル。普段のアイディアとは違った、最終回の展開には頭を使った。
“読み聞かせお話雑誌”『おひさま』はこの春から隔月刊になる。クレヨンまるは、5-6月号(4月15日発売予定)
で、さよならする。意外な結末……!? どうか、ご高覧あれ。
(Mar.11)
■これから制作する板絵の作品名を考える
現代童画2010春季展(4月5日~11日 於・銀座アートホール)出品作の制作に入る。
と言っても、鳩山アトリエ初日は雪降りでクローズ。渋谷に戻りエスキスを取る。
と同時に作品タイトルを考えねばならない。会場に置く出品目録印刷のため、作品名を申告する
ことになっているからだ。refuge, hide out, ……、悪事を働いて隠れる意が強いから、ぼくは「harbor」を選択。
隠れ家で遊ぶ父と子をイメージ。親とか子とかの意識をはずれ、幸せ無我の境で遊ぶ秘密の空間を描きたい。
今回のように作品名が絵より先行する例は、ままある。「瞬幸永憶」(F100号)もそうだ。
無論、瞬幸永憶などという熟語はない。言葉のイメージが絵を語らせた好例である。
(Mar.11)
■雪降り止まず退散
板絵制作に入ろう……遅れた時間を取り戻すべく一路鳩山へ。
予報では天気は午後から崩れるという。冷たい雨は昼前には雪に変わった。
とにかく寒い。久しぶりのアトリエ、震えながら板に向かう。が、外が気になって仕方がない。
春の日が射せば、シジュウカラやヤマガラそれにウグイスの声を期待できたのに、生憎の雪!
眼前に広がる田や畑は真っ白。積もれば、坂下にあるわがアトリエだ、
車はスリップして登れなくなる。何年か前、“脱出不能”となったことがあった。
というわけで、「アトリエ滞在2時間」のみ、の記録を本日つくった。
雪に埋もれていくフキノトウ、摘みたい気持ちを抑え帰京せり。
(Mar.10)
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
仕事に明け暮れHP更新もままならず。テニスにも行っていない。”外出”は現代童画会春季展作品用パネルを取りに行った
鳩山アトリエのみ。
おおよそ人間的でない生活。体が鈍ることを憂うも、窒息しないでやっていられるのは、表現欲求のなせるワザか。
このところ天気が優れない。菜種梅雨か。久しぶりに今日、雨上がる。最高気温18度、昨日より10度も高い。時間をきめて歩く。
代官山~恵比寿~渋谷、これで5000歩。恵比寿駅近くで「ロバの花売り」に出合った。暫し足を止めた。1メートルくらいの灰茶褐色の
ロバ、背中に花かごを付けている。チェック地のシャツにベレー帽姿。赤ら顔のおじさんはバラの花を一本一本小分けにしている。珍しさもあって
見物人が取り囲む。ロバは大人しくじっとしている。が、急に飛び跳ねた。おじさんのジャンパーの中に顔を隠した。おじさんはカメラの
フラッシュをやめてくれるように言った。
やさしいロバの目。花の中に桃の枝も……。「飼えたらいいなあ……」ロバは、ぼくの飼いたいものリスト、ベスト3上位だ。
(Mar.5)
| 2月のアトリエだより |
■「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」



『おひさま』連載の 「クレヨンまる」、次号で155話。これで見納め、読み納め。只今最終編を執筆中。別れは悲しいもの。
クレヨンまるはどうなる?仲良しのチェリーは?それに、大泥棒のワルズー、子分のコウモリ、コモリンは?三百数十歳の
ミイラばあやは………死ぬなよ!?………明るく明るくと念じても、想いがつのって……。さあ、どうなるか。〆切待ったなし!
描くぞー!!!!こう、ご期待!!!!
(Feb.28)
■「フータのひこうき」の朗読が放送されます
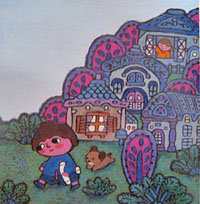



ぼくの絵話集「マーリと のうさぎ」の中から 『フータのひこうき』が放送されます。
童話として書いたものではないので、朗読でイメージがどう伝えられるか楽しみです。
(絵の世界がどう表現されるかなあ)
番組名:『童話の散歩道』
放送日時:32局ネット
「童話の散歩道」各局の放送時間
・ 北海道放送 3月27日(土)6:20~6:30
・ 青森放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ IBC岩手放送 3月28日(日)12:20~12:30
・ 秋田放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 山形放送 3月28日(日)7:15~7:25
・ 東北放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ ラジオ福島 3月28日(日)8:30~8:40
・ 新潟放送 3月28日(日)12:40~12:50
・ 北陸放送 3月28日(日)7:40~7:50
・ 北日本放送 3月27日(土)7:50~8:00
・ 信越放送 3月28日(日)8:50~9:00
・ 山梨放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 福井放送 3月28日(日)6:20~6:30
・ 静岡放送 3月28日(日)5:10~5:20
・ 中部日本放送 3月28日(日)8:35~8:45
・ ラジオ関西 3月27日(土)7:20~7:30
・ 京都放送 3月28日(日)17:30~17:40
・ 中国放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 山陰放送 3月28日(日)16:00~16:10
・ 和歌山放送 3月27日(土)16:44~16:54
・ 山口放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ 西日本放送 3月27日(土)7:00~7:10
・ 南海放送 3月27日(土)17:50~18:00
・ 高知放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 四国放送 3月28日(日)11:50~12:00
・ RKB毎日放送 3月28日(日)8:15~8:25
・ 大分放送 3月27日(土)8:20~8:30
・ 長崎放送 3月28日(日)7:00~7:10
・ 熊本放送 3月28日(日)9:05~9:15
・ 宮崎放送 3月28日(日)6:30~6:40
・ 南日本放送 3月28日(日)6:50~7:00
・ 琉球放送 3月28日(日)7:15~7:25
朗読アナウンサー 牛山美那子
(Feb25)
■コンソーシアム大学「作って遊ぼう」第三回
『コロコロ コロ玉バランスボード』を作る。ゲーム機では味わえない”微細な手の運動”。イライラさせて遊ぼうというもの。
長方形木片26個、円筒形4個使用。赤青緑黄に塗った木球4個を転がして遊ぶ。四隅から中央に集めたり拡散させたり、
時間を競ったり遊び方は色々。遊び方を考え出すのも狙いの一つ。シンプルで何度でも繰り返し遊べ何より”手加減の妙”を
味わう。勢いよく転がしても玉は思うところに入らない、留まらない。ビー玉、おはじきも皆そうだ。加減が技である。
教室に玉ころがしの音が響いた。気が付いてみれば二時間の授業中、トイレに行った子どもなし!何と言うことだ!えらい集中力!
授業の終わりに、ぼくはこのことに触れた。トイレさえ忘れ、夢中で頑張った子どもたちを褒め称えた。
(Feb.20)






■ コンソーシアム講座の終わり10分の”オマケ”
120分授業を、子供達が飽きさせないで楽しくやるのはたいへんなこと。これに一番頭を使う。絶対集中させるぞ……意気込んで!
メニューを幾つか用意するのも手だが、しっかりしたものを制作させるにはそうも行かない。所々刺激を与える仕掛けを用意したり、
あっと目を見張る(視覚効果)ものを隠しておいて広げて見せる等など、アシスタントの学生にも秘密の隠し物を前日から用意したりする。
講座終了10分前も大事!作品が完成し、自由に遊び、少々だれてきている。そこで強い印象で締めくくるには、新たな興味を惹く
出しものが必要となる。前回は「シュルシュル人形」。そして今回は「牛乳パックの水車」を用意。教卓に6っこずらりと並べ、
「さあ、こっち見てー!」子供たちが群がったのはいうまでもない。蛇口をひねり水車の羽根に当たるように置く……「ぼくにも!」
「やらせて!」「すげー!」子供達の楽しむ声が大人を気づかせる。「廃物利用、創意工夫……創造的遊びを」お母さん方は
作り方を熱心に聞いている。「お家で是非作ってくださいね。簡単で面白い工作を考えてね」……メッセージと共に授業は終了する。が、
帰らず遊び続ける子どもも多く、こんな姿をお母さん方は、目を細めてみておられた。子どもは輝く!凄い輝きを発す!



■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)
 |
雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
20日の日差しは春のもの。穏やかな日和。紅梅白梅の木立の間に銀杏が数粒ころがっていた。最後までしがみついていた
実が落ちたのだろう。キャンパスは人影もまばら、静寂。「コンソーシアム授業」会場に向かう足取りも軽かった。
■クレヨンまるファイナル 制作中!!必見!!クレヨンまるの最後!
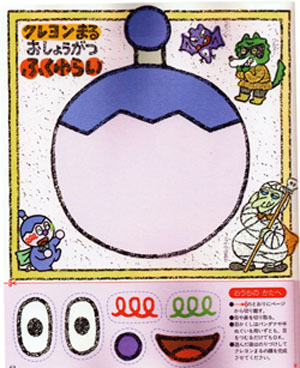
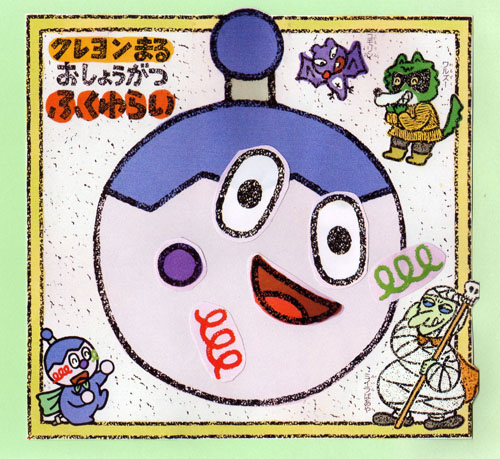 ・福笑い
・福笑い
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』
二日目 「回転円盤仕掛け絵本」”あんなかお、こんなかお、そんなかお、みななかお、どんなかお”」
雪交じりの寒い朝、20組の親子が集まった。前回同様みんなヤル気十分!お父さんの参加は4名、弟や妹を連れてきた方もいて
教室は満員。まず”宿題”の顔の絵を絵本の表紙に貼り付ける。もちろん”作家名”も記入する。絵本作家になった気持ちで、
制作スタート。子どもは4種類の”面白い””おかしな””楽しい””見たこともない”顔を描く。その間に保護者の方々は
仕掛け絵本のメカ(二枚の回転円盤、ジョイントなど)を制作する。顔の絵を上部と下部とに切断し本体に取り付ける。本体台紙に
開けられた二つの穴(目と口)に12個の表情を描きこむ。これで何百もの顔ができるのだ。製本は金属鋲をかしめる。これは、
かなり大変だったけれど、学生が要領よく流れ作業でこなしてくれた。世界で一冊だけの「ぼくのえほん」「わたしのえほん」で
子ども達は遊んだ。”へんてこな顔”が出現するたびに歓声をあげて……。作る楽しさ、遊ぶ楽しさ……、苦心して作り上げた
その達成感が子どもを成長させる。
講座終了間際にお家で簡単にできる工作を紹介する。今回は『しゅるしゅる人形』牛乳パックとストローとタコ糸があれば
誰でもできる玩具。試作品を吊るすと、子供達が群がった。シンプルだけど面白い。手加減で人形がしゅるしゅる昇っていき
スーと落ちてくる。子ども達は繰り返し繰り返し遊んでいた。つくり方をメモしているお母さんも。是非とも、お子さんと一緒に
作って遊んでほしい。

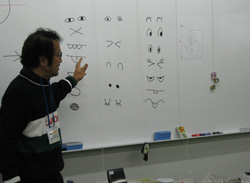

・「おもしろい顔ができたねえ」 ・表情の変化は色々だよ「泣いたり笑ったり、怒ったり眠ったり…」・「やって見せて!」



・糸を操り人形を天井まで昇らせて遊ぶ ・牛乳パックで作って見せる ・ちょっと”豪華な”「こんなこ」バージョン
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』 初日は「変身仮面を作ろう!きみの仮面はどんな仮面か、お話して!」
6歳~9歳の子どもに、お母さんお父さんを交えてのコンソーシアム大学「作って遊ぼう!」開講。
「●作って遊ぶ楽しさ●出来たものは、世界でただ一つの存在●表現は”自由”、この素晴らしさ」
第一回目は、『変身仮面』。仮面を作って、各自その仮面の秘密、凄さを語らせるもの。


・21人が仮面を制作。仮面にはそれぞれの秘密がある。想像させることが目的。



・マントは黒2着、白4着を用意。全員を写真に収める。 ・わが優秀なるアシスタント。子ども教育学科2年生
・下段中央は、河童(鼻から突き出しているのは”吹き戻し”が正義の味方○○仮面にやられるの図)
さて、この弱虫カッパは誰でしょう?
次回は『回転円盤仕掛け絵本』…………
「こんなかお、あんなかお、そんなかお、へんなかお、どんなかお」変な絵本のタイトルだねえ。
■クレヨンまる最終編! はたしてどうなるかクレヨンまる!


『おひさま』 が月刊から隔月刊になる。それにともない、クレヨンまるは『おひさま』6-7月号(5月15日発売予定)を
最後に休載する。おひさま創刊当初からクレヨンまるを描いてきたから感慨一入である。
第一話「クレヨンまる誕生」が1996年1月号、以来本年2月号「オリーブおばさんのプレゼント」が154話。
15年の連載を休止するのだが、ファイナル155話は特別編だ。クレヨンまるファンを悲しませないよう、そして、
最大級の”オチ”で締めくくろう。このところ毎日毎晩、結末をどうしようか考えている。
これじゃダメ!あれでもダメ!面白くて、悲しくて、くすっと 笑える……あっという最後で締めくくるんだ!ぼくは
クレヨンまると共に生きたから、ぼくなら出来るはず……言い聞かせて、寝ても覚めてもクレヨンまるの世界に
浸かっている。クレヨンまるファンの皆さん、待っててね。クレヨンまるの”最後”……悲しみを吹き飛ばすような
結末を、きっと描いてみせるからね。
(Feb. 10)
■二十四節気 <立春> 七十二候(一候.二候.三候)
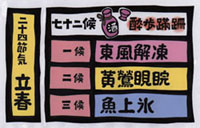 |
●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
暑いのは歓迎だが、ぼくは寒さに弱い。渋谷の仕事場は北側に位置しているから、部屋は外よりも寒い感じ……、そんな
バカなことは無かろうが暖めても暖めても室温上がらず。机の下には足温器、膝暖盤、更に温風ヒーター。背中にはハロゲン
ヒーターの遠赤外線をあてている。こうまでしないと、仕事が出来ない。ふくらはぎから下の冷え性だ。机に向かっている限りは
快適となるが、部屋全体が温まるわけではなく、よって机から離れられない。机にしがみ付き仕事をする破目に。
これが集中力のなせるワザならよいのだが……。
(2月3日)
■キャラクター{ミンミン}シール作製
もう何種類のシールを作ったろう。 相模女子大学の「子ども教育学科」は誕生まもない。いずれ
”卒業生の現場での評判”が歴史をつくってくれるであろうが、それまで手をこまねいているわけにはいかない。
イメージづくり(戦略)の一助にとキャラクター展開を試みている。
元気、明るい、素朴、自由……MINMINちゃん、頑張れ!!!
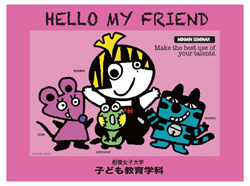
 、
、

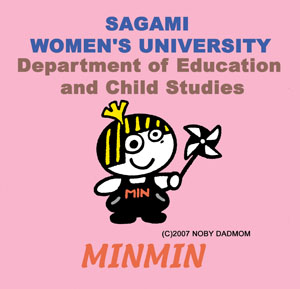
| 1月のアトリエだより |
■コンソーシアム大学……”仕込み”続く 「お化けの衣装」
渋谷の生地屋さんで白と黒の天竺木綿を買う。白はお化けの衣装、黒は○○○仮面のもの。頭からすっぽり
かぶる簡単な構造。子どもたちが作る仮面を引き立たせるよう体を覆い隠すのだ。まずはぼくが黒いので登場、
アシスタントの学生3名は白いお化けになってもらう。5日に試作品を作るが、学生もぼくも、子どもには勝てっこない。
”勝てっこない”は、競う気持ちの表れだ。もちろん、子どもなんかに負けてられない!想像力で、いざ勝負!
遊んで楽しんで、真剣勝負だ!”勝負”は”心のままの表現”と置き換えよう。そう、”心のままの表現”は
比べるものではない。当たり前のことであった。
(Jan.30)
■コンソーシアム大学 「作ってあそぼう」申し込み締め切り!
子どもと親とで作って遊ぶワークショップの申し込みは締め切られた。事務局より定員をオーバーしたとの報せあり。
熱心な方々の気持ちをかなえてあげたい。補助椅子を出して対応して貰う。
工作メニューは三つ。 2月6日、① 「世界に一つのミラクル仮面」(大きな覆面タイプと吹き戻しを使うもの2作)
13日 ②「絵変わり仕掛け絵本……あんなかお、こんなかお、どんなかお、みんなかお」20日 ③「イライライラ……コロ玉
バランスボード」作る喜びを味わってもらう。表現する素晴らしさを体験し、止みつきになってくれれば……。
頑張ろう!目一杯、精一杯やる!
5日にはアシスタントをしてもらう学生3名を特訓する。もちろん、ぼくも試作を楽しむ。それにしても教材の準備は大変!
仕事場は段ボール箱の山だ。買い集める、加工する、セットする(パーツを袋詰め)……、ああ今日も慌しく日が暮れた。
(Jan.29)
■造形応用 牛乳パックTOY② 「舌だし人形・・・愉快な仲間達」


 「こんなこいるかな」へ
「こんなこいるかな」へ
・アリガくん試作例 (「こんなこいるかな」バージョンを別項『こんなこいるかな』コラムに掲載)
造形表現活動(応用)最終回は牛乳パック(ミルクカートン)工作。材料はカートン一個半とゴム輪2本のみ。
カートンはTOY①同様裏返して使う。学生は始めの頃恐がっていたカッターナイフにも大分慣れてきた。手作業の
大事さ、それに廃物利用”創意工夫”する心を育てたかった。
TOY上部の持ち手を放すとパチン!の音とともに目が変化する玩具。単純素朴なことが「壊れにくい、飽きさせない、遊び方が工夫
出来る」など、よい遊びの条件の幾つかを満たしている。遊びといえばDSやPS一色の感があるが、自ら作る、その素晴らしさを
放棄しているようでもったいないことだ。遊びを創出する……ここにも自己表現がある。学習で疲れた学生が教室で
生き生きした表情に”蘇生”するのを見るにつけ、定まった答えのない表現の世界で遊ぶ(自由な心での表現)ことの
重要性を再認識する。
(Jan.27)





・学生制作作品例(舌は出たり引っ込んだりする。写真はすべて長い舌が伸びたところ)
■造形応用 牛乳パックTOY① 「回転円盤絵変り・・・六面相」



牛乳パックTOY制作その1 「回転円盤六面相」を作る
学生の積極性が感じられるようになってきた。バイト先のコーヒーチェーン店から、牛乳パックを大量に運んできた者、朝、研究室に
立ち寄り、パックの包みを置いて行く者……、牛乳離れが進んでいる若者が、何とかして授業に役立てようと頑張る姿……嬉しいことだ。
自主性こそ、創意工夫する心、自己表現する心、とともに学生に摺り込みたいことだから。
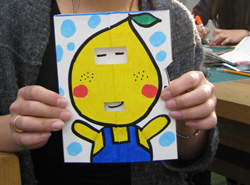

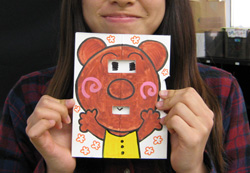

(Jan.22)
■二十四節気<大寒> 七十二候(七十候.七十一候.七十二候)
 |
●大寒は1月21日 ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
このところ寒い日が続いていたが、昨日今日は最高気温が14,5度。3月の温かさだ。明日は18度にもなるという。が油断は禁物。
あさって、金曜日はまたぐっと冷え込むとの予報。久しぶりのテニスを予定しているのに……。日差しに明るさが増してきた。
春が近づいている。もうすぐ立春だ(2月4日)。
(Jan.20)
■ NHK教育テレビ「絵本寄席」をご覧下さい


1月29日(金)午前7時45分~50分 NHK教育テレビ「テレビ絵本」にてえほん寄席のアニメが
再放送されます。『目黒のさんま』(有賀忍・絵 三笑亭夢太朗・落語)早朝ですが、どうぞお楽しみください。
■シラバス打ち込みと、紙芝居作画に明け暮れる
新年度の履修科目シラバス作りに大わらわ。昨年から提出がパソコン入力となり操作に戸惑う。キーボードから
20分離れると自動的にすべて消去されるし、「更新」「保存」が分かりずらく何度もやり直すはめに。10科目を
入力し終わる頃に漸く慣れたが。
授業が始まる前に、仕事の目処をつけねばと、紙芝居「だいじな たまご(仮題)」制作も頑張った。こちらの苦心は
鶏小屋の金網や、卵が割れて悲しむ少年の表現など。ストーリーが単調で、紙芝居の”単純明快、可視性”はクリア出来たとは
思う。が、やはり絵本も紙芝居も”面白くてナンボ”………不満がない訳ではない。
(Jan.15)
■エンターテイメント
正月テレビは殆ど見ない。ニュースを除いて。ただ、小朝の落語「親子酒」には抱腹絶倒。ろれつの回らない親子の酔っ払いの
掛け合いが見事。酔いが回るにつけ顔までが赤くなっていく様は感動物!話のおもしろさ、形振りの上手さ、完璧だ!
大学の帰り道、NHKラジオの「真打競演」を聞くことが多いが、漫才も落語も大笑いさせるもの少ない。話がつまらない。
生中継ではないし、”話芸”を収録するのなら、選ぶべきだろう。天才、小朝を聞いて思った。
■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候.六十八候.六十九候)
七十二候も最早六十九候。あと三候残すのみ。<小寒>の次は<大寒>。そして、
いよいよ<立春>……春の到来だ。
 |
●小寒 1月5日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
| 12月のアトリエだより |
■鳩山は冬景色。枯れ葉で埋め尽くされる
アトリエの周りはすべて枯れ葉で覆われた。この間まで鬱蒼と茂っていた木々は裸。空が広がり明るくなった。
ブナの木だけが薄茶色の葉をまだ落とさずにいる。風に飛ばされまいと、しわしわの葉の塊がしがみつくように付いている。
枯葉を集めて井戸を改造した腐葉土枡へ運ぶが枡はすぐ満杯。諦めた。「一面枯葉の野」に与すパワー不足だ。
創作行為とはことなるが、草取りや枯れ葉集め……これらは、妙に楽しい。いえ、楽しいとは違う。何も考えない時間を
すごす嬉しさかなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
ノロウイルスか、風邪か。張り切ろうにも力がでない。普段から低体温で、一寸でも熱っぽいと頑張ろうにもだるさには抗えずダウン。
今年も無事に乗り切ったかと油断したわけではないけれど、この暮れ、最後の仕事にブレーキがかかる。とはいえ、しがみつくように
ダラダラと作業。 熱が引いて、即コートへ。鈍った体に喝を!荒療治!………無謀なり。
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
師走になり、日が過ぎるのが一入早く感じられる。毎年のことだが……。追いかけられているようだ。追いかける位の
心の余裕がほしい。アクセク、バタバタ、アタフタ……で、今年も暮れそうだ。 嗚呼。
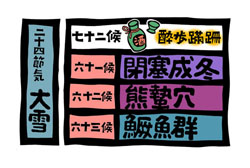 |
12月7日は大雪 (12月22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
■寒さものともせず(ウソ、大強がり)テニス
昨日は冷たい雨。幼稚園講演会。会場は100名を越し満員だったが、冷え冷えとしていた。終了後のサイン会では、足元が冷たく
膝をすりあうようにした。寒かった。
今日は曇り。オムニコートは湿っているだろうが打ちに行く。メンバーはぼくより高齢な方が多い。それも、週一のぼくと違って、
週三、四回はプレーしている兵ばかり。捻られるのを覚悟の上参戦!ただ時間を気にせず打ってみたい。忙しないなあ。
■鳩山は落葉の季節。”目の幸せ”紅葉もおしまい
モミジは峠を越えた。サクラはすべて葉を落とした。ブナの茶葉、カシワ、モクレンの薄茶色……、あたりは茶色に染まっている。
中で鮮烈な赤色を留めているのがハゼだ。植えてよかった。来年はもっと植えよう。ローズヒップ、ブルーベリーの葉も。
雨に洗われて秩父の山並みがくっきり見える。日差しも柔らかく、のんびり……としたいところだが、仕事仕事!
描いている10号の絵を二枚直しをいれる。フレームの製作にも着手。手を洗う間もなく車上の人。慌しい。よくないなあ……。
■師走……キャンパスを走る……アタフタ アタフタ
授業はいつも時間が足りない。演習科目のつらいところだ。準備や試作で休む間もない。研究室に来訪者があれば、昼飯抜きとも
なり、空腹と戦いながらの教室。この季節も汗びっしょりで、キャンパスの風が一入冷たく感じる。気力で持っているのだろうが、
おかげでメタボとも無縁、カゼ菌も寄り付かず元気。(多分に、やせ我慢)
■小石に絵付け 3


・ジェッソ(下地剤)を塗り描く。顔、顔、顔…… ・人面石 ・拾った(顔が描かれていた)石
| 11月のアトリエだより |
■小石に絵付け 2


紙芝居《やさしいこころ》に添えて配ろうと、小石に登場人物”おにぎりん”の絵を描いた。
今日の授業は先週に続きPEEK A BOO……「いないいないバー」は幼児が好む遊びの一つ。紙一枚で2場面、4場面
変化するカードを制作した。仕組みは簡単。学生は思い思いのイラストを描く。シンプルなものほど応用性がある。遊び方も
工夫できる。スイッチを入れたらお終いのICを使った高価な玩具より、やはり手づくりだ。工夫の余地があるかないか。
想像力と創造力を育む遊び、玩具とはどんなものかを学生には考えさせたい。
■二十四節気 <小雪> 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
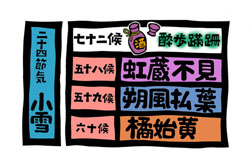 |
11月23日 小雪 (12月7日 大雪) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
アトリエまで、今日は関越高速を使わず川越街道を走る。三芳あたりのケヤキ並木の紅葉が目当て。春から夏、
街道を覆い隠すほどだった緑のトンネルは葉を落とし秋空をのぞかせていた。今年は遅いのか。黄色、茶色、赤色……の
紅葉はまだだった。このあと、一気に紅葉、黄葉がはじまり、嵐のように葉を落とすのだろう。残念だが見られそうもない。
アトリエの庭のハゼは鮮やかな紅色。ブナは茶褐色、桜、モミジ……冬の入り口、風に震え、舞い落ちる……色の饗宴、
静かな時間、心穏やかなる一時。
■小石を拾う……形を楽しみ、絵をつける



校内の駐車場の脇で小石を拾う。一つ一つ形を吟味しながらビニール袋に入れるぼくを、学生や教員が怪訝そうに見ている。
20個、30個、相当な重さだ。洗って改めて形を眺める。石に絵付けをするのだが、なんと”先客”がいた。顔が描かれた楕円形の
小石があったのだ。小学部もあり、子どもが描いたのだろう。見つけたときは、思わずにっこりだ!嬉しくてねえ。描かれた目、鼻
、口はかすれてはいたが白色が美しかった。これを描いた子と会いたいなあ。
紙芝居『やさしい こころ』を制作した。少年と作業服を着た工事現場のおじさんが登場するお話。そのおじさんの顔がおにぎり
そっくりで、少年は<おにぎりん>と呼んでいた。少年は図工の時間、小石に絵を描いた。ペンギンやカメや自動車などいろいろ。
<おにぎりん>もね。 中央の写真はぼくが作った<おにぎりん>。おにぎり形の小石は結構多い。幾つか作って、紙芝居を演じる
方に差し上げようと思う。”実物”を見て、子供たちが、自分でも作ってみようと言う気になったらうれしい。
■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)
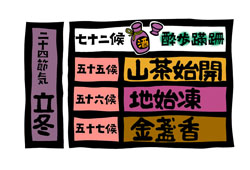 |
11月8日は立冬 (11月23日 小雪) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■赤い実の季節
鈴なりの渋柿が熟して枝を撓らせている。ナツメが落果。サルナシも柔らかに……、
カマツカの暗紅色、カラスウリの朱赤……陽に照り映え、今 秋真っ只中。






面白い実を見つけた。見たことのない形、蔓に二十数個の赤い実の塊まりが10センチおきについている。蔓は「長い。引っ張り手繰って
根元まで近づこうと試みるが、山の斜面が崩れやすいこともあって難儀。根は深く、球根を持っていた。わがアトリエの庭で育ててみたくなり
図鑑で調べた。サルトリイバラ……ユリ科の多年草。実もそうだが、葉の脇に一対の髭があり、この特徴からすぐ名前が解った。
細いさつまいも状の球根は漢方薬「山帰来」となる。北斜面の日当たりの悪い茂みの中で育ったサルトリイバラ……大事に、といっても
似たような場所に移植、根付くよう祈った。
| 10月のアトリエだより |
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
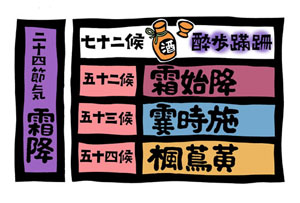 |
10月24日は霜降 (立冬……11月7日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
24日は二十四節季の霜降なれど、汗ばむほどの陽気。現代童画展審査に臨んだ。25日は一転襟を立てて歩く寒さ。終日、
審査会場に詰めていて分からなかったが、木枯らし一番が吹いたのだそうだ。賞の決定、推挙会議と慌しかった。
『現代童画展』第37回!ぼくも、まあよくも出品し続けたものだ。本年の目玉は、過去の大賞作品を集めての特別展示。
ぼくは第3回展で大賞を受賞したが、その作品も久しぶりに”お披露目”。ただ、会場が狭いため、『星の海』一点のみ。
『花の野』が飾れないのは残念である。
本展出品作は『星の道』。 7月の選抜展で発表した”『沈黙の闇』の後”を描く。 選抜展をご覧下さった方は、
イメージを重ねていただけたらと思う。
鳩山アトリエ、秋真っ最中。ハゼの紅葉がはじまり、パンパスグラスに絡むカラスウリが風に揺れている。こっちに一つ、あっちに一つ……
濃い朱赤が目の奥に染み込んでいく。雑草に負けずに蕾を抱いたニオイスミレを見つけた。数株集め周りを煉瓦で囲い”スミレの園”に。
イーゼルから作品を降ろし車に積み込んだ。いつもながら、アトリエ立ち去りがたし。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)
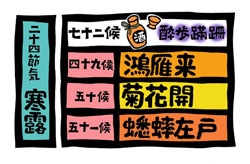 |
10月9日は寒露 (10月24日は霜降) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展は東京都美術館が改修工事のため、本年も上野の森美術館で開催される。会場壁面の都合で30号とサイズも
制限される。大作に臨みたい気持ちも強いが、この春以降モチーフが少し変わってきており、画面の小ささはさほど気にならない。
今まで <心のふるさと……懐郷の詩> <親子・父と母・父性・幸福感>を描いてきた。今回の作品も底辺に流れるものは、
そう変わらないが、さりとて明るいものでもない。春は『沈黙の闇』。今仕上げの段階にあるのが『星の道』。絶望感の中に一筋の
光明……出発だ!それも力強く、頼もしく、矜持を……ぼくは描く。是非ともご高覧あれ。
(展覧会詳細については後日)
■キャンパスのイチョウの木、銀杏落ち始める
教室の机の間を歩き、いや小走りで回っている。コマネズミの譬どうりチョコチョコ忙しなく。声がかからずとも、その人その人
描き出すものの、ユニークな点、おもしろい所を見つけようと。見逃すまい、学生は気が付かない線の流れ、動きを。
教室の暑さは一頃とくらべ過ごしやすくはなったが、ばくは汗びっしょりだ。授業を終え研究室に戻るまでの僅かな時間、
秋の風を満喫。深呼吸して歩く。銀杏を踏まないように避けて、コマネズミは時間を惜しみながらゆっくり歩く。
| 9月のアトリエだより |
■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)
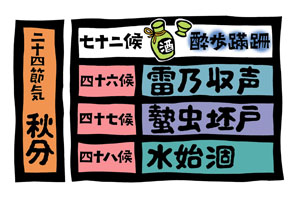 |
9月23日は秋分 (10月9日は寒露) ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
■鳩山、冷え込む!長袖で板絵に向かう



二日間、板絵に取り組む。
アトリエから一歩も出なかったと言うのはうそで、体、殊に目を休めるために鬱蒼としげる葉を掻き分け栗の木まで進む。
まさにジャングルを”進む”感じ。栗を拾おうにも腰高の草が邪魔して、落としても見つけるのが大変。それでもビニール袋は直ぐ
いっぱいになった。
幾種類か植えた萩は雑草に覆われてしまい目を凝らさねば小花が見えない。
自然に生えた道路沿いの柿の木には青い実が枝を撓らせている。大豊作だが残念ながら渋柿。辺りにフジバカマが咲いている。
紅葉は”ハゼが一番”と植えた苗木は雑草に囲まれながらも育っているが、葉の色はまだ緑。アトリエの窓からは見えないが、
工作部屋のわきの山葡萄の房が膨らんでいた。昨年、一昨年と実がつかず枯れたのかと……、今年ヤマブドウの苗木を求め、
近くに植えたのが良かったのかもしれない。ナツメもサルナシもよく実った。マタタビ、ムベ、アケビは葉を茂らせただけで終わった。
アケビは花を沢山咲いたので、実りを待っていたのだが……(アケビの皮のバターソテーは好きな酒肴)
「30分だけ」と予定しても、庭に出れば一時間くらいすぐ過ぎてしまう。制作に没頭も集中力のなせる業だが、自然に実を置くのは
もっともっと自然体。自分の素を丸出しにするという点で、自然に身を置くことと創造の世界に住むことは似ている。
下の田圃の主、石井さんが新米と玄米を届けてくださった。
軽四輪の助手席にはいつも満面の笑みの奥さん。アクをすくい、すくい丁寧に煮あげた栗の渋皮煮、栗の形をきれいにそのまま留めた
上品な味、見事な”作品”を持ってきてくださった。石井さんの前で、ぼくは二つもペロリ!美味い!感謝感謝!
秋の味覚、贈り物が嬉しかった。 気力充填して、仕事に戻る!
■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)
鳩山は大気澄み星が降るようだ。今晩は星の瞬きを妨げるような明るい月夜。十五夜だ。中秋の名月、観月のゆとりもなく、
アトリエでパネル作り。プリンター置き台も製作する。工作は性に合っており楽しくて、なかなかその後の、“本来の”制作に
はいれないで困る。
もろもろの教習、講習会も終わり、秋学期が始まるまで制作に没頭する。時間がなくあせりながら……いつものことだが。
ナツメが赤く色づき始めた。サルナシが頭を下げねばアーチをくぐれないほどたわわに実った。栗の実はやたら降り落ちている。大粒だ。
地域物産販売所でアスナロの幼木を見つけた。“明日は檜になろう”から翌檜と書く。百円!。植木鉢代にもならないだろうに。
勿論買って、杉の木の根元に植えた。吾、アスナロと思ったことなし。今思えども、もはや遅し!
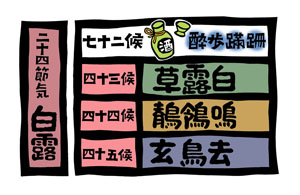 |
9月8日 白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
| 8月のアトリエだより |
■二十四節気<処暑> 七十二候 (四十候、 四十一候、 四十二候)
 |
8月23日は処暑 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月29日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月3日) ・いなほ みのる 稲が実る |
■楽しきかな、ブリコルール!
牛乳パック、ペットボトル、ガムテープや食品ラップの巻き芯などの山に埋まる生活をしている。図工の先生方の研修会に
ブリコラージュを基本テーマに選んだ。(ブリコラージュ人間をブリコルールという) 廃物を活用しての造形遊び。遊びといっても、
楽しめるだけではなく、美しくて飾っておきたくなるようなもの、かなり雑に扱っても壊れない頑丈なものの考案だ。遊戯性と造形美!
工作は楽しいが、わが渋谷の狭き仕事場は、ゴミ箱と化している。フローリングや空間はいつになったら、再び現れるのだろう。
■鬱蒼と生い茂る鳩山の庭……ハチとの戦いはじまる
鳩山のアトリエで教員研修会の“メニュー”作りをしている。最近、わが鳩山町は熊谷に次ぐ暑さで
、テレビに地名のテロップ流れる始末。地形が似ているのだろうか。暑い!でも夜は東京より涼しく感じられる。
土と緑のおかげだ。伸び放題の木々、背丈を越える雑草にも感謝だ。
喜んでばかりはいられない。誰も踏み込まないのをいいことに、ハチが我が物顔で飛び交っている。
デッキを補修、ペイントしようとして蜂の巣を発見!ご飯茶碗ほどもある。スズメバチなら手の負えないから業者に
頼むが、幸いにもアシナガバチだった。防護服でいざ戦!二挺拳銃よろしく両手に防虫スプレー、棒で巣を掻き落とした。
アシナガの群舞は恐ろしいほどだ。巣がなくなっても、ハチはどんどん集まってくる。ペイント作業は中止だ。
階段下の薪置き場にもう一つ、アシナガバチの巣を発見。これも退治。仕事どころではない。いま、巣作りの季節だ。
取っておかないと大変なことになる。昨年はスズメバチに悩まされた。そういえばミツバチがいない。アトリエの壁の間に
巣作りし蜜を部屋に滴らせたミツバチは何処に消えたのだろう。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
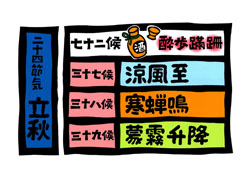 |
8月8日は立秋 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■大学のオープンキャンパス 《子ども教育学科》受講生みな熱心!
今年のオープンキャンパスはティーチングアシスタントに大学二年生三名を起用。万全の態勢で臨んだ。
一時限の授業で、早朝からの出席を心配したが、生徒がつめ掛け満室状態。アンケートでは「満足」が多く、
アシスタントと喜び合った。三名には、月末に行われる教員研修会でも、手伝ってもらう。彼女らがいると、
教室が明るくなる。
研修会が終わる間もなく、幼稚園教員指導が待っている。園児が作って遊べる、“凄くおもしろい”おもちゃを
披露しようと今、試作を繰り返している。仕事場は雑然!がらくたの山だ。本来の絵画活動が
疎かになっている。制作に入れるのは9月になってからか。目の前の仕事が多すぎる!
■ホップの間に植えたもの
珍しいものを植えた。日差し避けにゴーヤや朝顔が話題になっているが、ぼくは野ブドウを植えた。
ホップの苗が育ち、180センチのトレリスから蔓が巻きつくところを探して揺れている。そのホップの間に
これまた蔓性の野ブドウ。
山葡萄はある。枯れかけたが今年見事に再生、今小さな固い実をつけている。
山葡萄の掌より大きい葉っぱと違い、野ブドウは小さいが形が美しい。野ブドウは食べられないが
葉を見ているだけで、何だか嬉しい。この炎天下、根が着くか心配だ。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
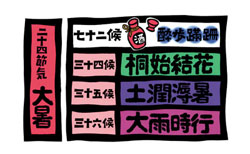 |
7月23日は大暑 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 3日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
■ミルクカートンTOY


・(左)3単位体 テーマ クリスマス菓子 ・(左上) スイーツ ・(右上) 泣き笑い
・(右)1単位体 こんなこいるかな ・(下) こんなこいるかな


・ペロ&ミャー
今回の廃物利用ミルクカートンTOY。牛乳パックを開き裏返してカット。三枚組み合わせたものが1単位体。
その単位体を三個単位でつなげて行く。学生は時間の関係で2単位体の構成がやっと。ぼくは3単位体構成、
4単位体構成の作品を見せた。一単位体で12面ある。それらすべてに絵を描くか、切り抜いた写真を貼る。
6面が泣き顔、6面が笑い顔……、コツが解れば絵変わりもスムーズにできるが、初めての人は面食らうだろう。
面白いキューブパズルだ。学生は思い思いの動物や表情豊かなお化けの絵をつけて、友と交換しては楽しんでいた。
遊びを通じてのコミニュケーションも狙いの一つ。時に”学び”は楽しさの中で行われる。
| 7月のアトリエだより |
■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 小暑 (7月23日 大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月13日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
7日は<小暑>。《温風至る》だが、熱風の”風”さえ吹かず。教室も節電のため空調の温度設定厳しく汗まみれの授業だ。
新校舎は”モダンデザイン”で窓が開かない。暑さには強いぼくも閉口の日々。絵の具を乾かすためドライヤーを使うときなど、
もう炎熱地獄。我慢我慢。
■現代童画会 選抜展開催中
現代童画会 選抜展が只今開催中。 (銀座アートホール10日まで)
板絵『沈黙の闇』を出品しております。ご高覧ください。”蒼”の表現に悩んだ作品です。

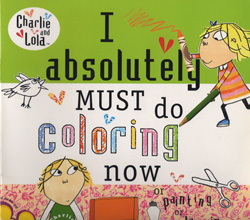
アストリッド・ リンドグレーン展(世田谷文学館) 《長くつしたのピッピ》《やかまし村シリーズ》《ロッタちゃんシリーズ》原画を見る。
子どもの時代、子どもの世界を生き生きと描いたリンドグレーン。見慣れた挿絵から、現代のアーティストのイラストまで多数展示。
中では、ローレン・チャイルドの《長くつしたのピッピ》。一目でわかる、キュートな表情。目が強い。
ローレン・チャイルドの塗り絵本(ペーパーバック)を持っているが、塗り絵には否定論者であるぼくも、この絵本には魅力を感じている。
ただ塗るだけのカラーリングブックではなく、自由に描きこめ、またそのリードして行くネームが効いている。塗り絵本は数々あれど、
このようなものがもっとあったらと思う。
| 6月のアトリエだより |
■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
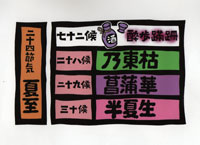 |
6月22日 は夏至 (7月7日/小暑) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■スタンピング……葉脈の美しさ……人工物との組み合わせ


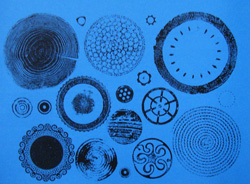
トチ、サンショ、トチュウ(杜仲)、ウメ、 クヌギ、ムベ、ベイ、リンデン、メープル、ブナ、ナナカマド、オニグルミ
絵画造形表現活動基礎Ⅰの授業。オートマティック技法(モダンテクニック)。要は子どもの造形表現遊びの基本。
デカルコマニー、フロッタージュ、スパタリング、ウオッシング、コラージュに続いて、今回はスタンピング。自然物(葉っぱなど)と人口物を
ペタペタ押して再構成。こらー^ジュ作品の制作。
鳩山で葉っぱを採取。形の面白いもの、葉脈が鮮明に写し取れそうなものを選ぶ。3クラス分を冷蔵ボックスに詰める。
クヌギ、山葡萄、菩提樹、桑、サンシュユ、ハナミズキ、オニグルミ、オオシマザクラ、イチョウ、モミジ、サトウカエデ、山椒、
ブナ、トチ、トチュウ、ワイルドストロベリー、ヤツデ、ミニチュアローズ、ローズゼラニウムなど。学生には植物の話(名前の由来、エピソード)も
聞かせた。ローラーを転がし刷り取った者をカットし台紙に再構成する。楽しめたようだ。
ウオッシングについで面白かったとの声も。演習は先ず楽しむこと。楽しんでこそ学習となる。みんな、始めはインクが手に付くのを
嫌がっていたが、仕舞いには指紋どころか手にローラーを転がし手形をペタペタ押していた。
とにかく夢中にさせること。集中させること、これに尽きる。
ローラーやインクバットを洗ったり、葉っぱの始末など後片付けが大変だが、学生の”満足感”が、ぼくの疲れを軽減させてくれる。
次回は墨流し、マーブリング。ぼくは市販のマーブリング剤やセットになったものは使わない。墨のマーブル模様の美しさ、そして
油絵の具を溶いたものを掬い取るカラー版にTRYする。出来合いのマーブリング液を使えばきれいでかんたんだが、それでは
力がつかない。すべて作る。大事なことは、「これがなければ出来ない、これが揃ってないとダメ……」ではなく、応用力、創意工夫する心。
表現とはそういうものだ。準備万端、用意周到からは生まれない。不自由なくらいがいい。足りなくてちょうどよい。恵まれすぎは、
想像力や創造性を培う環境によろしくないとぼくは思う。
■木っ端で名札を作る



・木っ端 (切り抜かれた円形の上部) ・両端をカット (ステインを塗ったもの) ・黒ペンキで名前を書いて完成
地域の産物の即売所ができた。米、果物、野菜の農産物が主だが、植物を売るコーナーもあって、鳩山に行くときは
必ず寄ることにしている。都会の園芸店では見られない面白いものがあって楽しい。キンズ、カマツカ、ヤブコウジ、ハゼ、
マートルの苗木はみなここで買った。一鉢500円~800円と安い。アトリエの畑に茂るムベやサルナシも珍しいと思っていたが、
これらも売られていたからびっくりだ。
即売所には木工製品もある。まな板や鍬の柄。ぼくが買うのは木っ端の束。何かを切り抜いた残材、10枚束ねたものが、何と120円!
昨年は100円だった。これをぼくは名札に利用している。もう数十枚は作っただろう。ブナやクヌギ、昨秋植えたオオシマザクラなど
樹木の苗木が主だが、まだまだ足りない。販売物にはすべて生産者の名前が記されている。木工製品も然り。○○清作……。
この木工の主はどんな方だろう。
このなだらかな山型の木っ端は何を作った後の物なのだろう。大量に出るから不思議だ。「清作さん」に聞いてみたい。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候
 |
6月5日は芒種6月6日 (夏至は6月22日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
■板絵「沈黙の闇」制作没頭。
夜来の雨があがり鉛色の空、水田は天を写す鏡だ。周辺緑一色の中で銀色反射、”何も無い美しさ”だ。小鳥もまだ訪れず
静寂そのもの。幾度も深呼吸をしてアトリエに入る。
このところ週末は板絵に取り組んでいるのだが、モチーフが<哀しみ>そのもの。描いていても辛くて苦しくて感極まってしまい、
「これではいかん」、冷静に冷静に……言い聞かせながらの作業。
顔の色が出来ない。塗っては「違う」、塗り重ねては「違う」の繰り返しだ。絵が重く暗い。描けなかった時から、絵筆を
取る、表現する気力漲るまで時間を要した。『哀しみの船』、『悲泣の丘』以来だろう。胸が塞がる思いの制作は。
■茶の木を探す
今年も茶の木の新芽を摘んでフリッターにして食べた。香りがよい。もちろん酒の友。制作の後の「反省の酒」だが、目一杯
表現出来さえすれば美酒となる。なかなか、そう美味くはいかない。
Sさんが、茶を育てたいと言う。苗木を差し上げたが、楽しみにしていた新芽が何者かに採られてしまった(消えてしまった
そうな)と、がっかりしておられた。そこで今回は少し大きめのものを用意した。零れ種からあちらこちらに発芽しているが、
適当なサイズのものを選ばなくてはならない。植木鉢がSさんの自転車の篭に収まらなくてはならないから。
新芽は手もみ茶に、おひたしに、天ぷらに……、すくすく育ちますように。
■学生の習作を発表する場がほしい
子ども教育学科には、ほぼ隔月発行の『ミンミン新聞』があるが、学生の制作物が発表できるページの余裕はない。
絵本でも数冊、ペーパーカッティング「シンメトリーデザイン」や連続模様制作でもかなりの秀作があった。講評して返却するのだが
何とも惜しい。作品を並べて見せるが、他のクラスの学生には鑑賞させられず残念だ。創作する一方、良い作品を見ることも大事だ。
一部修整、補作し学生に”作品集”として配布することにした。学生は色んな紙で(薄い色など)自由に制作するから、
版下にするには墨画線に置き換えなくてはならない。一昨年も作ったが、この作業は時間がかかりめんどうくさい。
「素晴らしい作品を作った」……学生に自信をもって貰いたい。園や学校の現場でも制作のヒントに資料としてきっと役に立つだろう。
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
ホップを植える! 実を何に使おうか……早すぎる夢想……
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (6月1日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
アトリエ周辺の田圃は田植えが終わり人影なし。水面を横切る鳥の影。静寂の中に時おり鳥の声。「ホーキョ」「ホーキョト」……
下手だったウグイスも「ホーホケキョ」。すっかりうまくなった。
東北の被災地では作付けを諦めた水田が多いという。緑の苗が黄金の稲穂に変わるまで、ずーっと惨い災厄が頭から
離れないだろう。
絵を描いていても、テキストを作っていても、お話を書いていても、胸は重苦しく、気が晴れない。集中力乏しく苛立ちを覚える。
創作はいつだって厳しいものであるが、これほどキツイとは……。
気分転換のテニスも楽しめない。”逃避”だからであろう。大分前のことだが、サッポロビールが運営していたクラブでプレーした
ことがある。このコート脇のフェンスで、さすがビール会社だ、ホップを育てていた。ホップが高さ10メートル以上も薄緑のカーテンを
作っていた。今ゴーヤなど壁面緑化が話題になっているが、あの、コートを覆い隠すようなホップは見事だった。
少し失敬してきて、ホップのリースをつくったこともあったっけ。
そして、とうとうホップの苗を手に入れた。野生のものではないが、自然に還したいと、竹やドクダミやスギナの生い茂る土地を耕し
腐葉土を敷き詰め苗床を作った。トレリスを立て水を遣る。
しっかり根付きますように!少しだけ、ほんの少しだけでも実をつけますように。
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
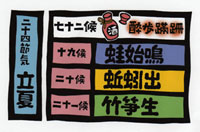 |
5月6日は立夏 (5月21日は小満) ・十九候 (5月 6日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
■アトリエのフェンス倒壊す
筆を取る、板に向かう気力興らず。胸は塞がったままだ。それでもアトリエに入れば……と、久しぶりの鳩山詣で。だが、
それどころではなかった。地震か強風か、フェンスが倒れていた。フェンスと言っても三寸の角材を組み合わせた頑丈なものだ。
それが、道路に沿って横倒し!滅多に人が通る道ではなく事故に繋がらなかったのは幸いだった。連休中だが、設計図をひき
工務店を呼んで交渉した。
■今年はミツバチ大丈夫…………か。
昨年は全国的にミツバチの姿が消え、何が原因かもわからず問題になった。わが鳩山の庭でも明らかにその数が減少した。
それまでは乱舞する大群、母屋の壁の間にも巣を作り蜜をたらすミツバチだったのに。今年は大丈夫……かもしれない。
花の間を忙しく飛び交っている。カマツカの小さな花から、アケビやムべの花、少し前までは、ミツマタ、杏、サンシュユ、
プラムなど、花の季節をミツバチは我が者顔だ。



・百花繚乱……ミツバチの季節 ・アケビの花(五つ葉) ・カマツカの花


・ムべの花 花弁に見えるのはガク。 ・たった一輪咲いたリンゴの花(ヤーノシュの絵本『おばけりんご』の一ページを彷彿)
乳白色で内部には紅の線
| 4月のアトリエだよりエだより |
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
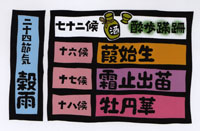 |
4月20日は穀雨 (立夏は5月6日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (5月1日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
新学期が始まった。『実践遊び学』3クラス。『絵画造形表現活動・Ⅰ』3クラス。昨年よりパワーアップした授業展開をしたい。
具体的にはカリキュラムの調整以外に、『実践遊び学』では殆ど毎回、”おまけ”と称してごく簡単にでき、子どもをアッと言わせる
楽しい造形手遊びを紹介していく。そして『絵画造形表現活動』では、”帽子百貨店”と題したクラフト製作を、今まで十数点だった
ものを、今年は創作5点追加、学生にはかなりハードな作業(時間がタイト・集中力勝負)となる。
月曜日『実践遊び学』第一回は、鏡面紙を用いたシンメトリー図形遊び(製作・発見)および万華鏡考察。製作だった。この時の
”おまけ”は、「紙一枚(A4大)左手のひらに穴を開ける」法………というものであった。紙をクルクルまるめ円筒形にする。これを
用いて掌に穴を開けるには、さてさてどうする?(授業では万華鏡作りに用いる紙筒でやらせた)
「あっ、あいた」「穴が開いた!」「向こうが見える!なに、これ!」「わあー!」教室がどよめいた。
「穴があかない」「えー、穴、見えない!」何人かは、始めうまくいかず、とまどっていたが、学性同士教えあって全員、手に穴が
開いたことを”確認”した。一体、どうやって手のひらに穴を開けたのでしょうか?
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
杏の花が咲いた。明るい青色の空のもとでミツバチを誘っている。ミツマタ、サンシュユの黄色
土佐ミズキの淡い黄、レンギョウも。やはり杏がいい。杏の白を際立たせるかのように、空には雲がない。
遠慮してくれているかのようだ。杏は梅の花をふっくら大きくした感じ。清らか。
穏やかな日和、春景色。平安なれど、このところの心中、苛立ったまま。
オニグルミ、カマツカ、ブナ……まだまだ、芽は堅い。ときおり吹き来る(荒れる)冷たい風が木々を揺らしている。
ケキョ…ケキョ… ウグイスの囀りトレーニングも始まった。 さあ、我も始動!!!
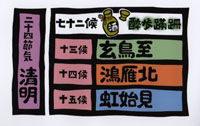 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
| 3月のアトリエだより |
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
板絵 『おやすみの前に』 完成!
 |
3月21日は春分 (4月5日は清明) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
天変地異、大震災。胸塞がる。
4月4日開催の現童春季展出品の作仕上げ作業中だった。言葉を失う。筆は止まる。
父と母と子の関係を描いた 『おやすみ前に』 は、もっとも心やすまる刻の物語。でも、
むごい光景を映像を見、今や表現の気力失せる。
何としても描かねば、表現せねば……。無力感。
己が抱えた悩みに埋もれているうちに世界は大変なことに。
厳しい便りもいただいた。その方は体の不調にもめげず”感謝の念”を
語っておられた。なんという心の広さ、包み込む温かさを感じ、
自分の甘えを情けなく思った。。厳しさ、苦しみの深さは人それぞれでも、みんな、みんな大変なんだ
……当たり前の事……、自戒自省。
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
過去はなし。未来も定めなし。あるは今のみ。脚下照顧。拘りから離れられれば活路もあろうというもの。が、その拘り
だらけで(雑事が人生ではなかったのに。いや人生は雑事の中にあるのかも)忙殺される日々。このところ寒暖の差が大きい。
それでも北風が止むと春を思わせる日差しが。春三月。怠惰の我が身に、鞭をくれねば!
■二十四節気<雨水> 七十二候(四候.五候.六候)
 |
2月19日は雨水 (啓蟄 3月6日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
激しかった夜来の雨嘘のように上がるもわが心、暗闇にあり。仕事に逃げ込む不埒な心を嗤い、
見張りの「もう一人の自分」が攻め立てる。手は止まり作業も捗らず。我慢……しかない。
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候
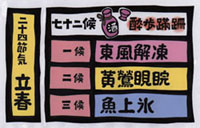 |
●2月4日は立春 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
鳩山の枯野。寒空、一切の葉を落とした木々の枝がくっきり。常緑樹も萎れ勢いは無い。ロウバイの香しさが消え、梅がプチッと
はじけ始めていた。幾分か柔らかになった光の中に春の訪れを感ずる。が、ぼくの心は今や冬真っ只中。芳しくないこと、
身に降りかかる哀しいこと……、暗澹たる思いに沈み、浮き上がる気力もなし。制作空間に身を押し込めて自ら鞭打つしか、
癒しはあり得ない(かった)ことはぼくの人生経験上の結論なのだが……。それさえも……今は。
| 1月のアトリエだより |
■二十四節気 <大寒> 七十二候 (七十候.七十一候.七十二候)
 |
●1月20日は大寒 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■現代童画展出品作 (上野の森美術館)


■二十四節気 <小寒> 七十二候 (六十七候.六十八候.六十九候)
 |
●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
| 12月のアトリエだより |
MERRY CHRISTMAS


師走でなくとも、アタフタ……。安らぐ時なきまま歳が暮れようとしている。嗚呼………。
[日々新生・日々創造] を胸に抱き歩むも、我が羅針盤、現実路線に針路。頑な。
”静かな創作の日々”は夢か!今年、描いた板絵の少なさよ……情けない。
自省自戒の念で多分また大晦日の深酒……。進歩ないなあ。
■二十四節気 <冬至> 七十二候 (六十四候.六十五候.六十六候)
 |
12月22日は冬至 (1月6日は小寒) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■『紋型切り紙』の研究 『紋型』から『切り紙』へ
江戸時代は寺子屋でも教えていた紋切り型あそび。明治、大正、昭和……小学校の図工教科書で
どう取り上げられて来たかを調べている。(昭和30~60年代は盛んだった)平成の教科書ではごく小さく載っている程度。
姿が消えたも同然だ。
紙を折りはさみで切る。開くときの驚き、ワクワクする遊びだ。壁面装飾、カード、モビールにと使い道は多く、折り方の
工夫やカットの技術、ポンチの活用など奥が深い。1回折から4回折まで、サンプル作品を100は作ったか。
今回は1、2、3、4回折りまで学生に試させたが、蛇腹折り(屏風折り)は連続模様として別に時間を設け制作させる。
時間があれば切り絵にも挑戦させたい。例としてデンマークの童話作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンの切り絵でも
見せようか。学生に思う存分自由に紙を切らせてみたい。
・創作切り紙
中央の「二つの馬蹄に挟まれた四葉のクローバー」は、明治39年1月1日小山内薫がドイツから
森林太郎に宛てた年賀状にあった図案をもとにデザインした。
上下の作品は、切り紙「一回折り」で制作
■二十四節気 <大雪> 七十二候 (六十一候.六十二候.六十三候)
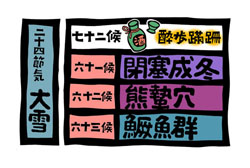 |
12月7日は大雪 (22日は冬至) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
| 11月のアトリエだより |
■二十四節気 <小雪>、 七十二候 (五十八候.五十九候.六十候)
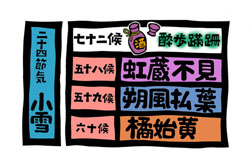 |
11月22日は小雪 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
冷たい雨。キャンパスの舗道にイチョウの葉が張り付いている。踏みつけられ潰れた銀杏も。研究室、先生の在室ランプも
殆ど消えた9時半、大学を出る。寒い。ノートパソコンと大量の制作教材の入ったバッグを肩に、傘を風に飛ばされないように
傾げ持ち駐車場まで歩いていく。
自分の制作が出来ない日々を送っている。このところ学生に見せる教材サンプル作りに明け暮れている。が、これはこれで面白い。
「PEEK・A・BOO(いないないばー)」カードのアイディアを考え、試作するのだが、1枚の紙の可能性追求でもあり、奥が深い。
基本形は裏、表の変化。回転(たとえば、こぶた→たぬき→きつね→ねこ)。めくり。折りなど。 今回は”めくり”に挑戦させる。
「カーテンの向こうは?」カーテンを開けるとどうなるか……。
この制作と遊びは、想像力を鍛えることになる。学生は日頃、「正しい答え」を求めて学習する。自らの考えを述べたり、表現したり
する機会は少ない。造形表現活動を通じて、答えのない世界もあることを、その大事なことを解ってもらう……それも狙いだ。
(NOV.22)
■ 現代童画選抜展 (地方巡回)作品戻る

現代童画展選抜展は銀座アートホールで開催後、四国、関西を巡った。
今年の出品作は「どんぐり嵐」 鳩山のアトリエに埋めたクヌギのドングリ(近くの公民館の庭で拾った)はあちこちで
芽を出し、今漸く腰の丈。
昔からあったマテバシイは剪定の失敗からか元気がない。毎年降るようにドングリを落とすが今年は地面にパラパラ
見かけるくらい。マテバシイのドングリでドングリ煎餅を焼いたことがあるが香ばしくてうまかった。クヌギのドングリは
食べられないけれど、ヤジロウベイやコマが作れる。なんといってもあの形が良い。
我がクヌギがドングリをつけるのは、ずうっとずうっと先のことだろう。下草を狩り、水を遣り幼木を育てる……”夢見”が楽しい。
■二十四節気 <立冬> 七十二候 (五十五候.五十六候.五十七候)
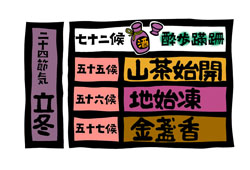 |
11月7日は立冬 ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■「紋型切り紙」を見直そう。けっして”紋切り型”のつまらぬ造形ではない
仕事場は紙くずの山。このところ「紋型切り紙」の原稿書きで色紙を折っては切る、折っては切る……。1回折りから5回折まで、
様々なモチーフをデザインしている。「紋型切り紙」は江戸時代は寺子屋でも教えていた。紋所を染めたり、商売でも子どもの遊び
でも紋切り型はポピュラーなものであった。明治大正、そして昭和の20年頃までは図工(当時は手工)の教科書にも載っていた。
”自由な制作”が教科書の編集方針に変わるとともに、紋型切り紙は姿を消した。昔からある紋や、定番の梅や桜や桃の花を切っ
ている限りでは”紋切り型”の名の如く、創造性、独創性は無いとの謗りは免れないだろう。が、日常性(紙一枚、ハサミがあれば
出来る)伝統の美しさ(継承)、幾何学性、手技の練磨(微細な運動----右脳の活性化)、コミュニケーション能力(教えあう母と子、
友達)など、得るものは多く、肝心の創造性に於いても、自由な造形をテーマにすれば、幾らでも独創的な、たった一つだけの作
品が出来るわけで、子どもに是非ともやってもらいたい造形表現の一つといえる。
1枚の紙でどれだけ遊べる?表現できるか? ……ゲーム機世代の子ども達を導くのは、大人の責任だ。素材の可能性を
最大限に引き出せるか否かは、想像力と創造力それに感受性次第。生きることはそれらを磨くことと考える。
■第36回現代童画展(上野の森美術館)
今年と来年は東京都美術館改修工事のため、会場が上野の森美術館となります。お間違えにならないように。
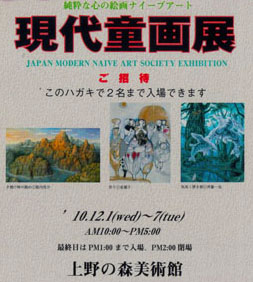 詳細は「展覧会」のページをご覧下さい
詳細は「展覧会」のページをご覧下さい■ 『相生祭』にて講演します -----きみはやだもんを しってる?-----
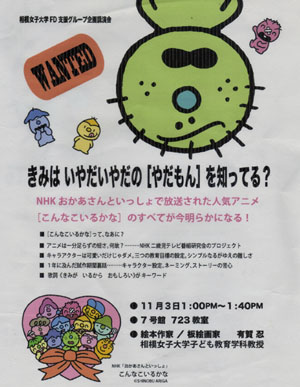

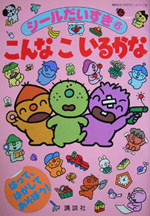


| 10月のアトリエだより |
■現代童画展(上野の森美術館)
出品作の板絵が完成した。東京都美術館が改修工事のため、《現代童画展》は今年と来年、上野の森美術館で開催される。
■二十四節気 <霜降> 七十二候 (五十二候.五十三候.五十四候)
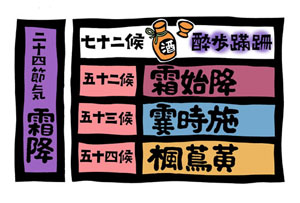 |
霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
■講演会準備に資料整理、パワーポイントつくり……時間が足りない
11月3日は《相生祭》。FDグループ主催の講演会で、ぼくは『きみは、やだもんを しってる?』と題して話す。
制作の裏側のすべてをラフ(下書き原画)などを展示しての講演。『こんなこいるかな』は、1986年から十数年にわたり放送され、
絵本も数多く出版された。現役の学生も、当時母親だった年齢層の方も聞きに来ていただけたらと思う。
ただ“可愛い”だけではないキャラクターの制作意図、NHKの教育目標、制作上悩んだ点、、そして何故今、”こんなこ”なのか?
など色々話したいことは多い。
■仕事の合間、息抜きは大好きな「工作」


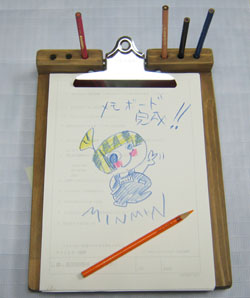

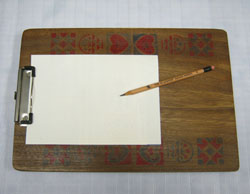

板絵の完成が近づいた。筆遣いが細かくなり遅くなった。今日は終日雨。時おり雨脚が激しくなる。息抜きに外にも出られない。
そこで”工作”。"図工少年"だったぼくは絵描きか大工さんになりたかった。その大工仕事を楽しむ。あり合わせの材料を使って
メモボードを作った。今までいくつも作っており、渋谷にも自宅にも大学の美術室や研究室にも置いてある。が、又一つ拵えた。
いいアイディアが浮かんだら即書き付ける……為だが、肝心のアイディアがそうそう浮かんでこない。
もっぱら忘れ物対策に使われている。情けないなあ。
ステイン塗料を刷り込んで完成。早速、完成間近の板絵を眺めつつ、作品タイトルを練る。メモボードの重量感が心地よい。
これで、「この絵には、これしかない」と思えるようなタイトルが浮かべば万々歳だが……。
(Oct.9)
■ハローウインをモチーフに切り紙トレーニング……学生の積極性、応用力を感じた
絵画造形表現活動応用の授業。保育、教育現場で図画工作、クラフトに使う、使える紙の説明とサンプル帳を作らせる。ラシャ紙、
エンボス紙、カラーケント紙、ミューズコットン紙、マーメード紙、レザック紙、上質紙、工作紙、波ダンボール紙、LKボード、
でんぐり紙等二十数種類切ったり破いたり描いたり、紙の特性を考えながら台紙に貼り付けていく。
…………紙の基礎知識も。「紙って、そもそも何?パピルスは”紙”ではない」「紙が現れる前は何に書いていたの?」
「紙のサイズにA版、B版があるのは何故?」「紙の裏表の見分け方」「ティッシュペーパーが水に流せないわけ」
「コート紙は”化粧”しているって本当?「奉書、麻紙、杉皮紙など和紙について」「紙の原料は?」「牛乳パックは何から
出来ている?」等等。
それだけではつまらないので、実習はハローウイン飾り作り。 紙を蛇腹折にして、ハローウインの”主役達”、パンプキン
{ジャックオーランタン}、コウモリ、魔法使い、ゴースト、ネコなどを切っていく。何体も連なるかぼちゃやコウモリに学生は
大喜び。型紙を渡しての制作だが、各自自由に切り出すから頼もしい。提供した魔法使いの型紙はお婆さん姿だが、ある学生は
「紋形四ツ折り」を使って5人の魔法使いのサークルを作った。それもお婆さんではなく可愛らしい少女のサークルだ。応用力の
芽生えが嬉しい。夢中になっての制作は必ずや身になるであろう。
■二十四節気 <寒露> 七十二候 (四十九候. 五十候. 五十一候)
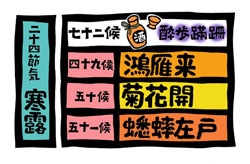 |
10月8日は寒露 (10月24日霜降) ・四十九候 (10月8日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月13日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月18日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
現代童画展出品作制作のため鳩山詣が続いている。鳩山では終日描くのみ。外に出て萩の花を愛でるゆとりも無いのが
残念である。白萩、宮城野萩、だるま萩……花のトンネル?………が出来ているはずであった。ところが、雑草刈を依頼して
おいたシルバーさんが、萩の木も殆ど刈り取ってしまっていた。かろうじて茶の木の間から伸びた萩が花を風に揺らせている。
萩、薄(ススキ)、桔梗、撫子、女郎花(オミナエシ)、葛、藤袴 秋の七草……このうち、野で桔梗は見かけない。絶滅危惧種と聞く。
絵は完成が見えてきた。絵柄は板絵の性格上(彫が施されているため)大きな変更は出来ない。色だ。色でもって情感の表現をするのだが、
塗り重ねによって絵の表情はがらっと変わる。好ましい、望ましい心象風景が現れるまでひたすら塗り続ける。描く行為はイメージが画面に
現出するまで停まらない。
| 9月のアトリエだより |
■秋の収穫を喜ぶ





2,3日前は30度。今日は十数度の涼しさ。朝からアトリエに籠り板絵を制作する。今年は猛暑のせいかハチが増え
飛び交っている。スズメバチにアシナガバチ。多くて恐いほどだ。アトリエにも舞い込んでくる。ラケット状の電池式蚊取り器で
退治するのだが、空振りすると大変。ハチは攻撃されたと思い攻めてくる。今日もそうだった。一匹見事命中と思ったら、背後から
耳をかすめるように別の一匹が飛んできた。二匹部屋に入っていたのに気づかなかったのだ。危ない危ない!
先日地塗りを終えいよいよ”描ける”。好ましい状態になるまで幾度と無く色を塗り重ねる。ぼくの唯一の贅沢か、絵の具のチューブが
いくつも空になって行く。下層に沈んでいく色は決して無駄ではない。重層的に”我が望みの色”をかもし出してくれるのだから。
この”色遊び”は小学時代の絵の時間、ワクワクして描いた、あの楽しさと同じだ。仕上げるのが目的ではなくそのプロセスが
幸せな心持にしてくれる。この時のぼくは多分、最高に生き生きしていると思う。
「気、澄み渡る……」秋晴れ。台風が来ているそうだが、鳩山は嘘のように上天気。ヒガンバナの群生、原色の赤が目に痛いほどだ。
自分では為し得ずシルバーさんに頼んで刈り取ってってもらった野に出れば、木の葉はも早散り始めていた。栗の実も鈴なりだ。少しだけ
叩き落して集める。石造りの釜で新聞紙を燃やして焼き栗。3つぶほどだが、初物の熱々を味わう。これも我が贅沢。
胡桃も気になっていた。昨年は収穫時期を逸してしまった。今年こそはと、来るたびに注意していた。いつ、もいで良いのやら……。
木の根元に一粒落ちていた。果肉からクルミが露出している。今が収穫時と判断。収穫といっても6粒のみだけど。クルミは
仲良く二粒ずつ寄り添うように成っている。上の写真(中央)は果肉を半分取り除いたところ。胡桃の殻を一粒一粒取り出すのは
大変だ。この後、割る工程があるし……。食べるのは簡単だが……恵みには感謝しよう。
(Sep.25)
■二十四節気 <秋分> 七十二候 (四十六候、四十七候、四十八候)
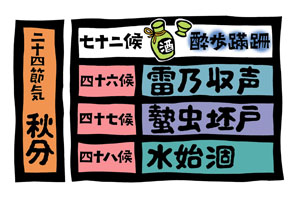 |
秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
HPの更新もままならず。慌しく活動の日々。落ち着いて制作なんて夢のまた夢。心やすまる時なし。情けない。
渋谷の仕事場→テニスコート(午前中二時間)→大学(レジュメ印刷)→自宅(今、HP更新)→鳩山アトリエへ。
創作に割り振る時間はまったくなし。嘆かわしい!明日は12時間はアトリエに籠り絵を描く決意。
創作といえば、紙皿で天使を作った。ペーパープレートクラフト、。そのゲージも学生の数分だけ用意(レジュメは豪華カラー版)したから
時間が足りなくなるわけだ。真っ白い紙皿の天使はシンプルで清らかだ。学生はきっと喜んで制作すると思う。手を使う。作って作って……
学生は体験を通じて何かを学ぶだろう。
■二十四節気 <白露> 七十二候 (四十三候、四十四候、四十五候)
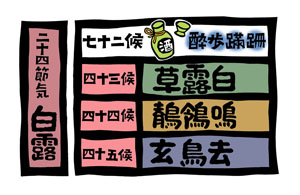 |
9月8日は白露 9月23日は秋分 ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (9月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
第三回『子ども教育学会』出席後、鳩山へ。板絵制作に集中する。このところ頻繁にアトリエを訪れるが、
それでも進行遅く焦る。眠る時間以外は彫っている。なんとか地塗りまで済ませた。この後も、塗っては彫る作業が続く。
板絵のしんどさは、終わりの時間が分からないところだ。今やっと”キャンバス”状態。やっと”描き”に入れる。”やっと……”の
ところまで漕ぎ付けたのに、アトリエを出なくてはならない。大学の仕事が待っている。
秋学期まで一週間。すべての時間をその準備のために使うが、それでも寸暇(あるだろうか)を見つけてアトリエに
向かうかもしれない。頭の中に作品の”骨格”がデーンと存在し、板絵作業の続行を促している。
栗の実が落ち始めた。古い木は元気ないが(2本は切り倒した)10年ほど前植えた3本は今年も”豊作”だ。 残念だが、
栗拾い(実際には口を開けたイガを叩き落す)する暇さえない。少しだけでも拾おうか……。
クルミは繁る葉の間から2個見えていたが、かき分けてみると5個!暗緑色の7~8センチ大の堅いボールが枝に
突き刺さるように付いている。昨年は収穫する前に落果したのか、動物に食べられたのか姿が消えてしまった。
この次鳩山へ来たときに実をもごう。クルミはいつ収穫してよいのかタイミングが分からない。表面の緑が段々黒ずんでいくが、熟れる
果実と違い大きな変化が無いから。いつもは袋で買うクルミ(カリフォルニア ウオルナッツ)だが、木に実るその姿は愛おしい。
割って「ウイスキーの友」に……、ゆとりのない日々の生活、夢想がしばしの慰めだ。
■《防災の日》はスズメバチ退治!





アトリエのシンボルツリー、チャンチンの老木(香椿)が枯れた。朽ち果てる寸前の幹にスズメバチが巣を作った。アカゲラが開けた穴が
日ごとに大きくなっていく。獰猛なスズメバチと、すぐ分かったがタカをくくっていた。いや、恐くて近づけなかったのだ。数百匹と群がる
スズメバチの大群、見るに見かねて役場に駆除を頼んだ。
消防署の車に、救急車。総勢8名。防護服に着替えた隊員2名。3名はバドミントン(?)のラケットを持って構える。ハシゴを架け
ほこらに薬品をぶち込む。窒息死させるのだという。そのあとバールで穴を大きくし巣を破壊、取り出した。何と6層も!
作業員は「これは大きいほうだ。巣に戻ってくるハチがいるから、暫くは近づかないように」。救護員は「今までに刺されたことは
ありますか?二度目なら死に至ります(ショック死)」と言い残し、引き揚げていった。スズメバチは恐い。
刺されて命を落としたというニュースも耳にする。 ふー、これで一安心だ。役場の方々、消防隊員に感謝感謝。
アトリエに入っても気になって仕方ない。デッキに出て、壊した巣の後を双眼鏡で見る。隊員が言った通りだ。スズメバチがまた群がって
きている。巣がなくなったことを諦めきれないのか、穴から出たり入ったり慌しい。大丈夫だろうか?又巣を作らなければ良いが。
板絵制作に入ったのは夕方。有線放送の『元気に遊んでいる良い子の皆さん、暗くならないうちに帰りましょう』が聞こえてきた。
「カラスウリの花が開くのを見たいなあ……」、「ビール&読書もいいなあ……」 ダメダメ!仕事仕事!、集中せねば……誘惑に蓋を
して……このところの低下した気力にカツを入れるべく水風呂、ねじり鉢巻! さあ、やるぞー!!!!
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■《愛媛の酒を楽しむ会》
京王プラザホテルで開催された蔵元18社出展の《愛媛の酒を楽しむ会》。畏友の杜氏、宇都宮君もブースを構えると言うので
出かけた。「千鳥」とならんで「月の滴」も展示されていた。「月の滴」はぼくの板絵(同名のタイトル)をラベルに用いた大吟醸酒だ。
会場はほぼ満員の盛況。利き酒しながら酒造主や日本酒党との歓談を楽しんだ。案内状通りの”ビュッフェディナー”だったが、
ぼくはテーブルから動かず、じゃこ天をかじったのみ。客の応対に忙しい宇都宮君とは一言二言話したのみ。握手して会場を後にした。
9月には大学。秋学期が始まる。その準備。板絵制作もある。造形遊び本の原稿も。明日は鳩山だ。アトリエの掃除も終わらせなくては
ならない。暑さで気力が萎えている。巻き返さねば!
■二十四節気 <処暑> 七十二候 (四十候、四十一候、四十二候)
 |
8月23日は処暑 (9月8日白露) ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
暦の上では処暑なれども、炎暑衰える気配なし。鳩山も暑い。板絵制作準備に訪れたが、暑さで退散する羽目に。
それでも掃除ぐらいはと収納庫をあけて溜息!思っていた以上にパネルがカビだらけ。パネルのみならずシナベニア板
すべてに白や黒のかび。炎天に日干しをする。幾度もパネルやベニア板を運ぶ。布で拭き落としながらの作業に体中の水分が
なくなるほどの
汗を流した。
胸が苦しい。深呼吸すると胸の上が板で覆われているような感じだ。カビを相当吸い込んだのだろう。なぜマスクを着け
なかった……、後悔しても後の祭り。いつもカビには悩まされているが、今回は大事だった。肺の中にカビ菌が育っている
のでは……ああ、胸が気持ち悪い!水道にホースを繋いで肺を隅々まで洗いたいなあ。

パネルを道路にならべて、”熱消毒”。枚数100枚ほどか、裏返してカビを殺す。湿気対策の名案なく、毎年板の天日干しに
時間を取られている。進歩なし!創作欲が削がれるし時間の無駄だ。東京への帰路も、今日一日の働きの虚しさが頭にあり
情けない思いでハンドルを握っていた。
我がアトリエが建つのは坂の下、更に半地下状態で湿気るのは仕方ないことだが、我慢我慢!贅沢を言うのはよそう。
”静かな小鳥の楽園”だ。「小鳥の帰る島」ではないか。
「小鳥の帰る島」は三十数年前現代童画展に出品した作品名
■交通渋滞覚悟で鳩山へ。

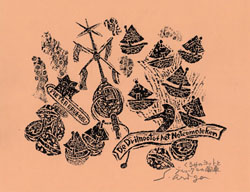
・「胡桃のヨットとブリューゲルの風車」 版画
講演会では板絵作品も何点か提示する。『胡桃のヨットとブリューゲルの風車』もその一つ。
ネーテルラントの画家ブリューゲルは1560年、《子どもの遊技》に91種類もの子どもの遊びを描いた。ブランコや、水鉄砲、竹馬など
分かりやすい遊びから、樽揺らし(シーソー)、煉瓦積み遊び、指骨あそび、目隠し鬼のスリッパ取り、洗礼ごっこ、お粥のかき混ぜっ
ごっこなど、フランドル地方の風俗、習慣色鮮明なもまで。
その中につくる遊びはただ一つ。「胡桃の風車」だけ。ぼくは絵を見て実際に作ってみた。それを板絵に描いたのが『胡桃のヨットと
ブリューゲルの風車』だ。10号Sサイズの小さなものだが、横浜の講演会で、胡桃の玩具ともども見せたいと思う。
炎天下、テニス3ゲームの疲れた体で、交通渋滞を恐れての運転、炎暑!気温が高いというより、この蒸し暑さ!鳩山のアトリエに
着いても、頭がボーとして他の仕事できず。ただ作品を積み込み帰途へ。
楽しみと言えば、庭で工事中の「井戸」の進行状況を確かめられたこと。誰も引き取り手が無いような巨大な砂岩の円柱形井戸枠を
破格の安値で購入。それを据え付ける土台工事を頼んであったのだ。井戸枠を何に使うか?地面を深く掘ろうとも、井戸が湧く保障もなし、
水をくみ上げる装置もないし。手押しポンプ設置も考えたが、これは井戸からの配管が必要で、大工事になる。そこで考えた。
名案浮かべり!!!!!この井戸枠の使途は?工事屋さんもぼくの描いた設計図を見て首をかしげた。構造を口で説明し、
わかってもらう。設置場所は庭の斜面だから、構造を描いた図面が理解できなかったのだろう。
< “名案”は工事終了後、この欄で答えを“白状” > ヒント………枯れ葉を入れる=○○○作り
工事は7割がた出来ていた。構造体はほぼ完成。煉瓦も積まれ後は配管と、井戸枠の運び込みだ。
あちこちに蝉のぬけがら。ミンミンゼミの鳴き声が蜩に変わった。アトリエのシンボルツリー《チャンチン》が、枯れた。アカゲラだろうか、
突いた穴が二つ寂しそう。主は見えず、チャンチンは今、アシナガバチの城となっている。ヤマカガシも手入れの無い庭で我がもの顔だ。
仕方ないことだが……。
(Aug.15)
■板絵運搬、準備を考慮しホテルの予約を入れる
18日の講演会会場はは横浜のホテル。当日車で行くつもりだったが、板絵、絵本、レジュメ(かなりの重量)の運び込みなどを
考え、前日宿泊することにした。『表現する喜び』と題し2時間の講演。一部<板絵の仕事>二部<絵本・雑誌の仕事>。いま資料
整理に忙しい。秋の現代童画展出品作(上野の森美術館)にも取り掛からねばならない。その前に、造形遊びの
指導本の原稿も。明日は大学へ。
風邪は何とか治まりそうだ。さあ、またフルスロットルで走らねば……。暑さにめげてはいられない!
(Aug.11)
■夏風邪!熱がある。仕事、スローペースにダウン!
疲れが溜まっていたのだろう、風を引く。頭痛が続き仕事ストップ!それでも、講演会の準備はしなくてはならない。
パワーポイントに板絵作品や絵本を取り込む作業。レジュメが先だが、今、考える力は無い。
講演会には板絵も持参して行こうと思う。その作品の決定は迷ったが、『いこい』『たたかい』(F50 1981)とする。
20年も前の作品だ。100人レベルの会場での可視性を考えると、”大柄”が良いだろうと。近作の小品も2~3点加える予定。
■二十四節気 <立秋> 七十二候 (三十七候、三十八候、三十九候)
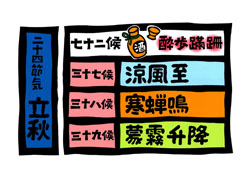 |
立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
■鳩山アトリエは伸び放題の木々に隠れる
雑草生え放題、手入れする暇なく荒れ果てた鳩山のアトリエの庭。庭と言うより原野かジャングルか。それでも、植えまくった
果樹、花木が育っている。”植えまくった”というのは、畑にない樹木の苗木を見つけると、手当たり次第手に入れ植えていった
ということ。柿、リンゴ、スモモ、キウイなど果樹のみならず、ユズリハ、クロモジ、リンデン(西洋菩提樹)、イタリアンパイン、メープル、
それに後先考えずに(大木になったらどうしよう)ブナやトチに、ヒノキやケヤキまで植えた。紅葉が好きだからモミジもハゼも。
この間は大島桜も植えた。桜は昔からある山桜、それに、染井吉野が昨年から咲き出した。大島桜の”ねらい”は花より葉っぱだ。
この葉で桜餅をつくろうという算段。二本植えた大島桜(知人が種から育てたものを移植した)が楽しみだ。
ナツメ、サルナシ、山葡萄は放っておいても育つが、心配はナナカマド。一本を枯らし、昨年植えた二本も危やしい。
ナナカマドの赤い実を小鳥にとの思いは今秋も叶いそうもない。
■夏風邪?鼻クシュンクシュン……
オープンキャンパスで張り切りすぎたのか(満員御礼、大盛況)、雨の中のテニス(サーブ打ち込み200球)が
ハードだったのか、はたまた熱中症か、鼻水が止まらない。夏は大好きで暑さにも強いぼくも、”35度”には閉口!
只今ギブアップ状態。それでも休めず動き回っております……。○○○○、暇なしか!
■クレヨンまるDVD <ハーブおばさんのスイカのパラソル>
『幼稚園』(小学館)9月号付録に「夏チャレンジDVD」がついている。アンパンマン、ドラえもん、お話、歌、水族館に行こう、
忍者修行など盛りだくさんの120分。その中に「クレヨンまる」も納められている。まだワルズーやミイラばあや、それにチェリーや
ふるもとくんなど友達が登場する前の、最初期の作品。「ハーブおばさんのスイカのパラソル」の再録。
ここ2~3年前から、幼児雑誌にDVD(その前はVHSビデオ)がつくことが多くなってきた。”お得感”はあるが、その分雑誌の
ページ数は減っている。本文が充実してこその雑誌だ。
毎号付く”本物付録”(表紙にもこの文言が載っている)も、手替え品替えのアイディア玩具ではあるが、創造性を育むような物は
少ない。雑誌の黄金期70~80年代の付録と比べると、見た目の豪華さとは裏腹に、<創意工夫>する心が育つとは思えないような
ものばかりだ。
キャラクターを付けた刺激的な玩具(多くはICやボタン電池を使っている)は子どもには魅力だろうが、その興味は長続きしない。
持っているだけのもの、あるいは遊び方を限定する玩具に想像性、創造性がないからだ。
■2010 オープンキャンパス・模擬授業・アリガクン参戦!
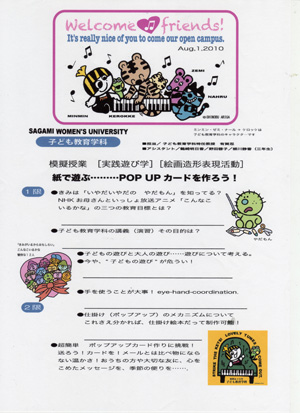
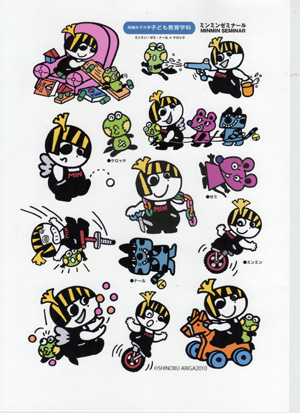
8月1日は相模女子大学のオープンキャンパス。真新しい建物、マーガレット本館5F2152教室でぼくは授業を行う。
昨年も一昨年も満員の盛況ぶり。補助机を出して対応した。当節の風潮として保護者の方々もお見えになる。ご父兄をも
納得させる講義でなくてはならず、頭をいためるところだ。(本来は制作を通じて自己表現し、体感が人間の底力を培っていくものだが)
今回はアシスタントの三年生が5名参加の強力体制だ。高校生諸君に「作る喜び、表現の素晴らしさ」を教えたい。
| 7月のアトリエだより |
■夏の法要は大変だ!寺は、今話題の植物園の傍らにあり
連日35度以上の「猛暑日」。先日は文京区にある寺で法要がありでかけた。本堂での僧侶の読経の後、炎熱の墓へ。
参会者はみな汗を滴らせている。お坊さんも配慮して短めの念仏。くらくらして倒れそうな暑さ、代わる代わる墓に水を
かけたが、かけた途端から乾いていく。
墓石には、○○家ではなく、倶会(旧字)一拠(旧字)と彫られていた。
寺から程近くに東京大学附属小石川植物園がある。いま、世界最大の花ショクダイオオコンニャクが開花し、大賑わいとの
報道。一万人以上が訪れ入園券の販売をストップしたとも。目と鼻の距離まで来ており、見ていこうか迷ったが、この暑さに
退散。 それにしても集まった10000人……。話題性……、本当に前々からこの植物に興味を持っていた人はどれくらい
いたんだろう? いろいろ考えてしまう。
■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
暑中お見舞い申し上げます。 23日は大暑! ”文字通り”を越していますよね。でも、
暦では大暑の次は立秋…………、”りっしゅう”の語感はいいねえ。暑さに負けませぬように、ご自愛専一に。
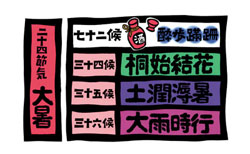 |
7月23日は大暑 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
猛暑日!夏が好き、熱さには強かったぼくも流石に閉口!先週まで頑張っていた”金曜テニス”も断念する。行かれないことも
ないが、コートに誰も集まらないだろうし。明日は法事がある、黒服の準備をする。汗だくだ。
HPの更新もできぬまま、8月1日のオープンキャンパスの用意、18日の講演会の準備に明け暮れている。講演会は長時間だから、
パワーポイントも活用する。そのためのデータ取り込みに大わらわ。
演題は『表現する喜び』一部は<板絵・版画……三つ子の魂、何とやら>で「幼少期の先生との出会い、環境、素材について」から現在に至る
表現人生を話す。 二部は<絵本の現場から>と題して、まず 「こんなこいるかな」誕生エピソードを。NHK2歳児テレビ番組研究会の教育目標などを紹介しつつ話す。これはぼくの基本的考え方、すなわち「色んな個性、それぞれを認め、一人ひとりを伸ばす」と、思いは一緒だから。
研修会は全国から集まる図工美術専門の先生方だから、絵本の様々な作法、制作技法も。更には小学校の先生方が受け持たれる子どもが、どのような環境に置かれて育ったのか、「月刊幼児雑誌の変遷」から見る試みも。30年間の幼児雑誌の本文はもちろん、殊に付録に着目。付録は
おもちゃだから、子どもに一番身近なもの。その変わり様から様々なことが見えてくる。大量の雑誌や付録の実物を提示しながら”驚くべき実体”を
知ってもらおうと。
大学の授業も大詰め。セメスター制は???だ。半年15回の講義(演習)では物足りない。いきおい詰め込むことになるが、学生が深く考え、自主的に制作するまでには至らない。学生は頑張ってついては来ているが、「これでもか、これでもか」と言うくらいやらねば力にならないと考えるぼくには
不満が募るばかりだ。”思いっきり””徹底的”にやりたいなあ……、学生には学ぶ時間が足りなすぎる。嗚呼。
■おでかけクイズ絵本『グー・チョキ・パーのいじわる魔女を追いかけろ』表紙初校あがる
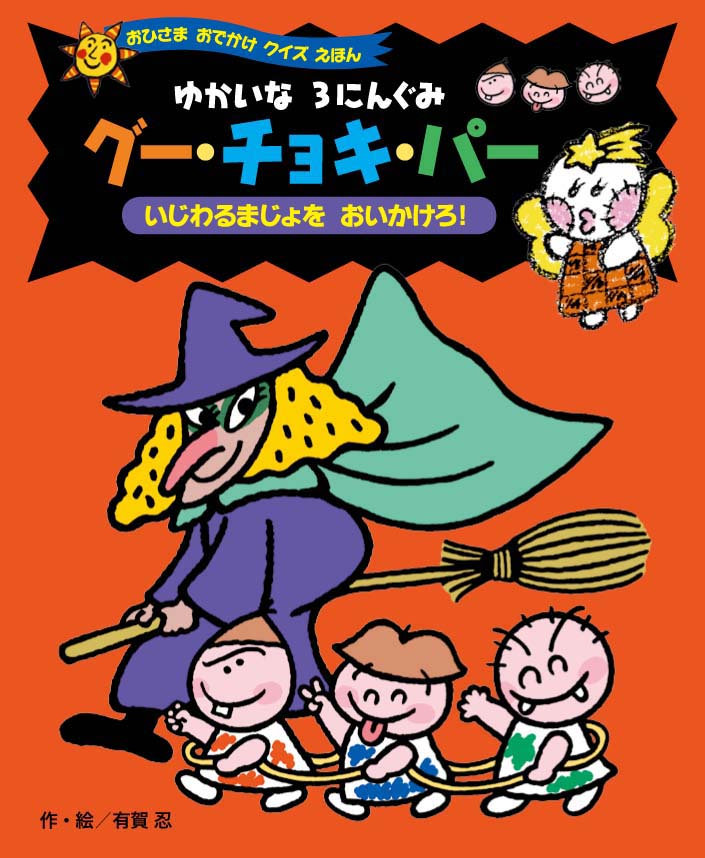
『グー・チョキ・パー』はお話とクイズ満載の絵本。<おまけクイズ>のボリュームもたっぷり。子どもを
長い時間楽しませたい。何度も絵本をめくって、隠されているものを探す楽しみも。
グー・チョキ・パーは腕白三人組。描いた絵から可愛らしい女の子が飛び出してくる。名前は『おやつちゃん』。
いじわる魔女『ズルーイ』との知恵比べ!乞うご期待!
(Jul.15)
■二十四節気 <小暑> 七十二候 (三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日 は小暑 (7月23日は大暑) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月18日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
現代童画選抜展終わる。今年は会場に行かれず仕舞い。出品作『どんぐり嵐』はこの後、坂出市民美術館展、神戸展で
展観される。お近くの方はご高覧を。
(Jul,5)
| 6月のアトリエだより |
■現代童画会選抜展が開催されます
「現童選抜展2010」開催。6月28日(月)~7月4日(日)
銀座アートホール
詳しくは展覧会のページをご覧下さい。
■古いスケッチブックが大量に出てきた 厚手の粗紙
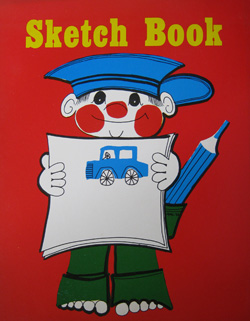
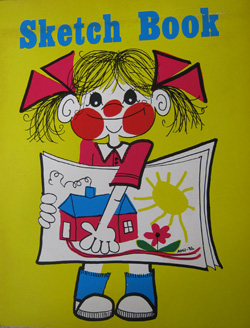
・粗紙32枚のスケッチブック。 27×34cm POLARPUBLISHING/FINLAND
絵本の原画やイラスト(教科書、雑誌、レコードジャケット、広告パンフ、百貨店ポスターなどに使用したもの)を捨てる。
ぎっしり詰まった紙袋を”仕分け”もせずに、幾つもゴミ置き場へ運んだ。見れば捨てるに忍びなくなるのが分かっているから。
版木の類もイラストを彫ったものから、版画作品まで山のよう。取っておきたい気も山々なれど、どこかで処分せねばと一大決意。
大量の和紙や紙類はカビや黄変したものを除き取っておく。中に写真のスケッチブックの束があった。数十冊、購入は
40年程前だろう。なぜ買ったのか?おそらくスケッチブックの粗い紙質が気に入ったのだと思う。ザラザラしていて厚さもある。
真っ白とはお世辞にも言えないが(藁半紙か馬糞紙の趣)、風合いが良い。一、二冊使った記憶もあるが、戸棚の奥に眠った
ままでいた。ツルツル、すべすべのコート紙や白い紙が当たり前の子ども達に、この”自然な紙の色”を見せてやりたい。
クレヨンの”塗り””滑り”が全く違う。”粗末な”ザラザラ画用紙の復活を望む。
何でも手に入る、恵まれすぎからは創造性は育たない。無いから工夫する、やっと手に入れたから大事にする……想像力と
創造力、この二つのソウゾウリョクは環境、人(導き)、そして素材(材料)で培われる。粗末なスケッチブックの山を見て
思った。物が無い時代に育ったぼくは幸せだったと。
(Jun.25)
■二十四節気 <夏至> 七十二候 (二十八候、二十九候、三十候)
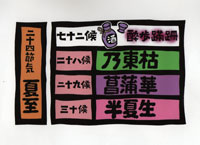 |
夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月21日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■いつも、アップアップ。切羽詰っての仕事……ゆとりがないなあ。
毎週木曜日は「自分の仕事日」としている。絵本制作、文書き、絵、研究といくつもメニューが多すぎて、大抵は
うまく行かない。時間を決めてやることを変えようとするのだが、仕事が不満足、区切りまで届かず延長となってしまう。
欲張り過ぎだが時間が足りないので仕方ない。睡眠時間も少なくてフラフラ状態……良いことではないなあ。
今日は絵本から入ろう。原稿書き(草稿)、それにやはり気になるレジュメ資料を作り直さねば。講演会の演目コンテンツも
考えたい。オープンキャンパスのメニューも、その他もろもろ、一つ一つ片付けてとは思うのだけれど、その一つが重たくて……。
昨日は小雨の中、キャンパスの植物の葉を採取した。キウイ、ドクダミ、ヤツデ……。「絵画造形表現」授業、スタンピングのためだ。
学生も色々な葉を持ち寄った。桜、銀杏、紫陽花、トマト、ヤマノイモ、柏、中に睡蓮なんてのもあった。残念ながら睡蓮は葉脈が浮き
出ておらず、スタンピングしてには向かないのであるが。
学生は自然物(葉など)と人工物(キャップ、容器)のスタンピングを楽しんだ。7色のインクをローラーに付け素材を写し取る作業に
夢中……、そしてその”転写コレクション”をコラージュする。自由に再構成する。完全自由を与えられた学生の表現は光った。いくつか
目を見張る出来栄えの物があった。
学生が制作自体を楽しんだ、その痕跡が作品なのだ。概念や意図しない無意識下のデザイン技法(AUTOMATIC……デカルコマニー、
フロッタージュ、ウオッシング、スパッタリングなど)を学んだ後の授業に、ぼくはスタンピングを選んだ。幼児造形教育の版画の元になる
スタンピングに、学生は時間を忘れて没頭した。その姿は無邪気に遊ぶ子どもと同じだ。幼児保育に携わらんとする者は子どもの心を
知らねばならない。作業に集中して子どもに還っている学生……、ぼくは学生が先生になって子どもに囲まれている情景を想像していた。
(Jun.24)
■リンデン(西洋菩提樹)の花にミツバチが……良い写真が撮れた



・リンデン(西洋菩提樹)の花の蜜を吸うミツバチ
「絵画造形表現活動」の今回のテーマはスタンピング。あらゆるものにローラーでインクを付け写し取ろうというもの。
自然物は葉っぱなど。学生は思い思いの葉っぱを集めてくることになっている。ぼくも葉脈のはっきりしたものを用意する。
桜、イチョウ、ヤツデなどはキャンパスにある。珍しいところで、杜仲茶、サンシュユ、ローズジェラニウム、ワイルドストロベリー、それに
きれいな形の”定番”モミジ。ハナミズキもアイビーも葉脈が美しく出る。全部で20種類くらい保冷材を敷いたバッグに詰めた。
リンデン(西洋菩提樹)の葉も珍しかろうと採取しようとして手を止めた。いまや激減、姿を消し問題となっているミツバチが、花の蜜を
吸っていたのだった。リンデンの花の蜜は最高と言われるが、一体このミツバチは何処に帰るのだろう?
アトリエを建てた頃は、ミツバチの大群の羽音うるさい群舞が見られたものだ。確かにここ、鳩山でもミツバチは減っている。
大急ぎでカメラを取りに。ピンとあわせに一苦労したものの何とか姿を納めた。
■クワノ実、グミ取り放題!ビワの実、甘露!



アトリエに籠りっぱなしは体に毒と、外に出る。荒れ放題の庭(庭と呼べないほど雑草が茂っている)、赤い実が目に入る。鈴なりの
グミ、ギッシリ密着する桑の実だ。どちらもいい具合に熟れて今食べごろ。口に含めば、かまずにとろける柔らかさだ。甘い。そう
たくさんは食べられないが、もいで食べるのは格別美味しく感じられる。びわの実も20粒ほどだが実を付けている。先週はまだ
固かったが、こちらも食べごろ。吐き出した種は辺りに埋めた。芽を出してくれるだろうか?忘れた頃、「あっ、あのときのだ!」
幼木を見つけられたら嬉しいだろうなあ。
■2010現代童画会選抜展搬入日迫る (展覧会詳細は別項)
毎年この時季恒例の「現童選抜展」も間近。銀座アートホール展示のあとは四国坂出、神戸と巡回する。作品の保護箱を
製作したが、利用していたホームセンターが閉鎖し材料の手当てが容易ではない。時間もなく、ありあわせの板で間に合わせた。
肝心の作品、タイトルは『どんぐり嵐』。毎年車の屋根に振り落ちるマテバシイのドングリが意識のベースにあった。それと、
旧作『どんぐり広場』だ。いま、種から芽を出したクヌギが育っている。”どんぐりの木”は種類が多いが、風に飛ばされてくるのか、
自然に生えてくるから嬉しくなる。ドングリノ木だけではない。サンショウ、ナツメ、スイカズラ、アケビ、モミジ……邪魔者扱いの杉も
あちこち芽を出して困る。さてさて『どんぐり嵐』の出来栄えは如何に……。
(Jun,22)
■「幼稚園実習」学生への試練……。耐えて超えてほしい。
昼休みのオフィスアワー(学生が質問等に自由に研究室を訪れる)に幼稚園で実地研修中の
学生が駆け込んで来た。園の先生から「責任実習」の制作物について厳しい指摘があったという。
廃材を用いての幼児の工作遊びで、学生は条件の一つ、「季節感を出す」から、カエルをテーマ
に選び、工作二種を用意した。新聞紙をまるめ先っぽにカエルを止らせゴムで“発射“するおも
ちゃ、 もう一つは、ティッシュボックスの中にカエルを4匹入れたもの。 蓋をあけると勢い
良く飛び出すおもしろい工作だ。
それが、「年長にはもう少し凝ったものを」「壊れにくく、長く遊べるもの」「カエルは4匹
いらないのでは」など等、相当言われ落ち込んでしまった。
”4匹”が面白いのに。学生がかわいそうになった。一匹しか入らない箱をわざわざ作るより、
4匹入るに越したことはない。カエルは3匹でも2匹でも自由だ。スペースを一匹用に限定して
しまえば、その後の遊びが広がらない。ぼくには何だか先生のアドバイスが”言いたい放題“に
思えてならなかった。
制作物をみてぼくは首を傾げた。いずれも問題はないと思えたから。「色んな見方があるんだね
この工作、子どもたちきっと喜ぶよ。頑張って!」ぼくも二点制作したものを見せたが、学生ので
十分行ける!「もっと自信を持っていいよ。」……励まして帰した。
聞けば、その園はセロハンテープ、ガムテープ類は一切使わせないという。段ボールを使う大形
おもちゃを作るときやペットボトルを束ねるとき等クラフトテープやビニールテーが重宝するのに、
すべて禁止とはなあ。先入観だ。そのくせ園児には英語を学ばせているという。何か偏ってる。ホチ
キスだって何だって危険視して使わせないのでは創造性は育たない。環境、素材(材料)それに、
やはり指導員だなあ。
子どもの感受性の萌芽期の立会人、極めて重責だ。
(Jun.14)
■実践遊び学……「連続模様切り紙あそび」
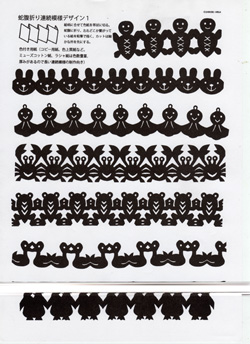
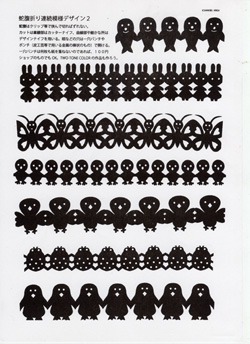
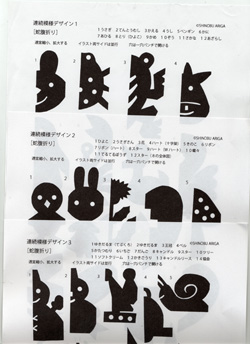
先週は江戸時代、寺子屋で盛んだった「紋型切り紙」を演習。昭和20年頃までは図工の教科にあった。3回折り、
4回折りを数多く制作。今回は「蛇腹折りの連続模様」。学生は思い思いのモチーフで数点の作品を仕上げた。
写真2枚
はそのレジュメ。右はデザイン参考資料1~3。このあと学生は”完全創作”に挑戦する。宿題にしたから、次週が
楽しみだ。自主性を喚起したい、いや何より制作”量”を求めたい。今は”質”ではなく、量だ。飽きるほど制作して初めて
身につくのだから。
毎回レジュメはこの調子だから、時間がかかる。今回は作りためた連続模様(すべて大型サイズで制作済み)その数40点。学生はこの40個を馬鹿馬鹿しいと思うのでなく、「だったら1個くらい作るぞー!」と発奮してほしいのだ。
(Jun.7)
■鳩山のアトリエ……目を休めに庭に出る。鬱蒼とした茂みに実りを見つけ嬉しくなる




週末は鳩山の生活が続く。現代童画展選抜展出品作の制作に入った。「アトリエだより」更新も儘ならぬ状態だ。
板を彫る手を休めて庭に出れば、嬉しい発見が!伸び放題のびた木々が実を付けていた。ビワはもうすぐ食べられそう。
サルナシはまだまだ小さいが、今年もどっさり実ったので楽しみ。グミは大粒が取りきれないほどだ。桑の実は口に含めば酸っぱく、甘くなるまで待とう。気にしていたオニグルミは(昨年はたった一粒しか生らず、それも収穫前に落ちてしまった)十個ほど実を付けた。クルミは信州で育った子ども時代の思い出があるので、何としても育てたかった。根元を虫にやられ穴が
開いてしまい心配していた。薬を塗布しロール布で養生する。
■二十四節気 <芒種> 七十二候 (二十五候、二十六候、二十七候)
 |
6月6日は芒種 (6月21日は夏至) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
| 5月のアトリエだより |
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
 |
5月21日は小満 (芒種/6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
2限3限授業の間に昼食をとるのだが、片付けがあったり、学生の質問などに時間を要し満足に食べられたためしがない。
10分くらいで立ち食い……出来ればいいほうだ。今日は昼飯を食べに研究室に入ったのが12時35分。そこへプロジェクト活動研究の
指導を求めて学生三名がやってきた。プロジェクト活動研究は学生が(教室外で)自主的に表現する科目だ。仕掛け絵本を作って、
幼稚園児の前で演じたいという。残念なことに、この学生達はぼくの「絵画造形表現Ⅱ応用」を受講していない。講座のコンテンツには
仕掛けを使っての「グリーティングカード制作」もある。ポップアップを中心に数種類の仕掛けを研究制作する。勿論カードのみならず絵本にも
応用可能だ。学生に授業で使った「仕掛けのゲージ」を貸し、コンセプトの再確認(仕掛けのおもしろさが狙い?しっかりした絵本?子どもたち
への読み聞かせが主?……いずれも大変なこと、中途半端にならぬように)をしてくるように言った。三人は仕掛けの習作を見せた。
すべては”ヤル気”だ。熱いエールをおくった。
先週は「なぜ絵が嫌いになったのか?いつごろから図工をしなくなったのか」アンケート調査をするという学生が訪ねてきた。文献を貸せと
いう。問題に即答といったものが簡単に手に入るわけが無い。子どもの絵、評価、造形表現等の資料として数冊渡したが、いずれもヒントには
なっても直接回答を求める者には不満だろう。考え迷い悩む……、研究する姿勢を見たい。
仕掛け絵本制作にせよ、アンケート調査にせよ、自主的活動の”芽生え”は素晴らしいこと。嬉しい。昼飯にありつけない日が続きそうだ。
(May.24)
■久しぶりの鳩山。雑草に庵埋もれそう。チェーンソーで木を切る。ブンブンゴマを作る。
多くの田圃で田植えが終わっていた。それも昨日か一昨日か、苗が植えられたばかりであることが直ぐ分かった。
鳩山には板絵制作用の木製パネルの在庫を見に来たのだが、アトリエに近づけないほどはびこる木の枝落としや雑草取りに
日がな格闘、板絵どころではなかった。
演習科目「コマの回転円盤デザイン制作」の前に見せる”伝承玩具”「ブンブンごま」を数個作った。ブンブンごまは回転するとタコ糸が指に食い込み引きちぎれるくらい引っ張られる。ブオーン ブオーンの音もダイナミックだ。ボール紙、ボタン、木片……何でも使える。昔は牛乳瓶のキャップで作ったものだ。路傍でメンコや釘刺しをして遊んだ少年時代、ぼくは毎日
何かを作っていた。このブンブンごまもその一つ。現代の子どもに糸巻きタンクなどと一緒に伝えたい遊びである。
(May.23)
■ウタリ神社の経木の風車を修理する

今年度の実践遊び学では4枚羽根に加えて8枚羽根の風車を制作した。紙製の風車以外にポリエステルベース
のものも学生に見せた。要は応用力だ。授業の始めには郷土玩具の「経木製の風車」も紹介したが、”経木”を
知る学生は皆無。「昔は肉屋でも魚屋でも包むのに使ったんだ。ほら、八百屋や魚屋の店先にあるだろう。あの墨で
値段を書いてある薄いやつだよ」……、そんなこと、いくら言っても無駄。隔世の感あり。
(May.22)
■子どもの造形遊びに「タイヤチューブプリント」を!
材料はたっぷり与えよう!「あれはいけない、これはやめよう」一切なしで、自由な「ペッタン遊び」を!


幼児や子どもの絵画造形は創造性を育む遊びだ。自由な造形をさせるには好奇心の喚起、環境、材料が必要。
環境は(お片付けのルールを教えるのは別)整理整頓された”キレイな場所”ではなく倉庫のような、思う存分”汚せる”空間がのぞましい。材料も高価な物や手に入れにくいものをちびちび”大切に使う”のではなく、身の周りに当たり前にある廃品利用、それも大量に与えることが肝要だ。壊したり、組み合わせたり、素材を本来の用途以外に応用する。正に想像力は創造力を育てることになる。
自転車のタイヤは廃棄物だ。入手簡単、大量に準備できる。絵画造形の素材にうってつけ、利用しない手はない。ゴムのチューブを木片に両面テープで貼り付けるだけで版材ができる。チューブ版画が幼児にも向くのは、彫刻等を使わないこと。
はさみ(カッターナイフの指導も)で簡単にカットできる。木版画、芋版画など、多くの版画は彫りミスしないよう神経を使うが、
チューブプリントは、粘着シートにチューブ片を貼り加えていくのだから、その心配はない。最も簡単な版画表現の一つと言える。
学生には、演習の前に版画の種別(凸,凹、平、併用版、モノプリント)の説明と、遊びの魅力を話した。が、何より大事なのは、造形教育に当たる者の”姿勢だ”。自らが楽しむ、目一杯遊ぶ、作る喜びを感じる……これらがなければ子どもの心は
捉えられない。「先生が、あんなに夢中になってる。おもしろそう!」教える側は”教える”のではなく、演じるのでもなく、楽しさを伝えられたら良いと思う。
(May.21)
■おでかけ絵本 愉快な三人組み『グー・チョキ・パー』制作順調
今月号で予告した、「ワン・パー・クー」は、ゆかいな三にんぐみ「グー・チョキ・パー」と名を変えた。クイズ、パズルを
どっさり盛り込む構成を楽しみながらやっている。<たぬき>クイズ……は、”た”抜きクイズ……”タ”の文字を消していくと
お菓子の名前が次々でてくる……、これは残念ながらカット!チョコレート、ドーナツ、ポテトチップス、キャンディー、
ビスケット、キャラメルなどカタカナが多く、編集部より幼児向きではないとの指摘。”狸クイズ?”の、ボケも入っているし
楽しめるのになあ。これに代わる面白い食べ物クイズを今考えている。もちろん絵本だから視覚的遊びの要素が大事……。
(May.16)
■クレヨンまる最終回!!掲載誌『おひさま』発売!!
■クイズ、パズル満載絵本の構想を練る
ゆかいな三にんぐみ グー・チョキ・パー
いじわる魔女を追いかけろ!
「おでかけクイズ絵本」のアイディアをまとめ,ダミーを制作する。意地悪魔女ズルーイが出す難問に、
腕白三人組グー・チョキ・パーが答えていく展開。描いた絵から飛び出てきたゲストキャラクターの
“おやつちゃん”が、それに絡む。
ことば遊び、迷路、シルエットクイズ、塗り分けパズル、形態パズル、絵探し、数遊び、本物探し、記憶クイズなど
満載予定だが、選択に頭を悩ましている。ボリュームたっぷりだが、読み終えても再びページをめくってクイズに
再度挑戦したくなる「おまけクイズ」付きだ。今は絵を描くというより、ゲーム的展開に頭を使っている。
スムーズな流れであるか?クイズは幼児に難しすぎないか?おやつちゃんの奪われたバッグの中身の秘密で、
ラストまで引っ張れるか?………キャラクターも(描いて描いて描いて)育てなければならないし、
ああ時間が足りない!今日は母の日。記憶の底から浮かび上がる母の微笑み……「ばかったいのを作りな!」
(“ばかったい”は母の口癖だった。非日常のおもしろさ、意外性、頓珍漢などを含めた、独特のニューアンス。
否定ではなくむしろ褒めことば)形式、常識、秩序、概念からフリーになるのがアーティスト!
母は厳しく、優しかった。
(May.9)
■移植したフキが根付き育った


テーブルソーやボール盤、ジクソーなどを備える作業小屋を建てた。用地はフキ畑。フキの根を少しだけ移植した。
芽は出したけれど、摘み取るには忍びず、蕗の薹はおあずけだった。来春が楽しみだ。その前にキャラブキという”手”もあった。
どうにも酒肴が頭から消えない。飲兵衛は春夏秋冬、恵みに感謝!
(May.5)
■おでかけ クイズ 絵本のタイトル決定!愉快な三人組『グー・チョキ・パー』のいじわる魔女を追いかけろ!
<おやつちゃん>て、何者?
キャラクター三人の名前、<ワン・パー・クー>、<ジャン・ケン・ポン>、<イチ・ニ・サン>、<ピー・カー・ブー>などの候補の中から、
<グー・チョキ・パー>に決めた。いたずらっ子が描いた絵から<おやつちゃん>も登場する。敵役のいじわる魔女、その名も<ズルーイ>。
いじわるクイズを連発する。<ズルーイ>は<おやつちゃん>のポシェットを奪って逃げる。<グー・チョキ・パー>は<ズルーイ>のだす
クイズを解きながら追いかけて行く。無事ポシェットは取り返せるか……?ポシェットの中味は……?
何度でも遊べるような仕掛けも。巻末には「おまけクイズ」を用意する。このノウハウは『こんなこいるかな』(知恵遊び絵本版4冊)で
用いたもの。楽しめる絵本にしたい。
(May.4)
■二十四節気 <立夏> 七十二候 (十九候、二十候、二十一候)
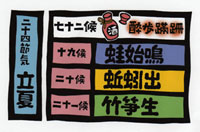 |
5月5日は立夏 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
久々のテニス。準備体操ももどかしくラリー。結果散散!右ふくらはぎの肉離れ。以前やったところだ。運動不足の鈍った体に
急激な刺激、”故障”は目に見えているのに。おお馬鹿者だ。足を引きずって歩く羽目に。
よって、また机に向かう生活と相成った。渋谷の仕事場からは中学校の校庭が見える。少年野球の練習試合が白熱を帯びている。
飛び交う声で分かる。皆、戦いに夢中だ。シップ薬を貼り、ぼくも絵本作りに精をだす。
(May.4)
■ペッタン、コロコロスタンプ 廃物利用による,幼児のための造形表現ツール




 テニスボールやボール缶の蓋を
テニスボールやボール缶の蓋を ペッタンコロコロスタンプは造形表現遊びの一つ。幼児は出現する轍の跡に目を輝かせる。型押し遊びの専用スポンジも市販されて
いるが、身の回りの物を活用することが、”応用する心”を育てる。手づくりした物は市販教材の完成品に、想像=創造……に至らせる
点で優る。材料は不要になったテニスボール(ゴミ処理に頭を悩ますクラブからは、いくらでも貰えるだろう)、クリーニングハンガー、
ペットボトルのキャップ。テニスボール缶キャップ(下段作品)いずれも廃物の再利用。
上段の針金ハンガーに通した二つのペットボトルキャップは頼りない装着に見えるだろうが、この”あそび”が大事。ボールをスムーズに
回転させるために必要なのだ。写真のほかにも数点試作した。転がした”おもしろ軌跡”は?また後日……
(May.2)
■鳩山は芽吹き……緑噴く。山笑う。春爛漫!



・五つ葉アケビ 雌花雄花 ・月桂樹の花 ・ダイコンの花群生
3本ある姫リンゴの木がいずれも白花満開。剪定を怠り屋根に届く高さに伸びた月桂樹も白黄、薄茶の細かな花を
ギッシリつけている。五つ葉アケビは至る所に育ち、赤薄紫の花を揺らせている。雌花、雄花が寄り沿うようで可憐だ。
今年色味がやや薄い紫モクレンははや散り始めている。ハナミズキが満開だ。手をかけて上げられないから、どれも伸び放題。
この間まで枯れ木同然だったブナが若緑の葉で覆われている。一番気にしていたメープルや(病気の)オニグルミも若葉を茂らせている。
一安心だ。白色、黄色、桃色……とりどりの色が咲き競うように乱舞。中で目に飛び込むのはダイコンの花の紫。何年か前までは
菜の花だった。隣地といっても境界もわからないような荒れ野原だが、今はダイコンの花で埋まっている。離れて見れば緑のなかの
紫模様のカーペット。
風もない穏やかな日和。日がな眺めていたいがそうもいかない。仕事に来たのだった。冷え冷えしているアトリエに入る。
目が慣れるまで闇だ。幼児造形教育のための教具教材作り……これはこれで楽しい。小鳥のさえずりを聞きながらアイディアを
考える。小さかったころから今に至るまで、ぼくは工作少年だ。
(May.1)
| 4月のアトリエだより |
■大学の研究室で仕事に没頭。先生の在室ランプも点灯まばら、訪れる者なし。静寂……わが天国!
先日学生がゴールデンウイークの過ごし方を聞いた。「どちらに行かれるのですか?」「仕事だよ。」
「えー、うっそー!」と言う具合。休日明けの授業のレジュメを準備し、さて我が仕事に取りかかる。
やっと取りかかれる。「おでかけクイズ絵本」の制作に入った。暖めていたアイディアをサムネールにおこし、
ネームを書き込んでいく。ダミーを作る。一冊36頁にストーリーを組み様々なクイズをちりばめる作業クイズや
パズルの考案、レイアウトなど楽しくもかなりハードな仕事ではある。
何より話が面白くなくてはならない。クイズやパズルを満載といっても、話の流れに不自然さがあってはならない。
頭を悩ませ、ため息をついては、それを打ち消すように、“面白く、楽しく”を念頭に……。
ぼくの“ゴールデンウィーク”は仕事三昧週間となる。
(Apr.30)
■一分間は楽に回り続けるコマを制作


身の回りにある廃物品の利用。今回はCD。どこの家庭にも一枚や二枚はあるだろう不要になったCD(CD・R、DVD)を
使ってのコマ作り。材料はCD一枚とビー玉。ビー玉をCDに接着するだけの簡単さ!誰にも出来る!これが実に優れもの。
よく廻る。一分間は当たり前に廻り続ける。。色紙を貼り合わせたり、模様を描いた回転円盤をセットすれば更に楽しい。
学生は回転円盤のデザイン(同心円、渦巻き、放射、格子、ドット、イラスト…・等)を多種制作させるが、コマ本体は
市販の物を使う。ただ、いつものことであるが「応用力」は要求する。身近なものを使ってのコマ遊びを考えさせる。これが
大事。その一アイディアとして「CDゴマ」を紹介する予定。
(Apr.25)
■晴れた!久々、光が目映い。風が香しい……かざぐるま かざぐるま かざぐるま……
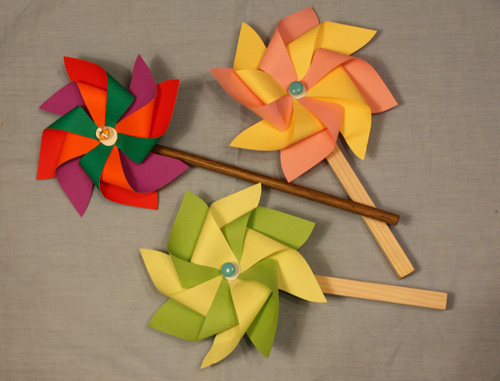


観測史上でも珍しい低温が続いたが、今日ようやく晴れ間が広がった。春風が気持ちよい。
風車をかざす。クルクル音もなく回る。幾つか並べて廻す。何てことないが、ホットする。知らず知らず幼き頃を想っている。
四枚羽根と8枚羽根を制作。8枚羽根(写真左)は、学生に型紙を提供するため、その準備も。風車をとめるピンやビーズや
丸棒も仕入れた。100人分、助手がいないのだから全部ぼく一人でやるしかない。準備がいつも大変だ。紙のカットや
組み立てはもちろん学生だが、配色やサイズなどでオリジナリティを演出してもらう。
{伝承工作}かざぐるまの次はでんでん太鼓だ。その準備もしなくてはならない。この一年、ほんの少し時間が空けば何か
作っていたが,でんでん太鼓も増えに増えた。その数数十個!ガムテープ、大小のセロハンテープの巻き芯、6Pチーズや
チョコレートのパッケージが溜ると気になり”でんでん太鼓化”したのだ。所狭しと吊るしてある。一つ一つみな音色が違う。
軽く重く小さく大きく、それぞれが愛らしい音を響かせる。「でんでん手遊び」は、仕事の合間の息抜きに一役買っている。
机の傍らにほんの小さなでんでんを一つ置かれたら如何だろう。ミニサイズは読書の妨げにもならない。耳を傾けたくなる
ような穏やかななんとも懐かしい音だから。
(Apr.24)
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
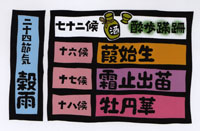 |
4月20日は穀雨 (5月5日は立夏) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
このところ震える寒さだ。校庭の桜はまだ散りきらない。駐車場の片隅、風に集められた
桜の花びらの山があちこちにできている。しゃがんで一掬い。ひんやり、しっとり……手に意外や、重みを感ずる。
ぼくは急に小人になる。花びらの褥に体を横たえ、埋もれるように花びらの間から空を見上げる。薄青の天、柔らかな日差し。
花びらの山を凝視している自分と中で休む自分。不思議な思いだ。日々の忙しさ、時に流されるわが身を
一瞬間蘇生させてくれた春よ、風よ,恵みをありがとう。
(Apr.20)
■子ども教育学会紀要扉絵

・胡桃のヨットとブリューゲルの風車
子ども教育学会の紀要が発刊された。創刊号の扉絵は『FATHER’S LETTER』
今回第二号は『胡桃の風車とブリューゲルの風車』。この愛らしいヨットも、風車も実際に
つくってみた。ヨットはアトリエに転がっている。風車は大事に飾ってある。父と子が物づくりを
通じて得るものは計り知れない。通い合う心……夢中になって遊ぶ……いつ何処で見ても
いい情景だ。幼き日の思いでは一生心で輝く宝。
(Apr.18)
■現代童画春季展出品作「harbor」


次回の発表は選抜展。乞うご期待。
(Apr.16)
■「こんなこ」工作。「二人は仲良し、いつも一緒」
『こんなこいるかな』コーナーに「★玩具を作ろう!⑦二人はなかよし いつもいっしょ」工作掲載。
次回は「スルスル シューTOY」を予定。 ★こんなこ いるかな のページへリンクできます
(Apr.11)
■現代童画春季展、(銀座アートホール)明日終了
明日11日、「現代童画春季展」最終日。一ヶ月の制作も、あっという間に展示期間が終わる。この次の展覧会は「選抜展」。
時間がなく制作も儘ならない状況だ。アイディアのラフスケッチだけでもと心がけてはいるが、思うようには行かない。
12日からは大学の授業が始まる「実践遊び学」「絵画造形表現活動Ⅰ基礎」。昨日は10時まで演習室、研究室でレジュメ制作。
一日の予定仕事分量の三分の一位しかできないもどかしさ。が、もう泣き言は言うまい!三年目、パワーアップして臨みたい。
(Apr,10)
■「ノビル畑」つくって、どうする!



春だ!でも鳩山の山桜の蕾は未だ固い。野原でノビルを見つけた。絡むように固まって生えるノビルを根こそぎ頂く。
幾塊ものノビルをアトリエ脇のヒイラギの根元に移した。ノビルには小さいころの思い出がある。引き上げ後、亡くなるまで
寝て過ごした父さんに、ノビルを摘むのがぼくの”仕事”だった。親父は医者から禁止されても酒をやめなかった。酒肴は
何でもよかったが、ノビルのヌタを好んだ。
「ノビルの畑」……記憶を蘇らせる場所を作った。
■二十四節気<清明> 七十二候(十三候.十四候.十五候)
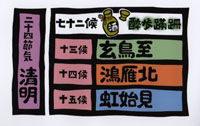 |
4月5日は清明 (4月20日は穀雨) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
金曜日は週一テニスの日なのだが、生憎小雨、風も強く仕事日となった。天が仕事を命じたのだと観念し、新学期のレジュメを
考える。新たに「8枚羽根かざぐるま」「変色コマ」「切り絵連続模様」のレジュメを制作しなくてはならない。今日は風車だ。
紙皿、紙コップ、ペットボトルを使っての風車作りは制作見本を見せるに留め、今期は学生に基本形の4枚羽根の風車と、配色を
楽しめる8枚羽根の風車を作らせる。その試作を行った。型紙を起こし、形や色を変え5個作ってみた。さらに学生に貸す(時間
節約のため)型紙(ゲージ)をテーブル数×3=18組、一組2枚構成だから40枚近く白ボール紙から切り抜いた。デザインナイフを
握る右手親指は痛んだが、仕舞いには感覚がなくなり、指先が凹んだまま戻らなかった。そうまでしてと、いつも思うが、90分授業で
出来る限りたくさんの課題をやらせようとすると、ゲージを用意するしかないのだ。学生は簡単に「このゲージください」という。それでは
なんにもならない。同じものをたくさん作るとき、ゲージがあったら如何に便利かを分からせるためでもあり、幼児保育、子ども教育の
現場で、自ら”できる”力を養って欲しいから、「型紙は自分で作りなさい」と言う。かざぐるまのレジュメは型紙を入れて4枚になるが、
本日完成せず。ぼくは、”試作”を楽しみすぎるキライがあるようだ。
(Apr.2)
| 3月のアトリエだより |
■板絵 『 harbor 』描きあがる 日暮れまでナツメの木の移植に精を出す
28,29両日は寒の戻りか、冷たい北風が吹き荒れた。裸木立の枝が折れて飛ばされる強風だ。ぼくは鳩山のアトリエで
ストーブにしがみ付くようにして絵を仕上げていた。完成!いつもより少し色合いが生っぽいか。子どもへの”童画”然だ。
今回の作品は「harbor」=隠れ家で遊ぶ父子を、想いをこめて描いた。小学3年生のころ、ぼくは隠れ砦を作った。その記憶、
ワクワク感が筆を進めさせた。感動は創作の原動力だ。
額装が終わり、初めて外へ出た。まず深呼吸。そして日が暮れるまでの短い時間、何をしようか考える。やることは山のように
あるけれど、欲張ってもはじまらない。春、新芽が吹き出す前に済ませたいこと……、今は枯れ木にしか見えないナツメの木を移植
することに決めた。ナツメは実が落ち、あちらこちらで育っている。土が合っているのか、サンショウや迷惑なスギ同様増えて
困るほどだ。一年目ものは未だ良いが、3年、4年たった木は、棘はともかく根が張っていて掘りあげるのに一苦労。
10本掘れば、もうお手上げ。このまま大きくなれば、実を付けるけれど、通路を塞ぐ枝の棘が厄介だ。
掘り残した分はハサミでカット。かわいそう、もったいないけれど、鳩山にそうしょっちゅうは来られないから仕方ない。
ナツメの親木の勢いに負けて山葡萄が元気がない。去年も一昨年も実がならなかった。ナツメの移植より、こちらの方が
心配だ。酸っぱい山葡萄の実を煮詰めてシロップを作ったことがある。あの喜びをまた味わいたい。大匙数杯分しかできなかった
貴重なシロップを”大事に”口に含んだときの気持ち……嬉しさを再び。
(Mar.29)
■桜咲くキャンパスに人影まばら
子ども教育学科新入生に配る画材、用品の袋詰めをする。14アイテムを110セット。昨年は二人でおこなったが、
今年はもう一人助っ人を加えたから、まだ明るさが残る時間に終了した。
大学には「100年桜」の老大木があるが、校舎からはやや離れている。桜を見て帰りたかったが、今日は断念。
それでも幾本もの桜が咲き始めていた。3分咲きくらいか。美しい。ぼくは冷たい風に震えながら佇んでいた。
ふと足元を見れば、しぼんだ銀杏の実が幾つか。梢につかまっていたものが、ようやく落ちたのだろう。ぼくは
銀杏並木が好きで、秋の終わりにはキャンパスで銀杏を拾う。ぼく以外には誰も拾う者はいない。果肉を洗い落とし
乾燥させるのだが、土に埋けて果肉を腐らせ取り除く手もある。そこで植木鉢に埋めておいたのだが、何と十数本が
発芽してしまったのだ。
今は、20センチほどの”枯れ枝”にしか見えないが、しっかした芽をつけている。植木鉢は大振りだが、”枯れ枝”には所狭しだ。
春になったら、鳩山に移植しよう。鳩山にもイチョウの木はあるが、実が成らない。大学の鈴なりのイチョウの子どもだ。あやかって
銀杏を雨のように降らしてくれるようにならないかなあ。
(Mar.26)
■アケビ棚を補強……石井さんにまたまた、大感謝


杭を打つ音で目が覚めた。わがアトリエは訪れる人は稀なので、あわてて外に飛び出した。
石井さんだった。昨日はヨモギ餅を持ってきてくれ、今日は、倒れそうに大きく傾いているアケビ棚を
直しに来てくださったのだ。石井さんは先日、杉の木を剪定してくれたのだが、そのとき、アケビ棚が
壊れそうなのが気になったのだという。四本の足に角材を打ち込み補強、古い蔓も取り除いてくれた。
「花芽は残してありますからね。今年は実が成るでしょう」……と。人の佳い石井さんのとびきり上等の
笑顔に、ぼくの制作が捗ったのは当然のことであった。深謝。今回は二日間のアトリエ生活。明日からは
渋谷の仕事場に戻って働くことになる。
(Mar.23)
■出来立てのヨモギ餅をいただく
昨晩の強風(東京では瞬間最高風速20数メートル)鳩山の庭も多くの枝が折れていた。
プラムやすももは蕾をつけた枝が……。相当強い風が吹き荒れたのだろう。


アトリエ北側の田圃の主、石井さんがヨモギ餅を届けてくださった。朝作ったばかりの出来立て。
越辺川で摘んだ蓬、自家産の上新粉(都幾川村で精米))、小豆もすべて石井さんの収穫品だ。ヨモギの香りが
鼻腔をくすぐる。口当たりの良い適度の柔らかさ。美味い!餡と黄な粉で二つペロリ。
毎年、この時季きまって春の味覚の贈り物。嬉しくて、でも秋にいただく栗の渋皮煮や、採れたての
米、それにぼくの大好物の玄米(これと梅干さえあれば、おかずが要らぬほどだ)など、いつも頂いてばかりで
心苦しい。アトリエに車が停まるのをみて軽四輪でおいでなさる。ありがたい。手を振り頭を下げ、見送るが
お礼に何も差し上げられず何とも申し訳ない心持だ。ご好意に感謝。
(Mar.22)
■二十四節気 <春分> 七十二候 (十候.十一候.十二候)
 |
今年の春分は3月21日 (清明は4月5日) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
17日の当欄、ミツマタの花の写真を掲載したが、ミツマタは沈丁花と同じ科だった。甘い匂いは同じなれど、ミツマタは
鼻を近づけ嗅がねば分からないほど”上品”。ミツバチが減って困っているというニュースをたびたび目にするが、
わが庭には、ミツバチが群がって飛び交っている。ミツマタの花の蜜を集めることに夢中で、ぼくの存在なんておかまいなし。
ミツバチの羽音を耳にぼくはミツマタの花に顔を埋めたていた。
(Mar.21)
■板絵『harbor』制作進行中
現代童画春季展(別項「展覧会」参照)に出品する板絵、作品タイトルを
「harbor」と決め制作中。絵の具が乾く時間も絵から離れられない。額縁を
塗装したり絵皿を洗ったりもするが落ち着かない。完成が近づくといつもこうだ。
最後の筆を入れ、いすに座リ込むとき、時が止まる。まばたきさえ止まるくらい
集中して見入っているのだと思う。その後襲う疲労感でわかる。
「harbor」……父と子の遊び場所。内緒の(自分たち以外は誰も知らないと思っている)
隠れ家。想像力を全開させる、ぼくにとっての「板絵制作」同様、時間の止まる宇宙だ。
その宇宙を、今描いている。
(Mar.21)
■紙芝居「だいじな たまご」出来上がる


・「だいじなたまご」① いずれも画面はカットされています


社団法人「小さな親切」運動本部製作紙芝居『心の教育プロジェクト』
……紙芝居で「豊かな心」を育てよう…… 「だいじなたまご」が完成した。
紙芝居を用いた道徳授業のための指導資料もついている。視認
性を重視、太いシンプルなライン、色も
絞りスッキリさせた。せっかくもらったチャボの玉子が壊れて怒り、悲しむ主人公たっくん。たっくんの心情は
とらえたつもりだが、紙芝居は演者の力量による所が多い。持論「絵本も紙芝居も童話も面白くなくては」が、
今回は少々叶わなかった面もあるものの、ストーリーも絵もシンプルなだけに、授業展開に広く活用できると思う。
■伸びた蔓をグルグル巻いて……何のリースでしょう?



・キングサリの花 ・ブナの枯れ葉(新芽が堅く鋭く尖っている) ・オリーブの木に
リースなんて洒落たものじゃない。枝をグルグル巻いただけ。何の枝?ここがポイント!蔓は藤、アケビ…材料に事欠かないが、
今日は始めての蔓で制作した。キウイの棚に絡まっていく枝も長く伸ばしているマタタビ。花が咲き、実を期待させてはがっかり……の
マタタビの蔓が地面につくくらい垂れ下がっていたんだ。30分間のお楽しみさ。
マタタビの冠は何で飾ろう。まず水仙、それからクリスマスローズにかけて見た。似合わない。キングサリの黄やオリーブの濃い
緑もマッチするが、やはりブナがいい。芽吹く前だというのに葉を落とさず寒風に身を震わしているブナがいい。マタタビのリースに
ブナの枯れ葉色……美しいなあ。30分の楽しみに幕を引き後ろ髪引かれる思いでアトリエに戻った。
体は冷えたけど、嬉しさがねえ……。いい仕事が出来そうだよ。
(Mar.18)
■日がな一日板絵制作に没頭……



・ミツマタの花(木の高さ2メートル、殆ど花は白く見える ・同、しゃがんで見れば黄色 ・沈丁花
10時から7時までアトリエに籠る。いや、花の香りに誘われて一度外へ出た。
仕事場に甘い芳香が漂ってくる。沈丁花だ。朝東京を発ち鳩山に来たが、車を降りたときは気づかなかった。
満開。近づけばきつい位匂い発つ。沈丁花から数メートル先にはミツマタがこれまた咲き誇っていた。上から見れば
白(淡い黄色)、ちょっとしゃがんで下からのぞけば濃い黄色。ほのかに甘い香りがする。
いつかミツマタの皮で紙を漉いてみたいと思う。早く成長して欲しいものばかり。メープルシロップをとりたくて
サトウカエデを、ブナ林を夢見てブナの苗木を、とちもちを食べたくてトチノキを、果実酒を目論んでナナカマドやサルナシや
マタタビを植えた。が、すべて夢の夢で終わるだろう。それでも、夢の種まきはやめられない。
一旦外に出るとアトリエに戻りたくなくなるから困る。草木の息吹に気圧されそうだ。板絵に向えば、すぐ”復調”するから
未だ大丈夫だが。”大丈夫”はおかしいか。自然は敵ではないし……一体感。抱かれての仕事のはずだよね。
(Mar.17)
■タイトル決定!クレヨンまるファイナル「バイバイ クレヨンまる」
春季展出品板絵の作品名は絵より先行したが、クレヨンまるは文・絵が完成してから考えた。タイトル案は数種。
でも、一番おとなしいものを選んだ。「バイバイ クレヨンまる」あまり強く内容を暗示させたり、
感情移入過多にならないように。
1996年1月号から連載開始、155話がファイナル。普段のアイディアとは違った、最終回の展開には頭を使った。
“読み聞かせお話雑誌”『おひさま』はこの春から隔月刊になる。クレヨンまるは、5-6月号(4月15日発売予定)
で、さよならする。意外な結末……!? どうか、ご高覧あれ。
(Mar.11)
■これから制作する板絵の作品名を考える
現代童画2010春季展(4月5日~11日 於・銀座アートホール)出品作の制作に入る。
と言っても、鳩山アトリエ初日は雪降りでクローズ。渋谷に戻りエスキスを取る。
と同時に作品タイトルを考えねばならない。会場に置く出品目録印刷のため、作品名を申告する
ことになっているからだ。refuge, hide out, ……、悪事を働いて隠れる意が強いから、ぼくは「harbor」を選択。
隠れ家で遊ぶ父と子をイメージ。親とか子とかの意識をはずれ、幸せ無我の境で遊ぶ秘密の空間を描きたい。
今回のように作品名が絵より先行する例は、ままある。「瞬幸永憶」(F100号)もそうだ。
無論、瞬幸永憶などという熟語はない。言葉のイメージが絵を語らせた好例である。
(Mar.11)
■雪降り止まず退散
板絵制作に入ろう……遅れた時間を取り戻すべく一路鳩山へ。
予報では天気は午後から崩れるという。冷たい雨は昼前には雪に変わった。
とにかく寒い。久しぶりのアトリエ、震えながら板に向かう。が、外が気になって仕方がない。
春の日が射せば、シジュウカラやヤマガラそれにウグイスの声を期待できたのに、生憎の雪!
眼前に広がる田や畑は真っ白。積もれば、坂下にあるわがアトリエだ、
車はスリップして登れなくなる。何年か前、“脱出不能”となったことがあった。
というわけで、「アトリエ滞在2時間」のみ、の記録を本日つくった。
雪に埋もれていくフキノトウ、摘みたい気持ちを抑え帰京せり。
(Mar.10)
■二十四節気 <啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
仕事に明け暮れHP更新もままならず。テニスにも行っていない。”外出”は現代童画会春季展作品用パネルを取りに行った
鳩山アトリエのみ。
おおよそ人間的でない生活。体が鈍ることを憂うも、窒息しないでやっていられるのは、表現欲求のなせるワザか。
このところ天気が優れない。菜種梅雨か。久しぶりに今日、雨上がる。最高気温18度、昨日より10度も高い。時間をきめて歩く。
代官山~恵比寿~渋谷、これで5000歩。恵比寿駅近くで「ロバの花売り」に出合った。暫し足を止めた。1メートルくらいの灰茶褐色の
ロバ、背中に花かごを付けている。チェック地のシャツにベレー帽姿。赤ら顔のおじさんはバラの花を一本一本小分けにしている。珍しさもあって
見物人が取り囲む。ロバは大人しくじっとしている。が、急に飛び跳ねた。おじさんのジャンパーの中に顔を隠した。おじさんはカメラの
フラッシュをやめてくれるように言った。
やさしいロバの目。花の中に桃の枝も……。「飼えたらいいなあ……」ロバは、ぼくの飼いたいものリスト、ベスト3上位だ。
(Mar.5)
| 2月のアトリエだより |
■「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」



『おひさま』連載の 「クレヨンまる」、次号で155話。これで見納め、読み納め。只今最終編を執筆中。別れは悲しいもの。
クレヨンまるはどうなる?仲良しのチェリーは?それに、大泥棒のワルズー、子分のコウモリ、コモリンは?三百数十歳の
ミイラばあやは………死ぬなよ!?………明るく明るくと念じても、想いがつのって……。さあ、どうなるか。〆切待ったなし!
描くぞー!!!!こう、ご期待!!!!
(Feb.28)
■「フータのひこうき」の朗読が放送されます
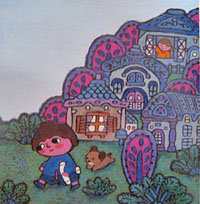



ぼくの絵話集「マーリと のうさぎ」の中から 『フータのひこうき』が放送されます。
童話として書いたものではないので、朗読でイメージがどう伝えられるか楽しみです。
(絵の世界がどう表現されるかなあ)
番組名:『童話の散歩道』
放送日時:32局ネット
「童話の散歩道」各局の放送時間
・ 北海道放送 3月27日(土)6:20~6:30
・ 青森放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ IBC岩手放送 3月28日(日)12:20~12:30
・ 秋田放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 山形放送 3月28日(日)7:15~7:25
・ 東北放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ ラジオ福島 3月28日(日)8:30~8:40
・ 新潟放送 3月28日(日)12:40~12:50
・ 北陸放送 3月28日(日)7:40~7:50
・ 北日本放送 3月27日(土)7:50~8:00
・ 信越放送 3月28日(日)8:50~9:00
・ 山梨放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 福井放送 3月28日(日)6:20~6:30
・ 静岡放送 3月28日(日)5:10~5:20
・ 中部日本放送 3月28日(日)8:35~8:45
・ ラジオ関西 3月27日(土)7:20~7:30
・ 京都放送 3月28日(日)17:30~17:40
・ 中国放送 3月28日(日)7:30~7:40
・ 山陰放送 3月28日(日)16:00~16:10
・ 和歌山放送 3月27日(土)16:44~16:54
・ 山口放送 3月28日(日)8:30~8:40
・ 西日本放送 3月27日(土)7:00~7:10
・ 南海放送 3月27日(土)17:50~18:00
・ 高知放送 3月28日(日)17:45~17:55
・ 四国放送 3月28日(日)11:50~12:00
・ RKB毎日放送 3月28日(日)8:15~8:25
・ 大分放送 3月27日(土)8:20~8:30
・ 長崎放送 3月28日(日)7:00~7:10
・ 熊本放送 3月28日(日)9:05~9:15
・ 宮崎放送 3月28日(日)6:30~6:40
・ 南日本放送 3月28日(日)6:50~7:00
・ 琉球放送 3月28日(日)7:15~7:25
朗読アナウンサー 牛山美那子
(Feb25)
■コンソーシアム大学「作って遊ぼう」第三回
『コロコロ コロ玉バランスボード』を作る。ゲーム機では味わえない”微細な手の運動”。イライラさせて遊ぼうというもの。
長方形木片26個、円筒形4個使用。赤青緑黄に塗った木球4個を転がして遊ぶ。四隅から中央に集めたり拡散させたり、
時間を競ったり遊び方は色々。遊び方を考え出すのも狙いの一つ。シンプルで何度でも繰り返し遊べ何より”手加減の妙”を
味わう。勢いよく転がしても玉は思うところに入らない、留まらない。ビー玉、おはじきも皆そうだ。加減が技である。
教室に玉ころがしの音が響いた。気が付いてみれば二時間の授業中、トイレに行った子どもなし!何と言うことだ!えらい集中力!
授業の終わりに、ぼくはこのことに触れた。トイレさえ忘れ、夢中で頑張った子どもたちを褒め称えた。
(Feb.20)






■ コンソーシアム講座の終わり10分の”オマケ”
120分授業を、子供達が飽きさせないで楽しくやるのはたいへんなこと。これに一番頭を使う。絶対集中させるぞ……意気込んで!
メニューを幾つか用意するのも手だが、しっかりしたものを制作させるにはそうも行かない。所々刺激を与える仕掛けを用意したり、
あっと目を見張る(視覚効果)ものを隠しておいて広げて見せる等など、アシスタントの学生にも秘密の隠し物を前日から用意したりする。
講座終了10分前も大事!作品が完成し、自由に遊び、少々だれてきている。そこで強い印象で締めくくるには、新たな興味を惹く
出しものが必要となる。前回は「シュルシュル人形」。そして今回は「牛乳パックの水車」を用意。教卓に6っこずらりと並べ、
「さあ、こっち見てー!」子供たちが群がったのはいうまでもない。蛇口をひねり水車の羽根に当たるように置く……「ぼくにも!」
「やらせて!」「すげー!」子供達の楽しむ声が大人を気づかせる。「廃物利用、創意工夫……創造的遊びを」お母さん方は
作り方を熱心に聞いている。「お家で是非作ってくださいね。簡単で面白い工作を考えてね」……メッセージと共に授業は終了する。が、
帰らず遊び続ける子どもも多く、こんな姿をお母さん方は、目を細めてみておられた。子どもは輝く!凄い輝きを発す!



■二十四節気 <雨水> 七十二候 (四候.五候.六候)
 |
雨水は2月19日 (3月6日は啓蟄) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
20日の日差しは春のもの。穏やかな日和。紅梅白梅の木立の間に銀杏が数粒ころがっていた。最後までしがみついていた
実が落ちたのだろう。キャンパスは人影もまばら、静寂。「コンソーシアム授業」会場に向かう足取りも軽かった。
■クレヨンまるファイナル 制作中!!必見!!クレヨンまるの最後!
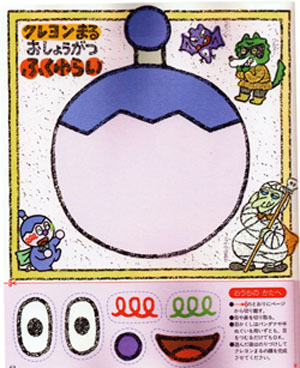
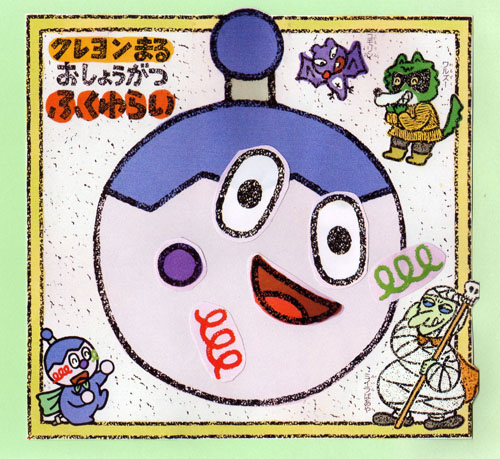 ・福笑い
・福笑い
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』
二日目 「回転円盤仕掛け絵本」”あんなかお、こんなかお、そんなかお、みななかお、どんなかお”」
雪交じりの寒い朝、20組の親子が集まった。前回同様みんなヤル気十分!お父さんの参加は4名、弟や妹を連れてきた方もいて
教室は満員。まず”宿題”の顔の絵を絵本の表紙に貼り付ける。もちろん”作家名”も記入する。絵本作家になった気持ちで、
制作スタート。子どもは4種類の”面白い””おかしな””楽しい””見たこともない”顔を描く。その間に保護者の方々は
仕掛け絵本のメカ(二枚の回転円盤、ジョイントなど)を制作する。顔の絵を上部と下部とに切断し本体に取り付ける。本体台紙に
開けられた二つの穴(目と口)に12個の表情を描きこむ。これで何百もの顔ができるのだ。製本は金属鋲をかしめる。これは、
かなり大変だったけれど、学生が要領よく流れ作業でこなしてくれた。世界で一冊だけの「ぼくのえほん」「わたしのえほん」で
子ども達は遊んだ。”へんてこな顔”が出現するたびに歓声をあげて……。作る楽しさ、遊ぶ楽しさ……、苦心して作り上げた
その達成感が子どもを成長させる。
講座終了間際にお家で簡単にできる工作を紹介する。今回は『しゅるしゅる人形』牛乳パックとストローとタコ糸があれば
誰でもできる玩具。試作品を吊るすと、子供達が群がった。シンプルだけど面白い。手加減で人形がしゅるしゅる昇っていき
スーと落ちてくる。子ども達は繰り返し繰り返し遊んでいた。つくり方をメモしているお母さんも。是非とも、お子さんと一緒に
作って遊んでほしい。

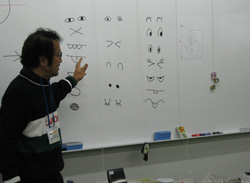

・「おもしろい顔ができたねえ」 ・表情の変化は色々だよ「泣いたり笑ったり、怒ったり眠ったり…」・「やって見せて!」



・糸を操り人形を天井まで昇らせて遊ぶ ・牛乳パックで作って見せる ・ちょっと”豪華な”「こんなこ」バージョン
■コンソーシアム大学 『作って遊ぼう!』 初日は「変身仮面を作ろう!きみの仮面はどんな仮面か、お話して!」
6歳~9歳の子どもに、お母さんお父さんを交えてのコンソーシアム大学「作って遊ぼう!」開講。
「●作って遊ぶ楽しさ●出来たものは、世界でただ一つの存在●表現は”自由”、この素晴らしさ」
第一回目は、『変身仮面』。仮面を作って、各自その仮面の秘密、凄さを語らせるもの。


・21人が仮面を制作。仮面にはそれぞれの秘密がある。想像させることが目的。



・マントは黒2着、白4着を用意。全員を写真に収める。 ・わが優秀なるアシスタント。子ども教育学科2年生
・下段中央は、河童(鼻から突き出しているのは”吹き戻し”が正義の味方○○仮面にやられるの図)
さて、この弱虫カッパは誰でしょう?
次回は『回転円盤仕掛け絵本』…………
「こんなかお、あんなかお、そんなかお、へんなかお、どんなかお」変な絵本のタイトルだねえ。
■クレヨンまる最終編! はたしてどうなるかクレヨンまる!


『おひさま』 が月刊から隔月刊になる。それにともない、クレヨンまるは『おひさま』6-7月号(5月15日発売予定)を
最後に休載する。おひさま創刊当初からクレヨンまるを描いてきたから感慨一入である。
第一話「クレヨンまる誕生」が1996年1月号、以来本年2月号「オリーブおばさんのプレゼント」が154話。
15年の連載を休止するのだが、ファイナル155話は特別編だ。クレヨンまるファンを悲しませないよう、そして、
最大級の”オチ”で締めくくろう。このところ毎日毎晩、結末をどうしようか考えている。
これじゃダメ!あれでもダメ!面白くて、悲しくて、くすっと 笑える……あっという最後で締めくくるんだ!ぼくは
クレヨンまると共に生きたから、ぼくなら出来るはず……言い聞かせて、寝ても覚めてもクレヨンまるの世界に
浸かっている。クレヨンまるファンの皆さん、待っててね。クレヨンまるの”最後”……悲しみを吹き飛ばすような
結末を、きっと描いてみせるからね。
(Feb. 10)
■二十四節気 <立春> 七十二候(一候.二候.三候)
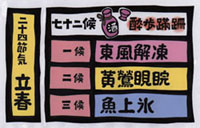 |
●立春は2月4日 (雨水 2月19日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
暑いのは歓迎だが、ぼくは寒さに弱い。渋谷の仕事場は北側に位置しているから、部屋は外よりも寒い感じ……、そんな
バカなことは無かろうが暖めても暖めても室温上がらず。机の下には足温器、膝暖盤、更に温風ヒーター。背中にはハロゲン
ヒーターの遠赤外線をあてている。こうまでしないと、仕事が出来ない。ふくらはぎから下の冷え性だ。机に向かっている限りは
快適となるが、部屋全体が温まるわけではなく、よって机から離れられない。机にしがみ付き仕事をする破目に。
これが集中力のなせるワザならよいのだが……。
(2月3日)
■キャラクター{ミンミン}シール作製
もう何種類のシールを作ったろう。 相模女子大学の「子ども教育学科」は誕生まもない。いずれ
”卒業生の現場での評判”が歴史をつくってくれるであろうが、それまで手をこまねいているわけにはいかない。
イメージづくり(戦略)の一助にとキャラクター展開を試みている。
元気、明るい、素朴、自由……MINMINちゃん、頑張れ!!!
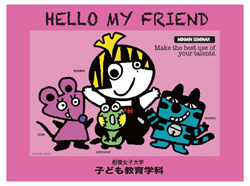
 、
、

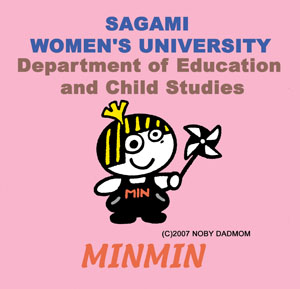
| 1月のアトリエだより |
■コンソーシアム大学……”仕込み”続く 「お化けの衣装」
渋谷の生地屋さんで白と黒の天竺木綿を買う。白はお化けの衣装、黒は○○○仮面のもの。頭からすっぽり
かぶる簡単な構造。子どもたちが作る仮面を引き立たせるよう体を覆い隠すのだ。まずはぼくが黒いので登場、
アシスタントの学生3名は白いお化けになってもらう。5日に試作品を作るが、学生もぼくも、子どもには勝てっこない。
”勝てっこない”は、競う気持ちの表れだ。もちろん、子どもなんかに負けてられない!想像力で、いざ勝負!
遊んで楽しんで、真剣勝負だ!”勝負”は”心のままの表現”と置き換えよう。そう、”心のままの表現”は
比べるものではない。当たり前のことであった。
(Jan.30)
■コンソーシアム大学 「作ってあそぼう」申し込み締め切り!
子どもと親とで作って遊ぶワークショップの申し込みは締め切られた。事務局より定員をオーバーしたとの報せあり。
熱心な方々の気持ちをかなえてあげたい。補助椅子を出して対応して貰う。
工作メニューは三つ。 2月6日、① 「世界に一つのミラクル仮面」(大きな覆面タイプと吹き戻しを使うもの2作)
13日 ②「絵変わり仕掛け絵本……あんなかお、こんなかお、どんなかお、みんなかお」20日 ③「イライライラ……コロ玉
バランスボード」作る喜びを味わってもらう。表現する素晴らしさを体験し、止みつきになってくれれば……。
頑張ろう!目一杯、精一杯やる!
5日にはアシスタントをしてもらう学生3名を特訓する。もちろん、ぼくも試作を楽しむ。それにしても教材の準備は大変!
仕事場は段ボール箱の山だ。買い集める、加工する、セットする(パーツを袋詰め)……、ああ今日も慌しく日が暮れた。
(Jan.29)
■造形応用 牛乳パックTOY② 「舌だし人形・・・愉快な仲間達」


 「こんなこいるかな」へ
「こんなこいるかな」へ
・アリガくん試作例 (「こんなこいるかな」バージョンを別項『こんなこいるかな』コラムに掲載)
造形表現活動(応用)最終回は牛乳パック(ミルクカートン)工作。材料はカートン一個半とゴム輪2本のみ。
カートンはTOY①同様裏返して使う。学生は始めの頃恐がっていたカッターナイフにも大分慣れてきた。手作業の
大事さ、それに廃物利用”創意工夫”する心を育てたかった。
TOY上部の持ち手を放すとパチン!の音とともに目が変化する玩具。単純素朴なことが「壊れにくい、飽きさせない、遊び方が工夫
出来る」など、よい遊びの条件の幾つかを満たしている。遊びといえばDSやPS一色の感があるが、自ら作る、その素晴らしさを
放棄しているようでもったいないことだ。遊びを創出する……ここにも自己表現がある。学習で疲れた学生が教室で
生き生きした表情に”蘇生”するのを見るにつけ、定まった答えのない表現の世界で遊ぶ(自由な心での表現)ことの
重要性を再認識する。
(Jan.27)





・学生制作作品例(舌は出たり引っ込んだりする。写真はすべて長い舌が伸びたところ)
■造形応用 牛乳パックTOY① 「回転円盤絵変り・・・六面相」



牛乳パックTOY制作その1 「回転円盤六面相」を作る
学生の積極性が感じられるようになってきた。バイト先のコーヒーチェーン店から、牛乳パックを大量に運んできた者、朝、研究室に
立ち寄り、パックの包みを置いて行く者……、牛乳離れが進んでいる若者が、何とかして授業に役立てようと頑張る姿……嬉しいことだ。
自主性こそ、創意工夫する心、自己表現する心、とともに学生に摺り込みたいことだから。
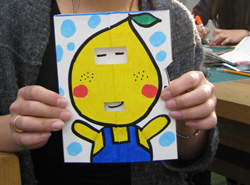

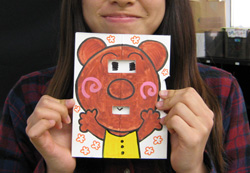

(Jan.22)
■二十四節気<大寒> 七十二候(七十候.七十一候.七十二候)
 |
●大寒は1月21日 ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
このところ寒い日が続いていたが、昨日今日は最高気温が14,5度。3月の温かさだ。明日は18度にもなるという。が油断は禁物。
あさって、金曜日はまたぐっと冷え込むとの予報。久しぶりのテニスを予定しているのに……。日差しに明るさが増してきた。
春が近づいている。もうすぐ立春だ(2月4日)。
(Jan.20)
■ NHK教育テレビ「絵本寄席」をご覧下さい


1月29日(金)午前7時45分~50分 NHK教育テレビ「テレビ絵本」にてえほん寄席のアニメが
再放送されます。『目黒のさんま』(有賀忍・絵 三笑亭夢太朗・落語)早朝ですが、どうぞお楽しみください。
■シラバス打ち込みと、紙芝居作画に明け暮れる
新年度の履修科目シラバス作りに大わらわ。昨年から提出がパソコン入力となり操作に戸惑う。キーボードから
20分離れると自動的にすべて消去されるし、「更新」「保存」が分かりずらく何度もやり直すはめに。10科目を
入力し終わる頃に漸く慣れたが。
授業が始まる前に、仕事の目処をつけねばと、紙芝居「だいじな たまご(仮題)」制作も頑張った。こちらの苦心は
鶏小屋の金網や、卵が割れて悲しむ少年の表現など。ストーリーが単調で、紙芝居の”単純明快、可視性”はクリア出来たとは
思う。が、やはり絵本も紙芝居も”面白くてナンボ”………不満がない訳ではない。
(Jan.15)
■エンターテイメント
正月テレビは殆ど見ない。ニュースを除いて。ただ、小朝の落語「親子酒」には抱腹絶倒。ろれつの回らない親子の酔っ払いの
掛け合いが見事。酔いが回るにつけ顔までが赤くなっていく様は感動物!話のおもしろさ、形振りの上手さ、完璧だ!
大学の帰り道、NHKラジオの「真打競演」を聞くことが多いが、漫才も落語も大笑いさせるもの少ない。話がつまらない。
生中継ではないし、”話芸”を収録するのなら、選ぶべきだろう。天才、小朝を聞いて思った。
■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候.六十八候.六十九候)
七十二候も最早六十九候。あと三候残すのみ。<小寒>の次は<大寒>。そして、
いよいよ<立春>……春の到来だ。
 |
●小寒 1月5日 ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
2010年元旦、鳩山、アトリエでの正月
アルコール漬け。 ワイン3本、それに畏友の杜氏、宇都宮くん恵贈の酒「月の滴」一本空にして二日間の正月終わる。
2日の午前二時頃だ、外は一面雪に覆われた。日本各地で大雪のニュースに、鳩山もかと。美しさたるや北欧の写真にある
銀世界(定番の表現だねえ)だが、喜んではいられない。わがアトリエは坂道を下ったところにあるから、四駆ではないぼくの
車は登れない。チェーンもないからこれ以上積もると脱出ピンチだ!が、心配も”幸酒”酩酊の身には響かない、”なるようになれ!”
ところが、朝起きてみて目を見張った。雪は跡かたなく消えていた。おかしい、全く残っていないのは。地面も濡れていない。
何だったんだろう、一体。 確かに雪だった。四方の窓を開け確認したのだから。幻視の雪の原……?
多分、多分、コウコウと照る月明りだったのだろう。満月の明るさが田圃も畑も野原もすべて白く染め上げたのに違いない。
いや何だっていい。美しいものを見させて貰ったよ、いい正月だったなあ。幻の雪風景は当分の間、記憶の底に沈みそうにない。
(Jan.4)
あけましておめでとうございます

心に <日々新生・日々創造> を思い描くも儘ならず。本年も創作時間確保が課題となる。
創り出す喜びを知っているが、それ以上に創作の悩みは深くきつい。頼りは”突き抜ける気力”なるも、
何とも心もとない。瞬間瞬間を燃焼させるほか手はないことだけは確か。
よい一年でありますように。
(Jan.1)
| 12月のアトリエだより |
■薪割りに鳩山へ。忙しなく日帰り
毎年、正月といっても元旦と2日のみだが鳩山のアトリエで過ごすことにしている。日がな飲み続ける為にはストーブにくべる
薪を手当てしておかねばならない。チェーンソーで丸太を切る。頭も体も大鋸屑だらけだが、作業は嫌いではない。太い丸太も
乾燥していると、鉞で気持ちよく割れる。薪作りは一歩も外に出ず酩酊読書三昧する二日間のための儀式だ。このまま鳩山に
留まりたいのを我慢して渋谷に戻る。溜息が出る、年賀状書きが待っている。
(Dec.30)
■コロコロ コロ玉 バランスボード……ゲーム盤試作
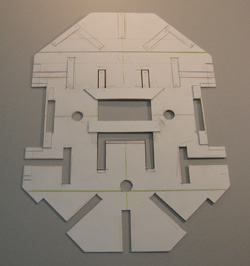
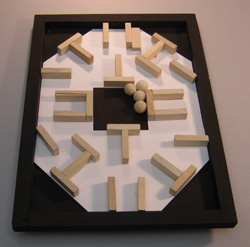

『さがまちコンソーシアム』(2月開講)の受講者は小学1~3年生と同伴父兄。ここ数日ワークショップの”メニュー”を
考え試作している。創造的造形遊びが大きなテーマだが、楽しく作る、遊ぶ……頭より手を使う遊びを提案する。
① 「世界に一つのミラクル仮面」(大きな覆面タイプと吹き戻しを使うもの2作) ②「絵変わり仕掛け絵本……あんなかお、
こんなかお、どんなかお、みんなかお」 ③「イライライラ……コロ玉バランスボード」①を除き材料費がオーバー、受講者は
得した気持ちで帰るだろう。いや、何より自己表現の素晴らしさ、楽しさを体感するだろう。①は覆面デザインの自由度、
②は回転版使用によるユニークな絵本のおもしろさ(親子合作)、③の微妙な手加減が勝負のポイント!……魅力一杯と自負。
興味のある方はご参加ください。
(Dec.28)
■メリークリスマス!


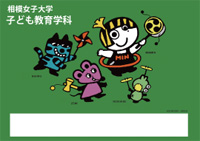
幼稚園、保育園、障がい者施設でのインターンシップ等で学生が着用するエプロンのシールや、IDカードのデザインを
制作。自分の年賀状も儘ならないのに大学の”雑事”に時間をとられる。この分だと年賀状は無理だ。
このところ、マックが不調でパソコンに向かう時間が多くストレスとなっている。シラバス提出の時期だが、メール送信が
義務付けられており、何としても修復を図らねば。
大学の図書館で冬休みに読む本を二冊借りた。アントワーヌ・ブールデル「芸術と人生に関する手記」これは昨年に
続きまた借りた。ミシェル・アンリ「見えないものを見る---カンディンスキー論」……デザイン学生時代が懐かしい……。
ウイスキー片手に酩酊読書の正月が、わが短くも豊かな幸せな時間。シラバス、仕事(紙芝居ほか)コンソーシアム大学の用意
(試作・レジュメ)教材購入手配……ああ読書三昧は夢と化すか。
(Dec.23)
■二十四節気<冬至> 七十二候(六十四候.六十五候.六十六候)
 |
12月22日は冬至 (1月5日)は小寒 ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (12月31日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
文字通り”師走”。あたふた走り回っている。慌しさこの上ない。水金土曜日は大学の研究室にいた。月曜日返却する絵本AB2クラス
41点の講評に時間を費やした。
昨日は今年最後の授業。何作かを取り上げ創作の魅力について話す。作品全部講評、合評も意義あることだが、学生は次の
課題に取り掛からねばならず数点のみとした。
絵本制作を中心とした「楽習絵画造形系」はかなり時間に追われる。ミニサイズとはいえ3冊作るのは詰め込みぎみかも。しかしながら、
短期間、緊張感、集中力を持って制作にあたらせる。努力した後には達成感があるだろう、これも一つの狙い。
ぼく自身の創作はこの後だ。大晦日までが勝負。
(Dec.22)
■切り紙の連続模様、パターン作成



実践遊び学の「紋型切り紙」の応用編、造形表現「連続模様」演習(実際はペーパーチェーン制作)。この授業風景の
撮影が入った。来年度の大学案内の学科紹介用だが今年同様、ぼくの担当する美術図工系となった。撮影は90分授業の
始めと、学生の制作物が揃う終わり頃にしてもらう。
前回は「不定形フォルム……お化け制作」がテーマだった。個性溢れるユニークなお化けたち、そして今回は壁面(構成)装飾や
絵カード等利用範囲が広い造形「ペーパーチェーン」。魅力的な作品が多いのにほんの一部しか掲載されないのが惜しい。
■師走ももはや数え日、テニスもまもなく打ち納め
5面あるテニスコートにぼく一人。かつてクラブの休業日だったこの日は会員登録が少なく(クラブは利用曜日指定制)
振り替え利用でもない限り誰も現れない。50分、フォア、バック200球サーブ練習する。気温10度に満たない肌寒さでも、
一汗かき気持ちよく仕事場に向かう。これで、サーブの威力でも増せば嬉しいけれどそうは問屋が……。
世田谷通りが渋滞。恒例のボロ市が開かれているのを忘れていた。繁華街は嫌いだが、この賑わいは楽しい。
”面白い物”をさがし、店主をひやかし、雑踏を押し合いへしあい歩く、年末の風物詩だが今年も通り過ぎただけ。残念!
■二十四節気<大雪> 七十二候(六十一候.六十二候.六十三候)
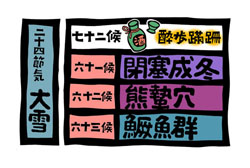 |
今年の大雪は12月7日 (冬至は12月22日) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
大学キャンパスの正門から図書館に続く銀杏並木は黄金のトンネル、であった。先週までは。今や降り落ちた黄葉でアスファルトの
両側は黄金の山。構内のイチョウは新校舎建設でダメージを負ったものの、まだ恵まれている。
街路樹のイチョウは、近頃は黄葉する前に枝を切り落とされてしまう傾向にある。落葉の清掃に手を焼くからだが、これは人間の
傲慢だ。緑陰の恩恵にあずかった後は”はい、お仕舞い!か……。目を楽しませる初冬の景色が心の栄養なのに。役に立たない
ものは徹底的に排除される……効率主義の人間界の犠牲者だ、イチョウも受難、可哀想。
(Dec.7)
■[ピリペンコさんの手づくり潜水艦]・・・・人生に大切なものは?
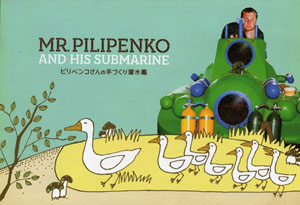
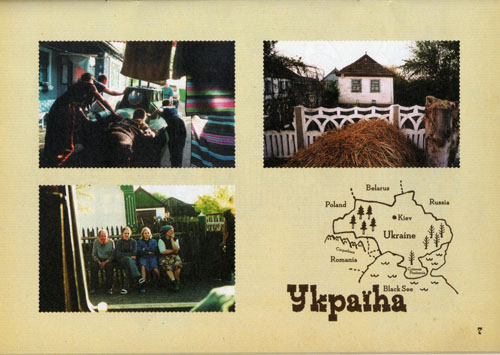
ミニシアターで『ピリペンコさんの手づくり潜水艦』を見る。
コルホーズでクレーン車の運転手をしていたピリペンコは30年来の夢「潜水艦を作って黒海にもぐる」を果たさんと
年金をすべてつぎ込み独り奮闘する。”道楽”に奥さんはしかめっつら。頼りは70年代のボロボロの雑誌
「水中スポーツマン」の記事。廃材を集め完成した”イルカ号”の試運転は村の沼。ピリペンコは水が漏れても
へこたれない。大草原に置かれた小さなワーゲンビートルを思わせる”イルカ号”がいい。リーフレット写真では
その手作り感が伝わらないが、工夫されたこの塊が可愛い。一つだけの夢をずうっと持ち続け、黙々と実行して
いく……、”静かな”執念に、その一途さに目が潤んだ。
淡々としている奥さんがピリペンコが黒海に向けて発つ日、目頭を抑えていた。心配なのだ。愛しているのだ。村人も
温かい。祝い会では、みな”最高の笑顔”。この笑顔こそ、人生の宝だ。この笑顔に究極の幸せがある。
今この世は金、金、金。政治もスポーツも。(たとえばプロ野球の年俸、たとえばゴルフの賞金王……金が目的化して
きた。いやだなあ)ピリペンコの生活は貧しいが、比べ物にならない大きな喜びがある。その表れが村人の笑顔だ。
現代人にあの笑顔は見られない。魚を獲って売る、ガチョウや羊や牛に囲まれる暮らし……昔は当たり前だった人間の
生活に感動を覚える。
この映画、新聞で見た監督ヤン・ヒンリック・ドレーフスの一言で興味を持った。「ウラジミール・ピリペンコの存在により、
この映画を作ることができたことを幸せに思う。そして彼のような人々の存在がなかったら、世界は今よりも貧しい場所に
なっているだろう」 『ピリペンコさんの手づくり潜水艦』は一年間のドキュメント。エンドロール前に流れる(映画には
描かれなかった)冬景色や生活風景が美しい。心がほんわり温まった。観客数数人のミニシアターを出て仕事場まで歩いて
帰った。余韻で、寒ささえ心地よかった。
(Dec.3)
■[ブルノ・ムナーリの言葉]
おとなのしるしに 懐中時計をつけてもらった
そのとき 僕は10歳で
でも 何時におとなになったらいいのか
よくわからなかった。 -ブルーノ・ムナーリ-
「遊び心」「創作・創造」「芸術とデザイン」それらの我が神様、ブルーノ・ムナーリ。ムナーリの絵本、「プレゼント」は
大大名作で、授業の始めに見せることにしている。同書と出会ったのが30年前、学生に見せて5年。超えるものナシ。
そのムナーリが生涯後半、新聞や雑誌、パンフレットに書き記した文章が『ムナーリの言葉』としてまとめられた。1~2分の
時間が空くと開いてみる。何処を開けてもよい。難しい言葉や記述は一つもない。闇雲に日々”独楽鼠”状態の自分には
自省の書だ。
「誰かが これなら僕だってつくれるよ と言うなら それは 僕だって真似してつくれるよ という意味だ
でなけれ もうとっくにつくっているはずだもの」
「芸術における 最大の障害は 芸術を頭で理解したがる人々」
「貧しい芸術家は ゴミ箱の中から見つけた ちびた鉛筆で 素晴しい詩を書く
金持ちの 芸術家は 純金のペン先のついた 高級万年筆で つまらない詩を書く」
(by Bruno Munari)
| 11月のアトリエだより |
■[絵本]に埋もれた一日
人間社会学科、社会マネジメント学科の学生制作絵本を講評。30点余り見る。一冊ずつコメントを書く。面白い着眼をほめ、
「こうしたら効果的」「ネームの推敲を」とか次作への期待を記していく。一つ見るのに10分は掛かるから大仕事だ。
ほっとして研究室をでれば、もう夜の帳が下りていた。土曜日、補講授業しかなく学生姿もまばら。一人の先生とも出会わず、よって
本日は”会話ナシ”で終わった。もっとも、冷気が身に染む中、駐車場までの呟き「繰り言」は別だが………。
(Nov.28)
■「いないいないばー」工作のテキスト作り (絵画造形表現活動 Ⅱ)
「こんなこいるかな」の雑誌連載で人気が高かったものの一つに「いないいないばー」遊びがある。幼児は動きのあるものに
興味を抱き絵がパッと変わると目を見張る。
「いないいないばー」は、紙の裏表に絵を描いたものや、ぺープサートなど色々考えられるが、学生には簡単な仕掛け
カードを制作させる。絵は自由に描かせる。そして、その”物語”をテーブルを挟んで学生同士演じさせる。つくりは簡単でも、
演じ方(言葉の間、絵を変えるタイミング、感情)が大事。”自分のもの(技)”にするためには数多く作って見ることだ。
(Nov.23)
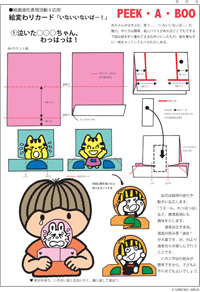
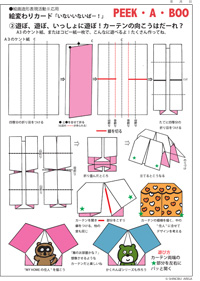
■二十四節気 <小雪> 七十二候(五十八候.五十九候.六十候)
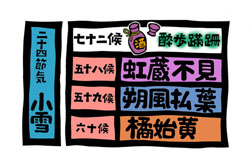 |
小雪は11月22日 ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
二十四節季も「立冬」から「小雪」へ。北風が身に染む。北からは雪の便りも。キャンパスのイチョウも銀杏をすっかり落とし
一部は黄葉が始まっている。が、”すっかり”は誤りだった。15~16日の激しい雨に叩かれ一粒も残ってはいないと思ったら、
一本だけ根元にバラバラ、撒いたように転がっている。木々にも、それぞれの”個性”があるんだなあ。最後まで頑張ったその
太い幹を見上げて、ぼくは何故か嬉しくなった。
(Nov,18)
■古代ローマの遺産展を見る (国立西洋美術館)
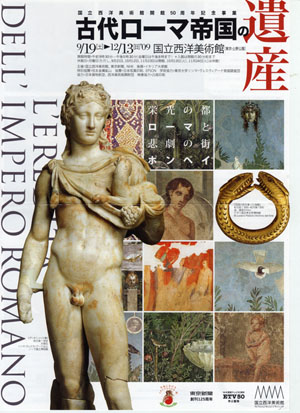
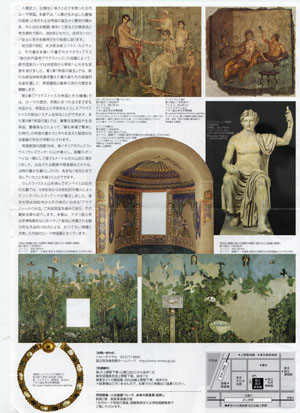
「黄金の腕輪の家」居間のVR(バーチャルリアリティ)映像に見入る
2000年前ヴェスヴィオス火山噴火で埋もれたポンペイ出土品と東京大学ソンマ・ヴェスビアーナ
発掘調査団の研究成果の紹介。ソンマ・ヴェスビアーナ出土の豹を抱くディオニュソスが優美。ポンペイ
出土のエロスの噴水彫刻(イルカを抱く天使)も完成された美しさ、息を飲んだ。古代ローマの美意識
たるや現代の比ではない。
豹を抱くディオニュソスは火山灰に埋もれ頭部だけ露出している発掘現場写真とを比べて見た。発見時の
興奮が伝わってくるようだ。金貨や装飾品も数多く出展されていたが、ぼくは、3つの火口のあるランプ、
ブロンズ製の秤、テーブルの足、ロシアのサモアールの原型やおそらく焚き火をしながら湯を沸かしたので
あろう砦形サモアール(取っ手が付いているからポータブル?)水道の弁、鉛製のフィルター(排水目皿?)
に興味を持った。水道の弁や目皿を除けば、いずれも精緻な装飾がほどこされている。家具調度が豪華
なのは帝政の皇族か大金持ちの邸宅からの出土だからだろう。ぼくの好みは“美術品”より、錆びた鉄の
鍬や熊手、30センチほどもある特大の庭バサミなど。
■現代童画展終了
展覧会最終日、上野に。美術館に通ずる公園のアスファルト道は、ケヤキの落葉が敷き詰められたように覆われている。
掃除人が掃いても掃いても追いつかない。一昨年前までは開催が12月で、落葉は黄金色のイチョウだった。
会場を一巡り、描きたいモチーフの追求が甘く、心まで届く作品が極めて少ないと感じた。簡単に”描いてしまう”、
”描けてしまう”危うさに気づかない制作者が多い。止むに止まれぬ表現欲求……これに尽きるのだ。その想いなくして
筆をとるべきではなかろう。
(Nov,12)
■第35回現代童画展出品作 『SHED』 91・5×145㎝ アクリル ・ ガッシュ


多くの方に見ていただきたい。上野の森にどうぞお出かけください。
<東京都美術館・11月12日(最終日1時)まで>
■二十四節気<立冬>、 七十二候(五十五候 .五十六候. 五十七候)
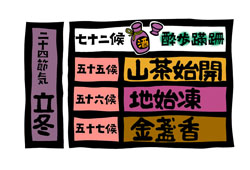 |
立冬は11月7日 ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
風静か、穏やかな日和だが、テニスコートにポロシャツ、短パンの姿はぼくだけ。若ぶっているつもりはなく、
冬のウエアを取り出す時間の余裕がなかっただけ。試合後の汗が冷たい。固くなっていく体をヒーターを入れ
温めながら帰る。普段なら食料を集めていくスーパーにも立ち寄らずまっすぐ渋谷へ。仕事の合間の僅かな
時間、慌しいテニスも打ち納めが近づく。晩秋から冬へ、景色が変わってきた。
■ピアノとコンピュータの競演は激しいものだった。
「生成する身体知のクオリア」と題する音楽を聴いた。(東京オペラシティ)
[*偶然「投発」無常「投失」]は尺八に舞踏、映像のコラボ。[*g・a・t・a・r・i]
ベースに映像、[*天使の梯子]がピアノ。フルートデュオあり弦楽四重奏あり。
他全7タイトル、いずれも難解。思考はやめ音に集中、風景や情景を頭に描き聞き入った。
CGのバックグラウンドのフラッシュがまぶしい。波が集合拡散燃焼する映像が音を喰う。
作り手のテクニックがぼくには邪魔だった。
[*天使の梯子](菅野由弘/曲・大竹紀子/ピアノ)は、大叙事詩。天使の梯子(厚い雲の
切れ間から、光の筋が何本も降りてくる光景をいう。光が降りてくる。が、私の中では、光の帯を
昇っていく感覚がある。〈菅野由弘〉パンフより)を、いつしかぼくも昇る体験をしていた。
演奏開始直後左端の鍵盤がドンドンドンドンドンと響く、まさに天に架かる梯子を一足一足
昇って行くようだ。腹に染み入ったころ静寂を破る嵐あるいは戦闘または破壊。これが激しい。
鍵盤を叩く大竹の腕が折れんばかりの強烈さ。シンセサイザーとのマッチングも流石、微動だに
できず金縛り状態。演奏いや格闘が、強烈な、心地よい緊張を与えてくれた。鼓動の高鳴りは
幾条もの光が見えたからだろう。
今日昼間、すべての時間を提出書類書きに費やし(過去の,データの処理)、うんざりしていた。
“後ろ向き”は嫌だ。義務付けられているとはいえ、苦手で嫌悪感さえある。前向き即ち、創造や
制作と対極の“後ろ向き生活”の後のコンサート。足を運ぶのが重かったが、救われた。芸術の持つ
力に救われた。感謝。
(Nov.1)
| 10月のアトリエだより |
■もうすぐクリスマス。その前にハローウイン!
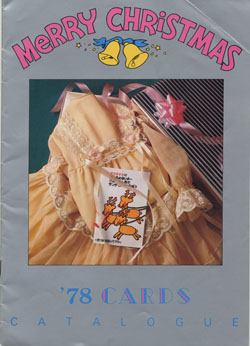


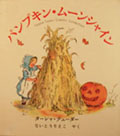
クリスマスカードに応用できるポップアップの仕掛けを教える。初日は3種、二日目は2種とそれらを組み合わせての
自由制作。これで仕掛け絵本のペーパーメカニズムの基本が分かったと思う。学生のもっとやりたいとの声があがるが、
次の課題に移らねばならない。いつも中途半端の感あり。先日は予定になかった「ハローウインペーパークラフト」を
はさんだ。”とび入り”だが喜ばれた。早速アルバイト先で創って飾ったとの報告も。かぼちゃのおばけ、魔法使い、コウモリ、
ゆうれい達が店先を飾ったのだろうか。
写真は資料にひっぱり出したカードのカタログ。ぼくは数点制作している。表紙の三頭のトナカイのイラストもぼくの作品。
左下に「この ひもを 引いてください」とあり、引くと………お風呂のシャワーカーテンがめくれ……
入っているサンタさんが、大慌てで飛び出てくる仕掛け。他のもユーモア、面白さを重点に作ってある。
もう30年も前のもの。若さで仕事に挑戦していたころだ。
ハローウインが近い。かぼちゃをくり抜きジャックオーランタンを作ったのは一昨年。まだ少しは余裕があったのだ。
慌しい毎日に、ちょっぴりでも息抜きを………出るは溜息のみ。
(Oct。26)
■現代童画セルビア展のポスターを受けとる
セルビアに行ったメンバーK氏よりポスター、チケットを受け取る。ぼくの作品『雪催い』がデザインされている。
ツアーの写真ファイルをI氏が見せた。宿泊したコテージ、バイオリン製作所、絵描きのアトリエ、……
ぼくを羨ませるのに十分だった。行きたかった。コバチッツア村のナイーブアート美術館よりむしろ、I氏のカメラが
捉えた田園や、野外彫刻物、市場の風景に興味をもった。セルビア行きは仕事を考えると如何にしても不可能、
残念であった。
(Oct.24)
■二十四節気<霜降> 七十二候(五十二候.五十三候.五十四候)
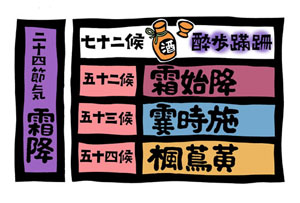 |
霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
いよいよ展覧会の秋。現代童画展も今年、35回を迎える。23,24両日は審査会。上野の東京都美術館
地下3階に籠ることになる。窓がない、陽がない、風がない……窒息しそうで気が重い。それでも、ワクワクするような、
ドキドキときめくような絵に出合えればと……。(滅多にはないが)
わが作品『』SHED』も、狭いアトリエで見るのと天井の高い展覧会場では感じが違う。搬入して暫くぶりに見る作品、
”ご対面”が楽しみだ。
(Oct.21)
■月刊幼児絵本「なかよしメイト」1月号は「もう いくつ ねると おしょうがつ……♪」
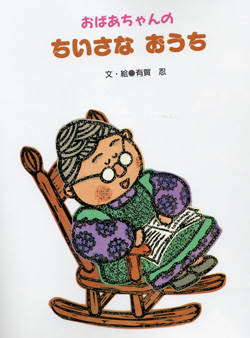

メイト刊「おばあちゃんのちいさなおうち」がおはなしメイト11月号として再刊された。15年ほど前でた初版本には
奥付にぼくのポートレートが載っている。若い。当たり前だが、別人かと思うほど若い。本人は別に何も変わらないと
思っているが、写真はまさに青年!”何も変わらない”点は創作姿勢、生活だ。「日々新生、日々創造」を座右の言葉として
描き創る日々……これからも生きている限り全くかわることないだろう。
2010年新年号巻頭の「うた」は「おしょうがつ」もう いくつ ねると おしょうがつ。おしょうがつには たこあげて
こまを まわして あそびましょ。はやく こい こい おしょうがつ♪♪♪
イラストには「おばあちゃんのおうち」に登場した面々を描いた。おばあちゃんと9ひきのネコたちだ。2009年11月号を
見た子どもが「あっ あの おばあちゃんだ!」「あっ、この ネコの絵本、持ってる」などと反応を示すだろうか。絵本と
月刊雑誌のリンク、おもしろいと思ってやってみた。
(Oct.20)
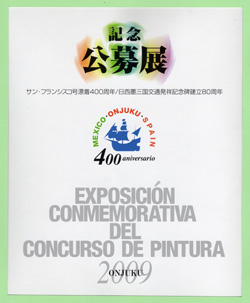

展覧会 9月17日(木)~12月8日(火) 月の砂漠記念館
主催 御宿町、サン・フランシスコ号漂着400周年日西墨三国交通発祥記念碑
建立80周年記念事業実行委員会
後援 外務省、メキシコ大使館、スペイン大使館、千葉県、NHK千葉放送局
■二十四節気<寒露> 七十二候 (四十九候.五十候.五十一候)
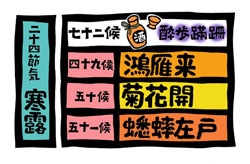 |
寒露は10月8日 (霜降は10月23日) ・四十九候 (10月8日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月13日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月18日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
8日、台風で渋谷の旧山手通りのエンジュの木にも被害が。太い枝が道路に落ちていた。落ちたばかりだろう、車が
避けるようにして走っていた。ぼくはこの道が好きで、バスで仕事場に向かうときは、終点の渋谷駅の二つまえの大坂上で
降りて歩くことにしている。国道246の交差点から代官山に至る大使館が並ぶ広い通りの両側はエンジュの並木道だ。
エンジュは今、長い莢豆を付けている。これが日ごと大きくなって降るように垂れ下がるのが見事だ。漢方の薬の材料と
聞き、4年前アトリエの庭に幼木を植えた。太さ7~8センチ、高枝バサミも届かぬほど伸びたが莢豆はいまだ付ける気配がない。
以前、旧山手通りの西郷山公園付近で枝切りされた莢豆を仕事場に持ち帰り活けたことがある。(アトリエ便りでも紹介)
ウグイス色の数珠を包んだ莢の形がおもしろく、写真にも撮った。
屋根が飛ぶかと心配させた強風だ。鳩山のエンジュは倒れてはいないだろうか。ここ暫くは出かけられず確認するすべもない。
9日(金)秋晴れ。風もなく”テニス日和” 朝1時間サーブの打ち込みに行こう。午後は大学へ。大学にも立派なコートがある。それを
横目に研究室と美術準備室に入る。
(Oct.9)
■愛用のくるみ割り器 胡桃の殻で”良いもの”作ろ! 仕事場のガラクタ達 vol,2


鳩山に植えたオニグルミが実をつけた。たった一つだけど、嬉しくてアトリエに行く度に家に入る前に真っ先に見ては
楽しんでいた。それが、消えていた!姿かたちがみえない。落ちたのかと思い雑草を掻き分け探したがない。
胡桃には幼少時の思い出があり、”収穫”を心待ちしていた。残念だ。
現代童画展出品作「SHED」をあらかた仕上げ、アトリエから運び出す。東京に運搬する車中も、消えたクルミが気になって
しかたなかった。
ぼくはクルミが好きで、店頭で見かける必ずといって良いほど買う。胡桃の収穫時期は夏の終わりから秋の終わりだが、
年中店頭にはなく、さりとて大量に買い込んでおいても酸化して”油が回り”ダメ!今がクルミの時季。渋谷の仕事場では夜、
ウイスキーのつまみに、胡桃を割っている。ナッツクラッシャーは鋳鉄製のもの。写真右のものは二十数年来愛用の英国製。
フォルムが美しく機能性も抜群だ。木製のスクリュータイプも試したが、スクリューの溝が磨り減ってクルミの殻を押しつぶす
圧力が減じ、鋳物製には敵わない。写真左のものはクルミを置き叩き割るもの。昨年大学の帰り、相模大野で見つけた。
50~60年代のUSA製品だろうか、鋳物の裏面にはOKLAHOMAの刻印が。こちらも機能性は?上手く割るにはコツがいるから、
ウイスキーや本に集中できない。まあ、クルミを割る作業を楽しむためのものだろう。
クルミ割り器はこれだけではない。最近では胡桃の袋に入っている三角の金属片を使うことが多い。胡桃の底の小さな穴に差込
ねじるようにすると、パカンときれいに割れるからだ。この胡桃の殻でぼくはいいものを作っている。いいもの?勿体ぶらないで
書いてしまおう。それは「鈴の鳴るクルミ」。 小さな鈴を入れボンドで張り合わせるだけだが、もう相当量たまった。何にするかって?
秘密、秘密。いずれ、使用時がきたらまた報告ということで……。
(Oct.7)
■漸く雨上がる。さあ額縁のペイントだ!

「現代童画展」出品作の額縁作り。ペイントは数回おこなうが、仕上げ予定の今日は生憎の雨。もう日もせまっており、
作品ともども完成させねばならない。午後漸く雨があがり薄日がさした。待ってましたとばかり、仕上げのペイント。
今回は使用しない、10号~30号の額縁も”この際”とばかり、塗りまくる。
作品も完成間近だが、額装は乾燥させてから。
「ずっと描き続けたい……」後ろ髪引かれる思いで大急ぎ東京にもどった。ハローウインのクラフト、レジュメ、クレヨンまる、
雑誌の仕事……雑事も多く片付けられないでいる。すべて、やらねばならぬことだけは確か。しんどい!
(Oct.3)
| 9月のアトリエだより |
■二十四節気<秋分> 七十二候(四十六候、四十七候、四十五候)
気澄み空晴れ渡る。気分爽快といきたいところだが、ゆとりなく仕事を”こなす”日々。夏の休みもとれぬまま、
大学の秋学期を迎える。ひたすら仕事。ただただ仕事。仕事三昧が幸せであるか否かはぼくの場合、すべて
集中度(燃焼度)による。忙しさを忘れさすほど夢中になれる仕事は、結果はともかくそのとき心は満たされているはず。
それにしても創作に拘われる時間が確保できない。16日学会、17日研修会での講演と慌しく過ぎていく時間に、
焦りもがく毎日。板絵制作も途中なのに鳩山のアトリエに行かれない。制作中の作品『SHED』(小屋)が「続きを描け!」と
呼んでいる。(幼き)わが子に幾年も合えぬような心持だ。筆をとりたい。うずうずしている。
(Sep.18)
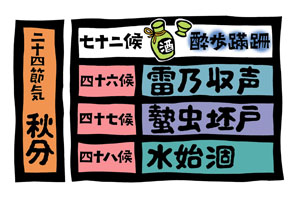 |
9月23日は秋分 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
■二十四節気<白露> 七十二候(四十三候、四十四候、四十五候)
アトリエの下の田圃、稲穂が垂れ秋の風に揺れている。田の主、石井さんの麦刈りが始まる頃には
ぼくの板絵制作も終わっていることだろう。とは言え、やがては完成し”筆を置く”状態になれるか自信の欠片もない。
白いパネルに絵が現れるか……、今は創作に入るとき感じる恐れに似た気持ちだ。
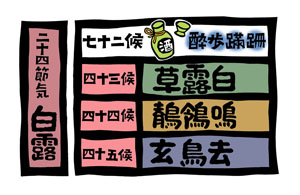 |
9月7日は白露 ・四十三候 (9月7日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (9月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
終日板絵制作に没頭する。
刈払い機のエンジン音が響いてくる。身の丈を越す伸び放題の雑草、手に負いかねて「シルバー人材センター」に
頼んで刈り取ることにした。枯れかけた栗の木も2本切ってもらう。切らないで残すものに赤いテープで目印をつけた。
栗は大きな古木があと一本、それに数年前植え大きく成長した3本となった。いずれも栗は今、正に収穫のとき!栗の
木の周りから草刈を始めてもらったから栗拾いはしようと思えばできる。が、時間がない。それでもと、棒で叩き落し
(落ちているものはほとんど、虫が食っていてダメ)20分ほどで数十個。仕事を気にしながらで楽しくない。一分が貴重。
一分でも板絵に向かっていたい。
制作は時間と戦うものではない。時間の経過に溜息をついては、進み具合に焦りを感じストレスでイラつく……、丸二日間、
仕事以外何もせず、腕や手や顔に地塗りの絵の具のついたままで、車を運転帰途につく。明日からは、大学の「絵画造形
表現活動Ⅱ(応用)」のレジュメを作成しなくてはならない。こちらも作品試作
→ テキストだから時間を要す。ぼくは
”ほどほど”ができない。”これでもか” ”こんなのはどうだ!”となるから、止まらない。止められなくて時間が足りなくなる。
悪循環!いつものことだ。進歩なし!
(Sep.6)



鳩山のアトリエで制作に入る。作品イメージはSHED……小屋。一体何が出てくるか。思い出か……、歴史か……。
板絵はタイトルやイメージが先行するときがある。描きたい世界が自然と溢れ出る状態がBEST。今回は時間が迫って
いるし、気が気ではなく辛い仕事だ。
雑草生い茂る小道をなんとか進み建物にはいるも、いつものことながら、カビ!カビ!カビ!パネルすべてが白い
ポツポツ、運び出し並べて日光消毒する。制作に水を差される。嫌になってしまうが仕方ない。観念して一枚残らず
乾したが、半日費やしてしまった。その後は10時間はぶっ通し彫っただろうか、右腕がパンパンだ。中腰にもなるから
太ももが張った。腰も痛い。
食料買出しにでる。薄明かりの中で、ボーと白く光るものがあちこちに……。カラスウリの花だ。レース状、繊細極まりなく
清らか。ボー、ボー、ボー……、幻想的な景色、朝にはしぼむ、ほんの今だけ、その姿ほとんど誰にも見せずひっそりと”
咲き誇って”いる。美しい。野辺が昼より美しい。
庭も中に入れないくらい雑草が生い茂り、鬱蒼としている。かき分け少しだけ進む。メープルシロップを採ろうと、夢を
描いて植えたサトウカエデが心配だった。大きく伸びたイタリアンパインの木立に囲まれてしまい日が当たらなくなっていた。
少し枝落とし、根元の雑草を抜いた。サトウカエデを”優遇”する。
大きな実が一つ、枝に突き刺さるように成っている。オニグルミだ。苗木を植えて5年目で、初めて実を付けた。6~7センチは
あろうか、大きな見事な実だ。たったの一つだが、嬉しい。信州藤沢村で少年期を過ごしたが、オニグルミを割るのに苦労した
思い出は忘れない。殻が西洋胡桃と
違ってバカ堅いのだ。鳩山のオニグルミは、いつ割ろうか。「板絵完成祝い」の、ささやかな楽しみにしよう。
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■ジョルジュ・ビコー展に、駆けつける。閉館前、滑り込みセーフ!(東京都写真美術館)
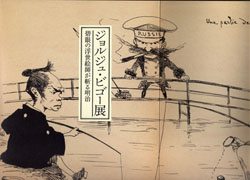
ジョルジュ・ビコー「碧眼の浮世絵師が斬る明治」展を最終日に観る。いつも展覧会はお終いに近い頃になってしまう、慌しい。
珍しい来日前の作品や小説の挿絵、それに日本滞在中(1882-1899)の「クロッキー・ジャポネ」等の四大画帳と見ごたえあり。
痛烈な皮肉を籠めた風刺画もさることながら、ぼくはエピナール版画に興味があって出かけた。(エピナール版画=18世紀以来
フランス各地で発達した民衆版画の一種(展覧会図録より) は石版で刷られているからとは言え、その表現は1枚の漫画だ。
聖人の画像、イソップの童話、各国の兵士像、道徳話、動物譚などがコマワリ漫画で描かれている。対象は女性や子どもだという。
行商人が宣伝用のチラシとして配ったとも。
ノンブルをみると、3110とか4248。凄い号数だ。フランスのみならず外国の風俗絵、話満載で、「日本の子どもの遊び」では、
兵隊さんごっこ、羽根突き、鞠つき、凧揚げが紹介されている。楽譜と歌詞のついたエピナールも多数あった。たて40センチ×
よこ30センチの色彩版画を覗き込むようにして見入った。美しいというよりは、大人がまじめに子どもに作っている姿勢が熱い。
それに比べ、現代の幼児雑誌のレベルの低いこと。(内容の薄いこと、テレビ偏重、芸術性、アート感覚なし)それでも、
昭和30年代、40年代、50年代の月刊雑誌は違った。季節感、童謡、生活絵話、魅力たっぷりの付録(工作)、知恵遊びなど満載で、
そこには失われた”熱さ”があった。
当時は通俗であっただろうエピナールが、ぼくにはとても”熱く”思えた。
板絵のモチーフが漸く決まった。『SHED』……小屋、納戸、物置。
鳩山のアトリエ、訪れるのは実に久しぶり。小屋に続く小道は雑草に覆われているだろう。通れるかなあ。
例年より一ヶ月遅い制作開始だ。身魂傾けるしかない。
■二十四節気 <処暑> 七十二候(四十候、四十一候、四十二候)
 |
処暑は8月23日 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
予定より一ヶ月遅れで展覧会用パネルを製作。キャンバスと違い前準備が大変だ。鳩山のアトリエには100号サイズが2枚
在庫あるものの、制作期間を考えると、今年は大作は無理だろう。60~80号が限界だ。
ここ一週間、仕事が思うように進まず焦っている。相模原市のコンソーシアム(市民大学)に、開講講座のメニューを
提示しなくてはならない。対象は小学生とその親としたものの、ユニークで面白い「創造的造形遊び」表現を組み入れようと
頭を悩ましている。
子どもは胸をワクワクさせて待っている(はず)。だが一旦つまらないと感じると直ぐそっぽを向いてしまう。
正直なのだ。おもしろくて、奥が深く……答えが一つではない……、右脳を刺激活性化する微細な手の運動を
ともなう、今まで見たこともないと言わせる造形表現(遊び)を提案しよう。
(メニュー三つは近日発表します。)
(Aug.23)
■うっとり……、闇に開くカラスウリの花

炎天下にノウゼンカズラのオレンジ色が暑苦しい。とはいえ、ぼくは橙色が大好きで、今日のTシャツも燃えるような
オレンジ。大学の頃、合宿にもって行ったオレンジの太糸木綿のサマーセーターを、今も覚えている。洗って洗って
色褪せしても着続けた。袖を通すときの肌触りがよく焼けた体に似合った(と思っていた)。
様々な記憶は飛んでいっても、色の思いではいつまでも鮮明。何故だろう。
昼の耐え難い暑さが嘘のように、夜風が心地よい。納戸の格子に絡みついたカラスウリの花を摘み取る。写真は
ブルーのタオルを敷いて撮った。繊細なレースのような白い花は朝には萎んでしまう。儚さを微塵も感じさせず、一時
”満開の歌”を奏でる。静かに、厳かに……。太陽に対峙するノウゼンカズラと対極の美しさだ。
わがアトリエのある鳩山の野辺が目に浮かんだ。夕刻から咲き始めるカラスウリの花は、月光の下、野辺の一角を
ボーと白く染める。その幻想的な風景を今年は東京で夢想するしかない。鳩山で板絵制作に入れるのは何時のことだろう。
(Aug.17)
■奇想の王国『だまし絵展』 (BUNKAMURAザ・ミュージアム) 6/13 ~ 8/16
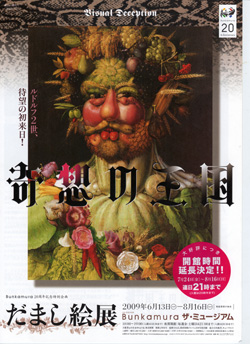
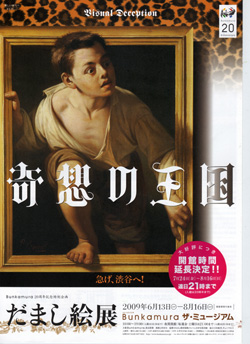
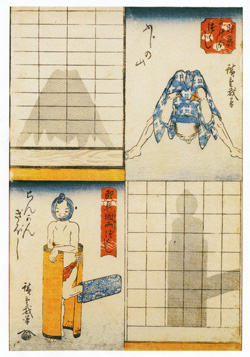
展覧会のチケットを無駄にすることが多い。この「だまし絵展」もまもなく終了とあって駆けつけた。ゴッホ展、フェルメール展の
ような混み具合。チケット売り場には長い列が。絵の面白さによることは確かだが、いささか複雑な思いだ。視覚を欺くような
仕掛けの絵は写実のもとで成り立っているのだが、”面白い”……目の満足はあるのだろうが、それまで。心の奥までは届か
ない、響かない。
歌川広重のさまざまな身振りを影絵にした一連の「即興かげぼしづくし」シリーズにユーモアとしゃれ心を感じた。想像させる
意味でのおおらかな楽しさだった。
連日満員、開館時間を21時まで延長している。美術が親しまれるのはよいことだが、視覚の満足から、どれくらい心を満たし、記憶に
残るのだろう。アイディア、面白さ、奇想……、ぼくはしっとりした絵を静かに見たくなった。
(Aug.13)
■二十四節気<立秋> 七十二候(三十七候、三十八候、三十九候)
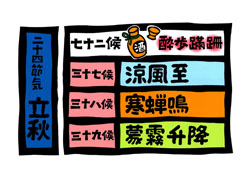 |
立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月12日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
暦の上では7日は「立秋」、なるも今、夏の真っ只中、この連日の暑さでは”立秋”など微塵も感じられない。今年も夏休みは早、
諦め、大人しく仕事のみの日々を過ごしている。とは言え噴出す汗に、仕事場からスターバックスへ”避難”。コーヒーのお代わりを
注文し、客が少なめ冷え過ぎの店内でアイディアを練ったり、講演の草稿を考えたりしている。快適は快適だが、ハサミを使ったり、
のり付けしたりの作業は憚られる。本を読む程度が一番だろうが、そのゆとりさえなく時間を気にしながら仕事に精を出している。
(Aug.6)記
”週一”となってしまったテニス。褐色の日焼けも褪せ、鏡に映る我が顔も生気イマイチ。今日はこれからコートへ向かう。
いざ参上……張り切ってはいるものの、常連さんに返り討ちに会うのは必定。夏休み、コートは学生たちに占領されているかも
しれない。ひとりサーブを打ち込みスカッとしたくても今日は無理だろう。それより、炎天の下で日干しにならないようにせねば。
午前中だけの暫しの息抜き。午後は睡魔と闘いながらの仕事と相成る。
(Aug.7)
■オープンキャンパス「紙で遊ぶ」切って折って組み合す……1枚の紙で君はどこまで遊べる?



体験授業は生憎の雨降り。にも拘わらず、受講者は開始時刻の30分前から集まり始めた。準備中であったが教室へ
入ってもらう。定員36名に42名の高校生と付き添いの母親2名、本学の先生と、連れの保育士……、もう超満員。熱気で溢れた。
補助椅子、テーブルを出して何とか凌ぐも、用意した教材は40セット。授業を進めながら何とか間に合わせた。
今回は催しのコンテンツをレストランのメニュー形式にしたが、盛りだくさん過ぎたか、主菜Ⅱの「絵変わりカード18面相」を
賞味していただけなかった。メインディッシュは「デンマーククラフト・ハートバスケット」。本学に来る来ないは別にして、楽しんで
もらえたと思う。「頭ではなく先ず手を動かす……」「手先の微細な運動が右脳を活性化するんだ」「切り損ねても失敗と思うな。
そこに新しい形がある。ヒントがある」「1枚の紙でどれだけ遊べるかが勝負。想像力だね」「想像力は創造力につながるんだよ」……
そんなことを喋りながら、110分が過ぎた。あっという間だった。子ども教育学科の二年生3名のアシストがありがたかった。
普段の授業さながら、与えるメニューは豊富。むしろ過食気味だったろう。ぼくはいつも多く与え、その内から何割かが消化できれば
よいという考え。今回出席した生徒たちも休む暇ナシで大変だったかもしれない。でも、充実した時間をすごせたことだろう。ときに緊張、
ときに集中……、これが肝要。ぼくの狙いは、ハードな作業の後の達成感を味合わせることだ。
(Aug.3)



・ペーパーチェーン。ネコの尻尾にしたものもあり ・ツリー両側の大型バスケットでアシスタントがキャンディーを配った
| 7月のアトリエだより |
■オープンキャンパスは8月2日。子ども教育学科「実践遊び学」「造形表現活動」模擬授業
2007年は「不定形フォルム……愉快な怪物たち」2008年は「ポップアップカードで遊ぼう!3種のメカ」
そして今年のテーマは「紙で遊ぶ……折って、切って、組み合わす!」盛りだくさんのメニューだ。
いかにして高校生に食いつかせるか。現代人は手工が苦手だからなあ。やるっきゃない!突っ走るぞー!
(Jul.31)
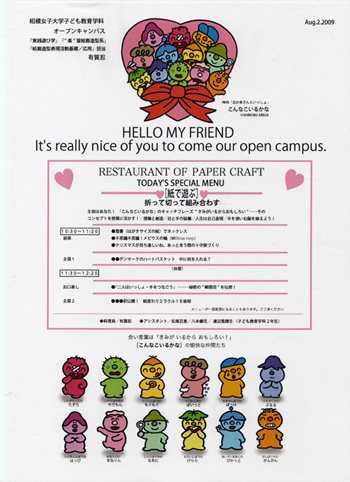
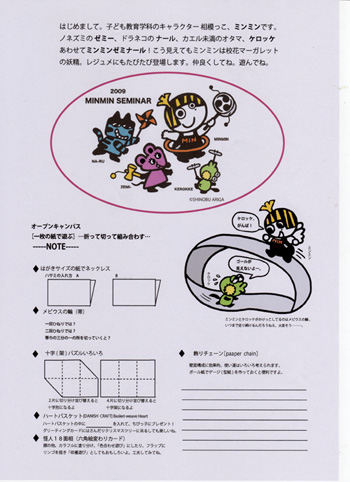
■春学期授業終了 (Jul.29)



■二十四節気 <大暑> 七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
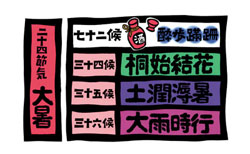 |
今年の大暑は7月23日 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
昨日2限の「絵画造形表現活動基礎」Aクラスの授業時間、11時過ぎ皆既日食が見られるはずであった。牛乳パックで
キューブパズルを作ろうというものだが、その手を休めて学生に日食を見る装置「ピンホール投影機」を制作させようと
材料を用意しておいた。が、生憎雨。雲は厚く、教室に入る前に日食のことは頭から消えていた。
いえ昨年来の学生からの”リクエスト”の課題制作に、皆熱中してそれ所ではなかったのだ。全員一秒も休まず手を
動かし続けた。一部の者は完成をみなかったが、多くは手こずりながらも厄介なキューブパズルのメカを作り上げた。
次回の最終授業でイラストを描き貼り付け完成させる。学生は春季末試験直前だが、「イラスト下描き」の宿題にも嫌な顔を
見せなかった。やる気を感じた。それも物づくりの楽しさを感じているからだろう。充実した時間を過ごさせること……これに
すべてを注ぐ。
8月2日はオープンキャンパス。ぼくは「1枚の紙の可能性」を追求する。ワクワク、ドキドキさせられる構成を考えねば。
山ほどのアイディアから選ぶのが大変。つい、制作に没頭、ぼく自身が遊びだしてしまうから。
(Jul.23)
■ペットボトルTOY 『イライラ ビー玉落とし』




”粗大な運動機能”に対しての”微細な運動機能”がある。”粗大な運動”は投げたり打ったり走ったり物を持ち上げたり、
体全体を使う運動。 ”微細な運動”は手先、指先を使うものであり、目と手の協働が不可欠。
(因みに他には、書字機能、音楽機能、口腔機能(話す)など)
「ビー玉落とし」は正に微細な運動。7個のビー玉をボトルを振り落としていく遊びだが、これがなかなか厄介。6段の棚紙が微妙に
波打ち平らでなく、ビー玉がすんなり穴に入ってくれない。そこでまた、ガシャガシャ振るのだが、焦れば焦るほど上手くいかない。
イライラが募る。
ビー玉はペットボトルの底に集めて又元に戻す。たとえ、往路がスムースにできたとしても、復路はそうは行かない。棚紙が
凹状であれば容易、凸状であれば、その丘なり山なりにある穴にそう簡単には入ってくれないのだ。所要時間を計らせる。
90秒もの、120秒もの、それ以上のものも。
この「ビー玉落とし」は別名『イライラビー玉タワー』。そもそも、タワーを作る(棚板6枚を差し込むのが大変!)のが、イライラの
始まり!学生には「今日は、がんがんイライラさせてもらうからな」と言っておく。誰だってイライラなんかしたくない。逃れたいもの。
それを、進んでイライラしようと言うのだから……、学生は初めは戸惑いを見せる。が、誰も助けてくれない。でもイライラしていてばかり
では、はかどらない。 仕方なく我慢してやる。やるしかないのだ。力いっぱい引っ張っても紙が出ない。ペットボトルの中に入ってしまう……、
棚紙が渡せない、そんな苛立ちも、苦労の末、完成を見ると大いなる喜びに変わる。テーブルあちこちでガラガラ、ガラガラ、そして
歓声があがった。これでよい。してやったり。何事も夢中にさせることだ。
(Jul.20)
■Tシャツ屋開店?


シルクスクリーン印刷で「ミンミン」キャラクターTシャツを作成。3バリエーション、それぞれ数枚の贅沢な少量生産。
狭い仕事場はプリント工場と化す。オープンキャンパスのアシスタントなど、協力してくれた学生に
プレゼントしよう。本日は白が中心だが、先日はピンクのTシャツ18枚を製作し学科長に届けた。
学生は擁護施設、介護施設をボランティアで回っている。そのときに着用するエプロンにミンミンを入れたいと申し出る者あり。
数名集まったところで、「エプロン、Tシャツにプリントする会」を開いた。ぼくからは声をかけない。学生の積極性を
待ちたい。自主性を伸ばしたい。
(Jul.16)
■テニスコート「貸切」状態!……ありがくん、アリバイなし!
関東甲信越地方が昨年より5日早く梅雨明けした。各地で猛暑日。東京も連日30度を超える暑さ。
このところ運動不足で気分が優れない。時間が取れない、仕事最優先、のせいにしてテニスもご無沙汰だ。
汗を流さねば、大したアイディアも浮かばない……、経験から分かっているのに「仕事」にかじりつく愚かさ。
思い切ってテニスコートへ。曜日を決めて規則正しく打ちに行った頃が懐かしい。今では出かけるのにも
決断がいる。
オムニコートに人影なし。ひたすら一人サーブ練習。ぴったり一時間フォアサイド、バックサイドに300球打ち
込むが納得いったサーブは一割もない。ただでさえ上達しないぼくが二週間のブランクだものなあ。ああ、
またこれがストレスになる。誰にも会わず、誰にも見られず(ハードコートのクラックを補修する工事人はいたが)、
11時にはコートを後にした。
(Jul.14)
■二十四節気<小暑> 七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
 |
7月7日は小暑 (大暑は7月23日) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月17日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
降ったり止んだりの一日だった。研究室と美術室まで傘をさしていくのが難儀。いつも荷物をかかえているから。
「スタンピング」ではティッシュペーパー12箱、新聞紙約半月分を使いきった。いつもこの調子だ。今日は
「キューブブロックパズル」制作で、新聞紙を運んだ。返却作品もあり両手は塞がっている。傘をさせない。
小雨の中を走る。移動の時間もない。いつものことだが。
(Jul.6)
■授業時間が足りない!
学生による教師評価(嫌な言葉だ)実施日が近づいている。非常勤も含め全教員が対象となる。肯定も否定もしないが、
アンケート記入に取られる時間が惜しい。学生の公欠願いも同様だ。介護施設や障がい者施設への実習に赴く学生が
堂々と「公欠届け」を持ってくる。本人がその日を望んだのではないが、ぼくの授業が受けられないのは痛いだろう。
演習科目は期末に試験をしないから、”帳尻合わせ”は不可能だ。体験が何をさておき肝要であり、欠席者は大変重要な
一コマを受講せずに終える。もったいない話だと思う。それくらい、ぼくは”中味の濃い講義を”やっているつもりだ。
半期15回授業にこだわる大学だが、学生評価に要する時間についても、当局は考えてほしいと思う。
(Jul.2)
■月の初めに……。 漢字が書けずとも、表現の楽しさを知っている学生は素晴らしい!エールをおくる!
アトリエだよりの更新もままならぬ忙しさ。「時間に追いかけられるな!仕事を追いかけろ!」は、新宿の小さな活版印刷屋の
壁に貼ってあった言葉だ。30年以上も前、封筒や私家版の絵本の印刷を頼んだ気のよいおじさんの”信条”だった。
今のぼくは、正に時間に追いかけられ、仕事にも追いかけられ四苦八苦の体。青息吐息、疲労困憊……、能力不足を認識
させられる日々。
学生は普段の授業のほかに基礎学力UP総合講座を受講する。その中に漢字トレーニングがあり、成績一覧を
見る機会があった。”ダメ……劣る”の学生には相当の叱咤がなされた模様。ぼくはその氏名を見て目を見張った。
我が「絵画造形表現活動」において優れているあるいは、ひたむきに、また楽しく取り組んでいる者が数名いたからだ。
無論、”漢字力”はあるに越したことはない。いや、基礎的、常識的な漢字くらい書けねばいけないだろうが、
さりとて、全面否定はいけない。ある部分が抜きん出ている者のそのポジティブな面を伸ばしたい。それを見逃さない、見つけて
応援するのがぼくの役目だ。漢字テストで傷を負った者たちを、次の授業で励ましたい。応援するぞ。答えのない、自由な表現の
世界で存分に自分を出してもらおう。「成績が何ぼのものじゃい!」と言わせたい。
(Jul.1)
・6月のアトリエだよりには1枚の写真も載せませんでした。カメラが壊れて以来の殺風景、ご容赦を!
| 6月のアトリエだより |
■キャラクタープリント用デザインを制作
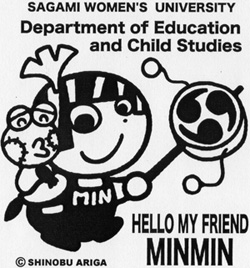
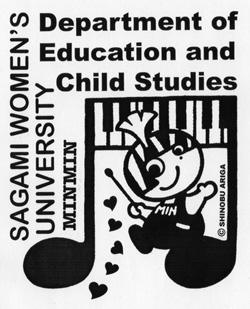
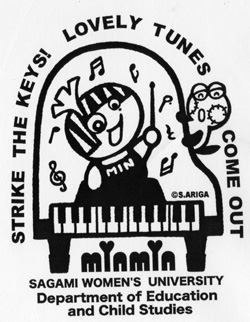
子ども教育学科の学生は授業の合間をぬって障がい者施設や保育参観、ボランティア活動に積極的に
取り組んでいる。先日は美術図工室でひとり教材の準備をしていると、学生が子どもを連れて入ってきた。
しばらく遊んでいってよいかと聞く。勿論大歓迎!マーカーと紙を使ってもらう。ダウン症の子どもを3人、学生たちは
精一杯のやさしさで相手をしていた。すごいネバリで、笑顔を作りもう必死だ。授業中には見せない底力を感じ
ぼくは嬉しくなった。確実に成長している。
エプロンにミンミンのイラストを入れたいと、学生が申し出た。水曜日の6限(放課後)シルクスクリーン印刷の
実習にもなるしOkした。数人集まるもよう。Tシャツにプリント希望もあった。そのデザインをおこす。学生はどれを
選ぶのだろうか。ゆくゆくは学生オリジナルも作製させたい。
(Jun,25)
■ミンミンゼミナール NO.22, NO.23, NO.24
相模女子大学に子育て支援室開設される。そのパンフレットの表紙にミンミンと
ゆかいな仲間達(ゼミー、ナール、ケロッケ)が登場。障害がいを持つ子ども、親御さんに
親しまれるようになってくれるいといいな。ミンミンちゃん、笑って笑って、はりきって行こうね!!!(Jun.23)

■二十四節気 <夏至> 七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
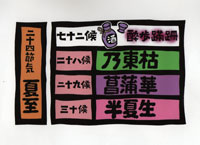 |
夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月21日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月26日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月 2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■忙中閑ナシ……寛ぎを望む心まで消え……
コンパクトデジカメを壊して以来、ブログの更新も怠りがち。鳩山は黄金(本当は薄茶色)の麦秋から、天を映す鏡面の
ような水田の季節に変わった。田植え前は雑草の畑。今は整然と植えられた苗の緑が美しく、日々育ちが分かるくらい
伸びている。
アトリエの庭に植えて10年、咲いたことがなかったリンデン(西洋シナノキ
= 菩提樹)が可憐な白花を見せている。カメラがなくとも
その感動を記すことは出来るはず。なのに、表現をしない。絵を描く、語る……ことを面倒くさがる自分がいる。普段から、
そう考えもせず写真を撮って”一件落着”で済ませていたのだろう。ぼくにも「感官の塊」であった幼少期があったろうに。
ああ情けない。自省自戒。
今回も『ミンミンゼミナール』掲載で凌ぐこと、お許しを!(Jun,18)
■ミンミンゼミナール NO.19, NO.20, NO.21
「絵画造形表現活動基礎」では様々な表現を試みる。デカルコマニー(転写)、フロッタージュ(こすりだし)、
ウオッシング(洗い出し)、スタンピング(摺り出し)、マーブリング(大理石模様)等々、それらのコラージュ作品を
制作。キーワードは”偶然を味方に”。多くの学生が、小学校、中学校の図工、美術でキズついてしまっている。
指導が写実に偏り、表現の巧拙に評価の基準が置かれたことによる自信喪失。本来楽しかるべき表現が苦痛にさえ
なっているのだ。そのトラウマを忘れさせるために”偶然の作用”で遊ばせるのだ。
生み出される模様の見事さに、夢中になって手を動かす楽しさに、あちこちの机から歓声があがる。人が物を創る
喜び……本来性を「美術教育」は忘れがちだ。学生はやがて子ども教育に携わる。図工は遊びだ。”教える”のではなく、
まず自らが楽しむ……その姿勢が肝要。先生が夢中になって面白がる……率先垂範、これにつきる。(Jun,17)

■ミンミンゼミナール NO.16, NO.17, NO.18
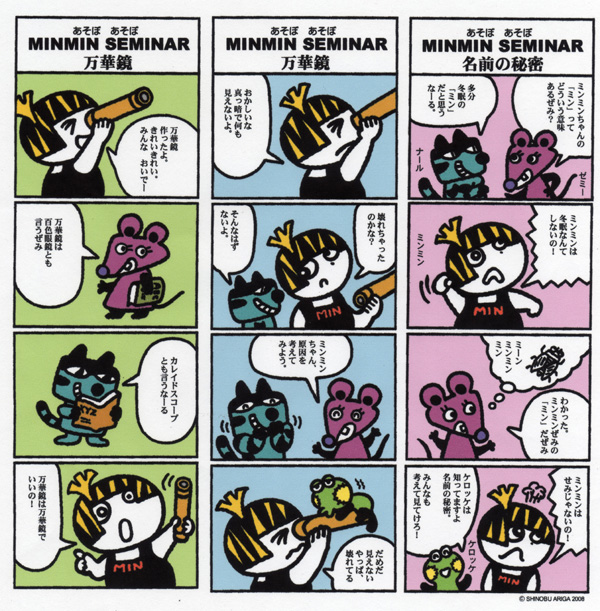
(Jun.13)
■「クレヨンまる」150話は花火のおはなし
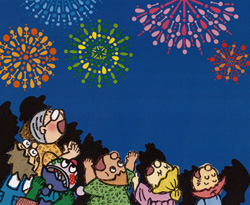

月刊読み聞かせ絵本雑誌『おひさま』連載「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」が8月号で150回となる。今回は
とても”小さな”おはなし。
大きな事件をとも思ったが、ぼくは「どうしても線香花火をやってみたい」と願うオオカミのワルズーの気持ちを
描きたかった。
親が子に、欲しがるものを何でも与える昨今、線香花火さえ買って貰えない子もいるんだと伝えたかった。
高価な玩具もちっぽけな何でもない物も、欲しいと思う気持ちの強さは時に同じだ。いやいや切実さはその人に
よって違う。ワルズーの場合、(育ての親、ミイラばあやの)貧しさゆえ、線香花火さえ買って貰えない。
線香花火を一度でいいからやってみたい……、ワルズーの思いつめる気持ちを書きたかった。
「ミイラばあやのけちんぼ!ミイラばあやなんか嫌い!」ワルズーは家を飛び出してしまう。
果たして、ささやかな希は叶うのでしょうか……。
(Jun.11)
■ミンミンゼミナール NO.13, NO.14, NO.15
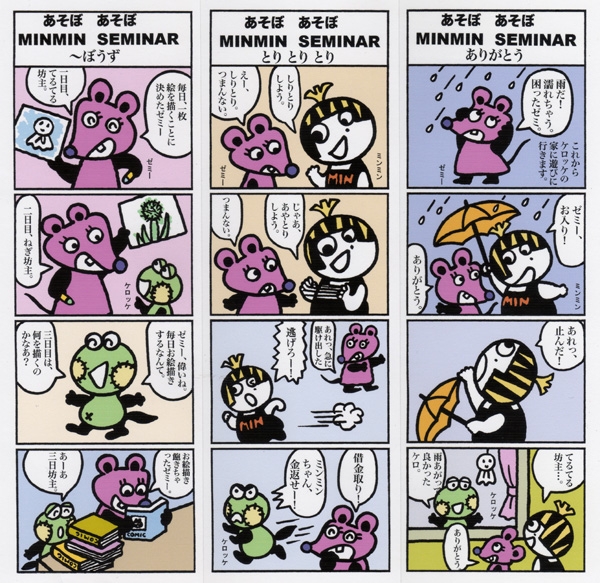
「実践遊び学」では、伝承からくり郷土玩具の仕掛けのメカを研究した。学生は製作した「回転円盤」の上に
思い思いのデザインをほどこした。ミンミンやケロッケのフィギュアを描き乗せた者も。
からくり玩具も動きは単純で「回転円盤」は他愛ない遊びだが、この素朴な遊びのよさを解ってほしかった。
手や指先を使う”微細な機能”(身体全体を使う”粗大な機能”に対して)の大切さ、”加減”のもつ意味は、
次の講義「回転クルリンリン(輪)」も同様だ。(機能はほかに書字機能、音楽機能まど)
(Jun,8)
■ミンミンゼミナール NO.10, NO.11, NO.12
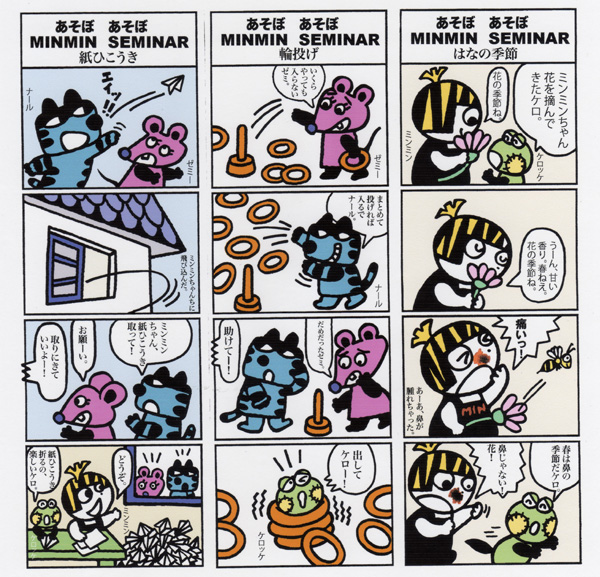
■ミンミンゼミナール NO.7, NO.8, NO.9
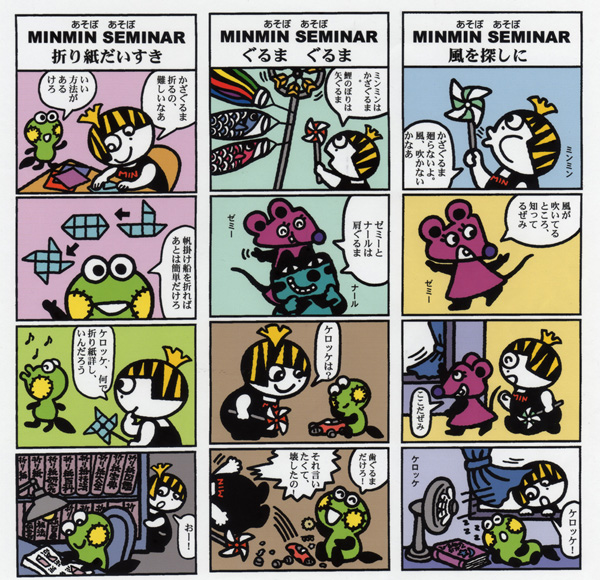
■二十四節気<芒種>、七十二候(二十五候、二十六候、二十七候)
 |
今年の芒種は6月5日 (夏至は6月21日) ・二十五候 (6月 5日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
| 5月のアトリエだより |
■「エルンスト」の絵を探す



ここ一週間ほど太陽が顔を見せない。今日も雨。迷ったが、鳩山のアトリエへ。周辺の田んぼは
今、田植えの真っ盛り。アトリエ下に軽4輪トラックが止っている。石井さんの車だ。畑に水を張りに来たのだろう。
代掻きが終われば辺り一面稲の苗で緑に染まる。
細雨に麦畑が煙っている。緑の野辺に所々パッチワークのような薄茶色の麦穂が波打っている。黄金色とは思わないが、
美しい。麦秋=麦の秋とは言いえて妙なり。田植えが終わり稲の緑が目に染む頃には、もうこの光景は消えている。
昨日大学の図書館でエルンスト〔Max Ernst1891-1976ドイツ画家〕の画集を探した。授業で行う
フロッタージュ(こすりだし)の参考資料にしようと。2冊借りたものの、思うようなものは見当たらなかった。そこで、鳩山へ!
昔「美術手帳」で見た記憶が……。本の山を崩し、束を解き、見つける!あった!記憶は確かだった。
1965年の12月号。特集「エルンストの博物誌」。板や葉っぱなどをこすって制作した作品
「振り子の起源」「光の車輪」「十四未満の光」など、モノクローム作品10点。
エルンストはダダイズム、シュールレアリズムの画家。『博物誌』はエルンストが初めて行ったと言われる
フロッタージュ技法による作品集だ。これを学生に見せたくて……、雨降りの中鳩山に来た甲斐があった。
黄変し表紙の破れた「美術手帳」の戦利品の他に、もうひとつの収穫あり。小ぬか雨に濡れながら摘んだ桑の実だ。
ぶつぶつが赤いのと黒いの。口中に広がる酸っぱさに、このところ、だるい、眠たいと愚痴るぼくも、
覚醒を促されり。朱紅色の艶やかな大粒のグミも収穫。こちらは甘みたっぷり。帰り道の慰めとなった。
(May.31)
■「タイヤチューブプリント」に使うローラーピン製作に鳩山へ



絵画造形表現活動では廃材のタイヤチューブを用いプリンティングをする。ゴムチューブをカットし、長方形(カマボコ板状)や
円形板切れに貼り版画の素材とする。さらに連続模様のプリント効果を求めてローラーピンで遊んでみる。実はこの下ごしらえが
大変。教師用、練習用を含めて120個、ブナの木管を小さくカット、軸棒を通し固定するのに時間がかかった。
ローラーピンをコンテナに詰め車に積もうと外に出れば、日が落ちるところ。おしゃもじ山の陰で我がアトリエはもう仄暗い。
鳩山のアトリエに来て一歩も外に出ないで帰るのも……と、カメラを片手に庭へ。腰丈まで伸びた雑草をかきわけ進めば、サルナシの
花が満開だった。今年もミニキウイのような実をたくさん実らせるのだろう。梅の実は正に今、収穫期。辺りに2,30個ころがっていた。
暮れかける中、大急ぎで梅をもいだ。ザルに山盛りの梅、庭に出てよかったと思う。ところが…………、
いいことばかりじゃない……。大失敗をしでかしてしまった!ポケットに入れたカメラに剪定鋏をぶつけてしまったらしい。らしいと言うのは
気が付かなかったからだが、カメラの液晶が破損していたのだ。記憶媒体は大丈夫だが、カメラが壊れた。アーア、梅酒を、梅干を
見るたびに、思い出すだろうなあ。
■二十四節気<小満> 七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
 |
小満は5月21日 (芒種は6月5日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
小学館の読み聞かせお話絵本雑誌『おひさま』創刊以来連載のクレヨンまるが8月号で150話になります。
夏にふさわしくテーマは、「花火」。クレヨンまるはまだ花火大会に行ったことがありません。打ち上げ花火を見たくて
ハーブおばさんに連れて行ってもらいます。が、トラブルが……。クレヨンまるはミラクルクレヨンで解決できるでしょうか。
ところで、オオカミのワルズーは線香花火さえやったことがないのですよ。「一度やってみたい!」召使のミイラばあや
(もう300年以上生きている怪しい婆や)に頼みますが……果たして……?
今月末発売の7月号は「たなばた」。クレヨンまるはハーブおばさんと七夕飾りを作ります。(作り方も載せます)短冊に
願い事を書きます。ところが、笹竹が消えてしまったのです!誰が、何の目的で……?
ぼくの話には悪者も登場しますが、必ずやさしい心も描きます。今春入学した大学一年生(18歳)が「子どもの頃、
『おひさま』を買ってもらい、クレヨンまるをお母さんに読んでもらったり、自分でも見た」と言ってきました。(当時は
おおかみのワルズー、子分のこうもり、コモリン、ミイラばあやは未だ登場していなかった)。
クレヨンまる、長いなあ……。
ぼくもちょっとだけ、ミラクルクレヨン借りて使ってみたい……。そして魔法の呪文を唱えてみたい……。
「ミラクル クレヨン クルミラ ゴー!」
(May.20)



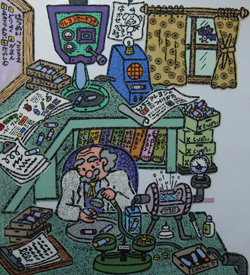


■教室にでんでん太鼓が鳴り響く。ポンポン、ボンボン、ゴンゴンゴンゴン……


「実践遊び学」では、光と遊ぶ、風と遊ぶ、廻して遊ぶ、転がして遊ぶ、折って切って遊ぶ、組合わせて遊ぶなど、様々な
遊びを考える。音と遊ぶは、でんでん太鼓。各自、和紙に絵の具で思い思いの図案を描き太鼓を製作する。
でんでん太鼓は民芸品店でしかお目にかかることもなくなったが、電子音全盛のこの世だからこそ、アナログの
温かい音色を創出し聞かせたい。どこか懐かしい音色。昔、赤ん坊がねんねこ半纏のおばあちゃんに背負われ聞いたで
あろう郷愁の音色を、今蘇らせたい。打ち鳴らすは棒を握る手の加減次第。
三クラス100人がでんでん太鼓を打ち鳴らした。教室に豆太鼓の音が鳴り響いた。世界一にぎやか、うるさい教室であったで
あろう。みな嬉々として、自分の太鼓を打ち振っていた。不快な騒音ではなく創作の喜びに裏打ちされた、”音をつくり
楽しむ”手ごたえを感じながら。
学生には、「何時の日か幼育、教育の現場でも子ども達に作るところを見せてあげてほしい。音を創り出す喜びを伝えてほしい。
さらには、君たちがお母さんになったとき、わが子のために小さなでんでん太鼓を手作りしてあげてはくれまいか。子どもの目から
耳から、温かい思いが刷り込まれていくだろう。わが子のために心をこめて作って鳴らす……何と素敵なお母さんでしょう……、
君達がそうなってくれたら、この上なくうれしいよ。」と話した。幼児期の体験のすべて、特に情操にかかわる良質な経験、感覚の
育ちが、いかにその後の人生に影響するかも。学生は直ちには理解できないかもしれない。無邪気にでんでん太鼓に興じていた。
(May.13)
■二十四節気<立夏>、七十二候(十九候、二十候、二十一候)
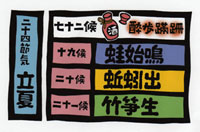 |
立夏は5月5日 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月10日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月15日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
Gウイークが終わった。今年は渋谷の仕事場に籠っていた。自分に向き合う、創作に身を入れる、表現、がぼくの仕事。だが些か
疲れた。”ノンストップ”は金属疲労の旧式機体には堪える。鳩山のアトリエに行かれなかったのが残念だ。緑風に機体を
休めたかった。
週末も仕事。月曜からは大学。先のことを考えると気が重くなる。やめよう。今日一日に集中、勝負と行こう。
(May.7)
■実践遊び学「音と遊ぶ」はでんでん太鼓製作


人工的なうるさい音、気を苛立たせる騒音……。現代社会から消えた静寂と闇。静けさと暗さが想像性を育てる。
”耳を澄ます””音を創出する”をテーマに実践遊び学「音と遊ぶ」では学生にでんでん太鼓を製作させた。
そうっと打つ、小さく打つ、強く打つ、早く打つ、激しく打つ……、手加減だ。良い遊びの要件の一つに、加減が出来る、答えが
一つではない、があげられるが、まさにでんでん太鼓はシンプルで飽きがこない。
昨年の「アトリエ便り」にはでんでん太鼓のバリエーションを掲載したから見ていただきたい。材料は何処にでもある。
太鼓の胴はセロファンテープやクラフトテープの巻き芯。6ポーションチーズの空き箱、ダンボールなどで出来る。皮(打つところ)は
和紙のほか障子紙、チラシ、ラシャ紙、薄でのケント紙などなんでも使える。球も木球のほか、ボタン、大豆、ドングリなど、要は
応用だ。創意工夫と遊び心、これがすべての基本だ。制作を通じて手わざの練磨も、手を使わなくなった、道具を使わなくなった
現代人には大事なことであるが。
(May.4)
■絵画造形演習『帽子百貨店』二日目は実物大の「覆面帽子」制作


心地よいそよ風に誘われてテニスコートへ。久しぶりのクラブはテニス日和というのに閑散。Gウイークのせいではない。
クラブのプレーヤー無視の一方的規約変更で、普段打っていた面々、三十数名が退会していったのだ。”年間「利用曜日」
契約”というシステムが導入され、打ちたい日に自由に(正会員・平日会員が普通だろうが)打てなくなった。ぼくは午前中
”ほんの少し”だけしか打つ時間がない。それも時間が取れる日は不定期だ。プレー曜日指定性には参った。それでも、
家から近いという一点でぼくは辞めないでいる。
コートはガラガラ。ダブルスが二組マッチングできない有様。ぼくはひたすら、サーブ練習に汗を流す。シャワーを浴びて帰る
時の爽快感。やはり運動することは素晴らしい。唇がヒリヒリする。顔や腕が焼けている。紫外線がかなり強いのだろう。
4月29日は祝日授業だった。世間は休みというのに、学生はまじめだ。嬉しいなあ。在籍99人中、欠席は4名。
授業にリキが入る。熱くなる。
「絵画造形表現」で実物大の帽子を二週に渡り制作させている。ジャンジャン作ってジャンジャンかぶる、……18種すべて
出来るか心配だ。学生は夢中になっている。楽しんでいる。やがて学生たちは子どもを導く。この経験が役立つだろう。
制作ぐせ、創意工夫する心が力となる。ぼくは「即座性」という言葉(勿論、こんな言葉はない)を使う。あれがなければダメ、
あそこへ行かなければ出来ない……と言うのではなく、臨機応変、何時だって、何処でだって、
何らか作り出せる”底力”を養ってほしいのだ。
(May.1)
| 4月のアトリエだより |
■手が絵の具だらけのまま、11時、家にたどりつく。
今日も、2限、3限,5限授業。ガッシュを10色、6テーブル分カップに溶く。60カップ。ほかに白色も。授業が終われば
補充や教材の準備があり、今日も昼食とれず。カロリーメートを立ってかじった。5限が終わり、研究室へ戻れたのは8時。
普段しっかり食べ、テニスをたまに……で作ってきた体の”貯金”が急速に減っていくのを感じる。
10時までは”自分の仕事”をと思うものの、疲労感に負けそうになる。コーヒーを淹れねじり鉢巻!研究室の「電気がついて
いたから」と学科長が顔を出す。励ましの言葉、嬉しいねえ。アート紙や教材購入を報告したり、聴覚に障害を持つ学生の指導
についてのアドヴァイスをいただく。
筆を洗い、頭に、この大量の絵の具が、この時間が、「作品制作に向かったなら……」の思いがよぎる。もちろん、授業中は
必死、夢中でこんなことは考えもしないが。作家性が頭をもたげる。うずうずしている。
(Apr.27)
■時代の大波に飲まれるも、何としても”自分性”は死守せねば……


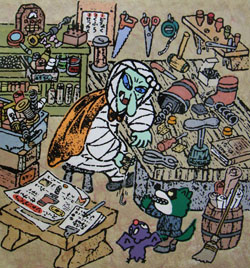
『おひさま』連載”ミラクルクレヨンの”クレヨンまる”が8月号で150回目を迎える。NHKおかあさんといっしょの
『こんなこいるかな』(『おともだち』『えくぼ』『おかあさんといっしょ』『げんき』ほか)の連載期間を超えそうだ。
”クレヨンまる”は画用紙に、クレヨンで描く”てざわり”感を表現したくて、イラストの黒い墨線のマチエールをクレヨン風に工夫、
色も線から敢てはみ出し塗りし柔らかさを出した。
クレヨンまるが持つミラクルクレヨンは、描いたものが本物になるスーパークレヨンだが、それも効力は3分のみ。しかも、自分の
ために使ったことは一度もない。友達や、どんぐりタウンの人、そそっかしいハーブおばさん達を助けたり、ミラクルクレヨンを狙う
大泥棒(本当は、ちっとも”大泥棒”なんかじゃない = ミイラばあや、オオカミのワルズー、子分のコウモリ、コモリン)から、
ミラクルクレヨンを守ることに使うことがほとんど。ミラクルクレヨンが”悪用”されれば、大変なことになると、クレヨン博士から
聞かされているからだ。
このミラクルクレヨンのクレヨンまるがピンチ!もっとも、作品制作に関してのことだが。ぼくの絵作りは墨線を描きマチエールを
切り貼りし、それを原寸大のフイルム化する。つまり、暗室作業をともなう。世の中、銀塩カメラの衰退とともに一部を除き、フイルム、薬品、
印画紙類の生産も終わってしまった。レントゲンフィルム大の大判フィルムや、感光材料(現像液他)が手に入らない。フィルムは
アグファ社から取り寄せ多めに在庫していたつもりだったが、底が見えてきた。暗室の機材、デザインスコープやプロセッサーも故障がち。
ハロゲンランプなどの消耗品も手に入らない。困り果てた。コピー機でフィルムを作製、急場しのぎをしたが、安定せず満足できない。
世の流れだ。CGしかない。『こんなこいるかな』も連載十年を超えた頃からはパソコンで作画していた。
だから、”どうってこと、ないか?”いえ、全然違う。手作り感、温かさの表現にはフイルム作りから入り一色一色、筆でゆっくり
色を入れていく作業が大事。これがなくなる。”心が籠められる時間”がなくなる。
しかしながら、ぼくは仕方なくコンピュータ作画に入った。パソコンのフリーズや言うことを聞かないストレスと格闘しながら、
どうやって”心を籠める”か、ぶつぶつ念じながら描いている。クレヨンまるや、ワルズーが救ってくれたら良いのだが。まだまだ
時間がかかりそうだ。
そのお披露目は、7月号。連載第149話「七夕飾り」。乞うご期待。
(Apr.26)
■二十四節気<穀雨> 七十二候(十六候、十七候、十八候)
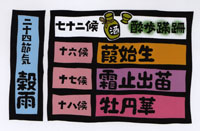 |
穀雨は4月20日 (立夏は5月5日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
大学の特殊演習室(美術図工室)はキャパシティ36人と小さい。キャパがないことは、対面授業(机の間を廻っての
アドバイス、個人指導)には悪いことではないが、机は広いほうが望ましい。立ったり坐ったりの作業、水場に離れたり、
特にカッターナイフを用いるときは、肩が触れ合うような狭さは危険だ。学生は皆夢中になっての作業、ぼくは目を見張って
いなくてはならない。神経が疲れる。授業終了後も残って後始末、次の準備もある。研究室になかなか戻れない。
特に2限、3限授業の”間”がタイト。2限の終わりが12時10分。3限の始まるのが1時。食事時間は20分取れればいいほう。
今日は悲惨だった。あと30分はある!大学構内に来る移動販売車で、ランチボックスを求めようとして並んだ。ぼくの前には
学生が3人。レンジで温めてもらっていたりするから、列が進まない。時間、時間……、焦って待つ。漸くぼくの番。ラッキー!
残り一つだった。「よかった」財布から500円玉を取り出したとき、後から声が!「先生!」ぼくの教えている学生だった。迷ったけど、
もちろん、ぼくはそのランチを学生に「どうぞ。買いなさい。お腹すくだろう」なんて格好つけちゃって。ぼくのお腹はペコペコ。
研究室での今日の昼食はビスコとコーヒー。
3限が終わり、次の授業5限までには時間に余裕がある。パン屋に走ったのはいうまでもない。
5月5日は、もう”立夏”。暦の上では夏の始まりだ。今日も汗ばむ陽気。キャンパスを渡る風が気持ちよい。
(Apr.22)
■幼児誌の広告に見る子ども対する「真剣なまなざし」

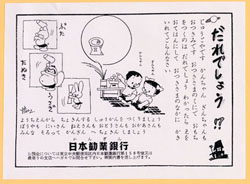
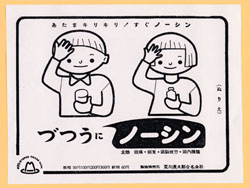
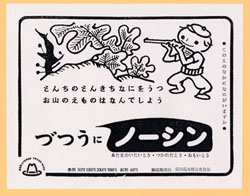
少子化、情報化社会、環境の変化、生活の変容等で子どもの生活は大きく様変わりした。遊べない子ども
遊ばない子ども……。いまや子どもの”遊び”が危うい。幼児雑誌の世界もかつての60年代黄金期から比べると、
見る影もない。種類、発行部数とも激減。数十万部を誇った雑誌も十万部を越えればまだ良いほうというのが現状だ。
内容も全く違っている。昔は編集もおおらかだった。季節感たっぷり。餅つき、節分、節句、子供の日、七夕…。
毎月童謡唱歌が掲載され、しっかりした挿絵(イラストに非ず)がついていた。日本昔話、世界名作、生活絵話、学習記事、など
それは豊かなものだった。”だった”というのは、それらはすべて姿を消し、現在の幼児誌にはみられないからだ。
現代の幼児雑誌は一口で言えば”華美”。テレビより、というよりはすべてがテレビキャラクター。かつて見られた「編集者の熱い
心意気」を感じられた巻末の編集後記もなく、毎号付く100~200枚のシールと、完成品の”玩具”の付録で存在を保っている、
極めて”寂しい”状態だ。
上の4点の広告はいずれも子ども雑誌の本文に添えられていたもの。粗末な紙、狭いスペースながら、子どもに”遊んでもらおう”、
”楽しませよう”の意図を感ずる。編集部も、企業主も子どもを真剣な眼差しで見ていたことが伺える。
ぼくは消えた”情操”という言葉を、ふと思い浮かべた。 心だよ。心。それしかないんだ……。嗚呼……
(Apr.21)
■「帽子百貨店」”総合カタログ”表紙を作らせる

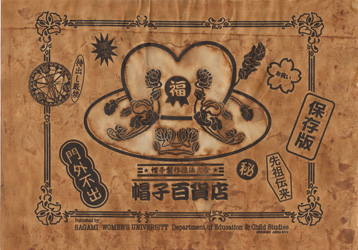
学生に”キレイ””超カワイー”の単純、記号化された美の概念を変えさせる。
「帽子百貨店カタログ」の表紙を古色蒼然とした装丁に制作させた。カビ、染み、汚れ、雨漏りの跡、はげた土壁……、
年月を経て褪色した古文書を思わせる表紙を作らせた。白かった紙が見る見るうちに”汚され”ていく。このマチエールの美しさに
気づいてほしかったのだ。
美しいものは、純白?色のハーモニー?グラデーション?いまや春、ソフトなパステルカラー?………。いやいや、そんなものでは
なかろう。カビが生えたような、染みが付いたようなものでも、目を凝らして見れば実にキレイではないか。羊皮の風合い?土壁?
時代の古文書?学生は大はしゃぎして制作した。これでいい。驚きや歓びの声が上がればそれでいい。
カタログの本文は次回制作する。新聞紙や、模造紙、ラシャ紙を使って実物大の帽子を十数個、製作する。(GIハット、ソンブレロ、
ペンギンハット、教皇帽、山高帽、黒面頭巾などなど)そして、そのミニチュア版をカタログページに見本として貼り付ける。学生は自分で
制作した自分だけの”生きた”教科書をつくるのだ。
(Apr.15)
■「ガラガラ引き車」一点を見に国立新美術館へ

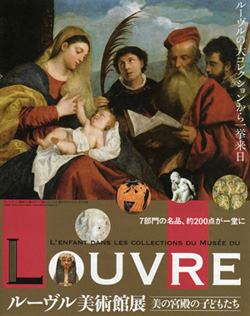
このところ睡眠時間も満足にとっていない。レジュメつくりに明け暮れている。現代童画会春季展も出品はしたものの、
とうとう会場に足をはこべなかった。ゆとりのないこと、この上なく、心も荒みイライラが募る。
思い切って、仕事場を出る。ルーブル美術館展「美の宮殿の子どもたち」を観に。中期エラム時代(紀元前12世紀頃)の
工芸品『台車に乗ったライオン』『台車に乗ったハリネズミ』を見たかった。
新聞記事や、パンフレットではサイズまではわからない。何で出来ているか、重さは?……二つとも思っていたよりずっと
小さなものだった。10センチにも満たない(高さ数センチ)愛らしい玩具、石を彫って作られているが重さもさほど感じられない。
この引き車、幼児の玩具としてというより、(死んだ子どもを悼む)埋葬品として作られたものではなかろうか。ライオンもハリネズミの
造形が見事、車のつき具合も精巧で紐をつけ引けば車輪も廻りだしそうだ。
子どもを題材にした絵画、彫刻、美術品の数々。人が初めて出会う玩具が「ガラガラ」だという。そのガラガラであろう土鈴も
見られたが、中ではやはり、この二つの台車の玩具の印象が深かかった。3000年以上も前の工芸品に、親の子を思う気持ち、
その深さを感じられて、何とも心ホッコリさせられたのだった。
(Apr.12)
■桜舞い落ちるキャンパス……春爛漫……花びらが頭に顔に体に……
新入生八百余名を迎えての入学式。この中の106人が「子ども教育学科」を選んだ。会場を見渡しても、
勿論、誰が我が学科の学生かはわからない。が、決意新た。「まかせてもらおう、4年間。ぼくのすべてをぶつけるから」
「子ども教育研究」誌創刊を受けて、子ども教育学会が開かれ出席する。同誌にぼくは研究・創作ノート『11片タングラム』を
寄稿。扉絵に『Father's Letter』を提供した。学会誌のイメージは”堅い”ものだが、少しは和らいだか。
(Apr.9)
■「墨洗い流し」のサンプル制作。おもしろくてたちまち十数枚。



●Apr.1 の「スタンピング」の答え キャベツの断面
(Apr.7)
■二十四節気 <清明> 七十二候 (十三候.十四候.十五候)
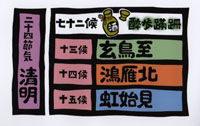 |
今年の清明は4月5日 (穀雨は4月20日) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
朝夕に寒暖の差、春一歩手前。成城の桜は五~六分咲き。相模大野の大学キャンパスは満開近し。9日の入学式は
薄桃色の花びらが舞うことだろう。
テニスの回数がめっきり減った。体が鈍ってしまいそう。テニスクラブの一方的な会則変更に嫌気をさした会員が
三十数名、いっぺんに退会した。よってコートは閑散。春風を受け、サーブ練習に汗を流す。やっても、やっても
追いつかない仕事を、一瞬でも忘れたい。が、頭から離れず渋谷の仕事場に。
(Apr.4)
■スタンピング遊び Ⅱ <教材参考資料つくり>
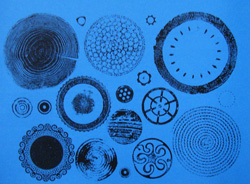


身の回りにある様々なものを教材参考資料として活用する。 Aは 円形物を片っ端からスタンピング。キャップ、容器の
底など色々。 Bは モミジ、ワイルドストロベリー、ツツジ、ヤツデ、ローズゼラニウム、ハナミズキ、シラカシ、アラカシ。
Cは ?………答えは次回に。
(Apr.1)
| 3月のアトリエだより |
■板絵「灯台POST」完成
現代童画会春季展出品作「灯台POST」(S10号)が描きあがった。アトリエから持ち出す前、額装してしばらく鑑賞する。いつも、
この”しばらく”が幸せな時間。完成してホッとすることもあるが、絵に見入り、その世界に浸る喜びが大きい。描き出したい心の
内が画面から伝わって来ると画家でよかった、画家でしかぼくはありえない……そう思う、強く。
(Mar.29)
(会場等は展覧会情報に)
■巣作りの季節


鳥の声が途切れることがない。先日の本欄には写真を載せたが、裸木に鳥の巣を4個発見。葉が茂っている季節は
気づかなかったが、鳥達はほんの目と鼻の先で巣を作っていたのだ。
先週、巣箱をかけようと、ガーデンテーブルに出しておいたものに、もう巣作りが始められていた。藁やコケのような
ものが運び込まれている。これには、ビックリ!木に取り付けたいが(昨年はヘビにやられた。注意せねば)、今移動して
警戒して寄り付かなくなるのではと、そのままにしておくことにした。ただ風に吹き飛ばされないように針金でテーブルに
固定。これで落下もしまい。ヘビも登れまい。人(ぼく)さえ寄り付かなければ、このテーブルの上が一番安全だ。ぼくは
ここではお茶を飲まないことに決めた。バードウオッチングさせてもらう楽しみを貰った。
(Mar.28)
■前回の写真……「スタンピング遊び」の答え 豆腐の容器
■二十四節気 <春分> 七十二候(十候.十一候.十二候)
 |
今年の春分は3月20日 (清明は4月5日) ・十候 (3月20日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月25日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月30日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
■スタンピング遊びいろいろ


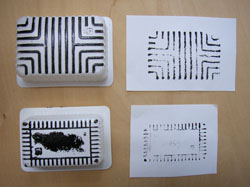
Mar.18クイズの答え = 食パンビニール袋の止め具(プラスティックの小片)
さて、今回もクイズを。中央の写真は、食品容器の底にゴムローラーでインクをつけ転写したものです。それでは、
右端は何をスタンプしたものでしょう?容器二個は形が違いますが同じ食品です。(答えは次回)
■「スタンピング」は版画造形のはじまり。その楽しさ、美しさを伝えたい



幼児は絵の具の付いた手をペタペタ……、紙に形が写ることに目を輝かせる。面白い形、色の重なり、偶然出来た模様に
興味津津だ。素材はほとんどすべての物。野菜、葉っぱ、木片、キャップ、ふた、プラスティック容器の底、壁紙、エンボス紙、
ミカンやタマネギのネット、畳、ザル、網など何でも大丈夫!
「造形表現あそび」は、子どもたちが材料(素材)を集めるところから始まる。そのヒントとなることを考えている。
今、テキストを作成中だが、”作品集”とならないよう心せねばならない。いつも、”ぼくは作りすぎて”しまうから。
●クイズ●
上の右端の写真は一体何でしょう?ヒント・日頃よく手にするもの、とくに朝の食卓で。
小さなもののアレンジですが、右三列、それぞれ微妙に形が違います。三列目の上の一個とあわせて、4タイプの型が
あります。さあ、なんでしょう? 答えは次回に。
(Mar.18)
「えほん寄席」スペシャル放送 3月21日(土)15:30~15:55 NHK【教育テレビ】
2009年2月放送の「えほん寄席」が まとめて再放送されます!!


「えほん寄席」スペシャル放送 3月21日(土) NHK「教育テレビ」にて ”見てね”
お薦めは「反対車」……抱腹絶倒。面白いですよー!
| 放送時間 | 作品名 | 落語家 | 絵 |
15:30~15:35 |
反対車 | 桂南なん | 山下勇三 |
| 15:35~15:40 | 目黒のさんま | 三笑亭夢太郎 | 有賀 忍 |
| 15:40~15:45 | のっぺらぼー | 柳家さん喬 | 山本容子 |
| 15:45~15:50 | 粗忽長屋 | 柳家はん治 | 五月女ケイ子 |
| 15:50~15:55 | 稽古屋 | 桂文也 | 林家二楽 (紙切り) |
■風柔らか…… 画室を出て”春”を探す


茶や梅ノ木の根元に蕗の薹が芽をだしている。ぼくの小さな”フキ畑”には木工小屋を建ててしまったので、
蕗は諦めていた。が、根はあちこちに伸びていた。おかげで今年も大好きな蕗の薹を味わえる。”フキ畑”の
蕗の根は移植しておいたが、こちらは未だ芽を出さず。来年以降の楽しみにしよう。
ノビルの塊を見つける。辺りが土色だから、ノビルの鮮やかな緑は目に染みこむようだ。こちらも採取。
酢味噌和え、恰好の肴だ。ただ、ただ、美味い酒、美味い肴は昼間の仕事次第!絵の出来具合による。
(Mar.9)
■二十四節気<啓蟄> 七十二候 (7候.8候.9候)
 |
|
■あちこちに鳥の巣発見。緑の季節には気が付かず……




・スモークツリー ・ロウバイ ・キンモクセイ ・モミの木
鳩山のアトリエで板絵制作開始。テーマ(モチーフ)は心象、「父性の原風景」。現代童画展に出品した『 Father's
Letter』の
続きを描こうと思う。10号Sサイズのパネルにシナベニア板を張り付け釘で仮固定。乾くまでドローイング。
鳥の声に誘われ庭に出る。わがアトリエは小鳥には別天地だろう。普段、人の姿ナシ、辺りに農薬ナシ、木の実多しなの
だから。
ムクドリが数羽遊んでいる。ヒヨドリの番いはぼくの姿を見ても飛び立たない。絵の具だらけのカバーオールの絵描きは
”無害人”と無視しているかのようだ。
葉を落とし裸になった木々に鳥の巣を発見。1時間くらいで4個見つける。モミの木は常緑樹だが、針葉。棘々が痛く
ないのだろうか。それにしても、モミの木は建物の脇に植えてある。小鳥のさえずりが繁くとも、その”居場所”は
分からなかった。こんなにも身近にあったとは驚きだ。
落葉や雑草の捨て場にしていた竹薮にキジの番いを見ることがある。以前エッセーにも書いたが、なぜか心がほっとする。
野鳥観察は梢に葉が茂る前の今、この季節が一番だ。とはいえ、アトリエの主は閉じこもり、耳で楽しむことになる……。
(Mar.5)
■枯野に花謳う。2月は梅、ロウバイ。 未だ首をすくめる寒風、3月春の香は……?



庭は雑草も枯れ、土色一色。その中で、水仙の黄色が目に飛び込む。鮮やかだ。植えもしないのに、毎年同じ場所から
芽を出し増えていく。花が終わると存在を忘れてしまう。季節の訪れ、嬉しいプレゼントだ。
”フキ畑”と呼んでいた一角に 木工小屋を建てた。土を掘り、フキの根茎を集め移植しておいたが、未だ芽を出さず。
今年は大好物の春の味覚、”フキ味噌、蕗の薹の天ぷら、醤油炒め”もお預けか。スーパーの8個入りパック二百数十円
で我慢しよう。
(Mar.1)
| 2月のアトリエだより |
■麦わら帽子から作ったマチエールボード


フロッタージュやスタンピング素材は色々。排水溝の目皿、洗濯ネット、小包梱包用テープ、植木鉢の中敷、金網、
壁紙、ビニールのテーブルクロス、板、竹かご、ザル……、挙げればきりが無い。すべて応用できる。創意工夫これにあり!
マチエールの研究には素材は多いほど良い。歩いていても、お店に入っても、目は”ごつごつ、ザラザラしたもの”に
行く。100円ショップで買うものも、本来の用途で使うものは少ない。紙をあて、こすったり、ローラーでインクを付け
写し取ったり……、このいマチエールボードの使い道は広く、仕事にも活かせそうだ。
(Feb.22)
■ある物を鋏でチョキチョキ……。一体何をカットしたのでしょう?

フロッタージュやスタンピングの素材を集めている。身の廻りにあるもので、ザラザラやごわごわしたもの。凸凹したマチエールは
すべて利用できる。机の数分、6箱のコンテナーにそれぞれ四、五十種。今日新たに写真の素材を加えた。ローラーでインクをつけ
模様を写し取るのだが、これが楽しい。幾つかコラージュし作品を作る。
写真はある物を切って2枚あわせてカードボードに貼り付けたものだが、一体何をカットしたのでしょう?答えは明日。
(Feb.21)
■二十四節気<雨水>、七十二候(四候.五候.六候)
 |
今年の雨水は2月18日 (啓蟄は3月5日) ・四候 (2月18日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月23日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (2月28日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
大学キャンパスのイチョウの並木。 根元に”残り銀杏”が転がっている。晩秋に枝から離れずにいたものが今、寒空から
落ちてくる。構内に人影少なく、もう拾う者なし。イチョウの木は、新校舎建設で傷められたにも拘わらず、実をたくさん付け
昨秋は袋一杯拾い集めた。。
冷え込む夜はギンナンを炒り熱燗だ。臓腑に染み入るも、「仕事」「絵」の進み具合が酔いを左右する。
この「二十四節気」の、お銚子と杯のカット横の”酔歩マンサン”も連日となれば、肝臓が泣く。心せねばならぬが、
描いては喜びの酒を酌み、また、描けずに悩み飲む。この繰り返し……嗚呼、進歩全くなし。いたずらに歳を重ねるのみ。
(Feb.18)
■絵の具カップ置き台を製作



「絵の具カップ置き台」を作る。30センチ角の板に径75ミリの穴が9つ。ヨーグルト容器やペットボトルががすっぽり入る寸法。
大学の美術室の机の数分製作した。早速使ってみたら、良い塩梅!使い勝手上々だ。ボックスに重量があり絵の具カップが
動かず粗い筆使いもこれなら大丈夫。絵の具を溶き,折りや絞り染めを楽しんだ。
(Feb.12)
■鳩山の野辺、北風が止む一瞬、日差しに春の兆しを感ず


「絵画造形表現活動」で使うローラーを製作しに鳩山に来た。卓上丸鋸でブナ材の木管を切断。軸棒を挿入接着。
100個作るのに一日かかってしまった。このローラーピンを自転車のタイヤチューブに差し込み版画素材とする。
「チューブプリント」の授業は2回行う。まず手始めに5センチほどの長方形や丸型の木片にチューブを貼り版画をする。2回目に
このローラーピンを転がしてパターンを作らせる。楽しんでもらえるだろうか。
鳥の声に外に出る。庭と境界の斜面に数羽集まっている。見れば餌台のようなものが。鳥は餌台からこぼれたヒマワリの
種を啄んでいる。いや、これは餌台なんかじゃない。トラップを載せる台だ。今日は罠篭はなかったけれど、このところ何回か
仕掛けられているのを見た。嫌な気分だ。ぼくは幾つか鳥の巣箱をかけている。鳥が集まるように。それを捕まえようと
するなんて、ひどい。餌のない季節、鳥が哀れだ。境界にくいを打ち、縄を張った。こんなことはしたくないけれど、仕方ない。
庭に入り、ここで鳥を捕まえることはやめてもらいたいから。
暗い心持で引きあげた。チューブプリント用ローラーを作り終え、ほっとする筈であったのに……。ロウバイの甘い香りも
今日は嬉しく感じられないくらい落ち込んだ。
■玉子計量器 <その二>試してみた
手に入れた玉子計量器“JIFFY WAY”は玉子のサイズをSMALL,MEDIUM,LARGE,
EXTRA LARGEの4種に分けている。 重さは1.5オンスから2.5オンス(1オンス=約28.35g)まで計れる。
垂直にたらした金属棒で設置する場所の垂平を知らせる仕組みなど、もう大真面目なのだ。
WORLD‘S LARGEST MFG’S EGG SCALESと豪語しているくらいだ(何とも大げさ!)。
裏側にはスケールの針を微調整する重りまでついている(TAKE BALANCE AT RED POINT .
USE ADJUSTABLE SCRLW FOR SPEED.)。実際計ってみた。
日本のMサイズはLARGE,LサイズはEXTRA LARGEの域を超え針は振り切ってしまう。
この道具を作った当時、玉子は現在ほど大きくはなかったのかもしれない。
しかしながら、この計量器、いったい誰が何の目的で使ったのだろう。家庭に一台だったのかなあ……、
まさか!食べる前に計ったのだろうか、まさか!今日はSサイズにしようとか、Lサイズを食べて元気に……とか。
ばかばかしくて面白い!
ぼくは計量器にかけた玉子をゆで、「ありがたく」いただいた。手のひらに乗るほどコンパクト、
この愛らしい計量器はあの「コッコッコッコッ コッケッコ コッコッコッコッ コッケッコ 私はミネソタの
卵売り」の歌のミネソタ(MINN.)で製造とある。もっとも、「ミネソタの玉子売り」の歌は日本製だが。
(Feb・3)
■”幻の”「鶏卵サイズ選別機」入手!!! 「仕事場の片隅の埃をかぶったガラクタ達」VOL.1


「鶏卵サイズ選別機」……この、面白くも馬鹿馬鹿しい機械を、やっと手に入れた。30年ほど前、ぼくは銀座のデパートの
アンティーク雑貨売り場で見かけたが、値段を見て買うのを躊躇った。”幻の”と書いたのは、あれ以来、夢にまで出てくる始末で、
奮発して買えばよかったと後悔の念が収まらなかった一品だから。
ぼくは”馬鹿馬鹿しいが生真面目に取り組み製造された”雑貨が好きだが、購入するには幾つかの条件がある。例えば、生活の用に
供する(した)もの(実動品でないとダメ)あるいは、機能的魅力、あるいは造形的な美しさ、あるいはユーモア、あるいはアイディア……
それに、ぼくの価値観に合致したプライス(高価なものは)と、かなりハードルは高い。
この「鶏卵サイズ選別機」が以上にの条件を満たしているかはさておき、今回買わねば、また”幻”を追いかけ続けることになるのは確か。
ウソみたいだが幸運にもバザールで半額!喜んで買った次第だ。さて、試運転?の結果は後日当欄で。
(Feb.2)
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候)
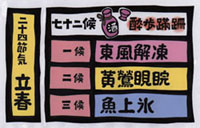 |
●今年の立春は2月4日 (雨水 2月18日) ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月13日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
昨日の東京は終日雨降り。風も強く、傘がさせないほどだった。ビニールが剥がれ骨が折れた傘も何度か目にした。持って帰る
気分ではないのは分かるが、そこらに打ち捨てるのはいただけない。
今日、雨は上がったものの、風は収まらない。渋谷の仕事場から中学校のグランドが見えるが、野球練習も普段どおりにはいって
いないようだ。時おり吹く突風に練習試合も難儀をしている。
工事現場の養生シートの留め金が取れ、バタバタバタバタ音を立てている。仕事は大雨の方が集中できる。強風は窓に当たり
ガラスを揺らす。ぶつかる音、はためく音、ゴミ容器などの転がる音……、風は本体のみならず、騒音を連れて来る。よって本日は
仕事進展せず。いや、風のせいにしてはイカン!
(Feb.1))
| 1月のアトリエだより |
■トートバッグ シルクスクリーンでプリント


学生用は業者に頼んだが、教師用はぼくがプリント。写真は学生用と同サイズの試作品。現物はA2サイズの大型。
美術図工室の机に刷り上げたバッグを20枚、乾燥のため並べた。出来具合上々。
(Jan.28)
■トートバッグ製作


相模女子大学子ども教育学科の学生にミンミンキャラクター入りトートバッグを配布。(紺色のものは四月新一年生の分)
キャッチコピーは「Make the best use of your talents.」美術図工室で画材、用具をたっぷり詰めて配ろうと思う。
(Jan.27)
■えほん寄席 落語「目黒のさんま」放送日決定



・NHK教育テレビ 「えほん寄席」
2月11日 朝7時45分~7時50分 「目黒のさんま」放送されます。(落語家=三笑亭夢太朗)
■二十四節気<大寒>、七十二候(七十候.七十一候.七十二候)
 |
●今年の大寒は1月20日 (立春は2月4日) ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
このところテニスクラブもご無沙汰している。仕事でなかなか行かれない。5日ほど風邪気味であったが、体を動かさないと気持ち悪い。
”荒療治”とばかり、思い切って大学のテニスコートで打つ。T先生とラリー、それにサーブも。ナイターの明りは、高く上がるボールが
よく見えない。それでも1時間少々楽しんだ。コートブラシをかけ終わると直ぐ雨が落ちてきた。一汗かき、「これで風邪菌は
吹っ飛んだぞ」と自ら言い聞かせ帰った。ラケットを握る手が凍えた。息が白い。体が冷え切って温まらない……、寒いわけだ。
昨日20日は大寒。今日は昨日よりも寒い。ナイターのコート、ほかに人影ナシ。
(Jan.21)
■学会誌「子ども教育」原稿ようやく脱稿
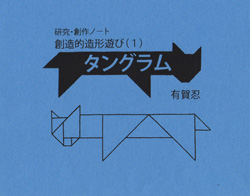
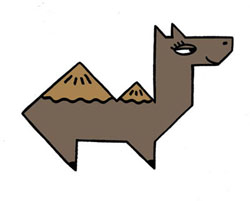
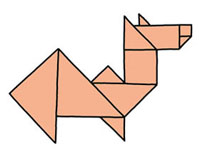
・学会誌原稿タイトル ・ラクダ ・構成図

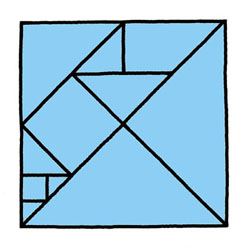

・11片構成タングラム ・シナベニアで作製
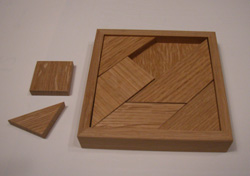 ・サントリー美術館のミュージアムショップで売られていた「清少納言の知恵の板」
・サントリー美術館のミュージアムショップで売られていた「清少納言の知恵の板」
ウイスキー樽の再利用で作られたもの。何となく香しい。堅いナラ材の質感もいい。
学会誌「子ども教育」掲載原稿書きあがる。「創造的造形遊び(1)」。創刊号はタングラムをとりあげた。タングラムは裁ち合わせ
パズルの一種。シルエットからその組み合わせを考える遊びであり、いわゆる”答え”があった。そのタングラムを”自由な造形遊び”
とするのがぼくの提案。タングラムといえば七片であったが、ぼくは11片構成とし、形の細部が作りやすいようにした。
ページの制限もあり、作成したシルエットも使用したのは約40点ほど。造形は無限、面白いようにできる。保育、教育の現場や、
家庭で、当たり前に置かれていたらいいなと思う。想像力、想像力、コミニュケーション能力(会話)の涵養も期待できる。
(Jan.19)
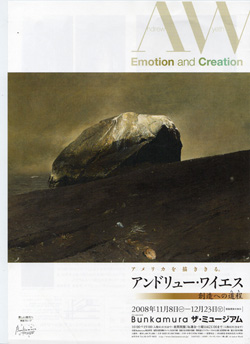 アンドリュー・ワイエス展 bunkamura ザ・ミュージアム
アンドリュー・ワイエス展 bunkamura ザ・ミュージアムアンドリュー・ワイエスが亡くなった。ワイエスはアメリカン・リアリズムの代表的画家。水彩、
テンペラ画で一世を風靡した。「アンドリュー・ワイエス -創造のへの道程-」展を見たのが暮れも
押し迫った12月の末。展覧会では「2008年7月アンドリュー・ワイエスは、夏を過ごすメイン州の家
で91歳の誕生日を迎え~中略~91歳になる現在まで創作意欲は衰えることなく~後略」とあったので、
死去のニュースには驚いた。ペンシルバニア州チャッズフォードの自宅で死亡、老衰だという。
アメリカの原風景を描いた水彩画、テンペラ画の緻密な描写力に、ぼくは1995年の展覧会でも圧倒
され言葉を失った記憶が残っている。今回はテンペラ画にいたるまでの“道程”が同じモチーフの幾
枚もの水彩画(下絵には見えない。すべて作品だ)展示によって明らかになる仕組みの展覧会で見ご
たえがあった。
緻密な描写力といっても、一部の評論家からは「(作品の多くは)芸術で無く、技術重視のイラスト」
と酷評もされた(東京新聞)こともあるそうだが、芸術の解釈を別にして、ワイエスの描く平凡な田舎
の絵に“気”が漂っているのは確かだ。忠実な“写実”だけではこの“空気感”は出でない。
アメリカ人の心を捉えたのは日常の暮らしへのノスタルジーか。ワイエスの絵画世界はどことなく
哀愁が感じられる。ぼくの最も好きな作品は「松ぼっくり男爵」。ドイツ兵のヘルメット(鉄兜)に
盛られた松ぼっくりが松の大木の根元に置かれている絵だ。アンナが松ぼっくりを拾う手の素描や、
松ぼっくり一個だけ、ヘルメットに入った松ぼっくり……、習作を経て、80×84センチのテンペラ画で
は遠近法で松並木が描かれそこに、松ぼっくりの入った鉄兜がある。木漏れ日の日差しと風と、
匂いまでもが伝わってくる。
先日ぼくは強風下、松ぼっくり拾いをした。ワイエスのあの一枚が鮮烈に頭にあって、あたかもあの
情景の中にいるような錯覚をおぼえたのだった。「松ぼっくりは夢のように燃え上がり、いい匂いを放
つものだ」
(展覧会図録より)とワイエスは言う。松笠は火を起こすのに最適なのだろう。図録にはアンナが拾
い集める松ぼっくりを落とす松の木はドイツ人カーナーが祖国の「黒い森」から持ってきて植えたものと
あり、その件は絵画にまつわるエピソードとして興味深く読んだ。
「今年はテンペラを2点完成させました。1点はペンシルバニア州で描いた大変大きな絵です。もう1点
はメイン州の彼の島で描きました。彼の年齢から考えますと意欲と体力の持続に驚かされます。(図録、
学芸員メアリー・ランダ)最後の最後まで描き通した、歩み続けた、完璧な“画家生涯”……倣いたい。
(Jan.17)
■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候、六十八候、六十九候)
「気候」という言葉は、二十四節気の”気”と七十二候の”候”がもとになっている。
めぐり来る季節、日一日夜一夜(ひ、ひとひ よ、ひとよ)花鳥風月を愛で、日々是好日と
感謝する心を忘れぬよう、また、酔生酔歩の身を自省。更には現代社会の流れの速さを、
僅かばかり止めてみようと、ここに季節の言葉を書き記して行く。 (2007年1月15日の「アトリエだより」より)
 |
●今年の小寒は1月5日 (大寒は1月20日) ・六十七候 (1月5日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月10日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月15日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
上記は2007年1月15日の「アトリエだより」。二十四節気掲載の始まりの文章。”酔生酔歩の身を自省。”が
恥ずかしい。毎晩毎夜、酔生酔歩とまではならぬも、仕事を終えて一日の”痛み,傷み”を酒でおさえている。
アトリエ開きは4日、仕事開始。 昨年と同じか……大晦日まで仕事日がノンストップであろうことは。
”日一日夜一夜(ひ、ひとひ よ、ひとよ)花鳥風月を愛で、日々是好日と感謝する心を忘れぬよう”………、この言葉、
多事多忙でも何とか”ゆとり”を見出せ!さもなくば、ロクな仕事は出来ないとの警句だ。
(Jan.6)
■『謹賀新年』……年賀状を書く。遅い?正月に出すのが年賀状





夜通し飲んでいた気がする。アルコール抜けやらぬ体、朦朧状態で年賀状を書く。今年はもう
年賀状を作ることをやめようかとも思った。時間がないとボヤキつつ流された日々、新年の挨拶すら
出来ないなんて、情けないなあ。一念発起、大英断、決意を固めて(何と大袈裟!)パソコンに向かう。
小学生~高校の頃は木版。それから活版印刷、シルクスクリーン、プリントごっこ、コピー機と作法が
変わった。ここ十年は現代童画展出品作の絵葉書で出している。昨年はPC。「アトリエだより」の”号外”として
主に「鳩山の風景 = ささやかな幸せ = 蕗の薹の味噌炒めやてんぷら、新茶のおひたし、柚子の蜂蜜漬等の
田園の味覚」をプリントした。そこで、今年は……。松ぼっくりやドングリで作った人形。大黒様に似ている
カラスウリの種にも語らせました。里山の風の囁きを。
「本年もどうぞよろしくお願いします」
(Jan.2)
■新年明けましておめでとうございます。



 吉祥御神籤絵 大吉四枚揃え
吉祥御神籤絵 大吉四枚揃え
大晦日、東急ハンズへ。ジャンク台を漁り金属板やウレタンの切れ端を集める。すべてマチエールの研究、
フロッタージュの素材に、また版画にも利用できるかと、持って帰る重さを省みず買う。クリスマスの騒ぎが
終わったといえ、明日新年を迎える街は華やいでいる。が、普段と変わって静か。このところ大学の絵画造形の
授業が頭から離れない。創造の面白さ、自由な造形の楽しさを学生にどう伝えるか、そればかり考えている。
自分だったらこうする、ああする……、創造の世界は想像に遊ぶこと。答えがない表現の可能性、多様性が
何よりも魅力。
時に思う。「制作者を辞めて専ら教える人になったら?」……それは違う違う違う。ぼくは器用ではないから
あれやこれや出来ないが痩せても枯れても表現者。創作しない自分なんて考えられない。こんな考えが脳裏を
かすめるのは創作できない自分を許そうとしているのだろうか,逃げようとしているのだろうか。創作、表現は
精神作業、一年間休みナシで、確かにぼくは疲れている。
(Jan.1)
| 12月のアトリエだより |
■ドングリで遊ぶ。 師走、最早今年も数え日。改年に想いを巡らす。



学生時代、ぼくは期末試験が近づくと、おかしなもので決まって何か勉強以外のことをやりたくなった。今も変わらない。
忙しさの極みなのに、今日はドングリと遊んだのだった。ドングリのリース(蔓はアケビ、袴を接着剤でクヌギのドングリに
履かせ、小枝に二つより沿うように留らせた)や、ヤジロウベヱを作った。落ちそうで落ちないヤジロウベヱを飽きもせず
人差し指で小突いていた。 <この辺の写真は年賀状に掲載予定>
古道具屋で見つけた「煎餅焼き器」でドングリ煎餅を焼いた。五円玉大の球状に丸めたドングリ粉(小麦粉3割)牛乳、
ベーキングパウダーを加え練る。ローラーでのし、型抜き。これが楽しい。ハート、木の葉、星、うさぎ等々。”ドングリ型”が
ないのが残念だ。火に掛け20秒ほどで、パリパリの煎餅が焼きあがる。素朴で、うまい。太古の昔、縄文人が主食にした
ドングリを、心して味わった。(ドングリクッキーは天火で15分)
ドングリ粉になるまでの手間(マテバシイの皮を取り、グラインダーで砕く。更にコーヒーミルで細かく挽く。水を張りアク抜きを
一週間。毎日水を取り替えた)が、何でもないように思えるから不思議だ。
あと二日で大晦日、何で今ドングリ?でも……、嬉しさがこみ上げてくる。作る楽しみ、少しづづ齧る楽しみ。喜び。忙中閑あり、
ぼくにとっては、これが幸せ。傷んだ心、静まる一日だった。だが、待てよ……、仕事はどうした!仕事はどうする!
明日、地獄が待っている!終日仕事、覚悟せねば!嗚呼。
(Dec.29)
■正月の準備に鳩山へ。慌しく日帰り、疲労困憊
年賀状を作る時間がない。正月の為の買出しもできない。教材教具を買い集めに奔走。ホームセンターや東急ハンズ、
100円ショップなどを歩き回るものの、自分のことは全く手付かずだ。
鳩山のアトリエで毎年、年を越すが、今年はどうなることやら。それでも、少しでも掃除をと出かけたものの、やり残した
仕事が気になって仕方がない。這う這うの体で退散。
冬枯れの庭の隅に鳥かごを発見!鳥かごと思ったら、それがトラップ!もうビックリだ。篭の中にオレンジの輪切りが入れられて
いて、小鳥が入って、出ようと羽根が一寸でも触れると蓋が落ちる仕組み。何と残酷!枯葉の地面に一個置かれ、ナナカマドの
幹に一個取り付けてあった。誰だ、こんなことをするのは。直ぐはずした。無人の庭に忍び込んで仕掛けたのだろう。嫌な気分だ。
ぼくのアトリエは小鳥の楽園と思えるくらいよく集まってくる。農薬はナシ、人影もナシ、巣をヘビが狙うのが唯一の危険かと
思っていたが、油断できないのは人間であった。
風は強く冷たいが空晴れ渡りいい天気。ヒヨドリが入れ替わりやってきて渋柿を突いている。行儀悪く、一つに集中せず
あれやこれや食べ放題!時おり実が落ちて潰れるが、果たして、あんな渋いのを……、そう思って高枝鋏で切って
熟し切った実を口に含んでみた。甘い!そうか、熟しきって渋が消えたんだ。今日は乱暴者のヒヨドリに教えられた。
(Dec.28)
■クレヨンまる 第148話は拡大版16ページ 『新発明は"いちごクレヨン"』

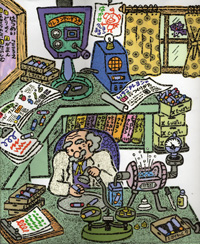

月間お話雑誌『おひさま』(小学館)が発売になりました。早いものです、雑誌の世界ではもう2月号です。今号では
「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」が特集として掲載されています。16ページ、読み応え、見応えたっぷりです。ぜひご覧ください。
クレヨン博士の下に一通の手紙が届きます。風船ガム王国のガムッチ王子からでした。「面白いクレヨンをつくってください。
ご褒美をあげます」………もちろん博士は挑戦します。考えた末!!いちごクレヨン” を発明することに決定。ところが大変!
大泥棒のオオカミ、ワルズーの子分、コウモリのコモリンが博士の計画を盗み見ていたのです。
ワルズーは召使のミイラばあやに頼みます。「ばあやも”イチゴクレヨン”作って!クレヨンまるたちより、先回りして、
ガムッチ王子からご褒美をせしめてよ!」
ワルズーとミイラばあやは、クレヨンまるたちの行く手を阻み到着を遅らせます。そして、ガムッチの下へ行き、”いちごクレヨン”を
披露します。果たしてご褒美はワルズーがせしめてしまうのでしょうか?
遅れてやってくるクレヨンまるたちは?クレヨンはかせの”いちごクレヨン”とは一体……? ご期待ください。
次回のクレヨンまるは7月号掲載予定です。8月号で通算150話。「クレヨンまる」は歳をとりませんねえ。「こんなこいるかな」の
「やだもん」「ぶるる」「たずら」「まねりん」「はっぴ」たちも歳をとりませんねえ。
ぼくも心はそんなつもり(若・若・若……”一瞬懸命”)でおります。創作の心が些かでも曇ったり、鮮度が落ちたら、歳を認めざるを
えませんが、体力の低下だけは目に見えてしまいますね。それをカバーするのが気力。がんばれー!がんばるよー!
(Dec,27)
■二十四節気<冬至> 七十二候(六十四候.六十五候.六十六候)
 |
冬至は12月21日 (小寒は1月5日) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月26日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (12月31日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
■紙で帽子を折る。かぶってみようと頭に……前の作品が頭にのっている……。新作が出来る喜びは創作全般同じだ
気忙しい師走だ。昨年の今頃は、まだ少しは心に”ゆとり”があったのだろう。鳩山で柚子を採ったり、まきを切ったりしている。
今年は何もできずに仕事に明け暮れている。いや、毎日バタバタしている。年賀状も手がけられず、気になるところ。
ぼくは集中すると何も見えなくなるからいけない。レジュメ一つとってもそうだ。先に進まずどんどん深みにはまっていってしまう。
「子ども教育学科」の絵画造形に折り紙を加えようと、それも新聞紙や包装紙でつくる”すぐ役立つもの”をと考えた。
決めたテーマが帽子。『CAP & HAT百貨店』と題して何点か作らせかぶらせる……、企画案は良いのだが、”集中して何も
見えなく”なってしまった。
昨日までに作った帽子………GI帽三種、王冠ニ種(キング、クイーン)、トンガリ帽ニ種、コーンハットニ種、ソンブレロ、コンビニ帽、
ナースキャップ、ナポレオンハット、ペンギンハット、ウサギ帽、Cat & Dog、Holy Father's Hat(教皇帽)。
作り方を製図するのに時間がかかったが、”定番”のものより、オリジナルを工夫して作るのが性に合っていて楽しい。
試作を重ね2~300は折っただろう。部屋中紙帽子が散乱している。狭い部屋の床が見えないくらい帽子の山だ。
ぼくは帽子大好き人間。普段ベースボールキャップ(取っかえ引っかえ幾つも。アトリエでも)を愛用しているが、一番の好みは
”ルンペン帽”。(ルンペンの言葉は使ってはいけないのかも)黒のフエルトをただ釣鐘型にしたものだが、三十数年来の愛用だ。
これ以上好きな帽子はなく、帽子を主題に私家版絵本『プックリおじさんの独身時代』を作ったこともある。
大学の授業、「帽子の造形」で学生にお披露目したら………、やはり笑われちゃうだろうなあ。
(Dec.22)
■カラスウリの種は招福財運?………あるものの形に似てる……感心!



鳩山の野、あちこちにカラスウリ。風に揺れ濃い橙色が光る。木々の枝に絡みついたまま、枯れ萎んでいく。
綺麗なうちに採取し種をとる。熟したカラスウリは簡単に潰れる。狙いは種。カラスウリの種のかたちは変わっている。
「打出の小槌」だと聞いたことがある。そう見れば確かに打出の小槌だ。でもぼくには、恵比寿大黒の顔に見える。
いずれにしてもお目出度い形だ。財布に2~3粒忍ばせれば財運来たりの伝承ありとも聞いた。
ぼくは絵描き。画家の形容は昔から”貧乏絵描き”。ぼくも財布にカラスウリの種を入れておこうか。いや、絵描きは
絵さえ描ければそれで満足する人間だ。それ以外大した欲も持たず、”貧乏”を考えもしないから、この種も形を
楽しむだけで十分。財布は軽くともね。
(Dec.13)
■二十四節気<大雪>、七十二候(六十一候.六十二候.六十三候)
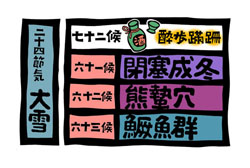 |
今年の大雪は12月7日 (冬至は12月21日) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月16日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
北風が冷たい。真冬並みの寒さになってきた。金曜日は強風下テニスコートへ。トスアップもラリーも儘ならぬ
”悪天候”なのに愛好者の熱心なこと!普段と変わりない賑わいぶりだった。2ゲーム、風に翻弄されながらも楽しみ、
その足で大学へ。
〆切が迫り来る『創造的造形遊び』の原稿書き。原稿といっても、タングラム図形の創作。40点ほどだが
シルエット、実像、構成図をそれぞれ描くから100点以上になる。時間がない。忙しない師走だ。
大学の裏門の駐車場で松ぼっくりを拾う。松の木の梢が揺れるほどの強風に、松ぼっくりがバラバラ落ちてくる。
ポトン、ポトン、地面にバウンドして転がる。オーバルなのと、尖ったものと二種類、拾った数4,50個。多くは車に
轢かれ潰されていく運命の松ぼっくり、ビニール袋一杯になるまで集めた。手にヤニがついたけれど何か嬉しい気分。
松ぼっくりはクラフトに使う。「リース」「松ぼっくり人形」「モビール」……、直ぐには作れないけれど、
材料がたっぷりあることも嬉しい。でも今、クラフトを楽しめる心の余裕がないのが問題だ。
■ 大晦日、初詣の準備……静かな寺に人影が。
法事で、港区三田にある魚籃寺(ぎょらんじ)へ。三田といえば泉岳寺だがこの地域は寺が多い。
田町駅を下り、桜田通りを歩くと寺また寺。魚藍坂の近くには「忍願寺」。寺の名前に思わず微笑む。
日曜日、真冬並みの寒さとあって、寺参りの人の姿も見えない。中には、「何方でも除夜の鐘がつけます」
の張り紙も。師走なんだなあ。
魚籃寺の境内には八分どおり葉を落としたケヤキと、常緑のスタジイの大木があった。「港区の指定樹」
は番号の名札をつけられ何か迷惑そう。吹いたり収まったり……風が線香の香りを運んできた。
(Dec.7)
■ 図書館の廃棄本を頒けていただく。
大学の図書館で廃棄本の頒布が始まった。図書館にはぼくの研究室からは30秒足らずで行かれる。初日を含め何度か
のぞいてみた。
素晴らしい本を入手!例えば、『初期ヨーロッパの美術』(1974年刊) 「総説・柳宗玄「ヨーロッパの美術の二潮流」。
「ケルトの伝統とその新展開」、「ゲルマンの伝統とその新展開」、「地中海美術」、「カロリング朝とヨーロッパ美術」……
この大冊、廃棄処分される理由がわからない。探しても容易には得られないだろう。座右に置こう。大切にしよう。
他にも『弥生の布を織る』(竹内晶子・1989刊)、「羊飼の暦」(エドマンド・スペンサー・1976刊)など。「羊飼の暦」は
1579年、倫敦ヒュー・シングルトン書店で刊行された。1月~12月まで牧歌12編のスタンザ。アレゴリーが考えさせられる。
それぞれの牧歌に添えられた木版画に興味を惹かれた。
良いものを見つけ嬉しかった。「初期ヨーロッパの美術」は大型本で重たくて持って帰れなかったが、電車の中では
『弥生の布を織る』を開いた。原始的な織り機の絵に魅せられた。「ぼくも織り機を作るぞ」……頭の中では、早や、”設計図”が
引かれていた。後は時間の確保だ。
(Dec.5)
■ 師走………走るも走るも追いつかず、時は非情に過ぎ行く
当「アトリエ便り」も更新がままならない。『絵本的生活日誌』の”絵本的”も危うくなっている。立ち止まり空を仰ぐ、
自然に身を置き観照するゆとりがない。流されてはならぬと思いつも、目の前の”仕事”に押し流されている。
創作に充てられる時間の少なさを嘆く。噴出するエネルギーの押さえ込みが哀しい。
(Dec.3)
| 11月のアトリエだより |
■鳩山は荒れ放題!


鳩山のアトリエを片付けに行く。今年は外に出る暇も無く庭は荒れ放題となっていた。足を踏み入れられないようなジャングル
状態だったが、草は枯れ木は葉を落とし視界が広がっていた。カラスウリの実が小鳥にも虫にも誰も相手にされずに揺れている。
ビワの木が細かな花が咲いている。6本サークルに植えたイタリア松の30センチほどの苗木は、身の丈以上に伸びていた。
嬉しかったのは、剪定を失敗したマテバシイが、2年ぶりに小粒だがドングリをつけたこと。車の屋根に弾むように降り落ちた
忘れえぬ光景も復活しそうだ。
母屋の階段は手すりに絡みつくノウゼンカズラの根とアリにやられボロボロ。木工小屋の階段も傷みが激しく取り替えることにした。
工務店に相談、湿気対策もありブロックを積み煉瓦タイル仕上げを依頼した。
日差しは弱いが、それでも”恒例の”パネルの虫干し。カビがひどい。悩みの種だ。いつも、このお陰で仕事にスムースには入れない。
パンパスグラスの大株からヤマカガシがニョロニョロ。冬眠の準備をしているのだろう。アトリエの片付けもそこそこ、鳩山を後にする。
(Nov.25)
■懐かしい”コハゼ”……掌で踊る

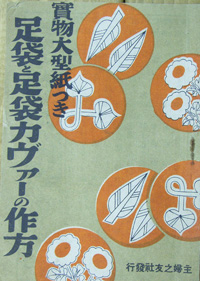
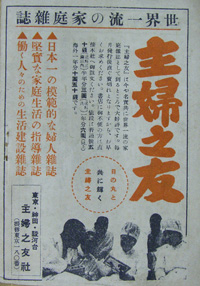
足が直りコートへ。何日ぶりだろう、久々のテニス。初めは恐々打っていたが、いつしか夢中。すっかり良くなったと
勘違いさせるから困る。準備運動は怠ってはならない。足の具合もだが、嬉しかったことがある。
テニス仲間のSさんが「持ってきたわよ。これも、よろしかったらどうぞ。」持ってきた、というのは「コハゼ」。よろしかったら、
というのは30年くらい前の図工の教科書や雑誌。以前もお嬢さんの子供の頃の本をくださった。コハゼは
「ぼくは、足袋を履いて
小学校に通った」 「当時の”足袋の作り方”の本を手に入れた」 と話したのを覚えていてくれたのだ。図工の教科書は
「参考になれば」というもの。感謝。ちょっと喋ったことを気にとめて置いて持ってきてくれた。(コートにいつ現れるか分からないぼくに)
日差しは温かいが風があり、プレーが途切れると冷んやり。初冬の寒さの中でのテニスだったが、心はポカポカ、
嬉しいなあ。Sさん、ありがとう。
写真の主婦の友社刊「足袋と足袋カヴァーの作方」は紙も粗末なハガキサイズ。定価50銭。驚くのは、いかに売れたかという事。
何と、昭和27年に105刷りがでている。それも30000部の発行。大ベストセラーではないか。家庭の主婦が端切れを集めて
足袋を作っている姿を想像する。(Sさんは8~9歳の頃、お母さんに教わりながら、足袋を作ったそう)。
物が無かった時代とは言え、生活が変容したとは言え、人間の力(生活力)、工夫、一針一針縫い上げる気持ち(愛情)……
大切なものが滅びたのは確かだ。”利便”を追い求め、行き着くところが、想像力や創造力の衰退か……。愚かしい。
(Nov.22)
■二十四節気<小雪>、七十二候(五十八候.五十九候.六十候)
各地から初雪の便りが……。初冬、挨拶文も「向寒の砌……」「お風邪にご用心」「今年も残すところ……」
師走が迫ってきた。忙しない気分ますます。「アトリエだより」を見ると、昨年の今頃ぼくは、白州次郎の武相荘を訪ね、
マテバシイのドングリを拾っている。忙しさは変わらないのに、心の余裕がまだあったということか。
(Nov.21)
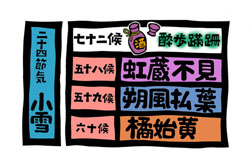 |
今年の小雪は11月22日 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月22日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月27日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
■学生行き交う中、銀杏を拾うは男一人


キャンパスの大銀杏がバラバラ銀杏を落としている。学生は頭に当たらぬように、踏まぬように避けて通っていく。
降るように落ちる銀杏にはまるで関心がない。ぼく一人、強い北風の中、しゃがんで銀杏拾い。潰され臭くなる前に
拾って片付けて居るとでも思っているのでは。掃除人か……、それも良い。 頭にあたる。背中にあたる。北風が梢をゆらし、
黄金の実を吹き落とす。バラバラ……、ターン!!トーン!!これは、アスファルトに当たった音。実が破れ白い殻が見えている。
拾いきれない。教材の空き箱2つ、またたく間に一杯。拾うのは、(拾うというより、集めるという感じ)簡単!後の処理が大変だ。
ゴム手袋をして果肉を取り除くのだが、臭くて鼻が変になる。昔は土に埋けておいて腐らしたものだが……。
でも、苦労もなんのその、「酒の肴」にと思えば大したことではない。楽しい作業にさえ思えるから不思議だ。
銀杏の木の恵みは、畏友の杜氏、宇都宮繁明君の大吟醸『月の滴』の酒の友としよう。
(Nov.19)
■寒さが苦手!冬対策!
普段から”足が冷える”ぼくは暑さには強いが、寒いのは苦手。渋谷の仕事場では机の下に足温器、膝暖板を
置いている。新宿で仕事をしていた時は電気スリッパ、電気チョッキそれに、テーブルコタツを改造して使っていた。
空調機から吹き出る温風も気持ちよいものではなく、今年もまた寒さ対策の苦労が始まる。
じっとして仕事するため、血の廻りが悪くなるのだろう。低血圧……、ぼくの場合、テニスをするに限るが、この一年
打つ回数が半減した。体調維持が問題だ。
大学の研究室、もちろん冷暖房完備(古い言い方だねえ)だが、それでも足元は寒い。スイッチさえ入れれば、研究室は
広くないからすぐ温まる。いや温まりすぎる。暖気が天井に集まり循環しない。シーリングファンを付ければ良いのだろうが、
そうもいかない。で、冷え対策としてセラミックヒーターの小型のものを購入した。これで、快適。研究室に居る時間が長くなりそう……。
(Nov.18)
■落語「目黒のさんま」アニメ原画イラスト14枚制作




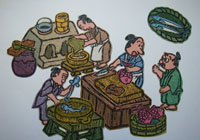
落語「目黒のさんま」を、CDの音源をもとに作画。オチが、お終いの「サンマは、目黒に限る」だけなので、映像化では殿様の
目黒での”初めての体験”、サンマを食すシーンが重要な意味を持つ。原稿ではその辺があっさりし過ぎていて少々物足りなかった。
目黒の田舎風景を印象付けるため、1~2秒しか映らないであろうが野駆けの場面を描いた。アニメではお百姓さんの焼く
サンマの煙が立ち上るだろうか。焼けたサンマがにおい立つだろうか。
(Nov.17)
■体調万全。気力漲る。
手の怪我は爪の割れは仕方ないとしても、包帯も取れ生活に支障はなくなった。何針も縫ったとはとても思えない。足の方も
痛みが薄れ、精神の”停滞期”を叱咤し、車を控え歩き廻っている。健康の身を感謝する。目一杯頑張れる喜びを感じている。
仕事場で、アトリエで、教室で、研究室で……。
大学の研究室は1F にあり、”専用”と思えるような図書館に通ずる出入り口がある。目と鼻の先だが雨にも濡れずに図書館を
行き来できる。図工遊び関連の教材の搬入搬出を考えて、ぼくの研究室を1Fにきめてくれたのだが、窓のブラインドを下ろしたままに
せざるを得ない点を除けば、大いに気に入っている。
(Nov.14)
■幼児保育雑誌「マミー」が消える!
小学館の月間保育雑誌「マミー」が1月31日発売の3月号で休刊となる。4月~6月の発行部数の平均は12万部以上も
あるのに……。少子化、電子媒体など読者環境の変化が発刊を取りやめる理由だろうが、十万部も出ていて惜しいなあと思う。
小学館ではかつて数十万部を発行した「よいこ」もいまや無く、「ベビーブック」「めばえ」「幼稚園」の三誌のみとなった。
講談社でも「えくぼ」が休刊し「げんき」「おともだち」「たのしい幼稚園」の三誌だ。70~80年代の子供雑誌黄金時代には
数社から保育絵本雑誌が発行されていた。手元にあるものを見ても、詩があり、童謡あり、昔話あり、世界名作あり。
生活絵話(しつけ)あり盛りだくさんだ。季節感豊かで、叙情味ある絵が多く、いまや全盛のキャラクターものなど皆無。
しっとりしていて心が落ち着いてくる。編集後記も雑誌に賭ける心意気が伝わってくる熱いもので、現行の雑誌には一切
みられない「つたえたい心」がある。いまや、すべての雑誌に手描きの絵(イラスト)は乏しくオール、キャラクターのオンパレード。
CGのイラストを見せられ続ける子どもが心配だ。
子どもの保育雑誌の仕事を長くやってきた。創刊から立ち会った本もある。”完成付録主義”の編集方針にぼくは首をついつい
傾げてしまう。雑誌文化の火が消えそうな気配に、世の流れに抗うような堅固な気骨を持つ編集者は現れないものか!
”消える”といえば、年賀状の季節に大活躍した「プリントごっこ」も姿を消すことになった。簡易孔版印刷機だが、ぼくは愛用した。
ファンも多いと思う。PCの利便さに敵うものではないが、”手仕事”の温かさは捨てがたい。アナログが又一つ消えていく。
人は”手作り”からまた遠ざかっていく。人間の力が衰えていくに等しいのに……。PCが手も汚れず綺麗だから……?
世の流れは万事こうだ。いも版画、紙版画、木版、ちぎり絵、貼り絵……、手作り年賀状なんて今や昔か。良しとしないぞ。
(Nov.10)
■立冬………、二十四節気、後3つで今年が終わる。
時の流れの速さに、自らの非才に、嘆息。夏の終わりに指を、秋の終わりに足を、不注意から怪我し、
仕事も進度が落ちた。展覧会にも行かれず、唯一の気分転換のテニスももちろんダメ。仕事場に籠っては
いるものの集中力に欠け、楽しくない。「楽しくないなら、やめちまえ!」悪魔が囁く。逃げ出したい気分。弱気の自分を
叱咤するもう一人の自分が恐ろしい眼差しで睨みつける。かつてA新聞のK氏が手紙に書いてきた「甘えない。これでもか
これでもかと仕事を!」の言葉が脳裏に浮かぶ。ひたすら仕事に立ち向かうしか術は無いのは経験から分かってはいるが……。
(Nov.9)
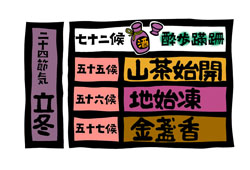 |
今年の立冬は11月7日 (小雪は11月22日) ・五十五候 (11月7日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月12日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月17日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■この秋初めての冷たい突風……木枯らし一号だった
面目ない。今日は現代童画展の陳列日なのに行かれない。階段を駆け下り踏み外し左足首捻挫、ふくらはぎ肉離れ。
情けない。35年間こんなこと初めて。不注意といえばそうだが、階段は上がるのも下りるのも二段ずつ、体は鍛えていた
はずなのだが……踏み外すなんて。成城外科の先生に診てもらう。幸いギブスの世話にはならずにすんだが、歩くと痛い。
冷たい突風は昨年より17日早い木枯らし一号だと知った。冷え込む中、足を引きずり歩いた……。情けなかった。
明日は表彰式。これも初めての欠席となる。残念だ。東京都美術館までが遠く感じられる。嗚呼……。
(Nov.1)
| 10 月のアトリエだより |
■銀杏を拾うゆとりもなく……
大学のイチョウの並木道に銀杏が落ちている。黒のアスファルトのあちこちに、イエローオレンジの実。行き交う学生は
見向きもしない。ああ、もったいない。が、ぼくには拾う時間がない。恰好の酒肴なのになあと、横目に見ながら、図書館へ。
アリストテレスの弟子、テオフラストレスの「人さまざま」を借りに。生憎く蔵しておらず、図書館で購入依頼書を書いてきた。
性格を書き表している最も古い本だといわれる。興味津々……。到着が待たれる。
(Oct.27)
■閻魔大王の絵を描く。「閻魔様」なんて描いたことないよ

落語「目黒のさんま」に絵を付けている。料理番が、殿様が「さんま」と言うのを「えんま」と聞き違える場面がある。えんま大王の
絵を描くのはもちろん初めてのこと。小さなカットだが、資料を集めて参考にした。その中の一冊が「地獄」。何と「地獄」は
子どもの絵本だ。驚いた!絵本に「地獄」があったなんて。この絵本、売れそうもない。多分、売れないだろう。暗い。恐い。悲しい。
でも、存在感は凄い!三芳村延命寺に所蔵されている16幅の絵巻が元になっているこの絵本、見ごたえがある。折檻、
人殺しなど残虐なシーンが随所。死出の山、三途の川、奪衣婆、閻魔王、なます地獄、火あぶり地獄、火の車地獄、それから
極めつけの無間地獄、賽の河原と続き酷いことこの上なし。絵本が”愛らしいもの”と思っている方々は手に取ることも憚るだろう。
刊行趣意書には、こう書かれている。”「地獄絵はいろいろな様相をもっていますから、見る人によって受け取る意味はそれぞれ
異なってくるでしょう。私たちは、これを見る子供が、「死ぬことは恐いことだ」ということを心に強く刻むであろうと、それを主題に
絵本づくりを思いたちました ー中略ー いま私たちが子供らにしてやらねばならぬこと、それは生きることのよろこび楽しさを
存分に教え、と同時に自らの生命を尊び、自らそれを強く守るという心を培ってやることでしょう。」”
存在感が凄い!と言ったのは、この絵本の必要度も凄い!と思ったから。日頃、絵本はよく見るが、この初めて見る「地獄」に
しばらくは、頭を占領されそうな気がする。
(Oct.26)
■二十四節気<霜降>、七十二候(五十二候.五十三候.五十四候)
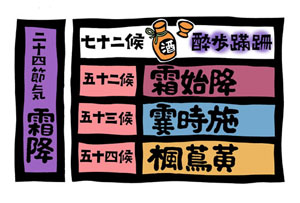 |
霜降は10月23日 (立冬は11月7日) ・五十二候 (10月23日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月28日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月2日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
23日は二十四節気の霜降。霜は下りないが23,24日と雨降りだった。24日は一時激しく降った。両日とも上野、東京都
美術館へ。第4回現代童画会展審査会に出席。毎年のことだが、美術館の地下三階にいると胸が重くなる。外気が
入らぬせいか、自然の光が届かぬせいか。審査を終えて”地上”にでると、東京の空気でもうまく感じる。靴も服もびしょ濡れで
渋谷に帰る。
疲れで仕事に入れず、パソコンの前に坐る。疲れていてもキーボードは打てるからいけない。これが後で疲れを倍増させるのだから。
フォトショップ、イラストレーターで、大学のトートバッグのデザインを試作する。学生に画材を詰めて渡したり、ノベルティにも使える。
帆布製のバッグが最上だが、予算でコットンのエコバッグになるかも。見積もりを取らねばならない。雑用多し。
(Oct.24)
■大学学長退任記念講演会とパーティーに出席
小泉学長の挨拶は,大学の歴史と建学の精神についてだった。設立は1900年(明治33年)。
「日本女学校」として文京区湯島に開校した。後に「帝国女子専門学校」の設立が認可されたが、昭和20年、
米軍の空襲により全校舎と7つの学寮が消失。当時の学生の手記が読み上げられた。
焼けて倒壊した建物から取り残された学生を救出できず4人の命が失われたくだりでは、生々しい証言に目頭が熱くなった。
現在の相模原のキャンパスは昭和21年から。建学の精神は「高潔善美」……いい言葉だ。
銀杏並木を歩くとき、ぼくは、この「高潔善美」を呟いている。ちなみに学習院は「自重互敬」。忘れえぬ言葉だ。
■訪問者は、秋の虫「カヤキリ」


板絵F100号作品が完成!画題は『Father’s Letter』額装し梱包。運送屋さんに搬入を託す。今さっきまではアトリエの
主は『Father’s Letter』だった。絵の前に座り、しばらく見ていた。いつもそうだが、ぼくにとって一番幸せな時間かもしれない。
アトリエで一人作品を眺める。仕上がったばかりの絵を飽きることなく見つめる。静かで心穏やか、何とも言えない時間が流れる。
これが”至福”というものだろう。
運送屋が去り、アトリエは火が消えたよう。主がいない。魂が抜けたようだ。11月2日から開催される
第34回現代童画展(東京都美術館)会場での”再会”が待ちどうしい。
今年は庭に出ることも無かった。雑草で荒れ放題、木々も伸び放題。入り口だけでもとナツメ、サンシュユ、サルスベリ、サンザシ
クリスマスホーリーをチェーンカッターで切断する。剪定なんてものではなく、乱暴に切り落とすだけなのだが、みるみる枝葉の山。
ホーリーの葉の鋸歯、ナツメとサンザシの枝の棘が痛い。捨てに運ぶのも一苦労。
ナツメが実を付けている。サンシュユも”大豊作”だ。艶やかな赤い実は美味しそうだが食べられない。ナツメ同様乾燥させ漢方薬
として用いられている。ぼくは薬草酒にしようと少しだけ集めた。5センチくらいの虫がとまった。ウマオイかと思ったが、ウマオイにしては
大きすぎる。図鑑で調べたらカヤキリ(キリギリス科)だった。「ススキの原に住み、ジーンと強く鳴く」と書いてあった。さすがにカメラの
前では鳴いてくれない。みどりの訪問者は写真を撮り藪に返した。外はもう真っ暗だった。
(Oct,18)
■古書に感激
図書館で『清少納言の知恵の板』を借りる。ハガキ大の小さな和とじ本。1742年(寛保2年)刊行、{知恵の板}タングラムの
図形が42題、問題と答えが載っている。正方形を切り分けた三角形5片、四角形2片の7片で構成する図形が美しい。
中国の文献『七巧八分図』(1803年刊行)は図書館には無く、他大学に借用依頼をした。どんなものか、早く見てみたい。
(Oct.16)
■大学のイチョウ並木。銀杏の降るキャンパスを歩く。
テニスコート前のクヌギからドングリが降り落ちている。まさに”降る”状態。地面はドングリで覆われている。辺りは
幼稚園送迎のお母さん方の車が駐車してあるが、屋根に弾む音がする。キズがつかないのかなあ。
はかまのついたもの幾つか拾った。袋を持っていなかったので、ポケットに入れた。左のポケットには
松ぼっくりが入っている。形のいいのを見つけると嬉しくなる。秋風が気持ちよい。研究室に戻りたくなくなるから困る。
(Oct.15)
■秋便り


秋の空、雲、風……、庭もノウゼンカズラやマンジュシャゲような激しい色合いの花から穏やかな菊にかわった。ふじばかま、
オミナエシも腰丈より伸び風に大きく揺れている。今年はワレモコウを見ない。ジャングルと化した庭で背丈の低い草花は
雑草に覆われ太陽が届かず育たない。手いれを今年は一度もしなかったなあ。アトリエに来ても庭には出ず仕舞いだったなあ。
栗の木が草に囲まれてしまっている。栗の木に近づけず、今年は栗拾いもしなかった。時間の余裕無く、高齢者事業団の方に
頼んで草刈をしてもらう。栗はもう収穫の時機をすぎていた。枝に残っているものも多くあったが、これとて叩き落す暇さえない。
目で秋の始まりをほんのちょっぴり楽しんだだけ。東京での仕事が待っている。テキパキと片付けられない仕事と、時間のなさを
恨めしく思う。慌しく帰京。
(OCT.9)
■山椒の実が弾けたよ


増えて困るものが杉と山椒。至る所に芽を出し、雑草にも負けずに育ってしまう。”しまう”と言うのは
後で抜き取る手間が大変だから。一昨年まではマテバシイがそうだった。マテバシイは雨のようにドングリを降らし、
芽を出した。が、剪定を失敗してから、めっきり発芽が減った。元気がないマテバシイを眺めては、「ごめんな。なんとか又、
大きく伸びてくれ」と、勝手なお願いをしている。
写真(右)は山椒の種が弾けるところ。決定的写真。この黒い種が多数落ち、発芽するんだなあ。あたりはすっかり秋の
景色。紅葉はまだまだだが、秋の花々が寂しげに風と話している。囁きが聞こえるようで、そっと耳を傾けてしまう。
風の向きによってキンモクセイの甘い香りが漂って来、鼻腔をくすぐる。3本植えた1メートルほどのキンモクセイの苗木は今や
屋根より高くなり、盛んに香りを振りまいている。アトリエの窓辺には白い花のギンモクセイを植えた。香りは弱いと聞いたが
どうして、鼻を近づけると、むせ返るほどの芳香だ。いずれも、好きな香り。でも、風に漂ってくるくらいが丁度よい。
(OCT.8)
■二十四節気<寒露>、七十二候(四十九候.五十候.五十一候)
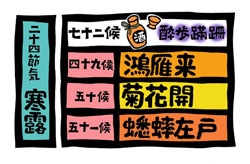 |
今年の寒露は10月8日 (霜降は10月23日) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
■あまり見られなくなった稲架(はさ)掛け。懐かしい風景、刈り取りの終わった田んぼを歩き廻る
 ・稲架(はさ)掛け
・稲架(はさ)掛け
鳩山のアトリエで100号大の板絵の制作に明け暮れる。鳥の声以外、物音一つしない。静寂が何よりだ。
軽トラックが止まり、石井さんご夫妻が降りてきた。下の田んぼでの主。新米を届けてくださった。ぼくの大好きな
玄米も。それに、奥さんの栗の渋皮煮も作ってきてくださった。。さっそく一つ丸ごとほうばる。形の崩れが無い見事な渋皮煮だが、
砂糖の分量がほどよく、栗の風味を邪魔していない。美味い。二つ目を口に入れる。見ている前で箱を開け、食べる失礼を
許してくださいと言うと、「すぐに食べてくれるのが嬉しい」と笑った。
昨日まで稲穂が頭を垂れていたのに、今日は刈り終わっている。昨今は機械だから刈り取りもアッという間だ。稲架掛けは?
と聞くと、「今、そんなもん、やってるとこ、ないよ。機械乾しさ。早やいからねえ」と笑っていった。
そうなると、子供の頃見た、田舎の稲刈りや稲架掛けが懐かしく思われてならず、カメラを持って、探した。
あった。ありましたよ。いいねえ、稲架掛け。(写真)長閑な田園風景、瞼に焼き付けておこう。
■横殴りの雨の中、松涛美術館「大道あや展」へ。

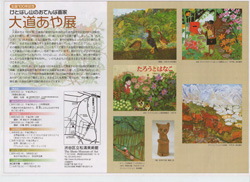
・大道あや展パンフ(渋谷松涛美術館)
相変わらずの忙しなさ。大道あや展も最終日に美術館に駆け込んだ。
台風の余波で横殴りの雨で全身びっしょりになって。
大道あやのまとまった作品群をみるのは初めて。
2009年に100歳になる大道あやの初の回顧展で、どうしても見たかった。
大道あやの母は丸木スマ、(長男,位里その妻俊子=原爆の図=丸木美術館はぼくのアトリエの
ある鳩山からすぐの所にある)ぼくはあやより、スマの絵がよいと思っている。
スマは70歳を過ぎて描き始めたが天真爛漫な子どもの絵。さいたま市の県立近代美術館で
「丸木スマ展 樹・花・生きものを謳う」と題して開催中で、大道あや展に行くか、
丸木スマ展にいくか大いに迷った。が、時間がとれず残念だが丸木スマはあきらめた。
あやとて、描き出したのは遅い。絵筆をとったのは花火工場で夫が爆発事故で亡くなった61歳から。
大道あやはの絵は「けとばし山のいばりんぼ」などの絵本で知っていたが大画面の絵は見る機会がなかった。
自然描写がいい。とくにニワトリがたくさん画面を埋め尽くす絵は、良く見て描いてるなと思った。
空間が全く無い絵だが描きたかった気持ちが分かる気がする。
大道あやらしさは院展出品作の大作より自由に描いた作品や絵本のほうにある。
とはいえ、やはりスマだ。スマの展覧会に行かなかった自分を責める。見たかった。
あやよりスマが自然体、自由度100パーセントだ。
心に響いてくるのは、生きる喜びがそこに表現されているからだ。
| 9月のアトリエだより |
■朝夕冷え込み、まさに「秋冷の候」と相成れり……制作時間の確保が難題、嗚呼忙しなし。
幾つかの仕事を抱え、すべてをやりきる気概はあり、今まで(ぼくにとっての難局)何とか乗り切ってきたが、走り続ける
速度は減じた。力が衰えたのは認めざるをえない。芸術の表現欲求は些かの衰退もなく、ますます身体中に横溢を感じる
のだから、そのギャップにとまどう。が、負けるわけにはいかない。勝ち負けでは無論ないが、挑戦とか,自らに負荷を
与えるなどとの考えが少しでも浮かんだら、それは甘えだ。選びし、この道。選びし、最良の孤独の時間なのだ。誰に言われた
わけでもない。自然体でこの道をひた走る以外、他に何も余計な考えなど無用なはず。忍び寄る邪念は、まだ仕事に余裕が
あるということか。忙しなく過ぎる日々に,溜息ついている場合ではない。カツを入れて仕事に精出そう!
信州の方言では頑張ることを”ずく”を出すという。休みたいなんて考えたら、それは”ずくなし”ということ。”ずくなし”は嫌だ。
(Sep,28)
■秋分の日。雨上がり快晴。空には秋の雲。
秋学期始まる。 昨日は大学の研究室で10時まで仕事。プリント作りに精をだす。
一昨日は鳩山のアトリエに閉じこもり制作に没頭。外には一歩も出なかったが、夜の静寂の中に響く虫の声に秋の訪れを
感じた。早朝、川越街道を走る。上福岡あたりで白い彼岸花を見かけた。多くは赤い花だが、白い蔓珠沙華は
混じることなく所どころに固まって咲いていた。毒々しく見える赤に対して、形は同じでも清らかだ。辺りの緑に映える赤と白が
しばらくの間、目の奥に残っていた。
(Sep.23)
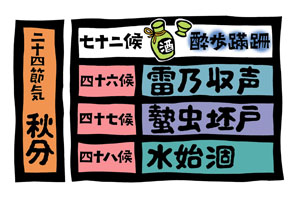 |
秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
■夜、天を走る稲妻、闇に轟く雷鳴に身をすくめる……朝、乾いた風心地よく空晴れ渡る。鳩山、秋の始まり
板絵制作に取り掛かる。昨年より一ヶ月遅れだ。鳩玉のアトリエに籠ってひたすら板と向かう。「3時間彫って1時間休む」の
繰り返し。初日、プロパンガスが出ず、コーヒーメーカーで湯を沸かしての食事。シャワーは水。10時間は彫っただろう、右腕が
ぱんぱんだ。
2日目、巡回サービスマンにガスを見てもらう。単純なバルブ開栓忘れだった。ああ恥ずかしい。人の良い青年の
笑顔に救われる。三日間で唯一話した人だ。
3日目、左手のケガは治りつつあるものの、彫刻刀を握る右手との”呼吸”が合わない。ベニア板を抑える指をかばってしまい
力が入らないのだ。彫り進み具合に不満だが、爪が割れているので仕方ない。仕事ができるだけマシと、感謝する。
腕に続いて肩が張って痛い。腰も限界だ。エスキースと板を眺めながら、作品のタイトルを思案。テーマは「手紙」。4月に
見た「GRAND FATHER’S LETTER」展のイギリスの退役軍人ヘンリー卿が4人の孫にあてた100通以上の絵手紙が
まぶたに残っている。が、ぼくの「手紙」は特定の誰かが誰かに届けるというものではない。「父さんの手紙」「父からの手紙」
「FATHER’S LETTER」……、いずれかだ。
三日間の彫りも半ば、いつも以上の”立ち去りがたい”思いで鳩山を後にする。移動は気分転換、さあ、渋谷で仕事が待っている。
新たな気持ちで立ち向かおう。
(Sep.10)
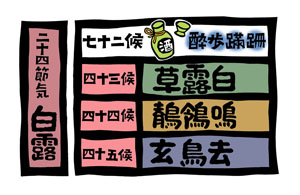 |
9月7日は白露 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月7日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月12日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月17日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
■駒ヶ根高原美術館 -童心の風景・有賀忍展-終わる
駒ヶ根高原美術館 -童心の風景・有賀忍展-終わる。降り続いた雨が朝、ピタリと止んだ。展覧会の無事終了を
祝うような快晴だ。気透明に澄み天は高い。新しい秋の涼風はさわやか。この夏、何度通っただろう、中央高速道。今日、
最後の駒ヶ根行き。視界には山並みが遠くまでクッキリ。7月の中ごろまであった雪渓は消えていた。山の顔は来るたび
に変っている。雲間のアルプス、霧にかすむアルプスも好きだが、今日の連山は緑が一層濃くそれも雄大、迫って見える。
展覧会を企画した美術館には感謝。館長、理事、学芸員、事務長、他支えて下さった全員に「ありがとう」。
来館者のなかに、遠来の知人の名も。大阪、和歌山、名古屋、沼津、静岡……。美術館で花は禁じているものの、多くの
方々から花が届けられた。一番大きな花台のものは、花屋泣かせ(入手、モチが悪い)の山野草、野に咲く花木、実で構成
された”自然のオブジェだった。送り主の心を感じ、嬉しかった。”さまざまな頂き物に恐縮。地方の名産、珍しい菓子。伊那小
時代の写真や作文。それに、恩師の遺品の矢立、これには涙を抑えられなかった。(恩師、”小池先生の矢立”は作品集
「有賀忍 童心の風景(日貿出版社)にエッセーを掲載あり」)贈り物の中には変り種も。見たことも無いような特大”お化け
スイカ”!。青森の旧知の版画家が届けてくれた。美術館にスイカ!!これには、みなビックリ。でも気持ちが嬉しいなあ。
自分としてはわが作品に四方を囲まれ、”生活”したようなもので、わが”分身”からの語りかけを多く耳にした。
一筋の道を歩む勇気に、ちょこっと頷く自分、心から突き上げる責め言葉も。制作へのボルテージ下降への警鐘、叱咤。
描くしかないのは分かっている。描きたいものも。 描かねばならない心の”突き挙げ”が、今の自分には弱い。
休む間もなく、たまった仕事との格闘が始まる。格闘なんて言ってるから甘い!ごく自然体での表現だろうが……!
作家として嬉しいこともあった。記すようなことではないが……。忙しく、濃い夏が終った。
(Sep,2)
| 8月のアトリエだより |
■ウイーン美術史美術館蔵『静物画の秘密展』(国立新美術館)
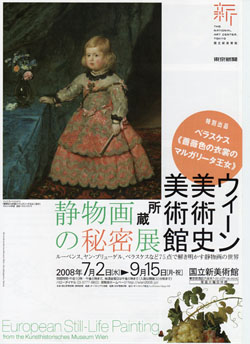 『静物画の秘密展』
『静物画の秘密展』 目玉は展覧会パンフにもあるディエゴ・べラスケスの「薔薇色の衣装のマルガリータ王女」と、ピーター・ブリューゲルの
息子、ヤン・ブリューゲルの「青い花瓶の花束」。両作品とも鑑賞者が群がっていた。
本物と見まごう「豹と禿鷹」「死んだ野鳥」
「狩猟用具」……精緻を極める描写はまさにトリックアート。動物が声をあげそう、猟銃が壁からはずせそう……質感の表現が
見事としか言いようがない。
ぼくは”子どもの遊び”を探した。「解体された雄牛」に、風船を膨らませて遊ぶ少年が描かれている。もう一人の少年は棒馬を
手にしている。「肉市場」では、風船を持っている少年がさらに大きく描かれている。風船は雄牛と豚の膀胱だ。ピーター・
ブリューゲルの「子供の遊技」の91種類の遊びにも、この風船遊びが描かれている。子ども達は肉やさんに牛や豚の膀胱をせびりに
行ったのだろう。ポピュラーな遊びだったことが伺える。顔より大きく膨らませて……この風船、ビニールと違ってさぞや丈夫だったことだろう。
(Aug.30)
■アンドレ・ポーシャンとマザー・モーゼス展 (損保ジャパン東郷青児美術館)
題して--- 「生きる喜び・素朴絵画の世界」 「自然を愛した画家からの心温まるメッセージ」---
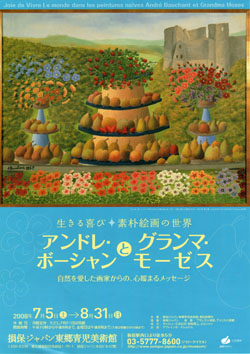
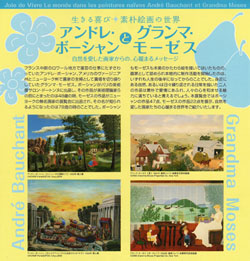 アンドレ・ポーシャンとグランマ・モーゼス展
アンドレ・ポーシャンとグランマ・モーゼス展
いつものことながら、展覧会は”最終日かギリギリ”だ。それも行かれればまだ良い。チケットを無駄にしてしまうことの
ほうが多い。「アンドレ・ポーシャンとグランマ・モーゼス展」も危ういところだった。美術館は新宿だ。渋谷から30分で会場
だというのに。億劫?よく見る絵だから?いや、今度今度と思っているうちに終わってしまうのだ。
手の怪我の功名か……、(困ったことに、ぼくはこのところ”サボりたい病”) 最終日、展覧会のハシゴと相成った。
アンドレ・ポーシャンもグランマ・モーゼスも今まで何度も見ている。そこで鑑賞というより、テーマを持って見て廻った。
アンドレ・ポーシャンの花、グランマ・モーゼスの井戸、メープルの樹液採りを画面で探す。(今回モーゼスは20点ほどで
樹液採りはごく小さく描かれているものだけだった)
ポーシャン『ニンフたちのダンス』では、妖精の絵に多く見られるスイカズラが、赤、白、桃色、三本木に巻きつくように描
かれていた。他に『ラヴァルダン城前のスイカズラ』も。 ポーシャンの人物描写は稚拙だけれど、神話的主題や情景を
描きたい気持ちが優っている。絵は、これでいいのだと思う。情景画に画家の心象を見る。モーゼスの描く四季の情感は
温かくいつ見てもほっとする。75歳で初めて筆を持ち、101歳でこの世を去るまで描き続けた、これだけでも驚異的、大
尊敬の画家だ。
もう一つの展覧会、ウイーン美術史美術館蔵「静物画の秘密展」六本木の国立新美術館については、この次に……。
(Aug.30)
■SEED AND GROW ファブリス・イベール たねを育てる展
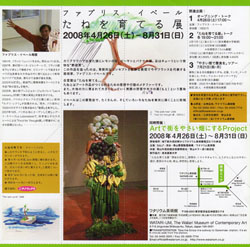 ワタリウム美術館 「種を育てる」展/ファブリス・イベール
ワタリウム美術館 「種を育てる」展/ファブリス・イベール 左指2本の怪我も順調に回復、今日抜糸。一週間右手だけの生活は何かと不便、仕事にならなかった。こんな時は
アイディアを練る……なんて、そう上手くはいかない。イライラしていても仕方ないので街に出る。
ファブリス・イベール「種を育てる」展をのぞいた。 ファブリス・イベールはフランスのアーティスト。1997年47回
ベニス・ビエンナーレでフランス館をテレビ局と見立てビエンナーレそのものを作品にするというアイディアで最年少で
金獅子賞を受賞した。環境保護をテーマの作品や舞台美術、モザイクなど、活動は多岐にわたる。
会場には野菜で出来たオブジェ、ドローイング、土を敷き詰めた小径、土が盛られた箱(ミミズがいる)、養蜂箱が置かれている。
[Artで街をやさい畑にするProjekt][たねとはアート作品がつくられるための思想や行動のメタファー]を合言葉に様々な
仕掛けがなされていた。例えば、青山の解体ビルの跡地の野菜畑化、大きな案山子を立てる等など。意識喚起だろうが、
コンセプト倒れの感も。美術館の野菜のオブジェ(カリフラワーの頭、レモンの目、サツマイモやアボガドの肩や胸バナナと
ピーマンの腰、)は面白かった(サツマイモからは芽が伸びていた)が、黒土の入った箱にミミズを入れたもの、ほんの
数メートルしかない、しかも行き止まりのススキの小径には興味が持てなかった。透明のパイプで外部と接続した養蜂箱は
”虐待”だと思った。蜜を集めてくる働き蜂が養蜂箱の出口でウロウロ、外にも出られず死んでいく。自然をコンクリートの
部屋に再現すること自体に無理がある。
この試みに一番欠けているのが、体感性、つまり触れ合い感じることの無さ、汗の滴りだ。ぼくはガラス越しではなく実際に蜂が
羽音をさせて舞う”自然”を思い浮かべていた。
ファブリス・イベールのコンテで描きなぐったような軽快なストロークのドローイングがよかった。
(Aug,29)
■二十四節気<処暑>、七十二候(四十候、四十一候、四十二候)
 |
今年の処暑は8月23日 ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
積乱雲に雷、そして昨日今日と雨。烈しかった暑い夏が早足で去っていく。長袖がいる肌寒さだ。駒ヶ根にはジャケットを
持って行こう。今日25日、駒ヶ根高原美術館へ。明日は「子ども学会」が開かれる。ぼくのテーマは「実践遊び学」だが、主題に
入る前に、二つの玩具の話をしようと思う。題して、「ブリューゲルのクルミの風車と菟足神社の風車」。ブリューゲルは”ふうしゃ”。
菟足神社のは”かざぐるま”いずれも実物を持参していく。
ピーター・ブリューゲルの(1560年作) 『子供の遊技』には91もの子どもの遊びが描かれているが、その中にあるのが、
胡桃の風車。海抜0メートルのフランドル地方独特の風車の玩具だ。胡桃の殻で作る何とも可愛らしい風車、素朴で温かい。
菟足の風車とも以前、このHPで紹介したから詳細は省くが、この二つを大事にトランクに納めいざ出発だ。雨よ、あがれ!
ちなみに、ピーター・ブリューゲルの次男、ヤン・ブリューゲルも画家。国立新美術館で開催中の「ウイーン美術史美術館所蔵
静物画の秘密展」にはオーク板に描かれた「青い花瓶の花束」が展示されている。ルーベンス、ベラスケスなどと並んで。
(Aug.25)
■指に怪我!嗚呼、油断。気のゆるみだ!
仕事でカッターナイフや彫刻刀や工具を毎日のように使用する。怪我は珍しくないが、今回は大ごとだ。左手の中指と薬指を
危うく落とすところだった。爪まで切れ血が止まらず救急車の世話になる羽目に!8針縫う。二本の指を固定して
包帯ぐるぐる巻き。不自由なことこの上ない。
25日は駒ヶ根だ。26日には大学の研修会がある。今、運転もままならないが切り傷の治りは早いぼくだ、何とかなるだろう。
それより、たるんだ気持ちを引き締めねば。
病院の帰り、目黒川に沿って歩く。花見の時季には賑わう桜並木も炎天下とあって行き交う人もない。川端の
ムラサキシキブの実が白から赤紫に変わろうとしていた。今日も炎暑だが、確実に秋は近づいてきている。
(Aug.20)
■嬉しい手紙……… ちびっ子からクレヨンまるへのラブレター!


小学一年生が画いたクレヨンまるへの手紙を担任の先生が届けてくれた。、心のこもった絵手紙を
美術館の片隅で「ありがとう。嬉しいねえ」感謝の気持ちいっぱいで、一枚一枚、宝物のように見た。30枚!
「返事を下さい」には出さねばなるまい。「クレヨンまるについての質問」には答えねばなるまい。幼心に映る
クレヨンまるは、作り出したぼくが思うより魅力的に見える。絵が生きている。たどたどしくもフレッシュな文章に
心が洗われる思いだ。横浜の小学校の30人の生徒、「ありがとう、みんな。クレヨンまるをこれからも応援してね!
クレヨンまるも頑張るからね。もっともっと活躍するからね。」
(Aug,16)
■感無量……恩師の遺品「矢立」が届く

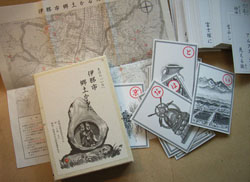
小学校時代の恩師、小池先生愛用の矢立が,わが掌中に。
岡谷のイルフ童画美術館(武井武雄美術館)での個展で先生とお会いしたのが50年ぶり。その直後、先生はあの世に
旅立たれた。先生から頂いた「愛語」と書かれた色紙をぼくはテレビ出演(レディース4)の折り、紹介した。絵描きの道を
歩むことになったのも先生のおかげ、恩師は小池先生ただ一人だとも……。
そして、この度の駒ヶ根美術館での展覧会、会場に小池先生のご遺族、昌子さんがお見えになって、矢立をお持ち下さったのだ。
この矢立、小学2年3年文組の担任だった小池先生が愛用されたもの。矢立から筆を取り出し”魔法のように”操る先生を、ぼくは
憧れの目で見ていた……確かな記憶があり、画集のエッセーにも書いた。ああ、先生のように絵が描けたらなあ……。その思いが
今のぼくを作ったのだ。
恩師のぬくもりが感じられる銅の矢立。触って触って、撫でて撫でて、開けてそうっと筆を取り出す……。泣けてくるから困るなあ。
ありがとう、小池先生。
(Aug,15)
■二十四節気<立秋>、七十二候(三十七候、三十八候、三十九候)
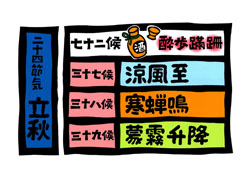 |
今年の立秋は8月7日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 7日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月12日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月17日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
暦の上では立秋なるも、連日真夏日。日本列島各地、35度を超える。もう、暑さにはうんざり。”一陣の涼風渡る”なんて書く日が
来るなんて思えない。
駒ヶ根美術館には日帰りで行っているが、やはり”高原”。湿度が低く過ごしやすい。多くの出会いがある。伊那小学校3年、
4年の級友と50年ぶりの再会。(これを機に初めての同窓会を開くという)恩師、小池先生のお嬢さんから遺品の「矢立」拝受。
(これはぼくが絵描きになった原点のようなもの。(画集にエピソードを掲載)。東京や、沼津、名古屋からも友来る。ぼくはいつも
美術館到着が昼頃になってしまい、会えずじまいの方々も多い。受付で名前を聞くたびに申し訳なく思う。また2度3度と見に来て
くださる熱心な方もおられ嬉しい。
次回は15日。美術館でお会いしましょう。
(Aug,8)
■2008相模女子大学オープンキャンパス「体験授業」
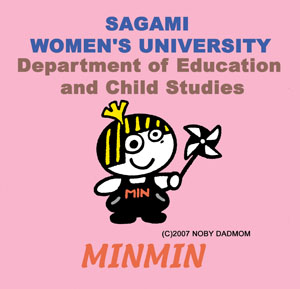

日曜日は大学のオープンキャンパス。子ども教育学科はぼくが担当。「実践遊び学」のメニューは
”一枚の紙で遊ぶ……ポップアップカード制作”。材料はA4サイズの紙。用具は鋏。他なにもなし。
ポップアップのメカニズムを3種類教えた。(下絵準備なし、画材なし、時間なしにより)「ミンミン」や
「こんなこいるかな」を切り抜き貼り付ける。紙が一枚あれば、いとも簡単にカードができ遊べる……
演習に集まった高校生はもう立派なペーパーエンジニアーだ。
「皆さん、家に帰ったら、自分の画いた絵を貼り付けてカードを作ってね。創作遊びはいつでもどこでも出来るんだよ。
そこにある材料で考える……創意工夫が大切。画くこと、作ること、生み出すことって、楽しいよ。
創作は自由な世界に遊ぶこと。表現って大事。生きるって、何かしら絶えず表現していくこと。皆、表現者なんだよ。
来春、又ここでお会いしましょう。そして心を開いて自由な表現の世界で遊びましょう」と結んだ。
参加者は美術図工室のキャパ(椅子の数36)を超えた。続々集まってくる。同伴の父兄は机からは
遠慮していただいたものの補助机も一杯。椅子を運び込む。教室の窓側と廊下側に父兄十数名が坐る。
高校生の数は五十名を超えたか。もう教室の限界、テキストも急遽追加プリント。大盛況で100分、一年生3名の
助けを借りながらなんとか終了。アシスタントの学生に感謝。学生は実践遊び学を半年受講した感想を受験生に
語った。これは参考になったことだろう。
来春、今日体験授業を受けた方々、桜吹雪のキャンパスで、また輝く瞳を見せてくれ。
(Aug,5)
| 7月のアトリエだより |
■「実践遊び学」最終講義 コリントゲーム………?


セメスター制は半年15回の授業。シラバスに沿って課題作品の試作、レジュメと慌しい日々だった。今日、水曜Aクラス、
Dクラスの最終講義。28日のB,C クラスが残っているから息は抜けないが、学生の制作物を個人ごとに”仕分け”しながら、
”答えのない自由な表現”の大切さを分かってくれただろうか、創作の楽しさに気づいてくれただろうか……制作物に本人の
顔をオーバーラップさせながら考えていた。
春、最初の授業で遊びに関するアンケートをおこなった。100の遊びの認知度、経験を問うものだった。時代と共に遊びは変わる。
データは、なるほどと思わせるものから、意外な数値まで様々。すっかり廃れた遊びや、全く知らない遊びが分かり興味深い
ものであった。
知らない、又は遊んだことが無いと答えたものの中に「コリントゲーム」があった。この低い数値は実は誤り。「コリントゲーム」の
名称を知らないだけであった。学生に写真の玩具を教室に持ち込み見せたところ、殆どの学生が遊びを記憶していた。
30年近くなるだろうか。このコリントゲームを息子と一緒に作ったのは。木を切り穴をあけ組み立てはぼく。二人の子どもが釘を
打ち、数字を書き込んだ。今夏の個展で空になった作品庫の奥から出てきた。埃だらけで裏板のベニアは波打ち剥がれ
かかっている。朽ち果てる寸前だが、子どもと遊んだ記憶は鮮明。子どものはしゃぎ声さえも耳に残っているような……。
楽しい創作遊びは幸せな記憶となるのだね。ぼくは学生にこの埃だらけの粗末な玩具を自慢して見せた。
因みに「コリントゲーム」のコリンは”小林”をローマ字読みしたもの。この玩具、輸入されたのが昭和初期。輸入したのが
「小林脳行」。「コリントゲーム」と名付けて販売した。西洋ではバガテル(Bgatell),フォーチュナ(Fortuna)
(Jul.24)
■駒ヶ根高原美術館 有賀忍展始まる
中央アルプス、南アルプスを望む駒ヶ根。深い緑の山々に囲まれた市街からは山の頂の残雪が見える。
中央高速道駒ヶ根インターから2~3分、美術館は霊犬、早太郎伝説の名刹、光前寺(天台宗 別格本山)と
寄り添うように建つ。
展示作品は板絵約100点、版画、絵本原画約30点。池田満寿夫、草間弥生、ゴヤ、藤原新也の各展示部屋を
経て続く、新館VITA AMORに並べられている。(写真左側の建物)
(Jul.22)


■二十四節気<大暑>、七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
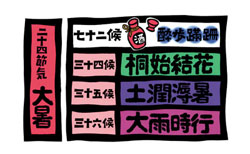 |
今年の大暑は7月22日 (立秋は8月7日) ・三十四候 (7月22日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月 2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
炎天下、ノウゼンカズラが暑さをむしろ望むが如く咲き乱れている。鮮やかな橙色の花が風に揺れる。
熱い風もごもっとも!今日22日は大暑。一年で一番暑いとされる夏最中なるも、次の節気は最早、立秋だ。
立秋前日までが土用。今年の土用の丑の日は24日。土用休みは取れそうもない。せめて鰻の蒲焼でも食すとするか。
(Jul.22)
■連日真夏日、如何がお暮らしですか。暑中お見舞い申し上げます。夏負けされませぬように
 |
平素は御無音に打ち過ぎ失礼の至りに奉存候。 酷暑凌ぎ難く候所皆様には御障りもあらせられず候や。 夏の個展も愈々19日に開催の運びと相成り申候。 遠隔地での開催にて、態々御越し願ふのも却って恐縮 至極と感じ居り候。繁忙なる御方、若しご来臨下さらば恭悦、 まことに光栄に奉存候。 <有賀の駒ヶ根美術館滞在予定日 7/19(土) 25(金) 8/5(火) 15(金) 25(月) 26(大学研修会) 今夏の暑気、別して烈しく候へば皆々様、殊更に御自 愛専一の程祈候。 敬白 |
(Jul.17)
■クレヨンまるの紙芝居制作
月間読み聞かせお話雑誌『おひさま』(小学館)10月号にははさみ込み付録としてミニサイズの紙芝居が付く。
クレヨンまる登場!本誌では「秋が来た」と題したクレヨンまるの栗拾い(9月号よりのつづき)。紙芝居では切り口を変えて
おおどろぼうのオオカミ、ワルズーを主役とした。ワルズーには未だ食べたことのないものがある。どうしても食べてみたいと、
育ての親、ミイラばあやに頼む。が、そんなもの買うお金ありませんと断られてしまう。ごく当たり前にみんな食べているものだけど、
貧しいミイラばあやには100円玉一つだって貴重。ワルズーは果たして”ハ○○○○ー”を食べられたでしょうか?乞うご期待!
(Jul.10)

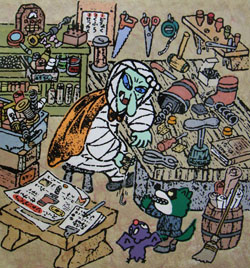
■二十四節気<小暑>、七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
各大学、オープンキャンパス真っ盛り
今大学ではどこでもオープンキャンパスが盛んだ。AO入試の受け入れ準備、模擬授業、個人面談(進路相談)と、
至れり尽くせり。6月は「授業体験」月間。わが実践遊び学がその対象になり、茅ヶ崎や横浜の高校から生徒が教室に
やってきた。授業は”演習”中心だから、ただ聴講していても面白くない。よって、美術図工室に入る者すべてに課題を課し
実際にお面や木製キュービックパズルを制作してもらうことにした。生徒たちは初めのうちは戸惑っていたが、すぐ制作に
没頭。楽しんでいたようだった。”珍客”に学生はもう先輩としてやさしく振舞っていた。大学志望者の情報収集にこれまで
するのかとも思うが、多くの大学が定員割れ、少子化で仕方ないことなのかもしれない。
昔はもちろんオープンキャンパス、模擬授業、体験授業、AO入試なんてなかった。現代はやる気のある者にとっては
大学選択をよりリアルな体験を通して出来るわけで、過保護ではあるが恵まれている。
5日は東京は30度を越えた。真夏日が続きそう。暦では7日は小暑。2週間後には大暑。そして早や立秋だ。
(Jul.6)
 |
今年の小暑は7月7日 (大暑は7月22日) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月17日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
■板絵作品整理額の点検。カビに溜息!
駒ヶ根高原美術館個展まで3週間。準備を焦るも生活は殆ど大学中心で儘ならず。梅雨の晴れ間をチャンスとばかり、
鳩山のアトリエを開け作品の点検。案の定カビが凄い。いつもカビには悩まされてきたが、ため息をつきたくなる様な
”惨状”。曇り空、薄日のもとで、虫干しする。板絵を持ち出し外に並べていると、「メヘへへー」ヤギの声。野原に繋がれた
白黒ぶちのヤギが笑ってる。「何をそう、あくせく働くの……」やさしい目だ。「メヘへへー」また鳴いた。カビに
うんざり、創作から離れている後ろめたさ、仕事の焦り……。ぼくも野原で日がな一日、舞い来るチョウチョウとお喋りしながら
のんびりしていたい。「メヘへへー」とも鳴いてみたい。静かで時間が緩やかに流れる……「メヘへへー」は何とも、幸せな響き。
(Jul.1)
| 6月のアトリエだより |
■演習「想像して遊ぶ」……… 想像=創造 ………「創作お面」と「不思議眼鏡」からのストーリー展開


造形を楽しむだけでなく、創造 = 想像 の実践。先ず自由にお面や眼鏡を制作。次いでそれらが持つ特性(魔力があれば
その力を、使い方を)を記述。お面や眼鏡にまつわるエピソードを創作する。入手は?何時何処で?言い伝えは?…………。
はじめ、とまどっていた学生もストーリーを考え書き進むうちに、すっかり夢中になり、教室一切のおしゃべりが消えた。
お話の”でっちあげ”だったのが、仮面や魔法の(秘密の)眼鏡を着用し、リアルな体験をしているがごとく感じていたようだった。
これぞ遊び!無我夢中、時間を忘れたから本物。
学生の眼鏡のタイトル(とりどりの造形、特性、エピソードも楽しいが)を幾つかあげてみる。
・泣き虫メガネ ・踊るメガネ ・思い出メガネ ・濁りガラスの透かしメガネ ・猫ネコ眼鏡 ・心メガネ ・お先真っ白メガネ
・感謝めがね ・スイートポップめがね ……。
(”メガネ、眼鏡、めがね”は学生表記のまま)ネーミングもユニーク。見てみたい?掛けてみたい?実に魅力的な作品だ。
(Jun.26)
■二十四節気<夏至>、七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
先日幼稚部の先生十数名との懇談会があった。大学の先生の挨拶(自己紹介)が自分の職歴や専門、研究テーマを
語る紋切り型だったのに対し、保育士の話は保育現場の生の声であり、熱い志とともにしっかり伝わりおもしろかった。
「ベビーシッターの仕事をして、気がついた。園児が持ち帰る製作物の家庭での扱い方が大事。作ったときの話を聞いたり、
壁に貼ったり、要は子どもを尊敬すること」「園で子どもと遊ぶとき、相手が小さいからと始めから手を抜くことはしない。ゲーム
でも相撲でも(もちろん安全には配慮)一生懸命取り組む」「オーストラリアの幼稚園で実習した折、日本では”危ないからよそう”
”そんなことしちゃダメ”となることが”試してごらん””やってみよう”だった。」等、若い先生方はみな目を輝かせて話した。
ベースは愛情。本当に子どもが好きな方々の体験談は、~論にはない面白さもあり、ぼくはこの話、そっくり学生に聞かせたいと
思った。保育士をめざす学生が、その仕事のやりがい、楽しさ、誇りを聞き、選んだ道を初志忘れることなく歩んでほしいから。
そして、辛い話、厳しい話に、(子どもは可愛いからスキ的甘さ)自らの取り組む姿勢を見つめてほしいから。
二日ほど前、沖縄は梅雨が明け、東北地方が入梅した。東京は雨。曇り。梅雨真っ只中。ザクロの花がはじける様に
開いていく。朱色が雨に濡れた緑の間でくっきり。花が落ちた後、実はちょっとずつ膨らんでいく。
駅に向かう坂道、歩を止め見入る。ザクロの木が楽しみをくれる。
(Jun.21)
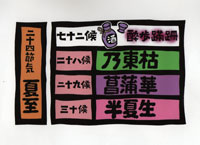 |
今年の夏至は6月21日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月26日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月1日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
●ミンミンゼミナール NO.4,5,6
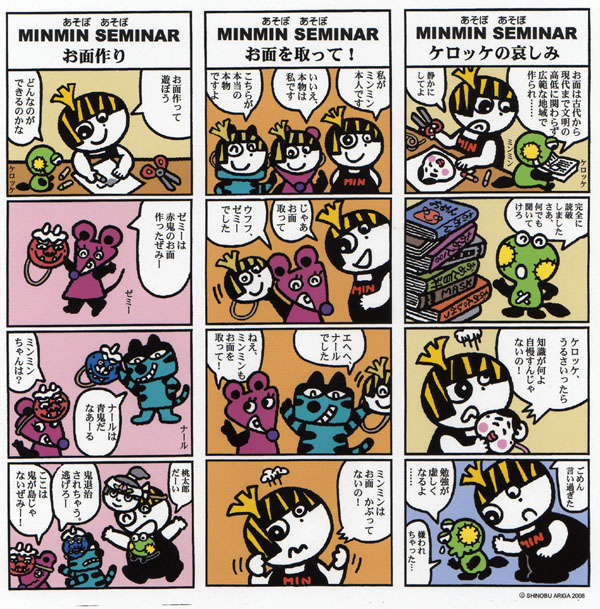
(Jun.14)
■相模女子大学子ども教育学科キャラクター「ミンミン」のミンミンゼミナール連載開始!
大学の『実践遊び学』レジュメ(すべてオリジナル)の端に漫画ミンミンを時折載せています。その中から
幾つかを紹介してまいります。『実践遊び学』は子どもの遊びを真剣に徹底的に考える科目ですが、最終的
狙いは”創造的造形遊び”の大切さの理解と実践です。いや、創造的造形遊びが出来る柔らかな感性の涵養を
めざします。「答えのない世界で遊べる」「創意工夫できる」ようになってほしいのです。
ミンミンゼミナールのメンバーは、丸っこい顔のおしゃまな女の子ミンミン、ネズミのゼミー、ドラネコのナール。
それに、カエル未満のオタマジャクシのケロッケの4人。しばらくはケロッケにご注目!生まれたてなのに博学。
ユニークな存在がストーリーを引っ張ります。
●ミンミンゼミナール一堂「はじめまして。どうぞ、よろしく。あそんで、あそんで、あそびまくるからね!」
●ミンミンゼミナール NO.1,2,3
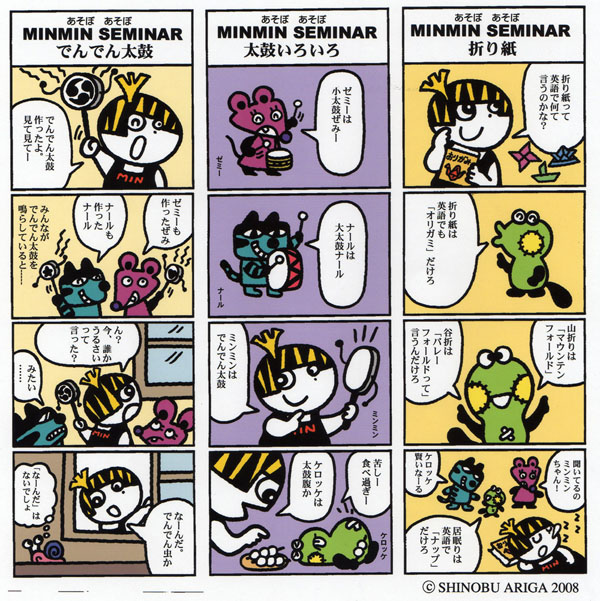
(Jun.13)
■二十四節気<芒種>、七十二候(二十五候、二十六候、二十七候)
例年より早い梅雨入りで、このところ雨続き。気温が低く、鬱っとうしくはないが肌寒い。渋谷の仕事場では用済みと片付けた
ヒーターを持ち出した。机の下の”膝暖板”にもスイッチを入れた。ぼくは暑さには強いが寒いのは苦手だ。大学の研究室も
冷え込み、トレーナーを重ね着している。
4月初めに始めた「実践遊び学」も、光と遊ぶ(万華鏡製作)、音と遊ぶ(でんでん太鼓製作)、紙で遊ぶ(紋型切り紙、自由
切り抜き)、風と遊ぶ(風車製作)、廻して遊ぶ(カラクリ玩具製作)、スタンプして遊ぶ(ゴム印製作、単位形デザイン構成)。
そして、転がして遊ぶ(クルクル輪製作)まできた。一コマ90分の授業時間はレジュメ解説、製作で一杯。”遊ぶ”余裕がないのが
残念だが、スタンプを押印したシールの交換会は盛り上がった。「交換してください」「一枚ください」「どうぞ」「ありがとう」の声が
教室中に響き渡った。声をかける、礼を言う……当たり前のことだが、コミニュケーションの大切さを、学生はスタンプ創作の楽しさ
と共に学んでいる。
100枚のスタンプ押印シールをボードに貼り付け掲示した。ぼくも学生と同じように子ども教育学科のキャラクター、”ミンミン”と
”ケロッケ”のスタンプを製作。こっそりその中に紛れ込ませた。
(Jun,5)
 |
今年の芒種は6月5日 (夏至は6月 21 日) ・二十五候 (6月 5日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月10日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
■有賀博スケッチ展開催 (ギャラリー・オーク) 6月6日(金)~11日(水)
- ペンで描く花と旅の風景 -
ギャラリー・オーク 三鷹市上連雀3-12-7 JR中央線三鷹駅南口 徒歩5分 さく通り Tel0422-44-9591
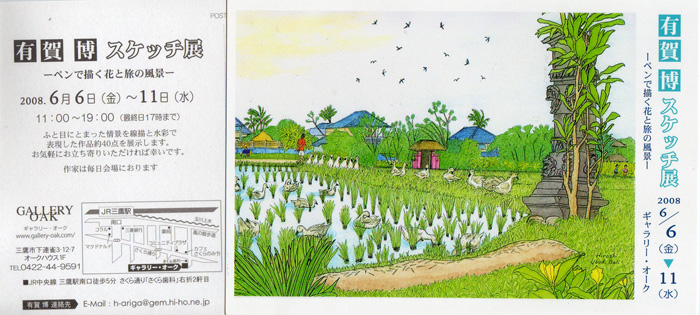
兄、有賀博の個展案内です。絵は人そのもの。誠実、実直.まっすぐな人柄通りのスケッチです。見えるものを
ありのまま素直に水彩で描く兄は、”現場主義”。下書きを全くせずに、細ペンでいきなり描き出し、その場で彩色します。
その”技”は一寸まねできません。画風はとても清らか、見る者を爽やかな心持にさせます。足を運んでくだされば幸いです。
(Jun,3)
| 5月のアトリエだより |
■郷土玩具のカラクリを活かして「回転色円盤」をつくる






■二十四節気<小満>、七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
鳩山は今、田植えの真っ盛り。小雨の中に人影が。殆ど機械植えのご時勢だが、それでも田んぼの角や
畦の脇は手植えだ。静寂、音の無い世界。再び目をやれば人影の位置が変わり、時間が確かに経過したのが分かる。
庭はスイカズラの甘い香りが漂い、噴出すように咲いたリラの花の回りにミツバチが群れ飛んでいる。
東京は真夏日だった。鳩山も暑い。熊谷では最高気温を記録したという。夏がすぐそこに来ている。
 |
今年の小満は5月21日 (芒種は6月5日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
■見事! 経木の風車の美しさ………菟足(うたり)神社の面能風車 (愛知県・宝飯郡小坂井町)


この色彩鮮やかな風車は、菟足(ウタり)神社で4月に行われる風祭で鐘き面と、お多福面とともに
売られる郷土玩具。風祭は”風鎮め祭り”の意味。お多福は招福を、鐘きは除災を祈願。経木の風車は
無病息災と開運豊作を願って作られた。
6枚の羽根は経木で作られており、米俵の形をしている。羽根の反対側には小石の入った紙筒が
付いていて廻るとカラコロ軽快な音がする。経木の羽根は薄く軽いのでほんの少しの風でも敏感に反応、
とてもよく廻る。
風祭には行かれない。見てみたい。学生にも「風と遊ぶ……風車」講義の折に見せたい。
どうしても手に入れたい。ぼくは神社の宮司さんに手紙を書いた。「大学の子ども学科の学生に是非とも
見せたい……」と。宮司さんのご配慮により、見事な経木の風車を入手することができた。
「日本郷土玩具辞典」(1965 岩崎美術社)では、「珍しい経木の風車で、全国風車中でも、
最も素晴らしいもので、玩具としての面白さを十分にあらわしている」とある。
多くの郷土玩具が消えていった。姿かたちの美しい、よく廻る、心地よい音がするユニークな経木製の
菟足の風車が、廃れることなくいつまでも作り続けられることを願う。
(May.20)
■孫に宛てた1200通の手紙『Grandfather’s Letters展』を見る(玉川高島屋・アレーナホール)
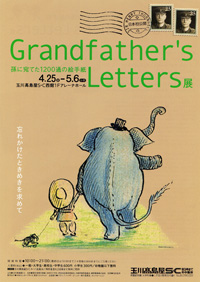
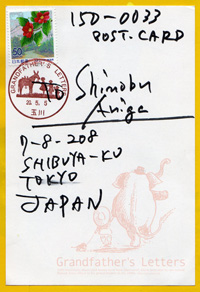
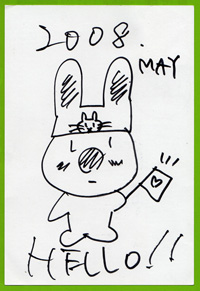
先日面白い展覧会を見た。退役軍人ヘンリー卿が4人の孫に20年間送り続けた絵手紙のコレクション。
直筆絵手紙、絵封筒100通以上の展示に圧倒された。この”絵手紙群”は25年前ヘンリー卿の曾孫が無き母の、
衣装棚から偶然発見した。絵本にもなりBBC国営放送が取り上げ英王室の愛蔵書として認定されたという。
その量も凄いが、一点一点、心をこめて描かれた絵がいい。カカ(口ひげの長身のおじさん = ヘンリー卿)と
孫たちや動物が楽しそうにペンと水彩絵の具やクレヨンで丹念に描かれている。ストーリー仕立てもあり、
いずれも愛情にみちあふれている。こんな絵手紙が成長に合わせて届けられたなんて、4人の孫たち、
この上ない幸せな子ども時代だったろう。
ぼくは、わが身を思い唇を噛んだ。自分の子どもに、この百分の一でも時間を費やしただろうか……。
ヘンリー卿の使った絵手紙を書くための道具を入れるボックス(スケッチブックや封筒が入っている)や30色の
絵の具(小さな皿絵の具)、ちびた筆を見つめているうちに、目の奥が熱くなるのを覚えた。愛情の深さだ!
■尊敬するムナーリの「芸術家とデザイナー」(みすず書房)を読む。
ブルーノ・ムナーリが美術批評家の様々な文体を模して書いた「美術批評」が面白い。
”文学的批評” ”叙情的批評” ”黄昏派の批評” ”疑問系の批評” ”博識過ぎる批評” ”ニセの批評”など、
いかに大衆がだまされていくか。”さもありなん”と思わせる。



(May.9)
ブルーノムナーリ「芸術家とデザイナー」
(Artista e designer, Laterza,1971)
注文しておいたブルーノムナーリの「芸術家とデザイナー」が研究室に届いた。授業を終え汗びっしょり、
疲れてはいたが、待ちに待った本だ、夢中になって読んだ。序文の前にある覚え書きからしておもしろい。
「写真類は、普通、技術的な理由から、別にまとめられる。なぜなら、文中に数字を見つけるたびに、対応
する注を探さねばならず、しかもそれは往々にして同じページにないからである。」「私はこの本で、一冊の
本があたかも連続した一枚の紙であるように、そして、どのページもすぐ下へ続いていくようにと、新しい
レイアウトの企画設計を試みた。」ブルーノムナーリは注釈、引用、図版などを連続的に配した。そうする
ことで、読者は“素早く読んだり、じっくり読んだりと、その読み方を選ぶことができよう”なるほど!
ぼくはまずは“サッと見“してみた。が、芸術家とデザイナーの真正面からの論述は、とても読み飛ばす
ことなどできない。「ファンタジアと創造力『美しさについて』「ニセモノの絵画」「本物の量産品
(マルチプル)」……。うなづいて読み進むうち、ぼくは思わず笑ってしまった。「美術批評とその利用法」で。
ムナーリはニセの美術批評に触れ警鐘を鳴らす代わりに、ムナーリ自らニセの批評をカテゴリーを定めてサンプルを
“再構築(本文とおり)しているのだ。《文学的批評》《叙情的批評》《黄昏派の批評》《疑問形の批評》《博識
すぎる批評》《ニセの批評》日常、世のあふれる批評の数々も上記のいずれかに該当している気がしてくるから
不思議だ。このような文章で大衆はニセの作品を公平に判断できなくなる。ムナーリの言葉は面白く、深い。
「芸術家とデザイナー」、しばらく座右に置いておこう。ブルーノムナーリ(ミラノ生まれ造形作家、絵本作家、
彫刻家、デザイナー、美術教育家。1998年91歳で死去)ぼくはムナーリの絵本『プレゼント』を4年前から、
大学の秋学期の授業で使っている。絵本の面白さ、魅力を紹介するのに最適。ぼくの大好きな絵本でもある。
■二十四節気<立夏>、七十二候(十九候、二十候、二十一候)
今日5日は立夏。暦では夏だ。昨日は鳩山へ。窓を全部開け緑の風の通り路をつくる。絵の具や彫り屑の散乱する
アトリエを掃除。片付けも楽しい。何時以来だろう、”制作場”に入るのは。制作欲求を封じ込めているが、もう限界点だった。
今晩中には東京に戻らねばならず、それでもギリギリまで、アトリエの住人でいた。板絵を描きたくも時間が無い。そこで、
「菟足神社の風車」をモチーフに木版を彫り、墨で数枚刷り上げた。試し刷りだが、久しぶりの制作に心が躍った。やはり、
ぼくは表現しているのが一番ぼくらしいと、当たり前の事を思っていた。
雨が上がった庭では薄黄色の木香バラがサルスベリの枝に絡みつき、芳しいアーチをなしている。球状のオオデマリが
はちきれそうに膨らんでいる。卯の花(ウツギ)の白と共に目に眩しいくらい。 鳩山の初夏、立ち去りがたし。
(May.5)
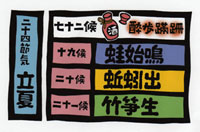 |
今年の立夏は5月5日 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 5日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月10日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月15日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
■でんでん太鼓 そのⅢ (郷土玩具と版画)


竹笛を吹くと風車が回り、一緒に桃太郎も回転。手の豆が背面の太鼓に当たりポンポン音を出す。
10センチにも満たない可愛らしい仕掛け郷土玩具。レジュメ、テキストには木版画を載せた。
でんでん太鼓は日本各地で作られ、子どもたちに親しまれてきた。安産、子育て、開運、商売繁盛、
五穀豊穣を祈願するものが多い。豆太鼓の図柄も鳥居、大黒、三つ巴、狸などめでたいものが多い。
一例 甚目寺ガラガラ (愛知県 甚目寺) ポンポコ狸(香川県 高松) ポンパチ(鹿児島県 隼人)
豆太鼓(栃木県 宇都宮) 甘木パタパタ(福岡県 甘木)など。
(May.1)
■でんでん太鼓製作 そのⅡ



| 4月のアトリエだより |
■懐かしい音……「でんでん太鼓」製作 そのⅠ
太鼓の胴は上段の「ミンミン&ケロッケ」は直径15センチと大きいが、
ガムテープやセロファンテープの巻き芯を利用する。重ねて棒に通し
二連太鼓、三連太鼓としても楽しい。
デジタル音とは違う温かな、懐かしい音が響く。心が休まる音だ。
棒を動かす加減で早く、ゆっくり、大きく、小さく、音が生ずる。
疲れたとき、落ち込んだとき、でんでん太鼓をそっと手にとってみたら……,
素朴で温かく懐かしい音が傷んだ心を和ませてくれるだろう。
(Apr.26)





■子ども教育学科授業開始

授業開始。光と遊ぶ、風と遊ぶ、音と遊ぶ………、連日課題作の試作、レジュメの用意と息つく暇なし。
大学へは荷物の運搬もあって渋谷の仕事場から車で行くことが多くなった。家には帰れない。帰路家に立ち寄り
夕飯を食べ、再び渋谷へ。4月に入ってからは自宅で休むことがますます少なくなった。
4クラス同じテーマで授業を行うこともとまどいの一つ。毎回新たな気持ちで立ち向かうのだが、瞬間瞬間
完全燃焼型のぼくには、これ意外とキツイこと。創作に情熱のすべてをぶち込んだ生活から一転。このままでは
いけないが、今は学生に想像=創造、そして創作の楽しさを体験させることに必死。学生がマニュアル的思考から、
呪縛を解き自由な心で制作できるよう、何としても導くつもりだ。
板絵を制作する鳩山のアトリエは暫く行っていない。桜が終わり遅れて咲き出す鳩山の野原に立つ老山桜、
その薄墨桃色も見られず。「鳩山の春」は今年、お預けだ。
茶の摘み取りがはじまったとのニュース。鳩山のぼくの小さな”茶畑”も淡い黄緑の新芽を風に揺らしていることだろう。
嗚呼、鳩山に行きたい。昨年は新茶葉のおひたしと天ぷらを食べた。食味が蘇る。それよりなにより絵を描きたい。
鳩山行きを胸に、今は今ある目の前の仕事に全力を注ごう。迷わず。
(Apr.25)
| ■二十四節気<穀雨>、七十二候(十六候、十七候、十八候) |
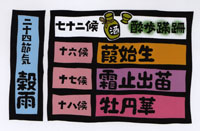 |
今年の穀雨は4月20日 (立夏は5月6日) ・十六候 (4月20日) ・あし はじめて しょうず 葦が生え出す ・十七候 (4月25日) ・しも やみ なえ しょうず 霜が止んで稲の苗が生長する ・十八候 (4月30日) ・ぼたん はな さく ボタンの花が咲く |
土曜日の大学キャンパス。学生の姿はまばら。研究室の在室ランプも点灯は少ない。美術図工室で一人プラズマパネルの
操作の練習をする。”やだもん”や”ぶるる”をマーキングペンを使って描いてみる。楽しい。これは便利だ。大モニターに
インターネットの画面を写し、よくテレビの気象予報でやっているような描きこみもできる。まあ、ぼくは絵本やイラストを
映し出すのに使う程度だろうが。
準備室にはレーザープリンターが設置された。これは有難いが今のところマックが接続できず、”カラーレジュメ”は
お預けとなった。学生にキャラクターが入った楽しいレジュメを配りたい。そして、自分でオリジナルの教科書を作って
もらおうと思う。
昼間、晴れていたのに夕方から雨。研究室も冷え込んできたので退散する。明日は二十四節季の穀雨だ。
(Apr.19)
■杉の丸太でスツールを作る。木工小屋で檜棒カットも。


昨日と一昨日は大学の美術図工室で終日過ごした。学生に渡す画材、用具の袋詰作業。アシスタントと二人でも
100袋セットは大変。午後はアシスタントも帰りぼく一人。見かねて学科長が手伝いに来てくださった。
ヘトヘト、フラフラで横殴りの雨の中を帰る。
数時間も休めず、鳩山へ。木工部屋で、風車を取り付ける檜の角棒を学生数×2(一人2本)、200本以上をカットする。
工作は好きだから苦にはならない。この作業、昨日と同じ単純作業でも神経を使うから、緊張するけれど、すべて切り
終えたあとは爽快感があった。
まだ外は明るい。研究室に持ち込む杉の丸太をきれいにする。皮をはぎ先日作ったテーブル板に合うよう
素朴な風合いを消さないよう薄めたステイン塗料を塗る。本当はこんな丸太がゴロゴロしている環境、教室で学生たちと
学びあいたいと思う。せめて研究室に木の香りを……。
(Apr.9)
■二十四節気<清明>、七十二候(十三候.十四候.十五候)
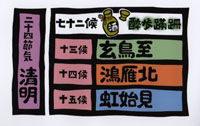 |
今年の清明は4月4日 (穀雨は4月 20日) ・十三候 (4月4日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月9日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
■大学「子ども教育学科」有賀忍研究室への引越しを始める
大学には学生が研究室を訪れる「オフィスアワー」が設けられている。スチールデスクにない温かさがほしくて、
9cm×180cmの木材12本使い、大きなテーブル板を作る。ステイン塗料をペイントしながら、脳裏にははや
絵本談義をしている自分がいる。椅子は杉かケヤキの丸太がいいなあ。新校舎のハイテク環境が無機的なだけに、
木の香りが漂う研究室にしたいと思う。
(Apr,6)
 ・トート・ガーボル先生のリクエスト、
|
  ・「ビー玉コロコロンA・B・C」構成例 ・「ビー玉コロコロンC」 『創造的遊び』を基本テーマの遊び玩具作り ●創造的遊びの条件 遊び方が限定されない。作り手により異なった設定、仕組みができる。 ゲーム、プレイの難易度を調整できる。シンプルな構造で飽きさせない。 写真の「ビー玉コロコロン」は正方形のベニア板(22センチ)2枚。 角棒4本(20.6センチ)使用。小木片15枚以内を学生に自由に構成 させる。100人の学生に100種類のレイアウトを求める。遊び方を 考えさす。またプレイの難易度は学生の主観で判定させる。 |
■板絵 「春風ブランコ」 と 「クルミのヨットとブリューゲルの風車」


●「春風ブランコ」(53㎝×53㎝)2005 (画像左)
鳩山の原(ぼくはフキノトウ畑と呼んでいる)、今年はフキノトウが芽を出すのが遅かった。
ボツボツッと出始めたときは紫茶褐色の小さな塊だった。数は増えていくのだがなかなか大きくならず、
このまま枯れてしまうのかと思っていた。それがびっくり!又がっかり。先週久しぶりに鳩山に行けば、
フキは大きく育ち、”しゅうとめ”(フキノトウが花を咲かせたものを言う)になってしまっていた。
これを味噌汁に入れて食べる好みの人もいるが、僕は何と言っても身のしまったフキノトウに限る。
(フキ味噌、てんぷら、醤油いため、酢の物など)膨らむ前は苦みも強いが春の香り、
春の味覚……大好物の酒肴である。
今年は(少しは口にしたが)春を待ちわびていたのに迎える心の余裕がなかったという訳だ。
仕事で忙殺された天罰だろう。(板絵「春風ブランコ」は2005年の作品)
●「クルミのヨットとブリューゲルの風車」(53㎝×53㎝)2008 (画像右)
先日現代童画会春期展出品作を鳩山のアトリエに取りに行った。作品を仕上げておいて良かった。
このところ、大学の仕事で「創作」をご無沙汰している。ぼくにとっては死活問題だ。
明日又鳩山に行くが、これも「子ども教育学科」の教具、教材を製作するためだ。
創作から離れた日が続くと精神状態も良好ではなくなる。絵が描きたい……が、しばらくはだめだろう。
7日からは美術準備室の整理。助手とも初めて会う。研究室への荷物の搬入も終えておらず、
授業も間近で気ばかり焦る。
鳩山では花咲き、鳥歌う春を満喫することもなくアトリエにこもることになるだろう。
ここは我慢、我慢。絵は気持ち爆裂の時、描けばいい。でもなあ……創作創造欲求ふつふつ……。
我慢、我慢のときだ。
(Apr,4)
■ゆとりのない日々……、「創造」への渇望
パソコンに向かえず「アトリエだより」の更新もできなかった。今年、未だ休みなし。
鳩山に行っても日帰り。アトリエにこもって教材、教具作りで春の訪れを確かめる楽しみもなく、
”過労死”が頭をよぎる。頑丈な体を親に感謝するも「いい加減にせな。お前は、体を使い壊すわ」……
生前の母の言葉を思い出す。
レジュメ、教材プリントを作っても、”これでもかこれでもか”の域まで行ってしまい、反省。
学生が学ぶ領域をいつの間にか超えてしまうのも、”熱中症”、職人性、作家性、の現れに違いなく、
創作行為を渇望しているのであろう。飢えを満たされる日は……?
(Apr,1)
| 3月のアトリエだより |
■多事多忙 。仕事の合間の息抜きに風車を作る


・タービン型 ロート型(紙皿) ・水車型(紙皿、紙コップ使用)
桜の便りがちらほら。空の色が変わってきた。朝夕は未だ肌寒いが陽気は春だ。光に強さが感じられ、
吹く風も花の下を通ってやってくるのか微香を含んでいる。
このところ家にも帰れず鳩山のアトリエにも行かれず渋谷で過ごしているが、部屋に閉じこもり仕事に明け
暮れるゆとりのない生活に疲れも蓄積。
創作、創造行為以外に興味も無く世情にも疎いぼくだけど、”多忙”が肝心の創作行為に寄るものでないことに
フラストレーションはたまる一方だ。
暗室からでる大量のネガフィルム(A3より大きく、レントゲンのフィルムみたいなもの)が、風車製作に最適と分かり
200枚ほどをカットする。教材の準備も大変だ。粘着色紙で装飾したり、ガッシュで彩色。よく廻る。廻り続ける。
手に持って歩くだけでクルクル廻る。ちょっとやそっとでは壊れない頑丈な構造に設計した。
上の写真は紙コップと紙皿を使って作った”個人用”。普通、風車は正面から風を受けて廻るが、これらはサイドから
風を受けて初めて廻る。タービン。水車そのものだ。造形的に美しいと思いジェッソやガッシュを重ね塗りし作品とした。
大学のキャンパスで並べて廻して遊んだ後は研究室の天井に吊るすつもりだ。
ぼくは、忙しいと決まって何か作りたくなるから困る。
(Mar,24)
■二十四節気<春分> 七十二候(十候.十一候.十二候)
備品や画材の発注状況確認打ち合わせに大学へ。大学の新校舎「マーガレット本館」は竣工秒読みだ。植木屋さんが
大勢で植栽に大わらわ。学生の姿が見えないキャンパスを春のまばゆい光が包んでいた。風も無く穏やか。一人何とも
贅沢な時間、惜しむように歩を止めては天を見上げる。心の安らぎ……。このところ多事多忙で、感じ得なかった幸せな
思いだ。
20日にまた訪れる。いよいよ教室、準備室、研究室に足を踏み入れることになる。
長閑な春の陽気に浮かれる気分はなく決意新た、四月はもうすぐそこだ。
(Mar.18)
 |
今年の春分は3月20日 (清明は4月4日) ・十候 (3月20日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月25日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月30日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
■「ビー玉落とし」用ガイドスケール作製


ペットボトル工作を考案。ペットボトルに穴を開ける。切る。接着する……。様々な玩具が出来ていく。
その中から一点。今回はビー玉を使った造形遊具「ビー玉落とし」A。
ペットボトルの両サイドにスリットを入れ、ベニア板(イラストボードでも)を差し込む。ベニア板は6枚。異なった
位置にビー玉が通るくらいの穴を開けておく。
ビー玉は7個。コロ、コロンコロンと落下していくが、思うほど簡単ではなく、そのじれったさが楽しい。
写真左はペットボトルに均等にスリットを入れるためのガイド。右は今回製作した玩具とは異なる「ビー玉落とし」の
応用作品B。中に見える黄色い円盤はテニスボール缶のキャップ。これはビニールで柔らかく、ドリルでビー玉の
通る穴を開けるのに手こずった。その点ベニア板は穴あけが簡単、きれいに出来上がる。(写真は後日この欄で)
遊び方はABとも、7個のビー玉をペットボトルの底まで落下させ、ひっくり返して再び落としキャップからとりだす。
Aは転がす。Bは振り回し落とす感じ。
いくつもペットボトルを繋いだりスリットに段差をつけたり、イラストボードをたるませたり、難度を上げることも出来る。
手の振り、微妙なバランス、集中力……、コロ、コロン……落ちて行く音が耳を刺激する。
面白いだけではない。この玩具、心身に色んな効能あり。楽しめるからリハビリにも最適だ。
(MAR.10)
■お面を作る



鳩山のアトリエでお面を製作。厚ボール紙を切り、モールディグ。ジェッソを塗り、青銅液、腐食剤をかけ
古代色仕上げ。インカの秘宝か……古代の仮面だ。Aは紙素材のままのもの。Bはそれに彩色したもの。
(顎の部分は可動式)
Cは先日、川越の小さな玩具屋で見つけた「こんなこいるかな」のお面。ドラエモンやアンパンマンに混じって
売られていた。古いものだからと値引き交渉したが、お店のおじいさんは定価500円を一歩も譲らない。これは
これで嬉しいこと。懐かしさに2個求めた。
「こんなこいるかな」の雑誌連載を始めたのは1986年。もう20年も経つのだなあ。
(Bの右側は十数年前「お面展」の折、作製した20作品の2点)
(MAR.5)
■二十四節気<啓蟄>、七十二候(7候.8候.9候)
今日は半袖シャツでテニス。めっきり春めく。気分ウキウキの春と言いたいところだが、4月からの
大学新設学科の準備に追われてこのところ、ずうっと休みなし。テニスの回数も減りコートに出ても
すぐ仕事場に戻らなくてはならずストレス解消にならない。
それでも立ち向かう気力、充実感が心中にあり、仕事に夢中になれる自分……幸せなことと思う。
(Mar.3)
 |
|
| 2月のアトリエだより |
■相模女子大学学芸学部『子ども教育学科』オリジナルキャラクター誕生!
『ミンミンゼミナール』へようこそ!
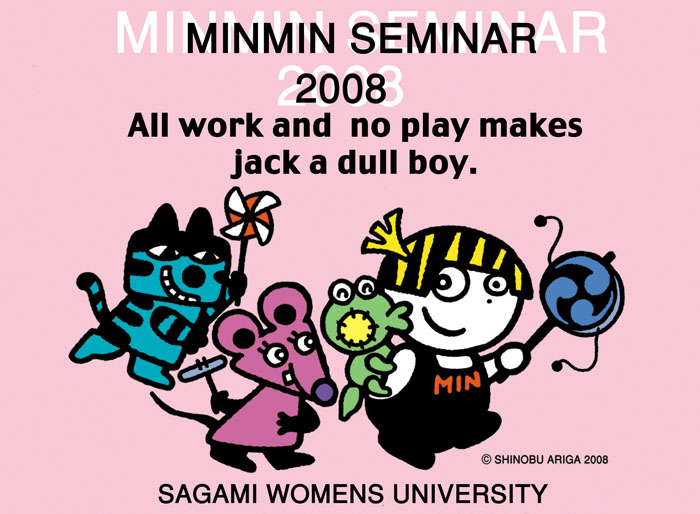
MINMIN SEMINAR(ミンミンゼミナールへようこそ!)
昨年作ったミンミンの周辺キャラ、いたずらっこ3人組、らくがキッズは形態が「こんなこいるかな」に近かかった。
そこで新たに、おしゃまなネズミのゼミー、どらネコのナール、カエル未満のオタマ、ケロッケの3人を生み出し
『ミンミンゼミナール』とした。
物語はミンミンを中心に進行するが、ゼミーとナールの性格の対比、さらに、ケロッケ(通称ケロ)の博識ぶりが
見所!大学のテキストにまずお目見えさせる。「でんでん太鼓」「竹とんぼ」「ブンブンごま」など伝承玩具の
詰まったおもちゃ箱をねぐらにする可愛い仲間達に、乞うご期待!
因みにイラスト中の”All work and no play makes jack a dull boy.は”遊ばなくては変になる!”だ。
しかしながら、ぼくはこのところ満足に遊んでいない。変にならないためにも遊ばねば!遊びたくとも時間がねえ……。
(Feb.27)
■子どもの造形絵本、工作本の役割は創造性喚起,「呼び水」
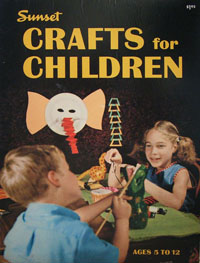
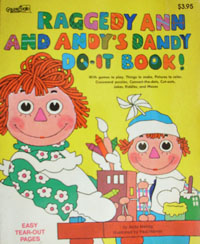
この手の参考書は先ず楽しそうなこと(やってみたいと思わせる)が大事。次にイメージを限定しないこと。工作の紹介は
あくまで”一つの例”。子どもは次から次から、表現できる特別の才能を持っているから”答え”を用意しないことだ。
『CRAFTS for CHILDREN』(AGES 5 TO 12)は30年ほど前に買った。古い本だが、中身は今見ても、創作の楽しさを
紹介しており新鮮だ。ラガディイ・アンの工作絵本も本文はモノクロ。ザラ紙で塗って切って折って貼る…….”DO
IT BOOK”
"EASY TEAR-OUT PAGES"。イラスト(黒線画)がシンプルでよい。子どもが遊べる好素材だ。
ぼくは 『CRAFTS for CHILDREN』で、タイヤチューブのプリンティング(スタンプ遊び)を楽しんだ。『RAGGEDY ANN
AND ANDY’S DANDY DO-IT-BOOK』ではクルミの殻人形を知った。クルミの殻を頭に、真鍮の事務用二股ピンを
足に使う、小さな何とも可愛らしい人形。いずれも素朴な味わいがある。素朴だからこそイメージを限定しない。思い思いに
作ったもの、みな表情が異なる、これぞ創作の醍醐味。
シンプル イズ ベスト……常に、心したい。
(Feb.26)
■ハンス・カロッサ 『序曲』(「幼年時代」の初稿)より
「乳呑み子の薄明のなかから身を起こしたばかりの健康な子供は、いかなる事物にも歓びを感じ、すべてのものに
ほほ笑みかけ、まだ同情をも恐怖をも知らず、動物と人のもつ輝く眼のほうに手を伸ばし、虎をも撫で、火さえも愛撫
しようとするのだ。」
無垢な赤子から幼児期へ。子どもは宝物。保育園、幼稚園、小学校の保育士や先生は、宝物の輝きを失せない
ように導かねばならない。
ぼくはこの春から、保育士や先生の育成に加わることになるが、学生に使命感、誇りを持たせるにはどうすればいいか。
感性、美意識、創造性、造形教育……。四六時中、頭から離れない。寝ても覚めても考えるはこのことばかり。
(Feb.25)
■枯れ野原に梅の蕾の紅、色を添える。まだまだ小さく固いが。



一面枯れ葉色の畑の隅に水仙の黄が鮮やか。梅の蕾はまだ固いが紅がのぞき、開く気配を感じる。明日かあさってか……・
枝を揺らす北風が止む一瞬を待ってオニグルミの新芽を写す。テニスコートで会うSさんはクロスカントリー好きな元気な
おばさんだが、先日フィールドワークのガイドブックを広げて見せた。オニグルミのデッサン、羊の顔に似ていると
はしゃいでいた。絵ではない、本物をどうぞ!接写してみました。ユーモラスな顔はまさに羊!
木々の新芽はさまざまな表情をしていて、面白い。鼻をくっつくくらい近づいて発見する冬から春、この時季だけの楽しみ。
■鳩山の春はまだ。寒風に首をすくめ庭に出る
”転がして遊ぶ”をテーマに遊具「クルリンリン」を考案。転がすためのボックスレールを大学の教室の大机の数分
6基とその収納ケースを製作した。
田んぼから吹き渡る北風が家を壊さんばかりに激しい。風音が恐ろしい。体がしびれるような寒さだ。かじかむ手を
ストーブにかざしての仕事。
身を劈くような寒風でも外に出なくてはならない。風が収まるのを待っていれば日が暮れてしまう。フリースの
トレーナーを重ねて着、ダウンジャケットで身をくるんで宝探しをする。求むる宝は春の味覚、フキノトウ。
発見!20個ほどが芽を出していた。が、透き通るような若草色ではなく、薄紫、薄茶色でたった今、土から頭を
もたげたばかりといった感じ。摘み取るのはまだ先だ。
東京にいて、フキノトウのことが気になっていた。旬が短いから。育ちすぎれば”トウが立ち”食べられない。まだまだと
油断すればあっという間に花が開いてしまう。
刻んでフキ味噌、醤油炒め、丸ごとてんぷらにしても美味い。今年はアルミホイルに包み、火を落としたストーブに放り
込んで蒸し焼きもと意気込んでいる。食いしん坊は夢想家。
春の苦味を肴に酒を酌む……、小さな幸せも一日の暮らし方、仕事次第だけれど。これでもか、これでもか、精一杯
やっても自省的になる。絵が自分を苦しめ苦い酒となること多し。いい絵を一枚描きたい。
■二十四節気<雨水>、七十二候(四候.五候.六候)
思わず首をすくめる寒風。それでも柔らかな日差しに、春の予兆を感ずる。
北風に負けじとテニスコートへ。気温5度、日陰に雪の残るテニスコートは普段よりはすいている。一人、一面占有しサーブの
練習に励む。天は努力は認めない。悪魔が囁く。適性の無さを認識せよ、いい加減に諦めよと……。止めてどうする。三十年
続けてきたテニスだ、諦めたらお終い。創作活動もしかり。この先どうなるか、考えても仕方ないこと。惑うのは人間の常なるも、
今やることが大事。昨日今日明日と続けることに真実あり。行為がすべて。思考にまけるな!表現したいものある限り、
板絵を描き続ける。孤独な作業、弱き身は自らを鼓舞せずにはいられない。
 |
今年の雨水は2月19日 (啓蟄は3月5日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (2月29日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
■残念!『主婦の友』休刊
『主婦の友』は1917年(大正6年)の創刊。5月に発行の6月号の通巻1176号で休刊になるという。
80年代~90年代に休刊した『婦人倶楽部』『婦人生活』『主婦と生活』に続き最後まで頑張った一誌『主婦の友』が
姿を消す。70年代の黄金期の発行部数は70万部を超えていたとも。このころ、ぼくは母がたまに買う雑誌を見ていた。
時代の流れとはいえ、寂しいことだ。
姉が服飾リフォームデザインを『主婦の友』に執筆しており、当時仕事があまり無かったぼくは、姉について編集部に
行ったことがある。編集長と面談するも、”童画”は本誌と関係なく仕事には結びつかなかったが。
雑誌が滅びていく。幼児雑誌もしかり。種類、発行部数とも激減。ぼくが仕事した『えくぼ』(講談社)『よいこ』(小学館)
(『よいこ』の最盛期は数十万部の発行部数を誇った)はじめ多くの雑誌が休刊した。現在出版されている幼児雑誌も
雑誌不況の中で喘いでいる。各誌ともテレビアニメのキャラクターのオンパレード。表紙もキャラクター満載、差別化もなく、
オリジナリティーを模索する力も感じられない。美しい歌詞の童謡、絵描きあそび、世界のお話、日本の民話、工作、観察、
生活など、殆ど紙面には見られない。情操、創意工夫とは無縁だ。
子どもの美的感性を涵養する、潜在的能力を引き出す……これこそ、幼児雑誌の存在価値だと思うのだが、
残念ながら、キャラクター追っかけ、キャラクター頼みの編集姿勢のままでは、幼児雑誌もいずれ姿を消してしまうだろう。
思い切って紙面刷新出来ないものか。いや、温故知新だ。虚心坦懐だ創刊時の原点回帰にヒントがある。当時発行された
幼児雑誌の編集後記を見るがよい。出版人の熱き心を知るが良い。
ぼくの所持している幼児雑誌からの「編集後記に見る心意気・志」「付録に見る創造性・手工重視」については、後日項を
改めて。
(Feb.14)
■昨日と打って変わって震える寒さ!
昨日と打って変わって真冬の寒さだ。冷たい風に背をすくめ本郷の現代童画会事務所へ。
会長辞任で新会長を選出する。休むわけにはいかない。選挙はそう幾たびもあるものではなく、
選挙メソッドが確立していない。創立三十数年となるのに事務レベルで混乱している。が、
決定はあくまで厳正に慎重に。拙速はならない。
肩の荷を降ろす間もなく上野文化会館会議室で行われる現童合同委員会へ。4時、
開放され上野の北海道居酒屋で一杯やる。メンバーみな、いい奴だ。30年来絵を見、
仲間と接してきたがよくいえば善人、悪く言えばアクが無さ過ぎ。破天荒な芸術家は見当たらない。
自分とてそうだ。突き抜けるエネルギーよ何処へ。いつだって”今”が精神の若さの頂点であらね
ばならぬのに。
酩酊して店を出れば冷たい雨。予報では午後は雪のはず。冷え切った体に地下鉄の暖房が
嬉しい。眠気と戦いつつ渋谷の仕事場に向かった。駅を出ると雨は雪に変わっていた。
(Feb.9)
■鏡で絵探し 万華鏡も製作
気温6度でも風がなく春を思わせる温かさ。柔らかな日差しの中、久しぶりにコートに立つ。風邪が治りきっておらず
呼吸が苦しい。正月から休んでおらず仕事のみに明け暮れていたが、熱のせいか集中力に欠けはかどらない。熱さましの
薬も効なく、今日思い切って荒療治!テニスはハードなスポーツだ。たるんでいる精神に気合を入れるつもりが、やはり体は
思うように動かない。それでも2ゲーム。気分を入れ替え午後の仕事に向かう。
「光で遊ぶ」のテーマ。万華鏡(カレイドスコープ)を幾つか作る。一般的なビーズや色紙片を入れて見る物、ビー玉を使った
景色を見る物(テレイドスコープ)、そして、ドロリとした糊の中でゆっくり落ちて行く物をみる万華鏡など。ガラスや反射紙で角度
60度の角柱をつくる。先日はオルゴールで糊の入ったガラスの小瓶を回転させる万華鏡を作ったが、ぼくは大きな透明のビー玉を
使ったシンプルなものが好きだ。対象物は景色。きらびやかではないが素朴な光景が展開され見飽きない。
「光で遊ぶ」では、鏡面紙(反射紙)を使う『鏡で絵探し』も。シンメトリーの図像の半身に鏡をあて正体を浮かび上がらせると
いうもの。ぼくはこの遊びを、幼児雑誌には何度か掲載したことがあるが、いずれも見開きに5~6個くらい。今日作ったものは、
60個を超える。A-4の紙に構成されたジクソーパズルのようだ。鏡を使っての遊び、造形と想像の楽しみ。
(Feb.8)
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候)
駒ヶ根高原美術館で夏に開催する個展の打ち合わせをする。素晴らしい美術館だ。展示スペース、空間、申し分なし。
可動壁の確認、絵本や装丁本の陳列ショウケースの設置場、ポスター、パンフレット、図録などについて話し合う。板絵の
並ぶ美術館の壁面を想像し胸ときめく。
道路の雪はとけていたが、あたり一面真っ白。聞けば、昨日(28日)降ったのだという。以前、駒ヶ根にクルミ屋があるとの
新聞記事を思い出し、蕎麦屋で聞くと難なく分かり地図まで書いてくれた。国道沿いにその店『大脇くるみ店』はあった。残念なことに
誰もおらず、クルミを求めることはできなかった。新聞記事ではおばあちゃんが石のうえにクルミを置いて槌で殻を割っている
と書かれていた。昔ながらのくるみ割りだ。ぼくの祖母もそうだった。祖母はオニグルミ(殻が非常に堅い)を割ってぼくに
食べさせた。上手く割れた形のよいのをぼくに、自分は細かく割れたものを口にしていた。6~7歳頃のことなのに、オニグルミの
思いでは忘れない。囲炉裏で炙ってくれた五平餅のくるみ味噌の味も。
鳩山のアトリエの畑にもにも3年前オニグルミの木を植えた。でも、実が成るのはいつのことやら。今まで果樹は色々植えて来たが、
苗木の幹が虫やカビにやられて腐ってしまうことも度々。消毒も、施肥もしない。それでも乗り越え大きく育ってくれたらと、我侭な
期待、願いをかけるのみ。
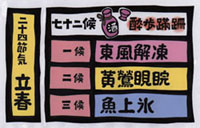 |
●今年の立春は2月4日 雨水は2月19日 ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
| 2008年1月のアトリエだより |
■蕗の薹の春、待ち焦がれて!
新聞に「ふきのとう芽を出す」の記事。暖冬で早まっている。ぼくは蕗の薹が大好きで、毎年この時季そわそわする。
昨年は摘み取りが少し遅れたために苞は開き気味だった。蕾が固くしまったものを収穫したいのだけれど、そのタイミングが難しい。
枯葉を掻き分け若芽を摘む。育ちが早くて、まだだ、もうちょっと、と思っているとすぐ大きくなり苞がひらいてしまう。次から次に
芽を出すから、何回も摘むことになるが、フキの畑(毎年大きなフキの葉で覆われる空き地3メートル四方)に毎日入るわけではなく、
”旬の”収穫を逃すことも。
スーパーでパック詰め蕗の薹が売られているが、鳩山の蕗畑のものには、春の香の鮮度で及ばない。”春の香りの鮮度”
は単純に苦味だけではない。瑞々しさ、噛み締めたときの喜びとでもいおうか。
丸ごと天ぷら、油炒めに。刻んで蕗味噌に……いずれも美味。アケビの皮のオリーブ炒めと共にぼくの最も好きな酒肴のひとつだ。
ああ、鳩山の畑が気になるなあ。何時行かれるのだろう。絵も制作途中だし……。今週末か、来週頭か。蕗の薹よ、今しばらく
頭をもたげずにいておくれ。春を待ち焦がれ、蕗の芽を待ち焦がれ、胸ときめく。
明日は信州、駒ヶ根高原美術館へ。夏の展覧会の打ち合わせだ。雪が無ければよいが……。信州は、冬真っ只中。寒かろう。
(Jan、28)
■『絵本による自己表現』講義最終日
23日は東京は2年ぶりの雪。大学へ重たいカバンを背負って行く。中には最終課題の手作り絵本が25冊。真っ白に覆われた
キャンパスのグランドを横目に降りしきる雪の中を教室へ。今日は授業最終日。作品を講評して返却する。
落伍することなく、学生は絵本を仕上げた。凄いぞ!!エライぞ!ぼくは誉め讃えた。答えが用意されている日常を生きる者が
マニュアル思考ではない自由に発想し、自分だけの表現をすることは容易なことではない。4年目の今年も、学生は戸惑いを
見せた。が、短期間に3冊の試作と最終課題の作品を仕上げた。学生達、素晴らしい。よく頑張った!
最後に製作した感想をレポートにしてもらったが、作る「楽しさ」「喜び」「満足」を記したものが多かった。一様にストーリー作りや
何も無い所から生み出すことの難しさを述べてはいても、苦労を超えたとき得られた「達成感」も味わっている。
社会に出てもこの”体感”を忘れずにいて欲しいと思う。創作は自分と(知らず知らず)向き合うこと。自分を知り、認める。自分の
価値観、美意識がどれほど大切か学生に伝わっていたら、ぼくは嬉しい。
帰り、雪は小降りになった。駅横の画材店に立ち寄る。空になったカバンに画材(アクリル、ガッシュ、トレペパッド、スティン塗料、
接着剤……)をどっさり詰め込む。外に出て後悔。道はすべるし、何も今日買わなくても。いつも、ぼくは後先考えないで行動する。嗚呼……。
(Jan.24)
■『元永定正』展、また最終日!
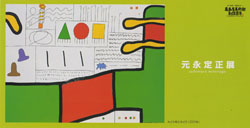
「元永定正展」。あたふた駆けつける。いつもこうだ。見たい見たいと思っていても、ずんずん日は過ぎてしまい、
二週間の会期は気が付けば最終日。
色が溢れ、形が歌い呟く……”自由””詩””リズム”が満ちている元永ワールドを満喫。『みどりあかみどり』
『しろいひかりいちのくろ』『てんせんやらかたちやら』……タイトルも直接的で笑える。
元永定正といえば、絵本『もこもこ』を思い出す。自由に描かれたな絵に詩人、谷川俊太郎が文を付けたものだが、
”感じる絵本””見る絵本”の極上の一冊だ。各ページに並んでいる擬音語、擬態語……、もこもこ、にょきにょき、もぐもぐ、
つん、ぽろり、ぱちん、ふんわふんわ……見飽きない。オノマトペの効果と、これぞ”自由”といった絵が気持ちよく感性を
刺激する。
展覧会はデパートの美術部創設100年記念と銘打っていた。いつもながら感じることだが、係りの方が話しかけてくるのが
”鑑賞者”には迷惑。「何点かお持ちですか」「お知り合いの方ですか」。セールストークがうるさい。控えめに、気を使いながらでは
あり商売上仕方ないことだろうけど……。そうそう買う目的の客ばかりではあるまい。ぼくはいつも、静かに見させていただくのみ。
■30年前のエッセー……当時は(も?)熱かった!
雑誌を束にして資源ゴミ置き場へ。括られた本の一番上に『カレーライス』があった。「何だ、料理本?」。
捨てる前、束から引き抜いてパラパラパラ。分かった。カレーについてのエッセーを書いていたのだ。
昭和53年(1978)主婦の友社刊。30年前の文章を、ゴミ置き場で読み、持ち帰った。
ぼくは料理が大好き。アトリエでも仕事の合間楽しんでいるが、現在は当時のスパイスをブレンドするような手の込んだ
カレーは作ってはいない。文中のスモーキング・キャニスター(薫製器)は、今は鳩山の農機具小屋で眠っている。起こして
使わねば!
文章からは、若かった頃の熱度の高い思いが伝わってくる。絵本的生活日誌の「エッセーの頁」に再録しようと思う。
(Jan.22)
■二十四節気<大寒>、七十二候(七十候.七十一候.七十二候)
今日21日は一年で一番寒いと言われる大寒。天気予報は雪だった。テレビ各局が自信たっぷりに雪を予想。降らぬを幸いに
コートへ。気温2度。さすがに人影まばら。ハードコートで一人サーブの練習をする。体が固い。ラケットを握る手がかじかむ。
息を吹きかけながら100球ほど打ち込む。ゲームは6-3、2-6。
昼前には仕事場に入り、まず掃除、片付け。お客様、編集部、が来ることがなければ部屋は汚いままかもしれない。
日はほんのちょっとずつ伸びているのだろうが、昼間が短くて明るい中での仕事は幾らもできない。やらねばならぬこと多く、
気ばかり焦る。遊び心での仕事を我は理想とするのだが……。
(Jan.21)
 |
●今年の大寒は1月21日 ・七十候 (1月21日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■フェルメール展とムンク展
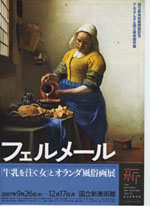
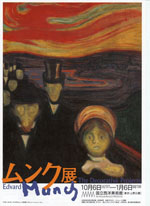

昨年暮れも押し迫った中、大急ぎで二つの展覧会を回った。国立新美術館(六本木)と国立西洋美術館(上野)。片や
入場者数40万人、一方は20万人を超えており大人気。チケットを持っていたから良いようなもの、切符売り場は長蛇の列、
一瞬入るのを躊躇うほどの混雑ぶり。ゴッホ展のときは美術館に至る道を行列が塞いだから、それよりはいくらかマシか。
館内は人いきれ、暑いし”鑑賞”なんてとんでもない。人はベルトコンベアーよろしく、すべての絵を見せられ(見たくない絵も)
、同じスピードで進んでいく。ぼくは人垣の肩越しに主だった作品を眺め、少しでもすいている絵に近づいた。幾点かに
目を凝らすのがやっとだった。
フェルメールは『牛乳を注ぐ女』一点のみ。パンフレットやポスターで大きくフェルメールとあるので、少々がっかり。いや、
大いに不満だ。確かにフェルメールの大きなタイトルの下には”「牛乳を注ぐ女と」オランダ風俗画展”とあるから、
嘘ではないが、あざとく思えてならない。「フェルメール展」と思う人は少なくないだろう。
「牛乳を注ぐ女」は生活の一瞬の時間を切り取ったようで、リアリティーがあり、光が溢れていた。確かに名品!
素晴らしいのだが、一点しかないからではないが、Ⅹ線で下描きされているものを見つけ出したり、構図を透視図法で詳しく
解説したり、リュートなどの古楽器などの展示で関連づけたりと、何だか水増ししているように思えてならなかった。
むしろ、充実していた17~19世紀までのオランダ風俗画、特に「台所の女たち」を堂々と、前面に打ち出しても
よかったのでは。フェルメールを”目玉”扱いするあまり、「えー、これだけか」の失望感を抱かせてしまったのだ。
45・5×41㎝の小さな絵は他の絵とは区別され広い部屋に展示されていた。係員の「立ち止まらないでお進みください」の声に
押されるように”鑑賞者”はベルトコンベアー方式で流れていった。誰も文句をいうわけでなく大人しいこと!ゆっくりじっくり見たい
ひとは流れに乗らず、後方から眺めるのだが、無論遠くてディティールなど分かるよしもない。
「フェルメール展に行った」方も、”満足に見られたか?”の問いかけには、かぶりを振るのでは。
ぼくは例によって人垣の無い作品を狙って鑑賞。ヤン・ステーンの『オウムに餌をやる女、バックギャモンする二人の男と
他の人物』という、えらく長いタイトルの作品を興味を持って見た。
一方、ムンク展は展示が面白く混み過ぎを除けば満足した。ムンクが試みた装飾プロジェクトを代表作など108点で構成
した企画が良い。
ムンクは作品を一つずつ単独で鑑賞するのではなく、<生命のフリーズ>と名付け壁面に構成した。絵は本来、一作一作
鑑賞するものだが、ムンクの場合、愛と死、喜びと絶望など心の叫びを一堂に全体として纏め上げたかったのだ。意図する
ものはよく分かる。展覧会でも作品は一般的には壁面に沿って並列展示されるが、<生命のフリーズ>では、ドアの開口部
の上にも掲げている。アトリエの壁面を作品で埋め尽くす……壮大なプロジェクトだ。絵描きとして、その空間は一つの
桃源郷であろう。
ムンク展はついこの間も、見た気がして調べてみたら、1997年(世田谷美術館)。こちらは絵画170点、写真110点。過去
最大規模の企画……とある。このときは<不安>を見た。今回は<絶望>。いずれもムンクの代表作。
それにしても考えてしまう……、時の流れの速さを。それに比し、歳をとらないなあ、良い作品は。これが芸術の醍醐味か。
(Jan.16)
■森山里子さんからの便り 続き
(3)●私のふるさと
私の住んでいた所は 何でも 音そのものを 見たまま呼び名にしていました。前にも書いた ぺったん(めんこ)
かっちん(ビーだま)等…。
あと パッカンというものもあって、それは ポン菓子のこと。授業中に パッカーンと 窓から大きな音が聞こえて
くると、「あっ!パッカン屋さんがきたー」と、気もそぞろ。学校が終わるとお寺に一目散! 歯の抜けたおじさんの
手伝いをさせてもらいました。楽しかったなあ。
海のそばだったのですが、『カバンため』と言われる家があって、明治ごろ、おじいさんのおじいさんが、海でカバンを
拾って 中を見ると大金が入っていて、それをおまわりさんに届けず、商売を起こし、大家さんになったとか…。そこの
子供は今でも『カバンためのとこの息子』などといわれています。
『ほんじゃけん』という店があって 他に栄軒(さかえけん)という菓子屋もあったから、どういう漢字を書くの?と大人に
聞くと、そこは本当は<中塚屋>というのだけれど、そこの養子さんが、九州出身の人で、<だけど>を『ほんじゃけん』と
いつも言うので そのほうが名前になったと聞かされました。
他に 馬車幸さん、センタさん、ますさん、良平さん…。
(申し訳ないけど)面白いエピソードだらけ。海と山に囲まれた、私のふるさとです。
記憶の中の褪せない輝き。故郷の想い出は宝物。宝物が多い人は心、豊か。ぼくはこういう話が好き。ずうっと
聞いていていたい。時に、自分の幼き頃とオーバーラップ。体を懐かしい風が吹き抜ける………。
(Jan.14)
■頂いたお便りに、心ホッコリ温まる
「アトリエ便り」をご覧になられた方から時折メールをいただく。メールは、絵本「こんなこいるかな」在庫の
問い合わせや展覧会の板絵」について、そして精神の発達障害をもつ子どものお母様(複数の方)からのものが多いが、
ここでは『絵本的生活日誌』をご覧になっての感想を認めた、懐かしい香りが漂うような心がホッカリ温まる手紙を紹介する。
□森山里子(仮名)さんのお便り
(1)●「ダイヤモンドゲーム」の世代です
リリアン、お手玉、おはじき、ぺったん(めんこ)、かっちん(ビー玉)、竹馬,石けり(ぞうきん、しょんぼけ、
いっぽせ)陣取り、ダイヤモンドゲームの世代です。
お手玉などは 愛知にいた頃 小学校に昔遊びの達人として 出前してましたよ。(男性は 鉄のコマを
廻して 蓋に受けるなど)
今 中学一年の娘には 幼い頃 リリアンをさせました。それを 肩紐にした合作ポシェットが 引き出しに
あります。保育園でも 牛乳パックの底を抜いて、上部を2cmくらいのデコボコの切り込みを入れたもので
(極太毛糸を使って)リリアン方式で マフラーを 作って着てました。そのまま今 編み物好きに 成長しています。
こどもたちの外遊びも減り、手先を使うことも少なく、本来遊びの中で作られるはずの体力、バランス、
工夫や器用さが全然 身につきませんね。私たちは 幸せな世代です。ホント
(2)●先日の”「カワセミ」を見た!”について
おはようございます。私は愛知県で一度 静岡に来て一度 会いました。
愛知で見たときは 冬の朝、新聞配達の途中で、皮の堤防に じっととまっていて…あまりの美しさに
息を呑み 見入った。 でも すっと川面に下りてしまった。探したけど もう 見つけられなかった。
その日は 初句会だったから『瑠璃色の寒禽にあふ 今日は吉』と詠む。東京の先生が とってくれました。
それから 数年して静岡に…。磐田の駅で娘と200円の自転車を借りて名所地図を片手に 川沿いの
小道を走っているときに 不意に すーっと飛んでいきました。 夏の終わりのその日は、よく晴れていたので
いっそうあの<青>がさえていました。
森町は カワセミの里といいます。町の鳥に指定されています。まだ この町に来てから 会ってはいませんが
私を迎えに来てくれた『青い鳥』と思っています。
さて<ブリコラージュ> <ブリコルール>という言葉、ご存知でしょうか?オモチャや リリアンの道具、いろいろ
作ってしまう有賀さんはブリコルールなのだと思います。 ちなみに 私も<ブリコルール>の一人です。
森山里子さんからの便り(3)は明日、この欄で。
(Jan.13)
■茶の種でサルの顔ができるって本当……?
運動不足解消にテニスコートへ。昨日今日と、仕事の前の2時間の楽しみ。
今年の初打ちは4日。2戦2敗の幕開けだったが、昨日2勝、今日3勝と気分がよい。
今年の課題はサーブのスピードアップだが、コートの関係で、サーブ練習もそこそこに試合となった。
練習しないほうが成績が良いのだから皮肉なものだ。
クラブメンバーの一人Sさんから「茶の種でサルの顔が作れる」と聞いていた。鳩山で採取した種を持参し
ゲームの合間に教わった。残念ながら、種は種でも木からこぼれる前のもの。3つの種がくっついているもの
でないと顔にならないという。種が二つ、まだくっついているものがあったので試してもらった。
種をコンクリートでこすると、現れた!確かにサルの顔の両目の部分だ。もう一つあれば口になると容易に
想像できる。今年の茶の種の採取が待たれる。鳩山の畑に出かける楽しみが増えた。
(Jan.11)
■生誕100年記念 「ブルノ・ムナーリ展」に大満足
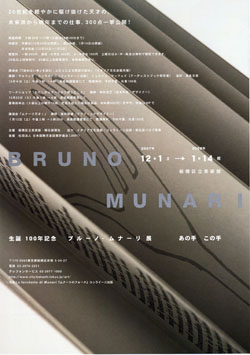
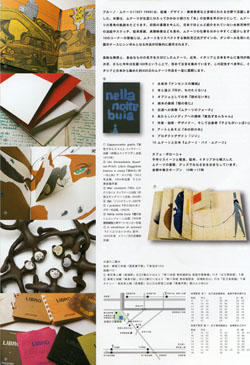


交通のアクセスの悪い美術館だが、催しが終わる直前駆けつけた。60年代からのムナーリファンのぼくは大感激。
ガラスケースをのぞきこみ、繰り返し繰り返し2時間も鑑賞してしまった。ムナーリは絵画、グラフィックやプロダクトデザイン、
彫刻、それに美術教育に才を発揮したアーティストだが、何といっても絵本!ぼくが仕掛け絵本「ねぼすけくんは
だーれ?」を出版した折、編集部からプレゼントされたのがムナーリの仕掛け絵本三部作だった。(「プレゼント」は
『絵本の小径・絵本の玉手箱』でも紹介している) あのときの興奮、凄いものを見た驚き。今では仕掛け絵本は
珍しくないが当時としては異端の絵本であった。
以来、ムナーリの作品に関心を持ち、幾つか手に入れた。上の写真のゴム印(ズッシリと重量のある木片にデザイン
。今月号の芸術新潮にも紹介されている)。鉄板を曲げただけのシンプルなカードケース(写真も立てられる。
ペンを置くところも配慮されている)などいずれも機能美溢れ愛用している。
展示作品は目を見張るものばかりであったが、一つ挙げるならば、『旅行用彫刻』。ペーパースカルプチャーの一種だが、
切り紙、折り紙で平面を立体に表現。折りたたんで持ち運びもできる”携帯彫刻”。彫刻だから、見る角度を変えて楽しめるが、
遊び心が溢れている。図録には「空間を占領し、不動のモニュメントだった彫刻に新しい可能性を見出した。」との説明が。
6点、いくら眺めていても見飽きないから不思議だった。
ぼくは余りの嬉しさに、美術館の学芸員に大満足の礼状を書いた。
(JAN.9)
■鳩山日帰り、慌し。喜多見の自宅(8am)→鳩山→渋谷(11pm) 休息なし
朝7時25分、NHKテレビ絵本「こんなこいるかな」を見て一路、鳩山へ。10時~夕方まで板絵を制作。
一度だけ外に出る。時折現れるキジの親子(母と4羽の子、なぜか父さんは見かけない)のためにパンくずを
置きに。いつも皿の上のパンくずは、跡形もなくなるのが嬉しい。
葉を落とした梢には鳥の姿がくっきりみえる。メジロ、ヤマガラ、シジュウカラ。普段人影のないわがアトリエの
庭に集まる鳥たちは、あまり警戒心をもたないのか、ぼくの目の前で囀っている。これも嬉しい。
ウメの蕾は小さく固い。ロウバイもまだ小さいけど、もうじき開きそう。何ともいえない芳香に目を凝らせば、
小さなロウバイが2つ、ほころんでいた。春を待ちきれないのか。芳しさに、またまた嬉しくなった。
(Jan.8)
■からくり回転玩具を製作。円盤模様描きも楽し



・ボール紙にガッシュでグルグル模様を描く ・完成した、からくり回転機本体と円盤 ・装着した円盤を回転させる
回転円盤機を作る。円盤台座はシナベニアをテーブルソーで切り抜き紙やすりで仕上げる。台座の下には
ワッシャー(筆の軸を利用)を接着する。本体となる棒にボール盤で垂直に穴をあけ、軸棒を通す。軸棒には
綿ロープを6回ほど巻きつける。シンプルで面白いからくり玩具の出来上がり!
色や模様が様々に変化し、飽きさせない。螺旋状に線を描けば、床屋さんの店先で見かけるグルグル上昇して
いく縞模様となる。回転速度を速めたり落としたり、順回転、逆回転も楽しいものだ。
(Jan7)
■アトリエ開き?正月も開きっぱなし!
毎年仕事開始は3日と決めているが、今年は鳩山のアトリエには元日から入った。板絵10号Sの制作は
酩酊状態ながら気分よく捗った。訪れる者なく、物音一つしない空間に正月の華やぎはない。ただ、ぼくには
贅沢な酒、大吟醸「月の滴」だけが、正月を祝祭していた。畏友の杜氏、宇都宮繁明君が送ってくれた美味し酒なり。
作品の出来具合は後日、この欄で……。(2日、3日はからくり玩具「回転円盤」を製作。これも、近日!)
(Jan,6)
■テニス初打ち無惨!連敗す!
4日、テニスの打ち初め。若干肌寒くも、風なくテニス日和。サーブ、ラリーの練習もそこそこに2ゲーム。
久しぶりで体動かず、5-6、2-6の完敗。まあ勝敗はともかく、ストローク、ボレーすべて悪く、肝心のサーブも
ままならぬ点が心残り。もう少し打ちたい気持ちを抑え仕事に戻った。
テニスをした回数、昨年は79回。ここ15年、平均約100回。最高123回、最低はテニスエルボーで
4ヶ月休んだ年の60数回。今年はテニスの回数は大幅に減るだろう。大学に通うようになり仕方ないことだけど、
残念だ。ぼくは頑丈な体はテニスのおかげと思っているから。大学にも新しいテニスコート(オムニ)が4面あるが、
そうそう打つことは出来ないだろう。機会は少なくなっても限られた時間(9時から11時まで)、中味の濃いテニスを
楽しむしかない。「継続」「努力」「一所懸命」………ぼくの気持ちは変わらない。
(Jan.4)
■二十四節気<小寒> 七十二候(六十七候.六十八候.六十九候)
 |
●小寒 1月6日 ・六十七候 (1月6日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月11日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月16日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
■あけましておめでとうございます
平成20年1月1日
今年もアトリエ便りをお楽しみください。鳩山の四季の移ろいの風景と、ささやかな
ぼくの喜びをお話しますね。 それでは「日々新生、日々創造」で参ります。

| 2007年12月のアトリエだより |
■柚子の蜂蜜漬。ビンのラベル作製も楽しい。


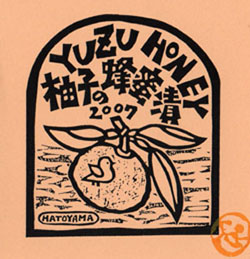
鳩山の今年最後の収穫は柚子。五十個以上もとれ、冬至には柚子湯を楽しんだ。ジャムを作った。蜂蜜に漬けた。
蜂蜜漬は十日ほどしていただく。大匙で2~3杯、湯で満たす。香り高き柚子茶は体が温まり、のどにも良さそう。
ビン詰めを眺めているうちに、ラベルを作りたくなった。葉の付いた柚子をデッサン。切り絵で作画。モノクロコピーで
仕上げる。なんて楽しいんだろう。昔、食品雑誌にイラストを描いていた頃を思いだした。丸や楕円、六角形にデザイン
された文字入りのイラストはまるでワッペンかメンコか。当時も楽しかったと記憶している。
PCで彩色し、ラベルフィルムで仕上げても良かったが、仕事の合間ではこれくらいでよいだろう。生活のほんの片隅に
楽しさや、幸せは転がっている。柚子の蜂蜜漬には香りと甘酸っぱさ。それに心をやさしくする効能があった。
(Dec.30)
■テニス、打ち納め会に行かれず!
28日金曜日はテニスクラブで打ち納めをするはずであったが、残念ながら行かれず。前夜遅くとも2時か3時には
寝ようとはりきっていたが、暗室で夜を明かすはめになってしまった!プロセッサーの調子が悪く一晩中機械と格闘。
ネガフィルム、ポジフィルム、無駄にすること数十枚。胸部レントゲンのフィルム大の感光材料は、ネガポジで7~800円
するからかなりの痛手だ。
現像液を温めたり、露光時間や絞りを調節したり……、夜が明けたが労は報われなかった。この先どうしよう。キャラクターの
仕事はセルを作り彩色する手法を20年以上やってきたが、機械の不具合を直す技術者はもういないし、感材も入手が困難に
なってきている。フィルムの時代は過ぎたということだ。
CGも使っているが、”手工”的なものが好きで、すべてパソコンに移すのは忍びない。絵の具を混ぜる、塗り重ねる。紙を切る。
剥がしたり糊付けしたり……、物を作る、生み出す楽しさはCGでは得られない。グラフィックツールとしてその利便性は認めるが、
性に合っているかどうかという問題。
パソコンモニターに向かい、心を籠める、一心不乱に”格闘”するなんてこと、ぼくには到底できない。
(Dec.29)
■NEWS!!! 「こんなこいるかな」新春放送決定!!!

新年早々、「こんなこいるかな」が放送されます。『母と子のテレビ絵本』用に製作したものを5日間連続で
お送りします。講談社の絵本で出版されなかったものも放送されると思います。「こんなこ」ファンは必見ですよ。
●1月7日~11日 朝7時25分 NHK教育テレビ 「母と子のテレビ絵本」をご覧ください。
(Dec.27)
■回転玩具「コロコロ転転・こんなこ版」



・「こんなこいるかな6人揃い」 ・いたずらっこの「たずら」 「やだもん」 ・ 「やだもん」 「ぶるる」
「コロコロ転転」を作製。スロープは牛乳パック3個使用。更に多く繋げて長いスロープを楽しんでもよい。角度は出来るだけ
低くおさえる。ゆっくりゆっくり回転しながら落ちて行くさまは見ていて楽しい。スロープはU字型にすれば行ったり来たりの反復
運動で遊べる。軸となる竹ヒゴにビニールテープを巻くのがコツ。摩擦抵抗をつけ、回転せずにすべり落ちるのを防げる。
幼稚園ではベニア板を細長く切ったスロープを用意しよう。180センチの長さのものを数本。園児には丸く切ったボール紙をわたし
自由に色を塗ったり、グルグル線を描きこんでもらう。保育士はそれに竹ヒゴを通して返す。コロコロ転がっていく自分の作品を
目で追う園児の真剣な姿が目に浮かぶ。これはやってみて、とても面白いから、うけることだろう。
(Dec.25)
■回転玩具「コロコロ転転」試作


回転玩具を作り 「コロコロ転転」と名付ける。シンプルで面白く飽きない。スロープは180センチの長いものを製作した。
傾斜を少なくすれば、回り落ちる速度が遅くなり、かなりの時間を楽しめる。続けて2個、3個と転がしてもよい。描いた模様が
回転によって変化する。予想外のパターンにびっくりすることも。創造力を高める玩具だ。
(Dec,24)
■カワセミのコバルトブルーにうっとり

朝、世田谷通りの歩道橋でバスが来るのに気づきバス停まで走るも間に合わず。こんなときぼくはバスを待つのが嫌いで、
次のバスが来るまで2~3の区間を歩くことにしている。今日もそうした。
日大商学部前に向かって歩き出してすぐ、大蔵団地で歩をとめた。団地は世田谷通りより低地にあり、鬱蒼とした森がある。
傍らに湧き水が集まり小さな沢になっている。そこでカワセミを発見!一羽のカモ浮かんでいたが(種類はカワセミに気を取られ
しっかりみておらず不明)が身動きせず、はじめ飾り物かと思った。それがスーと動いた風景の中にカワセミがいたのだ。
目を疑った。森とはいえ上空から見れば小さな林だろう。こんな都会にカワセミが?
コバルトブルーが輝いている。雨上がりで落葉が張り付く地味な色の中で、カワセミの青は一際鮮やか。感動!
言葉にできない喜びであった。ヒマラヤ杉の間を抜けて飛び去ったが視覚の底に焼きついた。
バスを乗り損ない仕事の進行が遅れてしまう……そんな溜息はすっかり消えていた。
(Dec.23)
■畑は一面、落葉で覆われた。今ある色といえば、柚子の実の黄色だけ


今にも降りだしそうな曇り空。庭に出て柚子を採る。収穫四十数個。柚子ジャム、柚子の蜂蜜漬け、柚子味噌にと
思いは膨らむが、いずれにしても十分過ぎる量だ。あとは風呂に浮かべよう。香りに包まれれば一年の疲れが少しは
癒されるかもしれない……と期待して。期待なら、創作アイディアが閃きますように……、こちらの方が優先だ。
(Dec.22
■二十四節気<冬至>、七十二候(六十四候.六十五候.六十六候)
 |
今年の冬至は12月22日 (小寒は1月6日) ・六十四候 (12月22日) ・ふゆ しょうじ なつかる 冬生じ夏、枯る ・六十五候 (12月27日) ・しか つの おつる 鹿角落つる ・六十六候 (1月1日) ・ゆき わたりて むぎ のびる 雪下りて麦のびる |
今年度、小寒(1月6日)より始めた当欄「二十四節季七十二候」も漸く22日の冬至で一巡,ほっとする。二週に一度の掲載だが
日が経つのが早いこと早いこと。休む間もなく次の二十四節季を用意しなくてはならない。しんどかったが漸く解放される。旧暦で
何となくピンと来なかったこともあったが、TVの天気予報や季節の便りとは違った視点で二十四節季をとりあげてきた。実際は
季節を観照し茜雲などを絵に描きたかったのだけれど果たせず残念だ。
年の瀬の大掃除が始まったのか、テニスコートもガラガラ。今日もハードコートに人影見えず。一人サーブ打ち込みの後、Sさんに
サーブを受けてもらう。その後ゲーム。6-5の辛勝。
毎年テニスをした回数を励みの為つけているが、今年は昨年の半分だ。来年はもっと大幅に減ることだろう。上達したいがそれも
夢だ!大学には新しく作られたオムニコート4面あるものの、新米先生にはコートに出る余裕はあるまい。
(Dec.21)
■サンタクロースについて悩む方へ
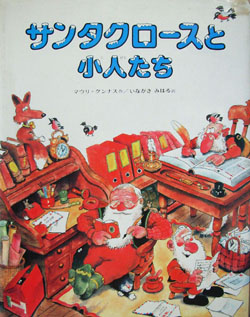
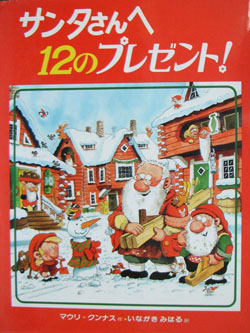
新聞の人生相談欄(読売12月4日)で、30代の主婦がクリスマスプレゼントに関する悩みについてアドバイスを
求めていた。
「小学2年生の息子はいまだにサンタクロースを信じており、高額なゲーム機を貰えると思っている。ゲーム機は去年
あげたばかり。サンタの正体を話すか、期待はずれのプレゼントでごまかすか悩んでいる」というもの。
回答者は作家の出久根達郎。「息子さんはサンタの招待を既に知っているのではないか。親としては子の成長を願い
ながら、一方で引き留めようとの思いがあるもの。プレゼントのことは高価なものは無理とはっきり話したほうが良い」
ぼくなら、絵本を見せるだろう。『サンタクロースと小人たち』作/マウリ・クンナス(偕成社)。サンタクロースの生活が
ユーモラスなイラストで綴られていて楽しめる。相談者の子どもの興味はさしあたり”プレゼントだろう。どうやって玩具を
用意するのかって?”実際は小人たちが大工工場、織物工場、瀬戸物工場、印刷工場でせっせと働いて作るのだが、
玩具が出来上がるまでが細かく生き生きと描かれている。人形やぬいぐるみ、汽車、自動車、笛、スケートの棚が
並ぶ倉庫は壮観。その中に、水車ゲームや絵本はあっても、相談者の望むようなゲーム機はない。一つ一つ心をこめ
手作りされた温かな玩具ばかりだ。プレゼントを包む場面だって足の踏み場もないほどの量に圧倒されるが、お店で
買ってきて渡すだけの物とは無縁で小人たちが皆嬉々として働いている。相談者の子どもも、きっと何かを感じるだろう。
こうも言おう。「パパもママもサンタクロースはいるって信じてるよ。でも、いつからか来なくなったなあ。ちょっとづつ
大人に近づいていくの、サンタさん分かってるんだよ、きっと。大人になれば、サンタさんはもうプレゼントはくれないだろう。
パパ思うんだ。パパはもうプレゼントは貰えないけど、サンタさんて、一度プレゼント配った子どものこと、永久に忘れないね。
だから、パパのこと、サンタさん覚えてるとおもうよ。もちろん、お前のことも大人になるまでずっと見守ってくれてるさ。」
ここまで書いて気がついた。この種の人生相談、前にもあったなあ。以前この「絵本的生活日誌」の当欄で取り上げたっけ。
興味のある方はバックナンバーをご覧あれ。
マウリ・クンナス作『サンタさんへの12のプレゼント』もお薦めの一冊。クリスマスまであと12日となり、小人の坊やビッテレが
毎日サンタさんに考え考え、プレゼントを逆にあげていくというもの。『サンタクロースと小人たち』とあわせてどうぞ。
(Dec.20)
■墓前に設えた供物台が吹き飛ばされる………と、心配させるほどの強風!
天気晴朗なれど風強し。北風吹きすさぶ中、体の凍えを辛抱して読経を聞く。八柱霊園の芝墓地、丈母の三回忌。
誰一人コートを脱ぐことが出来ない寒さだ。お坊さんも震えている。法話を取りやめ足早に去って行った。強風の空に
雲の姿薄く、気がつけば墓の供物がない。りんごやバナナはどこへ消えた……?カラスだ!一瞬の隙を見て咥え
飛び去ったのだ。
お清めの席では参会者の殆どが車ゆえ、冷え切った体に酒を流し込むのはごく一部の者。ぼくは子供たちを
集め遊んだ。ビールの王冠、箸袋、お膳の敷き紙などを使って。男の子とは以前、やはり法事の折(ぐずっていたので)
ビールの王冠で造型想像遊びをしたことがある。其の時、よほど楽しかったのだろう「おうちに来てもいいよ。あそぼ」と言った、
その子だ。(当時、未就学だった幼児に誘われ、”年長の”ぼくは嬉しく思った)
今回は少し凝った造型遊びを数種、その作り方も教えた。お清めの席で不謹慎かもしれないが、子供にとって法要の席は
退屈なもの。やはりぼくは子どもの味方でいたい。
(Dec.16)
■ブリューゲル『子供の遊技』の「クルミの風車」 その2
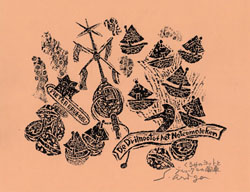
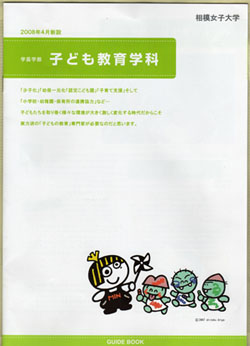
先日授業を終えて、子供教育学科のガイドブックを取りにF先生の研究室に寄った。お昼を食べながら雑談中
話は、ブリューゲルの絵「子供の遊技」に及んだ。F先生は授業に使っていると言う。100近い子供の遊びを、絵の
輪郭をなぞった線画を学生に渡し、其の遊びの名を書かせるのだと言う。もちろん、現代では何だか分からない遊びが
多いが、それも考えて述べさせる。狙いは、多種にわたる遊びの紹介ではなく、想像力涵養だろう。
”想像力は創造力に通ず”はぼくの基本的考えでもあるが、思わぬ所でブリューゲルの話が出て花が咲いたことが
今日は嬉しかった。
(Dec.14)
■ブリューゲルの『子供の遊技』に描かれた「クルミの風車」を作る



ピーテル・ブリューゲルの油彩『子供の遊技』(1560年、ウイーン美術史美術館)は様々な子どもの遊びが描かれている。
何とその数91種類。樽揺らし(シーソーの原型か)、目隠し鬼ごっこ、取っ組み合い、子守ごっこ、投げ独楽、ねずみの尻尾
ごっこ、洗礼ごっこ、うさぎ跳び、仮面遊び、短棒投げ、煉瓦積み遊び、お粥のかきまぜごっこ……などなど。半分以上が知ら
ない、分からない遊びだが、どんな遊びか考えるのが楽しい。遊びは文化を形成してきたが、この時代、遊びは実に豊か。
現代のゲーム機一色の遊びの貧しさを痛感する。
ブリューゲルは工作も遊びに描きこんでいる。『胡桃の風車』を少年が作っている光景だ。ぼくはこの胡桃の風車に興味を持ち
早速挑戦。胡桃の殻に窓を開けるのが大変。開け過ぎたり割れたり。回転棒に糸が絡んだり、切れたり……試行錯誤の末、
漸く完成した。
糸を巻き。ソロソロッと引き出すとリボンの羽根や回転盤がクルクル廻る。単純だが飽きない遊びだ。回り具合がよろしい。心が
温もるような玩具ができた。『子供の遊技』では少年が作っていたが、難しかろう。今の世は父さんが子供に作ってあげればよい。
作る過程を見せながら。
何が出来上がるか期待して食い入るようにみつめるだろう、その子どもは。父さんの手わざによる玩具……これ以上の
プレゼントはなかろう。
(Dec.13)
■薪を運び冬の準備



霜が降り枯れ草は地面に張り付くようにしんなり、冬景色の始まりだ。仕事の合間、(合間がほとんど無いのがいけない。
”合間”が心のゆとり、創作の源泉なのに)薪運びをする。今年のストーブの使い始めは11月の終わりだった。
アトリエの斜め前の雑木林が伐採された折り、シラカシ、アカガシの木を貰っておいた。チェーンソウでカット、積んで乾燥させたものを
部屋に運び込む。表の玄関に通ずる階段は傷みが激しく重たいものを持って上がることは危険。よって狭い階段を何回も運ぶ
羽目になった。腰が痛い。ストーブの前に坐る頃にはもう汗びっしょり。それでも、夜はトロトロ燃える火が暫し時間の存在さえも
忘れさせる特別の幸せをくれたのだった。
今日の薪運びの他の”戦果”。 板絵小品地塗り、タングラム塗装仕上げ、「ビー玉イライラタワー」試作。夜は遅くまで
酒を傍らに、新遊具(手、腕の機能リハビリに最適だろう。ボケ防止にも!)「ビー玉イライラタワー」で遊ぶ。
(Dec.8)
■二十四節気<大雪>、七十二候(六十一候.六十二候.六十三候)
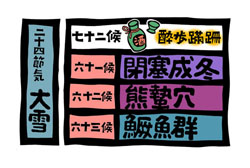 |
今年の大雪は12月7日 (冬至は12月22日) ・六十一候 (12月7日) ・そら さむく ふゆと なる 天が塞がり冬となる ・六十二候 (12月12日) ・くま あなに こもる 熊が穴に入って冬眠する ・六十三候 (12月17日) ・さけ うお むらがる 鮭が群れをなして朔上する |
初冬の日差し柔らかく、テニスコートに声はずむ。いつものように一人サーブ練習30分。その後2ゲーム。一勝一敗、まあ
勝負は二の次だけれど。
今年後半は漸く、本当に漸く、サーブがほんの少しだけど良くなってきたと思う。テニスに通う回数は半減したけど、
黙々とサーブを打ち込むことが楽しい。
テニスメイトのSさんが「茶の種を(コンクリートなどで)こすって、サルの顔を作ったことある?」と聞いた。鳩山の畑には静岡から
取り寄せた茶の木が20本ほど、”小さな茶畑”ほどに育っており、茶の種を採取している。が、種でサルの顔が出来るなんて
知らなかった。早速こすってみたが、要領を得ない。種のどの面をこすればいいのやら。色々やってみたが、サルには見えてこない。
次回のテニスで種を持参して聞いてこよう。その”お返しに”鬼ぐるみの冬芽が羊の顔そっくりなこと伝えてこよう。でも、Sさんのことだ、
知っていると答えるかも知れないなあ。
■相模女子大学「子ども教育学科」の認可おりる!
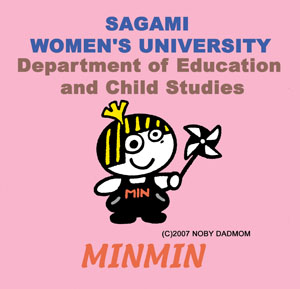
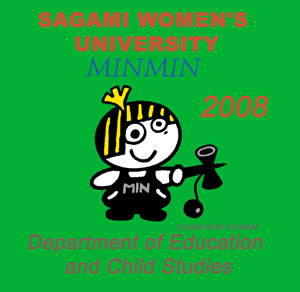
12月3日、相模女子大学の子ども教育学科の申請に対して認可がおりた旨の通知があった。
文部科学省、厚生労働省、の審査を受けるまでには様々な難題があり、担当した先生方には「お疲れさま」と
申したい。先ずはめでたし、めでたし。
来春4月から、ぼくは子ども教育学科で講義をすることになる。現在その準備に大わらわ。
時間との戦いだ。オリジナルキャラクターの入った学科パンフもでき、先生方も皆、大はりきりだ。
新校舎の建設も急ピッチ。美術図工室のある5階も姿を現し始めた。講義のシラバスを作らねばならない。
絵画造型表現、実践遊び学、楽習絵画造型など、コンテンツを決めるのが大変だ。想像=創造、手工、
答えのない遊び、自由な心の表現、などをテーマに一日中取り組んでいるが間に合うだろうか、心配だ。
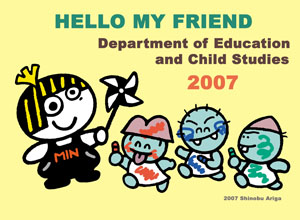
・認可前の制作で SAGAMI WOMENS UNIVERSITY と入っていない。
子ども教育学科オリジナルキャラクター ミンミンとらくがキッド
■クリスマスおめでとう! Feliz Natal! Maligayang Pasko! Joyeux Noel! Merry Christmas!
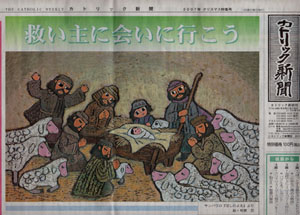
板絵絵本『ほしのよる』(サンパウロ刊)の掲載紙が送られたきた。子どもへのクリスマス特集版だ。
紙面は「12月の聖人から」「クリスマス豆知識」「小学生に薦める物語」「クリスマスリース型クッキー」「映画『マリア』の紹介」
などなど盛りだくさん。ぼくの絵本『ほしのよる』を一面に掲載してくれたことは嬉しいが、その場面は「馬小屋に羊飼いが祝福に
駆けつけたシーン」。
ベツレヘムの馬小屋のシーンには、生まれた赤ちゃんを抱くマリアと感謝するヨセフを描いたが、このシーンは敢えて羊飼い
のみにした。
祈る心はすべての者にあるということを強調したかったので。
板絵絵本『ほしのよる』を作って、3回目のクリスマスになる。
(Dec,6)
■『福笑い』の楽しさ。正月の遊びを再び!
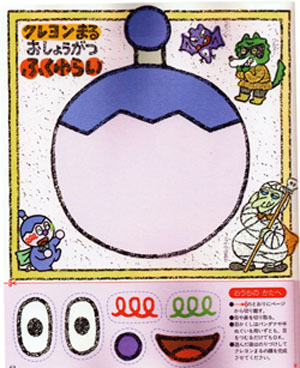
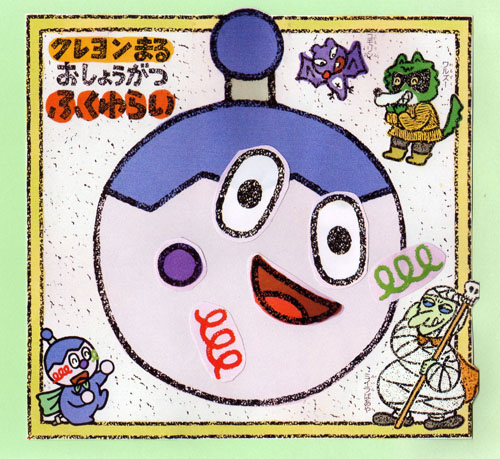
月刊「おひさま」も、早新年号が出た。ミラクルクレヨンのクレヨンまる、今回は福笑いを取り上げた。140回の連載で紙面を切って
遊ばせるのを考えたのは初めてのこと。遊びは見ているだけではつまらない。どうしても”体験”させたくて。
昨日の朝日新聞のbe betweenのテーマは「お正月」だった。現在と子ども時代の正月の違いについて、読者にアンケート。
2503人が答えている。初詣、年賀状を書く、スポーツ中継を見る、家でゴロ寝、年始回り、着物を着る……。いずれも予想できる数字だ。
ぼくの興味は遊び。
・かるた遊び(現在70 子ども時代856) ・たこ揚げ(現在13 子ども時代665) ・こま回し(現在6 子ども時代283)
・はねつき (現在5 子ども時代448)………。
「ふくわらい」に至ってはアンケートの設問にさえない。こんなに笑いを誘う楽しい遊びが消えるのは寂しいではないか。家族が、
大人も子どもも上手い下手関係なく大笑いする……!家族の幸せな光景が消えたということか。
(Dec.2)
■オープンキャンパスのテーマは「”こんなこいるかな世代”の学生に期待する」
12月1日は相模女子大学のオープンキャンパス。ぼくの模擬授業はK教授とのコラボレーション。
「こんなこいるかな」の秘密を語る。
「知育偏重から慈愛の子育てへ」のプリントを配布する予定だ。
開講13時30分~14時20分。1115教室。興味のある方はどうぞ。無料
(Dec. 1)
| 11月のアトリエだより |
■色々物づくりに忙しい一日、マテバシイのどんぐりでクッキーを焼く
ああ、何て楽しいんだろう。物を作ることは。仕事を中断し、ドングリクッキー作りに挑戦。熱湯を通し天日干ししておいた
マテバシイの実を殻を取りコーヒーミルにかけて粉砕。ほどなく断念!豆が堅くミルが故障。長年使ってきたミルはモーターが
不調気味だったが、とうとう動かなくなってしまった。
少しだけ出来た粗い粉を、ペッパーミル(胡椒挽き)にかけさらに細かくする。濃いこげ茶色の粉が杯3杯ほどたまった。
小麦粉を用意しておらず、グリッシーニをパウダーにしたもの(これは故障する前にコーヒーミルにかけて作っておいた)、
それに牛乳、バターをごく少量混ぜた。
耳たぶの柔らかさに練り、ラップし電子オーブンへ。3分後、バターを引き加熱したフライパンへ。大きさ6センチ、厚さ1センチの
クッキーが3枚焼けた。この手間が楽しい!黒色の”パン状の食べ物”に見惚れる。「マテバシイのどんぐり」は素朴な古代食。
木の実のクッキー、肝心な味は………?
口に含み全神経を集中……ナッツだ!ナッツの風味だ!凄い!………と思ったとたん、舌にこびりつく渋!アク抜きを怠ったからだった!
大失敗!でも、ドングリクッキーを作る自信はついた。アクさえ抜けば、美味しいクッキーが出来る、きっと出来るだろう。
30年前に買った、自宅の納戸に眠っている動輪式大型コーヒーミル(手動)を持ってこよう。それで、マテバシイをゴリゴリ、ガリガリ
粉砕しよう。首尾よく行きますか、後日本欄で……。
(Nov.29)
■クリスマスの季節

・絵本「ほしのよる」ベツレヘムの馬小屋
出版社から問い合わせがあった。
『新潟の聖書教会で子どもクリスマス会を行う。子どもたちが、それぞれの役の衣装を着て
演じる。場面説明としてナレーションと合せてスライドを映したい。「ほしのよる」の数場面を
使わせて欲しい』と。
快諾。子ども達の輝く瞳を想像する。ぼくも何十年も前、幼稚園でクリスマス会をしたことを
覚えている。幸せな記憶は大人になっても消えない宝物だ。
サンタクロースからのプレゼントは嬉しいものだけど、劇を演じることが何よりの思い出になろう。
「ほしのよる」の板絵が、子ども達の頭の隅っこに残るといいなあ。
(Nov,29)
■深秋の散策……武相荘(ブアイソウ)へ
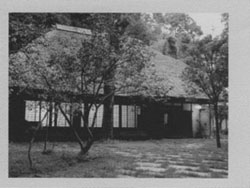

大学の人間社会学科で「自己表現としての絵本制作」の講座を持っているが、いつも資料や絵本の荷物が多くて大変だ。
先週の「製本演習」は学生が使う材料を持参したので特に重たく、手が抜けそうなくらい疲れた。今日は「キャラクター設定シート」の
返却日で、絵本鑑賞もなく荷物は軽く大助かり。足取り軽く晩秋の林に足をのばした。
小田急線鶴川駅で下車。以前から行ってみたいと思っていた旧白州邸、武相荘を訪ねた。日本国憲法の成立に深く
かかわったという白州次郎(昨年NHKの「そのとき歴史は動いた」で取り上げられた)は1943年に鶴川に移り住んだ。
武相荘の名の由来は武蔵の国と相模の国にまたがることと、”無愛想”からの着想だという。
坂道を上り詰めたところに長屋門があった。門をくぐると、眼前に茅葺の一軒家。ぼくが育った信州で子供の頃みた風景、
懐かしい田舎の家だ。茅の屋根には寿の文字が刻まれていた。茅葺職人のシャレだろう。
母屋にはダイニング(土間)があり、洋風の食卓(料理は当時は珍しかったであろうパエーリア)が展示されていた。和室
には囲炉裏が切ってあった。好物のマツタケを焼いて食べる様子が伺えた。季節ごとに展示は変わるという。晩秋の各部屋を
飾るアクセントは篭一杯のホウズキだった。薄暗い中に一際朱色が鮮やかだった。書棚には小林秀雄らの本がぎっしり。何者にも
邪魔されない静かな時間が流れる、ここは正に別天地だった。
裏には散策路があり、「鈴鹿峠」の道しるべも。来館者は展示室や売店や喫茶室にたむろし、誰も来ない。ぼくはここで、
マテバシイのドングリを拾った。拾ったというより、あたり一面ドングリを撒き散らしたような林だ、”敷き詰められた”ドングリを
かき集めたのだった。ドングリ拾いは珍しいことではないが、この豊作ぶりには目を見張った。
もう少し早かったら良かったのだろう。ドングリから根が出掛かっているものが多かった。それでも、選んで大粒のドングリを
持てるだけ拾い集めた。袋など所持しておらず、ハンカチを結んで納め嬉々として帰った。
さあ、これからだ。目的はドングリ料理。先ず30分ゆでた。それから天日干し……。楽しみは続く……。(以下後日掲載)
(Nov.28)
■秋日和。仕事の手を休めて庭に出る(鳩山)


昨日より気温が4~5度は高く温かい。朝からアトリエに入り板絵小品制作に没頭。
鳥の声が響くほかは、風の音もなく静寂そのもの。気がつけば昼飯を食べていなかった。
柔らかな日差しに誘われ外に出てパンをかじる。小鳥たちと、今日は姿を見せないが、目の前の
おしゃもじ山からやって来るキジの家族(5羽)のために、パンくずを残しておく。
ドッグローズの実が揺れている。ドッグローズ(DOGROSE/野生バラ)は花が咲いた後も、
ローズヒップ(実)ティーとして楽しませてくれる。ブナが黄葉し始めた。(ユズの写真の左側)枯れ葉色の
畑に、ユズの黄色が色鮮やかだ。今年もたくさん実をつけた。肥料もやらないのに……、嬉しいしありがたい。
手の届かぬ柿の木の梢に柿が幾つも残っている。ナツメの実も採取できぬまま枝先で萎んでいる。
長閑な秋日和だが、穏やかな秋の昼下がりも、おしゃもじ山が影を落とす頃には急に冷え込んで来る。4時半には
もう薄闇だ。
昨日今日、秋の終わりと冬の入り口を感じ、あと一月ちょっととなった今年に改めて想いを巡らした。
(Nov,26)
■牛乳パックで作る絵変わりキューブ (その2)



(その1の続き)
写真は新たに製作した絵変わりキューブ。今回はパックを丸ごと使用。補強のためパックを差し込んであるから、
2個つくるのに、パックを8個使用。パックの周りには和紙を貼り付けた。(張子状)軽くて丈夫な遊具が出来た。
各長方体は三段に別れ帯紙でつながっている。キューブを回転させればキャラクターが次々に姿を現す仕組み。
それぞれに6体を貼りつけていったが、一面が白いままなのだ。不思議!!!!いくら考えても分からない。
白いままにして置く訳にもいかず、「こんなこいるかな」の顔を一面に張ることにした。(中央の写真)
パタパタ、音を立ててキューブを折る。絵が瞬時に変わっていく。絵は色だけでも、花でも、動物でも何でもよい。
これはかなり面白い。
キューブからは、コロン、コロリ、コロと柔らかな音が響いてくる。中に実を抜いたクルミの殻を入れてあるのだ。
温かい懐かしい何ともいえぬ”嬉しくなる”音だ。
(Nov.25)
■牛乳パックで作る絵変わりキューブ (その1)


この絵変わりキューブには牛乳パックが8個使用されている。キューブは4個だが、それぞれパック(牛乳パックは
短辺7センチ)の下部7センチでカットしたものを補強のために差し込んである。キューブとキューブの間は接続紙により
つなげられている。これでパタパタと、キューブを折るごとに「こんなこいるかな」のキャラクターが6人の顔が、登場する。
正方体には無論6面ある。二組作れば「こんなこいるかな」の12人全キャラクターが登場する。……はずであった。が、
理解し兼ねることに相成ったのだ。仕組みは違うが、牛乳パックを使って新たな絵変わりキューブを製作したら、その作品では
6人のはずが、7人に増えていたから不思議。ぼくは数学が苦手だから深く考えはしないが未だ訳が分からないでいる。
以下次回掲載……。
(Nov.24)
■二十四節気<小雪>、七十二候(五十八候.五十九候.六十候)
先日は 鳩山でクヌギのドングリを拾う。これはクラフトに使う。幼稚園の道端でコナラ、アラカシの実を拾う。
大量に集めた大粒のマテバシイは美味しいからアクを抜いて食用にする。このアク抜きが手間が掛かる。
ドングリせんべい、ドングリクッキーの出来栄えは後日アトリエ便りで!
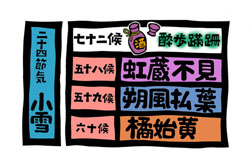 |
今年の小雪は11月23日 (大雪は12月7日) ・五十八候 (11月23日) ・にじ かくれて みえず 虹が見えなくなる ・五十九候 (11月28日) ・きたかぜ このはを はらう 北風が木の葉を吹き払うようになる ・六十候 (12月2日) ・たちばな はじめて きばむ 橘の葉が黄葉し始める |
■クルミのヨット


20年ほど前、「スカンジナビアのデザイン」というアートアニュアルで、クルミのクラフトを見た記憶がある。
クルミの殻で作られたヨット。帆は純白の厚紙。マストはマッチ棒で、マッチの先の赤いふくらみが白い帆にアクセントに
なっていた。シンプルで美しい。幾つか作ってモビールにしたらいいな……、などと思っていた。
ぼくは酒のつまみにクルミを割って食べるのが好きだが、普段は鉄製のナッツクラッシャーを用いている(鋳物で適度な重さ、
造型デザインも素晴らしい)。これだと、殻は簡単に割れ中味が取り出しやすい。しかしながら、殻は粉々になってしまう。
二つに殻をきれいに割るなどということは至難。
近頃袋入りのクルミはには、ご丁寧にもくるみ割りの金属片が入っている。この金属片をくるみの下部(尻)の穴にあて、
斜めに力を加えると、バリッと、くるみは縦の線に沿って二つに割れる。これだと殻はきれい。貝合せよろしく二つがピタリと
くっつく。
そこで、前述の「スカンジナビアのデザイン」よろしく、ヨットを製作。あいにくマッチ棒がなく、楊枝で代用した。モビールとなると、
バランスが大事。幾つか作って風と遊びたい。
■クルミの風車
クルミといえば、「クルミの風車」をご存知だろうか?ブリューゲル1560年作『子どもの遊技』と題された絵に載っている遊びだ。
『子どもの遊技』は91種類の子どもの遊びが描かれた有名な絵だが、何と250人もの子どもが遊んでいる。
其の中の一つ。ぼくはこの「クルミの風車」を再現してみようと思い立った。ため息が出るくらい昔の古い遊びを試してみたい。
果たしてどんな物……?近々公開。乞うご期待!
(Nov.19)
■キジのお父さんはいずこ?

二週間ぶりに訪れた鳩山。周りの雑草を抜き手をかけて育てているサトウカエデ(メープル)の紅葉を楽しみに
していたが、残念なことにサトウカエデは葉を落としてしまっていた。10本植えたブナは10年目の秋をを迎えたが、
黄葉はまだ。黄葉から茶褐色になり強い北風に吹き飛ばされ舞い上がる様は圧巻。ぼくは空からヒラヒラ、ゆっくり舞い
落ちる枯れ葉を目で追うのが好きで、飽きもせず眺めていることがある。今日は風もなく、その楽しみは味わえない。
庭にはイタリアンパイン(松の一種)を5本、円周上に植えたコーナーがある。其のサークルで何かが動いた。目を凝らすと
何羽かいる。キジだ!キジの親子。お母さんと子ども4羽。丸々太っている。ここなら安全と、ゆっくり何かを啄んでいる。
お父さんはどうしたのだろう。バサバサバサッ!キジが飛び立った。黒いノラ猫の出現が静かな平和のひと時を壊した。
翌朝、イタリアンパインのサークルのちょっと下、オリーブの植わる斜面にあのキジの親子が遊びに来ていた。やはり
お父さん見えない。お父さんはどうしたんだろう?心配になった。お母さんと4羽はとても元気。
後で見たらイタリアンサークルにおいたパンはきれいになくなっていた。キジの親子は庭で遊ぶと、畑の前にあるおしゃもじ山に
帰っていく。竹薮がキジの住処だが、今度はお父さんキジも揃って遊びに来てほしい。
(Nov.18)
■90分の愉楽
大学でのこと。授業終わり間近、F教授から呼び出しがあった。
研究室行くと、F先生、Y先生、K先生が昼食お預けで待っていて下さった。
テーブルには出前のカレーランチ(ぼくの分も)と、新設される「子ども教育学科」のパンフレットの校正紙が置かれていた。
表紙はぼくが作製した大学の学科オリジナルキャラクター”ミンミンン”ではなく、”こんなこいるかな”12体集合の
イラストだった。 今年度のみの使用という。ぼくは”こんなこいるかな”も良いが、”ミンミン”を育てたい。
キャラクターは描けば終わりというものではなく、いかに手をかけ育てるかが肝要。子育てと違わない。
そう思いつつもぼくはキャラクター完成以降、周辺キャラクター設定や大事なストーリー展開を怠っている。
校正紙を見て反省。自分の怠慢を責める。
帰りは生田駅での人身事故のせいで小田急線は前面ストップ。
玉川学園駅で度々、「新宿に向かわれる方は振り替え輸送します」の車内アナウンスを耳にした。
が、疲れた体を動かす気もなく、ひとり座席に座っていた。待つこと90分。電車はようやく動いた。
せっかちなぼくが、疲労感、億劫だからとはいえ、じっと車内に留まっておれたのは、読みかけの本があったから。
森洋子著、遊びの図像学『ブリューゲルの子供の遊戯』。ブリューゲルの絵「子供の遊戯」に描かれた91種類の遊び
(描かれた子供は250人以上)の、作品成立の背景を探り分析した労作。見ごたえのある、読み応えのある一冊だ。
ぼくは子供達の動作を一つ一つ確かめながら遊びを考えていた。
重い本をバッグに忍ばせていて良かったと、今日ほど思ったことはない。
(Nov,14)
■第33回現代童画会展終わる


現代童画展および特別展示「セルビアのナイーブアート展」は好評裏に終了した。一日の入場者が1000名を
超えた日もあった。童画展始まって以来のことだ。この催しのために相当の時間を割いたが、盛況に疲れが
吹き飛ぶようで、実現できたことを今、関係者各位に改めて感謝する。現代童画会ではセルビア側と交渉窓口に
なったK氏の働きが大きい。彼の大奮闘によって為しえたといっても過言ではない。仕事を投げ打っての働きぶりに
満腔から謝意を表したい。
(Nov.14)
■『こんなこいるかな』絵変わりキューブ作製

来る12月1日、大学の公開講座は「こんなこいるかな」がテーマ。K教授との対談が予定されていたが、F教授に
代わる模様。K教授は自分の子育てにも、大学の授業にも「こんなこいるかな」を使って来たというだけあって、”通”だ。
「K先生,対談は”デスマッチ”と思い楽しみにしておりましたが残念です」とメールを打つと、「今回はご一緒できないけれど
次回、必ずいたしましょう。”リベンジ”乞うご期待!”」との返信あり。
講座にはパワーポイントを使うか未定だが、「こんなこ」のイラスト入りの絵変わりキューブを作った。牛乳パックを8個
使用(立方体4個分)。他にパック4個使用のものも。やだもん、もぐもぐ、ぽいっと、ぶるる、ぽっけ、たずら、6人の顔が
パタパタと変わる玩具だ。もちろん作り方も教える。
工作って、何で、こう楽しいんだろう。面白さを伝えたい。プリント作りにも力が入った。
(Nov.12)
■伝承玩具『板がえし』を製作
『板返し』は変わり屏風、パタパタ、でんぐり等とも呼ばれた伝承玩具。江戸時代からあった。幾枚かの薄い木片か、
厚ボールを帯状の紙で連ねたもので、一番上の木片(カード)を親指と中指ではさみ持つと、他の木片がパタパタと
音を立てて落ちて行く。さらに、パタパタパタ……。列ごとに色を変えておけば視覚効果絶大。子どもは目を見張る。
シンプルで面白い。昔は観光地や駄菓子屋で売られていたが、今では見かけることも無い。
作り方はそう簡単ではない。いえ、仕組みは単純で薄板に帯状の繋ぎ紙を貼り付けていく(板の枚数分、繰り返し)
だけなのだが、工作本の”手引き”の図解が分かりずらく、失敗を繰り返した。繋ぎ紙の貼り方を間違えれば”パタパタパタ”
とはならない。
木片(ぼくは7×10㎝のシナベニア)と、子どもたちにも出来るようにと、牛乳パック(7×9㎝、1000mlパック4本)で
製作。試作を繰り返し、製作手順のプリントも書いた。「これなら大丈夫」となるまで一日かかった。それでも、プリントを
見ただけでは簡単には飲み込めないかもしれない。この手の”図解”は難しい。
外は雨。一日雨だった。めっきり寒くなった。秋が足早に過ぎていく。
(Nov.10)
■二十四節気<立冬>、七十二候(五十五候.五十六候.五十七候)
毎年降るように落ちる銀杏の恵みが当たり前のように思っていたキャンパスのイチョウが、今年は実をつけない。木々を
見上げると僅か1~2本に申し訳程度に実はなっている。いつもなら、舗道に落ち潰され嫌われるくらいに異臭を放って
いる頃なのに……。大学の6階建ての新校舎建設が原因か、剪定が深すぎたせいか……。
自宅近くのハゼの木も紅葉はまだまだ。このところ鳩山のアトリエにもご無沙汰している。現代童画展が終わるまでは
動けないが、木々の紅葉、黄葉が気にかかる。野山が色づく前には行きたいものだ。
今日8日は立冬。 ”立冬”を思わせぬ暖かさだ。久しぶりに午前中テニス。猛暑の頃の閑散がうそのよう。ハードも
オムニコートも混んでいた。サーブ練習(叩き込みが、ぼくのストレス解消)の後、2ゲーム。
4-6、2-6の快勝に気を良くして、上野(都美術館・現代童画展)に向かう。展覧会期間中は何かと忙しく仕事にならない。
いつものことながら。
(Nov.8)
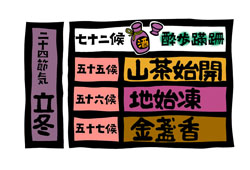 |
今年の立冬は11月8日 (小雪は11月23日) ・五十五候 (11月8日) ・つばき ひらき はじめる 山茶花の花が咲き始める ・五十六候 (11月13日) ・ち はじめて こおる 大地が凍り始める ・五十七候 (11月18日) ・きんせんか こうばし 水仙の花が咲き始める |
■ホピ族の精霊たち 『カチーナ人形展』

・FEEL THE SPILIT OF HOPI KACHNA DOLLS
カチーナ人形は1870年代に、国外に知られた。プリミティブな魅力が魅了する
ホピ族はアリゾナ州のネイティブアメリカン。(グランドキャニオンの東160キロの砂漠に住む)ホピ(HOPI)は
”平和に満ちた人々”という意味だ。ホピ族は万物に精霊が宿っていると考え、それをカチーナと呼んだ。カチーナは
ホピ族の特別な守り手で、子ども(とくに女の子)に玩具として与える慣わしがあるが、精神世界や儀式を教える教材的
役割を持っていたようだ。
カチーナドールは20~30㎝、コットンウッド(ポプラ)の木を彫って作るり鮮やかな彩色が施されている。羽や布の装飾が
施されているものもある。道化のカチーナ、黄色いガラガラヘビ、アナグマ、魚捕りもカチーナ、カクタス(サボテン)、フクロウ、
カエル、トンボ、トカゲ、鬼の母、牛、太陽のカチーナ……何と300種類ものキャラクターがあるという。(展示は3~40体)
造型はシンプル、表情は豊かでみな大らか。ユーモアが感じられ展示は楽しめたが、何か物足らない。カチーナドール製作者
(実演も見た)のマニュエル・シャバリエJr.の作品が手垢一つない”展示用”だったことだ。古い時代の塗料が剥げ落ち、足や
口ばしが欠けたカチーナでよかったのに。
ぼくは大分前、猪熊弦一郎の個展でカチーナドールを知った。小さなカチーナドールのドローイングを覚えている。それは
素朴で愛らしくヒューマンであった。
感激したのはフロンティア写真家、エドワード・カーチスの1901から10年間費やして撮った「北アメリカインディアン」の
写真と映像記録。部族の生活、伝説、文化、宗教儀式などが、人間の素晴らしさを改めて想起させたのだった。ポピの
子ども達は男の子も女の子も小さいうちからよく働く。粘土と石で家の壁を直すのと料理は女の子。男の子は畑仕事。
おかしいのは織物と縫いは男の子の役目だという。
遊びも盛んにする。コーンの穂に羽根をつけた矢で遊ぶ的当て。アーチェリー、鹿の皮で作ったボールでホッケー。好きなだけ
遊ぶんだと言う。時間の制限なく月が出ている限り、遊びは夜の闇が訪れるまで続く。翌日学校に誰もいかなくても平気。
叱られないのだという。嘘のような大らかさ、うらやましいような話だ。
カチーナドールの説明文にはピカソも興味を示したとあった。確かに魅力はある。時代の変化に寄り添うことはない。
グローバリゼーション、商業主義から守らねばならぬものもあると思う。
本展はスミソニアン美術館が協力し、世田谷と川崎の教育委員会が後援している。この催事が一箇所で終わるのは惜しい。
多くの人々に見てもらいたいイベントだと思う。
人間本来の生き方、失われた、忘れた、大切なものを、ホピ族の暮らしの中に見つけるだろう。胸に迫りくるものが、
きっとあるとぼくは思う。
■『第33回現代童画展』および特別展示『セルビアナイーブアート展』始まる
初日、東京都美術館開館してまもなく、セルビアの関係者が会場へ。昼食もとらず熱心に展示をみて廻られた。
通訳がセルビア語を英語にして伝えるものの、分かりかねること多く残念だった。それでも一作一作丁寧に語ってくれ、
写真をとり和やかな雰囲気で親交を結んだ。その後、セルビア大使がお見えになり会場を案内。大使館の書記官は
日本語が堪能で大助かり。大使もセルビアの作品を丹念にご覧になり、現代童画会メンバーの作品も時間をかけ
感想を述べられながら、会場をゆっくり廻られた。
夜は大使館でオープニングパーティー。現代童画会からは会長ご夫妻はじめ15名参加。セルビア交流協会理事の
コレクション、旧ユーゴスラビア時代のナイーブアートが飾られた部屋で楽しいひと時を過ごした。
画家ヤン・グロージック氏、エトノセンター代表、パベル・バプカ氏とも顔を合わすのは3回目に
なるも、両氏はセルビア語、ぼくの拙い英語では、なかなか気持ちが伝わらず、苛立ってしまった。
5日午後2時30分より、東京都美術館講堂で、ヤン・グロージック氏、パベル・バプカ氏の「セルビアの
ナイーブアート」について講演会が開かれる。講演は講堂を出て、会場で作品を前にしても話されるということで、
楽しみなことである。興味のある方はどうぞご参加ください。入場無料
(Nov.2)
■セルビアナイーブアート展の作品陳列終える
セルビアから届いた油彩55点、ドローイング11点を美術館の可動壁を広げ全点の展示を無事終了。
メインは、ヤン・グロージックの「コバチッツア村190年を祝う」80号の大作。
これはあらゆる職業をもうらした民族色あふれる見ごたえある作品だ。中にペインターも描かれているが、
その「画家」はヤン・グロージックの尊敬するセルビアを代表するマルティン・ヨナーシュだ。
マルティン・ヨナーシュは本展では馬のドローイングを出展している。馬のひずめ、人間の手足が大きく
デフォルメされているユニークな線描。ヤン・グロージックの描く画家、マルティン・ヨナーシュの
イーゼルの絵も手足が大きい。細やかな描写を見つけて楽しんでいただきたい。
なおマルティン・ヨナーシュのイーゼルの脇に立つ若い絵描きがヤン・グロージックである。
明日2日オープニング。日本セルビア交流協会の方々、エトノセンター代表パベル・バプカ氏、
ヤン・グロージック氏等が会場に見える。セルビア大使もおいでになる。展示に疲れた、などと言っては
おれない。素朴で温かい。民族の生活の謡……。素晴らしい展覧会、是非ともご覧になっていただきたい。
・「現代童画展」内、特別展示:セルビアのナイーヴアート展 東京都美術館 11.2(金)~12(月)迄
(Nov,1)
| 10 月のアトリエだより |
■エンジュの莢豆は翡翠の連珠



二子玉川からバスで渋谷に。国道246号線は渋滞。終点少し前の停留所で降りる。旧山手通りを
鉢山町を通って代官山、猿楽町までポカポカ陽気に上着を脱いで歩いた。道の両側の街路樹はエンジュ。
ついこの前歩いたときには白色の蝶形花をつけていたのに、もう莢豆を枝から垂らしている。おびただしい
薄緑色はまさに”翡翠の連珠”だ。
西郷山公園近くに先日の台風で幹を折られたエンジュがあった。道行く人は見向きもせず、莢豆は踏み
潰されていく。ぼくは道野辺に寄せ、一枝ちぎって仕事場持ち帰った。
鳩山のアトリエの庭にも数年前エンジュを植えたが、樹高3メートルを超えたのに、まだ花が咲かず、
よって莢豆は望めない。エンジュは中国原産のマメ科の高木。花、樹皮、果実とも薬効があるという。
漢方として用いるつもりはないけれど、花を見たい。莢豆を風に泳がせたい。秋の陽に映える
翡翠の連珠を身近で見たい。
■糸巻きが手に入り、戦車を作る
紙製やプラスチックに替わり姿をけした木製の糸巻きが何個か手に入り、少年時代遊んだ
『糸巻き戦車』を作った。ローソク(輪切りにしてワッシャーに使う)は、ほんのちょっとしかいらないのに
ほしいサイズのものは15本入りだ。それでも、どうしても作りたくて500円の出費。
走りが良い。トコトコ、ゆっくり止まりそうになりながら走る。超スロースピードだ。もう止まる、
もうだめだ、と思うと、またコロ、コロッと動く。じれったいほど時間をかけて4メートルは進む。モーターや
エンジンやICを使った精密な遊具にない手わざの面白み、温かさがある。今の子に伝えたいと思う。
作るのも、走らすのも、遊ぶのも、工夫や想像(ごっこ遊び)の余地のある伝承遊びだから。
(OCT,31)
■二十四節気<霜降>、七十二候(五十二候.五十三候.五十四候)
台風20号は上陸せずに過ぎ、今日は秋晴れ。仕事場に向かう足取りも軽い。天気晴朗気分よく
ちょっと寄り道。カチナドール展をのぞこうと思う。アメリカ・アリゾナ州ポピ族の精霊人形は、以前猪熊弦一郎の
個展で製作されたものを見たことがある。素朴で愛らしい造型だったが、今回のパンフの写真では極彩色。
はたして、精霊の姿は……?また後日。
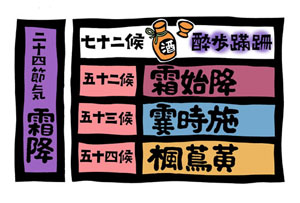 |
今年の霜降は10月24日 (立冬は11月8日) ・五十二候 (10月24日) ・しも はじめて ふる 霜が降り始める ・五十三候 (10月29日) ・こさめ ときどき ふる 時雨が降るようになる ・五十四候 (11月3日) ・もみじ つた きばむ 紅葉や蔦の葉が黄ばむ |
■図書館で雨宿り。帰り道、肩に荷物重く……
土曜日の授業は始めて。今日は朝から雨で欠席が目立った。他の科目はないのだろうか、キャンパスに学生の
姿が見えない。銀杏並木の水溜りに銀杏がおちている。例年より十分の一くらいの実りだが、強い風に落ち始めた。
台風20号、午後3時頃は八丈島を北東に進んでいたというが、大学のある相模大野はかなり激しい雨風だった。
授業終了後図書館に”避難”する。見ようと思っていた「文字の誕生と印刷文化の黎明」と題した展示の最終日であった。
展示物はインキュナプラ(15世紀中に金属活字を用いて印刷されたもの)の一つ、グーテンベルク聖書(グーテンベルク
聖書は殆どのページが42行組みであることから、42行聖書とよばれる)。もう一点は、百万塔陀羅尼経(陀羅尼を印刷
したものを百万基の小塔に納め法隆寺はじめ十大寺に分奉)この百万塔陀羅尼経は制作された年代が明確な(718~770)
世界最古の印刷物。たて数センチの薄紙にかかれた帯状のもの、巻いて収納したのだろう。サンスクリット語の陀羅尼の
印刷方法は木版か銅版か未だ解明されていない。
インキュナプラは複製版、百万塔陀羅尼経もレプリカであり、(本物の百万塔陀羅尼経と小塔は昨年3月、静嘉堂文庫
『中国の版本-宋代から清代まで』展でみた)展示ブースも小さかったが、ぼくには興味ある展示物であった。
図書館内に人影が感じられない。雨宿りのつもりが結構長居をしてしまった。芸術、社会関係の本を物音一つしない広い
空間を独り占めして優雅な時間を過ごさせてもらった。これも雨のおかげか。『木あそび』『ラスコーの壁画』『感性の思考』など
借り出して館を出て「しまった!」。
雨は収まるどころか、さらに激しくなっていた。横なぐりに傘も役にたたず、ヤケッパチになってエッチラオッチラ帰って行った。
今日は学生の課題制作の絵本も20冊ほど持っていたから、バッグの重かったこと!渋谷の仕事場に帰り着いたときには
全身ずぶぬれ、体は冷え切っていた。
(Oct,27)
■10月24日は二十四節気の「霜降」です。
二十四節気 五十二候「霜始降」、五十三候「霰時施」、五十四候「楓蔦黄」のUP遅れております。近日に……。
■現代童画展審査終了……上野でナナカマドの実に見とれる
二日間、上野の東京都美術館で第33回現代童画展の審査を行った。美術館の地下3階にこもり、公募作品と
会友、会員の作品数百点をみた。今年度は公募作品が充実していたものの、会友は質、量とも低調。会員は
安定してはいたが、描きたい世界の追求があいまいなまま、技術に全精力を傾注したような作品が多く見られた。
ナイーブアートは心の表現だ。表現したい世界に耽溺、モチーフにこだわる姿勢が大事だ。止むに止まれぬ思い、
心から突き上げてくるメッセージを、画布に話して欲しかった。
上野公園内で植木屋さんが苗木を売っていた。ぼくの目はナナカマドの赤い実にひきつけられた。3年前、ぼくは
ナナカマドを2本鳩山のアトリエの庭に植えた。一本は枯れた。一本は根付きはしたものの実を付けても赤くなる前に
すべて落ちてしまう。小鳥のレストランを開きたい夢が果たせずにいる。今年更に2本を植えたが未だ幼木。実を付ける
までには至らない。ナナカマドの赤い実と燃えるような紅葉を何としても身近で見たい。
植木屋さんのナナカマドは幹が太く枝ぶりもよく買いたかったが、コモでくるまれた根土の重さも相当で
断念した。赤いナナカマドの実は目に染みつき、帰り道は審査会で見た絵の数々はすっかり頭から消えていた。
(Oct,24)
■秋、木の実三題

1、クヌギ 公民館の林でクヌギのドングリを拾う。地面を敷き詰めるほどの量が落ちている。が、拾いにくるのが
遅かった。変色やひびが入ったものや虫食いが多い。それでも200粒ほどの収穫。昨年、一昨年拾ったドングリを
撒きいくつかは芽をだした。育つのが楽しみだ。丸くて大きなこのドングリはコマにするのが最適。
大学の「実践遊び学」の授業でも使えそうだ。
2、栗 今年は栗の出来が悪かった。例年の三分の一以下だ。剥くのに手間が掛かるのと店で安価に売って
いたりで、知り合いに送っても以前ほど人気がない。思い切って枯れそうな一番古い栗の木から切ろうと思う。
これまで、大きくて甘い栗どっさりと、ありがとう……、感謝の心。
3、大学のキャンパスのイチョウ 今年は何だかおかしい。銀杏が落ちないのだ。毎年鈴なりなのに、梢を見上げても
実はまばら!新校舎建設のダメージか、剪定が深すぎたのか、ぼくには分からない。が、毎年楽しみな銀杏拾いが
今年は出来ないとなると、寂しい。
(Oct。20)
■「セルビアのナイーブアート展」開催まで十日余り。漸く作品と対面。
同展は”第33回現代童画展の特別展示”として催行される。
・会期:11月2日(金)~12日(月) 午前9時~午後4時30分
・会場:東京都美術館(上野公園) 詳細は「アトリエ便り」10月6日をご覧ください。
昨日、セルビアから送られたきた作品をチエックしに現代童画会常任委員の小松氏と大使館に出向いた。
ここに至るまで、開催が危ぶまれるような難題山積。漸く本当にようやく、待ちに待った作品との対面だ。
セルビア交流協会の濱田、猪谷両氏立会いの下開梱する。
金属のコンテナを開錠するぼくの手は安堵と期待で震えた。
作品はタブロー55点、ドローイング11点、合計66点。タブローは民族色が鮮明。
農村の情景を描いたものが多く、生活感が溢れていた。
目玉は現代童画展のポスターにも掲載した画家、イワン・グロジックの「コバチッツァの100年」。
これは、あらゆる職業の人々を画面すみずみまでギッシリ描いた80号の大作。
30号の作品とともに新たに額装して展示する。
同氏は来日し、都美術館で講演も予定されている。(11月5日14時30分~16時)
打ち合わせ時にはなかった組み木絵やマルティン・ヨナーシュの躍動感溢れる馬のドローイングも
含まれており、全点展示することに決定した。
第33回現代童画展の特別展示「セルビアのナイーブ展」は見ごたえのある展覧会になるだろう。
日ごろ、あまり目にすることのないセルビアの素朴画家の絵をどうかご高覧くだされたし。
(Oct,19)
3年前から絵本の読み聞かせに関するアンケート調査を行ってきたが、それに加え、今年は人間社会学科の
女子学生に「幼少女期の遊び」調査を行った。来春より新設される子ども教育学科の「実践遊び学」の参考にする
ためでもある。
おみせやさんごっこ、石けり、かくれんぼ、ゴムとび……それに、お手玉、おはじき、あやとり、折り紙、コマ回し、
竹とんぼ、だるま落としなどの伝承遊び、玩具なども含め百近い遊びをあげ、遊んだことのあるものに丸をつけて
もらった。回答書にはよく遊んだ遊びも書き入れる欄も。
多くの学生がローセキ、コリントゲーム、リリアンを知らなかった。そこで、リリアン編み機を製作、学生に見せることにした。
駄菓子屋(余りみかけなくなったが)にはプラスティックのものが200円程度で売られているが、昔は木製だった。
姉が日がな黙々と編んでいたのを覚えている。校庭の隅でも二人三人とリリアンを編む姿があった。編んだリリアンを
何に使ったのかは不明だが、ひたすら編み続けていたのは確かだ。
今、リリアン編み機に糸を通し編んでみて、その大変さがわかった。五本の釘にかけたリリアンを鈎針で一つずつ
掬っていくのだが手間が掛かること!リリアンの糸が”紐”になるまでにはたいそうな時間がかかる、ため息が出そうだ。
それを毎日のように飽きずにやっていた少女たちは一体……。現代の遊びからリリアンは消えたが、手わざ、丹念さ、
持続力という手工の心はリリアンには詰まっている。復活してもよい遊びの一つだと思う。
(Oct,14)
■『慈(其ノ壱)清流遊楽』 『慈(其ノ弐)灯火静穏』 2作品額装

作品が漸く仕上がった。大学の秋期授業がはじまり、このところアトリエに入る時間がますますコマ切れになっていた。
今日秋晴れ。マットバーニッシュ(仕上げ剤)を塗布、乾くのを待って額装する。日が短くなった。「防災鳩山」のスピーカーから
流れる夕焼け小焼けのメロディーと子どもらに帰宅を促すメッセージが聞こえる頃にはあたりはもう暗い。
完成作を写真にとり一息。運送業者に出す前までの暫くが、ぼくにとっての至福の時。絵を前に酒を酌む。
この時の酒より美味い酒を知らぬ。酒量捗ること、むべなるかな。窓から鼻腔をくすぐる芳香が……キンモクセイの甘い香りだ。
(Oct.9)


鳩山で拾った茶の種を植木鉢に撒いておいたら発芽。みるみるうちに育ち、白い可憐な花を咲かせた。
うつむき加減に開く白い花は清らか。鳩山ではこぼれ種から茶が育ち、増えに増え茶畑のようになった。昨年は新茶を
すすったが蒸して揉むのは大変な労働だった。普段なにげなく飲んでいるお茶、手間が掛かっているんだと実感した。
シークワーサーの葉が虫食いの穴だらけ。よく見ると揚羽の幼虫がいた。取り除こうと思ったが、揚羽がさなぎになり
飛び立つまでシークワーサーには我慢してもらうことにした。体にちょこっと触れると口から黄色い舌状のものが伸びる。
威嚇だろうか。それにしてもこの幼虫、1枚、2まいの葉っぱにきめて食べてくれない。あちこち葉っぱを食い散らす。
シークワーサーが枯れなければいいが……。
(Oct.7)
■二十四節気<寒露>、七十二候(四十九候.五十候.五十一候)
十月に入りめっきり涼しくなった。鳩山の庭では今、萩が終わり、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの花が咲いている。
(秋の七草、残りはクズ、ナデシコ、ススキ(尾花)。他にワレモコウ、シュウメイギク、ヒガンバナも。真っ赤なヒガンバナ、植えも
しないのに昨年まで見られなかった場所に生えてきたから不思議だ。ヒガンバナといえば、ぼくの行くテニスクラブ(東京狛江)の
コート脇には赤花に混じって白花のヒガンバナも咲いている。鳩山にはヒガンバナの群生があちこちに見られるが白花はない。
柿の実が熟している。高枝バサミも届かず取れないでいる。渋柿だが完熟し落果する頃には甘くなっている。それまで待とう。
ただし、小鳥が食べ残してくれたらだが……。
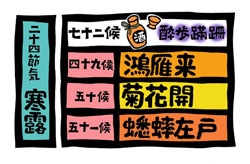 |
今年の寒露は10月9日 (霜降は10月24日) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
■セルビアのナイーブアート展
現代童画展覧会特別展示「セルビアのナイーブアート展」のお知らせ
11月2日(金)~12日(月) 東京都美術館 9;00AM~4;30
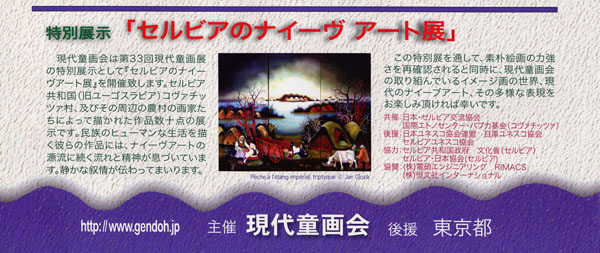
日本セルビア友好協会と打ち合わせ。70余点が9日ベオグラードから発送されたとの事。12日成田着予定。
一安心だ。13日セルビア大使館で開梱立会い。現代童画展会場に陳列する50点前後の作品を決定する。
ポスターに掲載作の画家、Jan Glozik氏の来日も決定。よい展覧会になりそうだ。全作品の展示は
都美術館の展覧会が終了後、地方の2~3の美術館で巡回展示される。多くの方々に見ていただきたい。
(Oct,6)
■タングラムそのⅢ
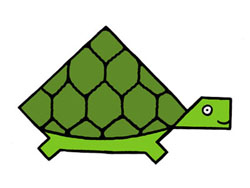
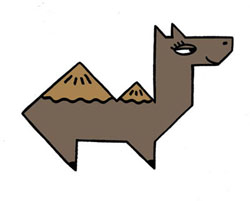
お問い合わせのX様、今回はタングラムのカメとラクダをご用意しました。挑戦されますか?
見事、出来ましたらまたご連絡ください。
(Oct,3)
■タングラム其のⅡ 11ピースタングラム

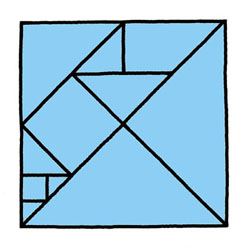
・タングラム(11ピース) ケース入り ・タングラム 製図(一辺12センチの正方形)
タングラムの作り方について問い合わせがあった、ぼくは12センチ角のシナベニア板を上図のように
11辺切断して製作している。両面均質の白又は黒いカードボードでもOKだが、ある程度の厚みが欲しい。
作るのが簡単な上、造型の妙あり奥深し。創造性を喚起、右脳を刺激する。是非多くの方に遊んでいただきたい。
■先日のタングラムの答え(構成)
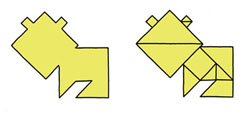
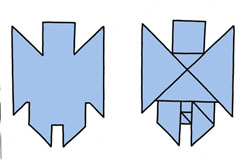
・ライオン シルエットと構成 ・天使 シルエットと構成
お問い合わせがありましたので、ライオンと天使の作り方を掲載します。
| 9月のアトリエだより |
■二十四節気<寒露>、七十二候(四十九候.五十候.五十一候)
十月に入りめっきり涼しくなった。鳩山の庭では今、萩が終わり、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの花が咲いている。
(秋の七草、残りはクズ、ナデシコ、ススキ(尾花)。他にワレモコウ、シュウメイギク、ヒガンバナも。真っ赤なヒガンバナ、植えも
しないのに昨年まで見られなかった場所に生えてきたから不思議だ。ヒガンバナといえば、ぼくの行くテニスクラブ(東京狛江)の
コート脇には赤花に混じって白花のヒガンバナも咲いている。鳩山にはヒガンバナの群生があちこちに見られるが白花はない。
柿の実が熟している。高枝バサミも届かず取れないでいる。渋柿だが完熟し落果する頃には甘くなっている。それまで待とう。
ただし、小鳥が食べ残してくれたらだが……。
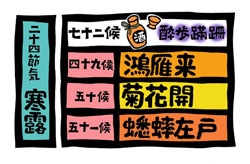 |
今年の寒露は10月9日 (霜降は10月24日) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
■セルビアのナイーブアート展
現代童画展覧会特別展示「セルビアのナイーブアート展」のお知らせ
11月2日(金)~12日(月) 東京都美術館 9;00AM~4;30
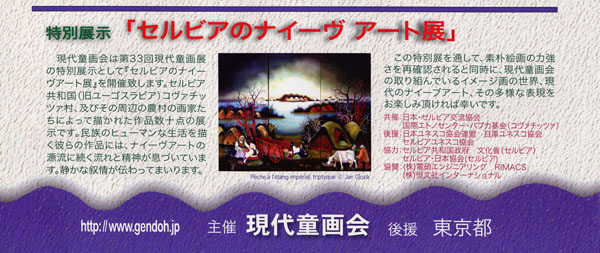
日本セルビア友好協会と打ち合わせ。70余点が9日ベオグラードから発送されたとの事。12日成田着予定。
一安心だ。13日セルビア大使館で開梱立会い。現代童画展会場に陳列する50点前後の作品を決定する。
ポスターに掲載作の画家、Jan Glozik氏の来日も決定。よい展覧会になりそうだ。全作品の展示は
都美術館の展覧会が終了後、地方の2~3の美術館で巡回展示される。多くの方々に見ていただきたい。
(Oct,6)
■タングラムそのⅢ
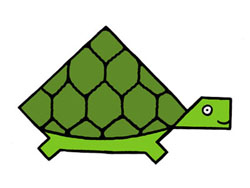
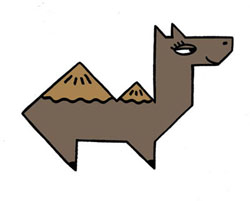
お問い合わせのX様、今回はタングラムのカメとラクダをご用意しました。挑戦されますか?
見事、出来ましたらまたご連絡ください。
(Oct,3)
■タングラム其のⅡ 11ピースタングラム

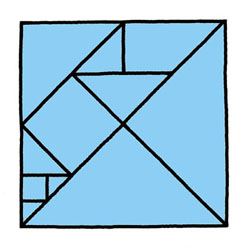
・タングラム(11ピース) ケース入り ・タングラム 製図(一辺12センチの正方形)
タングラムの作り方について問い合わせがあった、ぼくは12センチ角のシナベニア板を上図のように
11辺切断して製作している。両面均質の白又は黒いカードボードでもOKだが、ある程度の厚みが欲しい。
作るのが簡単な上、造型の妙あり奥深し。創造性を喚起、右脳を刺激する。是非多くの方に遊んでいただきたい。
■先日のタングラムの答え(構成)
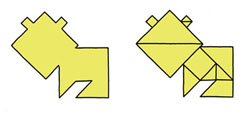
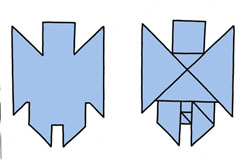
・ライオン シルエットと構成 ・天使 シルエットと構成
お問い合わせがありましたので、ライオンと天使の作り方を掲載します。
| 9月のアトリエだより |
■11枚構成のタングラムを作る(造型パズル) [実践遊び学]


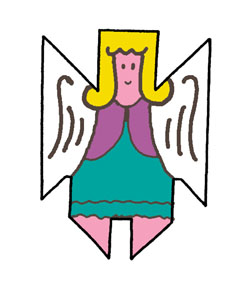
シナベニアを切りステイン塗装しタングラムを製作。枚数はいろいろ試して11枚構成に決めた。(幼児には二分の一分割、
四分の一分割から8枚構成程度で遊ばせるとよい)枚数が増え複雑になればなるほど難度が高くなり、組み合わせて出来る形の
バリエーションも増す。学生に自由に色々作らせて発表させる。その後もとの正方形に戻す。造型は想像力を必要とするし、
なかなか奥の深い遊びだ。
松浦政泰編「世界遊戯大全」には、”複式知恵の板”と紹介されている。7枚合せで人や器具を作る。同本は「室内遊戯」の著者
ゼー・キー・ベンソンの言葉を引用している。『玩具の考え物も数々あるが、此のものに勝るものは無い。決して新しくはないが常に
面白い。而して唯三角と四角とで殆ど在ゆる形を作ることが出来るといふ原理を照明するところが其の最も価値ある点である』また
同書には「益智図」という遊技書から十五枚合せ(七福神十二月ほか)や十九枚合せを紹介している。福助、牛若と弁慶、稲荷の狐、
松に月、大黒像と,解答を見なくては作りがたい形が多数載っている。
11枚すべてを使う。そしてユニークな形を作り出す。ぼくは上に掲載したライオンや天使のほかに、ニワトリ、キツネ、ラクダ、カラス、
ワシ、ゾウ、カエル、アヒル、ヘビ、ペンギン、それにロケットや植木鉢と花、船などを作った。実に楽しい。
形のシルエットからそれがどんな物(動物etc,)かを想像しどうやって出来ているか構成を考える遊び方も出来る。手を使い想像力を
駆使するから、タングラムは子どもにも、高齢者にも(ボケ防止)格好の遊具といえよう。
(Sep,30)
■リリアン編み機を作る


3年前から絵本の読み聞かせに関するアンケート調査を行ってきたが、それに加え、今年は人間社会学科の
女子学生に「幼少女期の遊び」調査を行った。来春より新設される子ども教育学科の「実践遊び学」の参考にする
ためでもある。
おみせやさんごっこ、石けり、かくれんぼ、ゴムとび……それに、お手玉、おはじき、あやとり、折り紙、コマ回し、
竹とんぼ、だるま落としなどの伝承遊び、玩具なども含め百近い遊びをあげ、遊んだことのあるものに丸をつけて
もらった。回答書にはよく遊んだ遊びも書き入れる欄も。
多くの学生がローセキ、コリントゲーム、リリアンを知らなかった。そこで、リリアン編み機を製作、学生に見せることにした。
駄菓子屋(余りみかけなくなったが)にはプラスティックのものが200円程度で売られているが、昔は木製だった。
姉が日がな黙々と編んでいたのを覚えている。校庭の隅でも二人三人とリリアンを編む姿があった。編んだリリアンを
何に使ったのかは不明だが、ひたすら編み続けていたのは確かだ。
今、リリアン編み機に糸を通し編んでみて、その大変さがわかった。五本の釘にかけたリリアンを鈎針で一つずつ
掬っていくのだが手間が掛かること!リリアンの糸が”紐”になるまでにはたいそうな時間がかかる、ため息が出そうだ。
それを毎日のように飽きずにやっていた少女たちは一体……。現代の遊びからリリアンは消えたが、手わざ、丹念さ、
持続力という手工の心はリリアンには詰まっている。復活してもよい遊びの一つだと思う。
(Oct,14)
■『慈(其ノ壱)清流遊楽』 『慈(其ノ弐)灯火静穏』 2作品額装

作品が漸く仕上がった。大学の秋期授業がはじまり、このところアトリエに入る時間がますますコマ切れになっていた。
今日秋晴れ。マットバーニッシュ(仕上げ剤)を塗布、乾くのを待って額装する。日が短くなった。「防災鳩山」のスピーカーから
流れる夕焼け小焼けのメロディーと子どもらに帰宅を促すメッセージが聞こえる頃にはあたりはもう暗い。
完成作を写真にとり一息。運送業者に出す前までの暫くが、ぼくにとっての至福の時。絵を前に酒を酌む。
この時の酒より美味い酒を知らぬ。酒量捗ること、むべなるかな。窓から鼻腔をくすぐる芳香が……キンモクセイの甘い香りだ。
(Oct.9)


鳩山で拾った茶の種を植木鉢に撒いておいたら発芽。みるみるうちに育ち、白い可憐な花を咲かせた。
うつむき加減に開く白い花は清らか。鳩山ではこぼれ種から茶が育ち、増えに増え茶畑のようになった。昨年は新茶を
すすったが蒸して揉むのは大変な労働だった。普段なにげなく飲んでいるお茶、手間が掛かっているんだと実感した。
シークワーサーの葉が虫食いの穴だらけ。よく見ると揚羽の幼虫がいた。取り除こうと思ったが、揚羽がさなぎになり
飛び立つまでシークワーサーには我慢してもらうことにした。体にちょこっと触れると口から黄色い舌状のものが伸びる。
威嚇だろうか。それにしてもこの幼虫、1枚、2まいの葉っぱにきめて食べてくれない。あちこち葉っぱを食い散らす。
シークワーサーが枯れなければいいが……。
(Oct.7)
■二十四節気<寒露>、七十二候(四十九候.五十候.五十一候)
十月に入りめっきり涼しくなった。鳩山の庭では今、萩が終わり、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの花が咲いている。
(秋の七草、残りはクズ、ナデシコ、ススキ(尾花)。他にワレモコウ、シュウメイギク、ヒガンバナも。真っ赤なヒガンバナ、植えも
しないのに昨年まで見られなかった場所に生えてきたから不思議だ。ヒガンバナといえば、ぼくの行くテニスクラブ(東京狛江)の
コート脇には赤花に混じって白花のヒガンバナも咲いている。鳩山にはヒガンバナの群生があちこちに見られるが白花はない。
柿の実が熟している。高枝バサミも届かず取れないでいる。渋柿だが完熟し落果する頃には甘くなっている。それまで待とう。
ただし、小鳥が食べ残してくれたらだが……。
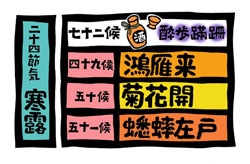 |
今年の寒露は10月9日 (霜降は10月24日) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
■リリアン編み機を作る


3年前から絵本の読み聞かせに関するアンケート調査を行ってきたが、それに加え、今年は人間社会学科の
女子学生に「幼少女期の遊び」調査を行った。来春より新設される子ども教育学科の「実践遊び学」の参考にする
ためでもある。
おみせやさんごっこ、石けり、かくれんぼ、ゴムとび……それに、お手玉、おはじき、あやとり、折り紙、コマ回し、
竹とんぼ、だるま落としなどの伝承遊び、玩具なども含め百近い遊びをあげ、遊んだことのあるものに丸をつけて
もらった。回答書にはよく遊んだ遊びも書き入れる欄も。
多くの学生がローセキ、コリントゲーム、リリアンを知らなかった。そこで、リリアン編み機を製作、学生に見せることにした。
駄菓子屋(余りみかけなくなったが)にはプラスティックのものが200円程度で売られているが、昔は木製だった。
姉が日がな黙々と編んでいたのを覚えている。校庭の隅でも二人三人とリリアンを編む姿があった。編んだリリアンを
何に使ったのかは不明だが、ひたすら編み続けていたのは確かだ。
今、リリアン編み機に糸を通し編んでみて、その大変さがわかった。五本の釘にかけたリリアンを鈎針で一つずつ
掬っていくのだが手間が掛かること!リリアンの糸が”紐”になるまでにはたいそうな時間がかかる、ため息が出そうだ。
それを毎日のように飽きずにやっていた少女たちは一体……。現代の遊びからリリアンは消えたが、手わざ、丹念さ、
持続力という手工の心はリリアンには詰まっている。復活してもよい遊びの一つだと思う。
(Oct,14)
■『慈(其ノ壱)清流遊楽』 『慈(其ノ弐)灯火静穏』 2作品額装

作品が漸く仕上がった。大学の秋期授業がはじまり、このところアトリエに入る時間がますますコマ切れになっていた。
今日秋晴れ。マットバーニッシュ(仕上げ剤)を塗布、乾くのを待って額装する。日が短くなった。「防災鳩山」のスピーカーから
流れる夕焼け小焼けのメロディーと子どもらに帰宅を促すメッセージが聞こえる頃にはあたりはもう暗い。
完成作を写真にとり一息。運送業者に出す前までの暫くが、ぼくにとっての至福の時。絵を前に酒を酌む。
この時の酒より美味い酒を知らぬ。酒量捗ること、むべなるかな。窓から鼻腔をくすぐる芳香が……キンモクセイの甘い香りだ。
(Oct.9)


鳩山で拾った茶の種を植木鉢に撒いておいたら発芽。みるみるうちに育ち、白い可憐な花を咲かせた。
うつむき加減に開く白い花は清らか。鳩山ではこぼれ種から茶が育ち、増えに増え茶畑のようになった。昨年は新茶を
すすったが蒸して揉むのは大変な労働だった。普段なにげなく飲んでいるお茶、手間が掛かっているんだと実感した。
シークワーサーの葉が虫食いの穴だらけ。よく見ると揚羽の幼虫がいた。取り除こうと思ったが、揚羽がさなぎになり
飛び立つまでシークワーサーには我慢してもらうことにした。体にちょこっと触れると口から黄色い舌状のものが伸びる。
威嚇だろうか。それにしてもこの幼虫、1枚、2まいの葉っぱにきめて食べてくれない。あちこち葉っぱを食い散らす。
シークワーサーが枯れなければいいが……。
(Oct.7)
■二十四節気<寒露>、七十二候(四十九候.五十候.五十一候)
十月に入りめっきり涼しくなった。鳩山の庭では今、萩が終わり、オミナエシ、フジバカマ、キキョウの花が咲いている。
(秋の七草、残りはクズ、ナデシコ、ススキ(尾花)。他にワレモコウ、シュウメイギク、ヒガンバナも。真っ赤なヒガンバナ、植えも
しないのに昨年まで見られなかった場所に生えてきたから不思議だ。ヒガンバナといえば、ぼくの行くテニスクラブ(東京狛江)の
コート脇には赤花に混じって白花のヒガンバナも咲いている。鳩山にはヒガンバナの群生があちこちに見られるが白花はない。
柿の実が熟している。高枝バサミも届かず取れないでいる。渋柿だが完熟し落果する頃には甘くなっている。それまで待とう。
ただし、小鳥が食べ残してくれたらだが……。
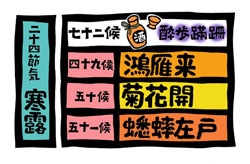 |
今年の寒露は10月9日 (霜降は10月24日) ・四十九候 (10月9日) ・がん きたる 雁が飛来し始める ・五十候 (10月14日) ・きくの はな ひらく 菊の花が咲き始める ・五十一候 (10月19日) ・キリギリス とに あり キリギリスが家の中で鳴く |
■セルビアのナイーブアート展
現代童画展覧会特別展示「セルビアのナイーブアート展」のお知らせ
11月2日(金)~12日(月) 東京都美術館 9;00AM~4;30
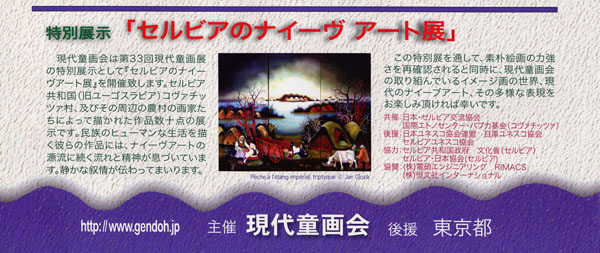
日本セルビア友好協会と打ち合わせ。70余点が9日ベオグラードから発送されたとの事。12日成田着予定。
一安心だ。13日セルビア大使館で開梱立会い。現代童画展会場に陳列する50点前後の作品を決定する。
ポスターに掲載作の画家、Jan Glozik氏の来日も決定。よい展覧会になりそうだ。全作品の展示は
都美術館の展覧会が終了後、地方の2~3の美術館で巡回展示される。多くの方々に見ていただきたい。
(Oct,6)
■タングラムそのⅢ
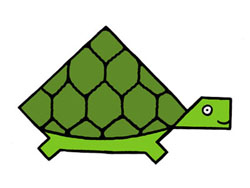
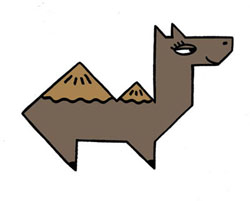
お問い合わせのX様、今回はタングラムのカメとラクダをご用意しました。挑戦されますか?
見事、出来ましたらまたご連絡ください。
(Oct,3)
■タングラム其のⅡ 11ピースタングラム

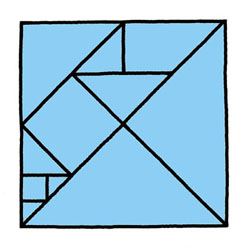
・タングラム(11ピース) ケース入り ・タングラム 製図(一辺12センチの正方形)
タングラムの作り方について問い合わせがあった、ぼくは12センチ角のシナベニア板を上図のように
11辺切断して製作している。両面均質の白又は黒いカードボードでもOKだが、ある程度の厚みが欲しい。
作るのが簡単な上、造型の妙あり奥深し。創造性を喚起、右脳を刺激する。是非多くの方に遊んでいただきたい。
■先日のタングラムの答え(構成)
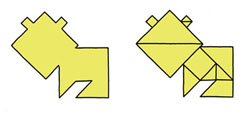
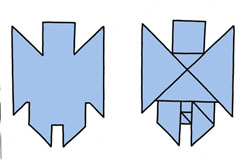
・ライオン シルエットと構成 ・天使 シルエットと構成
お問い合わせがありましたので、ライオンと天使の作り方を掲載します。
| 9月のアトリエだより |
■11枚構成のタングラムを作る(造型パズル) [実践遊び学]


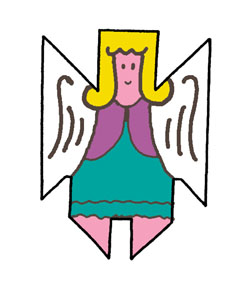
シナベニアを切りステイン塗装しタングラムを製作。枚数はいろいろ試して11枚構成に決めた。(幼児には二分の一分割、
四分の一分割から8枚構成程度で遊ばせるとよい)枚数が増え複雑になればなるほど難度が高くなり、組み合わせて出来る形の
バリエーションも増す。学生に自由に色々作らせて発表させる。その後もとの正方形に戻す。造型は想像力を必要とするし、
なかなか奥の深い遊びだ。
松浦政泰編「世界遊戯大全」には、”複式知恵の板”と紹介されている。7枚合せで人や器具を作る。同本は「室内遊戯」の著者
ゼー・キー・ベンソンの言葉を引用している。『玩具の考え物も数々あるが、此のものに勝るものは無い。決して新しくはないが常に
面白い。而して唯三角と四角とで殆ど在ゆる形を作ることが出来るといふ原理を照明するところが其の最も価値ある点である』また
同書には「益智図」という遊技書から十五枚合せ(七福神十二月ほか)や十九枚合せを紹介している。福助、牛若と弁慶、稲荷の狐、
松に月、大黒像と,解答を見なくては作りがたい形が多数載っている。
11枚すべてを使う。そしてユニークな形を作り出す。ぼくは上に掲載したライオンや天使のほかに、ニワトリ、キツネ、ラクダ、カラス、
ワシ、ゾウ、カエル、アヒル、ヘビ、ペンギン、それにロケットや植木鉢と花、船などを作った。実に楽しい。
形のシルエットからそれがどんな物(動物etc,)かを想像しどうやって出来ているか構成を考える遊び方も出来る。手を使い想像力を
駆使するから、タングラムは子どもにも、高齢者にも(ボケ防止)格好の遊具といえよう。
(Sep,30)
■秋風たたぬ秋分
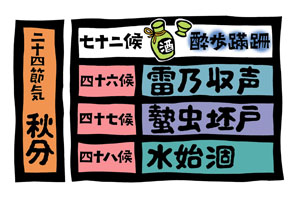 |
今年の秋分は9月23日 ・四十六候 (9月23日) ・かみなり こえを おさむ 雷が鳴らなくなる ・四十七候 (9月28日) ・ちっちゅう とを とざす 虫が地中に巣籠りする ・四十八候 (10月3日) ・みず はじめて かる 田の水を落として稲刈りの準備をする |
彼岸になってもこの暑さだ。いまだに真夏日、秋風立たず。
今年は墓参りに行かれない。観音崎の横須賀美術館に寄ってアンドレ・ウオリス展(17日終了。3月に東京都庭園美術館で見たが、
船乗りだったウオリスの絵を海辺に建つ美術館でもう一度見てみたかった)その後、父母の眠る鎌倉の寺を詣でるつもりだった。板絵
制作、仕事、大学の準備に忙殺され果たせない。
現代童画展の特別企画「セルビアのナイーブアート展」の、写真での展示シミュレーションもしておきたいところだが、ぼくは今日夕方
鳩山に行かねばならない。実行委員のK氏の連絡をギリギリまで待ったが、DVDが届かなかったのだろう、時間切れだ。セルビアからの
作品輸送も間に合うだろうか心配だ。展覧会の紹介文も書かねばならず気になること多し。
鳩山で先日、山萩の終わりかけた野で、この秋はじめての栗拾いをした。例年より実は小さめ、つきも良くないが、棒の届く範囲を
叩いただけで収穫二篭。夕闇が迫り残念ながら野原での焼き栗は諦めたが、昼の暑さは何処?秋の涼風が汗でシャツの張り付いた体に
心地よかった。その夜は栗ご飯を堅めに炊いた。かみしめかみしめ自然の恵みを有難いと思ったのだった。秋夜の一献、殊のほか旨し。
今晩から再び鳩山で板絵制作だが、もう栗を拾う余裕はないだろう。仕上げに入り切羽詰った状態だから。明々後日からは大学も
始まる。ゆとりがない。いつもの事ながらアクセクアクセク……、じっと立ち止まりゆっくり考える、思いに耽るひと時こそ大事なのになあ。
嗚呼アトリエで時間を気にせず一人静かに沈潜していたい。、
皮肉か、制作中の板絵2枚のうち、一つは画題が「慈(その弐) 灯火静穏」だ。”静穏”…………苦笑する。
(Sep,20)
■大雨に打たれ、秋の草ワレモコウ、オミナエシ……あわれ (鳩山の庭)
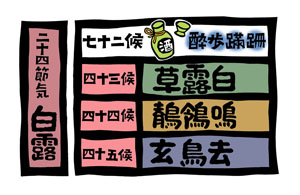 |
今年の白露は9月8日 (秋分は9月23日) ・四十三候 (9月8日) ・くさつゆ しろし 草の葉に白い梅雨が宿る ・四十四候 (8月13日) ・せきれい なく セキレイが鳴くようになる ・四十五候 (9月18日) ・つばめ さる ツバメが 南の国に 去って行く |
11日は「おひさま大賞」贈賞式だった。雨の中を一ツ橋の学士会館へ。例年になくプレス記者が多い。カメラマンの数も。
優秀賞受賞者が人気声優だったからだ。天は彼女に二つの才能を与えたようだ。
出かける前、歯が痛くなり歯医者に寄っていく。虫歯はない。、診察の結果はなんと「過労からくるもの」だった。この一年、
休みをとらず働きずめだったからなあ。仕事に向かう気力だけではどうしようもなく、体力の減退が恨めしい。創作欲が衰えない
ことを、今日は素直に喜ぼう。
(Sep ,12)
■台風でアトリエ浸水、漏水に、あたふた……。
 ・ハーブおばさんの編物「クレヨンまる」より
・ハーブおばさんの編物「クレヨンまる」より 台風でテニスコートも冠水。オムニコートの水が引くのを待って、サーブ練習。風が強くハードコートもあちらこちらに水溜り。風も
強い。こんな悪コンディションではテニスなどする者なし。たった一人黙々サーブ練習。一かご50球ほど。フォアサイド、バックサイドから
2かご打って、汗びっしょり。心地よい疲れ。一路鳩山へ。
サーブ特訓どころではなかった。アトリエの床に水溜り数箇所。壁面にたてかけておいた100号パネルは水を吸い、ボンドが
とけ、ラワン材が波打っている。あわてて外に運び出し天日乾しする。が、剥離したものはなおらない。台風が大型だったとはいえ、
いつもこうだ。わがアトリエは水に弱い。湿気るし漏水、浸水……たびたび。仕事の前の大仕事。掃除、片付けに追われた一日。嗚呼!
(Sep,10)
■田は禾乃登………、我が世代、身体は金属疲労……?
9月に入った。明日は二十四節気の七十二候{四十二候}禾乃登(稲すなわち実る)。稲がすくすく育つ季節だが、刈り入れは
まだまだ。アトリエ下の石井さんの田圃に人影は見られない。今日から3日間、仕事場に籠るつもりで鳩山へ。食料のほかに、
全体が卵の塊のようなフワフワのバームクーヘンも持参。雑誌の担当編集者が替わり手土産に持って下さったもの。口に入れた
とたん、蕩けるようでじつに美味く楔形に切って少しずつ食べている。
鳩山へ来る前、わが青春”童話工房”時代からの友人Mより電話あり。網膜はく離で入院一月。やっと退院したとのこと。糖尿病も
みつかり、手術まで日数を要したのだという。爽やかな少年の面影をもつ明るい男だ。病気とは無縁と思っていた。パソコンでの
仕事のやりすぎで目を痛めたのでは、と聞くと、「運動不足が主因」と医者から言われたという。電話の用件は退院の知らせと、Mの
主催する[大文化祭---ソレタ---]への参加要請だった。今年は現代童画展が早まりソレタと会期が重なってしまう。残念だが出品
出来そうにない。
彼はぼくのMACの先生でもある。視力の回復、糖尿病体質の改善を祈るものの、イラストレーターとして猛スピードでの仕事は
程ほどにと忠告した。が、言えた義理ではない。ぼくも定期健診を受けておらず、他人事ではない。
処暑から白露へ。季節の移り変わる頃、金属疲労を起こしているだろう身体をぼくもオーバーホールしようかな。
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■板絵の彫りに入る。息抜きに炎暑の野原に水を撒く。



刈り払い機で誤って幹を切ってしまった栃の根元から新芽がでていた。乱暴にエンジン機を振り回し切断してしまった時は
悪いことをしたと、後ろめたく、そのあたりにしばらく近づけなかったが、今日、ひこばえを見つけ嬉しくなった。大事に育てよう。
早速まわりの雑草を抜き、水を遣った。ハグロトンボが無風の野原に遊んでいる。打ち水の涼しさにやってきたのだろうか。
(Aug.25)
■ 「灯火静穏」 「清流遊楽」板絵制作、エスキースの段階


父と子、母と子の物語。笹舟を浮かべて遊ぶ子どもたち。笹舟が流れてお家まで。思いよ届け。
通う心。導く父さん。守り抜く母さん。父さん母さんの「覚悟」がテーマだ。連日、高校野球が
”熱いドラマ”を伝えているが、わが仕事も熱い心で集中したい。甲子園が終わるまでには
彫り始めたいと思う。
(Aug,20)
■二十四節気<処暑>、七十二候(四十候、四十一候、四十二候)
 |
今年の処暑は8月23日 (白露は9月8日) ・四十候 (8月23日) ・わたの はなしべ ひらく 綿を包むガクが開き始める ・四十一候 (8月28日) ・てんち はじめて さむし 天地の暑さがようやく収まる ・四十二候 (9月2日) ・いなほ みのる 稲が実る |
■自生のミョウガを採る


アトリエに閉じこもり終日仕事。腕が痛い。肩が張った。庭に出て深呼吸する。ミョウガの葉が茂り通路を塞いでいる。
葉をかきわけると白い花が顔をのぞかせた。ミョウガは花が咲く前に収穫するのだったが、まあいいや。おかげで滅多に
見られぬ花が楽しめた。刻んで冷ソーメンの薬味に。
炎熱の鳩山も宵闇せまり、カラスウリの花があちこちに開きはじめる頃には田圃の彼方から涼やかな風が
吹いてくる。電気をつけず薄闇のなかでソーメンをすすった。
(Aug,18)
■ 草鞋(わらじ)を編む


連日35度を越す”猛暑日”。負けるものかと気を奮い立たせ久々のテニス。炎天のハードコートは40度はあるのでは。
毎日通っているメンバーには敵わない。一時間も経たぬうち熱射病状態でフラフラ。いつもなら一人で100球ほどサーブ
練習をして帰るのだが、今日は打ち込みも取りやめ。
仕事場に閉じこもる生活が続きすっかり体がなまっている。試合どころではなく、”気つけ”に頂いたキャラメルを口に含み
退散する。ひ弱さを自覚。情けなく思う。仕事場の健康器具もこのところ、ご無沙汰している。体を鍛えねば。次回のコートには
颯爽と登場したいものだ。
仕事に向かう気なく、気分転換(気分転換にテニスに行ったのに)に、草鞋(わらじ)を編む。これが又、根気のいる作業。
汗だくになって藁と格闘するも、出来上がりは写真のごとし。履けるような代物ではなく、またまた落ち込む。だがテニス同様、
諦めることなく、再度挑戦だ。鳩山で今度、アトリエの下の田んぼの主、石井さんから藁をもらおう。草鞋を編むといったら、
笑われるだろうな。
昭和20年、ぼくが生まれた頃の婦人雑誌の付録を手にいれた。粗末な紙のハガキより小さな冊子。「足袋の作り方」。物が
なかった頃は家庭で何でも作っていた。ぼくは味噌や醤油を作り、行灯用の菜種油を絞るなど、すべて自前で生活する祖母に
育てられた。草履など朝飯前だったのだ。悔しいけどぼくは何も出来ない。祖母を思い起こし何とか草鞋が編めるようになったら、
次は足袋も作ってみたい。ただ、コハゼが手の入るかどうか……。草鞋も足袋も作ってどうする、何になる……、いえいえ、作る、
作れることに意味があるとぼくは思っている。
(Aug,12)
■第33回現代童画展 『特別展示セルビアのナイーブアート展』
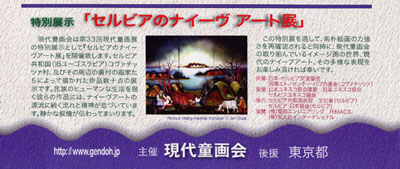
現代童画展は今年度から会期が変わる。今まで12月開催であったが、11月となり、会場面積も1フロア増える。
日展、二科会、新制作などが六本木の国立新美術館に移ったためだ。ぼくは上野の東京都美術館の方が好きだ。会場を出て
上野駅まで、芸術に触れその余韻を反芻するように歩ける上野の公園の環境は六本木では望めない。
今年は特別展示として、『セルビアのナイーブアート展』を併催する。現代童画会は先日、セルビア側と覚書に調印したが、
まだ安心できない。作品が無事届くまでは。民族の香りが漂う素朴な作品を数十点展示する予定だが、写真を、図録を見て
ぼくは是非とも日本で展観したいと強く思った。11月が待ち遠しい。ナイーブアートの一つの源流とも言えよう。
多くの方々に見ていただきたいものだ。
(Aug.2)
■二十四節気<立秋>、七十二候(三十七候、三十八候、三十九候)
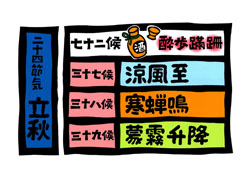 |
今年の立秋は8月8日 (処暑は8月23日) ・三十七候 (8月 8日) ・すずかぜ いたる 秋風が吹き始める ・三十八候 (8月13日) ・ひぐらし なく 蜩が鳴く ・三十九候 (8月18日) ・のうむ まとう 濃い霧が立ちこめる |
| 7月のアトリエだより |
■大学オープンキャンパス2007体験授業フェア
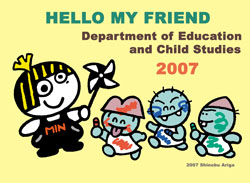


大学入学希望者を集めての体験授業フエア。ぼくの授業タイトルは「紙で遊ぼう!答えのない世界/表現はたのしいぞ~」。
約40名の高校生が参加した。来年より新設される子ども教育学科で絵画造型系科目を担当するが、その中の「実践遊び学」の
”さわり”を演習講義する。マニュアル思考で教育されて来た若者に自分で考える、何もないところから生み出す、答えのない
世界に遊ばせることが目的。○△□等、形にとらわれずに自由な造型にチャレンジ!課題は”見たこともないユーモラスな生き物”を作る。
はさみもカッターナイフも使わない。下書きもさせない。ただ黒い紙を指でちぎるだけ。頭で考えない。目と手を使う。そう、幼稚園の子なら
喜んでやる作業を高校生にさせてみる。何と受講生に混じって大学の他科の教授が3人も紙をちぎって遊んでいた。残念ながら、
”若い感性”の勝!表現された様々な形態をした生き物は、高校生のユニークさには敵わない。参加者が生み出した世界でたった
一匹(一人)の生物は名前がつけられた。40体のキャラクターができたのだった。ぼくの授業のテーマは”想像から創造へ”、
”答えのない世界で自由な表現を””生きることは自己表現”だが、瞬く間に過ぎた50分、受講者に思いは伝わっただろうか。
驚いたのは父兄の付き添いがあったこと。母親3人、父親1人。進学校を決める判断を親がするのだろうか。慎重に、あるいは
大人の広い目でと言うのは分からぬこともないが、何か心許ないなあ。自発性、自主判断は………。時代なのだろうか。
(Jul.28)
■アケビの蔓でリースを作る
 ・アケビのリース(5ワット豆球点灯)
・アケビのリース(5ワット豆球点灯) 昨日の雨もあがりカラリと晴れ上がった。暑い。三十度近くあるだろう。でも、普段は湿気で悩まされている”半地下”にある
わがアトリエは意外と涼しい。三方が窓、出入り口も土間に続くから風通しが良く冷え冷えする。(不在時、締め切っておくせいで
カビがすぐはえてしまうのが頭痛の種。)
北側の小さな窓が一つ、鬱蒼と生い茂るアケビで塞がれてしまった。アケビ棚も傾いたままだが、蔓が複雑に絡みつき取り
替えることが出来ない。
アトリエに風を呼び込もうと、アケビを剪定する。切り取った蔓をかき集め、捨て場に運ぶ。最後の一抱えを放ろうとして考えた。
これでアケビのリースを作ろうと。
5枚葉のアケビはもちろん生。ドライではないから、美しいのも今日だけだ。クルクル蔓を巻き中央に金網シェード付きの5ワットの
電球を配す。灯火が温かい緑のリースの出来上がりだ。
シャワーを浴び、冷やした酒も用意万端。宵闇迫り来たり、頃合を見てリースに点灯。暗闇に緑の葉が浮かび上がった。明りも
影も妙なり。酒の一滴が喉を伝わり臓腑にしみていくのを感じる。
今夜だけのリース、灯火、今一瞬の酒の余韻。どうしたことか、いつもはあんなに騒がしいカエルが今晩はまだ鳴き始めない。
”静寂な時に酔う”ぼくのため、田圃で息を潜めてくれているのだろうか。
(Jul.24)
■二十四節気<大暑>、七十二候(三十四候、三十五候、三十六候)
鳩山の庭は荒れ放題。伸びきったホーリーの茂みをかきわけつ、葉の棘に用心して中に入れば、目に飛び込む
ドクダミの緑、ホウズキの橙色。
春、花をたくさんつけて期待させたアケビは葉を茂らせるばかりで実らない。蔓が複雑に絡みつき重さで棚が崩れそう。
ヤマブドウやナツメはまだ米粒大だが、サルナシは形を成し熟すのを待つのみだ。生い茂る雑草でキウイやマタタビの
棚には近づけない。ウグイスが、ホトトギスが歌を奏でている。
気分転換も兼ね少しだけ草取りをする。エンジン式刈払い機で荒刈りし、買ったばかりの電動式草刈機を試してみる。
首に吊り下げ運転するエンジン式とちがい、電動式草刈機は左手で持ち続けなくてはならない。刈り込み具合は良好だが
二の腕が張った。しばらく手の痺れが収まらず、仕事は断念。
夜、酌む酒が震えた。心持ちよい震えだ。労働の後の美酒一啜り。嗚呼、日々是好日也。
(Jul.22)
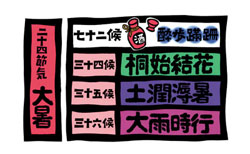 |
今年の大暑は7月23日 (立秋は8月8日) ・三十四候 (7月23日) ・きり はじめて はなを むすぶ 桐の花が実を結ぶ ・三十五候 (7月28日) ・つち うるおいて むしあつし 大地が熱を持ち蒸し暑くなる ・三十六候 (8月2日) ・たいう ときどき ふる 大雨が時々降る |
■近々アトリエ取材あり。頭痛し。 何故今、ゲーム製作?



大いなる勘違いをした。イラストレーターのN氏より、「アトリエ訪問取材」の打診あり。現代童画会の機関紙「現童通信」
には作家インタビューのコラムがある。「現童通信」の記事ならばと気軽に取材をOKしたものの、それが勘違いと知った。童美連(日本
児童出版美術家連盟)の機関紙「DOBIREN」のアトリエ取材であった。これは頭が痛い。N氏はぼくと同様、現代童画会と童美連の両会に
所属している。
童美連は童画家、イラストレーター、絵本作家の職能団体。著作権擁護の理念を抱く。季刊「DOBIREN」の『もっと怪しいアトリエ
探検隊』と題した取材ページは、絵描きのプロたちによって制作される。毎号、作家の仕事場が暴かれるので楽しみにしていたが、
こと自分となると、さあ大変だ!『もっと怪しいアトリエ探検隊』にはアトリエを俯瞰したイラストがつく。部屋の内部が洗いざらい描きだされ
れてしまう。
ぼくのアトリエの壁面(二面)はパネルだらけで面白くもなんともない。他の壁面はゴチャゴチャ汚らしい。今さら掃除しても狭くて片付かない
から仕方ない。取材はカメラ、イラスト、ご自由にとふてくされてそっぽ向いている事にしよう。と言ってもインタビューもあったっけ。嗚呼………。
今まで取材というと、アトリエをのぞき見るというより、作家の言葉を聞き出すというものが多かった。やっぱり頭、痛いなあ。
作業台の上にはペットボトルや牛乳パックが散乱している。今、玩具やゲームをあれこれ考えて作っているのだ。「コロリポトン ビー玉
落とし」はペットボトルの口からビー玉を5個落とし、黄色い円盤上に1個ずつ乗せるというもの。作ったもののこれは難しすぎて1時間
挑戦したが、4個が精一杯だった。 黄色い円盤はテニスボールの缶の蓋、その間の白いものはペットボトルのキャップ。造型的には美しいとは思うが
あまり難しい玩具は失敗作かなあ。
牛乳パックを使ったおはじき取りゲーム。これは二人でも四人でも遊べる。
25個のパックには開口部があり、ビー玉を四隅に一つずつ置き、盤を揺らしながら中央に集めるという遊びもできる。神経を集中させる、
こちらは面白い玩具だ。
それにしても今度の取材は気恥ずかしい。
(Jul.15)
■児童画展の審査
幼稚園から小学6年生の図画200点程を審査した。児童画を見るのはとても楽しい。
ぼくは大の児童画好き。普段でも、掲示されていると歩を止め見入ってしまう。
無心に描かれた子どもの絵から学ぶことは多い。3~6歳の”天才画家”の絵を見て感心したり、
喜んだり。時に自省的にもなる。
近年審査で気になっていることがある。出品された絵は個人より、園やクラスがまとめて応募したものが
断然多いが、それらに先生の過剰な指導が見られるようになってきたのだ。生活の感動を自由に描かせ
れば、もうそれで十分なのに、高度なテクニックを幼少期から教えている。”指導”が何たることが
わかっていない。素材を与え、あるいはテーマのヒントを出し、遊ばせる。それで良いはず。
”マーブリング” ”スパッタリング”などの技法を教え込むことが指導ではない。
子どもはそれに努めるあまり、絵はパターン的になってしまっている。
それもクラスから全員同じような絵が揃って出品されてくるから恐い。版画にもこの傾向が強くみられる。
版を使った絵画造型は技法が様々で、それはそれで楽しいものだが、高度な多色刷りをさせたりするのは
首を傾げてしまう。子どもの自由度を些かでも奪うことは避けなければいけない。
”指導”は難しい。「子どもの感動表現の立会人」または「見守り役」くらいに、
先生方は考えてもらえないだろうか。 (Jul.10)
■ミルテ(マートル)の花はじける (Myrtle)
 ミルテの純白、目に染みる (鳩山にて)
ミルテの純白、目に染みる (鳩山にて)
どんより重たい梅雨空。今年もミルテの花がはじけるように咲いた。霧雨にタピオカの
小球を思わせる蕾が微かに揺れる。この花の五弁の白は、正に純白。他のどの花よりも
白さにおいて優ると、ぼくは思う。ミルテの甘い香り、何よりこの白さ。ぼくの大好きなこの
時季だけの花。雨にぬれながら、長いこと見入ってしまった。雨に似合う花、静寂に似合う花だ。
ふさふさとした薄黄色の雄しべが白梅に似た花から溢れている。和名を銀梅花という。
(Jul.1)
■二十四節気<小暑>、七十二候(三十一候、三十二候、三十三候)
 |
今年の小暑は7月7日 (大暑は7月23日) ・三十一候 (7月 7日) ・おんぷう いたる 暑い風が吹くようになる ・三十二候 (7月12日) ・はす はじめて ひらく 蓮の花が咲き始める ・三十三候 (7月17日) ・たか わざを ならう 鷹の子が巣立ちの練習をする |
| ■6月のアトリエだより |
■『緑風疾駆』完成
『緑風疾駆』完成する。後は額装するのみ。今回は珍しく20号サイズで制作。
現代童画会2007選抜展に出品。銀座アートホール(7月2日~8日)詳細はアトリエ便り「展覧会のページ」を。

■二十四節気<夏至>、七十二候(二十八候、二十九候、三十候)
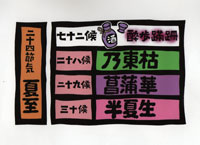 |
今年の夏至は6月22日 (小暑は7月7日) ・二十八候 (6月22日) ・だいとう かる 夏草が 枯れる ・二十九候 (6月27日) ・しょうぶ はな さく 菖蒲の 花が 咲きはじめる ・三十候 (7月2日) ・はんげしょうず からすびしゃくが 生える |
■ぶんぶんゴマと、竹けんだまを作って遊ぶ

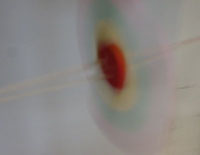

入梅宣言が出たものの一向に雨が降らない。玉堤通りを通って渋谷の仕事場に行く途中.岡本民家園に寄り道する。
民家園は裏の竹林が太陽を遮りひんやりしていた。気持ちよい涼風を感じながら、庭に敷かれたゴザに座り、伝承玩具の
ぶんぶんゴマと竹けん玉を作った。
竹を幅2センチ、長さ8センチ、厚さ5ミリにカット。紙やすりでこすった後、竹板の中央に1センチ離して、キリで穴を2つ開ける。
マーカーで裏表ともペイントし、90センチのタコ糸を通せば出来上がり。
このぶんぶんゴマ、遊ぶのが実に楽しい。両手の指にかけたタコ糸を引いたり緩めたりして回転させると、ビューンビューン音を
発する。力強い音で、指先に振動が伝わり止めるのが惜しくなってしまう。指が糸で引きちぎれそうで廻すのを止めるが、すぐ又
廻し始める。糸を操る指加減のテクニック、ペイントした色が混ざり合う美しさ……、シンプルで面白いブンブンごまに夢中。ぼくは、
すっかり子どもに還っていた。
(Jun.16)
■雨上がりの庭。 マタタビの花を見つける (鳩山にて)


昨晩はカエルの鳴き声に包まれ眠った。夜中、瀧のような雨音に起こされる。朝には注文したパネルが届くので
豪雨はマズイ。何とか小降りにと願ったが、トラックが着く少し前にピタリと止んだ。
80号~100号パネル、10枚。しまうのも大変。収納庫を大掃除、新旧入れ替えする。相変わらずカビがひどい。
板絵作品にも容赦なくカビがふいている。鳩山のアトリエは静かで制作にで集中できるがカビには悩まされる。
雨上がりの庭、木々の間にセキレイがやってきた。トカゲもチョロチョロ。ヤマカガシも姿を見せた。あの豪雨の中、何処に
隠れていたのだろうか、モンシロチョウが3匹、デージーの花園に遊んでいる。
伸び放題の草をかき分け歩きズボンもシャツもびしょぬれ。でも空気が澄んでとても爽やか。サルナシの実から水滴が
落ちている。マタタビがキウイの蔓にからみつき四方に伸びている。おや、マタタビが花を咲かせたぞ。蕾が多く、咲き始めた
ばかりだろう。清らかな白色でふんわりしている。植えて3年、マタタビの花を見るのは初めてのこと。甘い香りは梅の花そっくりだ。
<マタタビ酒>が出来るぞ!秋が待ちどうしい。
(Jun,10)
■深夜のアトリエで新作のタイトルを考える。下の田んぼではカエルが大合唱だ


新作板絵のタイトルを『緑風疾駆』とする。いつもは画題は絵の完成後に考えるが(画題を決めてから制作に入ることもある)、
『緑風疾駆』の語句はは制作半ばで浮かんできた。ぼくの板絵は彫るという作業がある上、肝心の色彩も一発できまることなどなく
時間を要する。いわば色のイメージの化石を掘り当てるようなもの。塗って塗って塗って、イメージの”情景色”が出るまで作業を続ける。
この作業、いつ終わるとも知れず、又イメージの”情景色”が確たるものとして定着するか心もとない。タイトルは絵の完成後となるが今回は
描き進む流れの中で決まった。
アトリエは低地にあり湿気がこもる。パネルにカビがはえるのが頭痛の種。たびたび数十枚の大小パネルを虫干しするが、追いつかない。
カビを吸い込むのだろうか咳がでる。胸が苦しい(気がする)。制作に入れば何時間もアトリエに居ることになる。新鮮な外気を吸いに庭に
出ればいいのに……とは思うけど。実際は絵と心中状態だ。
地面に並べたパネルが太陽光を反射して眩しい。その上を数百匹いやそれ以上のミツバチが飛び交っている。他の花には目もくれず
満開のブラシノキに群がっている。羽音がうるさいほどだ。紅赤の花(細い毛状態のものはオシベの花糸。花弁は緑色で目立たずすぐ
落ちてしまう。)に潜り込んで蜜を吸っている。一つのブラシに2~3匹。今、鳩山のアトリエで蜂蜜を集めれば「ブラシノキ蜂蜜」だ。
昨年はクリムソンクローバーにハチが群がっていた。どんな香り、味だろう?………一度”有賀養蜂所”産をなめてみたい。
(Jun,4)
■『日本jの幟旗』展………絵幟展(えのぼり)の迫力に圧倒される <日本民藝館>
日本民藝館 (駒場東大前)で絵幟展を見る。江戸時代から昭和初期までの絵幟のコレクション。初めての公開に期待感をもって
出かけたが、思った以上の迫力に圧倒された。男の子の初節句を祝い成長を祈念して作られた絵幟の大きいこと、数メートルを
超えるものも多数。展示には苦心しただろう。民芸館の壁面に天井から折り曲げられて吊るされていた。まさに”所狭し”だ。ぼくは青空に
はためく絵幟の勇壮な風景を想像した。藍や岩絵の具で描かれた絵柄は金太郎、昇り龍、七福神、鯉の滝登りと様々。こう育って
欲しいと願う親戚縁者の温かな心が伝わってくる。今も昔も子を思う心は変わらないと思うが、祈りを込め絵幟を立てるしきたりは
廃れてしまった。
200年前の文字幟、150年前の絵幟、約60点余りの展示は見ごたえ十分。幟の先に取り付けた小さな旗状のものが鯉幟の
原型だったとは知らなかった。
(Jun.1)
■麦が刈り取られ、裏の田圃に水が張られた (鳩山、アトリエ裏の田圃)
ついこの前までは土色だった畑に水が張られた。 銀灰色の水田に山影が映っている。視線の先の先の山が、こんなにも
近くに見えるとは。時折、鳥が風景を切り裂くように飛ぶ。銀灰色の鏡はその軌跡を映す。田植えは明日にも始まろう。
■二十四節気<芒種>、七十二候(二十五候、二十六候、二十七候)
 |
今年の芒種は6月6日 (夏至は6月 22 日) ・二十五候 (6月 6日) ・かまきり しょうず カマキリが姿を見せる ・二十六候 (6月11日) ・ふそう ほたるとなる 腐った草が蛍に姿を変える ・二十七候 (6月16日) ・うめのみ きばむ ウメの実が黄色に色づいてくる |
| ■5月のアトリエだより |
■茶畑の中のテニスコートへ
童美連テニス大会。西武新宿線入曽駅からテニスクラブまで茶畑を横切って近道を行く。ぼくのホームコートはハードと
オムニだから、久しぶりのクレーコートの土の感触が嬉しい。試合は4ゲーム。三勝一敗。
年々参加者が減って、春秋行われてきた大会が来年からは一回になりそう。絵描きも出版社の方々も高齢化。メンバーも
だいぶ入れ替わったが参加者数は減るばかり。残念だ。帰り道、茶畑も開発の波にさらされている現状を目の当たりにした。
コートが消える日も来るのか。
■『活版再生展』を見る
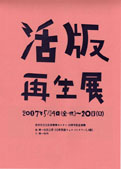 ・『活版再生展』パンフ (活版印刷)
・『活版再生展』パンフ (活版印刷)
30年前には印刷の主流だった活版印刷。オフセットや軽印刷、昨今のDTPにその座を奪われ完全に廃れた。
”活版の味”を知るデザイナーグループが世田谷の活版印刷所から活版印刷機を譲り受け、鉛の活字,込め物、締め具と
ともに展示。デザイナーによる活版を使用した作品も。(タイポグラフィー、詩集、ネームカードetc)本展のチラシは活版刷り。
文字には活字の圧力による活版特有のへこみが。鼻を近づけるとインクの匂いがする。
活版印刷に惹かれるのは、ぼくが活版世代だということ。(印刷はやがてオフセット、軽オフへ。グラビアは写真印刷で無縁だった)
当時、ぼくはプライベート ペーパー「童話工房便り」を活版刷りで発行していた。大学を出て、独立を考えアトリエ童話工房を設立。
イラストの仕事も少なく、毎月「童話工房便り」を制作してはクライアントや知人に送っていた。「童話工房便り」は20センチ角のクラフト紙
やラシャ紙、マーメード紙に、イラストと手書きの文章を墨一色で印刷した簡単なもの。それでも、内容は童話工房宣言に始まり、
創作状況、季節の便り、、童話、クラフト、料理とバライティー豊かだった。僅かばかりの収入は毎月、印刷代と切手代に消えたけど情熱は
熱くやる気満々であった。何より欲しかったのが表現の場だったのだ。
当時「童話工房便り」や私家本の印刷を頼んだ活版屋さんは池袋の保志生堂と新宿御苑前の中央プリント。いずれも封筒や名刺を
扱う小さな印刷屋さん。もう存在して居ないのでは。何しろ40年近くの歳月が流れたのだ。活版と聞くだけで思い出す。インクまみれの
親父さんのやさしい顔を。
『活版再生展』はぼくを興奮させた。青春の一コマ、創作活動を始めたあの頃を、昨日のことのように思い出させた。
(May.24)
■二十四節気<小満>、七十二候(二十二候、二十三候、二十四候)
エゴノキの白い花が咲いている。うっそうと茂る葉陰に見え隠れ、風が姿を教えてくれる。重なる葉をかきわけ
探す白い花、サルナシの花も今が盛り。ミツバチが働いている。レンゲ草の野から、わが畑にやってくる。
以前、ミツバチは家の壁の中に巣を作った。巣の周りを大群が群れ飛ぶさまは不気味、空を隠すほどだった。大げさに
言うのではない。巣の周りに集まるハチの羽音を耳が記憶している。壁中から室内の壁ににじみでた蜂蜜で部屋には甘い
香りが充満した。喜んだのはつかの間。その後、甘い香りに集まる虫たちに手を焼くことになった。その屋根裏の小さな部屋を、
ぼくはビーハウスと呼んでいる。 ビーハウスは空き部屋。未だ使用していない。
( MAY.21)
 |
今年の小満は5月21日 (芒種は6月6日) ・二十二候 (5月 21日) ・かいこ おきて くわを くう 蚕が桑の葉を食べるようになる ・二十三候 (5月26日) ・べにばな さかう 紅花の花が咲き乱れる ・二十四候 (5月31日) ・ばくしゅういたる 麦が育ち、麦畑が黄金色になる |
■新作の制作に入る。樹間より鳥の声、盛んなり。


公開講座のレジュメを大学に送り、鳩山へ。無人の庵に現れた人影に鳥たちがびっくり。
ライラック(リラ)が咲き始めた。白い花の周りをミツバチが舞う。ぼくの好きなスイカズラは今が盛りだ。紅色の
小さなラッパが揺れている。以前はこの場所で野生種が蔓をのばし甘い香りを放っていた。葉が茂る季節はスイカズラの
トンネルが出来るほどに育っていたが、迂闊にも草刈機でバッサリやってしまった。園芸種は花は鮮やかだが芳香がない。
ぼくの名前と同じ忍冬(スイカズラ)の、花を見るたびに、あの時の”そそっかしい自分の愚行”を思い出す。
(May.13)
■二十四節気<立夏>、七十二候(十九候、二十候、二十一候)
幼稚園の空に、こいのぼりが泳いでいる。風をはらんで大きく揺れる。紐がひきちぎれんばかりの勢いでうねっている。
この季節だけの風物詩。子どもの頃、新聞紙で鯉のぼりを作った。カブトや、パーンと音がするだけの新聞鉄砲も折った。
おもちゃはすべて作るのがあたりまえだった時代。 ”手工”の記憶は鮮明だ。
(May,2)
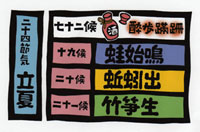 |
今年の立夏は5月6日 (小満は5月21日) ・十九候 (5月 6日) ・かわず はじめて なく 蛙が鳴き始める ・二十候 (5月11日) ・みみず いずる ミミズが姿を見せ始める ・二十一候 (5月16日) ・たけのこ しょうず 筍が生ずる |
■相模女子大公開講座
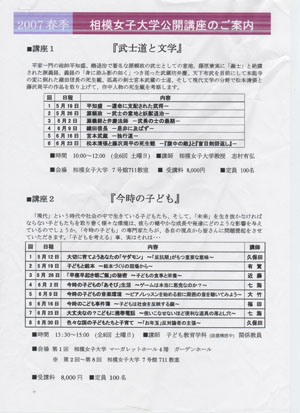
■会場 第1回 相模女子大学マーガレットホール4階ガーデンホール
第2~8回 相模女子大学 7号館711教室
■時間 :13:30~15:00(全8回 土曜日)
■講師 :こども教育学科(設置構想中)関係教員
■受講料: 8000円 ■定員 100名
(・第2回 5月19日 子どもと絵本~絵本づくりの現場から~で、有賀が講演)
| 4月のアトリエだより |
■『実践遊び学』のコンテンツを考える

 ←皿手前・土筆 後ろ・蕗
←皿手前・土筆 後ろ・蕗 先週組み立てた額(S30号2枚、S10号2枚)に電気サンダーをかけ、ミルキーホワイトで地塗りする。次作の構想を練りに
鳩山に来たが、ポカポカ陽気にアトリエに閉じこもるには惜しく、鶯の声を聞きながらの作業とあいなった。
手を休め、蕗の若葉を摘む。土筆も摘む。蕗の葉は細かく刻んで炒めよう。土筆は薄ピンク色に染まる酢の物や土筆飯に……。
食卓を想像してちょっぴり幸せな気分で摘み草に興じる。
夜は『実践遊び学』のメニューをあれこれ考えた。”手を使う” ”想像力を育てる”が基本。手と目と心を全開しての作業を楽しんで、
夢中になって貰えればそれで良い。”遊び”を真剣に考えるうちに、ぼくは知らず知らず鋏で紙を切り刻み遊んでいた。
風と遊ぶ、水と遊ぶ、光と遊ぶ、紙と遊ぶ、音と遊ぶ、木と遊ぶ………、それぞれの項目で、取り上げたい造型、工作、遊びが
沢山あって、一つ二つに絞らねばならないところが目下の悩みだ。
表現する”遊び”は創造行為なり。創造行為、表現の世界は無限だから面白い。何と楽しいことか。これを伝えたい。
(Apr.14)
■「実用家事宝鑑」 何事にも真剣、熱さが眩しい!
 ・「実用家事宝鑑」 帝国家事経済研究会 昭和9年刊
・「実用家事宝鑑」 帝国家事経済研究会 昭和9年刊 古書に遊ぶ。
この世は商業主義に流され欲望肥大化、生活は大きく変わった。利便性中心で失ったものも多いだろう。大量消費、飽食の時代
に生きる人の心からは、何時しか”後ろめたい気持ち”も消失してしまった。 面白半分に開く古の書物にほっとすることがある。
嗚呼、今宵も懐古の情が身中に疼く。今日は「家庭教育美譚」、「実用家事宝鑑」の二冊。
「家庭教育美譚」(明治31年刊) 勅語から始まるこの本、この辺りは飛ばし、拘らず、なるほどと思う所のみパラパラ頁を繰る。
巻末に「ワシントン(すべて漢字書き)の規箴(いましめ)」なる付録が掲載されている。「縦令(たとえ)仇敵(あだ)なりとも其の不幸に
罹る(かかる)時、己の満足を示す事なかれ」 「為す能わざる(あたわざる)事を選ぶ勿れ、唯約束を重んぜよ」 「良心と名くる(なづくる)
天の火を活かして、心を保つ事を務めよ」 等等。真っ当の事なれど、子どもの頃聞いた親父の言葉に似て、”耳にうるさく有難い”。
「実用家事宝鑑」(昭和9年刊) これは面白い。家庭食養編、家庭疾病編、廃物利用編に加え男女作法編や男女美身編なるものまで
ある。その中から1~2、タイトルのみ紹介しよう。
廃物利用編には、「枯松葉より結構な蒲団綿代用製造法」「柿の皮の陰干しは沢庵漬に妙なり」「柿のヘタは百日咳の妙薬、その製法」
と、わけの解らぬものから、一度試して見たいようなものまで、てんこ盛り。また、男女美身編には、「男女垢抜け法」「美顔水の製法」
「特に肌理(きめ)細かくする法」等怪しげな項目が並んでいる。馬鹿馬鹿しくて面白い。現代に希薄な生活感を、そして創意工夫する心を
そこに見るからだろう。
(Apr.6)
■二十四節気<清明>、七十二候(十三候.十四候.十五候)
現代童画会春季展出品作をとりに鳩山にくる。仕上げのマットバーニッシュをかけて乾くのを待つ。額装するまでの間、
外に出て春の柔らかな日差しの中を歩く。ミツマタの白黄色、水仙、菜の花、エニシダ、レンギョウの濃い黄色、モクレンの
赤紫、ムスカリの青紫が目に飛びこんで来る。薄桃色のアンズとスモモは終わったが、今盛りはプラム。白い小花が天に向かって
噴出すように咲いている。アンズは昨年、何粒かなって大喜びしたが、スモモもプラムも植えて10年になるが実をつけない。
東京では桜がほぼ満開だが、鳩山は寒く、2本ある染井吉野はまだ蕾開かず、花はちらほら数えるほど。満開も美しいが、ぼくは
この咲き始めが好きだ。道路沿いの山桜は開花が遅く未だ咲く気配がない。薄桃色の染井吉野と違って、こちらは薄墨色。華やかさは
ないが。”おしゃもじ山”を背にして煙るように咲く様は奥ゆかしい。
ローズマリーの茂みにコバルトブルーの宝石を見つけた。可憐な花だ。濃い緑に映えている。巣作りの場所を求めてやって来る
シジュウカラやヤマガラの鳴き声がうるさいほど。 春だ、春だ、新しい春だ。
お楽しみもこれまで……。モグラ塚を踏み固めながらアトリエにもどる。
(Apr,1)
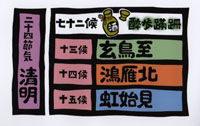 |
今年の清明は4月5日 (穀雨は4月20日) ・十三候 (4月5日) ・つばめ きたる つばめが南から渡って来る ・十四候 (4月10日) ・がん みずへ かえる がんが北へ渡って行く ・十五候 (4月15日) ・にじを はじめて みる 虹が見え始める |
| 3月のアトリエだより |
■ アルフレッド・ウォリス ARTIST & MARINER展 (東京都庭園美術館)
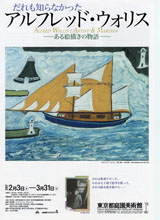 ・ アルフレッド・ウォリス 「青い船」1934年頃
・ アルフレッド・ウォリス 「青い船」1934年頃 ウォリスの絵が見られる。胸が高鳴った。1996年、世田谷美術館開館10周年記念展で見て以来だ。
今回はまとまって多数見られる。ぼくの目の奥に染みこんで消えないあの絵に遭える!
ウォリスは船乗りだった。絵を描き出したのは陸に上がり70歳を過ぎてからだった。画材は船に塗るペンキと
ボードや板切れ。モチーフは港や帆船、海、暮らしたセントアイブスの風景。すべて船乗りだった頃を思い出して
心の情景として描いている。
船より大きい魚、倒置した灯台、海を垂直に走る船、まるで幼児の絵をみているようだ。素朴、詩情……、
アカデミズムと対極の本能の絵画。ぼくは胸が詰まる思いで見入っていた。ウォリスは船乗りとして生き、
絵描きとして生きた。ウォリスの絵には生を貫いた強さがある。人生とは何か語りかけてくる。芸術と素朴、
芸術と素朴、芸術と素朴……、ぼくは考え考え、感激の展覧会を後にした。ウォリスの絵はずうっと見ていたい。
ぼくは木村忠太が好きだが、素朴さではウォリス。ため息が出るほど美しい!
(Mar.30)
■板絵『Daddy’s glove puppets』 完成間近

 ・S10号(53.0×53.0)板絵制作中 (鳩山アトリエ)
・S10号(53.0×53.0)板絵制作中 (鳩山アトリエ) すっかり春めいた。昼間は風がなければ快適。だが夜はまだまだ冷え込む。ストーブの火を絶やさないように、薪をくべに行く。
それ以外はアトリエから出ず板絵『Daddy’s glove puppets』の仕上げに入る。制作に没頭。ワインを飲み干し、ウイスキーも。
いささか飲みすぎ。案の定、今日は頭が痛い。
酔いを醒まそうと外に出ると、上の畑のOさんとバッタリ。朝収穫したキャベツを2個いただく。昼過ぎには、下の田圃の主Iさんが
奥さんと軽トラックでやってきた。「今年お初のヨモギ餅をどうぞ!」 Iさんは秋には栗の渋皮煮を、春にはよもぎ餅を毎年届けてくださる。
その度、忝い気持ちになる。ぼくには差し上げるものが何もないから。でも、とても嬉しい。深謝。早速、添えられていた黄な粉をまぶして、
2つ食す。よもぎの香り、春をいただく。
(Mar.25)
■二十四節気<春分>、七十二候(十候.十一候.十二候)
 |
今年の春分は3月21日 (清明は4月5日) ・十候 (3月21日) ・すずめ はじめて すくう 雀が巣作りを始める ・十一候 (3月26日) ・さくら はじめて ひらく 桜の花が咲き始める ・十二候 (3月31日) ・かみなり こえを だす 雷が鳴り始める |
■朝夕の寒さ……、1月下旬に逆戻り。アンズの花、今年も咲き始める。麗しや、薄紅色。
空晴れ渡りなんとなく気持ちまで明るい。日差しは春の到来を感じさせるが、昨日今日と北風が吹き荒れ、鳩山は
まだまだ肌寒い。アトリエに入る前に春の兆しを探す。菜の花、水仙、レンギョウ、サンシュユ……、黄色が鮮やか。
クリスマスローズのモーブやグレイピンク色の花が、ちぎれんばかりに揺れている。梅はいち早く春を演出。すでに
咲き終わり、代わりに桜の蕾が出番を待っている。鳩山は東京より10日~2週間程開花が遅いから、
枝々が桜色で埋まるのは制作中の作品が仕上がる頃だろうか。だと嬉しいが……。
アンズとスモモの花が咲き出した。(ともにバラ科サクラ属)アンズは去年は実を付けなかった。
実が成らなくても、アンズの花は目を十分楽しませてくれる。空に映える淡紅色は清らかな美しさだ。
今年の花の咲き具合からすると、大収穫の予兆……?いえいえ、花を見られるだけで満足!「よくぞ、咲いてくれました。」
今日は本当に寒い。1月下旬の気温だという。納得!風の冷たさに体は冷え冷え。退散する前に、
襟をたて手に息を吹きかけフキノトウを探した。収穫8個。今晩の酒が楽しみだ。蕗味噌を火で炙って”春の苦味”を頂こう。
(Mar.18)
■作業部屋は夢の入り口 ムットーニのからくり書物展 (世田谷文学館)
1995年、世田谷文学館は開館にあたってMUTTONIに文学作品をテーマにしたからくりボックスの製作を依頼。
萩原朔太郎「猫街」、海野十三「月世界探検記」、中島敦「山月記」の3作品をモチーフにした“自動人形”を常設展示してきた。
開館10周年の今年、MUTTONIこと武藤政彦の新作を含む10作品が、ルックスを落としたパーテーションで区切られた
特設会場で展示されている。
常設のからくり人形から、動き、音楽効果、光学(映像のコラボレーションが効果的)とも、格段の進化を見せている。人形は顔や、
腕を動かし回転しせり上がる。光はスポットライト、明滅、真空管の活用、半分に切ったミラーボールなど、自由自在だ。音響効果、
ナレーションの渋さも雰囲気を盛り上げている。
ぼくは夏目漱石『夢十夜』の第七夜、「漂流者」に見入って(聞き入って)しまった。「カンターテ ドミノ」には華麗な舞台に目を奪われ、
「ギフト フロム ダディー」の父親と子どもの物語は、懐かしさと温かさを感じ、憧れの思いで見つめていた。いずれの仕掛けられた
舞台も想像力を喚起させるものであった。
からくりボックスの部屋に入る前の通路にのぞき窓があった。暗闇の中にMUTTONIの人形が見えるか見えないかくらいに
浮かび上がるのだ。のぞき窓の一つはMUTTONIの作業部屋のミニアチュア。展覧会のパンフには本物のアトリエとムットーニに
自身が掲載されている。胸がわくわくする。仕掛けや人形の材料がごちゃごちゃ置かれている薄暗い小部屋だけど、ここは
夢の入り口だ。世の子どもたちが、こういう小部屋を体験したら、どう反応するだろう。ぼくには宝物が詰まった秘密の隠れ家に
見えるのだが。
夢の入り口といえば、絵本、アーサー・ガイサート著「銅版画家の仕事場」を思い出す。この絵本の”腰巻”のキャッチコピーは
”ようこそ、おじいさんとぼくの制作現場へ。………ぼくの夢はガレージから始まった………”。正に、仕事場は夢の入り口だ。
少年は冬になると、銅版画家であるおじいさんの、年一度のスタジオセール(仕事場に作品を展示して販売)のお手伝いをする。
少年の役目は、おじいさんの刷り上げる版画に一枚一枚手彩色すること。仕事場の様子や銅版画制作手順が、銅版のイラストで
描かれているが、何より物を創り出すおじいさんと少年がいい。淡々と作業をこなしていく二人。これが幸せの形なんだと感じさせる。
高価なおもちゃなんかいらない。がらくたが雑然と転がっている作業部屋、秘密の隠れ家こそ、少年の夢の入り口だ。
銅版画家も、MUTTONIもアトリエでは歳をとるまい。
(Mar.12)
■講演会「シュタイナー教育がモテる理由 ドイツの”いま”を取材して」子安美智子
クレヨンハウス(青山)の会場は満員。聴講者の熱気が溢れていた。7歳までを第一・七年期、十四歳までを第二・七年期、
二十一歳までを第三・七年期と呼ぶシュタイナーの人間観。第一・七年期の意志、「からだで模倣させる」、第二・七年期の感情、
「感じとらせるように学ばせる」、第三・七年期の思考、「思考力、知力、判断力をつくりだす」、知・情・意のバランスのとれた
人間を育てようというシュタイナー教育のあらましに続いて、シュタイナー学校の先生、牧師でもある○○○(名前は忘れた)の
著書から、子どもとのエピソードを3つほど語った。これは解りやすく、ぼくも感じるところがあった。
「ミュンヘンの小学生」で日本に初めてシュタイナー教育を紹介した子安美智子は73歳と年齢を口にしたが、とても信じられない。
90分、背筋はピンと伸ばしたまま。情感豊かな語りかけは最後まで聴衆を魅了した。立ち聞きの人も多かったが、要望されるまで、
シュタイナー教育がそうであるように、マイクを使おうとしなかった。聞いた年齢の逆数の若さだ。
講演の終了まぎわ、2008年春開校の「あしたの国ルドルフ・シュタイナー学園」についての思いを話した。房総半島に
21万坪(東京ドーム15個分)の規模。”頭、こころ、手足あらゆる感覚をまるごと使って学ぶ学校”だという。パンフの一部を
引用する。「明るい陽光、たっぷりの自然に恵まれたこの学校では、入学する子どもたち一人ひとりをかけがえのない存在として
迎え入れ、卒業の暁にはだれもが自分の生まれて来た意味に気づき、たくましく力を発揮する人間に育っているようにと、愛と
英知で子どもたちをささえつづけます。日本と世界の未来にとって歴史的な出来事となる学園の誕生に、みなさまのご関心と
ご協力をお寄せくださいますよう」
シュタイナー教育の関連図書は何冊か読んだが、ぼくが信州の小学校で3年生までに体験したことのように思えるから
不思議だ。素晴らしい先生との”幸せな出会い”が、ぼくにはあったということだろう。
(Mar.7)
■二十四節気<啓蟄>、七十二候(七候.八候.九候)
今冬の天候は記録ラッシュだった。平均気温は平年を大きく下回り、降雪量も全国的に観測史上最小。東京は
とうとう初雪も見られないまま、弥生3月を迎えた。
七十二候では草木萌動(3月1日)。まさに草木が一斉に芽吹き、野山が枯れ木色から草緑色に変わって行く季節の
到来だ。”山笑う”の季語、言いえて妙なり。
鳩山のアトリエの北斜面は杉の林だ。ぼくは”スギ花粉製造元”にいるわけだ。くしゃみが出る。鼻も頻繁にかむ。目も
かゆい。何度、この杉を切り倒してしまおうかと考えたことか。でも、ぼくは杉だらけの信州の田舎で育った。子ども時代は
何ともなかったではないか。柔な自分を叱る。
「杉よ、もっと花粉を撒き散らせ!」 今、ぼくは開き直っている。
(Mar.5)
 |
|
| 2月のアトリエだより |
■集中のあまり?忘れ物
あちこちで梅の花がほころび、春の気配。ポカポカ温かい日差しに誘い出されるように鳩山へ。今日は電車で行く。エスキース
した10号のパネルを抱え背中には黒のリュック。意気揚々だ。「鳩山では思う存分制作するぞー!」
ところが、事はすんなり運ばない。山手線の電車の荷物棚にリュックを置き忘れてしまった。中には本が3冊。カメラ、携帯、
筆記具など。池袋駅で東上線に乗り換えようと、改札を入ったところで気がついた。
大慌て、駅の事務室に急ぐ。「今、品川あたりかな」ダイヤグラムを見て、駅員さんは先々の駅に電話。荷物棚を見てもらう
ように頼んだが、いずれの駅もラッシュアワーで無理だと断られてしまった。
しょげていると、駅員さんは「山手線は1時間で一周して来るから、お客さんが自分でしらべては。」と言う。駅員さんが該当
すると思われる4本の電車の到着時間を紙に書いてくれた。ぼくは4本の電車に前後の2本も加え、それらの6~9号車をすべ
調べた。乗降客に睨まれながら飛び乗り飛び降り、午後6時台の人がごったがえすホームを駆け回った。
見つからず。落胆!
電車での忘れ物は初めてだ。なぜ忘れたのだろう?居眠りはしなかった。リュックは棚に置いたがパネルは抱えていた。思えば、
ずうっと制作の事ばかり考えていた。何処から彫り始めようか?マチエールは?色調は?表現したいメッセージ、画題まで……。
それは、ぼくにとって神経が集中する幸せの時間なのだけれど……、思い巡らすのはアトリエの中だけにすればよかったのだと
後悔しても後の祭り。
カメラも惜しい。携帯も滅多に使わないが、なくては困る。3冊の本もまだ読んでない。サンフランシスコのシュタイナー学校での
講演をまとめた、ルネ・ケリードー著「シュタイナー教育の創造性」。A.Jツワルスキー著「スヌーピーたちの性格心理分析」。それに、
何故こんな時に持ってきたんだと悔やまれる古書「妙薬植物図鑑」。
鳩山に着いても気分は沈みっぱなし。それでもと、奮い立たせウイスキーを持ってアトリエに入った。昼間とうって変わって寒い。
ぞくぞくするほど冷え込んで来る。ストーブをつけても暖たまらず、ついついウイスキーに手が伸びてしまう。遮二無二、板を彫る。
朝起きた時、「昨晩はよくやった」と思えなくては、その日が辛くなるから、目一杯、彫る。これはいつもの事。
彫刻刀は丸刀や三角刀を使うが、少しくらい酔っ払っても怪我をしたことはない。掘り進めている内に、絵以外の事に思いは
至らなくなっていた。情けない気持ちは、仕事を終え酩酊して眠りにつく頃には消えていた。
昼過ぎ、電話が鳴った。鳩山に電話が掛かる事は稀。訝りながら受話器をとると、池袋駅からだった。「リュック、見つかりましたよ。
大崎駅に保管してあります。」聞けば、ぼくが調べた6本の電車の他に、その時間帯に大崎止まりが1本あったのだと言う。ラッキー
だった。山手線をグルグル循環している内に、リュックは誰かに持っていかれてしまったかも知れない。大崎の車庫にそのまま
入ったなんて……。ぼくはすっかり嬉しくなって小躍りして、アトリエに入った。
(Feb.28)
■二十四節気<雨水>、七十二候(四候.五候.六候)
昨日(14日)関東から九州にかけて春一番が吹いた。(初雪観測前に吹いたのは観測史上初めてだという)東京は17度を
超えた。春一番は立春から春分の間に吹く南の強風。渋谷の仕事場から、道行く人々が風に難儀しているのが見えた。
風のせいではないが、今日は外出せず、部屋に籠りっきりだった。
そして今日(15日)、運動不足解消にと、一週間ぶりのテニス。コートは昨日に劣らぬ強風が吹き荒れていた。コート
サイドのベンチが風に倒され飛ばされていく。サーブもラリーも風に翻弄されテニスにならず、早々に退散する。天はぼくを
仕事場に戻れと命じたのだろう。板絵のラフスケッチやクレヨンまるのアイディア、それに講義のテキスト作り等々、山積。
季節の移ろいを感じ、身を浸し、心静かに詩画を創るゆとりが、今のぼくにはない。哀しいことだ。
(Feb.15)
 |
今年の雨水は2月19日 (啓蟄は3月6日) ・四候 (2月19日) ・つちが うるおいおこる 土が湿り気を帯びてくる ・五候 (2月24日) ・かすみ はじめて たなびく 春霞がたなびき始める ・六候 (3月1日) ・そうもく もえうごく 草や木が芽吹き始める |
■雑誌の山と格闘す!
毎日のように仕事場で探し物をする。物忘れもあるが、物置と化した部屋に問題がある。特に雑誌の山。出版社から毎月
送られてくる幼児雑誌が、マンションの低い天井まで届いている。数えてみたら毎月十数誌。季刊のものもある。
昔は処分していたが、ここ二十年は片付けていないから、幼児雑誌のバックナンバーは完璧に揃っていることになる。
感心している場合ではない。単純計算で一年で200冊、20年で4000冊?まさか、そんなにはないと思うが、空間確保のため、
”大移動”を決意。束ねた雑誌を持って資源置き場に向かう。が、躊躇。
自作『こんなこいるかな』や『あっかんぶーのスブタン』の掲載誌まで捨てるのが忍びなくなったのだ。
たとえば、『こんなこいるかな』は「おかあさんといっしょ」や「えくぼ」、「おともだち」や「げんき」に1986年から20年近く描いている。
『あっかんぶーのスブタン』は「テレビといっしょ」や「めばえ」で連載したぼくの一番好きなキャラクターだ。過去は過去だけど、
掲載誌を捨てるのが憚かられたのは愛着。それに雑誌の”量”だったかもしれない。ぼくはこの雑誌の山を鳩山のアトリエに
移すことにした。これは”覚悟”だ。鳩山の一部屋がこの馬鹿馬鹿しい量の荷物で埋まるのだから。
今日、その第一陣。一年分の束を手始めに30個ほど運んだ。腰が痛み、帰りの運転はとても辛かった。この続きが思いやられる
それで、成果は?空間確保は?……まだまだ。渋谷の仕事場の床は顔を見せない。雑然とした部屋は少しも変わらない。雑誌を
収める棚も作らねば落ち着かない。運送と大工……、鳩山での絵描きはしばらくお預けだ。
(Feb.5)
■二十四節気<立春> 七十二候(一候.二候.三候)
2月になっても雪が降らない。記録的なことらしい。喜んではいられない。世界各地で異常気象。地球温暖化が叫ばれているが、
改たまる気配なく地球の環境は悪くなる一方だ。「私は温暖化ではなく”高温化”と言っている」と、塚本こなみ氏(あしかがフラワー
パーク園長)が新聞に書いていた。確かにそうだ。温暖化では甘っちょろい。温暖と言う言葉には緊迫感がない。温暖の地は
寒冷の地より住みやすいイメージがあるから。ぼくもこれからは”高温化”と言おう。そして何が出来るか、考えてみよう。
厳しい寒さがあっての立春だ。「春は名のみの風の寒さや~」……、高温化で、歌も歌えない。
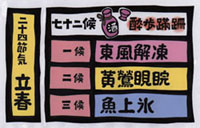 |
●今年の立春は2月4日 ・一候 (2月4日) ・とうふう、こおりをとく 春風が吹き氷を解かす ・二候 (2月9日) ・うぐいす、なく 鶯が鳴き出す ・三候 (2月14日) ・さかな、こおりにあがる 魚が氷の間から姿を現す |
| 1月のアトリエだより |
■23名の学生を誉めた。作品にその人らしさが出ていればすべて佳し。
 ・学生の提出課題「手作り絵本」の一部
・学生の提出課題「手作り絵本」の一部 大学の秋学期の講義最終日。本日の欠席者は2名。期末試験の真っ只中なのに全15回の授業で一番の出席だ。ぼくは
胸が熱くなった。課題制作「手作り絵本」を一人一人講評して返していく。”作者”をぼくの隣の席に呼び、自作を語らせる。
鑑賞者は”作者”の苦心したところや絵本作りの感想を聞き拍手を贈る。もちろん絵本制作なんて皆初めてのこと。小学校以来
絵など描いたことがない学生が、よく自己表現をしたものだと思う。「想像は創造に通ずる。オリジナル……たった一つの宝物。
絵は巧拙で見ない。自分の気持ちに素直に。子ども時代を思い出せ。表現は自由な心から。孤独の中で自分を見つめる。美意識
や価値観をしっかりと。完成よりもプロセスを楽しめ。頭ではなく手を使え……リアルな体験や感動を!」等々、授業はしばしば
絵本の話を超えて行ったが、学生たちの心に少しは響いただろうか。学生は課題制作「手作り絵本」の他に、授業でミニ絵本を
3冊制作している。それはハードな半年であったろう。が、それこそ皆”リアルな体験”をしたのだ。自信になったと思う。
達成感、満足感、作品への愛着を口にした者がいた。胸がさらに熱くなった。ぼくは今日23名、皆を誉めた。
(Jan.31)
■作業台の足を製作
 ・”足”を製作中。もう一組作り、オイルステインを塗る
・”足”を製作中。もう一組作り、オイルステインを塗る
板絵の彫りの段階はパネルを横にして作業する。そのために180センチ角の天板を作製し使ってきたが、
天板の重さはかなりのもので、4本の足にガタがきてしまった。30年も使い続けたからなあ。
グラグラするのを我慢していたが、応急で取り替えることにした。2×4のランバーウッドを丸鋸でカット。
金属のブラケットに取り付けクロスバーを渡すだけ。クロスバーの長さは随意。使用勝手が良いので、ランバーレッグを
二組(8本)作った。一つはワークデスク、もう一つは庭のテーブル用にと。しかし庭のテーブルは本来の目的に使われる
ことがあるだろうか。木漏れ日の下でゆっくり時間が流れる……食べて飲んで微睡……なんて今のところ夢だ。嗚呼、
ぼくの生活はせわし過ぎる。忙しいという文字は、心を亡ぼすと書くのに……。亡びる前にテーブルを使わねば……。
(Jan,23)
■『命を守るデザイン展』 世田谷文化情報センター ワークショップA・B


・アルマジロの体の模様はすべてピクトグラム ・朝日新聞1月19日朝刊
『命を守るデザイン展』(DESIGN TO PROTECT LIFE EXHIBITION Vol.01)を見る。ピクトグラムとは
絵文字のこと。非常口のサインや交通標識、ペットボトルにあるリサイクルマークなど、ありとあらゆるピクトグラムを紹介し命を
守るデザインについて考えてもらおうという催し。展示はクイズ形式になっており、入り口で渡されるブックレットに答えを記入
しながら見て廻る仕掛け。この試み、ピクトグラムに興味を持ってもらおうとの強い使命感からだろう。”あなたがもし「分かり
にくいな」と思うものがあったら、その事を是非私たちに伝えてください。”と姿勢は極めて前向きで真剣だった。
非常口のサインが日本でデザインされたものが世界共通に使われているとは知らなかった。(言葉や年齢、経験や学習の
程度を超えて一目で理解できるピクトグラムを作り、世界共通のものにしようという、世界的な流れを受け、日本政府は
1980年に「非常口」のサインのプロトタイプを、日本案として国際標準化機構(ISO)に提出した。)
ピクトグラムのデザインは視認度、理解度、記憶度、調和度の4ポイントが欠かせないという。日頃目にする小さなマーク、
家庭用品、医療器具、乗り物、街づくりなど、それら命を守る取り組みが深い思いでなされていることを知った。目が見えない
人に危険を伝える試みや、今話題になっている自動体外式除細動器(AED)のマークデザイン、今後の可能性まで、展示は
意義あるものであった。 (第2回『命を守るデザイン展』は2007年9月の予定)
朝日新聞19日朝刊6面では、ウイーン市におけるピクトグラムをめぐるもめごとを紹介している。「男女平等標識に”黄信号”」
公共交通機関の優先席の表示にクレームがついたのだ。問題のピクトグラムは、お年寄り、障害者、子ども連れ、妊婦のマーク。
日本でもお馴染みのものだ。
”男女平等”ということから、お年寄りと障害者が男性から女性に変わり、子ども連れが女性から男性になった。おかしいのは
道路工事を示す標識。男の作業員のデザインが、スカートをはいた女性になっている。もちろん手にはスコップ、土の山をすくって
いる。見慣れないというより、何か不自然。地下鉄のマークも男性が走り出す、よく見かける緑色のマークを、ポニーテールで
スカートにブーツ姿の女性のものも作った。笑ってしまった。非常時、咄嗟に避難するのだ。男とか女とか問題にするなんて
ナンセンス。”人間が”走り出すマークで、十分!なんら問題はないではないか。
ちなみに、朝日新聞の記事は不親切。スカート、ブーツ姿の表示はEU基準に適合せず。また、ポニーテール女性労働者の
工事中の標識も交通規則により使えないとあるが、どうせなら、その辺を詳述してほしかった。どんな基準、規則?これまた、
おかしいものだったりして……。
日本も近年、ジェンダー問題に敏感過剰。意識下からわざわざ”差別”を引っ張り起こそうとしているように思えてならない。
(Jan.19)
■二十四節気<大寒>、七十二候(七十二候.七十三候.七十四候)
昨日の雨は10日ぶり。よいお湿りに乾燥注意報も消えた。雲間に寒々しい空色。風穏やか、傘を干す。(Jan.18)
 |
●今年の大寒は1月20日 ・七十候 (1月20日) ・ふきのはなさく 蕗の花が咲く ・七十一候 (1月25日) ・みずさわあつくかたい 沢の水も寒さに氷る ・七十二候 (1月30日) ・にわとりとやにつく 鶏が卵を抱く |
■『掛図にみる教育の歴史』展 (玉川大学教育博物館)
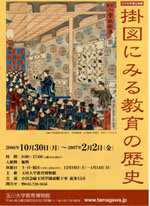 ・2006年10月30日(月)~2007年2月2日(金)
・2006年10月30日(月)~2007年2月2日(金) 玉川大学教育博物館は駅から続く広大な敷地の一番奥にあった。玉川学園駅から20分近く歩き、
キャパスに入って三度も道を訪ねた。山を切り開いたのだろうか、坂道が多く迷うほどの広さだ。中学や高校の校舎の
斬新なデザインには驚いたが、小さなゴミひとつ落ちていないのは何故?その謎はすぐに解けた。中学生か高校生か、
学生があちらこちらで、散り落ちる枯葉を箒で掃き集めていたのだ。外人の先生も一緒に。義務感からというより楽しげにさえ
見えた。博物館の入り口にさりげなく掲げられていた教育方針と言おうか学校の目指す道に、思わず足を止め見入って
しまった。そして納得。
『掛図にみる教育の歴史』展
掛図とは教室に掲げる学習資料。明治初年から昭和期まで使用された掛図数十点の展示。初期文部省発行掛図の
単語図、連語図は和紙に木版刷り。博物図は銅板墨刷り、木版色刷りした手が込んだもの。例えば、第一~第四
博物図(全葉之形や穀物之類や根塊之類、海草類など)。いずれも美術品のように美しい。子ども達に向かう姿勢の
熱さを感じる。明治初期の掛図、検定教科書時代の掛図(明治19~36)国定教科書時代の掛図(明治37~昭和20)と、
次第に軍国主義的性格を打ち出したものになって行く様子が、わかり易く展示されていた。
ぼくが小学生だった昭和20年代後半頃の掛図も見たかったが、第五学年用小学理科掛図一点のみで残念だった。が、
大判で損傷しやすく保管も容易でない掛図を、よくもまあ収集したものだと改めて感心。有難いことだと思った。
教育に携わる者、文部科学省の役人みなに、この展示を見てもらいたいなあと思った。掛図を作った者の真剣さが痛いほど
伝わって来るから。
(Jan.17)
■2007年の二十四節気<小寒>、七十二候(六十七候、六十八候、六十九候)
「気候」という言葉は、二十四節気の”気”と七十二候の””候”がもとになっている。
めぐり来る季節、日一日夜一夜(ひひとひ、よひとよ)花鳥風月を愛で、日々是好日と感謝する心を
忘れぬよう、また、酔生酔歩の身を自省。更には現代社会の流れの速さを、僅かばかり止めて
みようと、ここに季節の言葉を書き記して行く。
(Jan.15)
 |
●今年の小寒は1月6日。(大寒は1月20日) ・六十七候 (1月6日) ・せりさかう 芹が青々と生える ・六十八候 (1月11日) ・しみずあたたかさをふくむ 泉に温かさが残っている ・六十九候 (1月16日) ・きじはじめてなく 雉がメスを求めて鳴く |
■日頃気づかぬ葉っぱの美しさを絵本で知る
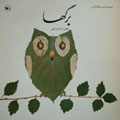




左の写真は『はっぱ』(モテルザ・エスマイリ・ソイ作)。実物の葉っぱをコラージュして制作した手作り感覚溢れる絵本。色々な
葉っぱを重ね貼りして、クジャク、ウシ、オウム、ライオン、チョウチョウなど18の動物を描いているが、文字は一切なし。葉の取り
合わせ、色、質感がよい。
葉っぱはすっかり動物になりきっている。子どもたちは身近な葉っぱの変身ぶりに「これは~だ!」と歓声をあげるだろう。そして、
葉っぱのコラージュに興味を持った子どもは自分でもやってみるかもしれない。絵や写真と違って想像させる楽しみをもつ葉っぱの
動物達。正しくキャプションは不要だ。
大学の授業で絵本の継起性、連続性について触れるが、この本は連続性の好例。幼少むきの文字のない絵本の好例でもある。
『葉っぱのきもち』 文/ヨゼフ・グッゲンモース 絵/イルムガルト・ルフト こちらはコラージュはコラージュでも版画の技法で
葉脈を刷り取り造型した絵本。いわば”葉の拓本”だが、とても新鮮。ハシバミの葉、シラカバの葉、ハンノキの葉、ヤナギの葉、
ニワトコの葉、オオバコの葉……それにカエデの種までも使われている。葉は木から離れ風に運ばれ海に落ちる。海は葉っぱたちを
海の生き物に変える。タンポポは魚の体、イチョウは尻尾……。大小様々な魚の誕生だ。レントゲンで写したような透明感ある魚の
体は淡い色合いが見事。柔らかそうなインクブルーのクラゲの造型などため息が出るくらい美しい。
この絵本、ストーリーも良いが絵が素晴らしく、絵本はやはり絵だと思わせる。『葉っぱのきもち』のタイトルも好翻訳だ。
”葉っぱ”をモチーフにした絵本といえば、『葉っぱのフレディ』も取り上げたい。アメリカの哲学者、レオ・バスカーリア博士が書いた
生涯一冊の絵本だ。副題は---いのちの旅---。先に挙げた二冊と違って、こちらはベストセラーだが、ここでは作者のメッセージを
記すに留め、絵本の紹介はまたの機会に譲る。
-----この絵本を死別の悲しみに直面した子どもたちと、死について適格な説明ができない大人たちそして、編集者バーバラ・
スラックへ贈ります。ぼくは一本の木であり、バーバラはこの十年間かけがえのない葉っぱでした。 レオ・バスカーリア-----
(Jan.13)
■枯葉舞い落ち舗道に踊る
喜多見の自宅を出て渋谷の仕事場まで車を走らせる。世田谷通りの砧あたりの街路樹はモミジバフウ。フウ(楓)の実は形が
独特。3~4センチの球形で棘が放射状に出ている。ウニのような形が面白く以前、拾ってリースのオーナメントにしてみたが、
細かな種が粉のようにこぼれ落ちて困ったことがあった。
今、街路樹は剪定の時期。職人がバサリバサリ、切り過ぎではないかと思う位、枝を切り詰めていく。赤い大きな葉が舞い
落ちる。きれいな暗紅色。車を止めじっくり眺められないのが残念だ。
萌える若緑から深緑。黄色、紅色、朱色……枯葉色。四季の移ろいを木々の葉が語る。その葉っぱを使った魅力的な絵本がある。
一つは実物の葉をコラージュしたもの。もう一つは葉に色を塗り刷りとったいわば葉の拓本のような絵本。これは新鮮。
日頃気づかない葉脈の美しさを画面いっぱいに見せてくれる。葉っぱを魚に見立ててのファンタジックな絵本の紹介は、近日この欄で。
(Jan.11)
■菩提樹の小枝にガラス玉の輝き (鳩山)




美しいものを見た。早朝の庭、霜柱をサクッ サクッ……。長靴の底から伝わる響きを楽しみながら歩く。
ふと見上げればキラキラキラキラ無垢の輝き!菩提樹の枝先に付いた小さな透明の氷の粒が朝日を受けて
光っているのだ。リンデンの芽という芽に宿った氷の粒はガラス玉、いや小人の国のランプシェード。清らかさにおいて
ダイヤに優る。溶けてなくなる”氷の精”の儚さは、潔さの美とも言えよう。いいものを見た。心洗われアトリエに戻る。
(Jan.7)
■新年早々、テニスコートにボールの音響く
冬晴れ、穏やかな日差しに誘われ初打ちに。コートは大賑わい。テニスの仲間の中には3日のオープンから来て
いたという者も。みな熱心だ。ぼくも意気込んで行ったものの、鈍らな体よう動かず。正月は酒漬けだった故に運動神経麻痺
状態。初戦惨敗も応報なり。30年来上達なしのテニスの腕前。されど人並みに向上心は有せり。今年も目標は掲げた。先ず
サーブのスピードアップ。サーブ&ダッシュ。それに苦手なボレー。嗚呼……、早くも課題を忘れかけている。こちらの方が
問題なり。幕開け早々反省多々。
仕事上々なればテニスも好調だろうにと押っ被せ、ぼやくこと頻り。こちらもまた年来進歩なし。
(Jan.5)
■明けましておめでとうございます。新春吉祥祈願 平成十九年元旦
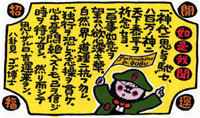
酔眼で戯言、朦朧として雑感……今年も吐露します。本当はぼくが心揺さぶられた温かい話を書きたいのですが、
なかなかそうも参りません。小さな喜びを、小さな幸せを、日々見い出して過ごしたいものです。本年もどうぞよろしく。
(Jan.1.2007)
| 12月のアトリエだより |
■テニス打ち納め。雲ひとつ無い青空なれどクラブ閑散
年の瀬、寒風の中テニスクラブへ。今年の打ち納め。唯一の趣味とはいえ、よく通ったものだ。午前中の
2~3時間だけだが、その回数127回。カレンダーを見ると、2002年105。2003年112。2004年79。
2005年89の丸がついている。この5年間の平均が102回だから、今年はやはり多い。他に童美連テニス大会、
春秋のUP&DOWNテニス大会にも顔を出しているから、やりすぎだろう。来年は少しセーブしよう。肝心の腕前は
進歩なし。30年やってどうしようもないのだから、神は努力を認めないらしい。絵は表現する行為がすべて。テニスも
そう考えると気が楽だが、ゲームは戦い。たまには勝たなくては……。
お相手して下さった皆様、ありがとう。新年もどうぞよろしく。
(Dec.29)
■師走、もはや数え日。鳩山日帰り、慌しく
来年の制作準備。木製パネル、額用木材を運搬する。ホームセンターで金物やボンドを購入。
例年正月は鳩山で過ごすが、今日その為の用意をする。デッキの下から丸太を引っぱり出しチェーンソウで
切る。斧で割り三日分の薪を確保。普段会う機会が少ない二人の息子も正月やってくるが、ほとんど寝正月を
決め込むから、力仕事もぼくがやっておくしかない。一息入れる間もなく、おととい降った雨の浸水の後始末をする。
今年は餅を搗く余裕がない。土間で臼と杵が年一度の出番を待っているが勘弁勘弁。とうとう今日はアトリエに
入らずじまいだった。掃除とアトリエ開きは正月にすることにして、深夜東京に急ぎ戻った。
(Dec.28)
■レイモン・サヴィニャックのポスターを見に
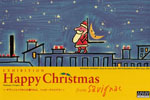
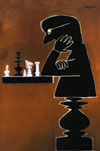

叩きつける激しい雨の中、レイモン・サヴィニャックの作品を見に渋谷パルコまで。ロゴスギャラリーに辿り着いた
ときはもうずぶ濡れ。ポスター(リトグラフ)40点とボードに描かれた原画5点程の展示。レイモン・サヴィニャックは
戦後フランスを代表するポスター作家。1949年、注文なしで牛乳石鹸のポスター”モン シャボン”を制作。雌牛の
乳房が石鹸に繋がっている、あの有名な絵だ。これでサヴィニャックは一躍名声を得る。以来、エールフランス、
シトロエン、ペリエ、オリベッティー、チンザノ、エルメスなど様々な企業広告ポスターを精力的に制作した。日本でも
サントリー、豊島園、森永製菓など手がけている。
誰でもサヴィニャックの絵だとすぐ解る温かみのある絵は、ユーモアがありウイットに富んでいる。ポスター全盛
だった頃のパリの街路の広告塔や地下鉄の壁で、単純な構図、おおらかな筆致のサヴィニャックのポスターは
さぞかし多くの人々の目を楽しませたことだろう。
デジタルがグラフィックの世界でも主流になり”手描き”はPCイラストに追いやられ影も薄い。しかしながら
サヴィニャックの絵は古くはないし、心に染みこんで来る。人の手わざそのものの絵だから温かい。
ギャラリーにいたのは1時間ほど。雨は激しさを増していた。傘も役立たず全身びしょびしょ。濡れ鼠になって
震えて帰った。後で新聞で知ったのだが、この雨、東京都心で154.5ミリも降ったそうだ。12月としては
異例。一日の降水量の記録を三十数年ぶりに塗り替えた大雨だった。
レイモン・サヴィニャックは2002年に亡くなった。(1907-2002)新作はもう見られない。
(Dec.27)
■枯葉舞い落ちる初冬のキャンパス
大学構内のイチョウ並木も大方葉を落とし、あちこちに掃き集められた黄色の山。ついこの前、この舗道は
銀杏が降るように落ち、踏みつけられ異臭を放ち汚れていた。
沿道に黄色の絨毯が残るまっすぐ伸びる道を、校門から校舎まで空を見上げながら歩いていく。
いつもよりゆっくり……。
文句なし!見事なスカイブルーの冬空だ。時折、イチョウの葉が枝を離れ音も無く舞い落ちてくる。
白に黄に金色に光ながらヒラヒラ……、フワリフワリ……。美しさに足を止め、落葉の行方を目で追った。
風の大サービスか、たまに時間をかけて枯葉を舞い躍らせてくれる。長い滞空時間といっても、
ほんの僅かなものだけど、”目を凝らし見つめる”ひととき。ぼくの顔はきっと柔らかな表情になっているだろう。
今年最後の授業。深呼吸一つして教室に向かう。
(Dec.20)
■第32回現代童画展(東京都美術館)始まる。 詳細は■展覧会案内へ ■板絵へ
2日間に渡る審査、会員総動員の陳列、そして開場!第32回現代童画展が始まった。このところ連日
都美術館詣でで仕事にならず。今日4日は贈賞式と懇親会。レセプションには九州他、遠い地から出品者、
受賞者が多数参集。熱き情熱に興奮する。賞を授与後、簡単なスピーチをする。
・現代童画展贈賞式メッセ-ジ
受賞者の皆さん、おめでとうございます。27名の受賞者の他に現童通信の速報には賞の候補に
あがった方の氏名も掲載されています。候補作の中には、1~2票の僅差で賞を逃した優劣の付け
難い作品もありました。来年度を期待します。頑張ってください。
受賞された方は賞を励みに一層精進して下さい。又、賞候補にあがった方もこれを機に
さらに努力を重ねられますように。
とは申すものの、あくまで賞は二の次三の次。決して目的ではありません。作家の制作姿勢
としては黙々と描く、表現する、発表し続けること、これに尽きます。
現代童画会の”童”は、童心の童、わらべです。幼児が一心不乱になって遊ぶ、夢中になって絵を
描く……その時の心は純です。無垢です。そんな精神状態で作家は絵に臨みたいものです。人の目や、
評価や賞、審査の思惑など気にしないで、表現することのみに執念を燃やして下さい。
回を重ねる事、32回……。現代童画会も歴史を刻んで参りました。時が経つと、とかくレッテルが
貼られがちです。先日”現代童画風”と言う言葉を耳にしました。こんな”~風”と一括りされては
たまりません。勿論”現代童画風”の絵と言うものはありません。現童は、作家個人個人の異なった
世界、異なった表現を徹底追及した作品にスポットを当てて参ります。
皆さんは心の内なる声に耳を傾け、世俗の声には時に耳に蓋をし、大人になって付いた余計な物を
そぎ落とし、表現上は飽くまで、我侭に徹して描いて行って欲しいと思います。もっともっと我侭に!
どうか、キャンバスに覚悟を決めて臨んで下さい。
(DEC.4)
| 11月のアトリエだより |
■紅葉はまだまだ。今年は初霜を見る頃になるのだろうか?



現代童画展(12月2日~9日、東京都美術館)出品作を運送業者に渡すため鳩山のアトリエへ。曇天、風もなく
穏やか。時折射す薄日に冬の到来が間近いことを感じる。渋柿の木に小鳥たちが寄ってくる。熟して甘くなったの
だろうか、盛んに食べている。地面に落ちた柿の実には一様に突いた跡が。ちょっと食べては又別の実を突く……。でも
食べ散らかした柿を掃き集めるのは苦ではない。静かな秋の昼日向、小鳥の声が嬉しくて。
(Nov.18)
■板絵『瞬幸永憶』完成。心に満つるものあり。
 ・板絵『瞬幸永憶』完成。アトリエで独酌。酔眼戯言。
・板絵『瞬幸永憶』完成。アトリエで独酌。酔眼戯言。 秋雨と冷たい風に身が震える。アトリエの中も外に負けず冷え冷え。風通しのために少しだけ開けておいた
窓から、容赦なく雨が吹き込んでいる。濡れた床を拭きストーブで手を温めてから、『瞬幸永憶』の額装にかかる。
昨年より一週間ほど早い仕上がりだ。
この後の独りだけの楽しみ。絵を眺め酒を酌む”儀式”……、ぼくにとって一番の幸せの時を過ごす。作品と向かい
合い、語りを聞き、話しかける……。いつも、忙しく過ぎ去る日々だが、この時ばかりは流れは止まるようだ。頭の
中は絵のことだけ。頭といっても、自意識は薄れているから、ただ絵を見つめる行為に没頭。至福。之に優る状態なし。
今宵の酒は地元、毛呂山町の「名栗川」と小川町の「帝松」。したたかに飲み酩酊せしも、アトリエを出る気起こらず。
秋の夜は更け行くも、まだまだ長し。
雨音は消えたが、風は増して激しく荒ぶり叫ぶ。山のアトリエに独り居、画家の”幸いなる孤立感”心底から覚ゆ。
東京では12日午前4時5分、木枯らし1号が吹いたと気象庁は報ず。昨年と同じ日であった。
(Nov.12)
■興行収入一位の映画と、ぼくの感動した映画
今年上期の映画興行収入ベスト5の順位。
邦画では(1)LIMIT OF LOVE 海猿 (2)THE 有頂天ホテル (3)男たちの大和/YAMATO (4)デスノート
(5)ドラえもん のび太の恐竜2006。
洋画では(1) ハリー・ポッターと炎のゴブレット (2)ダ・ビンチ・コード
(3)ナルニア国物語/第1章ライオンと魔女 (4)Mr.& Mrs.スミス (5) フライトプランだそうだ。ぼくの胸に迫った
1本は、この中にはない。美しくも厳しい大自然ロッキーで犬ゾリを使って罠猟をする男をドキュメンタルに描いた
映画『狩人と犬、最後の旅』、これこそ、ぼくの挙げるナンバー1だ。
マイナス40度にもなる極北の地、罠猟師と強い絆で結ばれる犬との生活。惹句は”生きるとは、こういうことだ”。
コピーに偽りはない。自信をもってお薦めできる作品、『狩人と犬、最後の旅』の詳細は、別項エッセーで。
(Nov.8)
■鳩山のアトリエ近くに熊出没!
 ・「また子グマ出没」埼玉新聞11月5日
・「また子グマ出没」埼玉新聞11月5日 昨夕、ホームセンターでドリルの刃を買って帰り、車を降りると防災無線が大音量で響いていた。
「鳩山にクマが出没しました!」アトリエは目の前の小高い丘”おしゃもじ山”の山陰に
あるから、夕暮れ時でも最早暗い。見上げれば黄昏の空はまだ明るく、真っ黒のおしゃもじ山の稜線
をくっきり際立たせていた。スピーカーの声は警戒を呼び掛ける。「小グマは捕獲したが、親グマが近く
にいると思われるのでご注意を!」、ぼくは慌てて家に駆け込んだ。
このところテレビは各地のクマ騒動を伝えている。が、まさか鳩山に現れるとは考えもしなかった。
もっとも、都幾川町や寄居町や日高市など”隣町”には今年すでに出没しているから、鳩山に
現れても不思議はないだろう。
夜の全国ニュースでは報道されなかった。もう珍しくはないからだろう。ぼくは朝コンビニに行き、
埼玉新聞(11月5日)を買ってみた。記事があった。”子グマ出没”の見出しで。「~庭に子グマがいるのを
発見。子グマは鶏小屋に逃げ込んだ。~署員らが生け捕りにしようとしたが、ロープが首に巻きついて
しまい子グマは死んだ。」 「町役場によると、ツキノワグマの子、体長80センチ、体重約10キロ」
子グマは鶏4~5羽を食べたという。町役場によればクマが発見されたのは町で初めてだそうだ。開発
のあおりで食べ物が少なくなったのだろう。山奥から人里へ、出て来ざるを得ないのも、人間の仕業だ。
何ともクマが哀れだ。
哀れといえば、こちらは人間の事件。同新聞に載った小さなニュース。大新聞では扱わない”田舎の
事件”だ。いや、事件として取り上げてよかったのか……。ぼくは、このニュースを哀しく読んだ。
『畑からハクサイを盗んだ男を逮捕 寄居署は4日、窃盗の疑いで無職男(79)を逮捕した。調べに
よると男は~中略~畑からハクサイ2個(2百円相当)を盗んだ疑い。~中略~男は犯行を認めたため
逮捕した。余罪もあるとみて調べている。』
(Nov.6)
■十三夜 月明りの散歩
霜月に入り秋気冷涼。今月、来月と雑誌の仕事は”年末進行”。締め切りが1週間早まる上、
現代童画展も控え何かと気忙しい。今日は十三夜、忙中閑あり。月明り、夜食を求めて恵比寿まで
歩く。仲秋の名月は(旧暦8月15日、今年は10月6日)あいにくの雨で見られなかったが、今宵の月も見事だ。
真ん丸には及ばないが、そこがまた良い。皓皓たる月夜の一人歩き、いつしか仕事を、生活を、現実を忘れている。
代官山や猿楽町は坂や路地が多い。そぞろ歩きはいつも道を変えているが、狭い街でも風景はガラリと変わるから
面白い。ただ、このところ増えた防犯センサーライトには閉口する。急に体を照らされドキリ!も、慣れっこになったが、
疑われているようで、心持良いものではない。名月を愛で風情を楽しむ静かな闇が少なくなった。表通りはクリスマスの
イルミネーションが月の存在さえも忘れさせる。ぼくは喧騒を避け暗く入り組んだ路地に入り月明かりを楽しんで歩く。
月が翳ったのか足元から影が消えた。見上げれば、十三夜の月は薄雲のベールに覆われている。天気が心配だ。
明日は早朝、額の塗装の仕上げに鳩山に向かう。
(Nov.3)
| 10月のアトリエだより |
■ブナ黄葉間近、作品完成も間近


板絵『瞬幸永憶』も描き進み、筆を使うより眺める時間が長くなってきた。吸い込まれてしまって
いた……、我に返ってそう思えるならば、ぼくにとって先ずは成功だけど……。
表現したかったのは、これか!これだ!強い表現欲はこのメッセージだったのだ!詩や物語が
絵筆で描けただろうか……。これから幾夜は、酔眼で絵と向かい合うことになる。至福の一時で
あればいいが。
(Oct.29)
■鳩山フラワーガーデンの十月ザクラ満開


100号額(130×162㎝)を組み立て、ミルキーホワイトのペイントを地塗りする。幸いにも天気予報は
外れ秋晴れだ。塗装は晴れた日に限る。乾く合間に、近くにある鳩山フラワーガーデンへ。
広大なハーブ園だが、果樹の苗木や採れたての野菜などを扱う売店がありたまに立ち寄る。今日は
赤米と大豆とギンナンを買った。のどかな秋の空の下で散策を、との気持ちを仕事、仕事と抑えこむ。
ガーデンの入り口近くに、秋たけなわなのに桜が咲いていた。”十月ザクラ”だった。高く濃い空に
桜花が映え映え、春とは違った風情だ。隣には八重桜。こちらはもう葉を落としていた。イチョウの大木
から音も無くギンナンが降っている。このギンナンがあの売店に並ぶのだろう。
(Oct.28)
■絵本『ほしの よる』(サンパウロ刊)初版第二刷届く
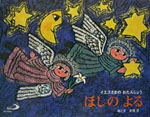

絵本『ほしの よる』 が二刷になった。この種の絵本はクリスマスを中心として売られる”季節絵本”。部数を伸ばす事は
あまり望めないが、制作に半年以上かかった絵本であり嬉しさ一入。(制作の苦労話はエッセー欄に掲載)イラスト原画は
絵本サイズより二廻りほど大きな板絵12枚 。ギャラリー高野での個展の折り展観したが、それっきりだ。『ほしの よる』の
板絵は額装されたまま眠っている。何方か展示できる道をお教え下さい。
(Oct.13)
■銀杏の落ちる季節
大学のキャンパスのイチョウが色づき、薄橙色の実が落ち始めた。ぼくは昨年も一昨年もギンナンを拾った。今年も
その季節到来だ。正門から校舎に至るイチョウ並木、舗道はまるでギンナンを撒いたよう。とても拾いきれるような落ち方では
ないが、拾うには若干勇気がいる。女子学生はギンナンには見向きもしない。踏みつけられたギンナンが異臭を放つ道を
何食わぬ顔で過ぎて行く。その中でビニール袋を持ってうろちょろする男は、やはり奇異に映るだろう。
それでも、秋の恵みを放っておくのは忍び難く、今年もぼくは背後に視線を感じながら、ギンナン拾いに興じるだろう。
酒の友にせんと。
あら塩の上に炒ったギンナンをぶちまけ殻を叩き割って食べる。”翡翠の実”の美味さよ。酒よし、肴よし、後は一日の仕事の
充実感次第。これが難物だ……。
(Oct.11)
■板絵制作なかば
 ・終日板絵制作
・終日板絵制作 『瞬幸永憶』の制作、一ヶ月半経過。思うような色が浮かばず難渋する。”浮かばず”というのは、ぼくは予め描きたい世界の
色彩を決めずに、画面上で作っていくことがあるからだ。色が産まれるまで、塗り続けるといったらよいか。主題は心に根を下ろし
些かの迷いもないが、イマージュを視覚化する、殊に色彩は”望む気配”を漂わすまでには時間を要す。いつものこと乍ら、
よぎる不安。完成を見るのだろうかと。 十六夜の月、空高く昇る。月明かり、懐中電灯要らずで鍵を掛けアトリエを後にした。
(Oct.8)
■満月、月明かりに酒を酌む
 ・栗の渋皮煮 ・団子(15個)のお供え
・栗の渋皮煮 ・団子(15個)のお供え 雨はからりと止み秋天晴れ渡る。気澄み爽やか。気持ち良いこと、この上なし。筆を休め、しばし外に出る。鳥の声が、
風の音が、秋の景色が、アトリエからぼくを誘い出す。多くの田圃が稲刈りを終えている。刈り取られ裸になった黄土色の
畑と、稲穂が揺れる畑がパッチワークのように広がっている。
アトリエのすぐ下の田圃の主、石井さんが奥さんを乗せ軽四トラックで現れる。採れたての米と玄米を届けて下さった。
奥さんの手製の栗の渋皮煮も。有難いことだ。毎年頂いているが、石井さんの米はうまい。ぼくは玄米が特に好きで、
渋谷の仕事場にも持って行き、米に混ぜて炊いている。
渋皮煮は大きな栗を破らぬようにそっと煮上げた逸品。栗の味を殺さぬ控えめな甘さは上品。以前、画集に掲載した
エッセーでもこの渋皮煮について書いたが、奥さんの腕前は変わらない。
新米も栗の渋皮煮も嬉しいが、この石井さんと奥さんの笑顔は天下一だ。破顔一笑……、相手に思わず笑みを催さす
笑顔はまことに魅力的。素晴らしい笑顔、まさにこれ以上はない「幸福感」のプレゼントを頂く感じだ。
ススキを採ってくる。団子を作る。(上新粉や白玉粉ではなく、今年はソバ粉。水に代え牛乳で練り、丸めて熱湯に落とす。
浮き上がって来たらソバ団子の出来上がり)仲秋の名月は「芋名月」。団子の他にサトイモを供えたいところだが手元に無く、
石井さんに頂いた栗の渋皮煮や梨や柿(庭のはすべて渋柿だが)をお供えした。
満月!皓々と照る月は雲までうっすらと映し出す明るさだ。月との語らい……、時に独り頷き酒を酌む。肴はソバ団子に
醤油をつけて炙ったもの一品。夜のしじま、虫の音繁く更けていく。
(Oct.7)
■仲秋の名月見られず
今日は仲秋の名月の、はずだった。鳩山でお月見をと、やって来たが、あいにく前日からの雨は降り止まない。アトリエに
向かう下り坂の小径は深くえぐられ、泥水が音をたてて流れている。大雨だ。名月を愛でようなんて騒ぎではない。
6日は旧暦の8月15日、仲秋。中秋は旧暦の7月から9月の秋たけなわ、真ん中の日。今年は旧暦のうるう年にあたり、
例年より一ヶ月ほど遅れた。(旧8月15日は2003年では9月11日、2004年では9月28日、2005年では9月18日。因みに
来年は9月25日)
虫の音かき消す激しい雨に、仕事は却ってはかどった。没頭できたこと……雨のおかげだ。毎夜、仕事の後には酒を酌む。
満足して飲める時も、そうでない時もあるが、我がささやかな楽しみ。今日は畏友の杜氏、宇都宮繁明君の酒、『月の滴』を
持って来た。でも今晩は我慢しよう。仲秋の今日は雨の一日だったけど、満月は明日だ。明日の晴れを期待して、美酒は
おあずけとする。
(Oct.6)
| 9月のアトリエだより |
■仕事の合間に栗拾い。焼き栗を食う。



夜来の雨は上がった。空は澄み渡りからっとした涼風が気持ちよい。これぞ秋晴れ。アトリエを抜け出し栗畑へ。
老木が3本。内1本が枯れたので5年前に苗木を3本植えた。自然に生えた1本を加え今年は6本の栗の木から
収穫だ。先ず栗の木の周りに生い茂る雑草を刈払い機で片付ける。栗の実はイガから顔をのぞかせて今にも落下
しそうなものを棒で落とす。落ちている栗は、新しくても虫が喰っているものが多いから拾わない。
1時間ほどでザルが一杯になった。あと数回は栗拾いできそうな実り方だが、今晩はもう東京に帰らねばならず、
美味しい栗は虫たちのご馳走になってしまうだろう。
庭で早速食べてみる。ダッチオーブンに放り込み焼き栗だ。ちょっと目を離したら、鉄鍋の蓋がずり落ちている。中で
栗が破裂したのだ。その勢いの凄ざましさ!さらに、栗をナイフで裂こうとしたら栗の中味が噴出した。ぼくは頭から
栗の粉を被ってしまった。栗を焼きすぎて失敗。(少し冷ましてナイフを入れれば大丈夫)
ダッチオーブンは熱の廻りが速いので、栗の表面が少し焦げたらもう食べ頃だ。熱い栗をスプーンでほじって
食べた。ほくほく……、甘くてうまい!明日の夜は栗ご飯にしよう。
(Sep.20)
■夕闇に目に染む紅と白

梢を叩く雨の音に起こされ7時、コーヒーポットを手にアトリエに入る。昨晩から開けたままの
窓から湿り気を帯びた冷気が入り込み部屋を充たしていた。この秋初めて長袖シャツを着て仕事する。
小止みなく降る雨は辺りの静寂さを一層感じさせ、仕事場の自分は,独歩孤立(=それだけであること)で
居られる幸せに包まれる。絵を描き終わり筆を置き、へたりこむように座る……。作品を眺め入るその時が、
ぼくには至福なのだが、完成の一瞬間だけではない。描いていく過程でも、時間の経過を忘れ集中できれば、
その充実感は優るとも劣らぬ悦びなのだ。
”きり”のない仕事を中断。明るいうちに東京に戻ろうと、車に荷物を積み込む。蕭条として降る
冷たい雨は止む気配もない。剪定を怠り伸び放題のサルスベリの木が花をぎっしりつけている。
サルスベリは夏の盛りに似合う花だが、長梅雨のせいか今年は開花が遅く今、群がるように咲いている。
曲がった幹の下には散り落ちた花が地面を覆う。濡れた土の黒と、ローズレッドの対比が
目にも鮮やかだ。
木芙蓉の白い花も揺れている。際立つ白の美しさよ。雨の中、ぼくは暫し佇んでいた。
鳩山はいつも立ち去り難い。
(Sep,13)
■一日の終わりの酒、菊の花びらを浮かべたかった


・一回目の地塗りを終える ・地塗りをつぶす
今日9日は重陽の節句。残念ながら庭に出て観菊する余裕はない。せめて、菊の花を摘み花びらを酒に浸して
菊酒をと思ったが、仕事を終えたら外は闇。部屋から一歩も出ず終日絵に没頭。日の暮れるのもわからなかった。
防災鳩山のスピーカーから流れる「5時になりました。良い子のみなさん、お家に早く帰りましょう」のアナウンスを耳に
したのは覚えているが。
菊の節句には朱ゆ(=山椒、”赤いグミは誤り)を袋に入れ、柱にかける慣わしがあったという。この袋は5月、端午の節句に
薬玉(麝香、沈香、丁字などを袋に入れ、五色のテープを垂らす)と交換するのだそうだ。アトリエの周りには山椒の木がやたらと
増えて困る。ちくちく痛くて抜くにも一苦労。でも、朱ゆの枝は邪気を払い悪気を防ぐという御呪いを、今日は信ずるとするか。重陽の
節句だもの。
板絵『瞬幸永憶』は地塗りが終わったところ。これから彫りを加え再度地塗りの後、筆で描く段階に入る。
(Sep.9)
■鳩山のアトリエ 板絵『瞬幸永憶』制作開始


・大まかに彫る ・部分
100号の板絵制作に入るため鳩山へ。関越自動車道を走れば早いが、気分転換にと川越街道を行く。
まだまだ暑いが雑草の繁茂も盛りを過ぎ、見上げれば高い秋の空が広がっている。アトリエは8月の終わりに
掃除しておいたから、直ちに仕事……と張りきるも、そううまく事は運ばない。パネルというパネルにカビが噴いていた。
シナベニアは湿気を含みやすく白いカビ黒いカビが一面びっしり!外に並べ太陽が沈むまで日光消毒だ。
毎年同じ目に遭う。低地に建てるのだからアトリエは高床式にすれば良かったと思っても後の祭り。締め切っていたせいで、
2階に掛けておいた作品にもカビ。絶望感でため息も出ない。
ところでタイトルだが、『瞬幸永憶』とする。一昨年『天辺の約束』を描いたがイメージを具体化させる言葉が大きな力になった。
今年も描きたい世界、その情景を表す「言葉」を探り当てた。これはきわめて大事なこと。ぼくは見たものをそのまま描くことを
しない。あくまで心に映る世界、それが小さな情景でもはっきり感動として浮かび上がるものだけを描いてきた。
イマージュが「言葉」を発し、「言葉」が絵を語りだす。ぼくの絵画作法に言葉の持つ意味は大きい。
エスキースを壁にとめ、板を彫り始める。静かな自分だけの戦いに沈潜する。残蝉の声に寂寥感を覚えながら。
(Sep.1)
| 8月のアトリエだより |
■遅まきながらの残暑お見舞い
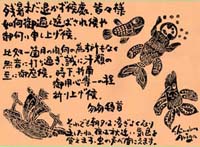
| 7月のアトリエだより |
■追懐、少年時代……雨の逗子にて
逗子を訪れたのは何十年ぶりだろう。雨の逗子駅に降り立つ。長梅雨の明けるのを待っていたら展覧会は終わってしまう。
「アルベルト・ジャコメッティ 矢内原伊作とともに」展(30日まで)を見に、神奈川県立鎌倉近代美術館葉山にでかけた。夏風邪で
咳が止まらず体長は良くなかった。葉山の美術館に行くバスは出たばかり。ついていないと思うところだが、むしろ「これ幸い」と
一人頷き逗子の町を散策した。
ぼくは信州伊那町や藤沢村で幼少期を過ごしたが、小学4年に転校、中学3年までを逗子で暮らした。もちろん今日はジャコメッティの
彫刻が目的だが、”少年時代の町”逗子にも展覧会に劣らぬ興味があった。懐かしい町は、思い出を囁きかけてくれるだろう……。
ぼくは胸の高鳴りを感じた。
しかしながら、期待は呆気なく萎んだ。そこに、少年の目に焼きついた町はなかった。駅周辺は昔そのまま。高層のビルも無く
町は再開発もされていない。それなのに、なんだか景色が違う。シャッターを下ろした店や売り店舗が多く活気がないのは今や
当たり前の事なのかも知れないが、寂しさはそのせいばかりではない。この季節、海岸までぞろぞろ続く海水浴客が見られない。
これも天気のせいだろう。
ぼくが違和感を覚えたのは、子どもの姿が皆無ということ。思い出の風景には遊び回る子どもの笑い声や叫び声がある。ぼくは
思い出の町を、当時の小学4年生の目のままで見ていたのかもしれない。記憶は時を経て、知らず知らず甘美な楽園に変えられて
行ったのだろう。ある作家の「記憶は想像力の産物である」というような警句がふと頭に浮かんだ。
嬉しかったのは、なぎさ通りで「龍生堂」を見つけたこと。ぼくがよく通った文房具店だ。貼付け文字の大看板も昔のままで懐かしい。
欲しいものだらけの魅力的空間は少年にはとてつもなく広いものであったのだが、今見ればも店の広さは10畳あるかないか。確か
出入り口は左右2箇所にあったはずと、よく見れば左側下に石で塞いだ跡あり。思い出が一気に蘇ってきた。ぼくにとって龍生堂は
工作材料調達基地であり夢空間であった。小遣いのすべてを龍生堂で費やしていた気がする。
買ったのは画用紙やボール紙、絵の具や筆、板や彫刻刀、蝶番や螺子釘、ラッカーやエナメル、スクリューやプロペラなどの模型
材料全般だが、欧文のゴム印や印鑑を注文したりした。
薄暗い店内。視線の先の壁には朱墨や筆、算盤の文字がある。ぼくは店の中に入ろうか迷ったが、外から眺めるだけにした。
思い出は、想像の余地を残す事によってしか喪失から免れることは出来ないから。
(JUL.21)
■選抜展が終って


今年の現代童画選抜展は寂しいものだった。久保雅勇氏、中山敦子氏を失い、別れの悲しみが癒える間もなく、
こうのこのみ氏がお亡くなりになった。このみ氏は30年来絵を描いてきた仲間だ。展覧会の案内状にも名が連ねられているし、
直前の会議でお話もした。まさに急逝。壁面が寂しい。ぼくの絵の隣にいつもの”あるべき絵”がないのだから。このみ氏は
命を閉じる最後まで絵を描き通した。誰でもが真似できることではない。素晴らしい人生だ。生涯”描ききった””生ききった”
画家の幸せな姿を見せてくれた。(現童だよりに追悼文掲載)
選抜展は20年以上、銀座8丁目のアートホールで行っているが、昨年まではギャラリーの前に目を楽しませてくれる
建物があった。昭和5年に出来た新田ビルだ。老朽化が進み取り壊され今は工事の鉄柵で囲まれている。大きなアーチ窓や
外壁のレリーフが特徴でアールデコ様式の昭和モダニズム建築は東京大空襲にも耐えた。ぼくはこのビルが好きで、
アートホールの受付に坐ってよく眺めていた。中に入って、蛇腹のついたエレベーターを動かしたりもした。
人も建物も、居て当たり前、あって当たり前……いや、当たり前なんかじゃない。生きている限り、万物との出会いがあり、
別れが続く。出会いの喜びと別れの悲しみの繰り返し。
大切なものが眼前から失せて初めて気付く愚か者。嗚呼、万物は滅ぶ……。
(JUL.10.)
| 6月のアトリエだより |
■映画『アダン』を観る (東京都写真美術館ホール)
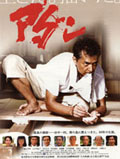 『アダン』 監督/五十嵐匠、脚本/松山善三 奄美群島日本復帰50周年記念映画
『アダン』 監督/五十嵐匠、脚本/松山善三 奄美群島日本復帰50周年記念映画 孤高の画家、田中一村の半生。(榎木孝明、古手川祐子、村田雄浩、加藤剛他)奄美大島に独り移り住み、69歳で
亡くなるまで極貧の中で亜熱帯の動植物を描いた田中一村の半生を榎木孝明が演じた。役作りのため、15kgの減量を
したと新聞で語っていたが、何か物足りない。富や名誉を追い求めるのではなく、絵を描くことだけに命をかけた男の凄みが
伝わって来ないのだ。榎木孝明自身画家でもあるし、制作時の眼光の鋭さや筆遣いの動作はリアリティが感じられたが、
キャラクター設定が甘く中途半端。人間臭さが希薄だった。
もう一点、訴求力が乏しくなった訳を。芸術家を描いた映画の多くは作品自体も映るものだが、『アダン』には田中一村の
作品は、展覧会の審査に落選するシーンに一枚しか登場しない。一村が洋傘を手に奄美の島を歩き回る場面や、”幻想の少女”
アダンと出会い(フィクションに演出過剰)に時間を費やし、2時間19分という冗長な映画になってしまった。もっと、「絵の力」を
借りて制作したら一村像が鮮明になりリアルに迫って来たことだろう。残念だ。
一村の才能を信じて一生を捧げた姉、古手川祐子のひたむきさ、母性を思わせる慈愛深さには感動した。それに美術学校
同期の画家を演じる村田雄浩には抑えた渋い存在感があった。
一村が奄美から故郷栃木の姉に宛てた手紙「死んでも、一村の手だけは生きていて、画布に向かって動いてゆく。そういう
生涯を送りたいと思っています。」重い言葉。胸に突き刺さるような一節。噛み締め反芻し、トボトボ歩いて帰った。
(JUN.25)
■選抜展出品作完成 (於:銀座アートホール 詳細は別項「展覧会案内」をご覧ください)
 ・板絵 『郵便船』 S30号
・板絵 『郵便船』 S30号 現代童画会選抜展に『郵便船』を出品する。三年続けて正方形の30号の板絵。春季展、選抜展は真四角の作品を
制作することが多い。会期終了後、選抜展は坂出、神戸を巡回する。板絵の醍醐味、マチエールは写真では伝わらない。
一人でも多くの方々に見ていただきたいと願う。
(JUN.24)
■獰猛なカラスが哀れ
小学館「おひさま大賞」選考会に出席。今年度から荒井良二氏が加わる。絵本部門、童話部門にそれぞれ秀作あり。
真剣に話し合うから審査はかなり疲れる。気持ちを切り替えて即仕事、とは行かず帰宅する。ボーとして歩いて
いたのだろう。家の近くで突然カラスが数羽ぼくを襲うかのように周りで羽ばたいた。角の家のビワの実を落としては突いて
いたのだった。道路は潰れたビワでグシャグシャで汚い。辺りに漂う甘い甘いビワの香りが救いだ。ゴミ袋にカラス除けの
ネットが被せられるようになっても、カラスの行動は大人しくはならない。カラスが哀れだ。
(JUN.21)
■展覧会の作品搬入に苦労する Lepure Shinjuku Gallery (詳細は別項「展覧会案内」をご覧ください)
企画展の作品搬入日。幸いにも曇天。会場は新宿の商業地域、交量の多い甲州街道沿い。作品を降ろす
にも、車から離れたら忽ち駐禁のステッカーが貼られるので、搬入も楽ではない。展覧会開催は大変だ。
道交法改正の厳しさを実感する。板絵7点、版画3点の出品。他に岡村好文、中村景児、本橋靖昭氏等6人が出展。
(JUN.20)
■強い雨止み、束の間の梅雨休み



雨降りしきる中、鳩山へ。ワイパーが効かぬほど強い雨。関越自動車道では前を走る車のしぶきと靄に難儀する。
坂戸の料金所を出ると小雨、高麗川の橋を渡る頃には雨はあがった。黒灰色の雲に覆われていた空は明るくなり、
灰白色の雲が秩父連山をくっきり際立たせている。雲間から一筋の陽光。このまま晴れれば茜空だが……。
残念ながら美しい光景も長くは続かず、鳩山に着いたらまた空は暗灰色の雲に覆われた。
アトリエの窓をすべて開け空気を入れ替える。その間、やぶ蚊を追い払いながら、草木伸び放題の庭に出る。
オリーブの小さな花が咲いている。ミルテの蕾はまだ固い。ミルテは花よりも、開く前のタピオカのような白い
ボール状の蕾が清らかでよい。紅ウツギの花びらが落ちている。エゴノキの白い花も散っている。
雑草よりも強いホオズキがあちこち根を延ばし、実をつけている。甘い香は落ちた梅の実だ。
実をもぎたい気持ちを抑えて、アトリエに戻る。留守にしていたアトリエの壁面は結露。
パネルには白いカビがふいている。開け放った窓から、珍しく涼やかな風が吹き込んで来た。
田植えをする自動田植え機のエンジン音が響いてくる。ぼくも、仕事しよう。
(JUN.16)
■田植えと麦刈り……水無月の田園風景


アトリエから水田と麦畑が見える。田植えと麦刈りが今たけなわ。植えるのも刈り取るのも機械だからあっという間に
終わってしまう。子供の頃、村では田圃に水が引かれると代掻きの牛が入り、各家々は総出で田植えをしたものだ。
田植え歌があり、長閑な風景があった。
機械化により風情はなくなってしまったが、今日は懐かしい光景を目にして嬉しくなった。麦刈りのコンバインを運転する
お父さんを、お母さんと子どもが軽四輪トラックで待っている。女の子がコンバインに向かって走って行き何やら叫んだ。
エンジン音で声はなかなか届かない。やっと気づいたお父さんが、分かった分かったと手を振った。畦道で三人がお茶を
飲む。昔は当たり前にあった情景だけど、その温かさにたまらなくなって、じっと見ていた。心がほんわかして、その場を
動くのが惜しかった。幸せが漂っていた。いいなあ、本当にいいなあ。
9日、関東地方も梅雨入りした。今日は一日曇り空。ウグイスやホトトギスの声が聞こえる。ホトトギスの異称が早苗鳥
だと聞いたことがある。誰からかは忘れたが……。
田圃は水面を、早苗の緑で染めている。早苗鳥の季節だ。
(JUN.10)
■板絵『郵便船』制作中

子どもの頃は切手少年だった。海外ペンパルと切手の交換をした。特に初日カバー(First day of cover)の収集には
力を入れた。カシエは自ら制作したことも。郵便史にも興味があった。飛脚状を開けて、穀物相場表など見つけ興奮した
こともある。わが国郵便の父、前島密の時代、黎明期の郵便事情は解明されていないことも多い。サザーランド郵便という
のもその一つ。サザーランド切手の写真は脳裏から離れない。馬上のひと、エキゾチックな図案だった。
手紙、郵便という言葉が好きだ。思いを認め封緘。祈りて投函。返信への期待感。手紙は時にかけがえのない宝物。
気持ちを託すとき、神妙になる。この絵も描いているうちに神妙になった。思いを籠めることは一緒だ。
(JUN.9)
■自動販売機の話
今、「スイカ自動販売機」の絵話を描いている。この怪しげな機械、海水浴客でにぎわう夏の砂浜に置かれている。
町中の八百屋さんからスイカが消え(盗まれ)たというのに、スイカ自動販売機では、スイカが売られているという話だ。
自動販売機と言えば7月に展覧会を行う、ラペア新宿の会場にも、ぼくが始めて見る新機種が設置されていた。100円
硬貨を投入すると、コーヒーなどのチューブが出てくる。口を切ってセットすると、紙コップに湯が注がれるというもの。
面倒臭いことをさせると思ったが、ビンや缶にようするスペースが要らないし、補充も楽なのだ。でも、このシステム、普及
されるかは分からない。(展覧会の案内は近日)
ぼくの描くスイカ自動販売機の構造は超アナログ。自宅のある世田谷では、農家の無人野菜販売所があちこちにあり、
ぼくも時たま利用するが、信頼関係を壊すような代金不払いも多いらしく、悲しい貼紙も見かける。アナログ的販売所よ
負けるな。廃れないでくれ。
スイカ自動販売機の行く末は……?果たして如何に……。
(JUN.4)
■銀灰色の鏡との対話


夜来の雨は上がったものの、昨日とうって変わって肌寒い朝。まだ梅雨入りはしていないが”梅雨寒”だ。ぼくは、くしゃみを
しながら水が張られた田圃を見ていた。美しい!田植えは明日か明後日か。銀灰色の水田は山影を映している。飛ぶ鳥や、
時折農道を過ぎ行く自転車の影も……。お百姓さんの姿も見えず、物音一つせずひっそりとしている。田圃は大地の鏡だ。
静かで平ら。この”静かで平ら”を、ぼくは飽きもせず眺めていた。心がこんな状態になることってあるかなあ。鏡はあれこれ
考えず、悩まず、意見せず、ただ映すのみ。「ぼくの心は僅かの時間だって”鏡”にはなれないなあ」なんて考えながら……。
アトリエの北側には畑が幾面か広がっている。この水田の隣は今”麦の秋”だ。畝に雪の白い帯が出来た冬はついこの間の
ことのように思えるが……。遠くに眼を遣りながら、ぼくは田園風景の移り変わりを頭に浮かべていた。四季って総ていいなあ。
制作に入った板絵は今、地塗りの段階。完成時には色がガラリと変わる。アトリエから見える景色も変わっていることだろう。
畑も田圃も、草も、木も、虫も。風も、日の強さも……すべて。
(JUN.3)
■ついこの前まで枯れ木に見えたヤマブドウに、小さな房が!
 ・ヤマブドウノの実(2ミリの球形、まだ赤ちゃん)
・ヤマブドウノの実(2ミリの球形、まだ赤ちゃん) 果樹が小さな実を付け葉陰から顔をのぞかせている。梅、スモモ、プラム、姫リンゴ、サルナシ。一番小粒がヤマブドウだ。
まだ2~3ミリ。小さくともしっかり緑の房の形をしている。秋の終わりに熟し濃藍のブドウに変わるのを想像して、ぼくは一人
嬉しがっている。
ヤマブドウは食べても酸っぱく、ブドウシロップやジャムにして楽しむのだが、このヤマブドウの紅葉の美しさは格別だ!
もみじ以外ではヌルデも綺麗だが山から取って来て移植したものが枯れてしまった。ニシキギやナナカマドもその赤さでは
負けないが、微妙な色合いでは、やはりヤマブドウが優る。多くの画家がこのヤマブドウの葉を描いている。絵の具で描き
きれないような美しさをぼくは感じる。
ヤマブドウが熟し紅葉が燃える頃、ぼくは「現代童画展」(東京都美術館)出品作の制作にかかっていることだろう。昨年も
一昨年もそうだった。一年の過ぎ去る速さを、今日はヤマブドウの若い実をみて思った。
(JUN.1)
| 5月のアトリエだより |
■ウグイスのさえずりに誘われて / 自生の忍冬を見つけた!



現代童画会九州支部展に出品した作品の梱包を解く。『忍冬の坂』S30号。忍冬の生える丘をイメージした板絵。
スイカズラは葉が冬の寒さに耐え萎れないので忍冬と呼ばれる。またスイカズラの茎や葉を乾燥させた生薬の名を
忍冬という。鳩山の庭に桃色と赤色のスイカズラを植えたら、つるが延び放題で角材で作ったバーゴラに絡まり木部が
見えぬくらいに繁茂した。『忍冬の坂』は忍冬の花の香に包まれた少女を描いたもの。
今日、新たな作品制作にアトリエに入る。パネルを用意しラフスケッチ。集中するも、盛んに聞こえるウグイスの
さえずりの声が気になって、おびき出されるように外へ。新緑の雑木林。声のするほうを見上げても姿は見えず。
それでも葉郡から聞こえて来る美しい響きを暫し楽しんだ。
どこからか甘い花の香りが……。木香薔薇のアーチからだった。薄黄色の小さな薔薇はもう終わったのに、何だろう?
おやおや、ほとんど白色、わずか薄紅色の花が木香薔薇の葉の間に混じるように咲いている。何と、ハニーサックル!
ぼくが植えた桃色と赤色のスイカズラではないし、場所も違う。よく見れば木香薔薇の根元から、蔓が隙間なくグルグル
巻きついている。自然に生えたスイカズラだった。
ぼくは甘い香りを吸い込み、ウグイスの美声を耳にしまい、アトリエに戻った。直後、雷鳴が轟き雨になった。
(MAY.30)
■『詩人の眼 大岡信コレクション』展 三鷹市美術ギャラリー
開催期間が長いからと安心していると展覧会はすぐ終わってしまう。見損なっての後悔しばしば。この
『詩人の眼 大岡信コレクション』は是非とも見なくてはと思っていた。なのに出かけたのは、最終日の前日に慌しく。
いつもこうだ。仕事はともかく、雑事にかまけ流されっぱなしの日々が情けない。
詩人、大岡信の集めた現代美術作品150の作品群の展示(総数は400を超えるという)。駒井哲郎、利根山光人、
加納光於、サム・フランシス、ジョアン・ミロ、菅井汲。詩人、瀧口修造などの顔ぶれは、よくもまあ、こんなにと
驚かされるが、多くの作品は作家からの贈られた物だというから感心する。その作品との関わりが書かれていて
興味深く、見飽きない。中には本人が購入した作品もあるが、そのエピソードがストレートで気持ちよい。オディロン・
ルドンの石版画9点しかり、パブロ・ピカソの絵しかり。例えば、ピカソの「黒い人」1948年作には、”1952年、当時
入院していた結婚前の妻に、誕生日のプレゼントとして白い額を贈りました。その額にあいそうだからと、彼女は
前年の『美術手帳』から切り抜いて持っていたピカソのモノトーンの絵を入れて飾っていました。白い額は今では
壊れてしまって残っていませんが、30年以上後になって東京の佐谷画廊で原作のリトグラフを見つけて、妻が購入
しました。よい状態の版画です”………と記されている。ぼくは温かい物語を頭に思い描き、見入ってしまった。
美術家、芸術家との人間関係から大岡信の下に”集まった"作品の数々。美術館の展示とは趣が違う異色の
コレクションは、詩人の生活空間に棲息していた匂いを放っているようだった。小さなデカルコマニーの作品『夜よ、
わが茂みわが土くれよ』には、「持っている瀧口さんの作品の中で一番気に入っています」の説明文が。心情も伝わり
面白い。ぼくは黒田征太郎による『大岡信ヨーロッパで連詩を巻く』の表紙原画が印象に残った。青と赤にセパレート
された画面から飛び出して来そうな白い鳩、二羽。色も形も自由で子どもの絵のように生き生きとしていた。駒井
哲郎の銅版画『岩礁にて At Rock Seashore』も海の藍色と、浮遊する魚の白さが何とも美しく、この一枚を見られた
だけでも,出かけた甲斐があった。
(MAY.27)
■童美連テニス大会間近!



雨続きでテニスが思うように出来ない。ハードコートは使えず、オム二コート(人工芝)は小雨でもかろうじて打てるが
混み合い、サーブの練習に一面を占拠しては顰蹙をかう。
23日は西武線入曽駅近くのコートで「童美連(児童出版物画家)テニス大会」が開かれる。もう30年も続いている大会で、
ぼくは初めのころから参加している。そのためもあり集中練習したかったのだ。先月は同じく西武線武蔵藤沢のクラブで
絵描きや編集者たちの、「UP & DOWNテニス大会」があり、散々な目に逢った。4戦全敗、エキジビジョンマッチも調子悪く、
"本業”にまで影響する有様。
ここ10年は年間、90~120回前後テニスクラブに通っているが(午前中のみのプレー。今年は現在44回)、パワーは衰えるし
技巧派にはなれず、悶々としている。唯一の趣味といってもよいテニスは,時にストレスにもなり仕事に影を落とす。困った
ものだ。テニスメイトにも「午後の仕事、頑張って!」「今日は勝てたから、良い絵が描けますね!」などと、冷やかされること
度々。
童美連テニス大会では悔いを残さぬよう戦ってこようと思う。戦績……?乞うご期待!それにしても、いい加減に晴れて
欲しいなあ。
春の野の草が咲いている。雑草……いやいや、可憐そのもの。目を近づけてみれば分かる。花屋で売っている華麗な
花にない清らかさがひっそりと息づいている。たとえば、オオイヌノフグリ。ひどい名前をつけられてしまったが、この1センチ
にも満たない小さな花は正に花の星、青い花の宝石だ。それくらい美しい。大会が行われるテニスクラブは狭山の茶畑に
囲まれている。都内より緑が断然多い。テニスの合間に春の野の花を探して見るのも悪くはない。勝敗にこだわらず……。
(MAY.18)
■八十八夜が過ぎて茶摘みの季節



・一芯二葉、新芽を摘み取る ・茶の実(15ミリ~20ミリ)右はドングリ ・種より育てた茶の苗木
五月晴れ、薫る風……と言いたいけれど、このところ天候が不順。夏日になったり肌寒かったり。アトリエに籠っていても、
晴れと曇りでは大違い。下描きしたりパネルを作ったり板を彫るのは、曇りでも雨でも構わないが、絵の具で描くのは晴れの
日が良い。絵の具の乗りや乾き具合のこともあるが、気魂の入りようが違うように感じて……。昨日も今日も曇り、目に止まらぬ
微細な雨が緑を濡らしている。
鈍色の空の下、茶摘みをする。茶の木は10年ほど前植えた。苗木の頃は新芽が出ても、採るに忍びず”新茶”はお預けだった。
20本の苗木は冬を何度か越え、しっかり根付き葉を青々と茂らせるようになった。一昨年あたりから存分に茶摘みを楽しんでいる。
摘むのは新芽の部分をごく僅か。一芯二葉。新芽を摘み取る作業は心安らぐひとときだ。蒸して揉んで(手揉みは大変な作業)
初摘みの新茶を味わってみる。縒りも細いのあり、太いのありで見た目は悪いけど、鉄瓶の湯で入れた色鮮やかな自家製茶は
若葉の香気。仕事も何もすべて忘れている自分がいる。ささやかな贅沢。
東京都内にある茶畑(出荷目的で生産)は、一つだけだそうだ。その茶畑で小学校の児童が課外授業に茶摘みを行っている
写真が先日新聞に載っていた。10キログラムの新芽は製茶工場で茶にしてもらい、全校生徒が飲むのだという。「自分達が摘んだ
葉っぱがお茶になった!」歓声が聞こえるようだ。この子達、この先ずうっとお茶は飲むだろう。新芽を摘んだ感触は忘れまい。この
体験、一生ものだ。
茶の木は秋に白い花を咲かせる。果実は翌秋成熟し種となる。ぼくはこの椿の種に似た黒褐色の実を大事に取っておいて、鉢に
蒔く。大きく育ち畑に移植するまで、この植木鉢はアトリエの窓から見える所に置く。育つのを見ていたいから。
今晩は茶の新芽を天ぷらにして食した。口中に広がる微かな苦味と渋み。両々相俟っての上品な風味は格別。目も鼻も舌も
喜んだ。茶畑の恵みが嬉しい。
(MAY.16)
■旧友来訪



何年ぶりだろう。大学の同期、Nと会う。Nはぼくが在籍した美術部の部長だった。ゴールデンウィークも明日でお終いという
日に鳩山のアトリエを訪ねて来てくれた。
残念ながらNは下戸。酒は振舞えなかったが話に花が咲く。「40年位前、高島屋で開催されたオール学習院展(幼稚園から
大学までの作品展)のポスターを持っている。 有賀の作品だから今度渡したい。」と言う。ポスターの絵を描いた記憶はあるが図柄
など忘れた。見てみたい。次回の楽しみとする。Nは子どもが生まれた娘夫婦にプレゼントするのだと、ぼくの版画を1枚買って帰った。
Nが選んだ作品は『カモミールとクリムソン』。(別項「版画館」に掲載あり)キジがカモミール畑やクリムソンクローバーの野で
遊ぶ絵だ。今正にクリムソンクローバーの真っ盛り。鮮やかな緑色から突き出る赤い花穂がそよ吹く風に揺れている。
この絵は「花畑に遊びに来るつがいのキジを”カモミール”と”クリムソン”と名付け、それをモチーフにしたんだ」と、Nをクリムソン
クローバーの咲く庭に案内して話した。
旧友との再会は時を一気に縮め、今日のぼくは青年時代の心持であった。
(MAY.6)
■アサツキとフキで一杯


自生のアサツキを見つけ小躍り。ノビルかと思って掘ったら長楕円形の鱗茎。(ノビルの鱗茎は球形。ネギに似た臭気)
長いもじゃもじゃの根。『山菜の味』(婦人画報社・1972)で酒井佐和子氏は、この根を「真っ白い髭状の根を翁の如くつけて
いますので、この頃のアサツキを白髭と呼びます。」と書いている。翁の髭とは言いえて妙なり。
臭みがないアサツキは古来野菜として栽培され平安時代の延喜式にも、島蒜の名で登場しているという。普段アサツキは
刻んで薬味にするくらいだが、今日はさっと湯がいて味噌をつけ炙って食べた。ノビルほど辛くなくアサツキは旨い。前出の
『山菜の味』には、生食の他、アサツキの味醂づけ、一夜づけ、味噌たたき、ひたし等が載っている。ぼくは自生のアサツキを
畑に移植した。増やして色々調理してみたい。
先月末に食べたフキノトウ。その後ほうけて、俗に言う”しゅうと芽”となり、花も枯れ、茎が伸び葉も大きくなってきた。まだまだ
伸びるけど、若い茎をおひたしにして食べた。葉は刻んで炒め醤油とからめた。アク抜きもそこそこに、ほろ苦さを堪能。野フキを
採り、透き通るような薄緑を愛でるのも春だけの楽しみ。フキの漬物や佃煮はこれからだ。酒は畏友、宇都宮繁明氏の手になる
大吟醸『月の滴』。酒肴とも、味わうには少量をよしとする。
(MAY.1)
| 4月のアトリエだより |
■スミレの群生




畑に根を張らせ、又は種を落とし増えるのは雑草だけではない。ドングリの木、スギ、サワラもどんどん増える。これらは
何の木かすぐ分かるから、抜いたり移植したりするが、得体の知れない雑木(ぼくが不知なだけで、調べようと思うまま、
年がすぎている)には閉口している。育ちが早く2年ほどで7~8センチの太さになってしまい、簡単には引っこ抜けない。(抜いた
ものは焚き木にする)竹を代表格に厄介者は多い。
山椒やナツメの木もよく生える。ナツメは実が落ちて転がる範囲だが、山椒は畑のあちこち何処でも生える。増えて困る。
この二つは抜くにも、棘が痛く手こずる。しかしながら、赤い実がたわわに実るナツメの木は故郷を思い起こさせるし、葉に
触れただけで特有の香気が残る山椒の木も、祖母や父の思い出に繋がり、決して嫌いな木ではない。
はびこる雑草には手を焼くが、雑草に負けない強い草もある。たとえば、クリムソンクローバー。赤いふさふさした猫の尻尾の
ような花穂が美しい。そよ吹く風に一斉に「おいでおいで」をし、緑の野をクリムソンレーキで彩る。ぼくはこの草が好きで、枯ればむ
季節に種を採っておいて,辺り一面にばらまくのだ。雑草除けだが、目を楽しませてくれる有難い草だ。(”クリムソンの尻尾たち”の
写真はしばらくお待ちください)
スミレも雑草に負けない強い草だ。スミレは群生する。写真の白いのはマルバスミレ、紫は香水の原料となるスイートバイオレット
(匂いスミレ)。斑入りのものは初めて見る"珍種”。春になると鳩山の庭や木々の間にまとまって咲くスミレだが、昨年はあまり見かけず
気になっていた。今年は繁殖著しくホッとした。日陰でも荒地でも、根を延ばし増え続けるスミレは、花の可憐さからは伺えない強さを
もっている。
(APR.30)
■コシアブラとトチノキを植える


アトリエを片付ける。描きかけの絵が4枚。長く中断している絵に何故か愛着が湧かない。集中して画面に心気を留める
ことを怠ったせいだろう。いずれも寂しい絵だ。処分する。ストーブが燃えていれば焼べるところだ。パネルの桟からシナ
ベニアをバリバリ剥がす。この桟に板切れを打ちつけ白くペイントする。植栽物用ネームプレートの出来上がり。
ネームプレートにはコシアブラと書く。今日植えた苗木だ。コシアブラはウコギ科の落葉高木。金漆(ごんぜつ)の木とも言う。
金漆はコシアブラの樹脂を精製した一種の漆。材は白色で柔らかく細工用とされる。でも、ぼくの狙いは食用になる若芽。
まだ口にしたことがないこの味覚を味わってみたい。今、春の酣。なのに早や来春の食卓をイメージしている。
ネームプレートは橡(トチ)の木の名前のものも作製。昨年植えた橡の幼木が雑草に負けて枯れてしまい、23日再度苗木を
植えた。今回は葉つきが良く少し大きいものを。ところが、枯れたと思った橡が芽吹いたのだ。根を抜かなくて良かった。
即断禁物!新しく植えた橡の木の根元にネームプレートを挿し、この棒は、あのパネルの桟なんだ……、当たり前のことなのに、
絵を壊したことが悔やまれた。早まった事をした。
(APR.29)
■鳩山より久々の春便り


東京の桜が終わり、それから半月ほど遅れて咲く鳩山の山桜も散った。薄墨色の名残の花が風に舞う様はうら寂しく、
春を迎えるというのに、里山は孤愁一入。ぼくはこの季節が苦手。沈鬱。一人落ち込みもがいている。昨年も一昨年も……、
いつもの事だ。木々の芽吹きの勢いに気圧されるのか、若緑の峻烈な眩しさに中るのか、知らず識らず内観過剰に
なり自己嫌悪。この心の状態からの脱出方法をぼくは分かっているはずだ。毎年繰り返すのだから。
それは休息でも、気分転換でも、薬に頼ることでもない。経験則では絵を描くこと、これしか、ない。こんな状態にある時、
制作しても苦痛あるのみだが、それがいつしか、ほんの僅かでも喜びに感じられたら”戻れた”ということになる。今は未だ
辛い作業の真っ只中。
木々は一斉に芽吹くのではない。トチやクヌギ、つる性のサルナシ等は生まれたての若葉を風に揺らしている。ブナも
負けじと芽を吹き出し始めた。正に芽が吹き出る感じで迫力がある。(写真参照)サトウカエデやクルミは未だ硬い冬芽のまま。
ナツメや山葡萄は枯れ木のままだ。芽吹きも開花も結実も木々夫々。人だって夫々だ。そう思って、ぼくは心の状態を認め、
憂悶の晴れるのを待っている。
アケビの棚はすっかり緑で覆われている。くぐると花の甘い香りがした。アケビの豊作の予兆より、今は萎えた心への
芳香のシャワーが嬉しい。
(APR.23)
■POLA ART EXHIBITION『本の仕立て屋さん』展
 ポーラ ミュージアム アネックス 4.3mon.-26.wed.
ポーラ ミュージアム アネックス 4.3mon.-26.wed. ”装丁を見る愉しさ、触れる愉しさ”と題した装丁家4人の展覧会。旧知の田中淑恵さんも出展しており
レセプションにでかけた。田中さんは商業出版物の装丁をするかたわら、自作の豆本を制作している。本を愛でる姿勢は
30年来変わらない。いつの日か、田中さんの主宰する「鏡書房」で、ぼくも”こだわりの”1冊を出版してもらいたいと思っている。
会場に卓上小型印刷機が展示されていた。アダナという英国製の機械に、ぼくはたまらなく懐かしさを覚えた。三十数年前
デザイン雑誌アイディアにこの機械が紹介されていた。名刺やはがき程度しか刷れないが、欲しくてたまらなかったのだ。
学生の身で買えなかったが、当時ミニコミの印刷を頼みに活版印刷所に行くたびに、何とかして手に入れたいと思った。
その後、取扱店も分からなくなり、夢は潰えてしまったが……。
今日その赤い鉄製のアダナを目にし、何とも懐かしくぼくは暫く立ち尽くしていた。このアダナは山室眞二氏所有。アダナで印刷
した手作りの小さな本が輝きを放っていた。活字をひとつひとつ拾い、組み込み、印刷、製本する様が映像で紹介されていたが、
すべて手わざ。そこには静かでゆったりとした幸せの時間が流れていた。
氏は「時代遅れの本作りです」と述べているが、温かい人間の息遣いが感じられ、行過ぎた効率主義の現代には見られない
確かな手仕事の存在感があった。
普段あまり目にすることのない世界。お薦めの展覧会だ。
(APR.3)
■花散らしの雨の中、現童春季展作品搬入
お花見日和の昨日と打って変わって、今日は冷たい雨。風も強く桜の花びらがアスファルトに張り付いている。
横なぐりの雨の中、銀座アートホールへ。板絵『父さんの話』の搬入。会員の面々とは12月上野以来再会になるが、
中山敦子さんの姿がなく悲しかった。もう彼女のテンペラ画は見られない。胃がんで亡くなったのだ。ついこの前まで
手紙のやり取りをしていた。「正月は病院で過ごし家に帰れそうもない」と書いてきた。励ます言葉も見つからず、
ただ「祈ってる」「祈ってるからね」と返すしかぼくには出来なかった。
「チューリップとムスカリの球根を植えました。春に、きっと花を見られると信じて……」中山さんの手紙が胸を詰まらせる。
ぼくも同じ頃、水仙とムスカリの球根を植えたのだった。ぼくも植えたことと、「春は来る。大丈夫。チューリップも
ムスカリも中山さんも」のカードを送ったけど、哀しいことになってしまった。明るくて真直ぐな、素晴らしい人だった。
心から冥福を祈る。生前のたくさんの優しさに感謝する。
渋谷駅を降りると、雨は一層激しくなっていた。アトリエにいたる道すがら、雷鳴がとどろき傘も役立たず、
ずぶぬれになって帰りついた。
(APR.2)
| 3月のアトリエだより |
■ユキヤナギの自生を発見
絵話『父さん』の版画を1枚追加して制作。イメージが広がるときはスムーズなもの。普段描けず悩むことも多いが、
旧作のコラージュとはいえ、今日は捗った。
仕事を終え外に出ると、どんよりとした空。そういえば夕方から雨の予報だった。伸び放題の月桂樹を剪定。通路に
はみ出てとげが痛いクリスマスホーリーもカット。捨てる場所に困る程の山ができた。
5時になってもまだ明るい。ネムの木に巣箱をかけた。これで仕事じまい。はしごを抱え戻ろうとして薄闇の中、泡状に
咲く白い花を発見。顔を寄せて見ると泡状に見えたのは細かな花の密生。ユキヤナギだった。ぼくは植えた記憶がないから、
自然に生えたのだろう。ドングリやナツメは実を落としあちこちで発芽している。杉やシュロもどんどん増えている。上の畑に
植えたマユミの種を小鳥がはこんだのだろう。下の畑に芽を出し、いまでは”親”よりも大きくなっている。種をまいたり、苗を
植えたりしなくてもいろいろ生えてくるからおもしろい。ユキヤナギの清楚な小花、漢名を噴雪花という。ぴったりだと思う。
(MAR.28)
■板絵 『父さんの話』現童春季展出品作完成
 ・現童春季展出品作 『父さんの話』 S10号
・現童春季展出品作 『父さんの話』 S10号 昨日今日ぶっ通し描いて、ようやく完成。展覧会の詳細は「展覧会の頁」を。
(MAR.26)
■てんとう虫異常発生 (鳩山・アトリエ)
 ・ニジュウヤホシテントウムシ
・ニジュウヤホシテントウムシ 床のあちらこちらにてんとう虫!注意して歩かないと踏み潰してしまう。ほうきで掃き集めると、気持ち悪いほど大量。
半分はまだ生きている。飛んできて食卓にとまるのも。てんとう虫は成虫のまま越冬するが、なぜ普段は”密室”の家の中に?
日当たりの良い3畳ほどの小部屋に特に沢山いる。この部屋は以前ミツバチが巣をつくり、大騒ぎしたことがある。板張りの
壁から蜂蜜が垂れ、甘い香りを漂わせたのだ。「これはいい。天然の蜂蜜がとれる。ビールームと呼ぼう」なんて喜んでいたら、
大変。蛾がわき虫が集まり、臭くなり不潔。煙で燻してハチを追い払ったものの、壁の間の蜂蜜はそのまま。取り出そうにも
壁を壊すわけにはいかず、放置。この度のてんとう虫異常発生もそのせいだろう。おそらく。
ちりとりに集めたてんとう虫は多くが二つ紋型。昆虫図鑑で調べたら、ほとんどのてんとう虫があぶらむしを食べる益虫だった。
ぼくは今まで益虫はナナホシテントウムシだけかと思っていた。(ニジュウヤホシテントウは、じゃがいも、なすなどの害虫)
ナナホシテントウムシは赤い体に黒い丸。二つ紋型は黒い体に赤い丸。紋のない無紋型、四つ紋型、まだら型、19個の紋が
あるのもいるそうだ。
ぼくはちりとりを持って庭に出た。満開の梅の老木と、小さな蕾がまだ固い2本の桜の木の根元にてんとう虫を"まいた”。
(MAR.25)
■『江戸の学び-教育爆発の時代-』展
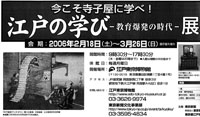
寺子屋に興味があり江戸東京博物館にでかけた。『江戸の学び-教育爆発の時代-』展。寺子屋での指導は全員
揃ってというのではなく個別授業に近かった。読み書き等、学びの実体が豊富な資料からよく分かった。喧嘩する子や
勉強しないで遊んでいる子もいるが、師匠が叱るそぶりはない。実におおらか。
多くの年中行事があり、特に書初めは大事だった。半紙に薄墨で練習を繰り返し、さらに上から濃い墨で書く。紙の
白い所が見えなくなってもまだ使う。真っ黒になった紙は水洗いしてまた使ったという。半紙を束ねた練習帳に残る
朱墨の跡……師匠の心が込められているように思えた。
様々な錦絵の中では、『子宝五節句遊 七夕』に見入った。ちょうど今、ぼくも七夕のイラストレーションを描いて
いたから。七夕飾りは短冊に願い事を書いて笹に吊るすのが普通だが、この時代は短冊の形も色々だ。葉っぱの
形をした紙もある。梶の葉だという。織姫の別名が梶の葉姫と呼ばれたことから吊るすようになったとか。もっと昔は
本物の梶の葉に文字を書いていたという。
寺子屋には実際は”寺子屋”という看板は掛かっていなかったようだ。 例「御家 筆跡稽古所 精光堂」
(MAR.24)
■作りたての草もちの差し入れ



現童春季展の搬入まであと10日。出品作『父さんの話』制作のピッチをあげる。今日もアトリエにこもり
仕事。いや来客あり。下の畑の主、石井孝平さんだ。軽四輪に奥さんを乗せて。「有賀さんの車が見えたから
来ているかなって……」。在宅を確認して帰っていったが、ほどなく戻ってきた。草もちを作って来てくれたのだ。
摘み立てのヨモギの香りがする、まだ温かさが残るもち。その場で黄な粉をつけパクリ。うまい!12個もある。
食べきれないよ。感謝。「いつも米や栗の渋皮煮など,頂いてばかりで心苦しい」と言うと、「喜んでくれれば、
それでいい」と仰る。石井さんと奥さんは仲がよくいつも一緒。二人の笑顔が素晴らしい。これ以上の笑顔は
ないと言う位、とびきり嬉しい顔をなさる。満面笑みと言うやつだ。人の心を明るくさせる。そんなわけで、
今日は草もちを頬ばりながら、幸せな気持ちで仕事をした。
(MAR.21)
■仕事の手を休めフキノトウを探す


今夜の酒の友は、鳩山フラワーガーデンの銀杏と、摘みたてのフキノトウ。銀杏は炒って空き瓶で
殻を割って食べた。フキノトウはフキ味噌。少量だからアク抜きをせずに口へ。もう少しあったらフキノトウ
の天ぷらを楽しめたのに……。この次を期待しよう。山菜の王様はタラの芽だというが、ぼくはフキノトウの
苦味が一番好き。春の味覚に感謝。仕事の後の酒……、星夜の静けさ……、一日を想う。勝る喜びなし。
(MAR.17)
■創作絵話 『父さん』彩色


■創作絵話『父さん』




(MAR.15)
■『こんなこいるかな』への思い
 NHKおかさんといっしょ『こんなこいるかな』12人のキャラクター
NHKおかさんといっしょ『こんなこいるかな』12人のキャラクター 月刊幼児誌「げんき」6月号巻頭にミニ絵本『こんなこいるかな』をつける企画。食いしん坊のもぐもぐを主役にして、
仕掛け、クイズも混じえて構成。裏表紙にはこんなこいるかなの歌詞と楽譜をと提案したが、編集部よりこんなこいるかなの
コンセプトや有賀のメッセージのほうがといわれ、今日、その文章を書く。
こんなこいるかなは、幼児に色んな子がいることを感じさせるキャラクターの性格を強調したアニメ、絵本、お話。一話に
一キャラクターが登場する。いやだいやだのやだもん、いたずらっこのたずら、こわがりやのぶるるetc。性格を際立たせる
ために、ニュートラに設定した小犬のペロと小猫のミャーを配す(無性格的または模範的な二人)。主役のやだもん、ぽいっと
たちに比べ、ペロとミャーの”優等生ぶり”が如何につまらないか。その人の持ち味、つまりキャラクターが大事だということを
書いた。子供の個性の萌芽をやさしく見守ってあげて欲しいとも。それも長い目でね、とも……。
100人に100の個性。1000人に1000の輝き!『 こんなこいるかな』のキャッチコピーは”きみがいるからおもしろい”だ。
(MAR.12)
■版画刷り上り(杉皮紙)を水張りする



父と子のお話といっても、視点は”父さん”。父の子を思う気持ちを描きたくて、表紙とも6枚にまとめる。音楽関係の
季刊誌だが、読者が子供に限らないところがいい。お父さんもお母さんもお爺さんもお婆さんも見るだろう。父親の
雄魂さと絶対的な愛情、それから大人になっても未だ失ってない童心、少年の心、感受性を表現したくて。
この後、彩色に入る。楽しみは続く……。
(MAR.10)
■今年はマテバシイのドングリが食べられないぞ!
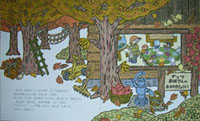

造園業者に家の周りの樹木(杉、栗、ネムノキ等)の剪定を頼んでおいた。今日来て見てビックリ!枝や丸太の山で家に
入れない有様。
それより、マテバシイの木が見るも無惨に切り詰められていて、これには言葉がなかった。「この木は切らないで……」剪定を
細かく指示しておけばよかったと悔やんでも後の祭り。今年は、どっさり実を付け喜んでいたマテバシイのドングリが、
常緑の茂みとともに、すべてなくなってしまった。マテバシイは、香椿(チャンチン)の大木が立ち枯れて以来、アトリエの
シンボルツリーだった。
秋にはドングリが降るように落ち、その音を耳にしながら仕事する……。幸せをくれる木だった。切ってはならぬ木なのに……。
葉を落とし枝を束ね、丸太と共にデッキの下に運ぶ。これに半日費やし、今日の仕事は版画2枚彫るにとどまる。
マテバシイの薪をくべるたび「すまない」思いに駆られるだろうなあ。
(MAR.5)
■ シラカシの丸太を頂き喜ぶ…………凛冽な北風吹き荒れた一日



父と子をテーマのお話。3見開きだけだから、思い切ってネーム(文章)を少なくして版画で表現する。まず裏表紙の
絵から彫り始めた。サクサクと彫り進めながら「父と子」の会話を考えていた。いや、「父」の心を思っていた。ぼくの父は
外地より引き揚げて以来病に伏し、50歳で亡くなったが、毎晩のようにぼくに寝台で”物語”を聞かせた。自分が果たせない
夢を語りたかったのだろう。ぼくが絵や話に描く父は、普遍的な父親像だが、どこか自分の父親が投影されているかも
しれない。満州の荒野に立ち向かう男、雄雄しい父、厳しい父、子を慈しむ父が……。
静けさを破るチェンーソーの音。人声も。隣接する雑木林を植木職人が剪定に来ていたのだった。伸びた枝を切るというより、
伐採の感じ。重機を使っての大掛かりなもの。ここまで切り詰めるのかと呆れていると、造園業者が挨拶にきた。大鋸屑が
風に飛ばされ屋根に落ち、庭一面を覆ったのだ。この大鋸屑は大地に解け込むか、また風に舞って消えるだろう。”植物の粉”
ゆえ、不快には感じなかった。
それよりぼくは、切り倒したシラカシの木が欲しかった。ストーブの薪としてシラカシは絶好。トロトロ燃え、火持ちが良いのだ。
話をすると、若い職人が二人、運搬を手伝ってくれた。有難かった。デッキの下に積み乾燥さす。もう、次の冬の準備。
ストーブの灰を埋けにいくと、ミツマタが枝を撓らせ揺れていた。弥生3月とはいえ、風はまだまだ冬風だ。
(MAR.1)
| 2月のアトリエだより |
■パウル・クレー展 (ベルン パウル・クレー センター開館記念)


久々のクレー展。没後50周年に行われたクレー展を見て以来だ。(1990年/佐谷画廊)学生時代ぼくは美術手帳などで
クレーを知り、抽象と具象をさまよう線と色の美しさに感動を覚えた。作品から発する詩的言語がペンとインクの魔術に思え、
一筆描きのようなドローイングに、穏やかな色彩のメルヘンに、うっとりしたものだった。その後、大規模なクレー展を見て
興奮、「クレーの日記」も夢中になって読んだのもこの頃。
大丸ミュージアムでのクレー展は昨年の8月、スイス・ベルン郊外に「パウル・クレーセンター」がオープンしたのを記念して
開催された。センターにはクレーの作品が4000点あまり所蔵されているという。が、今展はその中から60点の紹介。60点では
いかにも少なく物足りない。ポスターのキャッチコピー”クレー芸術の全貌”はオーバー。又、作品保護の為とはいえ、50ルックスに
落とした会場は暗くて色が分からない。フロアは狭く天井も低い。順路表示も不親切。パーテーションのつなぎ目に平気で映像を
映すなど……、配慮が足りない。とはいえ、様々な技法を楽しんで”作った”作品を間近で見られるのは嬉しいこと。ぼくは”糊絵の
具”で描かれた絵の不思議な筆致に目を凝らした。重なり合う色の奥の奥に惹き付けられ見入った。
図録は60点の作品では体を成さなかったのだろうか、約80点の作品を加え、「クレーARTBOX
-線と色彩-」として発刊された。
編者は日本パウル・クレー・センター、版元は講談社。編集は講談社総合編纂局/立山富貴子とある。立山氏とはイタリア・ボロ
ーニャでお会いしたことがある。国際絵本原画展ガラ・パーティーの席での写真を送っていただいた。もうあれから20年近くたつ。
立山氏は編集一筋。良い仕事をなさっておられる。掌に乗るほどのコンパクトな画集だけれど、クレーがぎっしり詰まっている。
イタリアの建築家レンゾ・ピアノが、クレーの作品からインスピレーションを受け設計したパウル・クレーセンターの紹介も。立山氏
も取材に行かれたのだろうか。ぼくもクレーの美術館にはいつか行ってみたい。 (PAUL
KLEE 享年60歳)
クレーは生涯に1万点近くも作品を制作した。デッサンが圧倒的に多く半数を超える。エッチングやリトグラフは以外と少なく
合わせて100点ほど。旺盛な制作欲なるも55歳、体調を崩す。進行性皮膚硬化症という難病。翌年は作品制作数25と激減。
驚くのは59歳、死の前年だ。この年制作された作品は実に1254点。芸術家の底知れぬ凄まじい創作欲に敬嘆する。
ぼくは明日明後日、鳩山で板絵を制作する。たぶん、訪れる人も無く日没……静穏。深沈と更ける冬の夜も”至福の孤独”。
吾が道、枝道、迷い道……。されど吾れは他の道知らず。クレーの画集もバッグに入れていこう。ページを繰りながら酒を酌む
ささやかな愉しみを思い描きて。
(FEB.25)
■ 春はすぐそこに……。(鳩山にて)




鳩山は東京より気温が2~3度低い。日差しは弱くまだ寒いけれど、風がないのを幸いに庭に出て食事。
アトリエの中もかなり冷え冷えするから、かえって外の方が暖かいくらいだ。ポットに熱いコーヒーを入れ、パンとチーズと
みかんの昼食。いつもなら食事を妨げる虫たちが、この時季は現れず快適。
ツーピー、ツーピー、ヤマガラが飛んできた。枝から枝へとび移りぼくの方を見ている。そうか、お腹がすいているんだ。
「よーし、ごはんをあげよう」と思ったら、そこへ2羽のヒヨドリがやってきて、小さなヤマガラは飛び去ってしまった。
残念ながら、みかんは食べてしまったので、パンを2かけら、離してテーブルに置いて、そうっとそこを離れた。”小鳥の
レストラン”は静かな方がいいから。
天は灰色を帯びた空色。春を待つ嬉しさが、ぼくをアトリエに戻り難くさせる。足は正直……、畑に向かう。先ず、
フキノトウを探す。まだ芽がでておらずがっかり。
あたり一面枯葉色、その中でロウ細工のようなロウバイの花の薄黄色が際立っている。ロウバイは梅より先に
咲くんだなあ。梅はバラ科、でもロウバイは梅じゃないんだよなあ。(ロウバイはロウバイ科)なんて考えていたら、
スモモとナシの間に植えた梅の木が目に留まった。スモモやナシが枯れ木然としているのに対して、梅の木は早や
蕾を膨らませ、先端に赤い花弁をのぞかせている。開花も時間の問題だろう。梅が咲き出せば春は早足で近づいてくる。
待ち遠しいけど、春間近の”今”も、心ワクワク……、幸せの時だ。
ミツマタの花も盛り。紫モクレン、サンシュユの蕾もふくらみかけている。ブナの尖った小豆色の芽、クロモジの天を
射るような鋭い芽も、春の近いことを教えている。ひと回りして、”小鳥のレストラン”に戻れば、お客様の姿は無く
ご馳走のパンも跡形なく消えていた。この次は、みかんやりんごもメニューに加えてあげよう。
(FEB.19)
■仕事中のスナップ(渋谷)
 ・アクリル絵の具で着彩
・アクリル絵の具で着彩 仕事場での雑誌インタビューがあり雑然とした部屋を少し片付けた。少しと言うのは、左に積まれた
物を右に移動したという程度だから。普段全く掃除をしないというわけではないが、何てったって絵を描く、
本を読む時間の方を優先(酒を酌むひとときも)……、これは口実。
上の写真はクレヨンまる制作スナップ。1色1色塗って行く。絵の具のビンの開け締めが大変。ふたが
絵の具が固まって、ちょっとやそっとでは開かなくなってしまうから。ヤットコのようなオープナーでふたを
挟んで開けることもしばしば。それよりも、この絵の具がいつまで生産されるかが心配。ぼくが使用している
大判ネガ、ポジフィルムも国内での生産はなくなり、入手が困難になって来た。そういえばCGの時代だ、
“手描き用”イラストボード類も種類が激減している。これは憂うべきこと。
“売れる物のみ作る”利便、効率の商業主義のもとで大切なものが失われて行く。表現の多彩さ、喜びまでも。
『おひさま』に特別付録「お話ビデオ」がつくことになった。「ミラクルクレヨンのクレヨンまる」のアニメ、過去
120話の中からどれを入れようか迷ったが、今回は第45話”お店やさんごっこ”に決めた。
しかし雑誌に掲載のお話をアニメに表現するには絵のカットが足りない。そのままでも話は分かるけれど
自然な流れにしたい。作るなら良い物をと、シーン2枚描き加えた。先ずは自分の納得、満足の先に、
作品がある。
(FEB.18)
■映画『ポロック 二人だけのアトリエ』 (エド・ハリス主演/監督 2000米)
新聞の「TVシネサロン」に『ポロック 二人だけのアトリエ』が載っていた。放送はWOWOW。見られず残念だ。
ぼくは2003年11月公開された折、現代童画展搬入も迫り気ぜわしかったが、日比谷のシャンテ・シネに駆けつけて
見た。もう一度見たいと思っていた。
前衛画家ジャクソン・ポロック(1912-1956)は40,50年代の米国モダン・アートの魁。十代の頃から飲酒、アル中で
何度も入院。精神分析治療を受けながら、絵の具をぶちまける、垂らす、撒き散らす……大胆かつ野生的、アクション
ペインティングという独特のスタイルを貫いた。俳優エド・ハリスは構想から映画製作まで10年かけた。その間、自らも
「自宅にアトリエをこしらえて床の上にキャンバスを置いて絵を描く特訓をした」と語っている。迫真の演技に圧倒された。
アーティストの生き方を描いた映画はシリアスで、楽しいといったものではないが、甘ったれた日常に楔を打ち込まれ
るようで、ぼくは好んで見る。ゴッホの新旧3作、カミユ・クローデル、フリーダ・カーロ等、芸術家を描いた映画の中で、
『ポロック 二人だけのアトリエ』は、特に制作ぶりをしっかり描いている。ドリッピング等のエネルギッシュな作業も、
ポロックの繊細かつ激しい性格もリアルに伝えていた。年上の妻はポロックの一番の理解者。時に幼児性、酒に溺れ
るポロックを母親のように支える。が、ポロックは自暴自棄になったのか、猛スピードで飲酒運転、命を落とす。
絵に行き詰まり自殺か、事故かは分からない。ただ、パーソンズ・ギャラリーの個展ではほとんど買い手が無かったし、
死の前年は中毒症で絵を描いていなかったという。
ポロックが妻に語った「10年は良い時(注目され脚光をあびた)があったじゃないか」が、物語っているかも知れない。
画家の強烈な表現欲、孤独、鋭すぎる感性の脆さ、絶望……。
ポロックの車が木に激突するラストシーンが焼きついている。車体の緑色が鮮烈に。50年式のオールズ・モビル。
ポロックが2枚の絵と引き換えに手に入れた車だという。
JACKSON
POLLOCK 享年44歳
(FEB.15)
■永久の別れと一冊の絵本
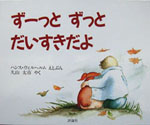 ・『ずーっと ずっと だいすきだよ』(評論社)
・『ずーっと ずっと だいすきだよ』(評論社) Sの父君が亡くなった。病院での闘病生活を数年来、昼間はお母さんが、夕方はSが支えていたが、正月5日、
天に召された。一日欠かさずの病院通い。いや、大雪で行かれなかった一日を除いて。その日が、1月5日だった。
Sは自分を責め、落胆。悔やむことしきり。心痛ましいメールに、返信の言葉も見つからなかった。
Sは二十数年前、ぼくがデザイン学校のイラスト科を受け持っていた時の教え子。現在は地方に在住、個展開催、
ポスターや銀行のカレンダーに作品を提供するなど活躍している童画家である。先年出版したSの画集『みんな大好き』
には、ぼくは”鮮やかな色使い、天真爛漫な童心絵画”とのオマージュを書いた。
愛する者の喪失、その受け入れ難い現実に慟哭。Sはあの日、”あの大雪の日”だけ病院に行かなかった自分を詰る。
罵る……。でも……、後悔はいらない。何年も通い詰め、物言わぬ父君の耳元に囁きかけたそうではないか。胸をさすり、
手を握りしめたというではないか。
少し元気を取り戻し歩み始めたのだろう。Sのホームページの、地元の新聞に寄せたエッセーには、最近では父親を
誇りに思う気持ちが綴られている。幸せな親子関係が文章から伝わってくる。
お悔やみの言葉はともかく、ぼくに他に何が出来るだろう。この深い哀しみは時が癒すしかないと分かっているから。
しかしながら、十分に愛し尽くした者には、心穏やかになる日が必ずや来る。そう時を待たずとも……。
ぼくは1冊の絵本を送った。『ずーっと ずっと だいすきだよ』(ハンス・ウイルヘルム/作絵)
飼い犬エルフィーが年をとり太った。寝ていることが多くなり、階段も上れなくなった。ある朝、エルフィーは死んでいた。
「ぼく」はエルフィーと毎日一緒だったから、悲しくてたまらなかったけど、毎晩「ずーっと ずっと だいすきだよ」って語り
かけていたから、いくらか気持ちが楽だった。………少年「ぼく」のやさしい気持ちがひしひしと伝わって来る絵本。
「ぼく」と一緒のエルフィーはさぞかし幸せだったろうし、「ぼく」もエルフィーからたっぷり幸せを受け取っていることだろう。
嘆き悲しむ沈鬱なSは、愛情に包まれ生を閉じたエルフィーに何を思うか……。
添状に「S君、己を責めなさんな。絵本の”ぼく”は貴方だ。良くやったじゃないか。」と、書いた。
気持ちの表現としての言葉、大切。温かい心を滲ます言葉、美しい。
この絵本、”いつかぼくも、ほかの犬をかうだろうし / 子ネコやキンギョも、かうだろう。 / なにをかっても、まいばん
きっと、いってやるんだ。 / 「ずーっと、ずっと だいすきだよ」って。”で終わる。
慈愛の心あってこそなれど、言葉の持つ力は大きい。
(FEB.11)
■春待ちわびて



暦では立春を過ぎたのに氷点下の寒さ。予報通り夜半から雪が降り始め、仄々明けには一面うっすら
雪化粧。七十二候では東風解凍。”春風が氷を解かす”なんて、まだまだ。それでも小正月を終えてから日が
延びているのを実感する。5時過ぎてもまだ明るい。仕事をしていても、夕闇が迫ることなく、いきなり暗くなる
感じが嫌だったが、これから季節は春に移る。希望ふくらむ、心ときめく春に向かう。そう思うだけで嬉しくなる。
雑誌連載は、「こんなこいるかな」も「クレヨンまる」も、4月号の色校正を済ませた。「クレヨンまる」(第124話)
では、ハーブおばさんがヨモギを摘んでお料理をする。このお話、ワルズーやミイラばあやはお休みだけど、春の
息吹を一足早く届けたくて書いた。乞うご期待!
ヨモギは、ぼくの田舎では"もちくさ"といった。枯れた草がよく燃えるので、善燃草(よもぎ)。春、燃えるが如く
芽が出るので、善萌草(よもぎ)。中国では仙人草とも。子供の頃見た、爺様が背中から煙を立てている不思議な
光景、お灸。そのモグサは燃え草から転じたのだそうだ。
アトリエのある鳩山の野辺がヨモギや春の草で覆われるのは3月か。今頃はフキノトウが顔を出していること
だろう。北風は厳しいけれど、冬はもう後ろ姿……。早春の味覚、蕗味噌がぼくを鳩山に誘っている。
(FEB.7)
■節分「鬼は外」と福豆
今日は季節の分かれ目、節分。節分は立春、立夏、立秋、立冬の前日のこと。でも今では、
「鬼は外、福は内」の節分だけが行事として残るだけ。室町時代に始まったと言われる豆まきは、
疫病や災害や寒さを追い払うためのもの。ぼくは福豆が大好物で、邪気払いの豆まきより
食すること専ら。美味しい豆が、この季節しか売り場に並ばないのが残念だ。だから食べる。
ウイスキーをグビグビやりながらボリボリ食べる。豆の数、年齢プラス1じゃ納まらない。このプラス1は
立春からの新年の分だが、ぼくはこの先、何十年もの分も食べてしまう。
マンションが立ち並ぶ都会では「鬼は外!」の光景を目にすることはないけれど
昔は、家々のあちこちから家族全員の声が聞こえて来た。「隣に負けるな。」父に言われ、ぼくは
蛮声をはり上げたことを覚えている。親父は豆を50粒食べて、世を去った。毎年欠かさず
鬼を払っていたのに……。
鬼が跳梁跋扈している世の中でも、一番恐い鬼は自分の心に住みつこうとする鬼。怠惰、
慢心、自己満足……、節分でなくとも、「鬼は外」を、ぼくは唱えなくてはいけない。豆を
頬張って酒を酌んでる場合じゃない。因みに、軽々しく「福は内」は言わない。之ばかりは願って
叶うこととは思えなくて。
(FEB.3)
2006年
| 1月のアトリエだより |
■ グランマモーゼス展とサトウカエデの木
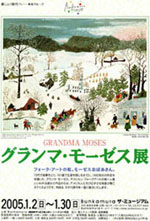

グランマ・モーゼス展を観たのは昨年の今頃だった。牧歌的なフォークアートは正に”懐郷の詩”。機会が
ある度に観ているが、まとめて観るのは久しぶりだった。有名になっても生涯農村で変わらぬ生活を送った、その
意思の強い生き方に共感、羨望。アンナ・メアリー・ロバートソンー・モーゼスは”モーゼスおばあさん”と親しみを
こめて呼ばれたアメリカの素朴画家。70歳を過ぎてから絵を始め、亡くなるまでに農婦として生きた生活体験を、
原風景を、油彩1600余点に描いた。
「雪がふる農場の引越し」「アップルバター作り」「古い樫の手桶」「農場に春が来た」「収穫期」「七面鳥」など、
多くが田園風景の絵だが、その情景は幸福感に満ち溢れ、たまらなく懐かしさを覚えさせる。
参考にした新聞や雑誌の切抜きのスクラップ、それをトレースしたあとも見られ、誠実な制作過程がうかがえた。
今回は60余点の展示だったが、会場が暗すぎるのを除けば(Bunkamuraザ・ミュージアムはいつも暗すぎ)、大満足。
見ごたえのある展覧会だった。
ぼくは「砂糖づくり」(Sugaring Off 1943)の絵葉書を買った。サトウカエデの木から樹液を集め、煮てシロップを作る。
大人も子供も一緒。牛もいる、馬もいる。雪野原の美しい風景から、喜びの声が聞こえる。愉しい歌も聞こえてくる。
感謝の祈りも伝わってくる。人間の幸せに形態があるならば、こういうシーンだろう。マザーモーゼスの絵は人間賛歌だ。
ぼくは琥珀色のメープルシロップが小さい頃から好きだった。あとで知ったことだが、このメープルシュガー作りは
大変!北米とカナダのサトウカエデの原生林での樹液採取は、厳しい冬の終わりの数週間だけ。しかも糖度
2パーセント程度の樹液を1/40量になるまで煮詰めるのだとか。
メープルシロップには思い出があるが、これは又の日ということにする。ぼくは園芸店をまわりサトウカエデを探した。
50センチにも満たない苗木でも、見つけて大喜び。早速求めた。ぼくは遠い遠い夢を胸に抱く。ブナを植えブナ林の夢を、
トチを植えトチの実を食べる夢を、オリーブを搾る夢を……。それらと同じく、メープルシロップを作る夢を見たくて。適うか
適わぬかは問題ではない。夢を馳せる植樹。100年掛かることでも、ぼくの夢の中では現実。ブナの林の木漏れ日の
中に自分がいる。サトウカエデの幹に穴を開け、樹液を採っているぼくが見える。
マザーモーゼスは1961年101歳で天寿を全うした。入院して絵を禁じられたが、生き甲斐を取り上げられてしまった
ように思えてならない。同年6月に制作された最後の作品のタイトルは「虹」。1951年にも同題で描いているが、モーゼス
おばあさんは自ら虹を渡し、天に昇って行ったのだ。
幸福とは、生き甲斐とは……考えさせ、勇気を与えたマザーモーゼスの死を、全米の人が悲しんだという。命日は12月
13日。ぼくの母も同日。サトウカエデの木に水を遣る度に、様々な思いが脳裏に浮かんでくる。
(JAN.31)
■版画『奇術絵師-猫-』完成 版画用紙、杉皮紙のこと

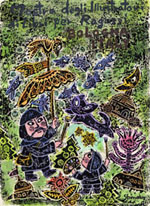
昨秋から制作していた版画『奇術絵師-猫-』が漸く完成。シルクスクリーンで刷り上げ手彩色する技法だから時間を
要する。多部数は望めず、今回も仕上がりは20部程度。紙は手漉き杉皮紙。文字どおり杉の皮を剥ぎ漉き上げた
和紙で、素材感が好ましくぼくの版画の表現には欠かせない。輪島の漉き師、故、遠見習作(トオミ・シュウサク)氏より
相当量わけていただいたが、今は残りを気にしながら使っている。
杉と言えば、杉はドングリを降らすマテバシイ同様やたら生え出す。アトリエの前には杉林があるが、杉の実が風に
飛ばされ、あちらこちらと芽を出す。成長が早く、2~3年たったものは抜くのも容易ではない。せっかく芽を出し50センチ、
1メートルと育った幼木をやたら引っこ抜くのも忍びなく、悩むところだ。でも繁殖力旺盛で、この地にもあっているので、
放っておけば、庭は杉やマテバシイの林と化してしまうかも。
毎年何本かは移植するけれど、多くは裏の捨て場に放り捨てる。いつも「ごめんよ……。」杉の子をいたわしくおもう。
ちょっぴり罪悪感、心の痛み。
遠見習作氏の杉皮紙はバーナードリーチも認めたと聞いたが、氏は創作和紙に挑戦する情熱家でもあった。50枚、
100枚と、漉き上げては送って下さるのだが、その箱の中にはいつも実験的作品が詰められていた。ヨモギを漉き込んだ
”ヨモギ紙”、コンブを漉き込んだ”コンブ紙”……菜の花、トウガラシ……、植物であれば何でも漉きこんでみる。漉いて
見なければ気がすまない凄い人であった。
杉皮紙も風合いが毎回異なり、色も乳白からセピア、黄土、こげ茶、黒に近いものまであって、職人というより遠見氏は
芸術家であった。「私の漉いた紙で作品を作って下さることが嬉しい」。との手紙に、ぼくは感謝の気持ちを伝えた。「創作
意欲を湧かせる素晴らしい杉皮紙です。」と。
(JAN.29)
■テニス、戦績続報
7連敗の後は2日で5勝1敗。まずまず。仕事もこの調子で頑張りたい!絵は我流、これで良い。テニスは我流で良いとは
いえないが、不器用な身、不恰好でもこのまま貫くしか手がない。
(JAN.27)
■テニス、新年いまだ勝利なし

このところ冬型の気圧配置が続き厳しい寒さ。20日は大寒。寒風何するものぞとコートへ。
今年2回目のテニス。ヒッティングパートナーは大正14年うまれ、81歳の渡辺九馬夫氏。高齢でも明治大学野球部(あの
名投手、杉下と一緒だったという)で鍛え抜いた体はいたって頑健。九馬夫氏はテニスに適性のないぼくに、私設コーチの
ように丁寧に教えてくださる。感謝。上達せず申し訳ない。
練習が終わってダブルスの試合を2ゲーム。ガットを張り替えて臨んだが、敢え無く2戦2敗。
翌日東京は何年ぶりかの積雪。当分テニスコートは使えないものと諦めたが、22日は晴れ渡り気温こそ低いものの、
日溜りは「もしかしたら……」と思わせた。
23日朝、コートへ。(ぼくのテニスは午前中のみ)オムニコートは砂が流れて砂場状態。ハードコートは使える。四方には
雪掻きの山で風も一段と冷たい。挨拶はお互い”精が出ますねえ!”だ。
唯一の趣味といってよいテニス。でも、”午前中の具合”が、その日の仕事に影響するから、ぼくの精神はガラスのように
脆いのだろう。絵描きの仕事を忘れる貴重な時間なのに、これがストレス?になったりして……。それくらい、下手だ。30年
以上続けているなんて誰も信じないだろう。
それで、今日の戦績……? 3-6,4-6 2連敗。通算、今年7連敗。
今年、未だ勝ちを知らず。どなたか、テニス短期上達術をご伝授いただけませんか。
(JAN.23)
■ミヒャエル・ゾーバの世界展「不思議な物語=ユーモアに秘められた、ただならぬ気配=」を観る
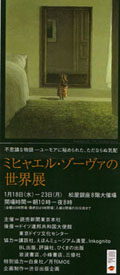

ミヒャエル・ゾーバの絵は見る者に物語をあれこれ想像させる。シュールで高尚なユーモア。例えば「ケーラーの豚」……
木立の緑色に染まる静まり返った沼。一匹のブタが今まさに沼に飛び込もうとするその瞬間を捉えた絵。傍らにはそれを
無表情で見つめるアヒル。草の上に敷かれたマット。二人でピクニックにでも来たのだろうか?不思議な絵だ。面白い絵だ。
あるいは「最後の買い物」……外套を着た七面鳥の夫婦が愉しく買い物。仲良く腕を組んで歩く情景をノスタルジックに
描いている。収穫感謝祭で食べられる運命を知ってか知らずか。縦長画面の右上には人影が……。
展覧会場でフランス映画『アメリ』のプロモーションビデオを流していたが、主人公の女の子アメリの部屋に掛かって
いたのがゾーバの絵。”病気のワニや治療中の犬の絵”2枚。ベッドサイドのブタの電気スタンドもゾーバの作品。演出を
細部まで徹底する監督も流石。この映画、見てみたいと思う。
映画といえば、気になるアニメが3月公開される。ウオレスとグルミットシリーズの新作だ。(ぼくはアニメはあまり好まない。
『岸辺のふたり』(オランダ)、『ベルビルランデブー』(フランス、カナダ、ベルギー)などは良かったが)ウオレスとグルミットは
ユーモアに溢れ視点がヒューマンな手間をかけたクレイアニメ。ぼくの数少ない好きなアニメ作品だ。ウオレスとグルミットの
新作『野菜畑で大ピンチ』でゾーバは背景製作のアートワークを協力しているという。絵コンテを見たが、温かみのある
ウオレスとグルミットの世界、そのエッセンスがあった。
「ゾーバは初めは諷刺画と呼ばれるような挿絵を描いていた。そして油絵ではマグリットやエッシャーのように仕掛けの
ある絵や、暗喩のある絵が好きー略-(MOE2004年7月号)」納得。でも、マグリットでも無い、エッシャーでも無い、ゾーバの
絵の世界には独特の空気感があり、豊かなユーモアが魅了する。
この展覧会の副題「不思議な物語ーユーモアに秘められた、ただならぬ気配」……、これもぴったりだ。
(JAN.21)
■冬木立 三題


<渋谷> 今日投函した手紙の書き出しは”寒威骨に徹するの候~”。きのう今日の吹きすさぶ北風は、体の芯まで
凍えさす冷たいものだった。渋谷の仕事場の前は乗泉寺。その一角にある幼稚園の古木、アカメガシワのいままで落ちずに
いた最後の一葉が、とうとう強風に吹き飛ばされてしまった。ぼくは木々の枝振りを見るのが好きで、葉を落としたこの季節、
梢を見上げて歩いている。アカメガシワの隣には桜。春、あたり一面を薄桃色に染め、夏、歩道に恵みの陰を落とす大木が、
今は寂しげに枯れ枝を揺らしている。いや枯れ枝なんかじゃない。青い空に黒のシルエット、膨らみ始めた冬芽だ。冬芽が
もう春の準備を始めている。
<鳩山> 何本か植えたブナの苗木が根付いた。もう10年にもなろうとしているのに、やっとぼくの背を越す程度だ。ブナは落葉
広葉樹の中では成長が遅く、40~50年もしないと花を着け結実しないという。それでも100年後のブナ林を夢想して植えたの
だった。(詳しくは画集『有賀忍板絵作品集』日貿出版社のエッセーに記す)ブナは葉の色変わりが楽しい。春から夏、、若葉の
黄緑から深緑。秋から冬、茶色のバリエーション。今、落葉樹の多くが葉を落とし裸木だが、ブナは違う。まだ薄茶色の枯れ葉を
枝から離さないでいる。落葉を掃き集めて燃やすと、パチパチ音をたててメラメラ炎を上げる。油分が多いのだろう。激しく燃え
上がる。怖いくらいに。
<相模大野> 大学のキャンパスのイチョウ並木では、昨秋は三度銀杏を拾った。いくらでも欲しいだけ拾えればよいのだけれど、
女子学生がぞろぞろ歩く道で、拾うのはぼく一人。勇気がいる。そのイチョウが葉を落とし歩道が金色の絨毯で敷き詰め
られたのは、もう大分前のことのように思えるけれど、ついこの間のことだ。あの頃は日差しがやさしく穏やかな秋であった。今は
冬真っ只中。確実に季節は移っている。イチョウは鉛色の重た気な空に梢を突き出して太陽を求めている。並木を見渡しても最早、
一枚の葉も見あたらないが、先週までは黄色い葉をヒラヒラさせている木があった。落葉の早さは同じイチョウでも木によって
異なることに気がついた。
さらに発見!黄葉に隠れて見えなかった銀杏は、木々が裸になるにつれて姿を現すけれど、ぼくは今日、まだ実をたわわに
着けているイチョウの木を見つけた。銀杏の実はもう、きれいな黄や薄橙色ではなく茶褐色になりしぼんでいるが、ぼくはなぜか嬉し
かった。
木枯らしに未だ抗っている銀杏。イチョウの小枝は寒空に震えるように揺れ、何やら囁いているように思えた。
(JAN.18)
■『トロースドルフ絵本美術館展』「赤ずきんと名作絵本の原画たち」を観る

今日、松も明ける15日は展覧会の最終日。板橋区立美術館にはイタリア・ボローニャ世界絵本原画展で何度か行った
ことがあるが、交通の便が悪い。最寄の駅、東武東上線の下赤塚駅から炎天下を(ボローニャ展は会期が真夏)汗だくに
なって30分も歩いた記憶がある。寒いし、仕事があるし、出かけようか迷った。
でも招待券を見ているうちに行きたくなった。絵がしゃれている。チケットとパンフレットは、絵本作家ビネッテ・シュレーダーの
赤ずきんがオオカミにキスしている軽妙な落書き風イラスト。それに何故か切手とミュンヘンの消印。スイスのエリザベス・ヴァル
トマン宛てのアドレスも。(ヴァルトマンが誰なのか、このイラストが何だったのか、それに展覧会の感想は別項エッセーで)
200年の間に描かれた赤ずきんの絵本240冊の絵本も凄かったが、ぼくの好きな絵本作家ヤーノシュ(別項絵本の小径で
「おばけリンゴ」「ふしぎなバイオリン」を紹介)のイラストや、多くの人に愛されている「あおくんと きいろちゃん」「フレデリック」
(ともに近々紹介予定)のレオ・レオーニの「フレデリックのバースデー」の絵本原画まで見られたのは幸いだった。
今回は成増で下車。運悪く1時間に2本しかないバスが出たばかり。美術館行きではないバスに乗り途中から歩いたが、
肌を刺す冷たい風の中にも春の光を感じ、足取りは軽やか。見ごたえのある展覧会に、今日は満足な一日だった。
同展の巡回 2006年 4月22日~5月28日 刈谷市美術館
6月10日~7月17日 北九州市美術館
7月25日~9月10日 高岡市美術館
(JAN.15)
■映画 『心の杖として鏡として』を観る


昨年の暮れも暮れ、もはや数え日となり新年のお飾りが街角で売られる中、東中野のミニシアターに行った。精神病院での
芸術活動・37年の軌跡『心の杖として鏡として』。60分のドキュメンタリー。「癒しとしての自己表現」の副題がついているが、
真剣な眼差しで絵と格闘している外来、入院患者の姿に癒しなんか意識させないもっと強い”生の叫び”を感じた。
正直に言うと、精神科に通う患者の日常の奇異な行為を映し出したとき、ぼくは一瞬引いた。しかしながら、アトリエに入ると
彼らは、キャンバスに黙々と向かう…ぼくも同じだ…懐かしさを覚え、頷いていたのだった。”患者ではない健常者”よりずっと、
自分を見つめ対話している、そのひたむきさに深く感動。もちろん患者は描くという行為を通じて結果的に癒されて行くかも知れ
ないが、今流行りの安っぽい和み、癒しとは別物。それらは与えられるのを待つだけだから。自己表現は楽なことではなく、
それによって癒されるのは能動的。
制作に入っている彼らは病気なんか感じさせない無邪気な幼子であり、幸せな時間を過ごす人間だ。
アトリエ仲間、女性のEさんが他の病院に入院させられたとき、共に絵を描いてきたHさんが1冊の絵本を制作した。主人公は
もとフェアリー(妖精)族。繊細な感性ゆえに心を病んで倒れるが再び立ち上がるというストーリー。30枚の絵をもの凄い集中力、
スピードで描いた。Hさんはそれを持ってお見舞いに行く。車椅子で現れたEさんはそれまでアトリエにいたときも無表情だったのに、
絵本を読み終わる頃にはポロポロ涙をこぼしていた。絵本の終わりには「Eさんの心の中にはアトリエのメンバーの応援が聞こえて
います。これから先もずっと、ずっと永遠に」と記されている。
映画館を出ると弱い日差しを吹き飛ばすような北風。背を丸め駅へ。アトリエ仲間の発表会で朗読された「芸術は治っては
ならない病気なのです。」の言葉が、頭に響いていた。
(JAN.2)
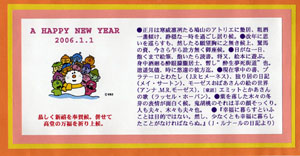
2005年
| 12月のアトリエだより |
■フィンランドの絵本展をのぞく
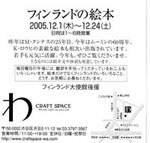
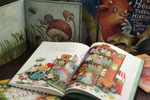
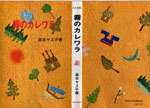
暮れも押し迫った23日、現代童画会の会合。クリスマス前日に男4人衆、何とも無粋だ。本郷の事務局に
向かう前に、<CRAFT SPACE わ>をのぞく。
ここでは、年一回フィンランドの絵本が展示される。各絵本一冊限りの販売が多く、高価なのは致し方ないが、
絵が素晴らしくても、フィンランド語が分からないのが残念である。今回はムーミンの作者トベ・ヤンソンの珍しい
油絵の画集や、デカルコマニーで、動物を表現した詩集、「サンタクロースと小人たち」でおなじみのマウリ・クンナスの
本邦未発売の絵本が何冊もあって楽しめた。又、カレワラ(フィンランド民族の一大叙事詩。国家創生、英雄伝説など、
日本で言えば古事記か)を、何人もの絵描きが絵本にしていた。フィンランドの子供たちは、みなこれを見て大きくなる
のだそうだ。写真の「霧のカレワラ」は30年前、装丁家の田中淑恵氏がプレゼントして下さったもの。「有賀さん、
カレワラのような大きな物語を絵にしてみたら如何」の手紙を添えて。魅かれる世界……、いまだ果せないでいる。
(DEC,23)
■サンタクロースの生活
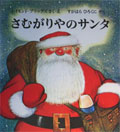
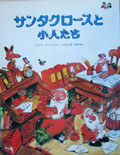
・寒がり屋のサンタと湯たんぽ
新聞の家庭欄、育児相談である。「サンタクロースは、いるのかいないのか。子供に聞かれたら、どう答えたら
よいか?」この人、自分の考えがないのだろうか。知育偏重、マニュアル教育の弊害がこんなところにも顕れている。
サンタのことまで、教えてはくれないからなあ。それにしてもこのお母さん、自信が無さ過ぎるよ。
子供に夢想させる。想像の世界で自由に遊ばせる……。これが親の務めだろうが。「ねえママ、サンタクロースって、
本当にいるの?」「ママはいると思うわ。だって、いた方が楽しいでしょ。パパにも聞いてみたら」「パパ、サンタクロース
見たことある?」「見たことはないけど、パパはいるって信じてるんだ。パパが子供だった頃、枕元にプレゼントが置いて
あって、それには”サンタより”って書いてあったからね。」とまあ、これくらいのこと、喋れないのかなあ。まったく。
一番楽しい子供との会話ではないか。大人は子供のイマジネーションをSHUTOUTすること勿れ。子供時代から遠く
離れた大人も、今一度絵本を開くと良い。幾冊か見ているうちに子供にとって、この時期、”サンタクロースの存在”が
必要なことが分かって来るはずだ。サンタクロースを題材にした絵本は数多くあるが、その生活を描いた作品を紹介する。
フィンランドの絵本作家、マウリ・クンナス『サンタクロースと小人たち』『サンタさんへ12のプレゼント』(偕成社)『サンタク
ロースと小人たち』にはオーロラの国フィンランドの山奥で小人と、クリスマスプレゼントを作る大勢のサンタクロースの
生活がユーモラスに描かれている。ワイワイガヤガヤ話し声が伝わって来る、とびきり楽しい絵本である。
もう一冊は、レイモンド・ブリッグズ作・絵『さむがりやのサンタ』(福音館書店)。こちらは、サンタさんは一人だけ。寒がり
屋のサンタが朝起きてから、プレゼントを配りに出かけ、家に帰りベッドに入る迄を漫画のようにコマ割りして描いている。
描写が細やか。たとえば、雪を踏みしめニワトリ小屋へ行き、ニワトリに感謝して卵をとり、ベーコンエッグを作る。ソリを
走らす場面では、雪、雨、嵐、霧……と変わる天候。入浴後、体にコロンを振り、顎ひげをとかすところ、飼っている犬と猫
にもプレゼントを忘れない。それも”恰好の”プレゼント”を……。発見も多く、何度見ても見飽きない。
近頃よく見かける「The Snowman」のキャラクターもレイモンド・ブリッグズの作品だ。『さむがりやのサンタ』はケート・
グリーナウエイ賞を受賞、世界の子供たちに愛されている。
『さむがりやのサンタ』に出てくるサンタさんは、夜寝る前にミルクココアを作る。入れ歯をグラスに入れる。コップ一杯の水を
用意する。それから、水枕のような形をした湯たんぽに湯を入れる。そしてそれらをトレーに乗せ二階の寝室に向かうのだ。
ぼくは笑ってしまった。”湯たんぽ”に。「そうかー。サンタさんも湯たんぽか。」ぼくもついこの間、湯たんぽを買ったのだった。
昔使った楕円形のブリキ製のものとは違って、銅製(ふたは真鍮)。ピカピカ輝いている。形はユニークな蒲鉾型。これ、使い
勝手が良くてとても気に入っている。今年最高の買い物だ。
因みに湯たんぽは漢字で、湯湯婆と書く。ぼくはアトリエに泊まるとき、湯を沸かして、”湯湯婆”に入れる”儀式”を、密かに
楽しんでいる。深夜一人、サンタさんと同じように……。
(DEC.19)
■『アンデルセンの生涯とその作品展』を観る

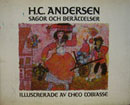
「マッチ売りの少女」「おやゆび姫」「「はだかの王様」「みにくいアヒルのこ」「人魚姫」……。160余編の童話を
綴ったハンス・クリスチャン・アンデルセンは正に童話の王様。今年は生誕200年。その記念展が3月、岡谷の
イルフ童画館を手始めに、国内8か所で行われている。デンマーク・オーデンセ市立アンデルセン博物館の131点
にも及ぶ所蔵品の展示だという。
ぼくが行ったのはその記念展ではなく、逓信総合博物館での催し。童話直筆原稿や、アンデルセンが使用した
調度品(テーブルやソファーや本棚)、童話の初版本に加え、”逓信博物館”だけあって、アンデルセンの手紙、19
世紀のデンマークの郵便資料(アンデルセンの時代の郵便ポスト、郵便ラッパ、ボール型郵便馬車の模型、切手)
などが展示されていた。(デンマーク王立図書館、国立ポスト&テレミュージアムの協力)アンデルセンの切り絵も
多数見ることができたが、何より興味深かったのは、アンデルセンが母に宛てた手紙。アンデルセンは旅行に明け
暮れた人生を送った。日記などから、母へ宛てた手紙の存在は判明していたが、これまで現物は見つかっては
いなかった。この<母への手紙>は100年ぶりの新発見で、世界初公開ということである。
定説ではアンデルセンの、母親<救貧院で亡くなる>に対する感情は冷ややか。<アルコール依存症、無教養、
金の無心ばかりする母親像が、日記から浮かび上がるという>。ところが、この手紙、「---親愛なるお母様」で始まり、
ーーー26歳のときの旅行記『影絵』の出版を知らせ、「ーーーお母さんからのお便りを楽しみにしています。僕は
元気ですよ。あなたのクリスチャンよりーーー」と、結んでいる。母を思い慕う、普通の青年に見えるのだが……。
内外作家のアンデルセンへのオマージュ作品も展示されていた。オブジェ、陶芸、タブロー。これといって見る
物は無し。いや、ラース・ルンドベアという画家の、アンデルセンの童話をモチーフにした50号大の連作は面白かった。
針金で縁取られたような盛り上がった線、石壁を思わせる地肌のマチエール、登場人物すべて口を描かないユーモ
ラスな表情……。インパクトがあり、新鮮に映った。
アンデルセンは失恋を繰り返し、生涯独身であった。幼少年期、経済的には貧しかった家庭だが、後年、詩には
こう書いている。「ーーー略ーーー世界はなんて すばらしいのか / 幼き日 わたしの思い出」
幼少年期を”輝ける宝物”に持てる人は、その後の長い人生が厳しく辛いものであっても、何とか生きて行かれると
、ぼくは思っている。もしかしたら、アンデルセンはこの詩を”幸せの光景!への憧れで書いたのかもしれない。親を
これっぽちだって恨んだら、人生に幸せなんてあるはずないもの……。
(DEC.15)
■『くまのプーさん』の初版本

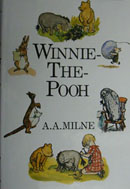
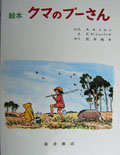
相模女子大附属図書館の特別展示「児童文学の世界---くまのプーさんを中心に---」を見る。
・Winnie-the-Pooh(1926) ・When we were very young(1924) ・Now
we are six (1926)
・The house at Pooh Corner(1928)いずれも思ったより小型本。新書版よりやや大きめで、4冊とも
同じ装丁。
表紙に絵は無くタイトルと作家名のシンプルなもの。作家名といえば、もちろん文はA・A・ミルン、
絵はE・H・シェパード。<BY A・A・MILNE DECORATIONS BY E・H・SHEPARD >の表記。
挿絵画家の扱いは多くが”ILLUSTRATED BY”またはまれに”PICTURES BY”だが、
このプーさんは、”DECORATIONS BY”となっている。なるほど。この絵があってこそだから……、と頷いた。
ショーケースでの展示で、実物を手にとって見られなかったのが残念だが、『PUNCH』紙(PUNCH,
OR THE LONDON CHARIVAL Nov.26.1913)に掲載されたプーさんの原型になった挿絵や、
ミルンの作品「When we were very young」(Feb.13.1924)の記事は珍しく、興味深いものだった。
展示は他に、絵本の原本とその翻訳本。ガース・ウイリアムス「くろいうさぎ しろいうさぎ」(後日、
「絵本の小径」で紹介の予定)、トミー・ウンゲラー「すてきな三にんぐみ」、エリック・カール「はらぺこ あおむし」等。
(DEC.7)
■絵本『やまあらしぼうやのクリスマス』
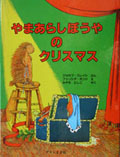 ・『やまあらしぼうやのクリスマス』
・『やまあらしぼうやのクリスマス』 クリスマスの季節。クリスマスツリーの飾りつけも随分変わったものだ。今や電飾は白や青のLED、クールな輝きが主流。
おしゃれ。赤や緑色の豆球が点滅なんて滅多に見なくなった。思えば何年か前までは、雪は綿、赤いガラス球や金色の紙の
星を吊り下げ、金モールを巻く……どこのツリーもこれが普通だった。
毎週水曜日に降り立つ相模大野駅コンコースにも、大きなツリーが置かれている。昨年は中央広場の吹き抜けに出現した
飾り気の無いモミの木に驚いた。その存在感と、辺りを浄化するようなフレッシュな深い緑に感動したものだ。今年もと期待して
いたが、失望。
神々しくさえ見えたモミの巨木に代わって、今年のツリーは周囲に豆球が点滅する赤い三角錐のオブジェ。造花のバラと音楽の
五線がグルグルッと巻かれ、金色の音符が貼り付けてある。スターヘッドはト音記号だ。 この人工的なツリーには素朴さや
清らかさがない。赤に金、豪華を演出したつもりだろうがセンスが悪い。お世辞にも美しいとは言えない。目に入れたくない物体だ。
ボタンを押せばクリスマスソングが流れる仕組みになっているが、四方に<監視カメラ作動中>のパネル。ああ嫌だ。
そびえ立つモミの巨木と、静かに対話をすることを楽しみにしていたのに……残念だ。
本屋の絵本コーナーには今、「クリスマス絵本」が所狭しと並んでいる。オーソドックスな聖書絵本からサンタクロースを主人公に
したものまで様々。聖書絵本はイエス様の誕生を扱ったものが断然多いが、同じベツレヘムの”馬小屋の物語”でも”クリスマスの
劇をする”ことを主題にした、心温まる佳品があるので紹介する。
ジョセフ・スレイト文、フェリシア・ボンド絵 『やまあらしぼうやのクリスマス』 (グランまま社)
動物の子供たちがクリスマスに劇をすることにした。ヤマアラシのぼうやも「かいば桶の赤ちゃん」の劇に出たいと思う。でも、みんなに
断られてしまう。「お前のやる役なんてないよ。かっこわるいんだもん。」「舞台係りならなれるよ。」「掃除係りなんて、どう。」と、キツネ、
ウサギ、ネズミ、リス、ブタ……みんなにばかにされてしまう。ヤマアラシぼうやは「ぼく、舞台係りもする。掃除係りもする。だから、
どうしても劇に出たいんだ。」と、お願いする。それでもダメ!「やーい とげとげボール!」とからかわれる始末。
ヤマアラシぼうやは泣きながら家にとんでかえる。「ぼくは、変なとげボールだ。」泣きじゃくるぼうやを、お母さんがギュッと抱きしめて
言う。「いいえ。そんなことないわ。ぼうやはお母さんの心の光。あなたなら、立派に舞台係りが出来る。掃除係りだって出来るわ。」………。
この絵本、素敵な結末が待っている。いじわるした動物達を咎めることなく、「かいば桶の赤ちゃん」はフィナーレを迎える。ヤマアラシ
ぼうやの健気さが胸に迫る。それ以上に、お母さんの慈愛の深さに心温まる思い一入。文章は甘ったるくなく明快。朴としてユーモラスな
挿絵は、気持ちよさや喜びを感じさせる。
お母さんはいつもヤマアラシぼうやを抱きしめて言う。「ぼうやはお母さんの心の光。」本の最後でもそっとつぶやく。「私の心の星。」
いいなあ、ヤマアラシぼうや……。
子供たちのすべてのお母さんが、この”ヤマアラシぼうやのお母さん”であって欲しいと思う。
(DEC.6)
■ お知らせ
メールの受信が不調でしたが、なおりました。ご迷惑をおかけしました。
 ・ぼくも冬眠して長い夢を見てみたい。
・ぼくも冬眠して長い夢を見てみたい。 葉を一枚一枚落としていく梢。くっきりとシルエットを空に突き出す。裸木を揺らす木枯らし。今日から師走。
(DEC.1)
| 11月のアトリエだより |
■ お知らせとお願い
有賀忍のホームページをご覧くださいまして有難う存じます。現在、メールの受信が出来なくなって
おります。ご迷惑をおかけしています。ご連絡はFAXにてお願いいたします。申し訳ございません。
■秋の野に色を拾う。時間はゆっくり流れていた……。




23,24両日は現代童画展の公募作品の審査をした。審査会場は東京都美術館の地下3階。毎年、
日展の案内係りの控え室の隣だ。人いきれがするくらいごったがえしていた。窓のないコンクリートの箱
の中は空気が悪い上にひどく暑い。”地上”に出るとフラフラした。審査に疲れ、ぼくは逃れるように鳩山へ。
現代童画展出品作を制作し、そのままになっていたアトリエを片付ける。それから小パネルをイーゼルに
のせ絵筆を握る。大作を仕上げた後は暫し放心状態になるが、決して気持ち悪いものではない。安堵心
からか筆が軽く感じられる。
本来、絵には完成の期限や締め切りがあるはずも無く、こうして自由に描けることが喜びである。窓ガラス
に翔ぶ鳥の影を感じる。舞い落ちる枯葉の影も。物音ひとつしない小さなアトリエに単独個体。至福の時が
静かに過ぎて行く。
外に出れば、ついこの間まで緑だった野が、今や枯れ草色。アトリエに籠っているうちに霜の降りる季節
になってしまった。それでも秋は素敵だ。もみじの燃えるような赤や花水木やブルーベリーの葉の暗紅色は
目を楽しませるし、ブナの黄や茶、柏の葉の濃い茶色だってとりどりに美しい。今日は日溜りで、風に舞う色
の入り交じった桜の枯れ葉を目で追って遊んだ。
樹陰には、じゃのひげ。あちこちに固まって生えている。細長い葉をかき分けると、濃青色の数珠玉が
光っている。まだ、青くなる前の翡翠のような色のものも。じゃのひげはユリ科の多年草。根の膨大部を
乾燥させたものが生薬、麦門冬(ばくもんどう)だ。碧色数珠のような種子が薬になるのかと思っていたら
違った。この辺り、春にはニオイスミレが群生する。
ぼくはアトリエに籠ると、仕事に没頭してしまって、なかなか外に出なくなる。でも、季節の移ろいや
自然界の生新な気をもっと体で感じなくてはもったいないと、つくづく思った一日だった。赤い実を啄む
鳥たちを、ゆっくり流れる時間の中で見ていて、そう思った……。
(NOV・26~27)
■板絵小品を制作する
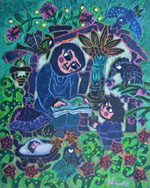 ・学舎(まなびや) NOV,2005 F3号
・学舎(まなびや) NOV,2005 F3号 現代童画展出品作『父は星』、『母は花』が完成。運送屋に託す。休む間もなく、小品を一点制作。画題は『学舎』。
童美連(日本児童出版美術家連盟)会員作品集「WHO’S WHO」掲載用のF3号の作品で、2006年出版される。
同時に作品展も予定されている。この作品展、出品作はすべて同じマットと額で統一されるという。
(NOV,21)
■仮リ額装
 ・鳩山アトリエ
・鳩山アトリエ 絵は仕上げる前に額にいれてみる。キャンバスやパネルに描いたものはいわば裸。作品はフレームをつけて見るのが
普通だから、一旦額装してマッチするか試してみる。木ネジでパネルを固定、良ければフレームをはずし、再び描いていく。
展覧会の搬入日が近づいているというのに、なかなか筆を置くことが出来ない。
焦る気持ちを笑うかのように、コオロギが一匹はねる。どこから入って来たの?アトリエの明りか、暖かさか、
何に誘われて?ぼくの板絵を見ていきな……。
まだ途中だけど、誰にも見せてない新作を、小さな訪問者に見せてあげよう。
(NOV.14)
■大学構内で銀杏を拾う


授業を終え校舎を出ると空は晴れ渡り、風がまことに心地よい。いちょうの並木敷に銀杏が落ちている。されど拾う
者なし。歩道では踏みつけられ潰れた銀杏が異臭を放っている。拾おうにもあいにく入れ物がない。備え付けの傘用
ビニール袋を二重にして使うことにした。細長く格好わるいことこの上なし。女子学生が通る道で、ああ恥ずかしい。10分
足らずで袋が3本も。この収穫、恰好の酒の友。
そう言えば学生の提出した課題「キャラクター設定メモ」に、イチョウの葉っぱを主人公にしたものがあった。ミノムシを
キャラクターにしたものも。2作品とも発想がユニーク。お話の展開が楽しみだ。アイディアは、枯葉舞うキャンパスを歩いて
いて思いついたのだろうか。生活のほんのすぐ脇に素材は転がっている。要は、気がつく、見つける、思うか思わないかの
違いだけだ。感受性は知らず知らずに鈍磨して行くから恐ろしい。大人にだってそう遠くない昔、赤ん坊、子供・・・・感官の
塊のような時代があったのに。だれにも・・・・。
臭いを気にしながら電車に乗る。銀杏、これだけあれば・・・・しめしめ。喜んだものの、おっと、今晩は酒は飲めないので
あった。夕方、歯医者に行かねばならない。親不知を抜く日であった。
(NOV.9)
■ムカゴ、再びどっさり収穫!


今年こそは自然薯を掘ろうと意気込んでいた。、秋たけなわ。掘るなら、ヤマノイモの蔓が枯れて見えなくなる
前の、今だ。でも仕事が間に合わない。、ほとんどの時間をアトリエで過ごさざるを得ず、諦めた。ヤマイモの茎をたどり、
堀さえすればよいというものではない。太い物を収穫するには、前の年から目印をつけておく。太く長く育つのには年数を
要すのだ。掘るのも大変。先まで折らずに収穫するのは至難の技。根気がいる。
自然薯が好きで手に入ると、海苔でくるんでさっと揚げて食す。粘りの強いヤマノイモは絶品!酒が捗って困るくらいだ。
楽しみは来年にとっておこう。
今年は例年になくムカゴがよく実をつけた。2~3日前に両手にいっぱい採ったけど、今日も夜の酒の供に十分な量を
15分ほどで確保。
仕事を終えての酒は、酒とつまみ、それに何よりも、その日の仕事の満足度による。つまみのムカゴはまずまず。
酒も用意した。あとは、今日の仕事の出来具合だけ。これが、一番厄介者だ。
(NOV.6)
■絵本『おばあちゃんのちいさなおうち』再々刊 (メイト)
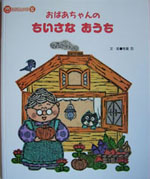

鳩山のアトリエは、おしゃもじ山の北斜面の低い所にあり、湿気がすごい。カビがついたパネルを時々虫干ししなくてはならない。
今日は秋晴れ、絶好の虫干し日。小さなパネルだけ天日に干した。山の陰で4時にはもう薄暗くなり、虫干ししたパネルを取り込んだ。
忙しなく東京に戻る。渋谷の仕事場の郵便受けに茶色の冊子小包がはみ出している。マンションのドアにも、宅配便の不在通知が
数枚。すべて出版社が送ってくる月刊幼児雑誌だった。幼稚園直販誌を含め10冊ほど。12月号揃い踏み。その中に、ぼくの絵本
『おばあちゃんの ちいさなおうち』があった。この幼稚園直販誌は、1992年出版され、「お話メイト傑作選」として1998年に再刊。
そして今回3回めの日の目を見ることになった。素直に喜びたい。はじめのはハードカバー、再刊行の2冊は中とじのペーパーバックで
あるが、ハードカバーのみに作者のプロフィール欄に写真が載っている。驚いた。若さはつらつ、目は輝いている。何だか強い意志までも
感じられる・・・・。
思えば”日々新生、日々創造”を座右銘とし、燃えていた頃だった。朝から晩まで、創作しか頭に無い時代だった。
体は衰える。集中力も落ちている。でも、ぼくの創作欲は涸れまい。絵を描く事がたった一つの好きなことゆえ。酒があって、
仕事さえ出来れば他にもう何を望まん。
(NOV.3)
■秋の山の恵み・ムカゴを採る



アケビが成らない。昨秋はアケビのオリーブ炒めに舌鼓をうったものだが、今年は収穫がなく残念だ。
それでも食卓には美味しい玄米がある。下の田圃の石井さんより、奥さんの手作りの栗の渋皮煮とともに頂いたものだ。
石井さんは毎年届けて下さる。全くもって恐縮、忝く思う。新米は鳩山名産キヌヒカリ。とくにぼくは、玄米が大好き。この
玄米、胡麻塩でも振れば立派な酒肴。酒は捗り臓腑は満足。稲を刈り終えた畑の広がりを、虫時雨の闇の向こうに
思いながら、米を収穫地で味わえる幸せに酔っていた。これは現代では贅沢な幸せだ。
アケビは不作だったが、ムカゴは両手に余るほど収穫。パンクし放置しておいた自転車にまで、ヤマイモの蔓が絡み付いて
いた。蔓に向かい合って付く細長いハート型の葉の元にある黒褐色の実がムカゴ。触れただけでボロボロ落ちる。自然薯は
栽培ものとは、擂り下ろした色も濃度も、もちろん味も違うが、掘るのが一苦労。枯れた茎を頼りに掘ってみても、まだ
細かったり、途中で折れてしまったり。なかなか簡単には口に入らない。今年も (根気よく掘る時間もないし) ムカゴで我慢した。
我慢といっても、これも、この季節だけの山の恵み。秋を存分に味わうことにする。
○ムカゴ玄米ご飯 米に対し玄米は1割。(もち米を2~3割加えると旨い)ムカゴ、塩、酒、やや多目の水加減。酒も
たっぷり入れたほうが香り立ち美味しい。コロコロしたムカゴ、これ自体が美味というのではないが、ねっとりした食感が
楽しめる。野趣あふれる炊き込みご飯は季節感たっぷりだ。
○ムカゴと蒟蒻オリーブ炒め ムカゴ、厚くスライスした生マッシュルーム、サイコロに切った蒟蒻、ペッパー、酒、醤油を
バターソテーし、仕上げにオリーブオイルを絡める。これはいける。小鉢いっぱい作ったが、大吟醸『月の滴』が空になる頃には
ムカゴは一粒も残っていなかった。
『月の滴』は畏友の杜氏、宇都宮繁明氏の手になる美酒。この酒については、後日この欄で。
(NOV.2)
■川越・蔵の街
1日は川越街道を通って鳩山へ。関越自動車道を利用すれば1時間半だが、一般道を和光、志木,所沢、川越、坂戸と
行けば、3時間近くかかることもある。道を挟むように置かれた石の道しるべが川越街道の往時を偲ばせる。夏には
茂る葉が空を閉ざすケヤキの並木も、秋には紅葉街道と化す。が今年は、まだまだだった。
道がすいていて、予定より早く川越に入れたので、「蔵の街」で一休み。黒い瓦屋根に鬼瓦が鎮座する昔ながらの街並み
を歩いた。屋根の見上げ続けで首が疲れた。
蔵の1階はすべて同じような土産物屋だ。土蔵の中を体感できると期待している観光客には物足りないだろう。鬼瓦の蔵を
外から眺めるだけなら、昭和初期に東京都心の商店街で流行った看板建築と考え方に大差はない。街の活性化には
レピーターが不可欠。体験型、学習型、そしてエンジョイブル。蔵を活かした街づくりを、歩きながらぼくは考えていた。
川越の名産,薩摩芋の菓子を知人に送ろうと、明治20年創業という「くらづくり本舗」に入る。スイートポテト”べにあかくん”
福餅入り最中”福蔵”芋焼菓子”ポクポク”・・・・どれにしようか迷っていたら、笑顔の店員さんがサンプルとお茶をだしてくれた。
丁寧な言葉遣い、やさしい仕草にほっとする。こんなことが、近頃とてもうれしく感じられる。川越から鳩山まではあと30分だ。
(NOV.1)
| 10月のアトリエだより |
■どんぐり発芽 マテバシイとクヌギ (鳩山にて)


・マテバシイ ・クヌギ
彫りをほぼ完了。彫りくずを捨てに外に出る。秋の午後の陽光なのに眩しく感じられる。ずうっとアトリエに籠って
いたからなあ。昨日は午後アトリエに入り、夜中に仕事。今日も朝8時から4時まで彫り続けた。やっと、これで絵を描く
作業に入れる。板絵は描くまでの下ごしらえに時間がかかる。大きな板2枚ともなるとなおさらだ。
ごみを埋けようとしてふと見れば、薪用に切っておいた丸太の割れ目から、マテバシイが育っていた。どんぐりが
丸太の割れ目に偶然落ちたのだろう。あたりにマテバシイの幼木が育つのは少しも珍しくないが、この発芽には
目をひきつけられた。
植木鉢のどんぐりの木はクヌギ。昨年10月31日、鳩山公民館の林で拾ったどんぐりが、ここまで育った。全部で7本、
そろそろ畑のすみに移植しようと思う。ぼくの頭にはもうクヌギ林に木漏れ日の景色がある。
畑には色んなどんぐりが発芽するから楽しい。自然の嬉しいプレゼント。小鳥や風にも感謝。
静かな、穏やかな、秋の夕暮れ。たまに柿の実が落ちる音。 渋柿が熟して自然に落下。モグラが作った山の黒土と
濃いオレンジ色のコントラスト。
昨日、今日と誰にも会わず、電話も鳴らず、仕事のみ。一人創作、幸せな時間。
(OCT,30)
■HALLOWEEN<万聖節前夜祭>の,かぼちゃ提灯を作る



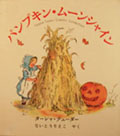
・かぼちゃ提灯を作る ・jack-o’-lantern ・ターシャ チューダー作『パンプキン・ムーンシャイン』1938年刊
額の塗装用ペイントを買いにホームセンターに行く。ぼくは絵に合わせて額も自分で作る。材はモミやツガ。
今回は『父は星』『母は花』用、120センチ×170センチの額を2枚製作。サンダーをかけ塗装。乾燥させては5回塗る。
色はミルキーホワイト。絵を描き始めたばかりで、一分たりともアトリエを離れたくはないが、額も用意して
おかねばならないので仕方ない。
ホームセンターはクリスマスの飾り付けをしているところだった。早い。年々早くなる感じがする。園芸用品
売り場のレジの脇に、おばけかぼちゃが置いてあった。10月31日のハローウインに合わせて陳列したのだろうが、
あと1週間でお払い箱。580円のディスカウントプライスに、思わず買ってしまった。20キロ以上あるだろう。かなり
重い。腰痛を気にしながら運ぶ。何しろこのかぼちゃ、持ちずらい。抱きかかえて運ぶしかない。仕事を中断、
ぼくはかぼちゃ提灯作りに夢中になった。
ハローウインは、もとはイギリスとアイルランドのケルト民族の宗教行事だった。もう2000年以上前のこと。
アメリカにハローウインの習慣が定着したのは19世紀頃。我が国で”かぼちゃのお化け”が目につくように
なったのはここ数年位前からか。クリスマス、バレンタインデー同様、コマーシャリズムの仕掛けによるもので
あって、すべて上辺だけの真似。だから、夜、子供たちが「Trick or treat」(お菓子をくれないといたずら
するよー)と言いながら、家々を徊るなんてことは、ない。
ハローウインを描いた絵本と言えば、やはりターシャ・チューダーの『パンプキン・ムーンシャイン』だろう。(9月の
アトリエ便りでも紹介)ハローウインの日、小さな女の子シルビー・アンはかぼちゃ提灯を作るために、大きな
かぼちゃを探しに出かける。シルビーが見つけたかぼちゃは坂道を転がって行く。ヤギやニワトリやガチョウを
驚かせながら………。(省略)アンはおじいさんと、かぼちゃ提灯を作る。「かぼちゃの ああたまのさきを ほうちょうで
すぱっ。シルビー・アンが かぼちゃの なかの たねや すじを きれいに ぬきとると、おじいちゃまが ふたつの
めと。まんなかに はなと、さいごに まがった はを むきだして わらう くちを つけて くれました。(訳文通り)」
日暮れを待ち、シルビーとおじいさんは、かぼちゃの提灯にロウソクを灯し、門の柱にのせて隠れる。みんなが
驚く様子を藪の陰から眺めて楽しむのだ。
シルビー・アンはかぼちゃの種を取っておき、春に蒔く。ぼくも掻き出した種は捨てずに取って置く。いい事に
使うためだ。食べるため?お化けかぼちゃの種は薄っぺらで食用にはならない。それでは何のため?答えは
後日、このアトリエ便りで!
かぼちゃ提灯、jack-o’-lantern作りはもちろん初めてだ。ターシャ・チューダーは上記絵本のタイトルに
、jack-o’-lanternを”punpkin moonshines”としている。ターシャ・チューダーの美しい絵本、
『A Timeto Keep』(絵本の小径で紹介済み)の”10月の行事”にも、圧搾機によるリンゴの果汁絞りと並んで、
かぼちゃ提灯作りが描かれている。が、いずれもかぼちゃの上部を横に切り、果肉を取り出している。(クレヨンまるの
頭と同じだ。)
ぼくはかぼちゃの上ではなく、顔になる部分の反対側に、窓をくり抜いた。10センチ×15センチ。くり抜いた皮は
窓の蓋に使う。これで、後ろから光が漏れることはない。楽しい工作時間が過ぎ、気がつけば夜の帳が………。
出来たてのかぼちゃ提灯にロウソクを灯し玄関先に置く。悪霊除けだ。オレンジの顔に、燃える火の赤々とした目。
写真を撮ったら手ぶれのせいで、目から炎が吹き出して写ったものがあった。失敗も時に面白いものだ。
スヌーピーでお馴染み、PEANUTSキャラクターズのお話には、ハローウインのシーンがよく出てくるが、1973年刊の
『The charlie Brown Dictionary』(by Charles M・Cchulz)の”Halloween”の
項目より、一節紹介したい。
”(-前略- Now most kids gather money on Halloween for poor children
all over the world”)………子供たち、「Trick or treat」で遊ぶばかりじゃないんだ。日本でも
ハローウインを楽しむのは結構。でも、上辺だけの行事、仮装して馬鹿騒ぎ、ではなあ………。
額のペイントを再度施し撤収!我がjack-o’-lanternも飾る間もなく方付け、アトリエを後にする。せわしなく、いつも
後ろ髪引かれる思いだ。東京での仕事が待っている。気持ちを切り替えて車のハンドルを握る。横で、お化けかぼちゃが
揺れている。笑っている。ロウソクの消し香を漂わせ………。
(OCT.23)
■板絵『父は星』『母は花』制作開始
 ・板絵彫り始め (鳩山アトリエ)
・板絵彫り始め (鳩山アトリエ)
パネルに下描きするのももどかしく、彫刻刀を握る。アトリエに入る前日見たギュスターブ・モロー展の、
聖俗,生ける者、死せる者、愛憎……、妖しい幻想的な画面がまだ頭に居座っている。振り払うのには
三角刀で板を大まかに彫り進むに限る……乱暴なくらいに。(ギュスターブ・モロー展 BUNKAMURA
ザ・ミュージアム 8/9~10/23)
歴史画家を自認するモローはギリシャ神話、聖書に画想を求めたが、文学性、物語性が
強いと、批判を浴びた。確かに”歴史のイラストレーション”的絵画ではあるが、誠実過ぎるほどの、
強い実証主義によって描かれたこの神秘的、あるいは普遍的世界のモロー芸術は、鑑賞者に
眩暈を起こさせるような魅(魔)力がある。(マチス、ルオーがモローの教え子だったとは知らなかった。
因みにモロー美術館初代館長はルオーである)
文学性が排除されるなんてナンセンス。ぼくの板絵”懐郷の詩”はすべて、物語からなっている。
ぼくは想いを、詩を、歌を,色で、形で語りたい。それだけだ。
休まず彫り続けて、腕がこわばり肩もこった。肩を廻しながら薄闇の外に出ると、おしゃもじ山の頂に
あるスピーカーから、子供たちに帰宅を促す呼びかけが、赤とんぼのメロディーとともに流れてきた。
<元気に遊んでいる良い子の皆さん、もうすぐ5時です。車に気をつけて早くおうちに帰りましょう……>
子供の姿など、どこにも見えないよ。聞きなれた曲だけど、なぜか今日は物悲しく感じた。メロディーが
消え再び静寂。梢を揺らす風の音はさらに一層孤独感を募らせた。
(OCT.16.2005)
■鳩山の畑の蜘蛛と、クモのヘレンの絵本


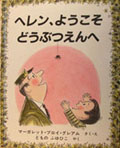
畑に続く通路を伸び放題のクリスマスホーリーが塞いでいる。
鋸歯が痛いので枝を刈り込むことにした。はみだした枝をチョキッ チョキッと落として行く。
剪定はいつも、すまないなぁ、ごめんよ、という気持ちだ。高さは2メートルくらいに揃えた。
生け垣を鮮やかな緑と赤のコントラストで飾り、目を楽しませてくれるホーリーの赤い実が
今年は少ない。秋、ドングリを雨のように降らせるマテバシイの大木と同じく“豊作”は
一年おきなのだろうか。
1本のホーリーに蜘蛛が巣をはっていた。朝露のかかったまるい網はすこしたわみ、
その中央に黄色と黒の縞模様、ナカコガネグモがいた。獲物が掛かるのを待ち、
微動だにしない。生きた昆虫を網を張り捕まえて食べる、どうみても可愛くない奴だが、
体長3センチもある大物ゆえ、写真におさめた。
クモをモチーフにした絵本といえば、「The Spider and its Web」(ERMANNO CRISTINI
AND LUIGI PURICELL作 Adam & Charles Black・London刊 1975) が先ず頭に
浮かぶ。1匹のクモが網を張る様を描いた一種の観察絵本だが、巧みな造型、色彩、
構成に、ぼくは唸った。参った。この絵本については別項「絵本の小径」で改めて取り
上げることにして、今回は、楽しいクモのお話を……。
『ヘレン、ようこそ どうぶつえんへ』(マーガレット・ブロイ・グレアム作 キッズメイト刊
2000)ビリー少年は ペットを飼ってはいけないアパートに越すことになり、”ヘレン”を
動物園の門の前に置く。「ヘレンの世話をどうかお願いします」 と、手紙を添えて。
ヘレンと言うのは、ビリー少年が飼っていたクモだ。ビリーの気持ちがいじらしく、意外性の
ある始まりが笑わせる。
この動物園でヘレンは大活躍。ライオンの檻に巣を作りハエを捕まえては食べる。
ハエに悩まされていたライオンは大喜び。ハエを全部食べ終わると、
ゾウの檻へ、次はシマウマの檻へ……。(ゾウは水浴びを楽しめるようになり、シマウマは
ゆっくりと、干し草を食べられるようになった)……。
ところが、市長さんが視察に来ることが決まり、動物園は隅から隅まで掃除される
ことになったから大変!動物園の係員は、クモの巣に水をかけ、ごしごしこすりとって行く。
ヘレン大ピンチ……!
クモが主役のユニークな絵本。話が面白い。そして、何より愛らしく温かい。
鉛筆画線に色を抑えた水彩が軽やかでユーモラス。
網がかけられる過程もさりげなく描かれ、獲物のハエがどんどんかかり、
まん中でヘレンがにっこりしているところと、赤ちゃんクモに囲まれている場面の
表情がいい。
ヘレンは、ピンチを脱し動物園では、<クモを 大切に>という決まりがつくられた。
さらには新聞にまで登場。
<今年、大評判の動物園、クモに大喝采!動物園の園長が語るーーーーー>
この記事を、ヘレンを動物園に置いて行ったビリー少年が目にする……。
見終わったあと、さわやか。絵本ていいなあーと実感する。
憎たらしいと思ったナカコガネグモ、この絵本を見て好きになることはない。でも、
ヘレンの愛らしさは、“心を持った”すべての生き物に、その生き物の「物語を聞かせて
もらいたい」 と思わせる力がある。これが絵本の魅力だ。
(OCT・9・2005)
■現代童画展出品作の制作準備
 ・パネル、シナベニア両面にボンドを塗る
・パネル、シナベニア両面にボンドを塗る
何日ぶりだろうか。鳩山のアトリエに来たのは。板絵用パネル製作に一日を費やす。
木製パネルにシナベニア板を貼り付ける。畳よりやや小さなサイズ4枚作るのに使用した
ボンド3キロ。空になったポリ容器をみて、いつものことながらあきれる。
今回は2作描く予定だが、果たして出来るだろうか。制作にかけられる時間があまりにも
少ないからだ。大きな板に取り組む前の恐怖感も払拭せねばならない。妙案はなく、ただ
やみくもに彫り進むしか手はないと分かってはいるけれど……。
板絵は彫り、そして描く技法だ。カンバスに筆でという訳にはいかない。パネル製作という
下ごしらえの”儀式”を通じて創作心の昂ぶりを徐々に上げていき、一気呵成……忘我の
境……となれば、よし。
ボンドが乾き、仮止めの釘を抜くまでは、制作に入れない。仕方なく東京に戻ることにする。
その前に、雨上がりの庭に出てみた。はや、薄暮れ。主の長き不在で草も枝も伸び放題。
掻き分けなくては前に進めない有様。それでも、腰より上の木々が、繁みから聞こえる虫の
音とともに、秋の到来を教えてくれている。
マユミの鮮やかなスカーレット。茶の花の清らかな白。芳しい金木犀の黄橙色。散り急ぐ
萩の紅、白。いまだ落ちず枝に残る濃赤色の姫リンゴ。キウイ味のサルナシは今年も蔓枝に
たわわ。ナツメの実はまだ赤くならず緑色。ぼくが一番好きなヤマブドウは、もう紅葉を風に
震わせている。(ヤマブドウの紅葉は絵の具を混ぜても出来ないくらい美しい)残念ながら
実りは、ブドウジャムやシロップを作った昨年には及ばないが……。お礼肥やしを怠ったせい
だろう、きっと。実はまだ緑色がほとんどで、雨に濡れて光っている。青紫に熟した実を見つけ、
一粒口に含んでみる。酸っぱい果汁が口中に染みザラザラ感が広がった。秋ならではの
刺激をぼくはしかめっ面して喜んでいた。栗はほとんど実を落とし終わっていた。落ち栗は
見事な大粒でも虫がついていてダメ。残ったイガを棒で叩いて落とし、食べられる分量だけ
籠に集めた。
2,3日後には再び鳩山に来る予定だ。秋は一段と深まっていることだろう。板絵制作がこの先、
順調に進んだとしても、秋の早足にはとても勝てそうにない。
(Oct.6)
| 9月のアトリエだより |
■秋祭りが終わって……。
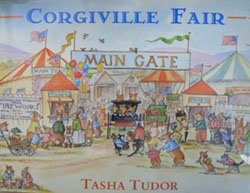 ・「CORGIVILLE FAIR」 TASHA TUDOR
・「CORGIVILLE FAIR」 TASHA TUDOR
夜の訪れがめっきり早くなった。18日は仲秋の名月。高い位置に見事な真ん丸。十五夜を
過ぎ、十六夜、立待月、居待月、寝待月……。23日は秋分の日。季節は急ぎ足で変わろうと
している……風が、草木が、虫の音が教えてくれる。
方々で秋祭に出くわした。三軒茶屋、大橋、いずれも運転中に窓越しで。仕事場の前の道路も
暫し通行止め。はじめは子供御輿、次の日は大人御輿が通った。練り歩くというような熱いもの
ではなく、行列は坦坦と進み、掛け声もなく盛り上がらない。行き所の広場さえない。何だか
この行事、義務でやっているみたいだ。参加者も目に見えて減り、年々都会の”街の連帯”が
希薄化している。かく言うぼくも、マンションの2階から眺めているだけだが……。犬にまでお揃い
のはっぴを着せる感覚がわからない。嫌だ。アスファルトの道を御輿をかつぎ、太鼓の山車を曳く、
ただそれだけ。都会の祭りは寂しすぎる。想いは幼い頃の信州の村祭。森があった。寄り集まる
神社があった。祭は神様にその年の平安や豊穣を感謝するものだが、”土の上”が当たり前。
喜びがそこにあったのだとは、考えもしなかった。
ターシャ・チューダー作『コーギビルの村まつり』は、土の匂い、村のざわめきが感じられる絵本
だ。古きよき時代の“ニューハンプシャーの西、バーモントの東”(原文通り)が舞台。“洋風”にも
かかわらず、懐かしさを覚えるから不思議。この本の扉には“To my beloved corgis”の言葉と
8匹のコーギ犬が並んでいる。ターシャの挿絵にしばしば登場する愛犬だ。(コーギー犬を飼い
始めるいきさつは娘、ベサニー・チューダ著『小径の向こうの家』に詳しい)
コーギビルの住人はコーギ犬、ネコ、ウサギ、スウェーデン生まれの木の妖精マート・ボガート。
御祭りの“目玉”はヤギレース。コーギ犬のケイレブと、策略をつかって、優勝を狙う悪役トム
キャットの勝負。息詰まる展開もおもしろいが、何よりこの絵本、見る者をCORGIVILLE FAIRに
誘い、紛れ込ませてくれる。
動物達の表情が素晴らしく、“土の上の”豊かな生活ぶりには「うん、こんな村に住んだ事があっ
たかもしれない……」と錯覚させてしまうほどのリアリティだ。レース場、ヤギの背で手綱を操る
ケイレブとトムキャットの息遣い、観客の大歓声が土ぼこりの中で聞こえてくる。
立ち並ぶテント、ひるがえる旗。出店、音楽隊、スクエアダンス、最後は村びと全員囲んでの花
火大会。“懐かしい情景”がふんだん。絵の一つ一つに、現代社会から消えた“生活感””喜び”があり
羨望を覚える。 秋祭りの太鼓や笛の音は消えたが、ここにはいつも祭りがある。一度コーギビルに
足を踏み入れてみては如何……。
(Sep.30)
■パンダのイラストを描いてから、嗚呼、33年が……。
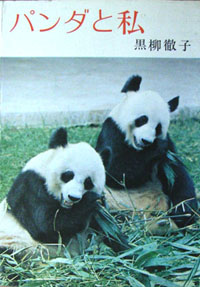
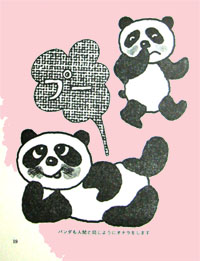

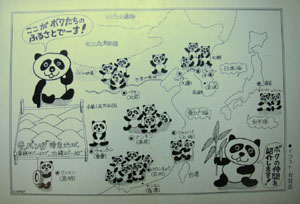
● 『パンダと私』 黒柳徹子 朝日ソノラマ 1972年 ●イラスト/ 有賀忍
上野動物園のジャイアントパンダ、シュアンシュアン(メス18歳)が、故郷のメキシコに26日に
帰ることになった。2003年12月にメキシコのチャプルテペック動物園から上野動物園のリンリン
(中国より1992年来園・オス20歳)とのペアリングのために来園。人工授精を試みたが残念ながら
赤ちゃんはできなかった。今日が見納め。昨日の新聞には、パンダの檻の前の”携帯カメラマン”の
人垣の写真が載っていた。
パンダが初めて日本に来たのは1972年。カンカン(オス2歳)と、ランラン(メス4歳)の2頭。当時の
パンダブームはまだ記憶に残っている。79年ランラン、80年カンカンと続けて亡くなり、パンダの飼育、
繁殖の難しさがわかった。85年には父フェイフェイ、母ホワンホワンから、待望の赤ちゃんが産れたが、
その日のうちに死んでしまった。
黒柳徹子著『パンダと私』は、まだ誰もパンダを見たことがなかった頃の出版。前書きは團伊玖磨。
「1972年冬 日中国交回復を心より喜びながら」と結んでいる。
もちろんぼくも、パンダの知識はなく、編集部から資料を借りてカットを描いた。「パンダってなあに?」と
題して100の質問と答え。それに、徹子さんと上野動物園の飼育課長、中川志郎さんとの対談、エッセーも
充実していて、今見ても楽しい本だ。もう、30年にもなるんだなあ……。
本誌のイラストでご一緒した漫画家の岡部冬彦さんは、今年5月お亡くなりになった。ぼくは「差別問題で」
絶版となった『ちびくろさんぼ』(フランク・トビアス絵/岩波書店)を大切にしているが、この絵本のパート2は、
岡部冬彦さんの筆によるものである。多くの子供の心をとらえた百万部のベストセラー。その魅力は、別項
「絵本の玉手箱」で近日。
(Sep.25)
・パンダの情報は<日本パンダ保護協会>で。 http://www.pandachina.jp../
■銀杏拾いはおあずけ
 ・写真は2004年度受講生の制作絵本
・写真は2004年度受講生の制作絵本
大学の講座がはじまる。初日は緊張する。1時間早く到着。相模大野駅構内のカフェでエスプレッソを一杯。
今年はどんな生徒が待っているのだろう……、胸の高鳴りを感じつつキャンパスを歩く。校門から校舎に至る
銀杏の並木が好きだ。まだ黄葉してないのに、道の両側に銀杏の実がもう落ち始めていた。
ぼくは教室を間違えたかと思った。学生に聞いて笑われる。受講生が大勢で面喰ったのだった。あとで分
かったことだけど、履修希望者が多くて抽選にしたのだと。昨年の倍。絵本・イラストの講義は広い教室で行え
ばよいというものではなく、個人個人にアドバイスするにも限界がある。でも、ぼくはファイト!(時代がかって
る?)で立ち向かうつもり。
他科に比べ“自由度”が断然高い科目だけれど、受講生はこの“自由に表現する”ことの難しさに気付き、とま
どうかもしれない。社会生活の中にはルールや約束事が多い。が、心までマニュアル化され、一つの答えしか
見出せなくなってしまってはいけない。既成概念に囚われない、人目を意識しない、「自由な心の表現」を制作
を通して考えてもらおうというのがぼくの授業。幼い時の自分を思い起こす。楽しむ。夢中になる。没頭する……。
そうして出来あがった物は世界にたった一つの存在。相対比較もいいけれど、もっと大事なのは、自分にとって
の価値観、美意識。これをしっかり持つという事。
創作は表現したいメッセージが希薄だったり、ブレていては伝わらない。何を語りたいのか……それは、
とりもなおさず自分を見つめ、自分を知ることでもある。美術大学ではないし、普段から、絵を描いている人はい
ないかもしれない。いや、多くは幼稚園以来クレヨンも握っていないだろう。 大丈夫!絵の巧拙なんて、2の次
3の次だから。技術以上に大事な「発想」のトレーニングも行うが、自己を解放し(素直になって、または幼児の
ように)制作されたものは、きっと見る者の心に届くであろう。
作品に“自分らしさ”が出ていれば、まずはそれで良い。作者には、比べられない大切なもの、かけがえのない
ものが、きっと見えているはずだ。
授業を終え、運動場を見遣りながら歩く。銀杏の梢から、葉が舞い落ちてきた。昂ぶった気持ちを落ち着かせ
るかのように、ヒラヒラヒラ……静かにゆっくりと……。このつぎ訪れる時には、銀杏を拾う心の余裕ができている
だろうか。
(Sep.21)
■たむらしげるの世界展
八王子夢美術館で『たむらしげるの世界展』を観た。明後日から始まる大学の講義の準備もそこそこに。
会期は2ヶ月もあるから大丈夫と思っていたら、今日が最終日。でも駆けつけてよかった。
水彩、色鉛筆、貼り布、CGなど多彩な技法による絵本原画やイラストの展観は楽しく、見ごたえがあった。
とりわけ、アニメ作品、『クジラの跳躍』 『銀河の魚』は幻想的。、何とも不思議な時間が流れている
ファンタジーの世界に引き込まれた。アニメの、いわゆるチャカチャカした動き、生々しい色のイメージは
そこにはない。しっとりと情感たっぷり。ゆったり優しく語りかけてくる・・・・・懐かしいけれど非現実・・・・・、
これがanother worldの魅力だ。
ぼくは、たむらしげるの絵本より軽妙洒脱なイラストに興味がある。特に1990年代のTV情報誌、
『TV=STATION』のCG。タブレットに一筆描きしたようなイラストが表紙を飾っていたが、シンプルで
おしゃれ。この”雑誌の顔”のファンは多いだろう。ぼくもその一人。ひょうきんで温かいイラストが好きだ。
日本を代表する映像作家の一人、たむらしげるのアニメーションは土曜10時、TBSの「ブロードキャスター」
のオープニングで流れている。
それにしても、この”夢美術館”の名前、何とかならないものか。行政が決めたのだろうか。”夢”は押し付け
がましい。美術館の”箱”に色をつけないで。色は”箱”の中にあればいい。夢なんて、抱くもの、感じるもの。
形になったら夢じゃない。
(Sep.19)
■『岸辺のふたり』 アニメーションと絵本
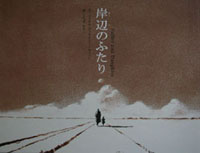
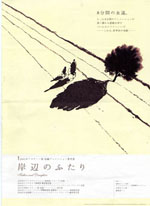

『岸辺のふたり』 くもん出版 2003年
昨年暮れ、たった8分のアニメを映画館のレイトショーで見た。『岸辺のふたり』(原題Father and Daughter
2000年イギリス・オランダ製作35mmオランダ・マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督)この短い1本だけではロード
ショウは無理。同監督の他の作品2本と併映、それでも30分足らずの映写時間であった。(併映の『お坊さんと魚』
『掃除屋トム』は絵の動きを目で追わせるのみで、着想に新鮮味がなくユーモアにも深みが感じられなかった。)
『岸辺のふたり』・・・・・DVDを、劇場上映しただけのことはあった。人を思い続ける強い心を描いた映像詩だ。
小さな女の子を岸辺に残しボートを漕いで行ってしまった父。父は消えても思慕の情は不変。面影を胸に少女は
待ち続ける。少女から大人、そして老婆になっても、岸辺を訪れ想い続ける。かけがえのない人を、ただひたすら
待ち続ける一途さに、ぼくは心の震えを覚えた。体の底に大切なものが何であるかはっきりと響いてきた。
映像はほぼセピア、ブラックのモノクローム。コントラストの効いた清らかな絵が見る者の想像力をかきたてかきたて
迫ってくる。とても8分なんて信じられない。季節の移ろい、年月の流れにリアリティがあり、哀しく身につまされるのだ。
使用曲はドナウ川のさざなみ。時に静かでスロー、時にUPテンポで活気を帯びて・・・。
さて、この絵本であるが一口で言うとアニメの絵本化は難しいということ。フィルムの一コマを取り出し組み合わせても
アニメには敵わない。アニメの魅力である動きは望むべくもないから。右開き絵本の場合、視覚誘導は右から左。
それに対しアニメは左右、前後、それに音響の効果も大きい。絵本『岸辺のふたり』は美しい絵のイメージの幾らかは
伝えるものの、長い時の流れを感じさせないのが致命的、残念だ。小口に入れたノンブルも邪魔。
このアニメ、絵本は、”不条理な喪失”を題材にしているが、身近に喪失なんて無いなどと、誰が言えよう。生きる上で、
喪失、離別はいつだって隣り合わせ。覚悟して生きていたいと思う。
■ クレヨンまるにファンレター
台風14号の影響で4日、東京は豪雨。世田谷通りは冠水、川のようになった。低地は池のようだ。ぼくの車も
水の中でたびたび立ち往生。ヘッドライトの高さまで迫る水に恐怖を覚えた。何とか脱出し帰ったが車内は水浸し。
エンジンに水が入ったのか警告灯が消えない。デーラーで調べた結果、オーバーホールすることになった。しばらくは
電車、バスで仕事場に通うことになる。
そんな中で、ちょっぴりホッとすることが・・・・。ミラクルクレヨンのクレヨンまるを連載している「おひさま」編集部より一通の
手紙が回送されて来た。読者からの"クレヨンまる宛"の手紙だった。毎月、読者のはがきはコピーして見せてもらっている
けれど、クレヨンまる宛ての”封書”は少ない。、こういう嬉しくなる手紙がたまに来るからやめられない。(以前、小学校
低学年の読み聞かせに「おひさま」を用い、先生が生徒の感想文、絵を束で送ってくださったこともあった)
創作欲とか言うけれど、クレヨンまると同じくらいの年齢の子供に励まされ、描いているのも事実。今描いている12月号は
120話め。丁度連載10年ということになる。
手紙をくれた”ゆうかちゃん”に、”クレヨンまる”は心ウキウキ、「ありがとう」の手紙を書いていた。
■銀杏拾いはおあずけ
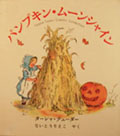
デジタルハイビジョンでの放映で見られなかったターシャ・チューダーの『四季の庭』が、高人気、要望により再放送が
決まった。思ったより早い再放送、これは嬉しい。BS2は11日。総合は23日。楽しみだ。
上の写真、『パンプキン・ムーンシャイン』はターシャ・チューダーの処女作(1938年刊)。『がちょうのアレキサンダー』
『こぶたのドーカス・ポーカス』など5冊の小型絵本「キャラコブックス」の一つ。絵は当然のことながら、文字も手書き。
表紙はプリント模様のキャラコが張ってあったことから「キャラコブックス」のシリーズ名となったそうである。
”キャラコ”・・・・何とも懐かしい響き!。昔、母が割烹着やエプロンを縫っていた、あの生地だ。
ターシャ・チューダー19歳の時の手作り絵本は、現在も長女ベサニー・チューダーの手元にあるそうだが、この
”キャラコシリーズ”の元になった手作り絵本も温かさが容易に想像できる。
『パンプキン・ムーンシャイン』は、ハロウイーンのために、女の子が大きなかぼちゃを探しに、遠く離れた丘の上の畑に
出かけるお話・・・・.。女の子、犬、ヤギ、鶏、がちょう、すべて慈しんで描かれていてとても優しい。かぼちゃ提灯で
びっくりさせて楽しんだ後、女の子はとって置いたかぼちゃの種を蒔く。かぼちゃはずんずん育って実をつける。
その後がいい。「かぼちゃは ゆめを 見ているようです。おおきく そだって パンプキンパイや かぼちゃちょうちんに
なるひを。」(ないとうりえこ/訳より)
パンプキン・ムーンシャインとはかぼちゃの中身をくり抜いたかぼちゃ提灯のことである。
(ターシャ・チューダークラシックコレクションとして、メディアファクトリーより2001年刊)
■ターシャ・テューダー 『四季の庭』
『小径の向こうの家』ベサニー・テューダー 食野雅子/訳 メディアファクトリー 1999年
8月31日憧れのターシャ・テューダーがテレビで見られると聞き、楽しみにしていた。が、放送はデジタルハイビジョン。
受信できず地団駄踏んだ。ターシャはアメリカで最も愛されている絵本作家。90歳。バーモントの山奥の広大な敷地で
自給自足、昔ながらの生活をしている。自分らしさと、日々の暮らしを大切に生きるターシャは夢を持ち常に前向きだ。これは
絵本ではないが、『ターシャの庭』『暖炉の火のそばで』『小径の向こうの家』(いずれもメディアファクトリー刊)等を見るたびに
ため息が出る。五感を研ぎ澄まして楽しむターシャのナチョラルライフに、喜びに満ち溢れた”幸せの姿”を垣間見るのだ。
ぼくの鳩山のアトリエは今どうなっているのだろう。草木が生い茂り,アトリエに続く小径は雑草で埋まり行く手を阻んで
いることだろう。行かねば。近々出かけよう。12月の現代童画展出品作に取りかからなくては。ターシャのような生活は
できない。鳩山と東京を行ったり来たりだけど、いつも心には憧れのターシャの素朴な生活がある。真の幸せを心に描ける
だけでもいい。あとは、それを絵に表現する力がほしい。
ターシャ・テューダーの絵本の紹介は「絵本の小径ー絵本玉手箱」で。
| 8月のアトリエだより |

 ・くまのマーク『パパだいすき』
・くまのマーク『パパだいすき』
なかよしメイト8月号 メイト
■今月は幼稚園直販誌2誌に作品を掲載。
『パパだいすき』は食いしん坊で、寝ぼすけで、忘れんぼうのパパ。でも、パパはマークの誇り。いざというとき頼れるのは
やっぱりパパ。ずぼらに見えるパパの格好よさ、存在感を描いた。
『熊太の波作り』は、もり・けん氏のミニ童話を絵本化。はじめのページ、熊太が海に漕ぎ出す場面と、家に帰って一日の
”冒険話”を、お父さんお母さんに得々と話す場面を加えさせてもらった。不可欠の大切なシーンだから。子供が外から帰った
ときの親の役目は唯一つ。信じようと信じまいと,そして馬鹿馬鹿しかろうと、子供の話をじっくり聞くこと。「ほー」「ふーん」
「それから」「へー」「そうかー」。子供は目を輝かせ夢中になって話すだろう。親は真剣に耳を傾ける……。これは簡単な
ことのようでも、存外難しいことだ。


・『熊太の波作り』 出会い文庫8月号 登龍館
■世田谷文学館のこと
<日本絵本賞>受賞絵本原画展(世田谷文学館)に行った。過去10回の日本絵本大賞、日本絵本賞、
読者賞の中から20点ほどの展示。
先日お亡くなりになった長新太さんの「ゴムあたまポンたろう」、自由に筆を走らせる遊び心そのものの感性。これからもう
新作が見られないと思うと残念でならない。友人の南塚直子さんの「キリンさん」(詩:まど・みちお)もあった。カラー銅版画、
手をかけた仕事だ。同時開催の「仕掛け絵本・とびだす!妖怪の絵本展」の作品は、おどろおどろした世界を描いたとはいえ、
絵がごちゃごちゃしていて、色も濁っているものが多く気になった。
会場の世田谷文学館はいつも思うのだが、観覧料が安く良心的。「寺山修司展」、「安部公房展」で500円、今回の「日本
絵本賞」は300円。ロビーには1300冊の絵本が自由に読めるコーナーも設けられており子供たちが楽しめるようになっている。
2003年の「スイスの絵本画家 フィッシャー、ホフマン展」は見ごたえがあった。世界の子供たちに愛されるハンス・フィッシャーと
フェリクス・ホフマンの絵本原画、下絵などはじめて目にするものだった。これとて300円、名ばかりの展覧会が多い中でこの企画は
出色、記憶に鮮明である。
■二人劇『列車でGO!』を観る
 |
|
■ドイツの劇団テアター・ハントゲメンゲ・ベルリンの二人劇『列車でGO!』を観る。(吉祥寺シアター)
子供と大人のためのヨーロッパ演劇「EU Theatre Artsu for Children and Young People Festival
2005 in a vertical tour of Japan」EU児童青少年演劇日本縦断招聘公演、18カ国の劇団による公演のうちの
1プログラム。
鉄道模型に熱中するオタク系の二人が、実際に模型機関車を走らせながら、運転手や駅員、乗客になって物語を
作って行く。機関車が蒸気を吐き出す音や動き始めるときの音、駅のアナウンスから犬や牛の鳴き声まで……、肉声や
ハーモニカによるオノマトペが巧み。
トーマス少年の愛犬を乗せて発車してしまったワルシャワ行きの列車を追う父親の心情が胸に迫った。舞台に敷かれた
レールは憧れのレーマングロースバーンだ。(ドイツの軌間45ミリゲージ。日本ではGゲージと呼ばれる模型では最大のもの)
蒸気機関車が音をたて走り回るたびに、観客の少年たちは盛んに歓声をあげていた。思えば、男の子には鉄道少年の時代が
誰にでもあるものだ。
字幕が不鮮明な上に翻訳が粗く、それもダイジェスト。役者のセリフとの時間差も気になったが、照明は見事。とくに、犬の
ぬいぐるみ”がたがた”を抱きしめ立ち尽くす父親と、その周りを走る列車越しに、もう一人の役者が黒子になって、移動しながら
照明をあてて行く場面は、現実を超えて美しく、舞台劇であることを忘れさせた。夜汽車の影は天井まで大きくなったり、
消えそうに小さくなったり……、闇の中を小さな明りを灯した汽車はひたすら走り続ける。そのなかで黙して動かない父親の
気持ちがひしひしと伝わって来た。シルエットが交差する幻想的な光景は今も脳裏から離れない。
劇中、役者が演じたのは”少年の心”のまま大きくなった人間だ。ぼくは、あまりに熱い二人の男を羨望の眼差しで見ていた。
大人が遠い昔に置き忘れてきた宝物の一つが”少年の心”なのだろう。
ムーミン展に行ったが期待はずれ。会場はキャラクターグッズの即売会だった。多くの人は買い物に大忙しで
、7~人座れる椅子に坐る者は少なく、DVDがじっくり見られたことはラッキーだった。トーベヤンソン唯一の
仕掛け絵本を動かしたというアニメ『それからどうなるの』は絵本の絵と仕掛けがそのまま活かされており、岸田
今日子のナレーションも不思議な世界にマッチしていた。嬉しかったのは、毎年何ヶ月かを暮らすヤンソン島で
ヤンソンさんが大きなのこぎりで丸太を切っている写真を見られたこと。ここでムーミンが描かれたことを思い、その
写真をぼくは食い入るように見つめ、想像を巡らせたのだった。
MOOMINN I’m sure of Tove Jansson’s words.